お断り
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたい方には不向きだ。
よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。
ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。
とある本を読んでいて、この「あなたの日本語だいじょうぶ?」を薦めていた。興味を持ってというか、裏を取るために図書館から借りてきた。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| ★あなたの日本語★ だいじょうぶ? |
★金田一秀穂★ | ★暮らしの手帖社★ | 9784766002355 | 2023/07/10 | 1500円 |
手に取る前は、タイトルが「あなたの日本語だいじょうぶ?」とあるから「だいじょうぶ」な日本語を教える本かと思った。
読んでみるとそういった"だいじょうぶな日本語を教える本"ではなく、「サライ」とかいう雑誌で連載していたものと若干の書き下ろしをまとめたエッセイであった。少しガッカリした。
そして中身は日本語を語ると言うより、年寄りが愚痴ったり小言を語ったりするだけであった。おっと、著者を年寄りとはいったが私より何歳も若い。体は老化しても気持ちは老化したくないね。
ここで中程度にガッカリした。
エッセイと随筆の違いは? なんて言われるかもしれないが、随筆は体験した事実を基にしたもので、エッセイは体験せずに考えたこと思ったことを書いたものだそうだ。
語義に従えば、この本は随筆とエッセイ両方が混在している。
高校のときの先生が、元海軍中尉で終戦後アメリカ軍の通訳をしていたそうだ。
先生が授業で「わしはアメリカの士官に、日本が負けたのは日本語を使っていたからだ、日本人が日本語を使っている限り戦争に勝てないと言われたんじゃあ」と悔しそうではなく、苦しそうに語っていたのを覚えている。
日本語は論理的でないと言われる。その理由として、主語がない(ことが多い)、形容詞の意味があいまいだ・位置によってはどこにかかるか分かりにくい、否定か肯定かはっきりしない……などいろいろ聞いたことがある。
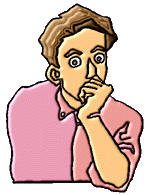 |
|||
社会に出るとYES・NOをはっきりさせなければならないことは多いし、文章を書くときは読む人に分かってもらうためには、誰が・いつ・どこで・何を・どのようにと、キプリングの召使を呼ばなければ目的を果たさない。
となると社会人はあいまいどころか、論理的でない文章を書いてはいけないことになる。
私は仕事で15年、現場作業の要領書を書いた。自分が書いたものを読んだ人が仕事でミスすると、非常に悲しく悔しかった。ミスの原因としては、文章や絵が誤解しやすいとか、意図を表現し仕切れなかったものが多かった。
そんなことを長年していて……15年は短くはない……少しは上達したと自認していたが、40を過ぎて会社規則を書くようになった。自信をもって決裁伺いすると、SVOCが明確でないと上長から差し戻されることが多々あった。主語のない文章を書くな!と何度言われたか分からない。
既にこの文章は主語がない(笑)
主語だらけでは煩わしいと思ったが、上司は主語がないと感覚的に受けいれられないと言う。彼は英語がTOEIC満点と言う方で、英語が得意だからそう感じるのだと思っていた。
一般的な日本語では、主語が一度出れば二度目からは主語が出てこないのだが、規則のようなものは前後の文章を読んで文脈から理解するのでなく、センテンス単位で読まれ、引用され、解釈されるから、ひとつひとつの文が完結していないとダメなのだと教えられた。
気になって、法律を何本も読んだが、確かに法律で主語のない文章は見あたらない。
再度であるが、私のほとんどの文章には主語がない(笑)
ただ書き方として、「○○は以下の事項を○○する」という風に、S+Vだけ書いて複数のO、Cをかっこでくくる書き方も多い。普通の文章とはちと違うところもある。
学校で教える文章に法律の文章を使えば、実用文を書く上では大いに意味があると思う。少なくても私のしていた仕事では大いに役立ったと思う。
そもそも小学校、中学校の教科書で、会社で扱うEメールとか手紙の文章の書き方を見たことがない。詩とか俳句とか小説なんてばかり載っている。
昔、寺子屋では三行半の描き方を教えたと聞くけど、そういう現実的な実用的なものを教えるべきだ。
人間は教養が必要だというかもしれない。私は文芸を教えるのは否定しないが、実用文を教えないことは問題だと思う。そしてどちらかを切り捨てるなら、文芸、詩とか俳句とか小説をなくすべきだ。
そんなことに気づくとSVOCがないと気分が悪い、受け入れられないというのは、別に英語でなくても当たり前のことなのだと気づいた。
私は小説家ではないから、名文を書こうなんて考えは毫もないが、規則や要領書を書いていると気になることは多々ある。ひとつは文末が同じだとちょっとひっかかる。
「○○する」「○○する」と何度か続くと、ちょっと「○○すること」と変えようかと思ったりする。また「電動ドライバー」が何度も登場すると、たまには「ドライバー」と略すかと思ったりする。
昔、手紙とか書くとき、同じ音が続くと、隣接回避といって同じカナが並ぶのを嫌い、変体仮名を使ったという。(変体仮名を使う理由は他にもある)
確かにその方が見た目は良くなる感じはする。
だが、法律だけでなく、規則や要領書の文章は、センテンス単位で取り扱われると考えると、馬鹿の一つ覚えのごとく同じ単語を略さず使うことは意味あることだ。
また文末に使う表現を予め決めておいて文章を書くことは、読む人の誤解を防ぐ効果が大きい。
実際に法律の語尾は標準化されていて、「する」「による」「できる」「できない」「しなければならない」「限りでない」など8種類くらいしかない。
最後の一字まで読んで文章の意味が分かるようでは、情報通信の観点から効率的でない。
私が他人の書いたものを疑うように、あなたも私の書いたものを疑わなければならない。
電子政府と検索して法令検索をクリックして、適当な法律を表示してじっくりと眺めてほしい。
私の語ることをご理解いただけると思う。
英語では否定・肯定が冒頭にあるから読み始めた瞬間に分かるが、日本語だって記述に気を使えば、つまり文末を標準化しておけば、文章の最後の句点「。」まで読まなくても意味がつかめるのだ。
それらは非常に有意義な作文作法だと思う。その結果、文学的ではないとか、表現が単調だと言われても私は気にしない。
自分が書いたものの、意図が正しく読み取られた方がありがたい。いやそれこそが文を書く目的ではないか。
自分が書いた要領書を誤読されたとか、規則の言い回しが分かりにくく、それによって問題が起きたという経験を山ほどすれば、どんな文章が実用的なのかというのを嫌と言うほど認識する。
私の書いていることを理解できない人は会社で仕事の文章を書いたことのない人だ。
多くの会社では「文書作成の手引き」などと称して、会社独自の文章作成の要領書を新入社員に配布して教育している。
会社によっては独自ルールで、「下さい」は「ください」にする、ワン センテンスの文字数は〇文字以下、漢字割合を40%以下にするなどと決めているところもある。
柔らかい感じにするとか、文章を黒っぽくしないとか、読みやすい感じにするとか、それぞれの会社の方針があるのだろう。
会社によって基準は違うが、いずれも誤読・誤解の予防、失敗の反映、内外からの意見などを反映してリファインされてきたのだろう。
もとろん一般論としても、風流な文章でなく誤解のない、論理的な文章を書こうという本は過去から多々あった。
もう40年も前「理科系の作文技術
私にとって「理科系の…」よりもためになったのは「マニュアルバイブル」とか「論理的思考の技法I
さて、この本を読んで思ったことである。
一言で言えば、なんだ、こりゃ!である。決して松田優作ではない
まず本の内容は「だいじょうぶな日本語」を教えるものではなく、年寄りの愚痴、小言ではある。そして出てくるものは論理的な日本語、誤解しにくい言い回しとは縁のないものばかりである。
■読み始めてすぐにがっくりきたのは「見える化」のお話である(p.28)。
だいぶこの先生、パワーポイントがお嫌いなようだ。昔、1980年代まで会社の説明会、発表会となると、OHPと決まっていた。90年代になるとパソコンとプロジェクターの普及によってパワーポイントに変わった。
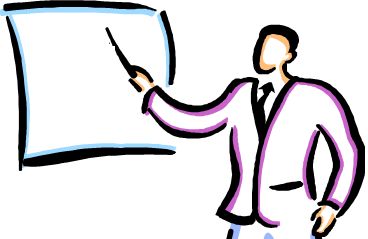
伝えたいことを誤解なく伝えるという道具として最適とは言わないが、有用であることは間違いない。単にプリントした資料を配って説明するよりもはるかに伝達効率は高く、情報を伝える上でのエラーは少ないだろう。
文明の利器は使わなければ損だ。だって話すのは自分の考えや心証を伝えるためだ。それを効率的に少ないエラーで伝えるための手段があるなら、利用することは自分のため、人のためである。
先生は昔の武士の勉強のように、ひたすら論語読むような、効果がわからない方法に精進する勉強がお好みなのだろうか?
百聞は一見に如かずという。文章だけより絵があるととても分かりやすい。絵よりも写真、白黒写真よりカラー写真の方がよい。現代は科学技術が進歩して、動かない絵から動画に、一方通行の動画からインタラクティブ(対話的・相互作用するもの)なものと進化した。
英会話なんて本を読んでも分からない。音を聞くと分かった気になる。映像を見ると分かりやすく、相手と話せば上達は早い。それは体験から分かるだろう。
英会話を会話せずに上達することは可能成りや?
さて、パワーポイントを使うことの非はどこにあるのか?
ひょっとして、著者は鍛えた話術の価値が、相対的に下がるのが嫌なのであろうか?
■著者は文章の構成も気に入らないようだ。
下記のように述べている(p.29)。
「まず最初に結論を2・3行で出す。次にその結論を出すに至った理由を述べる。最後にもう一度結論を述べる」
先生はこの文章構成が面白くないという。
注:このコンテンツでは引用文を紫色でしめす。
先生は語る。
「人が話を聞くのは、何をどうするか先が分からないからだ。それが最初に分かってしまっている。結論を先に言われたら(それ以降を)聞くのは時間の無駄である」
先生より数歳年寄りの私には何が不満なのか理解できない。
必要十分な情報を、短時間で伝達するというのが、言語の最大の、いや根本的な価値ではないのだろうか?
新しいアイデアや概念を知ることより、他人が考えあぐねたことを追体験することに価値があるのだろうか?
あそこに獲物がいるぞという情報を伝えるとき、一生懸命探したとか、太陽がまぶしくて目が疲れたとか、あいつが憎いとか、理解しなければならないのですか?
なこと言っているうちに獲物が逃げちゃいましたよ。
 |  |
そんなことを考えるのは私のような無名な爺だけではない。チャーチルが首相になった時の第一の指示は、次のようだったという。
(1)報告書は要点をかけ、
(2)要因分析などは付録にせよ、
(3)要点を記したメモを用意せよ、
(4)もって回った言い回しをせずに、一言で言い切れ、
 チャーチルの写真といえば、いつも葉巻をくわえている。あちこちに出かけると吸いさしの葉巻の火を消して聴衆に放り投げたという。すると皆この葉巻を記念にと取り合って、怪我人も出たそうだ。
チャーチルの写真といえば、いつも葉巻をくわえている。あちこちに出かけると吸いさしの葉巻の火を消して聴衆に放り投げたという。すると皆この葉巻を記念にと取り合って、怪我人も出たそうだ。
なんのために、そんなことしたのか理解できない。教えてチャーチルさん。
チャーチルが首相になったのは1940年5月10日だった。ドイツがデンマークとノルウェーに侵攻したのは1940年4月、フランス侵攻が5月、あっという間にフランスのペタン政権は白旗をあげて休戦協定を結ぶ。
バトルオブブリテン(1940/08/08〜09/15)のとき、チャーチルは報告書があまりにも繁文縟礼なので「結論を真っ先に書け」と怒鳴ったそうだ。当時は毎日イギリスの戦闘機が何十機と撃墜されていて、チャーチルは気が気でない。しかし生産の報告書はページ数ばかりある、昨日何機生産されたのか、明日は何機作れるのかを読み取るのが一苦労だったらしい
結論を最初に書いたら面白くない……頭の中はお花畑かとチャーチルに笑い飛ばされるだろう。あるいは平時の指揮官はいらぬと怒鳴られるかもしれない
バトルオブブリテンとはなにか?
フランスを抑えたヒトラーが次にイギリスを攻略するために、陸軍が侵攻するアシカ作戦を立案した。
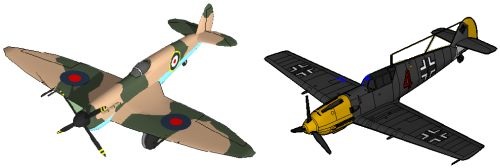 アシカ作戦の前提としてイギリスの戦闘機を撃滅する必要があり、双方がその重要性を認識して大航空戦が行われた。これが英国の興亡を決めるものとしてバトルオブブリテンと呼ばれる。
アシカ作戦の前提としてイギリスの戦闘機を撃滅する必要があり、双方がその重要性を認識して大航空戦が行われた。これが英国の興亡を決めるものとしてバトルオブブリテンと呼ばれる。
実際にはフランスがドイツに負けたとき、フランスのマキシム・ウエイガン将軍が「バトルオブフランスは終わった」と語ったことから、チャーチルが議会で「バトルオブフランスが終わり、これからバトルオブブリテンが始まる」と語ったことによる
現在バトルオブブリテンとは、イギリス侵攻を狙うドイツとそれを止めようとするイギリスの航空戦に限って使われている。
以来今に至るまでバトルオブブリテンは世界最大の航空戦と言われる。
ちなみに世界歴代二番目に大規模な航空戦はノモンハン事件と言われる。がんばれニッポン
文章にはビジネス文章・実用文章と、芸術的というか風流な小説や和歌・俳句などがある。
だが先生の文章では非実用文の価値観しか見えない。世の中の9割は実用文だろう。そして言葉が生まれたのは実用のためではなかったのか?
俳句とか詩なら、韻を踏むのに価値があるかもしれない。小説なら人によって受け取り方が違っても実害はない。だが報告・連絡・相談において、発信者の意図を受信者が読み取れないなら、それは全く意味がない。
そしていくら通信の高速化が進んでも、読むのは人だ。1000文字で済むところを、2000文字費やすのは人の時間を盗むことだ。
いかに、伝えたいことを、要領よく、短く、誤解されないように記すことが現代の文章の価値である。
ここまできて本当にがっかりした。
■先生の語ることは理解できないことが多々ある。きっと高尚なので、無学な田舎者の私には理解できないのだろう。
師曰く
「最初から結論を書くのは、およそ無理なことである。作文を書くということは、それについて考えを深めていくということだ(p.32)」
いや、まったくそうではないです!
文章を書く前に、伝えることがまとまっていなければならない。考えながら話すこともあるかもしれないが、考えながら書いたものを人様に呼んでもらうのは失礼だ。
もちろん考えるときメモを取ったり、参考文献を調べたりするのは当然である。調べた結果、現象、原因、当面対策、恒久対策などが決められる。
それらをまとめていかに相手に伝えるか、相手を動かすかが文章の目的だ。そしたらそれの起承転結を考えて文章にするのが当たり前だろう。
小説を書くのも俳句を詠むのも、まさか考えながら歌い始めるわけがない。考えてはメモし、それを良くするためにレビューを繰り返すのではなかろうか? 詩吟でも都々逸でもポップスでも歌うのは完成したものであるはずだ。
弘法大師でもなければ、目的のものを一発で仕上げることなぞできるはずがない。
■「英語でもアルファベット順を分からない人が増えているらしい(p.78)」
本当か!?
と思ってアメリカのGoogle とか漁った。学校で習うのだから、アルファベット順を知らない人はいないというのが事実らしい。
ただアルファベット順をいえるかという動画がYouTubeにあった。
アメリカ人に「Sの次の文字は何か」と聞く、すると聞かれた人は頭の中でA・B・C・D・Eと考えてからTと言っていた。多くの人はそんなとこではなかろうか。
それは知らないというのとは違うだろう。
忘れたというのではないのか?
日本だってあいうえお50音順を忘れた人は多いだろう。実を言って私も「『へ』の前の音は何か?」と言われたら、頭の中で「は」行を思いだし「はひふへほ」と唱えないと分からない。その程度のことではないか?
それをあいうえお50音を知らないとは言わないだろう。
先生!「アルファベット順を分からない人が増えている」ことの
■「すみやかに、ただちに、遅滞なく(p.133)」
著者は電車の車掌が「到着後すみやかに発車します」と語ったのを聞いて、なぜ「すぐ発車します」と言わないのかと不満である。「『すみやかに』とは『グズグズしてんじゃねえよ、このノロマ(p.134)』と言われている気がする」とおっしゃる。
先生!変なことに拘らないでくださいよ。私は法律なぞ学んだことはありませんが、公害関係で法律はだいぶ読みました。法律を理解するには、こういう言葉の使い分けというか基準を知らなくちゃだめです。
こういうのは業界用語とか専門用語というものです。それを知らなくちゃしっかりと理解できません。
注:法務翻訳のノウハウ 「直ちに、遅滞なく、速やかに」
| 種 類 | 直ちに | 速やかに | 遅滞なく |
| イメージ |
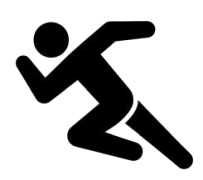 |
 |
 |
| 具 体 例 | 親父さんが亡くなった? だめだ、すぐ会社に来い | 親父さんが亡くなった? 納骨済んだら顔を出せ | 親父さんが亡くなった? 忌引き開けたら頼むわ |
天気予報を考えてみましょう。
・天気予報で夕方って何時から何時までですか?
・天気予報の「ときどき雨」と「一時雨」どう違いますか?
・天気予報の「ときどき」と健康診断の「ときどき」の意味は同じですか?
天気予報の用語というか約束事を知らないと天気予報を理解できません。もちろん健康診断のときの約束事を知らないと(以下略)それにいちゃもん付けますか?
法律を読むとか、天気予報をしっかり理解しようとか、料理を……というときは、やはり入門書を買って読むこと。そうするとそういう基礎的な用語がありますから、覚えましょう
約束事は予め言えなんて、駄々こねないでくださいね(キリッ
先生!ダメ押しです
広辞苑では「すぐ」は「時間や距離の間のないことあらわす。直ちに、さっそく、ごく近く」とあり、「すみやかに」は「早いさま、ひまどらぬさま」とあります。
|  |
これを読みますと「すみやかに」より「すぐ」の方が「グズグズしてんじゃねえよ、このノロマ」というニュアンスに近いようです。
ここはやっぱり「すみやかに発車します」が適切のようですね。
■「その音をどのようにしたら漢字で表せるかを工夫して古事記や日本書紀、風土記を作った(p.170)」
先生 質問で〜す![]()
古事記は万葉仮名で書かれたそうですが、風土記は間違いなく漢文 中国語で書いたはずです。
日本書紀の原文は中国語かと思っていましたが、万葉仮名の原本もあるのでしょうか?(ネットの情報では漢文であるが訓読みされているとありました)
上記で間違いなく該当するのは古事記だけのようです。日本書紀とか風土記を漢文で書いても「その音をどのようにしたら漢字で表せるかを工夫して古事記や日本書紀、風土記を作った(p.170)」と書いて良いのでしょうか?
もっとあるけど疲れたからおしまい。
最後にどうしても納得できないことがある。売値が1500円+税だ。
どう考えても高すぎだ。せいぜい新書で800円程度なんじゃないですか?
一度読んだらおしまい、大事に取っておくような本じゃない。
![]() 本日の心配
本日の心配
先生は「小言を言う人は上から目線で始末が悪い」とおっしゃる(p.232)。
私の駄文は問題点を指摘して改善策を述べている。
故に小言ではありませぬ。
ちょっと心配なのですが、あなたの日本語だいじょうぶ?
注1 |
「理科系の作文技術」木下是男、中公新書、1981 | |
注2 |
「マニュアルバイブル」エドモンド・H・ワイス、啓学出版、1987 「論理的思考の技法I」鈴木美佐子、法学書院、2004 | |
注3 |
若い人は知らないだろうが、石原裕次郎主演の刑事ドラマ「太陽にほえろ」は1972年〜86年まで放送された。その53〜111話に出演した松田優作の有名なセリフが「なんだこりゃ」であった。 | |
注4 |
「空軍大戦略」リチャード・コリヤー、早川書房、1976 | |
注5 |
「平時の指揮官・有事の指揮官」佐々淳行、クレスト新社、1995 | |
注6 | ||
注7 |
推薦する本に戻る
     |