お断り
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたい方には不向きだ。
よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。
ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。
私は現役時代は環境管理(環境管理というとかっこいいが、公害防止のこと)の仕事だったから、今も環境に関する本を見かけると必ず手に取り、パラパラ見て面白そうなら大体読んでいる。
図書館で環境のコーナーを歩いていたら、この本が目に入った。分類は生態学だがパラパラ見ると、里山について書いてあるようなので借りてきた。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| ★唱歌「ふるさと」★ の生態学 |
★高槻成紀★ | ★ヤマケイ新書★ | 9784635510202 | 2014/12/12 | 880円 |
| 🐇 |
「ウサギ お〜いし♪」で始まる「ふるさと」という歌は、日本人なら誰でも知っていると言っても過言ではないだろう。
サザンの桑田が最高の歌と言ったとか聞く。
この本はその唱歌「ふるさと」を
偶然にも著者は私と同じ年の生まれである。しかし彼の子供時代と原風景は私とだいぶ違う。彼は私より古い日本に生きたようだ。
この本を読んで感じたのは、語っていることにとりとめがなく、何を言いたいのか分からない。主張の賛否以前に、いったいこの著者は何を言いたいのか掴めない。
ということで感じたことをつらつら書く。
さてこの歌の歌詞と、私の子供時代の思い出と照らし合わせてみよう。
ウサギ追いし かの山、
小鮒釣りし かの川
1950年代末、私の小学生時代、我が家から6キロほど離れたところの親父の実家に行くと、道幅1メートルほどの道路とかその周囲に、野生のウサギのフンを見かけたし、冬に雪が降ると足跡は多々見かけた。たまには高い草の陰に姿を
見たこともある。
だが追いかけたとか捕まえたという思い出はない。そもそも10歳の子供につかまるようなウサギはいない。大人だって捕まえられるはずがない。
夜になると「ギャー、ギャー」と狐の鳴き声が聞こえた。
後年、家内の家に泊まったとき、狐の鳴き声が聞こえた。家内の祖父が「あれは何だか分かるか?」と聞くので「狐です」と即答すると、いたく感心していた。狐の鳴き声など、知らないと思っていたのだろう。
| 🦊 |
キタキツネなどは餌付けをする人がいるそうだが、私の知るキツネは、そんなに愛想が良くなく、人の声が聞こえるとパッと姿を消す恥ずかしがりであった。
なお、野生の狐は感染症などの危険があるから、接触してはいけない。
親父の実家の畑の周りには野ネズミがたくさんいた。これも捕まえたことがない。のろまな子供に捕まるような動物は生存競争に負けてしまうだろう。
一度リスの赤ちゃんだと思い、目も開いてない赤ちゃんを巣から何匹も捕まえてきたら、営林署に勤めている叔父が「こりゃリスじゃない。ネズミだ」と笑った。
注:ネズミ(齧歯目ネズミ科)とリス(齧歯目リス科)の違いは大きくない。元々ネズミからリスは分岐したそうだ。
見た目の違いは、しっぽに毛が生えているのがリス、生えていないのがネズミだ。
しっぽの形だけで片方は好かれ、片方は嫌われるとは、生き物は見た目が100%だ。
子供時代近くに小川はなく、小鮒など釣った記憶はない。魚を釣るには阿武隈川(日本で6番目に長い川である)に行かねばならず、危ないから子供は水遊びも釣りも禁止されていた。
遊んで良いのは浅いため池で、釣れるのはアメリカザリガニだけ。
| 🦞 |
おっと、子供時代アメリカザリガニを釣っていたなどというと、著者から日本人の心がないなんて言われるかもしれない。
著者の持つ里山のイメージは、私より10歳上、いや10年昔の感じではなかろうか。著者と私の年は同じだが、私の住んでいるところでは歌の情景は既に過ぎ去っていたようだ。
夢は今も めぐりて
忘れがたき ふるさと
当時だって都市部では高校進学率が7割近かったが、田舎では5割なかった
当時はまだ集団就職列車が走っていたが、同級生たちを集団就職列車でなく普通の汽車で旅立つのを見送った記憶がある。
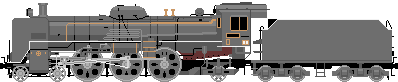
東北本線は1968年まで蒸気機関車だった
工業高校では同級生49人のうち、田舎に留まったのは10人いなかった。田舎にはろくな就職口がなく、みんな都会で働きたかった。初任給も田舎は16,000〜18,000円くらいだったが、都会は2万円超だった。私は1万7千円ちょうどだったのを覚えている。
田舎に残ったのは自転車屋など家業を継ぐとか、長男で農業もしなくちゃならないという者ばかりだった。
進学ですか? 私のクラスからは一人だけでした。1960年代の工業高校は、頭は良いけど大学に行く金がない子供の行くところでした。だから東京就職組は都立大の夜間に入るのが当然で、卒業すれば転職も予定の行動でした。
志を はたして
いつの日にか 帰らん
世はまさに高度成長期、金の卵とおだてられた中卒、高卒の若者は東京へ、東京へと流れていった。
東京に行った者たちはこの歌詞を聞けば涙したであろうが、私たち残留組にとっては「忘れがたき ふるさと」ではなく「忘れたき ふるさと」であり、「おら東京さ行くだ」という気持ちだった。
東京に出ていった者たちは唱歌「ふるさと」に感情移入したかもしれないが、著者が一般論として「ふるさと」に焦がれると思うことを理解できない。
著者が田舎で崩壊していった古き慣習や長老の序列などを懐かしく語ることに反感がある。これは単にジコチューな意見ではない。
それに都会に行った者たちだって、なぜ都会に行くのかといえば、お金だけではなかった。古い伝統、慣習、人間関係、そういう
柵が嫌で都会に出て故郷を思うとは、なんという矛盾だろう!
見方を変えると、自分たちは快適で便利な暮らしをしたいが、田舎に残った人は俺達が帰ってくるときのために古いものを大事にしろよという横暴、傲慢ではないのか?
田舎が崩壊して悲しむ人がいることを否定しないが、田舎が変化してほしいと願った人もいるということだ。そして田舎という社会だけでなく、里山が連綿と続いてほしいと思う人がいることを否定しないが、里山の価値を認めない人もいるのだ。
幸か不幸か、私は齢50にしてご赦免を許され、都会に出てきた。本当は仕事が変わって都会に出てきたのだ。
まず感じたのは暮らすのが便利なこと。医者も床屋も選び放題。言い換えると田舎では医者も床屋も選択肢がない。
しかも床屋やコンビニに行くのに車が不要だ。サンダル履きで行ける距離に複数ある。
都会に越してくるとき、床屋や歯医者にいくのに車が必要と思って、車を持っていくべきか、廃車にすべきか悩んだ。来てみれば悩んだのが馬鹿みたいだ。勤め先の同僚で車を持っている人は少ないし、免許をもってない人さえいた。車の有無の差は大きい。年間の維持費は70万くらいかかると思うが、それがゼロになる。
それに買い物に行って駐車料金を取られるスーパーがあるのに驚いた。駐車場のないコンビニがあるのにも驚いた。田舎では100台駐車可とか、大型トラック歓迎なんてコンビニは珍しくない。
都会では人間関係も面倒くさくない。家族とどこかに出かけるのに、隣近所から行先、理由、日程など聞かれる心配もない。
一度オーナー一家が住んでいるマンションに住んだが、当時同居していた娘がオーナーに会うと挨拶するのが嫌だというのに納得した。
野菜だって値段は田舎と変わらない。欠点は家賃が高いことだが、それは便利さで余りある。
では各論に入ろう。
まずは里山から考えてみよう。
自然保護を語る人は、里山スバラシイ、里山は日本の原点という発想があるようだ。著者は里山が日本の原点とは書いてはいないが、里山の崩壊を非常に残念がっている。
里山とは何だろう?
実を言って私が子供の頃、いや40歳まで里山という言葉を聞いたことがない。明治生まれの私の親父も、里山なんて言葉を使ったことはなかった。
身近で信頼できる辞書となると広辞苑だろう。昭和44年(1969)発行の広辞苑第2版に「里山」は載っていない。
最新の広辞苑ではどうか?
私は持っていないから図書館まで行って調べた。
書架に第6版と第7版があり、どちらにも「里山」は載っていた。その語釈はどちらも同じで「人里近くにあって、その土地に住んでいる人のくらしと密接に結びついている山・森林」とあった。
第6版の発行は2008年であるから、それより以前に里山は市民権を得たことになる。
里山の定義はあるのだろうか?
環境省のウェブサイトによると「(里山とは)原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域です
といって法律の中の文言ではないから定義とは言えない。
憲法や法律では「里山」を使っているだろうか?
電子政府で全文検索をした。法律、省令、規則で29件ヒットした。
内容を見ると、地名が4件あった外はすべて平成10年の制定、改正のものであって、以下に示す同文において定義なしで使用していた。
環境要素に係る選定事項については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。
![]()
里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
条文を読むと、定義がなくても、里山への該否とか定義が争点になることはなさそうだ。
里山という言葉がいかに広まってきたかと研究した方もいる。
研究によると「里山」という言葉が現れたのは17世紀後半だそうだが、「深山」に対する言葉として使われたとある。
そして驚くことに1970年代に某森林生態学者によって「村里に近いヤマ(農用林)をさす指す言葉として提案された」という
里山とはわずかこの50年間に使われるようになった新しい造語であった。
話は変わるが、明治維新前後の写真を見ると集落近くの山(高くなっているところ)は、9割方ハゲ山である。もっと古い写真があれば良いが、残念ながら銀塩写真が発明されたのは1839年である。
だが写真ができる前の北斎(1760-1849)の版画を見ると、人の住む周辺の野山は草地であり、木々が生えそろっている情景はめったにない
つまり明治維新前には、今 里山と言われる様相の林はない。里山は人が作った。それも江戸時代とかもっと前でなく、明治以降の話である。
つまり今言われる「里山」という概念は150年前の明治維新前は存在せず、「里山」という言葉が現在の意味でつかわれるようになったのは半世紀しかないということだ。
そして大事なことがある。
このいわゆる「里山」というものを作った当時の人たちは、素晴らしい生態系を作ろうとか、子供たちの情操教育のためとか、心が和むからと作り上げたわけではない。
売るために炭を焼く、そのために雑木林を定期的に伐採する。日々の
このとき伐採量と再生産量が一致したことにより、草原が林になり林が一定量に維持された。それは我が国が日本海の東側にあったという偶然のおかげだ。日本が多雨なのは日本海のおかげだ。もしユーラシア大陸の東端であったなら、雨が少なく木材の再生産量は少なく、バルカン半島と同じく、あるいは黄河上流と同じく、木々のない土くれが広がる風景になっただろう。
人がそのバランスを考えて炭焼きをしたとは思えない。人間がそういうことに気遣う性質があるなら、バルカン半島やヨルダンやレバノンにも森林は残ったはずだ。だから私は偶然に過ぎないと思う。
| 🍄 |
要するに誰かが里山を作ろうとしたわけでなく、自分たちが生活するために木を切ったり歩き回ったりした結果、里山と呼ばれるものができたのである。
そして生活様式が変わって山の幸が不要となり山に入らなくなったから、里山と呼ばれる姿から変わってきた、それだけのことだ。
里山の様相が変わったのを見て、里山が崩壊するとか、里山を守れという発想はどうしてなのだろうか?
それって大きな盆栽を維持しようとしているだけじゃないの? その盆栽は誰のためなのだろう?
山は青き ふるさと
水は清き ふるさと
この歌詞って、年に数回来る人の発想だよね。そこで暮らしている人は、早いところ宅地造成してもらいたい。そうすれば道路も広く舗装されるだろう、家も会社もできて過疎にならなくて済む、ウチの土地の値段も上がり売れたらいいな❤
第三者の観察者である著者が、里山が失われると生態系も失われると嘆く気が知れない。
里山の生態系というのは里山が成立してのことであり、里山がなかった江戸時代には別の形の生態系があったはずだ。里山ができて失われた生態系は嘆かないのか? 里山以前の生態系になることを喜ばないのか?
里山がなくなるのは困るというのは、科学ではなく人情でしかない。
 話が変わるが、私が福島にいたころ、東京電力が超高圧送電の試験とかすると、都会からぞろぞろと反対者たちがやってきて「超高圧送電、ハンターイ」とやっていた。
話が変わるが、私が福島にいたころ、東京電力が超高圧送電の試験とかすると、都会からぞろぞろと反対者たちがやってきて「超高圧送電、ハンターイ」とやっていた。
地元民は警察とか出てきて騒ぎになって困っていた。騒ぐなら東電本社前でやれ。田舎に迷惑をかけるな。
里山信者はそれと同じにしか思えない。
そもそも地元民にとって里山が必須なら、何も語らずとも里山は維持されるはずだ。維持されていないということは、現状を維持する必要がないからだとなぜ考えないのか?
真に里山を守り(維持)たいなら、ぜひとも故郷を遠くから眺めるだけでなく、里山近くに住み、常日頃里山に入って薪を取ったりキノコを採ったりしましょうね。
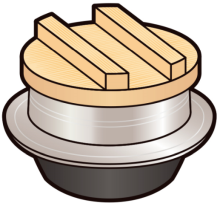 |
|
| 釜と鎌の違いは分かる? | |
ガスや電気釜を使わず、羽釜で煮炊きしてくれないと困りますよ!
まさか羽釜を見たことがない人はいないよね。まして羽釜を知らずに、里山を守ろうなんて言うはずがないよね?
そのように里山を愛してくれれば、地方活性化に貢献するだろう。
ここで終わっても良いのだが、いろいろ気になることがあるので記す。
 古い
古い
 だけど稲刈りしていてマムシが顔を出すのは気に入らない。いや、命に関わる。
だけど稲刈りしていてマムシが顔を出すのは気に入らない。いや、命に関わる。
稲刈りしていて、私の手のそばにマムシが顔を出したとき、家内の叔母が鎌でマムシの首を切り払ったので助かった。
義叔母は旦那さんから「首をはねると飛んだ先で噛みつくから、胴体を抑えるようにしないとだめだぞ」と叱られた。
2025.02.23追加
私の危機を救ってくれた義叔母は、2024年暮れに亡くなったと聞いた。享年92歳。
既に彦も高校生となり、大往生だろう。
後顧の憂いもない義叔母は、天国で農作業をしているのだろうと少しほっこりした。
私は蛇の頭を見たとき、持っている鎌で切るという発想が浮かばず、噛まれたら血清のある病院まで20キロかと思ったのを覚えている。血清投与は3時間以内というから、交通渋滞でもなければ十分間に合う距離ではある。
当時の勤め先の人がマムシに噛まれたことがあり、噛まれたときどうだったか聞いた。噛まれた後も、血清を打った後もとんでもなく痛いと言っていた。
最近は血清でなくセファランチン錠剤らしい。
田んぼにカエルや蛇がいるのが正常だと簡単に言ってほしくない。カエルも蛇も生きているが、私のようなパート農民も生きているのだ。
お前は稲刈りをしたのかと問われるか?
 結婚した頃、家内の家は現役の農家だったので、毎年
結婚した頃、家内の家は現役の農家だったので、毎年
だが2年ほどしたら、もう来なくてよいと言われた。働きに対して酒を飲みすぎるのがいけなかったらしい。
残念ながら、これは本当だ。
「奇跡のリンゴ![]()
この本は2014年に書かれているが、そういった批判を間違いと考えたのだろうか。
調べて気が付いたのだが、奇跡のリンゴを実現した木村氏も著者も私も、同じ年生まれであった。
著者の考えを問いたいことは多々ある。
農薬を多量利用(p.109)、圃場整備(p.102)、水の多量利用(p.121)、冷暖房(p.197)、旬の時期以外にハウス栽培のものを食べること(p.198)、などを批判している。そういった暮らしの変化と著者の意見の是非はとりあえずおいておく。
私は問う。そういう変革はなぜ起きたのか考えていないのだろうか?
高度成長というのは豊かな楽な暮らしをしたいというのが原動力だ。それを悪いというのか?
冷暖房によって住環境が良くなり、腹いっぱい白米が食べられるようになり、冬も新鮮な野菜を食べて栄養を取り、毎日お風呂に入る生活ができるようになり、日本人は健康になり寿命も延びた。著者が74になっても元気なのはそのおかげだ。
まさか私と同じ年の著者は、子供の時から白米を食べていたとか、お風呂には毎日入っていたとか、家には水道があったとか、冬には部屋の暖房があったとか言うのではないだろうね。
![]()
 子供の頃、我が家の飯は大麦の押し麦100%だったが、中学になった頃には米と半々の食事になった。麦飯はすぐに臭くなり、弁当を食べるのは正直嫌だった。
子供の頃、我が家の飯は大麦の押し麦100%だったが、中学になった頃には米と半々の食事になった。麦飯はすぐに臭くなり、弁当を食べるのは正直嫌だった。
白米100%が食べられるようになったのは1970年以降だろう。
![]()
子供の頃、銭湯まで15分ほど歩いた。もちろん毎日なんて入れない。週に2回か多くて3回だった。下着もそれに合わせて二日か三日着た。住んでいた長屋は土地が悪くて井戸が出ず水道だったが、30戸以上あった長屋の中央に蛇口が10個くらいある水場があり、そこに行って炊事や洗濯をした。
![]()
冬の暖房といえば練炭の炬燵だった。火鉢なるものがあると学校で習ったが、大きな商店で見た長火鉢しか知らない。
![]()
そう考えると、この著者は相当良い暮らしをしていたのではないだろうか?
きっと庶民ではない。
ちなみに古来より人間の寿命が延びてきた要因は、医療よりも住環境を含めた衣類、栄養、そして清潔だそうだ。まさにそれを実現してきたのが戦後日本である。
1960年頃、私の祖母が76歳で亡くなったとき、お坊さんが「これほど長生きした人は珍しい」と語った。そういう時代が良いのでしょうか?
高度成長期、日本人は皆、明日は良くなると坂の上の雲を目指したのではないのか?
あなた、奇跡のリンゴ、そして私が生まれた1949年の平均寿命は63歳でした。
著者はそのとき短命でも良い、貧しくても良い、古くからの暮らしを続けようと思ったのだろうか?
ウサギを追い、小鮒を釣って、農薬を使わず、圃場整備をせず、水を節約する暮らしをしたいなら、それでも良い。ならば1960年末から、そういうことを声を大にして叫ぶべきだった。ええかっこしいはいけないよ。
そして2012年頃に、この本を書く2014年前に天寿(1949年の平均寿命)をまっとうし、臨終を迎えたわけだ。
それもひとつの生きる道ではある。
私は選ばないけど。
快適な暮らしをしようとするなら、代償を払うのは必定だ。道路を作れば野生動物は轢かれることもあるだろう。それを防ぐには動物の橋を作ったりトンネルを作ったり、あるいはサンクチュアリをつくるとか費用が掛かる。
著者のように考えるなら、お金をかけても良い。ならば前述した動物保護策を土地開発や道路建設と同時にしろと言うべきではないか。愚痴るのは止めよう。
いや今からでも良い、愚痴るのではなく動物保護のための施策を主張すべきだ。
本に書くだけで自己満足してはいかん。
だが無制限に動物保護の施策を打つのは不可能だ。だから妥協できる範囲で手を打ち、そこから先は救えない、絶滅する動物があってしょうがない。
例えばトキはつがいがいればよいのではない。田園、豊富な餌、冬も水を張った田んぼ、そういう環境があって成り立つのだ
それから原発事故と里山の荒廃を抱き合わせて書いていること(p.173)は、ちょっと違うのではないか。原発事故のために避難地域になって里山が荒れたと言われても、あたおかとしか言いようがない。それじゃ、里山保全要員として志願者を配置するんですか?
原発事故によって運命が変わってしまった人は数多い。自然だって影響を受けるのは納得しなさい。
注:東日本大震災で福島県で原発が被災したことで、金のない県に原発を作って東京に電気を送っていることに憤った人もいたかもしれない。
 だがちょっと待ってほしい(朝日新聞調)
だがちょっと待ってほしい(朝日新聞調)
福島県で水力・火力・原子力によって作られた電気の78%は東京に送られているという事実を知ってほしい
それがいけないとは言わないが、その代わりもっと、いやほんの少しでも福島県の雇用を考えてほしい。
できるなら福島県から持ち出している電力の1割くらいを消費する工場を福島県に作ってほしい。すぐに10万人くらいの雇用が生れるだろう。
そういうことに思い至らず、里山を守れとか好き勝手なことをぬかす人はエゴにすぎない。
この著者はいろいろと問題点、疑問点をあげる。個々に捉えるともっともなことばかりだ。
だが世の中、あれも大事、これも大事と言われても、彼方立てれば此方が立たぬのだ。
大人なら、これは必須だからやろう。その代わりこれはやらない。これは切り捨てる。そういうことを決めないとならない。
諦めることを受け入れられなくちゃならない。トリアージだ。
駄々をこねるのは恥ずかしい。
私は「ふるさと」に描かれた風景があるべきものとは思わない。
私は昭和24年生まれである。貧乏でおもちゃもなく、小学に入る前から遊びと言えば歩いて数分のところにある雑木林(里山なんて呼ばれていない)で、
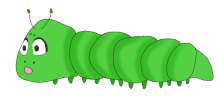 クモをつかまえたり芋虫をつかまえたりということをしていた。
クモをつかまえたり芋虫をつかまえたりということをしていた。
雑木林といっても平たんではなく凸凹がある。土手の上から頭から落ちて気を失っていたこともある。だいぶ経ってから近所の遊び仲間が見つけて、大人を呼んでくれたそうだ。幸い死にもせず、頭がおかしくなることもなく今まで生きてきた。
実を言ってそんなことになったのは私ばかりではないし、私も三度ほど経験がある。
「そんな危ないところダメよ、公園で遊びなさい」そんなこと言われたら笑いますよ。
終戦から10年そこそこ、国も自治体も貧乏で公園なんてありません。私の住んでいるところで、市のごみ収集が始まったのは1960年代末です。それまでは燃えるものは庭で燃やす。燃えないものは庭に埋める、雑木林に捨てる、竈の灰なら道路にまく、今なら不法投棄だね。当時は市も手が回らず自家処理してくれと言っていた。庭で燃やすときは消防署にごみを燃やしますと連絡する。すると消防署も「水を入れたバケツをわき置いて、気をつけてください」でおしまい。
サッカーをやれとは言わないよね。皆貧乏だからボールひとつないのよ。
それに当時は母親も働かないと一家食っていけません。小学前でも5歳くらいになれば、家で待っててねと言って仕事にいきました。5歳児は下の子の面倒を見るわけよwww
私より4つ上の姉は、私を背負ったら私の足が床についたと今でも笑う。そんな時代もあったよ。13歳未満の子供を一人で置いてはいけないなんて笑っちゃうよね
もちろん子供を危険な目に合わせたくはない。
野生動物が直接的に人に危害を加えるほかに、病原菌、寄生虫など危険がいっぱいだ。破傷風、ツツガムシ、スズメバチ、血を吸うヒル、漆の木、それらは話の上だけでなく、友人、同級生、同じ地区の住人が被害を受けた身近な危険だった。
![]() 本日の檄
本日の檄
著者は私と同じ年であり、著者がこの本を書いたのは10年前の2014年である。まだ64歳で年寄りの繰り言を語るようではしょうがない。シャキッとせい。
同年の爺から言う。振り向くな、前を見ろ。
注1 | ||
注2 | ||
注3 | ||
注4 | 「森林飽和 国土の変貌を考える」太田 猛彦、NHKブックス、2012 | |
注5 |
相州箱根湖水、甲州三坂水面、甲州犬目峠、下目黒など | |
注6 |
「奇跡のリンゴ」石川拓治、幻冬舎、2008 | |
注7 |
「「環境」都市の真実 江戸の空になぜ鶴は飛んでいたのか 」根崎 光男、講談社α新書、2008 | |
注8 |
推薦する本に戻る
うそ800に戻る
     |