お断り
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたい方には不向きだ。
よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。
ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。
「人は学び続けなければならない」とは、福沢諭吉が「学問のすゝめ」で語った有名なことば。
とある本を読んでいたら、ちょっと興味があることが書いてあり、参考文献として福沢諭吉の言葉をタイトルにした本を挙げていた。
私は本を読んでいて気になることがあれば、その出典を調べるという習性がある。ということで斎藤孝という人が書いた「人はなぜ学ばなければならないのか」を読まねばと思った。
いや、ほんとのことを言えば、別に出典まで調べることもないのだけどね。
とうに現役を引退した私は、本は買うものでなく借りるものである。市図書館にあるだろうと蔵書検索しようとして図書名を忘れたことに気が付いた。それでも著者名と著書名が福沢諭吉の冒頭の文句の一部だったことは覚えていたので、「斎藤孝+学ぶ」で検索した。すると図書館蔵書だけでも驚くほどざくざくとヒットした。
| 書名 | 出版社 | ISBN | 発行年 | 価格 |
| 図解 学問のすすめ カラリと晴れた生き方をしよう |
ウェッジ | 978-4863102378 | 2021 | 1,540円 |
| 学ぶための教科書 | 辰巳出版 | 978-4777825738 | 2020 | 1,340円 |
| 13歳からの「学問のすすめ」 | ちくまプリマー新書 | 978-4480689863 | 2017 | 924円 |
| 人はなぜ学ばなければならないのか | 実業之日本社 | 978-4408456188 | 2016 | 900円 |
| NHK「100分de名著」 福沢諭吉 学問のすゝめ |
NHK出版 | 978-4140815236 | 2012 | 1,000円 |
| おとな「学問のすすめ」 | 筑摩書房 | 978-4480878458 | 2011 | 1,650円 |
| こども「学問のすすめ」 | 筑摩書房 | 978-4480878465 | 2011 | 1,650円 |
| 人はなぜ学ばなければならないのか | 実業之日本社 | 978-4408108834 | 2011 | 1,500円 |
| 学問のすすめ 現代語訳 | ちくま新書 | 978-4480064707 | 2009 | 902円 |
注:「斎藤孝+学ぶ」でこれ以外にもヒットしたが、あまり古い本ではないだろうと考えた。
多作な著者のようで、諭吉関連ばかりでなく著書が数多くある。100件近く書いているのではないか。図書館蔵書だけで60件を超えている。
諭吉関連は2010年頃がピークでそれ以降ガタッと減っている。もう書くのに飽きたのか、書くことがなくなったのか?
タイトルがうろ覚えで、どれがどれだか分からない。しかし「おとな」とか「こども」とか「年齢」はタイトルになかったのは間違いないのでそれらを除き、これかなと見当をつけて「学ぶための教科書」と「人はなぜ学ばなければならないのか」の2冊を借りてきた。
福沢諭吉の解説本かあるいは現代流の解釈でもされているのだろうかと、ノートとポストイットを脇に置き期待して読み始めた。
 |
私は集中して読むと非常に速読になる。関心がないと速さを維持できない。
まずは「人はなぜ学ばなければならないのか」を読み始めた。最初の50ページは息も切らさずに読んだが、50ページで息切れというか集中できなくなった。
理由は簡単だ。つまらないからだ。
だが、せっかく読み始めたのだから後半に素晴らしいことが書いてあるかもしれないと、我慢して読み続けた。最後まで読んで、ポストイットを貼った数も10か所くらいだし、ノートのメモも数件しかなかった。要するに大したことがなかった。
普通ならもう満腹、読まなくて結構ですとなるのだが、せっかく借りてきたことだし、これから素晴らしいことが書いてあるかもしれないと期待して「学ぶための教科書」も最後まで読んだ。
結果は、つまらなかった。
読んだ後、なぜつまらないか考えた。
それは簡単だ。面白くないからだ。面白いという意味はギャグとかコメディということでなく、知的な情報があるかどうかだ。知らなかった知識や考え方とか、そういうのがなければ読む甲斐がない。いや、知らなかった知識とか新しい考え方を知るために本を読むのではないだろうか。学ぶってそういうことだよね?
もちろん詩とか絵画などはまた別の価値観があるだろう。
論文で大事なことは新規性、有効性、信頼性と言われる。人によりそれに了解性を加えて四要素という人もいる。
書籍も同じだろう。過去に知られているものばかりで新しい情報がなければ書く意味がなく、書いてあることが証拠などに裏付けられていなければフィクションである。そういうものを読めば、期待が裏切られること間違いなしである。
もちろん小説なら証拠や根拠がなくても面白ければ良い。また読んで楽しければ有効性は十分あるだろう。
だがこの本はタイトルから見て真面目なお話であろうし、読者はそう受け取って読むだろう。新規性と信頼性は必須条件だ。
いろいろ考えると問題は三つあると思う。
●その1
一番目に章立てが構造化されていない。
もしかしてこれは書籍として書かれたものでなく、斎藤教授の講義を録音してワープロ起こししたものなのだろうか?
それなら事前に内容を決めておいたとしても、実際の話は流れや聴講者の反応で話を端折ったり繰り返したりということがあるだろう。
そう思って本のまえがき・あとがきを見たが、いついつの講義録とかの記載はない。書きおろしのように思える。
ともかく前述の了解性において問題ではある。1冊の本の中で章が進んでも、似たようなことを繰り返しているだけだ。そしてどこから読み始めてもよく、ひとつの章だけ読んで終わっても良いという、病院などの待合室向きの本という感じだ。
●その2
次にもっと重大な問題は、何を語っているのかが分からないことだ。
メインテーマである「学ぶ」であるが、何を学ぶのか、対象者は誰かが分からない。
具体的に言えば学生に学べと言っているのか、青壮年に学べと言っているのか、高齢者に学べと言っているのか、定かではない。そして読んでいくと、場所により学べという対象がどんどん変わっていく。
思うのだが学ぶのは大事だとしても、年代や立場により学ぶことが違うだろう。学生なら専攻をしっかり学んでほしいとかリベラルアーツも身に着けてほしいとかいうだろう(例えばだ)。
青壮年なら第一義に仕事の知識、経験を身に着けてほしいし、社会生活特に家庭での家事や育児を男もしっかりと学ぶ必要がある。
およそ本を書こうとするなら、年代、立場、指向、などによって学ぶべきことも、学問、常識、趣味、教養などを明確にして論じることは重要だ。
そういう考慮するべきことを明確にして、高齢者はいくつになっても学ばねばならないと書かないと趣旨は伝わらない。
特定の年代や人を対象にしていない全年齢層が対象というなら、それならそれで、そのように書かねばならないだろう。
そしてまた学びとは、生きるための手段なのか、人として向上するため・あるいは知的好奇心を満たすためなのかがはっきりしない。実際には両方だろうが、この先生はそういった区分をせずに語るから、訳が分からなくなってしまう。
まさに曖昧を敵にしては神々の戦いもむなしく、ましてや人間がなにかことをなしえるはずがない。
●その3
書いている内容に疑問が多々ある。
例として、あるところでは日本人は学校を出ると学ばなくなると語り(その根拠は書いてない)、あるところでは学生は学ばないと語る(同前)。となると日本人は学校を出る前から学んでいないことになるが? 矛盾であるが単なる書き間違いとも思えない。
著者は確固たる考えとかデータベースがあり、それを基に書いているとは思えない。その時の気分、思い付きで書いているのか?
それから大人になると学ばないと書いていることについて、これも根拠不明である。
大人、仮に20代から40代のフルタイムで働いている男女としよう。そういった人は学んでいないのだろうか?
学ぶというのはどういうことなのか?
私の見解だが、「Study」であれば勉強という意味で、学問を座学で学ぶということだろう。
しかし「学ぶ」とはもっと広い概念だ。修行の末に悟りを開くのも、現場作業において
私の経験だが工場の現場にいたとき、夏季連休前にA4サイズで厚さ数センチもある電話帳のような新設備の資料(書籍)を何冊も与えられ、夏季連休に設置するから休み明けには動かせるように勉強しておけなんていわれたことが何度もある。それが学びでなくて何なのだ?
もちろん読解には四苦八苦する。300ページの仕様書や取扱説明書が3冊として、合計900ページだ。夏季連休が8日あったとして、一日100ページくらい理解しないと休み明け大変なことになる。そして実際に機械を動かすまでの休み明けの数日は焦りと緊張で汗ぐっしょりになった。ちゃんと動かすには半月はかかったけどね。あんな無理偏に拳骨と書くようなやり方では、垂直立ち上げは無理だ。
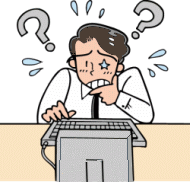 1980年頃16ビットパソコンが出たときだが、同僚はパソコンと取説を与えられ、これを使って日程計画を立てるようにしろと上司に言われて途方に暮れた。
1980年頃16ビットパソコンが出たときだが、同僚はパソコンと取説を与えられ、これを使って日程計画を立てるようにしろと上司に言われて途方に暮れた。
彼は艱難辛苦の果てマルチプランでなんとかそれらしいものを作った。担当者の努力は評価するけど、やらせ方は評価しない。
高校の同級生などに聞くと、どの会社もそんなものらしい。学ぶどころかもう試行錯誤の研究といえるレベルだ。
ということで働く人は常に学ぶことを強要されている。そういうのは仕事であって学びではないという理屈はない。
そういうのを学びの範疇から外して、純粋な知的好奇心から学ぶことのみが対象だとすると、現役世代は学ぶ暇はないだろう。
仕事のことでも学ばない人もいるだろうというかもしれない。そりゃいるかもしれないが、多くの人は仕事上 学ばなければならない状況にある。いや、自ら己の力量を向上させようと努めている人たちしか私は知らない。
私は引退後、老人クラブの役をしていたときは、市の補助金や申請手続きを知らず、市役所に電話やメールやじかに行って相談した。けっこう手間暇がかかり大変だった。
マンションの役に就いたときは、大規模修繕工事について本を読んだり、既に大規模修繕工事を行ったマンションを訪ねて教えを乞うたりした。
そういうことは学びではないのだろうか?(反語だよ)

家内の友人の夫が、定年退職してからシルバー人材センターに登録して、市の公園整備の仕事をしている。
枝を払ったり落ち葉を片づけたりなど、誰でもできる簡単なお仕事と思ってはいけない。植木にして良いこと悪いことをしっかりと知らないとならない。
そのためには職場の講習だけでなく、自腹で園芸とか剪定などの勉強をしている。まさに70の手習いである。
蛇足であるが、彼は奥さんでも女子高生でも知っている大企業の部長さんであった。
定年後、ガードマン会社に入った知り合いがいる。工事現場の道路で棒振りをしていると自嘲していたが、
 話を聞くと簡単ではない。
話を聞くと簡単ではない。
道路で交通誘導をするには、1か所に1名以上交通誘導警備業務検定資格者がいることと法律で決まっているそうだ。その人の指揮の下で動く人は資格がなくてもよいが、実際には多数の工事現場があり、多くの人が資格を取っていないと仕事が回らないという。それで勉強しているという。
試験の難易度は論点ではない。人は生きていく上で常に学ぶことが求められている。
郵便配達が書留を玄関まで配達に来てくれたので「お疲れ様です。大変ですね」と労わると、日本人は楽だという。今は中国人が増えて受付とか配達に関する会話を、中国語ができないとダメなんですという。寸法が大きすぎるとか、荷造りがしっかりしていないとか、依頼者に伝えられないと仕事にならないという。
それでテレビ講座で学んでいると語った。驚いた。
郵便の人ばかりでなく、宅配便の人たちも勉強しているのだろうか? マンションでは郵便でも小荷物でも宅配ボックスに入れてもらうので、自宅まで配達してもらうことはめったになく、そういう話を聞いたことはなかった。
街を歩けばポルトガル語も聞くし、フィリピンのタガログ語も聞こえる。そういう言葉も学んでいるのだろうか?
一般人は学ばないなんて語る著者は、現実に学んでいない。
大きなことではないが気になったのは、この先生は常識という言葉をどう理解しているのだろうか?
常識とは昔からある言葉ではない。これは英語のcommon senseの翻訳語である。
多くの人は「常識」を、ニュース、流行歌、芸能人などを知っていることと理解しているが、それは違う。常識とは現実に起きるいろいろな事柄を合理的な方法で考え、判断し、行動する能力である。
注:安い国語辞典ではどうか知らないが、広辞苑にはしっかりとそう書かれている。
ロングマン英英辞典ではthe ability to behave in a sensible way and make practical decisionsとある。
言い回しはいろいろあるが、流行歌や芸能人を知っていることではない。
この先生は「(小学生なら)一定程度の漢字が書けるとか、計算できるというのが一般的な常識です(学ぶための教科書 p.21)」と語る。
そうだろうか?
読み書きとか計算とは、abilityじゃないのか? common senseとは違うぞ、
|
||||
|
|
||||
|
|
先生の考える常識はワイドショーを眺めていれば身につくだろうけど、真の常識を得るには思索が必要だ。
昔、大宅壮一が一億総白痴化といったくらい、テレビは低レベルのマスメディアなのである。
まさか、その程度のことを学ぼうと語っているんじゃないよね?
![]() 本日の要約
本日の要約
この本を読むのは時間のロス以外なにものでもない。学ぶ時間を無駄にしてはいけない。
この本を読むなら、ぜひとも下記の現代語訳「学問のすすめ」を読んでほしい。
注:「学問のすゝめ」、福沢諭吉・檜谷昭彦(訳)、三笠書房、2001
しかし、1冊の本を読めば、そこで引用している本を何冊も読む、その結果つまらない本だと判明したとは、私はなんと無駄な生き方をしているのだろう。
生き方を学びなおさねばならない。
推薦する本に戻る
     |