お断り
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたい方には不向きだ。
よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。
ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。
ちょっと事情があって田舎に行くことになった。往復の新幹線で何か読むのはないかと本棚の未読本の山から、これを1冊選んで出かけた。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| SDGsエコバブルの終焉 | 杉山大志 |
宝島社 | 978429905549 | 2024/06/28 | 1430円 |
もう地球温暖化懐疑論は廃れたかと思っていたが、未だ沈黙せず頑張っている方々であった。とはいえ宝島社から出すあたり、もう大手は相手にしないのかもしれない。
杉山大志編集となっていて、いろいろな専門家が地球温暖化への懐疑論、SDGs批判論、世の中でメジャーになっている環境の論や説に対して様々な観点から反論を語る。いずれも温暖化懐疑論を語るから、主流ではないようだ。いや、こんなことをしていると冷や飯食いだろう。
大声で「CO2ガー」とか「温暖化地獄ダー」と叫んでいると、テレビにも呼ばれるし、大学でも幅っていられるだろう。だがその昔、多くが太陽は地球を回ると信じていたとき「それでも地球は回る」と語った人もいた。
最後に笑うのは誰か?
この本を書いた13人の侍に笑って欲しい。
元々、杉山氏はIPCC
この本は2024年編集・発行で、彼を含めて13名がそれぞれ独自に論を書いている。
2022年には「SDGsの不都合な真実」を13名で書いている。
表紙を開いてすぐの遊びと呼ばれる紙の裏側、目次より前に記載されている「はじめに」に、もう結論が書かれている。
「ごく近い将来、気候変動はもはや国際的な『問題』ですらなくなるだろう(p.4)」
これがこの本の結論である。
私は地球温暖化が正しいか否かに関わらず、既に地球温暖化は国際的な問題から滑り落ちていると思っている。
重要なことだから地球温暖化の定義を確認しておく。
これが日本の定義である。法律ですから議論するなら、この定義を使いましょう。
国際的には今は「地球温暖化」ではなく「気候変動」という呼称に代わっている。気候変動に関する国際連合枠組条約の定義も、「地球温暖化」から「気候変動」と変わっている。
海外での一般的呼び方や国連の定義が、「地球温暖化」から「気候変動」に変わっても、日本では呼び方を変えていない。 というのは日本では呼び方を変えるだけでも法改正が必要となり、温対法の名称を変えるだけで法律39本、施行令・省令を合せると103本の改正が必要となるので、変えないそうです。
温対法を引用した法律や施行令を数えたのかと問われますと、YesでありNoであります。
電子政府
上記を読めば、地球温暖化とは「地球が暑くなってきた」ことではないことが分かる。また産業が活発になって、その排熱により地球が温かくなってきたとも違う。
人間活動により地球の大気に温室効果ガス(水蒸気やCO2等)を増やしたことによって地球全体が温かくなることを言う。
だから太陽の活動によって暖かくなる、原子炉の排熱で温かくなる、火山が爆発して暖かくなる、野生の牛やヒツジ、シカなど反芻動物
「牛が出すメタンが地球温暖化させる」というのは、正しくない。正確には「人間が飼っている牛の出すメタン排出がふえて、温暖化させる」です。野生の牛やシカが出すメタンは人間の管理外ですから、ノーカウントです。
![]()
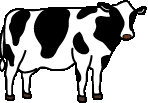 じゃあ、牛を牧場で飼わないで野生で生かしておいて、それを狩猟して食料にすれば統計上のメタン排出量は減るのかとなると、「Yes」です。
じゃあ、牛を牧場で飼わないで野生で生かしておいて、それを狩猟して食料にすれば統計上のメタン排出量は減るのかとなると、「Yes」です。
もっとも統計上のメタン排出は減っても実質は変わらず、統計上の温暖化ガスが減っても温暖化は止まらない。
![]()
おかしいと言ってはいけません。定義からそうなります。
でもさ、火山の爆発とか太陽の変化で地球が高温になっても、地球温暖化とか気候変動と言わないのは、ちょっと変だよね(笑)
「地球温暖化は国際的な問題から滑り落ちた」と聞くと、じゃあ、地球温暖化は解決したと思うだろう。
そうではない。地球温暖化が正しいにしろ間違いにしろ、そもそも国際的な問題になったのは、国際政治の環境変化によってだった。自然環境ではない、国際政治の環境である。
 ソ連崩壊は1991年だったけど、実際には1986年のチェルノブイリ原発事故からソ連がおかしくなり……いやいや、ソ連がおかしくなったのはそれより前の1981年にレーガンが大統領になってから、「力による平和」政策でアメリカをはじめとする西側諸国の経済や軍備に、ソ連が追いついていけなくなったからだ。
ソ連崩壊は1991年だったけど、実際には1986年のチェルノブイリ原発事故からソ連がおかしくなり……いやいや、ソ連がおかしくなったのはそれより前の1981年にレーガンが大統領になってから、「力による平和」政策でアメリカをはじめとする西側諸国の経済や軍備に、ソ連が追いついていけなくなったからだ。
それは国力である。社会主義を半世紀もしてきたソ連は、自由競争で弱肉強食の経済活動をしてきた国々に国力で勝てなかったのだ。
ともかくソ連という体制は崩壊し、中国と北朝鮮を除いてソ連と東側諸国は社会主義を放棄して資本主義に切り替えた。
それで冷戦は終わって体制の違いによる衝突はなくなり、世の中は変化のない安定した世界になるだろう、それはまさに歴史は終わったと考えた人もいた
実際、それは喜ばしいことだ。1960年代は、いつ核ミサイルが飛び交うかと、子供心にも私は恐怖の日々だった。
しかしそうなると次の戦いの場はどこか? そう考える人たちがいた。世界中の政治家、投資家、事業家はビジネスの場を探した。
それが環境である。現在が問題であるなら、それを改善する需要がある。その分野でコンペティターを叩きのめせば次の一世代は勝者でいられる。
そう考えたと思う。
この本では、はっきりと地球温暖化は政治問題であった、それは先進国が支配を継続させるためであったと書いている。そうかどうかは私が判断できるわけではないが、そうだろうとは思う。
いや善意に解釈すると、今まで冷たい戦争でできなかった環境保護をしようとしたのだろう。
1990年からの動きを見ていると面白い。
リオ会議は1992年だった。
世界中で環境問題が騒がれ、企業は環境方針を作り環境報告書を発行した。
心配事がなければ作ればよい。鉛の害を取りざたし、化学物質の危険性が言われ、海面が上昇してツバルが沈むと騒いだ。
オゾン層が破壊されるとなって、世界中のエアコンの冷媒が切り換えられた。
全て巨額のお金が動く。経済活動には大変良いことだ。
勿論そのお金は消費者が負担するのだけど。
そして最大の切り札が地球温暖化だった。人間に限らず世界中の動植物の命の危機だと、生態系を人質にした勝負だから絶対に負けない。
再生可能エネルギー、風力、水力、太陽光、地熱、今まで小規模に利用されていたものを大々的に取り入れようという。
悪い意味ではなく、この世の中、すべてお金である。
太陽光発電が離島とか海のブイなどにしか使われていないということは、高くつくからだ。ガソリンエンジンが電気自動車や蒸気自動車を駆逐して20世紀の覇者になったのは、経済的で力強く機構や燃料供給が他と比較してハードルが低かったからだ。
要するに再生可能エネルギーに切り替えようということは、利用者が負担する費用が大きくなるということだ。
太陽光を普及させようと、屋根に太陽光パネルを付ける人には補助金が出る。その補助金は誰が払っているかというと、太陽光パネルをつけない大多数が電気料金に8%前後上積みされて強制的にとられている。

「電気代が高いわ、ひと月13,535円も取られているのよ
お待ちなせい、あなたが払っている電気代の8%は、どこかで誰かが屋根に太陽光パネルを付けるときの補助金です。
実際の電気代はその9割の12,400円ですよ。
環境保護のための施策(?)がスイスイと進んで、環境に良いこと(?)が実現されお金が回れば、見かけだけでもみんなハッピーになっただろう。だがやろうとした環境保護のための施策は今までコストとか技術で、実用化されている技術より劣っていたから実用化されてなかったわけだ。
太陽光発電は、電線が引けない孤島とか海上のブイなどには以前から採用されていた。だが太陽光発電の短所はとにかく場所を食うことである。
原発とか火発とか面積は必ずしも発電量の関数ではない。だが太陽光発電は発電量で太陽光パネルの面積が決まる。もちろん効率アップの研究は行われているが、限度がある。太陽のエネルギーは広く薄まっているために、それを電気にするには面積が広くなるのはやむを得ない。
家庭用としてはコストを度外視すれば実用になるが、車の場合は一般の乗用車を走らせるほどの電力を発電することは面積的にできない
太陽光発電は面積だけでなく、自然破壊、施行の悪さによるがけ崩れ、パネルからの反射による光公害、熱公害が大問題になっている。
福島の田舎を車で走ると、いたるところに太陽光パネルが設置されていて、環境立国日本を実感するかもしれない。
だが車から降りて近くば寄って見れば、設置してある基礎が破壊していたり、そのせいで配線が切れていたり、なによりも傾斜地が多く、下の土壌が雨水で流されて、基礎もパネルも浮いていたり傾いているのに気づくはず。そして流された土壌は、河川の汚染を起こし公害の元である。
まあひどいもんだ。
風力発電も問題ばかりだ。2025年春に秋田市では風力発電の下を通りかかった人に、落ちてきた羽(ブレード)が当たり死亡した。
欧州のように風が一定で台風も来ない、人も住んでいなところに風車を置くならそれは良い。日本のように台風も来る、春一番もやませも吹くところで、住居に近いでは元々無理なのだ。
家畜が低周波で体調不良になるとか、台風で倒壊するのは、風力発電が始まったときからある問題だ。
自然エネルギーの活用をするなとは言わないが、人間との共生(?)を考えて設置しなければ犯罪である。
フォルクスワーゲンの排ガス捏造事件はもう10年も前、過去のことになったようで忘れてしまっただろう。だがこれはEUにおける環境保護挫折の始まりだったのではないだろうか。
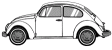 技術革新でクリーンディーゼルができました。ハイブリッドにように余計な部品や機器を追加しなくても、従来の理屈のエンジンでも高度な技術で環境によく経済性も良いものができました……というストーリーだったわけだ。
技術革新でクリーンディーゼルができました。ハイブリッドにように余計な部品や機器を追加しなくても、従来の理屈のエンジンでも高度な技術で環境によく経済性も良いものができました……というストーリーだったわけだ。
ところがきれいなディーゼルエンジンというのは、試験方法に合わせてきれいな排ガスを出したり、燃費を良くしたりしているということがバレちゃった。
ハイブリッドができないなら、それよりも進んだもの(かどうかは定かではないが)である電気自動車にしなければ、大義名分が立たないとなったというのは全く正しいと思う。
だが残念ながら、脚本通りには行かなかった。
環境事業がスイスイと進まなかっただけでなく、歴史は終わらなかった。二大大国による冷たい戦争は終わっても、科学技術の進歩によって、武器、兵器が簡単に作れて使われるようになり、テロとか小規模な戦闘は簡単に実行され、その被害は過去の戦争に比べて甚大になった。
 科学技術の進歩により、プラスチック爆弾、ドローン、テクニカル(SUV車両に機関砲などを備えた簡易な軍用車両)などがどこでも使われるようになった。
科学技術の進歩により、プラスチック爆弾、ドローン、テクニカル(SUV車両に機関砲などを備えた簡易な軍用車両)などがどこでも使われるようになった。
信頼性や防御力はプアでも、攻撃力はオーセンティックな武器に劣らない。
そして、ロシアが資本主義になったと言っても、国家間での競争がなくなったわけではない。ロシアがアメリカを主軸とする西側諸国に、対抗し続けたことに変わりはない。
資本主義国家であるアメリカとフランスが武器や飛行機の輸出で競合することも、アメリカと日本に貿易戦争と言われるような軋轢もある。
ロシアと旧西側諸国が資源や市場を争うことは明白なことであったが、気づかない人もいたのが不思議だ。
そして更に世界のフェーズが変化した。
ドイツは自国のCO2排出を減らそうと、フランスに電力を外注した。それって真っ当な手法じゃないよね。欧州全体がロシアの天然ガスに依存するようになった。ロシアはウクライナを欲しがった。
そして2022年2月24日に武力侵攻を開始した。
ウクライナと聞くと東欧の国くらいしかイメージがないだろう。子どもの地図帳を見てもなんでロシアと西欧が争うのかな?と疑問に思うだろう。 メルカトル図法では実際の相対関係が分からない。
そこで地球儀の出番です。

地球儀で見ると、ウクライナはロシアとEUの間の緩衝地帯だ。ドイツとロシアの距離は、1100kmしかない。青森市と防府市の距離だ。
陸続きだからロシアの戦車が時速40キロで二日半でやって来る。ドイツ人もフランス人も不安だろう。
2004年にポーランドはEUに加盟している。ポーランドはれきとした西側諸国なのだ。
EUサイドから見れば、ウクライナがロシアの支配下になれば、緩衝地帯がなくなってしまう。ロシアと国境を接することになる。
反対にロシアから見れば、ウクライナがEUになれば……以下同文
ドイツのエネルギー政策は裏目になり、EU絶賛推進中の電気自動車も先行き怪しい、環境重視で経済が回らず黄色いベスト運動が激しくなったのは2018年以降だった。
黄色いベスト運動とは、2018年に始まり今に至るまで毎週土曜日にデモが行われている。
ものすごく複雑だが簡単に言えば、石油燃料に環境保護のために石油燃料に税をかけたため、輸送トラック、家庭の暖房、一般家庭の自動車燃料での負担が増えて経済活動が低迷し、また生活が苦しくなった。そのことへの抗議である。
甲子園では決勝の相手を心配する前に、目の前のチームに勝つことが最重要だ。この3連戦は2勝すれば良いというペナントレースとは違う。
負けたら終わりです(by 安西先生)
100年後は大変かもしれないが、今、困っている人は今の問題を乗り越えなければ100年後を考える必要がない。
100年後のクライシスよりも、今のクライシスをなんとかせねばならない。
この状態では、地球温暖化のプライオリティは下がるしかない。
大統領になるには輝かしい明後日より、今、困っている人を救う明日が選挙に勝つ手段だ。だが大統領としては、長期的視点でものを考えないと職務を果たせない。
もっとも温暖化対策が良い判断かどうかも疑問である。
環境保護のボロ、ウソもだんだんと知られてきた。
アル・ゴアが主演を務めた映画「不都合な真実」は「都合の良いウソ」と言われた。

-
「シロクマが滅亡する」
やらせでした。シロクマはCGだったそうですね。実際はシロクマは増えています。
- 煙突から出ているのは煙ですか?
日本で今どき煙が出ている煙突はありません。あれば違法です。
誰もが見たCO2の絵
おっと、中学校で習いましたが、CO2は見えません。もっとも偉大なる環境のジャンヌダルク、グレタトーンベリはCO2を見ることができるそうです。
じゃあ、私が大好きな「白い恋人」ではなく、ゴアが大好きな「白い渦巻」は何なのでしょうか?
白い渦巻はたぶん水蒸気が露結したものでしょう。
- ツバルは未だに沈みません
2000年前後はツバルが沈むと言われたが、2025年現在、ツバルの国土面積は20年前より増加しているそうだ。
それとダーウインさんも言ってたけど、環礁というのは火山島ができてから消滅するまでライフサイクルの一段階である。だからいかなる環礁も必ず消滅する(注7)。
よく「ツバルは隆起することもありますが、長期的には沈みます」というのは当たり前のことだ。すべての火山島は必ず沈む。
ハワイ諸島も数十万年後には海に沈みます。
- アル・ゴアは環境保護に努めていません。
アル・ゴア家の電気使用量は、アメリカの一般家庭の20倍(日本の家庭の35倍)だと叩かれましたね、
IPCCで多くの人が大金をかけて研究していることを、一人二人の研究者が否定できないだろうとおっしゃるかもしれない。確かにそうとも思えるが、実はIPCCとは研究機関ではない。全世界の研究者の論文を集めて、どんな研究成果が出ているかをまとめるのが仕事である。
だからIPCCが権威とか研究所であるということは全くない。
まったくの素人である私が、SDGsが全くの嘘っぱちであることを説明しよう。
| SDGs |  |
SDGsとは何かご存じだろうか?
SDGsとはSustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略語。読めば持続可能性とSDGsの関係は、「目的」とそのための「活動目標」ということになる。
なおGOALとObjectiveやTargetとは何が違うかとなるが、GOAL≒Objectiveであり、TargetはGOAL/Objectiveを達成するために、小分けした目標(途中時点の目標とか、小分けされたプロジェクトの目標)とみなして良い。
「持続可能」とは日本語では「長い期間、保ち続けることができる・中断しないでいられる」という意味である。英語の「Sustainability」も「長時間継続できる」という意味で日本語と同じと考えて良い。
ただ「Sustainable Development Goals」は日本語で「持続可能な開発目標」と訳されているが、その意味は持続可能とは、ちと違う。
ブルントラントの報告書「我ら共有の未来」において「sustainability」とは、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たす経済」と定義されている。
つまり我々の世代のニーズを満たして、更に将来の世代のニーズも満たすことがSDGsだ。
くだらないことをグダグダ言うんじゃねえよ……と言われそうだ。ここは大事なところだから、もうちょい話をさせて。
貧乏でも飯が食えて暮らしていければ持続可能とは言える。だが今の世代が満足して、次の世代も満足できることが持続可能だとしたら、そんな夢みたいなこと実現するのだろうかと疑問を持たないか?
そんな夢のような国があれば、ユートピアか桃源郷か、天国か極楽に違いない。私はそう思う。
中国人は桃源郷を探し求めたが、2000年探しても見つからなかった。
SDGsは実現するのだろうか?
ところで持続可能とは何年間なのだろうか?
100年ではない。だって今手を打たないと22世紀は灼熱地獄になると言っているのだから、100年でないことは間違いない。
では1,000年だろうか? 5,000年なのか? もっとか?
![]()
私が現役時代だから2013年頃、とある講演会に行って、大学の先生が持続可能のすばらしさを語るのを聞いた。講演の後、質問時間に私は手を挙げた。
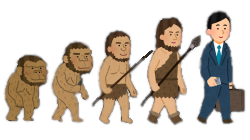 「先生、持続可能とは何年ですか?」
「先生、持続可能とは何年ですか?」
先生少しも慌てず
「永遠です」
![]()
いくらなんでも永遠はないだろう。
宇宙の寿命は1,400億年という。だがそれ以前に、地球の寿命は45億年という。ところが太陽が赤色巨星になるので、生物が存在できるのはあと15億年という。
しかし人間の生物としての寿命もある。一説にはホモサピエンスの種の寿命は100万年で既に登場してから30万年経過しているから、あと70万年という。長いけれど永遠ではない。
簡単に永遠とか無限と言うべきじゃないね。
SDGsを語る人たちは、将来世代をどう定義しているのだろうか?
では次に進む。
SDGsはどんなことを実現しようとしているのか?
SDGsは17のテーマを掲げている。人間の欲望は限りないからよくぞ17に絞り込んだと感心することはない。国際会議で議論して17に妥協したというだけらしい
| 1 | 貧困をなくそう |
だが、よく考えてみよう。貧困をなくすことが持続可能になる条件でもなく、貧困のないことを持続させることなのか、どちらか分からない。
私の感じだが、全員が貧困になったほうが持続可能のような気がする。それが良いか悪いかはともかく、
貧困が悪いイメージなら、清貧と呼ぼう。
| 2 | 飢餓をゼロに |
当時は白米を食うことは贅沢なことだった。我が家は押し麦というものと米を半々にして食べていた。白米といっても当時は今のように白くなく、五分ツキとかそれ以下だったのだろう。
2025年の現在、米不足で騒がれている。米の自給ができるようになってから米不足が騒がれたのは1993年頃の平成の大飢饉のとき作況指数はなんと79(平年の79%しか収穫できない)、2003年も作況指数が90未満だった
技術が進んでも、お天道様のご機嫌や台風には勝てません。
北朝鮮のように国民が餓死しているのに、金電話が核開発、ミサイル開発に浪費していることは「貧困をなくそう」に真逆である。
SDGsバッチを付けている誰か、北朝鮮に行って金電話に文句を言ってくれ。

私は今農業の一番の危機はリンだと思う。
リンとは元素Pだ。異世界ものの小説を読むと、三圃式農法とか魚肥を作るなどのお話が出てくる。実は肥料を施すという考えは古いものではない。そしてリンの効果が大きいと知られたのはそんなに古くなく1840年である。
リンのクラーク数は0.08%順位は13位で少ない物質ではない。しかしそれは薄く分布していて採取するのが困難だ。たいていは南洋の孤島で海鳥の糞が溜まって堆積したものを使うことが多い
ナウルはリン鉱石を掘り切ってしまったようだ。リンが枯渇すれば日本に限らず農業は200年以前に戻ってしまう。
| 3 | すべての人に健康と福祉を |
だが最近は健康になりすぎて別の問題が起きている。私が生まれた1949年日本人の平均寿命は、男59.6歳、女63歳だった。それが2023年では、男81.1歳、女87.1歳だ。過去74年で男21.5歳、女24.1歳、増加率で言えば男36%増、女38%増という異常な事態となっている。
ネットでは年金をなくせとか高齢者に医療を施すななど過激な意見が飛び交う。
「全ての人に健康と福祉を」目指すのは理想だが、すべての人の理想ではなさそうだ。そしてそれが実現すると「持続可能」でもなさそうだが?
| 4 | 質の高い教育をみんなに |
中学の同級生の6割が就職した私には信じられない世界だ。1995年に大学に入った私の娘が、私の一族と家内の一族で最初に大学に行った子となった。それが田舎の貧乏人の現実である。
日本の現状を顧みるにつけ、今以上高等教育を受ける必要はなさそうだ。大学は勉強したい人が行く場所で十分だろう。能力があっても経済的事情などで行けない人を支援すれば十分だ。
| 5 | ジェンダー平等を実現しよう |
それを知りたい。皆大学に行けば持続可能になるとは思えないと同じく、ジェンダー平等が成れば持続可能になるとは思えない。
思う人はその思っていることを上げ、証拠を示してほしい。
| 6 | 安全な水とトイレを世界中に |
きれいな水を得るためのインフラ、トイレの処理施設、そういうもののコストは誰が持つのか、実現可能なのか、よく分からん。
| 7 | エネルギーをみんなにそしてクリーンに |

太陽光パネルの施行が出鱈目で、台風での損壊、雨のとき太陽光パネルが流される、それに伴い発火、火災も起きている。
そんなものを作るのに補助金を出し、その補助金は電気利用者の料金に8%もプラスしている。我々は新エネルギーの被害ばかり受けていて、メリットは何もない。
どうして再エネはクリーンなの?
お金もクリーンじゃないよね?
| 8 | 働きがいも経済成長も |
現実には、働き甲斐のある社会も、経済成長だけでも、実現していないのだ。
どうして「働きがいと経済成長と持続可能が両立する社会」が作れるのよ?
単に働き甲斐と経済成長が両立した持続可能社会になればいい、と思っているだけではないの?
まったく付き合いきれんわ、
| 9 | 産業と技術革新の基盤を作ろう |
そういうものを構築する計画書を見せてください。
話はそれからだ、
| 10 | 人や国の不平等をなくそう |
そんなことを実現してから言おうね。夢を語るのは子どもでもできる。
語ったことをしなければ政治家ではない。そいつは詐欺師だ。
| 11 | 住み続けられるまちづくりを |
タンブルウィードの転がるゴーストタウンで日本版西部劇が撮影できます。
住み続けられるまちづくりの前に、住み続ける人をどうするか考えよう。
正直言って、バカバカしくて話にもならない。
| 12 | 作る責任使う責任 |
いいねえ(棒)
| 13 | 気候変動に具体的な対策を |
 |
|
| ・ ・ ・ 出るのはゴミだけ |
| 14 | 海の豊かさを守ろう |
チャイナの軍備拡張を止めろ
100年後の夢を語っていて、明日殺されるなよ、
EUの首脳はロシアのウクライナ侵攻と、天然ガスを止められて気づいたようだ。
| 15 | 陸の豊かさも守ろう |
まずはそこから始めよう。
| 16 | 平和と公正をすべての人に |
川口市のクルド人問題を解決しよう。
外国人犯罪を見逃すな。
| 17 | パートナーシップで目標を達成しよう | 国連開発計画より |
考えているけど、方法がないからせめてSDGsバッチを付けているんだって!
どう考えても、SDGsの17項目の実現は、持続可能性の実現とは全く無関係です。
でも実現できれば良いね、しかしながら実現可能かどうかも立証されてない。私は「SDGsは不可能である」に一票を入れる。

ご注意
私はこの本の主張に100%同意するものではない。いや同意するのは10%くらいである。
![]()
一例をあげる。
「温暖化の影響を誇張して伝える偏向メディアによる印象操作の実態」小島正美
「気候変動の歴史的変遷に詳しい田家康氏が著した『気候で読み解く日本の歴史』や『異常気象で読み解く現代史』など一連の書物を読めば、NHKの桑子さんがレポートした自然災害や貧窮ぶりは産業革命が始まる19世紀以前にも数えきれないほど存在したことが分かる。(p.212)」
私は環境に関心があるから、田家康の本はほとんど読んでいる
彼の本は記事内容の出典が不明確であり、また新しい情報が少ない。あの本を読んで参考になったとしているようでは、他の記述も似たようなものかと疑心を持ってしまった。
もちろん他の著者方はそうではないと思いたい。
![]() 本日のお断り
本日のお断り
ここに書いたことの95%はこの「SDGsエコバブルの終焉」に書いてあることではない。私がこの本を読んで考えたことというか、以前から考えていたことを思い起こされたということだ。
だから「SDGsエコバブルの終焉」をお読みになっても、上記についての情報を得ることはできません。
むしろあなたはこの本を読めば、あなたなりのエコ狂騒曲を書けるでしょう。
![]() もう一つお断り
もう一つお断り
タイムスリップISOはどうなっているんだ!?
そうおっしゃるお方々、あいすみません。
正直言うと、あっちを書く時間がなかったので、電車で移動中に本を読み、頭に浮かんだことを書きました。これって読書感想文じゃなくて、読書連想文ですからね。
読書妄想文ではありませんよ。
タイムスリップっていろいろ調べないと書けないのですよ。
お許しあれ
| 注1 |
IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)とは、「気候変動に関する政府間パネル」の略で、これは、国連の専門機関のひとつである世界気象機関(WMO)と国連環境計画 (UNEP)によって1988年に設立された、政府間組織です。 要するに国連をはじめ各国の政府が参画している地球温暖化を研究している機関ということだ。言い換えると真理を追究する機関ではなく、政治家、行政官、科学者、マスコミの妥協を図る機関である。 | |
| 注2 |
気候変動に関する国際連合枠組条約 和文:環境省サイト 英文:国連サイト "Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. | |
| 注3 |
電子政府の総合窓口「e-Gov ポータル」 | |
| 注4 |
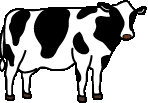 反芻動物とは、一度飲み込んだ食べ物を再び□の中に戻して、
反芻動物とは、一度飲み込んだ食べ物を再び□の中に戻して、植物繊維は分解しにくく、人間や馬は消化できません。そのため植物繊維を効率的にそして有効に消化するために4つの胃を持ち、順繰りに分解消化する仕組みを持つ。 | |
| 注5 |
「歴史の終わり」フランシス・フクヤマ、三坂書房、1992 | |
| 注6 |
・「電気代の平均はどれくらい?」 | |
| 注6.5 |
太陽光発電とは太陽の光から電気を作る方法である。電気を作るとは、他のエネルギーを電気エネルギーにすることだ。つまり発電はエネルギーの変換である。位置エネルギー(ダム発電)、運動エネルギー(風力発電)、化学エネルギー(乾電池)、熱エネルギー(火発)など多種あるが、エネルギー変換であるから、変換前のエネルギーより変換効率分、返還後の電気エネルギーが減少するのは理屈から当然である。 太陽光の持つエネルギーは、真上から日が差す正午、晴天、直射日光という条件で1kW/m2である。 このとき太陽電池の変換効率は市販のパネルで15〜25%と言われている。 日本列島は北緯27度〜46度に位置し、日射はその逆になるから水平面から44度から63度の高さから日が刺す。季節の変化によって地軸の傾き23.4度がプラスマイナスされる。 この他、雲、周囲の影、気温(発電効率が変わる)、パネルの汚れ、経年劣化による発電効率の減少等を考慮すると、実際の変換効率は10%程度と言われる。 この他、一旦整流して充電・放電すると80%程度になる。リチウムは95%と言われる。 そういったことを考慮すると太陽光パネルの発電は100W/2と言われている。一般家庭での太陽光パネルの面積は25〜30m2と言われている。 自動車の全面に太陽光パネルを設置したとき、5ナンバーサイズなら幅1.7m長さ4.7mで、maxで7m2となる。このときの発電量は7×100W=700Wとなる。この電力を馬力表示すると0.94馬力となる。原付バイクは4kW(5.4馬力)以下に規制されているが、その2割だ。まともに走れるはずがない。現実には窓、バンパーなどには太陽光パネルを付けることはできない。車に太陽光パネルを付けるとすれば、駐車時の充電などが目的になるだろう。 言いたいことは、太陽エネルギーは大きいものではあるが、非常に希薄だから扱いにくいということだ。 かってTOKIOの番組「鉄腕ダッシュ」で、ソーラーカーで日本一周するチャレンジがあった。前述したように、太陽光発電しながら走るのはありえない。ウェブで見かけた説明によると、3日間充電して撮影するとき数時間走ったという。10時間発電で3時間走行としても計算が合わない。10時間日照はそもそも無理だろう。 軽自動車なら法で幅1.48m長さ3.4m以下であり、5m2で発電できるのは0.67馬力、3日間毎日8時間発電して3時間で消費として充電効率を無視しても、3×8×0.67÷3=5馬力しかならない。通常自動車は最大馬力の25〜30%の力で走っているというが、原付バイクより少ないパワーでは平坦な道を静かに走るだけだろう。 | |
| 注7 |
・「温暖化で沈む国」は本当か?ツバルの意外な内情 環礁について勉強しようとするなら、小説「ハワイ」をお勧めする。小説でありながら冒頭30ページは人が一人も登場せず、火山島の出来上がるまでを描いている。 「ハワイ」ジェームズ・ミッチナー、時事通信社、1962 | |
| 注8 |
「SDGs―危機の時代の羅針盤」南 博・稲場 雅紀、岩波新書、2020 | |
| 注9 |
JA新聞 (199)1933年:コメ作況指数120【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】 | |
| 注10 |
「ユートピアの崩壊 ナウル共和国」リュック・フォリエ、新泉社、2011 | |
| 注11 |
オバQ(私だ)のウェブサイト「田家康の環境本」 |
推薦する本に戻る
うそ800の目次に戻る
     |