*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
2023年10月である。
環境の仕事は年間スケジュールがあり、それによって粛々と進む。その他に省エネ、廃棄物削減、化学物質削減、環境投資のフォロー、事故などの突発的対策とフォローもある。
環境管理課の現在のメンバーは皆ベテランだし、工場での仕事ぶり、判断力、行動力を見て本社に招集したわけで心配事はない。
2023年になってから管理状態は異常である。異常とは問題が起きることではない。「異常」とは「
今年になってから水質事故も起きないし、煙突からばい煙が出たとか排ガス測定結果が基準より外れたなんて通報もなく、委託している廃棄物業者が廃棄物処理法で摘発されたなんて電話が鳴ったこともない。
暇である。
磯原は坂本、余部、松村のベテラン3名に、30工場を分担して点検に行けという。どうせ緊急事態対応で出張する予算はある。事故が起きてから行くなら事故が起きる前に行ったほうが良い。
管理が良くて問題がないのか、管理していないから問題が見つからないのか、よく見てこいという。そして工場の点検が一巡したら関連会社だ。
磯原の指示を受け、坂本さんを中心に行先、日程、点検項目を考えて交代で出かけている。
ひと月くらいして報告があった。
![]() 「結論から言えば各工場とも作業標準が整備されて、それに基づいて仕事をしていること、管理も日常管理、工場の内部監査(ISOのではない)が行われており、結果だけでなく勤務状況の監査も行っていて、点検作業や操作などについても見ており、作業に当たっては資格者や指名業務者が行っていること。作業標準で業務をウォッチしましたが、いずこもしっかりと手順に従って仕事をしていました」
「結論から言えば各工場とも作業標準が整備されて、それに基づいて仕事をしていること、管理も日常管理、工場の内部監査(ISOのではない)が行われており、結果だけでなく勤務状況の監査も行っていて、点検作業や操作などについても見ており、作業に当たっては資格者や指名業務者が行っていること。作業標準で業務をウォッチしましたが、いずこもしっかりと手順に従って仕事をしていました」
![]() 「余部さん、本当にそうだったの?」
「余部さん、本当にそうだったの?」
![]() 「私の見た工場では間違いなくそのように仕事をしておりました。書類の決裁も書類に応じた権限者とか有資格者が行っており異常はありません」
「私の見た工場では間違いなくそのように仕事をしておりました。書類の決裁も書類に応じた権限者とか有資格者が行っており異常はありません」
![]() 「このままじゃウチは廃業、皆さんは失業だよ」
「このままじゃウチは廃業、皆さんは失業だよ」
![]() 「素晴らしいことじゃないですか」
「素晴らしいことじゃないですか」
![]() 「まあ素晴らしいことでしょうけど、それで事故や違反が起きる恐れはないのですか?」
「まあ素晴らしいことでしょうけど、それで事故や違反が起きる恐れはないのですか?」
![]() 「現時点、見る限りではありませんね。そして以前と違い管理者も担当者も仕事の目的、遵法と汚染の予防でしたね、それを維持しようと考えが変わりました。
「現時点、見る限りではありませんね。そして以前と違い管理者も担当者も仕事の目的、遵法と汚染の予防でしたね、それを維持しようと考えが変わりました。
以前ISOを認証していたときは、審査で不適合を出さないようにと考えていたことと比べると大きな変化です。ISOで不適合を出すなとなると手段ですが、その目的を考えれば意識が変わるというものです」
![]() 「じゃあ、もう期待するレベルになったのでウチの存在意義はなくなったということかな?」
「じゃあ、もう期待するレベルになったのでウチの存在意義はなくなったということかな?」
![]() 「いえいえ、課長、そうじゃありません。私は前から考えていることがあるのです」
「いえいえ、課長、そうじゃありません。私は前から考えていることがあるのです」
![]() 「例のあれですか?」
「例のあれですか?」
![]() 「そうです、そうです」
「そうです、そうです」
![]() 「あれって、なんでしょう?」
「あれって、なんでしょう?」
![]() 「我ら
「我ら
省エネと称して設備投資とか更新とかしているわけですが、実はその成果はあまり出ていません」
![]() 「えっ、ほんとう?」
「えっ、ほんとう?」
![]() 「導入当初は環境貢献の鳴り物入りですから工場は成果をだそうとします。だけど導入を企画した人が転勤したりすると、その多くは活用されなくなってしまうのです」
「導入当初は環境貢献の鳴り物入りですから工場は成果をだそうとします。だけど導入を企画した人が転勤したりすると、その多くは活用されなくなってしまうのです」
![]() 「何年か前、投資計画で予算が取れたらそれを流用(第8話)して……ということがありましたが、そういうことはないのでしょうか?」
「何年か前、投資計画で予算が取れたらそれを流用(第8話)して……ということがありましたが、そういうことはないのでしょうか?」
![]() 「その話は聞いており、そういう点も見ております。
「その話は聞いており、そういう点も見ております。
少々怪しいものを投資計画に合わせて購入したりしているのはありますが、申請と大違いなことをしている工場はありませんでした」
![]() 「そういう方向ではないのですが、工場では内情をいろいろ聞かされます。
「そういう方向ではないのですが、工場では内情をいろいろ聞かされます。
たとえば省エネ投資をしたものでも、導入後数年は稼働していても、企画した担当者がいなくなると使いこなせなくなったとかで遊休状況にあるのも珍しくありません。本当は捨てたいのだが固定資産だし償却期間内は廃棄出来ないという。本社に対しては最初の1・2年改善効果などの報告を出せば以降現地でのフォローはないのです。
設備が老朽化して更新したというようなものを除いて、改善のための環境投資で計画通り稼働しているのは珍しいありさまです。」
![]() 「元々の計画がずさんというか流行に乗っただけというのもある。営業所の屋根に風力発電をつけて、投資が回収できるはずがない。
「元々の計画がずさんというか流行に乗っただけというのもある。営業所の屋根に風力発電をつけて、投資が回収できるはずがない。
だが、そういうのは投資とか回収ということではなく、宣伝とか意識付けという観点で評価すべきでしょう。なら投資計画も省エネのイメージアップのためとすべきだ。実際は営業所の電気代削減としていた」
![]() 「トランスの効率化で更新するというのがありました。実態を聞いてみると本当は劣化診断で危ないと分かったものの、耐用年数とのからみで更新する予算が取れないから、トランスの効率が向上するという理由の投資計画にしたといいます。まあ必要は必要だったのでしょうけど、論理としては支離滅裂でしょうね」
「トランスの効率化で更新するというのがありました。実態を聞いてみると本当は劣化診断で危ないと分かったものの、耐用年数とのからみで更新する予算が取れないから、トランスの効率が向上するという理由の投資計画にしたといいます。まあ必要は必要だったのでしょうけど、論理としては支離滅裂でしょうね」
![]() 「話は分かりましたが、それでどうしようというのでしょう?」
「話は分かりましたが、それでどうしようというのでしょう?」
![]() 「工場を訪問するときに、遵法と汚染の予防だけでなく、そういうことをひざ突き合わせて話し合いをしたら、何か効果があるのではないかと考えたのです」
「工場を訪問するときに、遵法と汚染の予防だけでなく、そういうことをひざ突き合わせて話し合いをしたら、何か効果があるのではないかと考えたのです」
![]() 「投資するなら本音でしてほしいし、そうであれば投資したものは真に活用されると思うのですよ」
「投資するなら本音でしてほしいし、そうであれば投資したものは真に活用されると思うのですよ」
まさしくそうだ。磯原は次回からベテラン(ロートル)メンバーが工場に行くときは、製造管理部門の部長級にそういった観点からの議論もさせていただきたいと公文を発信することにした。
ベテランチームが工場巡回するときに、施設の運転状況、施設の保守管理状況、遵法と汚染の予防になっているかの観点に加えて、環境投資のその後の状況を点検することになった。
交代で毎週ひとりが一つの工場に行くとして、ひと月で4工場の点検実績が蓄積する。
そんなことを各工場に行くたびにしていると、工場の担当者同士あるいは管理者同士の報連相で、まだベテランチームが来ない工場にも、どんな点検がされるのか議論がされるのかが伝わり、自分の工場に来たらどんな話題が出るかと考える。
当然だが他の工場の話を聞いた管理者も担当者も、投資するには真に投資が必要なもの、投資すれば正真正銘の効果があるものをしなければならないと思う。
だが今までの投資計画はそうではない。……まず投資計画は工場で予算を取りたいというのが優先する、その大義名分にどんな投資なら確実に予算が取れるかということになるのが現実だ。
だが予算を取ることが目的描いたきれいな投資計画は、結果として負の遺産増すだけだ。そうではなく本音で何が必要なのか、それは絶対に予算を取らねばならないのだという論理でなければ良い結果にはならない。
すぐにどこの工場でも環境投資だけでなく、怪しげな発想からした投資計画を見直そうと認識するようになる。
その結果、ロートルチームが工場に行きますよと通知をすると、環境以外の設備投資についても検討したいので、そちらの検討会に参加してほしいという声がかかる。
そんなことを10工場も続けていると、本社の生産技術課の人たちも参加するようになった。
自動機とか計測器などを導入しても、それを完璧に使いこなしていない事例は多々あるのだ。
そうなるとロートルチームも自分たちが参画するのは筋違いと考えた。投資計画は生産技術部門のマターだ。環境部門が余計なことに口出しするのはまずいだろう。
磯原はロートルチームからの報告を受けて環境投資も含めて、投資の見直し議論から外れることにした。
その代わりというわけではないが、今までの実績から、設備投資の分析や評価のパターンも固まってきたので、それをまとめて生産技術に提供した。それを参考にこれから分析や投資効果を評価してほしいお願いして、環境管理課はそういう検討会から抜けてしまった。
翌年の社内技術報告会では、「設備投資の有効性向上」というタイトルで本社生産技術課のメンバーが、過去数年に投資した事例の状況をまとめて、投資した直後だけでなく長期的に有効であったかを評価すべきであるという発表が評価された。
同じオフィスであるが20メートルほど離れたところにある机から、生産技術課の課長が磯原のところに来て頭を下げてお礼を言った。
磯原は自席で頬杖をついてボーっと考えている。磯原が考えているのは自身の個人的なことである。
磯原は決断して、人事の下山に会って相談したいとメールを出した。
下山からすぐ日時の返信があった。
今、磯原は小さな会議室で下山と面談している。
![]() 「なんか心配事でもあるようですね」
「なんか心配事でもあるようですね」
![]() 「私の今後のことです。私はこれからどうなるのでしょうかね。
「私の今後のことです。私はこれからどうなるのでしょうかね。
本社の課長は工場なら部長です。工場には総務、技術、営業、製造という部長の席はあっても、環境部長なんて役職はありません。工場では環境は施設管理のほんの一部でしかありません。ですから工場に帰っても私が座れる椅子はない。
関連会社に出向としても、関連会社で環境だけ担当するのでは部長どころか課長もいないでしょう。
とはいえ本社で課長を5年もしている人を見たこともありません。私の業歴で本社の部長になれるわけもなく、もちろんそんな能もありません。
となるとつまるところ私の行く末ってどうなりますかね?」
![]() 「アハハ、42歳で本社の課長にスピード出世した磯原さんが、44歳でそんなことを心配しているとは笑ってしまいますよ。
「アハハ、42歳で本社の課長にスピード出世した磯原さんが、44歳でそんなことを心配しているとは笑ってしまいますよ。
40代は後先考えず、仕事をバリバリしてほしいところです」
![]() 「人事の人から見たら笑いごとかもしれませんが、私にとっては笑い事じゃないんです。
「人事の人から見たら笑いごとかもしれませんが、私にとっては笑い事じゃないんです。
娘が来年、高校に入るのですが、娘も家内もずっとこちらに住むつもりでいます。仮に私が転勤になれば娘は転校できませんから逆単身赴任です。
人生設計がどうなるのか、予想が付きません」

![]() 「人事の場合は他の職種とは全く違いますから、参考になるかどうか分かりませんが……入社から退職するまで転勤の連続です。その期間は短ければ数か月、長くても5年、とにかくどんどん移動します。人事屋という仕事は変わりませんけど。
「人事の場合は他の職種とは全く違いますから、参考になるかどうか分かりませんが……入社から退職するまで転勤の連続です。その期間は短ければ数か月、長くても5年、とにかくどんどん移動します。人事屋という仕事は変わりませんけど。
だからそれを納得してくれる人でないと結婚もできません。妻も大変ですが、子供も大変です。
もちろん数か月で転校はないですよ。短期の場合は、個人的に問題を起こしたとかでなければ、新工場立ち上げとかリストラとか、ある意味イベントの応援のようなものです。そのような場合は、初めから短期と分かっていて単身赴任です」
![]() 「人事の場合、転勤が多いのは負担でしょうけど、他の職種に移らないからキャリアパスでは不安はないでしょう?」
「人事の場合、転勤が多いのは負担でしょうけど、他の職種に移らないからキャリアパスでは不安はないでしょう?」
![]() 「確かにそういう点では人事は、心配というか悩みはありませんね。
「確かにそういう点では人事は、心配というか悩みはありませんね。
それと評価の仕組みが他の部署とは違います。磯原さんの環境でも営業でも技術でも、昇進は成果次第でしょう。人事はそうではなく減点主義です。成果を出すのではなく問題を起こさない、問題が起きたら素早く処理することが評価されます。というか、できないとマイナス評価ですね。
人事は国家公務員と同じですね。工場の課長級までは、一定年齢になると同期そろって昇進する。しかしその上は椅子が減っていきます。部長になれない人はそこに留まることは許されず、関連会社や他の民間企業への出向となり、すぐに転籍になります。それがだいたい30代末から40前半ですね。
私も今、課長を卒業したところで、次のステップに行けるかどうかの段階です。部長になれればまた何年かいられますが、ならないと出向転籍です。そして部長級になっても、その上は人事担当役員だけですから、なれなかった全員がどこかに出ていくことになります。それは50代初めですね。
人事で生き残るには、目立つ成果を出すことでなく、ミスをしないことですね。
営業や技術の昇進競争は、プロジェクト崩れをしても、それ以上の成果を出せばよい。一度同期より遅れても、どこかに飛ばされることはない。その後すごい成果を出せば追いつき追い越すことができる。敗者復活戦があるからいいですよ。セーフティーネットですね。
人事にはそれはありません」
![]() 「人事はまさに国家公務員の世界ですね」
「人事はまさに国家公務員の世界ですね」
![]() 「但し人事の人たちは潰しがきくというか、人間関係を扱う技能を鍛えられますから、出向や転籍の行き先はけっこうあります。言い方変えるとどこに出されるか分からない。
「但し人事の人たちは潰しがきくというか、人間関係を扱う技能を鍛えられますから、出向や転籍の行き先はけっこうあります。言い方変えるとどこに出されるか分からない。
既に私の同期の半数は社外に去っています。その内半数は関連会社ですが、半数はグループ企業以外で、地方自治体へ出向とか、縁も所縁もない病院や大学の事務長とか、公的な財団法人の総務とかいろいろあります。
先が見えないのは磯原さんと同じですよ」
![]() 「私は元々電気主任技術者でエネルギー管理士でしたから、そういう方面の法人、例えば省エネセンターなどへの道がありますかね?」
「私は元々電気主任技術者でエネルギー管理士でしたから、そういう方面の法人、例えば省エネセンターなどへの道がありますかね?」
![]() 「人事の話をしちゃったから、出向前提になってしまったな。
「人事の話をしちゃったから、出向前提になってしまったな。
あのね、磯原さんの年齢で今の地位なら、普通の人は今から出向を考えようとか、出向先を探そうなんて発想しませんよ。
磯原さんのように環境管理全般の管理ができる人なら、どこでも欲しがります。転職、転社したければいつでもできるという強みがあると認識しなくちゃ。
言い換えると我々は、磯原さんが他からヘッドハントされることがないように、気を使わなくちゃならない。
だからあと何年経ったら現職にいられないとか、ネガティブなこと考えなくて大丈夫ですって」
![]() 「いやいや、娘が高校に入ってから転校になる可能性を考えると、大きな悩みですよ」
「いやいや、娘が高校に入ってから転校になる可能性を考えると、大きな悩みですよ」
![]() 「うーん、ざっくばらんに言いますと、磯原さんがあと3年、つまり娘さんが高校生卒業するまでは転勤はありません。もちろん大チョンボすれば別ですが。
「うーん、ざっくばらんに言いますと、磯原さんがあと3年、つまり娘さんが高校生卒業するまでは転勤はありません。もちろん大チョンボすれば別ですが。
それからですが、まあ役員は無理としても、本部長室のスタッフ……山内さんや田村さんのような立場ですね……そういうコースもあるでしょうし、状況次第ですが社内あるいは関連会社として環境管理のコンサルを立ち上げても良いでしょう。
以前ならISO審査員というのもありましたが、もうISO認証は先細りですし、磯原さんとしては審査員をやろうという気はないでしょうね。
先のことなど気にすることなく、今のお仕事を頑張ってください。仕事で悩むことはありません」
結局、先のことなど心配することはないから、現在の仕事をしっかりやれと言われて終わりだった。
|
| ||
工場にしても関連会社にしても、ロートルチームが来るのと本社の環境課長が来るのは対応が違い歓迎してくれた。いつも本社は命令ばかりしているわけで、挨拶なり御用聞きに来るなら言いたいことがあるという雰囲気だ。
自分の目で見るとロートルチームが問題視したことは良く分かるが、そればかりでない問題も見つかる。
やはり公害防止にしても廃棄物処理にしても、法改正動向などの情報が足りない。それは本社が情報を流していないのか、日常業務が多忙すぎて本社発信の情報に気が回らないのか。
その辺をもう少し強化しなければならない。
それと新人教育が不足している。
例えば現場の職長が役職年齢で引退して、環境課に回されたとしよう。現場の職長をしたような人は、日常50名くらいの人を動かしていたわけだ。だが伝票の入力とか起票などはあまりしたことがない。
廃棄物処理をしてほしいと言われて電子マニフェストのインプットするのも前任者がしたのを見てやってくださいでは、できなくて当然だろう。実態は皆負けるものかと老眼鏡をかけて何とかしようと格闘している。
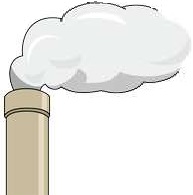
そればかりでない。高校を出てきた人が排水処理とか担当させるとき、どんな教育をするのか聞くと体系的なものがなく心底不安になる。
スラッシュ電機には工場が30ほどあるが、排水処理とか煙突のばい煙除去とかになると該当する設備を持つのはせいぜい3割である。そういう工場では設備の担当者はひとり、予備を考えてもふたりいれば間に合うわけで、新入社員が来てもしっかりした教育もせずに、OJTで何とか育てているのが実態だ。
そういう徒弟制度でも平常時の対応はできても、異常時に対応できるのか、いや平常時でも大局的な考えがなかなか身に付かない。客観的に言って劣化コピーを作っているのではないだろうか?
どうすべきだろう?
数年前、山内さんがいた時代に、工場の環境担当者を本社で数年教育して工場の中堅にしようという発想で30前の人を本社に呼んで教育をするようにした。それが石川君とか宇佐美君なのだ。本社に来た人たちは3年前後で工場に戻ると係長になるエリートと目された。
だがそういう工場の環境課長候補の養成でなく、もっと対象を広げて環境業務従事者全体のレベルアップが必要だ。
磯原はロートルチームと議論して環境業務担当者短期研修制度の案を作った。工場の環境課長宛て実現への意見を求めた。それは類似設備を保有する工場の中から一つ選択して、そこでその設備担当の新人を1週間程度の座学と実技の教育するものだ。
工場の環境課長宛て実現への意見を求めたところ、トライアルをしろということで、水処理でトライしてしようと、場所を提供する工場と受講者の志願を求めた。
実施してみると受講者も教育担当も成果も出たし効率的だという意見で、設備を保有している工場が少ないものだけでなく、環境管理全般についてどこかの工場に集めて集合研修……といっても数人だが……を行うことにした。
教育はマンツーマンが最も効率が良いと思われるが、受講者が数人いたほうが、競争心も持つし、受講者同士の意見交換も研修の有効性を上げる。
環境業務は工場の中では特異なものだが、どの工場にもあるという意味では人事と同じだ。
だから環境担当者は問題が起きても疑問があっても、工場内では類似作業がなく相談相手もない。だが社内で考えると同じ仕事をしている人は30工場あるのだから30人いるはずだ。トラブルが起きたとき同業者のアドバイスほどありがたいものはない。一緒に研修を受けた相談できる知り合いは貴重な財産である。
当然、教育するには作業手順の基本というか標準を定めたテキストが必要で、工場の作業手順書を集めて最大公約数的なものを作ると、それを全工場で使うようになった。
環境管理の新人教育の体制ができると、それを定着するために会社の仕組みに取り込むように会社規則も改定した。
ついでに非製造事業所における環境管理業務についても作業標準を作り共通化を図った。非製造業においては仮に事故や違法が起きても、製造業ほど重大な問題が起きないと考えているのか、適切な環境管理手順を決めているところは少ない。
磯原は問題発生時の広報や謝罪会見の仕方まで網羅したテキストを作った。
結局、何年も前に田中さんや坂本さんと語ったが夢物語と思っていたことが、なし崩しに実現されていく。
そういった標準類も一過性としたくなく、生産技術部の技術文書管理課に相談して、設備管理要覧という位置づけで正式文書にした。
設備管理要覧とは製造部門対応の標準らしいが、事務部門でも作成でき業務で引用もできるという。その性質は指針となるが強制力は持たないものであるらしい。なるほど差しさわりのない位置づけのようだ。
ロートルチームがそういった標準類を作ったわけだが、作成するのも結構大変だった。最初はキーボードを打つのも左右の人差し指だけだったロートルチームも、ひと月もするとブラインドタッチ(タッチタイピング)で打つようになった。
教えることも学ぶこと、教えることで自ら力量もつくものだと余部さんが語った。
注:私は1970年代末からNC機械のプログラムを作っていた。
当時の紙テープ穿孔機は単なる電動のタイプライターで、作ったプログラムを電子的に記憶しておく装置がない。あまりにも原始的で笑ってしまう。
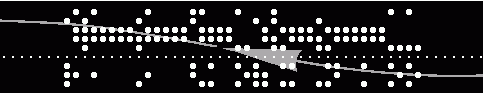
キーボードでNCテープを作っていたら、ブラインドタッチができるだろうと思うかもしれなが、NCプログラムは、G、M、Hなどいくつかの英文字と、数字さえ覚えれば間に合う。
1990年頃、現場監督から品質保証に異動になったとき、速くタイプが打てなければ仕事にならないと、当時流行っていたブラインドタッチ練習用のカセットテープを買ってワープロ専用機で練習した。驚くことに数日で打てるようになった。
2017年の調査データでは、事務職でブラインドタッチできない人が6割だそうだ。
ちょっと頑張ればブラインドタッチはものにできます。
磯原は肩意地を張らず自然体と言えば聞こえが良いが、実際になにもしてないのに物事が進んでいくのをみて、不思議なこともあるものだと思う。
それは機が熟したということなのだろう。
昔はどんな仕事にも
磯原も入社当時はそういう人を
ところで最近は事務作業に情報システムが使われるようになってから、事務作業も標準化され手順も文書化されるようになった。となると会社の規則や不文律をすべて覚えていて、必要な時即座に該当するものを思い出せれば誰でも職場の権威になれるはずだ。
いや覚えなくても、庶務とか業務のように定型化されているものなら、具体的なマニュアルが作られ、それに従い仕事ができるはずだ。
注:「庶務」とは、一般事務とも言い、部門において電話対応や書類の作成・維持、部門の予算管理、来客対応、場合によっては清掃やお茶出しなどのこと
「業務」とは、事業において日々継続して行う仕事のこと。企画やプロジェクトなどは業務の範疇ではない。
もちろんマニュアルを作るまでもないことが多いだろう。確かにISO9001のオリジナル版でも、文書化の程度は職場の人の質、業務の複雑さによるなんてあったように記憶している。
だがこの職場なら常識だという考えは禁物だ。今日来た人でも仕事ができるようにするのが目指すところだろう。そうするとベテランには余計なノイズになると思われるかもしれない。
だが時代は変わった。
IT化が進んだ今は、会社のルール、規定や規則をデータベースに放り込んで自動的に仕事の起承転結を表示することができる。あらかじめ仕事ごとのマニュアルを作っておくのではなく、会社の定款から会社の規則(procesure)、仕事の要領書(work instruction)すべてを記憶装置に放り込んで、担当者が命じられた仕事を入れると、その担当者専用の作業要領書、つまり会社規則から業務の手順や決裁者を抽出して仕事のプロセス、権限、裁量などのワークフローを自動生成すればよい。
その手順も、生成された要領書を使う人のレベルに応じて、精粗を調整することもできるだろう。
AIの発達した今は、正しい名称とか質問でなく、「あんなこと」「こんなこと」「したいこと」を入れれば、文章で仕事の手順を示してくれるものが簡単に(?)実現できる。
ルール通りの運用は、すべてこの方法に順を切り替えることもできるはずだ。いやイレギュラーと言ってもその9割は過去に起きているだろうから、発生した時の顛末をデータベースに放り込めば会社の仕事の99%をカバーする。
磯原は情報システムに行ってそんな夢を語った。
半月後、情報システムの連中が「会社規則から業務手順を作る自動生成システム」という検討報告書をまとめて磯原のところに来て筆頭著者になれと言ってきた。
最近、磯原は『自分はいったい何をしているのだろう』と自嘲する。幸いなことに磯原のすることを、お節介と文句を言う人がいない。
そして最近はどう考えても、環境管理には自分は不要であること、そして自分の5年後の仕事というのが想像できないことが確実に思えた。
工場には帰れないだろうし、関連会社に行くにはあまりにも自分は環境管理に特化しすぎている。ラインに沿った昇進ができるとは思えない。
磯原は柳田さんが暇しているのを見て、話をしたいと声をかけた。
柳田さんも状況を理解して茶請けとコーヒーを二人分もって会議室に来た。
 |  |
![]() 「柳田さんのアドバイスを聞きたいのだけど…」
「柳田さんのアドバイスを聞きたいのだけど…」
![]() 「どうぞ、どうぞ。コンサルは無料よ」
「どうぞ、どうぞ。コンサルは無料よ」
![]() 「端的に言って自分の道が見えないんですよ」
「端的に言って自分の道が見えないんですよ」
![]() 「おやおや、一担当者だったのに環境管理課を大掃除して、人を育て、当社の環境管理レベルを大きく上げた大課長が何をおっしゃるかと思えば、なんと悲しいことを」
「おやおや、一担当者だったのに環境管理課を大掃除して、人を育て、当社の環境管理レベルを大きく上げた大課長が何をおっしゃるかと思えば、なんと悲しいことを」
![]() 「長い付き合いですから率直に言います、私はここに来て7年になります。5年後はここにいないでしょう。
「長い付き合いですから率直に言います、私はここに来て7年になります。5年後はここにいないでしょう。
5年後でも49歳。私は会社内でどういう職務、職階に進むのでしょうね? 私が必要とされる仕事が浮かばないのです」
![]() 「前任者の大西課長は関連会社に出向して営業マンをしているそうです。その前の鈴木課長は関連会社に出向して、今はそこの製造部長をしているそうですよ」
「前任者の大西課長は関連会社に出向して営業マンをしているそうです。その前の鈴木課長は関連会社に出向して、今はそこの製造部長をしているそうですよ」
![]() 「鈴木さんが出向して5年か、5年あれば製造部門の経験がなくても、製造部長になれるのですか?」
「鈴木さんが出向して5年か、5年あれば製造部門の経験がなくても、製造部長になれるのですか?」
![]() 「どうかしらねえ〜。小さな会社に行けば管理者の職責が肩書と一致していないこともよくあります。何とも言えませんね。鈴木さんは親会社からの出向だから、肩書だけ付けてくれたのかもしれませんね」
「どうかしらねえ〜。小さな会社に行けば管理者の職責が肩書と一致していないこともよくあります。何とも言えませんね。鈴木さんは親会社からの出向だから、肩書だけ付けてくれたのかもしれませんね」
![]() 「そういうこともありますね」
「そういうこともありますね」
![]() 「磯原さんは、環境の専門家と思っているかもしれませんが、私はそうでなく標準化の専門家だと思いますね」
「磯原さんは、環境の専門家と思っているかもしれませんが、私はそうでなく標準化の専門家だと思いますね」
![]() 「標準化の専門家! ご冗談を、そんなことしていませんよ。
「標準化の専門家! ご冗談を、そんなことしていませんよ。
ただ環境管理課の仕事で、ここ1年、事故も違反も起きていません。
それで環境管理業務の省力化を考えているだけです」
![]() 「環境管理だけでなく事務全般の改善を図っているように見えますね」
「環境管理だけでなく事務全般の改善を図っているように見えますね」
![]() 「多少ははみ出ているかもしれません。
「多少ははみ出ているかもしれません。
ちょっと今の仕事に張り合いがないのです」
![]() 「磯原さんは以前から環境管理というよりも、標準化とか作業の効率化をしてきたように思います。今は環境が終わってどうしようと迷っているのではないですか」
「磯原さんは以前から環境管理というよりも、標準化とか作業の効率化をしてきたように思います。今は環境が終わってどうしようと迷っているのではないですか」
![]() 「確かに環境管理課は、もう手順もノウハウも完成してしまったのではないかと思うのです。
「確かに環境管理課は、もう手順もノウハウも完成してしまったのではないかと思うのです。
その手法を他の業務にも適用すれば事務の自動化……自動化と言っても電子化とか人が要らないという意味ではありませんよ。迷わず仕事ができることの意味です。
そうすれば省力化、時短にならないかと思いましてね。
アハハハ、今まで余計なことをするなと言われたことはありません。みなさん心が広い」
![]() 「磯原さんがあちこちで改善をしているのを、見ている人が大勢います。
「磯原さんがあちこちで改善をしているのを、見ている人が大勢います。
皆さん高く評価していますよ。私も見ていて思うのですが、多くの人は、合理化、自動化というとコンピュータ化、情報システムの利用という発想をします。
でも磯原さんは現行の処理や情報の流れがどんな意味を持つのか、それをほぐして、目的を果たすにはより簡単な方法、エラーを防ぐためのフィードバックをどうするかとかを考えてますね。
そういう地に足を付けた発想がすごいと思いますね」
![]() 「アハハ、それは私がコンピュータなど知らないからですよ。私は電子工学ではなく電気工学つまり発電とか送電でしたから」
「アハハ、それは私がコンピュータなど知らないからですよ。私は電子工学ではなく電気工学つまり発電とか送電でしたから」
![]() 「磯原さんは既に自分がしたい仕事を実践しているのではないですか?」
「磯原さんは既に自分がしたい仕事を実践しているのではないですか?」
![]() 「はて何でしょう?」
「はて何でしょう?」
![]() 「来年の春に本社組織の見直しをすると聞いてますか?」
「来年の春に本社組織の見直しをすると聞いてますか?」
![]() 「そういうことには疎いんですよ。ご存じなら教えてください」
「そういうことには疎いんですよ。ご存じなら教えてください」
![]() 「情報システム部は今生産技術本部の中にあります。文書管理は総務部管轄です。図面や技術文書などを管理している生産技術課の文書管理は、たてまえは総務部から技術に関わるものについて管理を委託されている形になっています。
「情報システム部は今生産技術本部の中にあります。文書管理は総務部管轄です。図面や技術文書などを管理している生産技術課の文書管理は、たてまえは総務部から技術に関わるものについて管理を委託されている形になっています。
生産計画や受発注のシステム化はされていますが、今後はより広くというか全面的に文書管理も情報管理も包括した事務作業の業務の効率化、情報伝達の高速化を推進するそうです。
イメージのひとつに会社規則とか種々の作業標準から、特定の事務担当者の一人一人用の手順書を自動生成するようなイメージですね。
そのために総務部文書課、生産技術部の技術文書管理課、そして情報システム部をまとめて情報システム本部に格上げして役員が見るようになるそうです」
![]() 「それはなかなか
「それはなかなか
![]() 「磯原さんも勘が鈍いのね、磯原さんはそこの事務改善の課長に、異動することになっているのですよ」
「磯原さんも勘が鈍いのね、磯原さんはそこの事務改善の課長に、異動することになっているのですよ」
![]() 「ええぇ、本当ですか?
「ええぇ、本当ですか?
そんなこと言われても、私はシステム構築なんてしたことないですよ」
![]() 「いえいえ、それこそ磯原さんが今している、仕事の流れをしっかりと調べること、仕事の目的をいかにスマートに実現するか考えることを仕事にするだけです。
「いえいえ、それこそ磯原さんが今している、仕事の流れをしっかりと調べること、仕事の目的をいかにスマートに実現するか考えることを仕事にするだけです。
だから転勤の心配もないし、単身赴任の心配もありません。
頑張ってください。環境管理課は仕組みも手順も出来上がっているのですから新任課長でも大丈夫。それに影の環境課長である私も残りますからね、アハハハ」
磯原は柳田の語ることは冗談でなく、間違いないことは今までの経験から知っている。
話の内容には驚いたが、仕事は面白そうだ。事務の仕事は標準化最後の秘境だ。きっと改善の宝庫だろう。
可能なら、環境事故とか違法発覚時の対応も、AIで快刀乱麻を断つようできないかなと思った。
えー、2年2か月に渡り178話も書きました、ISO第3世代もこれにて終了でございます。 お読みいただいた方、ありがとうございました。
これで終わりか?と問われそうですので、次のお話の予告です。
次に書こうと思っているお話は、『無敵のISO担当者のお話』です。
私も能のあるISO担当者だった気はするのですが、上長が審査員におもねる人が多く、私の主張は論理的には正しくても、政治的に負けたことは数知れず。
そんな悔しさを吹き飛ばす正義の味方を想定しております。
私は「ISO事務局」という言葉が大嫌いです。たかがISOごときに専任者とか事務局があるなんて許しがたいこと。審査が終われば支払伝票を切ってオシマイって仕事なんて恥ずかしくないですか?
私はISO事務局ではありませんでした。たくさんの仕事をしましたが、ISO審査の発注から支払いもしていました。そんな仕事に誇りを持つわけありませんよ。
![]() 本日のレポート
本日のレポート
ふとし様から2年前の7月に頂きました「ISOの物語を書け」という課題のレポートを提出します。ご査収のほどよろしくお願いいたします。
修了できるか論文の再提出か? 不安です。
蛇足ですが、コメンスメント(commencement)とは卒業式で使いますが、卒業とか修了の意味ではなく、何かを始めることです。
卒業式で使うのは、これで学ぶことを負えたのではなく、新しく学び始めるという意味です。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
わずー様からお便りを頂きました(24.07.11)
素敵な物語をありがとうございました 毎日更新を楽しみにしておりました。更新されていない日には異世界審査員を読んで次回を心待ちにしておりました。 首尾一貫したお話に快哉を叫んだことが何回もありました。磯原さんには仕事とは何かを常に教えていただきました。 自分の考えが上西イズムに近かったのを少しは矯正できたのではないかと、心より感謝申し上げます。 次回作を楽しみにしています。 どうぞくれぐれもお体をお労りくださいませ。 |
わずー様、お便りありがとうございます。 あまり褒められると舞い上がってしまいます。 稚拙な作品を読んでいただき感謝です。 次回作は最近(でもないか)流行っている「なろう系」という、転生とかチートでいってみようかと、 もちろん私はISOしか能がありませんから背景は変わりません。 来週月曜日開演(?)予定です。 |
外資社員様からお便りを頂きました(24.07.11)
おばQさま 内容の濃い読み物を、よくぞ最後まで書いて頂きありがとうございました。 リアルさを追求しつつ、最後まで参考になる読み物に感謝いたします。 最後も、再就職や転職を踏まえたお話で、リアルですね。 結局 自分が転職しても通じるかという見直しを続けられる人間は、強いですね。 だって、大会社の中だけで勝ち残れる人間なんて、結局数人しかいない訳ですから例外中の例外。 >昔はどんな仕事にも主とか神様なんて呼ばれる人がいたものだ。 これが、昔の日本の強みでした。 それが通じるには、設備や生産環境が変わらない事が前提。時代が変わり、産業構造が目まぐるしく変わるようになると、当然 名人はいなくなる。 むしろ、名人不要で、素人が使えるシステムを作り上げることが重要になる。 その辺りが、私達が働いている時代に起きた、大きな変革なのだと思います。 >標準化の重要性 これは時代が変わろうが重要で、上記の「素人が使えるシステム」には重要な要素だと思います。 大学時代の指導教官が、戦時中 海軍技術士官として電探を作っていました。 オリジナルではなくて友邦ドイツが供与した「ウルツブルグ・レーダー」 先生は、テレフンケンによる図面を見た時に、図面番号が階層構造になって、階層を上に辿るとモジュールから全体のシステムへ、下に辿ると個別部品から電装品などまでつながる事に驚いたそうです。 当時の海軍の図面では、図面の書式はバラバラで統一性無し。現場ごとに図面管理の名人がいて、特定の艦船や兵器の事は精通していたそうですが、名人がいないとシステムが捉えられないし保守部品も不明。 そうした名人は、繰り上げ卒業した技術士官を、階級が上だろうが相手にしてくれなかったようです。そうした名人不要にするには、図面表記や発番の標準化が必要なのだと強く感じたそうです。 そういう意味では、日本の技術的敗因には、標準化や生産管理など、直接生産にかかわる部分は軽視があり、標準化は今でも重要なのですよね。 磯原氏のコメンスメントをお祝いし、おばQさまに感謝いたします |
外資社員様 毎度ご指導ありがとうございます。 なんとか結末までたどり着けました。 私の場合、竜頭蛇尾になるのが多く、今回は竜頭蛇尾どころか竜頭虫尾くらいしょぼくてすみません。 標準化のこと、 おっしゃること良く分かります。「あなたの日本語だいじょうぶ」という本で、結論を先に書くのはまずいという論を堂々と唱えている先生がいるので呆れました。 論理的に考えるという基本が分からないのですかね。いくら大先生でも話になりません。 標準体系とか図面構成もちろんプログラム作成も同じです。スパゲッティとか蜘蛛の巣のようなプログラムでは書いた人は良いけれど保守などしたくありません。 そういう人が幅っているのですけどね。 それはもう企業での教育でなく、小学校からやらないとダメですね。 最近知った話ですが、小学校で一皿にミカン3個、4皿ならミカンが何個あるかという問題の正解は3×4で、4×3はバツなんだそうです。私は頭が悪くて良く分かりません。 そういう教育をしていると、ガウスのような天才は現れません。ガウスが小学校のとき先生が疲れて、1から100まで合計しろといったら、ガウスは即5050と答えたそうです。 100+1が50組ということですね。 実は私は掛け算九九を全部覚えていないのです。1の段は覚えることない、2の段は2×1は覚えることない、3の段は3×1と3×2は1の段と2の段で出てきている。9の段では9×9だけ覚えればよい。結果、99は81個覚える必要なく、たった36個覚えれば済みます。 なんでそれがダメなのか、ガウス先生に叱ってほしい。 |
ふとし様からお便りを頂きました(24.07.11)
いつもお世話になっております。ふとしです。 時が経つのは早いもので、もう2年になるのですね。 ともあれ、リクエストに応えて頂きありがとうございました。 レポートの出来は最高です。大満足です。 が!留年です。 卒業できませんので、次の物語をお願いいたします笑 無敵っぷりを楽しみにしております。 |
ガッ、ガッ、ガーーーン ふとし先生の愛のムチありがたくお受けします。 精進しますんで、お待ちください。 無敵と言ってもチートのバフ付きですから |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |