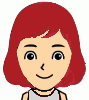*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
2023年10月
 暑さも過ぎて、湘南もめっきり涼しくなった。毎朝三木は、朝食前に庭に水やりをして、家の前の通りを掃除というか簡単に箒で落ち葉やゴミをはらう。
暑さも過ぎて、湘南もめっきり涼しくなった。毎朝三木は、朝食前に庭に水やりをして、家の前の通りを掃除というか簡単に箒で落ち葉やゴミをはらう。
いや自慢することではない。私の住んでいる地域は古くからの人が多く、自宅の前をきれいにしようと朝は皆掃除をするのだ。つきあい半分で義務みたいなものだ。
近所の引退者は早朝や涼しいうちに海岸まで散歩する人が多いが、三木はぞろぞろ歩くのが好きではない。
三木がそんなことをしている間に、妻は朝餉の支度である。二人とも70代半ばであるが大病なく、ありがたいことである。
三木の年代は、60歳で定年退職、嘱託で勤めても63か65で引退というのが多い。しかしISO審査員をしていた三木は、契約審査員になり会社から声がかかれば仕事をするという形で働いた。
実際には契約審査員は月の半分も仕事がない。しかし几帳面な三木は審査の参考にしようと、行く先の事業や製品そして経営状況を会社のウェブサイトや四季報で調べた。それでけっこうパソコンに向かっている時間が長かった。
まあ実際は審査に役立つというより、経営者インタビューのとき話のネタになるくらいなのだが。
もちろん年齢と共に仕事も減らし、行先も近場に限定してもらっていた。60代も半ばを過ぎると、朝一の飛行機とか、
| 🛫 |
70歳で契約審査員を止めて、それ以来 悠々自適といえば聞こえがいいが、何もしない浪人生活である。
正直言って、仕事を止めてホッとした。審査員といっても普通の会社員で、同僚とも葛藤があり、仕事ではトラブルもあり、三木はリーダーたる立場が多かったので気苦労も多かった。そんなことから解放された今は気をもむことはない。
2020年に引退したのだが、ちょうどそのとき老後の暮らしに年金だけでは年66万円足りず、老後2,000万円不足するという金融庁の報告があり、日本中で「2,000万円問題」と呼ばれて騒がれた。
テレビでは引退組も引退予備組も、そんなにお金を持ってないという声が多く、また実際にそうだろうと思う。
だが多くの人が2,000万持っていないという事実があるのに、2,000万なければ生活できないという結論になるのもおかしなことだ。多くの人が2,000万持っていないのに生きていることから考えれば、2,000万円必要という論がおかしいと思わなければならないだろう。
その後、銀行などで様々な試算を出している。年金で不足する分は暮らしぶりによるが、概ね年間16〜25万で65歳からの30年間で必要となるのは480〜750万とするのが多い。
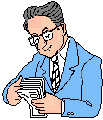 我が家の場合であるが……引退して数年は、毎年預金が50万ずつ減った。65歳の頃だから95歳まで生きるとすると、30年間で1,500万足りないことになる。我が家の場合は2,000万ではなく1,500万問題である。
我が家の場合であるが……引退して数年は、毎年預金が50万ずつ減った。65歳の頃だから95歳まで生きるとすると、30年間で1,500万足りないことになる。我が家の場合は2,000万ではなく1,500万問題である。
振り返ると当時は働いていた時と同じ感覚で現役や引退した元同僚と飲んでばかり。それもわざわざ千葉から東京まで夕方行くのだからアホとしか言いようがない。更に年1回は家内とグアムやタイなど海外旅行に行った。
だが不思議である。あれほど遊び歩いていて年50万不足なのだから、金融庁の語る年66万不足とはどんな贅沢三昧なのだろう?
 ともかく年を取るにつれて生活がドンドン変わる。
ともかく年を取るにつれて生活がドンドン変わる。
数年経つと、元同僚たちが病気だ体力がないなど出てこなくなり、飲む機会が激減した。家内との外歩きも外食も減るし、海外旅行より温泉♨が良くなる。
そして70になると酒が弱くなった。もう缶ビール350ml 1本で充分だ。
ダメ押しで2020年からはコロナ大流行で外出、外飲み、旅行禁止である。年50万減るのが20万になった。そして95歳まで25年間だから1,500万問題が一挙に500万問題に変わった。いや500万では問題とは言えない。そして周りの年寄りを見ていると、75歳超えるとますます金を使わない。医療費は1割負担だし、私が宝くじを買うのを見て「何億当選しても使う当てがない」という。宝くじを買う私は、未来がある若者である。
金融庁の騙る「2,000万問題」は「うそ800問題」ではなかろうか?
仕事を完全にやめて4年、その間いろいろなことにチャレンジしてみた。
まず市民大学(正式名称は違うが忘れた)である。そこで自分の住む市の地形とか歴史などを勉強したが、2年もすれば興味のあるものは受講してしまった。
公民館の囲碁クラブにも行ってみた。三木のような級位者にも相手してくれるが、皆有段者それも高段者ばかりで居心地が悪く、数回行って止めてしまった。
老人福祉センターで高齢者の運動を教えていると近所の人に誘われて行ってみた。いやはや高齢の老人たちが椅子に座って、首を回したり指折りしたりしていた。まだ10年は早いと思い二度と行かなかった。
結局は平日にはフィットネスクラブで軽い運動、週末には妻と近くの博物館とか公園を歩く平坦な日々である。三木夫婦は、お互いに金のかかる趣味はない。
それでも学ぶことは多い。生まれ育った町にも思いもよらない歴史があり文化財があると知ると郷土愛が増す。なによりも、知らないことを知ることは喜びである。
三木には今もメールのやり取りしている仲間がけっこういる。大学を出てから53歳まで勤めた機械部品メーカー、出向し後に転籍した認証機関、そこも定年になって是非と誘われて契約審査員として働いた認証機関、それらで知り合った上司や同僚で親しくした人とは今もメールをやり取りしている。
年賀状となると印刷したりあて名を書いたり面倒だが、今はメールで新年の挨拶をしてもおかしくない。
近々年賀状も値上がりするようで、そうなれば年賀状を出すのも大金である。
三木がある夜、自分の部屋でメールを見ていると、発信者が松本愛という人からメールが来ている。
 |
|||
メールボックスで過去にメールを受けたことがあったか検索してみたが、該当するものはなかった。
最初に怪しいメールではなかろうかと思ったが、メールはテキストだけでとりあえずウイルスの心配はなさそうだ。
メールを開いて読む。
ここまでメールを読んで、三木は思い出した。
あれは娘が大学生で京都に住んでいたときだった。私が京都で審査があるので前泊しようと日曜日に着いて少し京都見物していた。すると街で娘に声をかけられた。突然のことで驚いた。
あのとき娘は22歳で、今から18年前になる。娘も今年40歳、結婚して孫も来年は中学生になる。イヤハヤ、時が経つのは早いものだ。
そのとき確かに娘は友達と一緒で、その子の名は愛ちゃんといった。その後、一緒に食事したのだが、その子は私が審査員だと知ると、ISO審査員になりたいといろいろ質問してきた。それが印象に残った。
そうかあの子か……
三木は差出人が面識ある人と知って、安心してメールの続きを読む。
・
・ ・ ・ 三木さんに相談していろいろお世話になりましたが、その後就職とか結婚とかありまして、すっかり忘れておりました。 私は大学を出て中堅の機械部品の商社に入りまして、以来ずっとそこで働いております。 入社してすぐ会社でISO14001認証のプロジェクトのメンバーになりまして、認証活動をしました。どんな形でもISO14001に携われてうれしかったです。 しかしその後、リーマンショックのとき会社の経営がだいぶ厳しくなり、無駄排除という理由で認証を返上しました。2009年だったと思います。 残念でしたがやむをえません。 それが私とISO14001の縁の切れ目でした。それ以降、ISOに関わったことがなく過ごしてきました。 ・
・ ・ ・ |
三木は愛ちゃんのメールを読むにつれて、当時のことをだんだんと思いだした。もちろん18年も前のことだ。
パソコンだってもう4・5代変わっているから、メールの記録など残っていないが、確か審査員になる方法とか、審査員のお仕事を聞かれた覚えがある。
・
・ ・ ・ 私よりひとつ先輩だった方は、某認証機関に審査員候補として卒業と同時に入社しました。親しかったのでときどきどんなことをしているのか教えてもらいました。 入社して審査員研修を受けて、半年ほど見習いをして審査員になり張り合いをもって仕事していたそうです。 ところが1年後、社長が交代して会社の方針が変わりました。 多くの認証機関は、企業の年配者の出向を受け入れて審査員にするそうです。 当然、出向してきた方々は50代以上で給料が高いのですが、出向者の場合は出向元が半分ほど負担するし、人件副費(下記注)は100%出向元負担だそうで、トータルすると若い人を雇うより認証機関の負担は少ないそうです。 その他に大きな理由があったそうです。 業界設立の認証機関の存在目的は、社内の遊休人材の活用そして社外流出費用の削減だそうです。 それじゃ新卒を採用する意味はありませんね。 ひょっとして日本で第三者認証制度が流行したのは、企業内失業者を働かせることだったのでしょうか。仕事しない人に賃金を支払うのでなく、余計な仕事を作ってそれをさせたという意味合いがあったのか? いえ、それは私の下種の勘繰りですね。 ともかく後任社長は新卒を審査員にするという方針を覆し、翌年から新卒採用はゼロとなったそうです。先輩の年に採用された女性審査員は4名いたそうですが、最初もてはやされたものの、社長交代後は塩対応になり、せっかく主任審査員までなったのに2年ほどで全員退社してしまったそうです。 彼女たちのその後はいろいろですが、先輩は別の認証機関に就職し今も審査員をしています。 ・
・ ・ ・ |
注:人件副費とは、企業が従業員に支払う給与や賞与以外の費用を言う。
社会保険料、福利厚生費、退職金、研修費用、作業服、業務用の携帯電話などがある。
確かに審査員とは大学を出たばかりの若い人がする仕事じゃないと思う。また年配のほとんど男性だから、若い女性は大変じゃないかと思った。
それに愛ちゃんの文章にもあったが、賃金の構造がまともじゃない。民間認証機関なら費用負担は50:50が普通と思うが、財団法人系は出向元が100%負担するところもあると聞く。法的に問題ないのだろうか。
いずれにしてもそんなところでは新人を採用するはずがない。
契約審査員でも仕事量が確保され、適正な勤務条件なら良いだろうが、三木が契約審査員をしていた過去10年くらいはかなり労働条件が厳しくなってきた。
中小認証機関では、労働法の規制を受けない幹部が休みもなく審査をこなさないと損益的に立ちいかないと聞いたこともある。
審査員の仕事が良いか悪いかは、その仕事の意義とか社会的地位などばかりでなく、雇用条件なども重要な要素だ。
企業内失業者の見た目だけの活用説は、三木も初めて聞いた。だが言われてみればそうかもしれない。三木の出向先がなければ、会社に行ってお茶を飲んで過ごしていたかもしれない。
そういうことを考えると、遊休社員に仕事をした気持ちにさせるだけでも意味があったのだろうか?
 |
だが、時と共に経営環境がドンドン厳しくなって、そんな失業対策もできなくなってきたのか?
それなら認証の意義など真剣に考えることもなかったなと苦笑する。
・
・ ・ ・ 三木さんには審査員になりたいと相談したことがありました。そのとき三木さんから審査員の多くは出向者で賃金も複雑だとお聞きしました。 いろいろ考えると、私は普通の企業に総合職で入って良かったと思います。昔は出産すると退職が普通だったと聞きましたが、今は法的にも無碍なことはできませんし、自分が選んだこの人生で良かったと思います。 ・
・ ・ ・ |
あのときの愛ちゃんの相談に対して、夢を壊すような回答をして悪いことをしたかと思っていたが、良かれと思って書いたことを理解してくれてよかった。
質問には誠実にアドバイスしたつもりだが、辛口だったとは思う。
考えてみれば世の中に寿命のないものはない。形あるもの全て壊れる。
人間が必要なものも欲しいものもどんどん変わる。だからすべてのビジネスモデルも事業も製品も寿命がある。
三木が大学を出た頃はオーディオとかカメラが趣味という人は多かった。今もオーディオもカメラもメジャーな趣味だろうが、当時のようにオーディオ機器に100万、200万(当時のお金でだ)かける

昔は社会人になれば一眼レフカメラを持つものだったが、今はそんな習慣はない。フィルムが高いからと、ハーフサイズの一眼レフカメラもあった。
なんで高校大学出て月給をもらうと、皆一眼レフを買ったのか、不思議でならない。他にほしいものがなかったのか?
そういやスキーもあったしボウリングも流行したな。20世紀末にスノーボードも流行したが、70年代のスキーの流行はあんなものじゃなかった。
趣味ばかりではない。
三木が営業マン時代に扱った製品や部品は数多い。基本的な機械要素はいつまでも変わらないが、その中身はどんどん変わる。たとえばボルト・ナットの寸法は過去60年変わらないが、表面処理は変わっている。三木が働き始めた頃は錆びにくいといえばカドミメッキだった。それが毒性で規制され六価クロメートとなり、更に六価クロメートが禁止されてと、どんどん移り変わっている。
 |
正しく言えば、カドミメッキは禁止されたわけではない。用途限定で使用可能である。
まあそれを言えばPCBだって、劣化ウランだって使用禁止ではない。
だからISO認証にも寿命があるだろう。
そういえば三木が退職する前から、認証機関はISO認証件数減少に対して、いかにするかを検討していた。結局今に至るまで代替えになる新規ビジネスは見つかっていない。
認証事業は年々シュリンクしており、審査員の仕事量も減っている
三木が審査員になったのは2005年、まだISO認証件数は増加していた。ISO9001の認証件数のピークは2006年でISO14001は2009年だった。当時の認証件数は二つ合わせて6万件を超えていた。
引退した2019年にはピーク時の75%に減ってしまった。そして2023年の今は60%、4年間で15%も減ってしまった。(この物語は今2023年である)
自分はISO認証の最高の時期に仕事をしていたわけだ。
愛ちゃんの先輩が65まで働くとして2045年、それまで認証制度が存続しているものだろうか? どう考えても無理気味だろう。
今はQMSとEMSだけじゃなく、多様なISOMS規格があるから認証件数は多いと思うかもしれない。しかし2009年頃QMSとEMSしかなかった時代はその二つの合計で6万以上あったが、2023年の今認証規格は9種類あるが、その合計はたったの37,000件なのだ。制度的にもう寿命かもしれない。新しい認証規格ができても、増えない。カニバリズムなのか認証というものの流行が過ぎたのか。
・
・ ・ ・ なぜ今になって三木さんにメールを出したかですが、経済誌で最近ISO認証を返上した会社が増えているという記事を見て、私が就活していたときのことを思い出しました。そしてそこから三木さんがISO認証も長くは続かないと教えてくれたことなどどんどんとを思い出しました。 それで三木さんにお礼と言いますか、そんな心の内をお伝えしたいと思って、三木さんのお嬢さんにメールアドレスをお聞きしました。 三木さんのアドバイスに感謝しております。 ありがとうございました。 |
もはやISO審査員は審査員としての力量アップではなく、別業種へ転職のためのスキルを身に着けることが必要だろう。
もちろんこれはISO審査員だけの問題じゃない。
世の中の動きは速いから、今まで必要だった業種が不要になることは多い。ガソリン車ディーゼル車が電気自動車に代われば、ガソリンスタンドも充電設備に代わるだろうけど、危険物取扱者は全くいらなくなってしまう。タンクローリーの運転手は大型免許の他に危険物取扱者の資格が必要で高給と言われているが、これからは仕事がなくなってしまう。
そういうことがドンドン起きるだろう。
だから自分がいま就いている仕事でプロフェッショナルになるのも大切だが、その仕事がなくなったとき新しい仕事に転身できるように常に学び続けないといけないな。
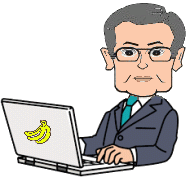
三木が入社した1970年頃、書類や手紙を和文タイプする専門の女子社員がいた。1990年頃、既に管理職だった三木もブラインドタッチができるようになれ、書類も手紙も電子メールも自分でやれと言われた。
今じゃ、偉い人が紙に手書きで草案を書いて、女性がそれをタイピングするなんて風景はどこに行っても見られない。
三木はいろいろ考える。
少なくても愛ちゃんは自分の半生を、後悔していないようで良かった。
やはり愛ちゃんがISO審査員なるのを止めたのは、結果から見て正解だったのだろう。
そして三木も自分の会社人生は間違っていなかったと思う。俺の人生も捨てたもんじゃないとニヤリとした。
おっと、愛ちゃんに返信しなければならないな。
三木は気分よく返信メールを書いて送信アイコンをクリックした。
![]() 本日の疑問に備えて
本日の疑問に備えて
なぜこの物語に無関係な「審査員物語」の三木が登場するのか?と不思議に思われたお方、
実は三木は「ISO第三世代」のこれまでの176話中25話、14%もの回で、出演あるいは名前が出てくるのです。主人公磯原の上司・同僚のレギュラー陣に次いで、最多出演の脇役でございます。
もう一つ疑問に思われるだろうこと、
20年も前に付き合いがあった方に、連絡を取ることがあるだろうかということ?
私の場合はありますね。お世話になった方に、先方やこちらが転勤や転職で挨拶する間もなく別れてしまった方の現在をご存じの人に会うと、連絡先を教えてもらい直接お会いするとか、メールだけでもお世話になったお礼を申し上げたことは何度もあります。
じゃあ私にも来るかとなりますと、感謝のお便りはありません(キリッ
それ以外はいろいろ来ます。
15年ほど会ったことのない元同僚からフェイスブックにお便りが、見ると某革新政党に投票を頼むとか、即座にゴミ箱へ
○○を買ってくれ(悪名高い販売結社でした)。もちろんゴミ箱一直線
メール発信者が懐かしい名前ですと、構えてしまいます。
でも、私が金の
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
ふとし様からお便りを頂きました(24.07.04)
いつもお世話になっております。ふとしです。 急に暑くなりましたが、体調はいかがですか。 私は気圧の変化に弱いので毎日ヘトヘト・・ 私、三木さん大好きですので今回の登場は嬉しかったです。 何を隠そう、審査員になろうとしたことがありますので、今思えば、ならなくてよかっなと思います。 この歳で無職になるのはキツイですよね。 審査員をやっていたら、他社でやっていけるような経験やスキルが身につくとも思えないですし・・ |
ふとし様、毎度お便りありがとうございます。 私も50代初めは審査員になろうと思っていました。いろいろありまして転職して、新しい職場ではISO審査員になるのは2流的な価値観でした。1流は企業で環境行政をすることだったのです。事故を起こさない、法を知り守ること、そうさせることが価値あることでした。 ISO認証はお墨付きを与えることでしょうけど、お墨付きの価値がないのですね。そういう実態を知ると、企業で環境管理をしっかりすることこそが大事だなと思いました。 引退して10年、振り返るともっと努力すればよかったとは思いますが、けっこうやったんじゃないかなんて自分に甘い評価をしてます。 まあ年寄りの昔話です。 余話をダラダラ書いていますが、頭の中で新作(笑)を考え中です。 やはり一作ごとにメインテーマを変えないといけないので(オイオイ)次回はなろう系でいこうかと(笑)。 期待しないで待っててください。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |