*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
スラッシュ電機本社ISO審査の第1日目である。オープニングミーティングが終わった。
高藤審査員はこれから昼飯を挟んで午後まで、関東支社の審査である。
関東支社といっても、所在するところは同じビルの中だ。所在地は同じだが、組織上では本社ではなく、本社の下にある各地方の支社と同じ位置づけである。
支社とするのでなく本社の一部門として、首都圏の営業活動をするのもありだろうが、支社を一つ作れば支社長以下の役職がワンセットできるから、人事処遇に都合がよいと考えたのかもしれない。なにしろ長の付くポストを用意するのも大事なことだ。
いやいや、そこまで大規模でなくても、人事処遇で部下がいなくても部長がいたり、課がなくても課長がいたり(以下略)
高藤審査員のアテンドは礒原である。今回の審査対応の責任者である岡山は、メインの仕事は自分でするが、審査員を評価するために磯原に見てもらおうと考えた。
 |
 |
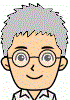 |
 |
||
| 河島業務部長 | 池村総務課長 | 高藤審査員 | 磯原 | ||
| 関東支社 業務部 | ISO審査員 | アテンド | |||
![]() 「関東支社で環境に影響する業務とか物とか活動には、どんなものがありますか?」
「関東支社で環境に影響する業務とか物とか活動には、どんなものがありますか?」
![]() 「関東支社は営業のみですから、オフィスの電気と営業用車両の燃料や排気ガスですかね」
「関東支社は営業のみですから、オフィスの電気と営業用車両の燃料や排気ガスですかね」
![]() 「オイオイ、池村君は営業じゃないから思いつかないかもしれないが、我々の扱っている商品があるだろう。我々の売っている商品は製造による環境負荷より、使用時の環境負荷削減は何倍にもなるはずだ。負の影響よりも益の方がはるかに多い」
「オイオイ、池村君は営業じゃないから思いつかないかもしれないが、我々の扱っている商品があるだろう。我々の売っている商品は製造による環境負荷より、使用時の環境負荷削減は何倍にもなるはずだ。負の影響よりも益の方がはるかに多い」
![]() 「ああ、そう言われるとそうですね」
「ああ、そう言われるとそうですね」
![]() 「忘れては困るよ。我々が自信をもって売ることができるのは、環境保護に役立っているからだ」
「忘れては困るよ。我々が自信をもって売ることができるのは、環境保護に役立っているからだ」
![]() 「扱っている商品といいますと、家電とかですか?」
「扱っている商品といいますと、家電とかですか?」
![]() 「残念ながら家電ではウチに限らず国内メーカーは、中国の安物に駆逐される寸前ですよ。日本の産業構造から、もう低機能・低価格・高い技術を必要としないものでは勝負になりません。素晴らしいドライヤーといっても、高けりゃ買ってもらえません。ユーザーは髪が乾けばよいので、高機能なんて求めませんよ。コモディティ化というのでしょうな
「残念ながら家電ではウチに限らず国内メーカーは、中国の安物に駆逐される寸前ですよ。日本の産業構造から、もう低機能・低価格・高い技術を必要としないものでは勝負になりません。素晴らしいドライヤーといっても、高けりゃ買ってもらえません。ユーザーは髪が乾けばよいので、高機能なんて求めませんよ。コモディティ化というのでしょうな
ま、我々もテレビやオーディオでアメリカを席巻した時代もあるわけで、文句は言えません。
おっと、今弊社の主力はファクトリーオートメーションの機器や設備ですね。正確に言えば省エネ機器ではなく、省エネ支援機器というべきでしょうね」
![]() 「ファクトリーオートメーションといいますと?」
「ファクトリーオートメーションといいますと?」
![]() 「PLCとかプログラマブルロジックコントローラーなんて言葉を、聞いたことありませんか。昔はシーケンスなんてリレーやタイマーを組み合わせて組んでいたわけですが、現代はパソコンのように、画面上で回路を組めば動いてくれるものになりました。
「PLCとかプログラマブルロジックコントローラーなんて言葉を、聞いたことありませんか。昔はシーケンスなんてリレーやタイマーを組み合わせて組んでいたわけですが、現代はパソコンのように、画面上で回路を組めば動いてくれるものになりました。
それから省エネするにも電力使用量の把握が必須です。前世紀は測定個所にセンサーを付けて有線で電力量計につないでいましたが、まさに蜘蛛の巣のようでした。今のデータ伝送は無線です。大したことないと思うでしょうけど、その違いはすごいです。もちろんデータ集計だけでなく、使用量が増減したら、設備の休止や変更などをするところまでいっています。そのためのアプリケーションも用意しています。
その他ファクトリーオートメーションを進める様々な機器や素子ですね。そういうツールを使って、製造の自動化、無人化、省エネ化が進められるというわけです」
![]() 「なるほど、そうしますとそういう製品の販売に携わる人たちは、知識と高い教育が必要でしょう。関わる人の教育や研修は、どうなっているのですか?」
「なるほど、そうしますとそういう製品の販売に携わる人たちは、知識と高い教育が必要でしょう。関わる人の教育や研修は、どうなっているのですか?」
![]() 「私は業務部で営業を支える業務ですので、そういうことには直接は関わっておりません。営業部でご確認願います」
「私は業務部で営業を支える業務ですので、そういうことには直接は関わっておりません。営業部でご確認願います」
![]() 「分かりました。業務部では環境に関わることとなりますと、どんなものがありますか?」
「分かりました。業務部では環境に関わることとなりますと、どんなものがありますか?」
![]() 「本社ビルにいるものですから廃棄物もエネルギーも、本社総務部におんぶに抱っこです。まあ本社ビル勤務4,000名に対して、関東支社は300名で1割にもなりません。もちろん我々が本社に払う家賃に、それらの費用はオンされているわけです」
「本社ビルにいるものですから廃棄物もエネルギーも、本社総務部におんぶに抱っこです。まあ本社ビル勤務4,000名に対して、関東支社は300名で1割にもなりません。もちろん我々が本社に払う家賃に、それらの費用はオンされているわけです」
![]() 「業務部として、創意工夫を図るところはないのでしょうか? 例えば輸送とか営業車両での工夫ですとか」
「業務部として、創意工夫を図るところはないのでしょうか? 例えば輸送とか営業車両での工夫ですとか」
![]() 「製品はほとんど工場から直送で、関東支社は在庫を持ちません。支社は伝票、といっても今は電子データですが、それを動かすだけです。
「製品はほとんど工場から直送で、関東支社は在庫を持ちません。支社は伝票、といっても今は電子データですが、それを動かすだけです。
製品の流通ルートですが、我々が最終顧客と直接取引するのは大量受注の場合だけですね。ほとんどは代理店経由になります」
![]() 「それでは輸送方法の改善は、工場の役割になるのですか?」
「それでは輸送方法の改善は、工場の役割になるのですか?」
![]() 「生産技術本部にロジステクス部というのがありまして、そこが音頭を取って工場や代理店などと最適なルート、手段などを検討します。ほぼ2年の間隔で見直しています」
「生産技術本部にロジステクス部というのがありまして、そこが音頭を取って工場や代理店などと最適なルート、手段などを検討します。ほぼ2年の間隔で見直しています」
![]() 「それでは業務部の活躍する場がないですね」
「それでは業務部の活躍する場がないですね」
![]() 「いえいえ、省エネ製品を売るだけが支社の仕事ではありません。当社と一般社会の接点は支社です。地方では弊社の代表ですからね。
「いえいえ、省エネ製品を売るだけが支社の仕事ではありません。当社と一般社会の接点は支社です。地方では弊社の代表ですからね。
担当地域の自治体や学校、NPOなどがイベントするときは、支社がお手伝い、まあお金を出したり製品を貸し出したりします。そういう活動で弊社の製品だけでなく環境活動を知ってもらうのが、業務部にとっては環境に関わる大きな行事ですね」
![]() 「なるほど、それは重要ですね。その活動はどういった体制で行うのでしょう?」
「なるほど、それは重要ですね。その活動はどういった体制で行うのでしょう?」
![]() 「業務部の下に広報課というのがありまして、イベント主催者から声がかかると話し合いして決めております。また我々も機会をとらえて独自のイベントを開催しています。夏休みに自然教室を開くとか、学校から教室でのお話を要請されることもあります。
「業務部の下に広報課というのがありまして、イベント主催者から声がかかると話し合いして決めております。また我々も機会をとらえて独自のイベントを開催しています。夏休みに自然教室を開くとか、学校から教室でのお話を要請されることもあります。
そういった手順は全社共通に定めておりまして、ええと会社規則に決めてあります」
![]() 「関東支社の規則ではないわけですか?」
「関東支社の規則ではないわけですか?」
![]() 「イベントの方法や内容、いかほどお金を出すかということは、全社でレベル合わせをして、支社間で差がないようにしています。
「イベントの方法や内容、いかほどお金を出すかということは、全社でレベル合わせをして、支社間で差がないようにしています。
もちろん細かいところは支社が調整します。関東支社でも、都市部と交通が不便なところでは、客層も違いますし展示物も同じとはいきません。そういうことは多々あります」
![]() 「なるほど、広報担当者の教育はどうされているわけですか?」
「なるほど、広報担当者の教育はどうされているわけですか?」
![]() 「アナウンサーや芸能人ほどではありませんが、そういう研修を請け負う会社がありますので、新たに広報担当になった者には研修を受けさせています」
「アナウンサーや芸能人ほどではありませんが、そういう研修を請け負う会社がありますので、新たに広報担当になった者には研修を受けさせています」
![]() 「効果はありますか?」
「効果はありますか?」
![]() 「今の若者はそういうのに長けていますから。カラオケだって我々年配者は恥ずかしさがありますが、若者はアイドルのつもりで歌います。
「今の若者はそういうのに長けていますから。カラオケだって我々年配者は恥ずかしさがありますが、若者はアイドルのつもりで歌います。
教育することはそればかりではありませんが、支社の職務ごとに入社から40代くらいまで概要を決めています。10年も経てば世の中変ってしまって常に見直しをしておりますが」
![]() 「教育体系を拝見しても……」
「教育体系を拝見しても……」
![]() 「これが年度ごとの人材育成計画です。これが広報担当者の研修ですね。
「これが年度ごとの人材育成計画です。これが広報担当者の研修ですね。
申し忘れましたが、ここにありますように営業マンも、話し方とかコミュニケーションの研修に行かせています」
![]() 「かなり精緻に作られていますが、当然予算の裏付けもあるわけですね?」
「かなり精緻に作られていますが、当然予算の裏付けもあるわけですね?」
![]() 「もちろんです。先ほどの司会者教育でも一人行けば何十万とかかります」
「もちろんです。先ほどの司会者教育でも一人行けば何十万とかかります」
![]() 「大金ですね。内部ではできないのですか?」
「大金ですね。内部ではできないのですか?」
![]() 「へたすると劣化コピーになってしまいますから、やはり専門家に習うのがベストでしょう」
「へたすると劣化コピーになってしまいますから、やはり専門家に習うのがベストでしょう」
・
・
・
・
![]() 「それでは予定したことは、完了しましたのでおしまいです。ありがとうございました」
「それでは予定したことは、完了しましたのでおしまいです。ありがとうございました」
河島部長と池村課長が打ち合わせ場を去る。
![]() 「ええと次は?」
「ええと次は?」
![]() 「次は関東支社の営業部です。場所はこのままです。
「次は関東支社の営業部です。場所はこのままです。
予定より8分早く終わりましたので、しばしお待ちください。
ちょっと高藤さんとお話をしたいのですが……」
![]() 「はい、なんでしょう?」
「はい、なんでしょう?」
![]() 「審査員によって流儀はあるかと思いますが、もう少し証拠を確認されたらよろしいかと思います」
「審査員によって流儀はあるかと思いますが、もう少し証拠を確認されたらよろしいかと思います」
![]() 「はあ、どのような点でしょうか?」
「はあ、どのような点でしょうか?」
![]() 「営業部門のテキストは、これから営業部門の審査でチェックすると思います。しかし広報は業務部ですから、今のインタビューで調べないとなりませんでした。
「営業部門のテキストは、これから営業部門の審査でチェックすると思います。しかし広報は業務部ですから、今のインタビューで調べないとなりませんでした。
また外部研修を受けて効果がありますかと問い、相手からありますと聞いてOKしましたね。そこはどんな成果であるか証拠を見せてもらうべきでしょう
![]() 「でも研修は外部とのことで、成績のようなものはないのかなと思いました」
「でも研修は外部とのことで、成績のようなものはないのかなと思いました」
![]() 「審査ですから相手をおもんばかることはありません。
「審査ですから相手をおもんばかることはありません。
聞くべきことはいろいろあります。まず必要な力量は明確になっているのか、教育訓練のニーズはどのように決定したのか、外部研修がニーズに見合っているのか、研修した結果ニーズは満たされたのか、そういったことを確認しなければならないでしょう。
それに認識の項番も確認しなければなりませんね」
![]() 「ああ……おっしゃる通りですね」
「ああ……おっしゃる通りですね」
![]() 「あなたは審査員ですから、結論に至った経過、収集した情報や証拠を明確にする必要があります。
「あなたは審査員ですから、結論に至った経過、収集した情報や証拠を明確にする必要があります。
昔、証拠を確認せず口頭の説明だけで適合として、認定停止になった認証機関がありました」
![]() 「そんなことがあったのですか、不勉強で知りませんでした」
「そんなことがあったのですか、不勉強で知りませんでした」
![]() 「余計なことをもっと言いますが、関東支社のオフィスは本社総務部に廃棄物処理などを委託しているわけですが、支社の下に各県に営業所があります。そこの廃棄物や省エネなどを管理監督する機能は先ほどの業務部です。
「余計なことをもっと言いますが、関東支社のオフィスは本社総務部に廃棄物処理などを委託しているわけですが、支社の下に各県に営業所があります。そこの廃棄物や省エネなどを管理監督する機能は先ほどの業務部です。
もちろん今回のISO審査では抜き取りで営業所を審査しますが、アドミニストレーション
それも審査しなければなりませんが、来年に期待します」
![]() 「ああ〜、確かに関東支社の環境側面には営業所の管理というのがありましたね。今回は私は関東支社内部しか気が回りませんでした。
「ああ〜、確かに関東支社の環境側面には営業所の管理というのがありましたね。今回は私は関東支社内部しか気が回りませんでした。
ご指導ありがとうございます。次の営業部では、そこんところ注意して行います」
営業部の審査が始まった。
 |
 |
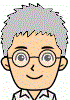 |
 |
||
| 樋熊営業部長 | 宇佐見課長 | 高藤審査員 | 磯原 | ||
| 関東支社 営業部 | ISO審査員 | アテンド | |||
![]() 「営業部のお仕事とはどんなことですか?」
「営業部のお仕事とはどんなことですか?」
![]() 「物を売ることです。とはいえ売るのは一瞬ですが、クロージングまで持っていくのが大変ですし、売ってからお金を回収することも、次の注文につなげるのも仕事です。
「物を売ることです。とはいえ売るのは一瞬ですが、クロージングまで持っていくのが大変ですし、売ってからお金を回収することも、次の注文につなげるのも仕事です。
そのためには担当地域で顔を売る、顧客、同業他社、自治体の上から下まで、地域の顔役に知ってもらう、それが基本ですね。そのためには法人でも個人でもボランティア活動もしなきゃならん。もちろん金のためでなく心底そう思わないと長続きしません。
それと売り物についての知識、自社製品、競合他社品、性能、需要、顧客のこと
あとは営業の基本ですが、手形・小切手・ローン・リース、契約書の知識
もちろんスキルは研修とか系統立てた業務経験で育成しますし、お金や法的なことは常に研修を受け知識を最新化します」
![]() 「営業のテキストがあるのですか?」
「営業のテキストがあるのですか?」
![]() 「宇佐見君、持ってきたか?」
「宇佐見君、持ってきたか?」
![]() 「はい、これは営業用の共通テキストです。会社規則のなかに『業務教育規則』というのがありまして、その付表で教育体系というのがあります」
「はい、これは営業用の共通テキストです。会社規則のなかに『業務教育規則』というのがありまして、その付表で教育体系というのがあります」
宇佐見課長が会社規則を開いて説明する。
![]() 「この表をご覧いただければ、マス目の中に番号がありそれぞれのテキストを記載しています。営業部員の研修用テキストとして、この営業用テキストのタイトルがありますね」
「この表をご覧いただければ、マス目の中に番号がありそれぞれのテキストを記載しています。営業部員の研修用テキストとして、この営業用テキストのタイトルがありますね」
![]() 「おお、さっき業務部で見せてもらったのは会社規則の付表だったのか。
「おお、さっき業務部で見せてもらったのは会社規則の付表だったのか。
そういうふうに体系化され、かつ使用するテキストなどとの対応が明確になっているのがすばらしいです」
![]() 「それらは一般的な営業のテキストです。弊社はさまざまな製品を作っています。家電を売る人と、エレベーターを売る人、レーダーを売る人は実は本籍が違うのです」
「それらは一般的な営業のテキストです。弊社はさまざまな製品を作っています。家電を売る人と、エレベーターを売る人、レーダーを売る人は実は本籍が違うのです」
![]() 「弊社は事業部制ですから、事業部をまたぐ人事異動はなくはないですが非常に少ない。他方、一つの製品に関わって設計、製造、販売を移ることは珍しくありません。またエレベーターの工場からエレベーターを売るために支社に転勤することも多い。
「弊社は事業部制ですから、事業部をまたぐ人事異動はなくはないですが非常に少ない。他方、一つの製品に関わって設計、製造、販売を移ることは珍しくありません。またエレベーターの工場からエレベーターを売るために支社に転勤することも多い。
他方、製品が異なる工場間での転勤は少ないし、家電営業からエレベーター営業に変わることはありません。所属と本籍は違い、所属が変わっても本籍は変わらないのです。
ですからエレベーター営業のテキストは、エレベーターの事業部が作ることになります。もちろんテキストは製品対応のものと、型名ごとのものがあります」
![]() 「ええと今のお話では、支社の営業はひとつにくくれるものではなく、それぞれの事業本部から来た営業担当を集めたという感じなのでしょうか?」
「ええと今のお話では、支社の営業はひとつにくくれるものではなく、それぞれの事業本部から来た営業担当を集めたという感じなのでしょうか?」
![]() 「そうそう、そういうイメージですね。エレベーター担当は支社を代わってもエレベーター、工場に戻るならエレベーター工場と決まっているわけです。
「そうそう、そういうイメージですね。エレベーター担当は支社を代わってもエレベーター、工場に戻るならエレベーター工場と決まっているわけです。
半面、総務や経理、人事といった職種は普遍的ですから、事業部を気にせず異動しますね」
![]() 「なるほど、組織がそのようになっているから、教育も組織というか必要に応じで行うということですね」
「なるほど、組織がそのようになっているから、教育も組織というか必要に応じで行うということですね」
![]() 「営業は製品によって異なるし、新製品が出るたびに、いや他社から新製品が出ても研修を受けることもある。
人事や経理は製品に関係ないし、工場でも支社でも仕事が同じだから、全社で同じ教育をすれば済む。人事や経理は楽でうらやましいよ」
「営業は製品によって異なるし、新製品が出るたびに、いや他社から新製品が出ても研修を受けることもある。
人事や経理は製品に関係ないし、工場でも支社でも仕事が同じだから、全社で同じ教育をすれば済む。人事や経理は楽でうらやましいよ」
![]() 「教育や研修は営業マンを一人前にするために行うのでしょうけど、一人前と判断する基準は決めてあるのですか?」
「教育や研修は営業マンを一人前にするために行うのでしょうけど、一人前と判断する基準は決めてあるのですか?」
![]() 「それは永遠の謎だろうね。ISO規格は斜め読みしたけど、『力量を備えていることを確実にする(ISO14001:2015 7.2b)』なんてあるけど、力量って点数とか箇条書きで示せるものなのかね。
「それは永遠の謎だろうね。ISO規格は斜め読みしたけど、『力量を備えていることを確実にする(ISO14001:2015 7.2b)』なんてあるけど、力量って点数とか箇条書きで示せるものなのかね。
車の運転なら免許証の有無を見れば良いかもしれない。しかし営業はそう簡単ではない。
大卒で新入社員教育をひと月、営業の研修を半年したから、売ってこいってわけにはいきません。長年の教育や経験で段々と力をつけていく。それはイチゼロというか階段を上るようなものではなく、遠浅海岸のような感じですかね。
そう考えるといつ力量を満たしたと言えるのか? 力量を満たすってどういうことなのですか?」
![]() 「いやいや、それは皆さんが決めることであり、私はそういう基準を決めているか、運用されているかを調査するわけでして……」
「いやいや、それは皆さんが決めることであり、私はそういう基準を決めているか、運用されているかを調査するわけでして……」
![]() 「それが明確でないと不適合というわけですか?」
「それが明確でないと不適合というわけですか?」
![]() 「高藤さん、質問があります。ISO審査員の力量は何で評価するのでしょう?
「高藤さん、質問があります。ISO審査員の力量は何で評価するのでしょう?
私もこの仕事が長いですから、ISO審査で応対するのはもう10回以上になります。とんちんかんな質問をされた方もいますし、何も質問をせず我々の説明を聞いて終わってしまった方もいます。そういう実態を見ると、審査員に要求される力量の水準は低いのか、それとも力量を満たす審査員は少ないのか分かりません。
高藤さんも一般企業で働いていて審査員になられたと推察しますが、何をもって審査員の力量があると判断されたのでしょうか?」
![]() 「いや、厳しい質問ですね。正直言って、営業マンより審査員のほうが力量を見る項目は少なく単純だと思います。規格要求事項つまり『しなければならない(shall)』とあるのは80個です。審査員の仕事は、それをしっかり覚えて、それが満たされているかどうかを調べるだけです。
「いや、厳しい質問ですね。正直言って、営業マンより審査員のほうが力量を見る項目は少なく単純だと思います。規格要求事項つまり『しなければならない(shall)』とあるのは80個です。審査員の仕事は、それをしっかり覚えて、それが満たされているかどうかを調べるだけです。
もちろん全部は見られませんから抜き取りで行うわけですが……
それなら簡単だと思われるかもしれませんが、それでも大変です。審査員研修を受けて基本を覚えたとみなされると、アプレンティスつまり見習いとして実際の審査に参加させるわけです。それを何回かして大丈夫となると一人前に数えられるという感じかと」
![]() 「営業も同じですね。ただ業務が多岐にわたる。そして仕事が定常的に進むことはないです。客の希望が標準品で済まないことが多く、仕様を変更したりオプションを付けたり簡略化したり。
「営業も同じですね。ただ業務が多岐にわたる。そして仕事が定常的に進むことはないです。客の希望が標準品で済まないことが多く、仕様を変更したりオプションを付けたり簡略化したり。
製品についての知識も自社品だけでなく、客から競合他社との比較を説明させられる。客先での使用条件によっては、耐久性などを見直す必要もあり、実施可能かどうか工場との交渉となる。
客がリースとか希望するもあるし、資金がなければ銀行に一緒に行くこともある。やっと売ったとしても、売り上げを回収するまで安心できない。おっとその前に信用状況の調査もしなければならない。
はっきり言って1年や2年のアプレンティスでは足りない。不渡りが出た時の対応なんて実際に経験できるかとなると、10年に一度あるかないか。経験しないほうが良いけれど……
すべてを経験して一人前になるときは定年ですよ」
![]() 「他社の状況はどうかは、もちろん守秘義務で言えないでしょうけど、力量が明確に記述されていて、それを満たしていることを確認しているなんてことはないと思いますね」
「他社の状況はどうかは、もちろん守秘義務で言えないでしょうけど、力量が明確に記述されていて、それを満たしていることを確認しているなんてことはないと思いますね」
![]() 飛行機のパイロットであればシミュレーターで、故障とか事故とかを模擬的に体験できるでしょうけど、不渡りが出たというのを模擬的に体験はできませんからね。本を読んで分かった気になるのと、泡食って走り回るのは大違いですからね。
飛行機のパイロットであればシミュレーターで、故障とか事故とかを模擬的に体験できるでしょうけど、不渡りが出たというのを模擬的に体験はできませんからね。本を読んで分かった気になるのと、泡食って走り回るのは大違いですからね。
それと営業というのはしっかりした足場の上での仕事じゃないのですよ。常に揺れ動く地面の上で仕事しているようなものです。半年一年かけて交渉してきて、いよいよ刈取りの時期と思っていると、内閣改造で政策が変わったとか補助金がなくなったなんてことは、よくあることです。
ああ、言いたいことは『力量を備えていることを確実にする』という文章はいかなることを意味するのか、実務においては想像できません。正直言えば幻とか虚像だと思います」
注:該当箇所の規格原文 ISO14001:2015 7.2 b)
Ensure that persons are competent on the basis of appropriate education, training or experience.
深く厳密に考えることではないのかもしれない。となると「力量があっても、仕事が務まらない」ことになるが?
![]() 「宇佐見君の話を形而上のことと受け取らないでほしい。我々は銭金の世界で生きているので、針の先で何人の天使が踊れるかなんて議論はしない
「宇佐見君の話を形而上のことと受け取らないでほしい。我々は銭金の世界で生きているので、針の先で何人の天使が踊れるかなんて議論はしない
今日の審査を上手くやり過ごすとか円満に終わっても、我々にとっては意味がありません。この話し合いの結果、一人前の定義がはっきりすれば相当の成果だといえる。
この機会によく聞いておきたい。本当を言ってどういう判断基準なのだろうかね?」
![]() 「審査員が不適切な行為や判断をした場合の手続きが決まっています。無礼な態度、誤った判断をすれば、みなさんは認証機関にでも審査員登録機関にでも苦情を言うことができます。
「審査員が不適切な行為や判断をした場合の手続きが決まっています。無礼な態度、誤った判断をすれば、みなさんは認証機関にでも審査員登録機関にでも苦情を言うことができます。
このとき審査員は力量がなかったことになるのでしょうか? それとも力量はあるけど誤ったということなのでしょうか?」
![]() 「となると営業マンが取り込み詐欺にあえば、それは力量がなかったのか、あるいは力量の基準が低かったのか、犯罪者が強かだったからしょうがないとなるのでしょうか?」
「となると営業マンが取り込み詐欺にあえば、それは力量がなかったのか、あるいは力量の基準が低かったのか、犯罪者が強かだったからしょうがないとなるのでしょうか?」
![]() 「現実には取り込み詐欺ばかりじゃないけど、営業を30年もしていれば何度か痛い目にあうもんだ。それをもって力量がないとは言えないと思うね。
「現実には取り込み詐欺ばかりじゃないけど、営業を30年もしていれば何度か痛い目にあうもんだ。それをもって力量がないとは言えないと思うね。
銀行なら貸倒れのリスクを混みで金利は決めているわけだ。サラ金の金利が高いのはそのリスクが高いから。
つまりどんな商取引でも設定した割合以下のエラーなら力量があるといえる……気がするが」
![]() 「磯原さん、どうなんでしょうかねえ〜」
「磯原さん、どうなんでしょうかねえ〜」
![]() 「もう審査はおしまいですか?
力量とは、イチゼロとか階段のようなものではないのでしょうね。
「もう審査はおしまいですか?
力量とは、イチゼロとか階段のようなものではないのでしょうね。
何事でも経験を積めばミスは少なくなり効率はあがる。でも犯罪にあうこともあるし、自分自身がミスすることもある。エラーレートを設定できるならよいけれど、エラーレートを決められない仕事もありますね」
注:エラーレートとはデータ伝送で誤りが発生する割合を数値化したもので、回線の質を表す。エラーレートが一定以下なら妥協することになる。
郵便の不達率、電子メールの不達率などすべて妥協の産物である。いや妥協すべき値というべきか。その不達率に我慢できないないなら、別の方法を採用するしかない。
ちなみに普通郵便の不達率は0.001〜0.01%という。電子メールの不達率は私の体験から、これより一桁以上多い気がする。
 |
|
|
|
|
|
|
電子メールが途中で消えることは珍しくない。
![]() 「運転免許があれば運転手が務まるかと言えば、そうではない。弊社の場合、社有車を運転するには社内で講習と技能試験を受けて合格しないとできない。ということはそうすることによって、会社のリスクを減らすために運転技能の高い人のみ運転を認めているわけです。
「運転免許があれば運転手が務まるかと言えば、そうではない。弊社の場合、社有車を運転するには社内で講習と技能試験を受けて合格しないとできない。ということはそうすることによって、会社のリスクを減らすために運転技能の高い人のみ運転を認めているわけです。
営業マンに限らず、会社が定める基準が失敗を負担できるかどうか、あるいは予防コストと失敗コストとの比較で決めているということに過ぎないのではないでしょうか?
となると力量とは客観的なものではなく、その組織がリスクを負えると考えた水準となるのではないですかね。かつ、その水準は雇用状況や教育水準によって上下することになる。
ISO審査では許容リスクをいかに定めたかは、技術レベルではなく経営判断と考えるべきでしょう。その場合でも、担当者がその水準を満たしたことの確認、あるいは満たすための施策をチェックすることはできるし、審査しなければならない」
![]() 「ということはどの会社も無意識であっても、費用対コストで力量を決めているはずだから、ISO審査ではその水準を是認せよということでしょうか?」
「ということはどの会社も無意識であっても、費用対コストで力量を決めているはずだから、ISO審査ではその水準を是認せよということでしょうか?」
![]() 「高藤さん、あなたも話すことが一貫していませんね。ほんの数分前に『力量の基準は会社が決めることであり、審査員は基準を決めているか、運用されているかを調査するだけ』とおっしゃいましたよ。
「高藤さん、あなたも話すことが一貫していませんね。ほんの数分前に『力量の基準は会社が決めることであり、審査員は基準を決めているか、運用されているかを調査するだけ』とおっしゃいましたよ。
組織が定めたリスクについては是認も何も、それが現実であるとしか言いようがないのではないですかね」
![]() 「磯原節なら現実はすべてOKになるのかね?
「磯原節なら現実はすべてOKになるのかね?
つまり上長が『あの人は一人前になったから仕事を一人でさせよう』と決めたらそれで十分と…」
![]() 「それが現実ではないのですか。まさかペーパーテストで何点以上なんてするのは意味がないでしょう。
「それが現実ではないのですか。まさかペーパーテストで何点以上なんてするのは意味がないでしょう。
もし決定した上長の判断が適切でなければ上長が責任をとるわけで、責任と権限は表裏でかつ釣り合っているのだから妥当じゃないですか」
![]() 「任された人は、誠心誠意、仕事に最善を尽くすのでしょうか」
「任された人は、誠心誠意、仕事に最善を尽くすのでしょうか」
![]() 「うーん、何とも言いようがないですが、地方公務員法でも国家公務員法でも『職務に専念すること』を宣誓します。それが有効かどうか知りませんが(注5)。
「うーん、何とも言いようがないですが、地方公務員法でも国家公務員法でも『職務に専念すること』を宣誓します。それが有効かどうか知りませんが(注5)。
自衛隊はもっと厳しくて、任官するとき『事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います(注6)』と宣誓します。
だが一般企業の就業規則(注7)では『労働者は(中略)、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない』とある程度で、宣誓を求めていません。
公務員並みに『専念』あるいは自衛隊並みに『危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務める』ことを要求できるでしょうか?」
![]() 「ちょっと、それが力量とどう関係するのですか?」
「ちょっと、それが力量とどう関係するのですか?」
![]() 「高藤さんが言い出したからですよ、最善を尽くすのかと。
「高藤さんが言い出したからですよ、最善を尽くすのかと。
その意図は、力量だけでは不十分だからでしょう。力量があってもそれを発揮してもらわないと」
![]() 「ならわが社の現実は、十分規格要求を満たしていることになるよな。ミスがあっても、それは許容範囲なら、規格不適合といわれる筋はない」
「ならわが社の現実は、十分規格要求を満たしていることになるよな。ミスがあっても、それは許容範囲なら、規格不適合といわれる筋はない」
![]() 「でもその発想なら、力量を確認もせずにいても、リスクを取るから良いのだということにもなる。一番大事な顧客あるいは環境に対する責任が漏れていませんか?」
「でもその発想なら、力量を確認もせずにいても、リスクを取るから良いのだということにもなる。一番大事な顧客あるいは環境に対する責任が漏れていませんか?」
![]() 「顧客に対する責任や環境汚染が発生した時の原状復帰の費用は、失敗コストと言える。現実にそれらの責任は企業が負う。ならば力量がどうあれ、最終的にリスクを負うのは会社だ。であれば持つべき力量を企業が決定して、外部からそれをどうこういわれることはない」
「顧客に対する責任や環境汚染が発生した時の原状復帰の費用は、失敗コストと言える。現実にそれらの責任は企業が負う。ならば力量がどうあれ、最終的にリスクを負うのは会社だ。であれば持つべき力量を企業が決定して、外部からそれをどうこういわれることはない」
![]() 「大震災の原発の場合、企業が責任を負いきれませんでしたよ」
「大震災の原発の場合、企業が責任を負いきれませんでしたよ」
![]() 「今はそんな極限の議論をしているのではないでしょう。通常の営業マンが持つべき製品販売における力量を論じていたはずだ。普通の能力のある人に、弊社の教育訓練をして、並みの管理能力のある管理者が指揮監督しているならば、万が一発生した問題には十分対処できるだろうということだ」
「今はそんな極限の議論をしているのではないでしょう。通常の営業マンが持つべき製品販売における力量を論じていたはずだ。普通の能力のある人に、弊社の教育訓練をして、並みの管理能力のある管理者が指揮監督しているならば、万が一発生した問題には十分対処できるだろうということだ」
![]() 「我々は暗黙のうちに最低限の能力、識字、道徳、責任感を持つ人を想定しています。しかし規格は、そういう要件を満たさない誠意もなく、職務に忠実でない人々を、想定しているのかもしれません」
「我々は暗黙のうちに最低限の能力、識字、道徳、責任感を持つ人を想定しています。しかし規格は、そういう要件を満たさない誠意もなく、職務に忠実でない人々を、想定しているのかもしれません」
![]() 「法律であろうと契約書であろうと、書かれた文言がすべてです。作文した人がどういうものを想定していたにしろ、それはまったく意味がありません。
「法律であろうと契約書であろうと、書かれた文言がすべてです。作文した人がどういうものを想定していたにしろ、それはまったく意味がありません。
規格作成者がその意図を文章に書き表せなかったなら、規格作成者に力量がなかったというだけです。
ISO規格において解釈改憲なんて許されませんよ。なにせグローバルスタンダードですからね」
15時頃に、高藤の本社での仕事は終わった。
![]() 「高藤さんはこれから岡山ですか、新幹線で3時間半、大変ですね」
「高藤さんはこれから岡山ですか、新幹線で3時間半、大変ですね」
![]() 「まあ、商売ですから。飛行機にしようかとも考えましたが、天候とか変更が生じたときを考えると、新幹線のほうが安心でしょう」
「まあ、商売ですから。飛行機にしようかとも考えましたが、天候とか変更が生じたときを考えると、新幹線のほうが安心でしょう」
![]() 「ここから東京駅まで歩きですか?」
「ここから東京駅まで歩きですか?」
![]() 「地下鉄に乗っても半分以上は歩かないと……
「地下鉄に乗っても半分以上は歩かないと……
あの、まだ20分くらい余裕があるのですが、お話しできますか?」
![]() 「私はよろしいですが、高藤さんは乗り遅れないように願いますよ」
「私はよろしいですが、高藤さんは乗り遅れないように願いますよ」
![]() 「磯原さんのお考えを知りたいのですが、この審査で不適合を出して良いのか、出さないでほしいのか?」
「磯原さんのお考えを知りたいのですが、この審査で不適合を出して良いのか、出さないでほしいのか?」
![]() 「そんなこと我々は関心がありません。あるがまま見てもらい、まずければいくらでも不適合を出してほしいですね」
「そんなこと我々は関心がありません。あるがまま見てもらい、まずければいくらでも不適合を出してほしいですね」
![]() 「弊社を選ぶ前に、御社はだいぶ難しいことを要求したと聞いております」
「弊社を選ぶ前に、御社はだいぶ難しいことを要求したと聞いております」
![]() 「誤解されているかもしれませんが、私どもはちゃんとした審査をしてほしいということです。
「誤解されているかもしれませんが、私どもはちゃんとした審査をしてほしいということです。
異議を申し立てたのは、合法であることを違法だとして不適合を出したこと、更にはそれに対する問い合わせになんら回答を返さず不適合を取り消さなかったこと、翌年の審査ではその不適合はなかったこととして審査したなど誠意も正義もないことに怒ったのです。
おっと、御社ではありませんよ、他の複数の認証機関でそういうことがあったということです」
![]() 「そうだったのですか。詳細を聞いておりませんでした。ということは普通に審査をしてよいということですね」
「そうだったのですか。詳細を聞いておりませんでした。ということは普通に審査をしてよいということですね」
![]() 「当たり前でしょう。悪いものを見逃せなどと語ったことは一度もありません。要求したのはISO17021に基づいた審査をしてほしいということです。
「当たり前でしょう。悪いものを見逃せなどと語ったことは一度もありません。要求したのはISO17021に基づいた審査をしてほしいということです。
もちろん見逃しはマイナス評価となります」
![]() 「なるほど、良く分かりました」
「なるほど、良く分かりました」
![]() 「正直申しますが、今回の審査は我々にとってISO認証の意味の再考につながります。端的に言えば認証を続けるか、止めるかです。
「正直申しますが、今回の審査は我々にとってISO認証の意味の再考につながります。端的に言えば認証を続けるか、止めるかです。
審査の結果、しっかりした証拠と根拠で不適合が出されれば、弊社は認証の価値を認めて認証を継続するでしょう。あるいは真にためになる意見が付記されていることも評価されるでしょう。
しかし間違えた判断とか、見逃しとか、規格にない有益な側面とか、突飛な解釈を賜れば、弊社は認証を返上します。これはオープニングミーティングで山内が申しあげたとおりです」
![]() 「ご期待に応えるよう頑張ります。もし期待していないなら意表を突きましょう」
「ご期待に応えるよう頑張ります。もし期待していないなら意表を突きましょう」
![]() 「山内が申しておりました。三日後を楽しみにしていますと」
「山内が申しておりました。三日後を楽しみにしていますと」
![]() 本日の不思議
本日の不思議
私は昔から「力量」(1996版は「能力」と訳していた)というものを、明確にできるのか疑問だった。ISO9001のときは製造や検査だったから、割合とcompetenceをイメージできた。だけどMS規格となり書いていることが漠然となってきて、理解というかイメージすることが困難になってきた。
販売なら力量をイメージできるが、営業となると漠然となるし、更にマーケティングとなると創造力を要する世界となる。それは設計でも購買でも同じである。
創造力を求める仕事、非定型な仕事、そういった業務において必要な力量を設定できるのか?
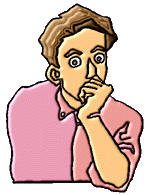 いや逆に考えてみよう。与えられた業務を遂行できる力量を具備する人ばかりなら、エクセレントカンパニーであることは間違いない。
いや逆に考えてみよう。与えられた業務を遂行できる力量を具備する人ばかりなら、エクセレントカンパニーであることは間違いない。
そしてISO認証している企業(全規格合わせて37,000件 2023.11.08時点)の中で、エクセレントカンパニーと称されるのは数十社だ。その比率がコンマ以下であることから、規格でいう力量はとんでなく甘いに違いない。
このロジックの連鎖のどこかおかしいだろうか?
IBM社は過去現在、エクセレントカンパニーとみなされている。1990年頃、報告書に社内で起きた横領や会社が支払った罰金などを記載して、公明正大な会社だと高く評価された。
しかしあれから30年経った今も、毎年横領事件や罰金を記載している。正直でエクセレントカンパニーであることは間違いない。しかしそういう会社であっても社内犯罪や違反をゼロにはできないのだ。
かように解釈困難な文章を基に、無造作に審査できるという力量は私にはない。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
コモディティとは元々は、日用品、消耗品などを意味する言葉であった。 コモディティ化とは、当初は高機能、高性能、高付加価値であったものが、技術の進歩や市場の扱いが一般的な商品になること。 家電品はもちろん自動車も高級車以外は日用品になった。50年前、車を買えば日曜日には洗車してワックス掛けをしたものだが、今はファミリーカーや軽自動車をピカピカにワックス掛けする人はめったにいない。 | |
注2 | ||
注3 |
「針(ピン)の上で天使は何人踊れるか」とはいわゆる中世の神学論争の例として取り上げられる事例である。多くの場合、ばかばかしいことを議論するという意味でつかわれる。 | |
注4 |
品質コストとは、品質を維持するためのコストをいう。品質コストは大きくは失敗コストと予防コストに分かれ、細かくは評価コストや内部失敗コスト、外部失敗コストなどに分ける人もいる。 予防コストは問題を起こさないための費用であり、失敗コストは問題の対策に要した費用である。 | |
注5 |
地方公務員法 「第30条すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」 「第31条職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」 国家公務員法 「第96条第1項すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」 「第97条職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」 | |
注6 | ||
注7 |
厚労省 就業規則ひな形では下記のように記述されている。 「第10条 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。」 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |
