*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
岡山が自信をもって計画したロールプレイだったが、あまりにもストーリーが複雑なためかうまい具合に進まない。それで1回目は面白みのないお芝居になってしまった。
ただシナリオだけでなく演者たちもオロオロとしていたので、同じシナリオでもっと良く演じられると、手を挙げた人は多数だった。
しかし磯原は最初のメンバーにリベンジしてもらいたいと、同じメンバーで再演してもらうことにした。
メンバーが話し合った結果、役割も最初通りで行くという。
今度はスイスイといくだろうか? いやスイスイといくことはないが、客観的に見て適切な判断行動をしてほしい。
| 力丸 | 池神 | 新沢 | 人見 | 中沢 | ||||
 |
 |
|||||||
| 環境課長 | 水質 | 廃棄物 | 省エネ | 排水処理運転 |
指定された人たちが各部屋に入ったのを見て、山内が課長役の力丸のスマホに電話する。
![]() 「スラッシュ電機さんですか。私はお宅の工場北側の町内会長をしております山内と申します」
「スラッシュ電機さんですか。私はお宅の工場北側の町内会長をしております山内と申します」
「はい私は環境課の力丸と申します。どんなご用件でしょう?」
![]() 「お宅の工場の北側道路とお宅の塀の間に用水路がありますね。そこに大量の魚が浮いてるんですよ。近くに住む人からお宅に苦情を言ってほしいといわれましてね。
「お宅の工場の北側道路とお宅の塀の間に用水路がありますね。そこに大量の魚が浮いてるんですよ。近くに住む人からお宅に苦情を言ってほしいといわれましてね。
大至急調べてください。もし有害ならば水を堰き止めるとか、近隣住民への注意とか避難させる必要があるなら広報してほしいのです」
「はっ、ご連絡ありがとうございます。すぐに調べまして対応します……」
力丸は立ち上がり大声を出す。
「全員聞いてくれ。
工場の北側の道路と工場の間に用水路がある。そこに大量の魚が浮いていると町内会長から電話があった。
役割分担するから各自協力してくれ。
人見君と新沢君は自転車で用水路に急行する。状況を確認してほしい。工場の東端から西端までみてほしい。途中で発生しているのか、上流からなのかとか、よく見てほしい。
それから工場から水が流れ出ているかどうか、排水口と塀とか土手からの染み出しなどあるかもしれないから点検を頼む。
現場を見たらすぐに状況を私に電話してほしい。二人で同じことをしてもしょうがないから分担してくれよ。
皆ヘルメット着用のこと。スマホ忘れるな」
「工場の側溝の系統には雨水しか流れませんが?」
「分かっている。だが万一がある。今日は晴天だから、本来側溝は乾いているはずだ。もし側溝に水が流れていればどこからなのか調べること」
二人が部屋を出ていく。
「池神君は、今ここから排水処理の中沢さんに電話して、今から排水処理施設の点検をするように伝えてほしい。君はそれから排水処理施設に向かい、点検結果を確認すること。その結果を私に電話報告をしてほしい。
点検結果によってどう対応するか相談しよう。
では行ってくれ」
二人が出ると、力丸も部屋を現場に向かいながら電話をする。
![]() 「はい、こちら製造課です」
「はい、こちら製造課です」
 「あっ、製造課長ですか? 実は外部から用水路に魚が浮いているという苦情がありました。
「あっ、製造課長ですか? 実は外部から用水路に魚が浮いているという苦情がありました。
メッキと塗装をしているのはお宅の課ですので、製造工程とか工場のピットから外部に液漏れとかしていないか点検してほしい。私は今そちらに歩いているところです。
はい、お願いします」
力丸は歩きながら次に総務に電話をする。
![]() 「総務の石川です」
「総務の石川です」
「環境課の力丸です。
近隣住民から工場北側の塀の外の用水路に、魚が浮いていると電話がありました」
![]() 「大至急、原因が当社かどうかの確認。当社なら対応をお願いします。続報を待ちます」
「大至急、原因が当社かどうかの確認。当社なら対応をお願いします。続報を待ちます」
「ただいま調査中です。私は工場内を点検して現場に行く途中です。数分後に第一報を送ります。
もし行政とか住民から問い合わせあれば、現在調査中と回答してください」
![]() 「もう少し状況をはっきりさせてください。まず原因究明と当面対策をお願いします」
「もう少し状況をはっきりさせてください。まず原因究明と当面対策をお願いします」
「了解、詳細わかり次第報告します」
こちらは役者以外の人がいる会議室だ。
役者以外はコーヒーを飲んでモニターを観ている。こちらは気楽だ。
 |
|
 |
![]() 「おお、前回と違って力丸さん迷いがなくなり行動的になったなあ〜」
「おお、前回と違って力丸さん迷いがなくなり行動的になったなあ〜」
![]() 「そりゃ、二回目ですから」
「そりゃ、二回目ですから」
![]() 「次のシナリオも1回目はグダグダになるかもしれませんね」
「次のシナリオも1回目はグダグダになるかもしれませんね」
![]() 「何事も経験を積むしかありません」
「何事も経験を積むしかありません」
中沢さんがいる屯所である。
池神さんが部屋に入ってくる。
![]() 「ええとシナリオを見ると、廃水処理施設には異常がないとあります。ですから私は点検結果異常がなかったことを確認しました……でいいのよね?」
「ええとシナリオを見ると、廃水処理施設には異常がないとあります。ですから私は点検結果異常がなかったことを確認しました……でいいのよね?」
「それでよろしいと思います。では排水処理施設には異状なく、漏洩もなかったことを確認しました。
ちょっと待ってね」
池神は力丸に電話をかける。
「課長ですか? 池神です。中沢さんと排水処理施設を点検しましたが、異常ありません。
側溝への漏洩もありません
……
了解しました。私たちは構内の側溝に水や油の溜まりがないか点検します。
中沢さん、用水路に魚が浮いているそうです。課長からの話ですが、北側の側溝の排水口で雨でないのに水が外に流れているので、側溝をたどって漏れているところを探せということです」
![]() 「了解しました……といってもどうするのかな?」
「了解しました……といってもどうするのかな?」
「最初にやったのと同じく、モニターで見てみましょう。Google Mapと同じようなものでしょう。工場全体から見たいところをクリックして、ほうほう、先ほどと同じ場所にバキュームカーが停車していて、そこから液漏れしているのが見えます。
課長に電話しよう。
課長ですか? 構内の通路に廃棄物業者のバキュームカーが停車していて、そのタンクから液漏れしています。大した量ではないですが継続して流れています。とりあえず側溝を土嚢で塞ぎましょう。車両の周囲をスピルキットで囲ってうまくいくとは思えないので、側溝に溜める方が安心ですね。側溝の容量はバキュームカーよりは多いでしょう。
それと運転手を捕まえて対応させましょう。
了解、後はそちらかの指示待ちということで
中沢さん、守衛所に連絡してバキュームカーの運転手を捕まえて車からの漏洩を止めるようにさせて」
中沢は守衛所に電話する。
![]() 「環境課の中沢です。廃棄物業者のバキュームカーが入場してますね。そのバキュームカーから液漏れしています。大至急、運転手を捕まえて漏れを止めるよう指示してください」
「環境課の中沢です。廃棄物業者のバキュームカーが入場してますね。そのバキュームカーから液漏れしています。大至急、運転手を捕まえて漏れを止めるよう指示してください」
![]() 「ええと資材に来ていますね。このままお待ちください。
「ええと資材に来ていますね。このままお待ちください。
……
資材にいた運転手を捕まえました。すぐに車のところに行かせました。運転手が到着するまでそこで待っていてください。状況を運転手に伝えてほしい」
![]() 「側溝に流れているほか、路面も濡れています。水ではないようなので、通路の閉鎖もすべきかもしれません」
「側溝に流れているほか、路面も濡れています。水ではないようなので、通路の閉鎖もすべきかもしれません」
![]() 「ええと資材に来ていますね。電話を切らずにお待ちください。
「ええと資材に来ていますね。電話を切らずにお待ちください。
……
バキュームカーの運転手が今そちらに向かいました。
路面の液体を流すとか除去する必要があれば、自衛消防隊を出動させます。必要ですか?」
![]() 「私には分かりません、守衛所の人が現場を見て判断してください」
「私には分かりません、守衛所の人が現場を見て判断してください」
![]() 「了解しました。私も今から行きますから、私たちが現場に行くまでそこでお待ちください」
「了解しました。私も今から行きますから、私たちが現場に行くまでそこでお待ちください」
池神は石川に電話する。
「おーい、石川さん。側溝を閉鎖するってどうするのかな?」
![]() 「そこまで決めてないんですよ。お二人が側溝を塞いだことにしましょう。
「そこまで決めてないんですよ。お二人が側溝を塞いだことにしましょう。
本当は土嚢で塞ぐのも簡単じゃないんですけどね。最初はビニールシートでも側溝にテープでも止めてそれを土嚢で抑えるとかしないと、土嚢を置いただけじゃ止まるわけないですよ、アハハ」
![]() 「それじゃ私たちは、課長に電話してと……」
「それじゃ私たちは、課長に電話してと……」
中沢が電話する前に、池神の電話が鳴る。
「用水路に市と消防署が来た。採水して酸性の廃液が流れたと判断された。
市が業者を手配して用水路は閉鎖して汲み取りするようだ。
もう我々は用水路には手を出すことはない。その代わり我々は構内に漏れた分の対策をしなければならない。
側溝のほうはどうした?」
「今、ガードマン役の磯原さんが来ました。彼と話をしましょう」
![]() 「お疲れ様です。2回目のロールプレイを終了します」
「お疲れ様です。2回目のロールプレイを終了します」
「おお、上手くいったのですかね?」
![]() 「これから討論会です」
「これから討論会です」
・
・
・
・
また全員会議室に集まる。
今回は前ほど時間がかかっていない。
![]() 「さて、意見交換といこう」
「さて、意見交換といこう」
![]() 「二つの面からの検討がありますね。
「二つの面からの検討がありますね。
ひとつは前回に比べてどのように変化、まあ改善されたかということ。
もうひとつは、この方法のロールプレイは意味があるのかというと厳しいかもしれませんが、効用としてはどうなのかという疑問があります」
![]() 「では前者から、まず役者の方が慣れてきたことが大きいと思いますが、今回は迷うことなく即断即決、即行動になったと思います。実際の緊急事態では、これほど早くは動けないでしょうね」
「では前者から、まず役者の方が慣れてきたことが大きいと思いますが、今回は迷うことなく即断即決、即行動になったと思います。実際の緊急事態では、これほど早くは動けないでしょうね」
「まあ、最初は無様でしたが、今回程度なら合格かと思います」
「役者をしましたが、条件設定が難しいというか複雑なのですよ。自分の工場じゃないから、何を作っているか、どんな設備があるのか、レイアウトも覚えなければならない。
この工場でメッキをしているというのは二度目の前に配布された資料を読み直して気が付きました。最初の時はメッキをしているとは思ってもいませんでした」
![]() 「最初のときの反省会で、問題が起きるのは異常が二つ重なったときだという話がありましたね。私もそう思うのですが、こういったロールプレイでは条件を単純化しないと、スイスイと進まないのではないですかね」
「最初のときの反省会で、問題が起きるのは異常が二つ重なったときだという話がありましたね。私もそう思うのですが、こういったロールプレイでは条件を単純化しないと、スイスイと進まないのではないですかね」
![]() 「おっしゃるのは良くわかります。しかし現実に当社で起きている事故とか違反は、なにかひとつ異常になって問題が起きたというのはないのです。
「おっしゃるのは良くわかります。しかし現実に当社で起きている事故とか違反は、なにかひとつ異常になって問題が起きたというのはないのです。
問題の原因を追究すると、必ず何かしら異常があって、そこに新たな異常、別の故障とか振動などが加わって表面化しています。
ですからロールプレイでも、複数の原因があって問題が起きたという流れでないとお芝居にすぎません」
![]() 「問題は複数の異常が重なって起きるというのは、事実なんですか? 」
「問題は複数の異常が重なって起きるというのは、事実なんですか? 」
![]() 「実例をあげましょう。工場名は伏せますが昨年起きた重油の漏洩事故です。工場内で建設工事がありまして、そのとき工事車両が屋外タンク貯蔵所の防液提と中のタンクにぶつかり破損させた。
「実例をあげましょう。工場名は伏せますが昨年起きた重油の漏洩事故です。工場内で建設工事がありまして、そのとき工事車両が屋外タンク貯蔵所の防液提と中のタンクにぶつかり破損させた。
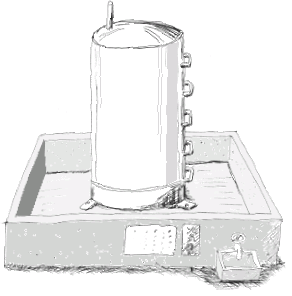 担当者が詳しく調べず問題ないと判断してそのままにした。だけど実際はタンクの足が損傷し、また防液提が破損していた。
担当者が詳しく調べず問題ないと判断してそのままにした。だけど実際はタンクの足が損傷し、また防液提が破損していた。
その数か月後にタンクが倒れて中の重油が漏洩して工場外まで流れたということがありました(第66話)。このとき車がぶつかったときに点検しなかったことを隠すために、漏洩事故をもみ消そうとした。
因果を見れば工事車両がぶつかったとき、しっかりと点検しておけばその後の問題はなかった。また漏洩事故が起きても、下手に隠さずしっかりと対応して是正処置をすれば良かったということです」
![]() 「なるほど、異常が重なってか……」
「なるほど、異常が重なってか……」
![]() 「ひとつの部品が公差を外れても、それが直に不良になるとか組み立てできないということはないよ。もしそうなら公差の決定が統計的じゃない。たいていは関係する部品双方が公差を外れたから問題になるんだ」
「ひとつの部品が公差を外れても、それが直に不良になるとか組み立てできないということはないよ。もしそうなら公差の決定が統計的じゃない。たいていは関係する部品双方が公差を外れたから問題になるんだ」
![]() 「ええと改ざんの発覚もありました。通常の業務でしていれば担当者は故意、管理者は黙認しているはずです。双方が気付かないようなら能無しです。問題になるのは担当者が変わった、管理者が変わった、監査が入った、あるいはそれを知っている担当者が上司を貶めようとしたときでしょうか(第82話)。
「ええと改ざんの発覚もありました。通常の業務でしていれば担当者は故意、管理者は黙認しているはずです。双方が気付かないようなら能無しです。問題になるのは担当者が変わった、管理者が変わった、監査が入った、あるいはそれを知っている担当者が上司を貶めようとしたときでしょうか(第82話)。
正確なところは分かりませんが、社内で改ざんしているところはあるだろうと思います。担当者も管理者も変わらず、つじつまを合わせていれば見つかりません。何かが変わるとぼろが出るわけです。
今回のシミュレーションでは、関係することが多すぎたかもしれません。今回は社内だけの問題ではなく、入場していた廃棄物業者の車が漏洩事故を起こしたということで、通常の緊急事態としては想定外だろうと思います。
しかし関連会社では、納入に来た運送会社のトラックが構内を走行中に、グレーチングを跳ね上げて、それが燃料タンクに当たりタンクが破損して燃料が垂れて、路面に垂れた燃料が側溝を経由して外部の用水路に流出したことが起きてます。火災にならなくてよかったです」
注:グレーチングとはいろいろな意味で使われるが、ここでは側溝のフタや足場などで使われる網目状の鉄板です。鉄板やコンクリートより軽くて丈夫で排水が良いので広く使われる。
![]() 「余計な話になってしまいましたが、要するに実際に起きる事故とか違反は、異常がひとつということはまずありません」
「余計な話になってしまいましたが、要するに実際に起きる事故とか違反は、異常がひとつということはまずありません」
![]() 「う〜ん、そうかねえ〜」
「う〜ん、そうかねえ〜」
![]() 「事故ばかりではありません。昨年ですが社内の某工場から業者に渡した産業廃棄物が不法投棄されたという相談がありました(第89話)。
「事故ばかりではありません。昨年ですが社内の某工場から業者に渡した産業廃棄物が不法投棄されたという相談がありました(第89話)。
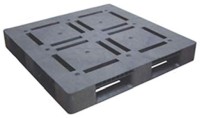 調べると工場が出した廃棄物が不法投棄されたのではなく、廃棄物処理業者が不法投棄したときに当社の名入りのパレットを使っていたということでした。坂本さんと私が出張して状況を調べ、特段問題ないだろうという結論になりました」
調べると工場が出した廃棄物が不法投棄されたのではなく、廃棄物処理業者が不法投棄したときに当社の名入りのパレットを使っていたということでした。坂本さんと私が出張して状況を調べ、特段問題ないだろうという結論になりました」
![]() 「そんな問題くらい本社が出しゃばらなくても、工場のメンバーが処理できるだろう」
「そんな問題くらい本社が出しゃばらなくても、工場のメンバーが処理できるだろう」
![]() 「工場で対応できなかったから本社にヘルプ要請が来たのです。
「工場で対応できなかったから本社にヘルプ要請が来たのです。
このときも単に知らなかったとか誤ってとか単純でなく、行政や廃棄物業者など外部との関わりがあります。要するに社内だけで完結する不具合なんてまずありません
環境事故や違反について原因究明や対策を考えようとすると、簡単な問題はないということです」
![]() 「なるほど、言われてみれば分かります」
「なるほど、言われてみれば分かります」
![]() 「すぐにストーリーが分かってお芝居できるようなシナリオでは、現実には問題にならないでしょう。状況をリアルにするなら、細かい情報が欲しいし、それは社内だけとか自分の知識と経験だけではだめなんです」
「すぐにストーリーが分かってお芝居できるようなシナリオでは、現実には問題にならないでしょう。状況をリアルにするなら、細かい情報が欲しいし、それは社内だけとか自分の知識と経験だけではだめなんです」
![]() 「石川君の大演説というのを初めて聞いたぞ。ともかく言いたいことは分かった。
「石川君の大演説というのを初めて聞いたぞ。ともかく言いたいことは分かった。
環境業務に就いていると事故とか違反はつきものだ。それを処理するために予行演習をしようとすると、簡単で分かりやすい筋書きなど現実にはない。
実際にあるものにしようとすると、状況を設定するにはさまざまな情報が必要となる。その情報を一覧にでもして渡せばよいのだろうが、現実にはその情報を歩き回って収集しなければならないということだ」
![]() 「まさしく山内さんのおっしゃる通りです。
「まさしく山内さんのおっしゃる通りです。
そういうことから、今回の研修は実践的にしようと考えたのですが、そういうものはお芝居には向かないのかもしれません。過去の事故違反の顛末をまとめて、ひたすらそれを読んで追体験してもらうしかないのかもしれない」
![]() 「真に力をつけるには、実際に事故や違反を経験してもらうしかないのかもしれないね」
「真に力をつけるには、実際に事故や違反を経験してもらうしかないのかもしれないね」
![]() 「だが開会の挨拶で山内さんが語ったように、事故や違反は経験を積むほど発生しないのだよ。
「だが開会の挨拶で山内さんが語ったように、事故や違反は経験を積むほど発生しないのだよ。
だからそういう発想でなく、なんとかシミュレーションする方法を考えないとならないということだ」
![]() 「作成したシナリオ全編を通さなくても、例えば今回のお芝居なら、課長が連絡を受けて部下に指示するところまででも意味はあるよね。
「作成したシナリオ全編を通さなくても、例えば今回のお芝居なら、課長が連絡を受けて部下に指示するところまででも意味はあるよね。
力丸さんにこんなこと言うのは失礼だけど、最初より二度目のほうが指示命令はしっかりしていた。それは練習の効果だよね」
「1回目終わったときに、皆さんからいろいろ言われて反省したということです」
![]() 「余部さんのおっしゃるように、あまり物語が長いと分岐も多くなり単なるお芝居になってしまいますね。インプットがあって、そのインプットを受けてどのように判断してどのような行動をするかを決断する部分だけなら、もっとシンプルにそして現実味のある話にできそうです」
「余部さんのおっしゃるように、あまり物語が長いと分岐も多くなり単なるお芝居になってしまいますね。インプットがあって、そのインプットを受けてどのように判断してどのような行動をするかを決断する部分だけなら、もっとシンプルにそして現実味のある話にできそうです」
![]() 「なるほど、そういうあまり複雑でない実効性のあるロールプレイを検討することが必要だな」
「なるほど、そういうあまり複雑でない実効性のあるロールプレイを検討することが必要だな」
![]() 「そうですね、主催者である私どもの検討不十分であることをお詫びします。
「そうですね、主催者である私どもの検討不十分であることをお詫びします。
次のロールプレイから長さを半分にちょん切るなど短くして進めたいと思いますが、よろしいですか?
初回のように丸投げということではなく、事前にシナリオを説明してそれを部外者が関わらないパートだけでも演じてもらうということでいかがでしょう。
本日はあと2話だけやってみようと思います。
それから明日の予定ですが、ロールプレイをちょっと棚上げにして、本来は終了時にお土産として配布予定だった事故違反事例集がありますので、その中からいくつかを解説するという内容に変更して行いたいと思います。
いかがでしょう?」
![]() 「とりあえずそうしよう。皆さんご了承願います。
「とりあえずそうしよう。皆さんご了承願います。
事例集はワシも読んでいるが価値あると思う。ロールプレイはその中から選んだものなのだが、事故事例をもとにしているため関係者が多すぎることと、ストーリーが複雑すぎたようだ」
![]() 本日の疑問に備えて
本日の疑問に備えて
「なぜ順調にいかないお話を書いたのか?」という疑問があろうかと
私自身の経験では、仕事がうまくいったと思えるのは、3割くらいじゃないでしょうか。
もし5割が成功だったならものすごく優秀だと思うし、8割が成功と思うなら要求水準が低すぎるのではないでしょうか。開発者に限らず製造部門でも、チャレンジした結果、ダメだったとかプロジェクト崩れになってしまうのも10回に1回や2回はあるものです。
まっ、そんな風に思っています。
現実がそうであるなら小説もそう書かねば、ご都合主義でしかありません。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
外資社員様からお便りを頂きました(23.12.21)
おばQさま とてもリアルで参考になる記事を有難うございます。 >簡単で分かりやすい筋書きなど現実にはない >仕事がうまくいったと思えるのは、3割 本当にその通りと思いますし、そうした体験を蔑ろにしなかったから、こういう記事がおかきになれるのだと思います。 とても勉強になりました。 私が体験した状況設定訓練では、問題設定は一つで、目的も一つにされておりました。 例として設定は「災害発生への対応」 目的は「適切な指揮命令」 この場合は被験者は「災害発生の指揮責任者」の立場で、管轄内で災害が発生。 その対応の適切さを見ます。 事前に手持ちの消防隊が駒で示され、大きな地図がおかれる。 災害発生の通知が入り、それに対する指揮と対応を行う。 対応が不適切だと、その時点で中断して、講評と反省。 適正に対応していると、次から次への災害が発生してゆきます、つまり指揮能力が高ければ設定が過酷になる。 体験できる人間は一人ですが、一回のサイクルが短いので、交代して演習ができます。 その経験から言えば、むしろ初期設定は簡単にして、状況を対処したら、適宜 厳しい状況を追加してゆけば良いのだと思います。 例として「バキュームカーの運転手は昼食で外部に出て連絡取れず」とか「工場外で死んだ魚をスマホで写真にとっている人を発見」とか。 そういう状況で、どう対処するかは、とても興味深いのです。 |
外資社員様 毎度コメントいただきありがとうございます。 会社や工場によって消火訓練でも緊急時訓練でもいろいろあると思います。 私は計測器管理をしていたとき、同じ課だったので火災報知器がなると一緒に現場に駆け付けました。 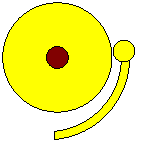 実際にボヤだったこともあり、禁煙のところで喫煙して火災報知器が検知したり、まったくの誤報だったこともありました。
実際にボヤだったこともあり、禁煙のところで喫煙して火災報知器が検知したり、まったくの誤報だったこともありました。たったそれだけの経験しかありませんが、訓練と実際の出動は全く違いました。ひとつはやはり気持ちですね。今回はこうゆう想定でするぞと計画があり、当然そこで出火したことになり、ナンバーのない社内の消防車をどこに停めるか、どこの消火栓を使うか、そこからホースをもって駆けつける道筋など考えることがありません。体力つくりにはなりますが、訓練ではないでしょう。 そういった現実をどのように訓練するのか、工夫のいることですね。 不良発生とかライントラブルという訓練は聞いたことがないですが、やろうとするといろいろな条件設定をどうするのかと途方にくれます。技術的な問題とか材料未着でラインストップしたときの、人の扱いとか仕掛をどうするかということなら紙上演習でも済みそうです。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |