*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
11月も中旬となった。外は木枯らし、と言っても東京は磯原が住んでいた福島と違いまだ手袋はいらず
 コートなど無縁だ。
コートなど無縁だ。
東日本大震災のとき、福島の工場では雪まじりの寒風の吹く工場の空き地に何時間も避難していて凍えた。同じ災害でも暖かかったらだいぶ心理的にはよかっただろう。
ともかくいつ何時再びそういうことにならないとは限らない。また本社の立場では、被災した工場に支援や指導をする役割であるから、準備や対応を考えねばならないなと磯原は思う。
今日は山内参与から指示されているパンデミック発生時の対応を、どう進めるかの話し合いである。メンバーは磯原と田中、坂本である。
![]() 「会議の前にちょっと話があるんだ」
「会議の前にちょっと話があるんだ」
![]() 「どうぞ、どうぞ」
「どうぞ、どうぞ」
![]() 「先だって緊急事態の研修会をしたでしょう。それでさ、参加した課長が広めたのか、それとも関係者が感じたのか、工場の担当者レベルから多々問い合わせというか勘繰りのメールが来ている。
「先だって緊急事態の研修会をしたでしょう。それでさ、参加した課長が広めたのか、それとも関係者が感じたのか、工場の担当者レベルから多々問い合わせというか勘繰りのメールが来ている。
噂を抑えるのに、何かしなければならないかなと思っている」
![]() 「具体的にはどんなのことだい?」
「具体的にはどんなのことだい?」
![]() 「ざっぱくに言えば、本社はこれから工場の問い合わせとか相談に対応しないのかという意味合いだ。元々磯原さんが本社に来る前は、本社が工場の手助けなどしてなかったから、またそういうふうに戻るのかと心配している。良し悪しはともかく、工場の担当者は本社を頼りにしているわけだ」
「ざっぱくに言えば、本社はこれから工場の問い合わせとか相談に対応しないのかという意味合いだ。元々磯原さんが本社に来る前は、本社が工場の手助けなどしてなかったから、またそういうふうに戻るのかと心配している。良し悪しはともかく、工場の担当者は本社を頼りにしているわけだ」
![]() 「山内さんが工場は主体的に自立的にと、だいぶ強調していたからね」
「山内さんが工場は主体的に自立的にと、だいぶ強調していたからね」
![]() 「まあ、相談や支援はともかく、山内さんの語ったことはそういう意味だろうな
「まあ、相談や支援はともかく、山内さんの語ったことはそういう意味だろうな

![]() 「それで工場は主体的に判断し行動すべきであるが、本社が問い合わせや相談に対応するのは当然だと表明しておいたほうが良いんじゃないかな」
「それで工場は主体的に判断し行動すべきであるが、本社が問い合わせや相談に対応するのは当然だと表明しておいたほうが良いんじゃないかな」
![]() 「今日予定しているテーマを話し合ってから、それについて相談しませんか。関連していると思うので」
「今日予定しているテーマを話し合ってから、それについて相談しませんか。関連していると思うので」
![]() 「そう言えば今日は集まれと言われたけど、議題が何かは聞いてないな」
「そう言えば今日は集まれと言われたけど、議題が何かは聞いてないな」
![]() 「だいぶ前から山内さんから指示されている緊急事態の対応だけど、パンデミック発生時の検討報告を求められています。今日はそれについて考えてもらいたいということです」
「だいぶ前から山内さんから指示されている緊急事態の対応だけど、パンデミック発生時の検討報告を求められています。今日はそれについて考えてもらいたいということです」
![]() 「パンデミックって病気が蔓延することだよね。日本語で感染爆発っていうんだっけ?」
「パンデミックって病気が蔓延することだよね。日本語で感染爆発っていうんだっけ?」
![]() 「病気の流行もレベルがあって、特定の施設とか町など限定的なのはアウトブレイクといい、国レベルの流行になるとエピデックとなり、複数の国や大陸レベルまで流行するとパンデミックと呼ぶそうです」
「病気の流行もレベルがあって、特定の施設とか町など限定的なのはアウトブレイクといい、国レベルの流行になるとエピデックとなり、複数の国や大陸レベルまで流行するとパンデミックと呼ぶそうです」
![]() 「パンデミックって今まであったのかい?」
「パンデミックって今まであったのかい?」
![]() 「大昔からパンデミックはたびたび起きています。時代をさかのぼればパンデミックといっても地域的には狭かったですけどね。人の移動が少ないから。ペスト流行なんて中部から南部ヨーロッパだけでしょう」
「大昔からパンデミックはたびたび起きています。時代をさかのぼればパンデミックといっても地域的には狭かったですけどね。人の移動が少ないから。ペスト流行なんて中部から南部ヨーロッパだけでしょう」
![]() 「私も山内さんに言われてから本を読んだ程度ですが、次のようなものが載っていまし
「私も山内さんに言われてから本を読んだ程度ですが、次のようなものが載っていまし
- 1968年 香港カゼ。世界で死者100万人以上
- 1981年 エイズ(後天性免疫不全症候群:HIV)20年間で死者2,500万人
- 1996年 プリオン病 イギリスで流行
- 1997年 高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)、死者249人
- 2002年 SARS(重症急性呼吸器症候群)9ヶ月で死者774人
- 2009年 新型インフルエンザ(A/H1N1)214カ国・地域で死者1万8,449人
インフルエンザは子供の頃からたびたび流行したね。インフルエンザなんて大した病気じゃないと思っていたけど、大人になってから知ったのは第一次世界大戦のときはやったインフルエンザが20世紀では最大の5,000万もの死者を出したそうだ」
注:第一次世界大戦の死者の数字は多々あり、戦死か戦病死か病死かは厳密には不明である。
![]() 「そうそう、私が10歳くらいのとき、当時は香港カゼで大騒ぎだったのを覚えている。あのときの死者が日本で1000人、世界では100万だ。第一次世界大戦のときのスペイン風邪では日本は40万、世界で5000万てのはすごいね。
「そうそう、私が10歳くらいのとき、当時は香港カゼで大騒ぎだったのを覚えている。あのときの死者が日本で1000人、世界では100万だ。第一次世界大戦のときのスペイン風邪では日本は40万、世界で5000万てのはすごいね。
インフルエンザで第一次世界大戦が終わったと学校で習った。敵も味方も病気でどんどん死んでいけば戦争どころじゃない」
![]() 「そう考えると、山内さんがいうパンデミックに備えろというのも分かる気はする」
「そう考えると、山内さんがいうパンデミックに備えろというのも分かる気はする」
![]() 「最近のSARSのときは結構みんな心配したよね。中国帰りなんて肩身が狭かった。みんなが離れていくんだよ、まあ気持ちはわかるけど、本人は辛かっただろう。
「最近のSARSのときは結構みんな心配したよね。中国帰りなんて肩身が狭かった。みんなが離れていくんだよ、まあ気持ちはわかるけど、本人は辛かっただろう。
でも結局流行したのは中国だけだった。世界のどこかで流行しても日本で大騒ぎになるとは思えないな
![]() 「田中さん、15年前とは状況が全然違うんだよ。SARSが流行した2002年に中国からの観光客は20数万人だったけど、今年2019年は740万人、香港を含めると950万だ
「田中さん、15年前とは状況が全然違うんだよ。SARSが流行した2002年に中国からの観光客は20数万人だったけど、今年2019年は740万人、香港を含めると950万だ
![]() 「おお、さすが坂本さんは外国通だね」
「おお、さすが坂本さんは外国通だね」
![]() 「しかし、分からないのだが、なんで環境課がパンデミックっていうか、病気対策を考えなくちゃなんないんだい?」
「しかし、分からないのだが、なんで環境課がパンデミックっていうか、病気対策を考えなくちゃなんないんだい?」
![]() 「あっ、説明不足でしたか。パンデミック対策ではなくて、パンデミックが発生した時に、環境事故とかが起きてもしっかり対応できるようにしろというご指示です」
「あっ、説明不足でしたか。パンデミック対策ではなくて、パンデミックが発生した時に、環境事故とかが起きてもしっかり対応できるようにしろというご指示です」
![]() 「……通常の状況での環境事故対応ではなく、パンデミックが流行しているときの環境事故対応か……なるほど分かった。
「……通常の状況での環境事故対応ではなく、パンデミックが流行しているときの環境事故対応か……なるほど分かった。
でもパンデミックで緊急事態が起きれば大変さは倍になると思うけど、それ以外でも台風が来たときとか近場で火事が発生したときだって緊急事態は起きるかもしれないよね」
![]() 「確かにそうですが、台風ならせいぜい数日です。近隣で火災が起きたとしても数時間です。だから重なって起きる可能性は低いと思います。
「確かにそうですが、台風ならせいぜい数日です。近隣で火災が起きたとしても数時間です。だから重なって起きる可能性は低いと思います。
パンデミックとなると、先ほど話に出たインフルエンザ流行なら数か月、SARSの場合は1年近く流行したと思います。だからそういう周囲環境が平常時と大きく違う場合でも、対応できるようにという意味合いです」
![]() 「台風だって大被害があれば復旧に時間がかかるよね。今年の千葉県に来た台風では停電が半月も続いたし、道路も復旧に時間がかかった」
「台風だって大被害があれば復旧に時間がかかるよね。今年の千葉県に来た台風では停電が半月も続いたし、道路も復旧に時間がかかった」
![]() 「おお!確かにそうです。確かにパンデミックだけではないですね。まあ、そういう場合でも事故とか起きたときどうするかということです。消防も救急車も来れないときはどうするかというのを、我々のような仕事を担当している者としては考えておかないとならないでしょう。
「おお!確かにそうです。確かにパンデミックだけではないですね。まあ、そういう場合でも事故とか起きたときどうするかということです。消防も救急車も来れないときはどうするかというのを、我々のような仕事を担当している者としては考えておかないとならないでしょう。
私の想像ですが、山内さんは環境条件が大きく変わったときには緊急事態対応が定常時と変わるだろうということ、だからその時の対応あるいは姿勢だけでも、しっかり示しておくべきだという思いだと思うのです」
![]() 「なるほどねえ〜、私はISO14001認証するときに講習会に行ったんだ。そこで講師が語ったことを今でも覚えている。
「なるほどねえ〜、私はISO14001認証するときに講習会に行ったんだ。そこで講師が語ったことを今でも覚えている。
ええと、ISO9001は周囲の環境が変わらないときに工程を一定に保つことを決めていて、ISO14001は周囲環境が変わっても工程を一定に保つことを決めていると言った。実際にはISO14001だって周囲環境が変わっても対応しなさいよというだけで、そんなに深い意味を持っているとは思えない。
今の話を聞くと、山内さんの意図は周囲環境が大きく変わったときに緊急事態が起きても対応できるようにしなさいと、一段上の要求のように思えるね」
![]() 「パンデミックといっても、どんな病気が流行するのかによって対応は違うだろう。エイズとインフルエンザでは感染経路は大違いだ。
「パンデミックといっても、どんな病気が流行するのかによって対応は違うだろう。エイズとインフルエンザでは感染経路は大違いだ。
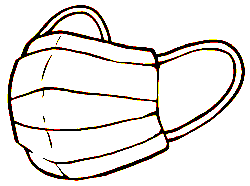 エイズは接触感染だが、キスした程度ではなく血液にウイルスが入らないと感染しないそうだ。カゼも接触感染といわれるけど、飛沫感染もする。だから対応が異なるよ。つまりマスクが必須とか無意味とか違うだろう。
エイズは接触感染だが、キスした程度ではなく血液にウイルスが入らないと感染しないそうだ。カゼも接触感染といわれるけど、飛沫感染もする。だから対応が異なるよ。つまりマスクが必須とか無意味とか違うだろう。
そういう違いでパンデミック発生時の対応も変わるだろうね」
![]() 「なるほど、感染経路の違いによって対応は異なると」
「なるほど、感染経路の違いによって対応は異なると」
![]() 「ええと流行している病気が飛沫感染ならマスクとか保護具とかを専用のものとか、体を近づけないような方法をとるということかい?」
「ええと流行している病気が飛沫感染ならマスクとか保護具とかを専用のものとか、体を近づけないような方法をとるということかい?」
![]() 「そうそう、ちょっとした切り傷などでも感染するようであれば、すべての作業で手袋着用とかになるだろう」
「そうそう、ちょっとした切り傷などでも感染するようであれば、すべての作業で手袋着用とかになるだろう」
![]() 「意味合いは分かった。だけど対策をどうするかとなると雲をつかむようだね
「意味合いは分かった。だけど対策をどうするかとなると雲をつかむようだね
![]() 「そうなんだよ、それでも分かることは取り上げて、分からないことは要検討ということだけでも提案することに意味があるだろう」
「そうなんだよ、それでも分かることは取り上げて、分からないことは要検討ということだけでも提案することに意味があるだろう」
![]() 「スタートはなかなかスピードが上がらなかったですが、一応ここまででお互いに認識は合わせられたということでよろしいでしょうか。
「スタートはなかなかスピードが上がらなかったですが、一応ここまででお互いに認識は合わせられたということでよろしいでしょうか。
私たちは何をしなければならないかというと、感染症の感染ルートごとの検討事項とか対象となる作業と使用する保護具とかの情報提供ですかね?」
![]() 「ちょっと待った、山内さんからのご指示はパンデミック対応なんでしょうか?
「ちょっと待った、山内さんからのご指示はパンデミック対応なんでしょうか?
パンデミックに限定してもよいものなのか?」
![]() 「私と山内さんは長い付き合いなんだ。私が工場の設計で山内さんは研究所の研究員だった。長い付き合いで感じたことだが……彼は幸運に恵まれていたのか予知能力があるのか、失敗したことがない。
「私と山内さんは長い付き合いなんだ。私が工場の設計で山内さんは研究所の研究員だった。長い付き合いで感じたことだが……彼は幸運に恵まれていたのか予知能力があるのか、失敗したことがない。
問題があって解決策と思われる方法がふたつあるとき、彼はパット進むべき道を決めるんだよね。そして間違えた方を選んだということはなかった。
つまり彼がパンデミック対応を考えろと言うからには、パンデミックが起きるんじゃないかって気がするんだ」
![]() 「ほう〜、彼が特許をたくさん取ったのはそういう能力があったからか!」
「ほう〜、彼が特許をたくさん取ったのはそういう能力があったからか!」
![]() 「いやいや、彼は研究員として優秀だよ。だけど実力が成果に結びついたのは、そういう能力があったからじゃないかと思っているんだ」
「いやいや、彼は研究員として優秀だよ。だけど実力が成果に結びついたのは、そういう能力があったからじゃないかと思っているんだ」
![]() 「それならどこでいつ発生するのか、どんな対策をすればよいのかも教えてほしいなあ〜」
「それならどこでいつ発生するのか、どんな対策をすればよいのかも教えてほしいなあ〜」
![]() 「山内さんを社長にすれば当社は超優良企業になれる」
「山内さんを社長にすれば当社は超優良企業になれる」
![]() 「そこまでは無理みたいだ。それに山内さんは営業とか財務なんて担当外だしね」
「そこまでは無理みたいだ。それに山内さんは営業とか財務なんて担当外だしね」
・
・
・
・
![]() 「すこし頭が疲れてきました。議題を変えましょう。今日初めに田中さんから提起されたのは、本社が工場対応を変えないと声明を出すかどうかでしたね。
「すこし頭が疲れてきました。議題を変えましょう。今日初めに田中さんから提起されたのは、本社が工場対応を変えないと声明を出すかどうかでしたね。
まずそうする必要性があるのでしょうか?」
![]() 「公式なことは、まずは会社規則があり、そこでは本社の役割が決めてあり、工場の業務の支援がある。またそもそも相談窓口があり質問の事例もアップされていて、質問するなとか対応しないというのはあり得ないね」
「公式なことは、まずは会社規則があり、そこでは本社の役割が決めてあり、工場の業務の支援がある。またそもそも相談窓口があり質問の事例もアップされていて、質問するなとか対応しないというのはあり得ないね」
![]() 「そもそも論では本社が工場を支援しなければ、本社費をもらえるはずがない」
「そもそも論では本社が工場を支援しなければ、本社費をもらえるはずがない」
![]() 「まあ一般論としては田中さんと坂本さんがおっしゃる通りですが、役割分担はあると思いますよ。例えば欧州の化学物質規制の調査とか対応策の検討といったことは、それぞれの工場が行うのではできることは少ないし、重複すれば効率が悪い。だから工場がお金と人を出し合って共同して検討するというのがそもそもの発祥ですからね。
「まあ一般論としては田中さんと坂本さんがおっしゃる通りですが、役割分担はあると思いますよ。例えば欧州の化学物質規制の調査とか対応策の検討といったことは、それぞれの工場が行うのではできることは少ないし、重複すれば効率が悪い。だから工場がお金と人を出し合って共同して検討するというのがそもそもの発祥ですからね。
でも廃棄物の処理をどうすれば安くなるとかリサイクル推進するなんてことは、地域の特性もあるし、個々の工場が検討しても大してお金も手間もかからない。
つまり本社は手間暇のかかることを支援すると決めてもおかしくないです。
お断りしておきますが、私は工場の問い合わせに対応する必要はないと言っているわけではないですよ。実際に前任者が無視していた工場からの問い合わせを、片っ端から片付けて本社の信頼回復してきたわけですからね」
![]() 「分かった、分かった。磯原さんとしては、工場が本社に疑念を持っていることについてどう考えているんだ?」
「分かった、分かった。磯原さんとしては、工場が本社に疑念を持っていることについてどう考えているんだ?」
![]() 「私のときは工場から問い合わせ受けたものは、すべて馬鹿正直に回答していました。田中さんもそうしているかと思います。
「私のときは工場から問い合わせ受けたものは、すべて馬鹿正直に回答していました。田中さんもそうしているかと思います。
でも運用してもう3年経ったのですから、過去のQ&Aをまとめてアップして、まずそれを見て考えろということでも良いのではないでしょうか。過去にあった質問であれば、そのQ&AのURLを教えるだけで済むでしょう。
もちろん過去に事例のないことについては、個々に回答というか対応を説明するとかすれば十分でしょう」
![]() 「なるほど、確かに問い合わせのパターンは大きく何種類かになる。それをイントラにアップしておけば質問が半減し、私の手間は半減するね。そういうことを説明すれば工場の不満というか不安は解消できるだろう」
「なるほど、確かに問い合わせのパターンは大きく何種類かになる。それをイントラにアップしておけば質問が半減し、私の手間は半減するね。そういうことを説明すれば工場の不満というか不安は解消できるだろう」
![]() 「役員交代による手続きなどはどうなるんだい?」
「役員交代による手続きなどはどうなるんだい?」
![]() 「それは問合せじゃなくてルーチンの業務です。ですから会社規則に定める様式、今はワークフローですが、それで所定の書類をいついつまでにそろえてほしいと申請すれば自動的に進みます」
「それは問合せじゃなくてルーチンの業務です。ですから会社規則に定める様式、今はワークフローですが、それで所定の書類をいついつまでにそろえてほしいと申請すれば自動的に進みます」
![]() 「なんだ余計な心配をすることはなかったようだ」
「なんだ余計な心配をすることはなかったようだ」
![]() 「じゃあ、そういうことを公文で出すかい?」
「じゃあ、そういうことを公文で出すかい?」
![]() 「公文で出すってほどのものじゃないでしょう。ルールを変えるわけでなく、運用を少し変えるだけのことです。環境管理課のウェブサイトにお知らせを載せる程度でよいのではないですか」
「公文で出すってほどのものじゃないでしょう。ルールを変えるわけでなく、運用を少し変えるだけのことです。環境管理課のウェブサイトにお知らせを載せる程度でよいのではないですか」
![]() 「うーん、やはり相手を納得させるために磯原さんの名前で、工場の課長宛てに簡単な公文を出したほうが良いよ」
「うーん、やはり相手を納得させるために磯原さんの名前で、工場の課長宛てに簡単な公文を出したほうが良いよ」
![]() 「じゃあ、そうしましょう。田中さんドラフト作って送ってください。
「じゃあ、そうしましょう。田中さんドラフト作って送ってください。
じゃあ、これで一件落着と……
次は、パンデミック時における緊急事態発生時の対応に戻りましょう。ええとアウトプットは何になりますか?

山内さんの言葉のままですと、条件はパンデミックに限定すれば良いかどうかがあります。坂本さんの言われたように台風で被害が出た場合なども該当しそうです。
田中さんがおっしゃるように山内さんの第六感によればパンデミックに限定して良いようですが。
アウトプットとしてはパンデミック発生時の条件を定めて、緊急事態が発生したときに通常時に追加される制約に対応する方法でもまとめますかね」
![]() 「追加される条件って何ですかね?」
「追加される条件って何ですかね?」
![]() 「先ほども出ましたが感染予防のために、マスク着用とか他人との接触禁止とかでしょうか?
「先ほども出ましたが感染予防のために、マスク着用とか他人との接触禁止とかでしょうか?
台風でしたら交通途絶や通信途絶、それに伴う救急車や消防車の活動停止とか」
![]() 「事業活動の規制はないのかい?」
「事業活動の規制はないのかい?」
![]() 「事業活動の規制とは?」
「事業活動の規制とは?」
![]() 「想像だが、例えば電気や水道などのインフラが使えないとか、警察や消防などの社会サービス以外は活動してはいけないとか。具体的には許可された車以外の走行禁止とか営業禁止とか」
「想像だが、例えば電気や水道などのインフラが使えないとか、警察や消防などの社会サービス以外は活動してはいけないとか。具体的には許可された車以外の走行禁止とか営業禁止とか」
![]() 「そうなったら本当の国家的非常事態ですね。確かに重大な感染症の流行になれば、社会サービスと食料品以外、我が社のような製造業は営業停止命令とか出るんじゃないかな?」
「そうなったら本当の国家的非常事態ですね。確かに重大な感染症の流行になれば、社会サービスと食料品以外、我が社のような製造業は営業停止命令とか出るんじゃないかな?」
![]() 「とはいえ会社の設備には常時稼働していないとならないものもあるでしょう。廃棄物などは事業が止まれば仕事がありませんが、排水処理の生物処理とかは停止してきれいにしちゃうんですかね? 再稼働は大変ですが。もっとも出るものが出ないと反応もしないか。
「とはいえ会社の設備には常時稼働していないとならないものもあるでしょう。廃棄物などは事業が止まれば仕事がありませんが、排水処理の生物処理とかは停止してきれいにしちゃうんですかね? 再稼働は大変ですが。もっとも出るものが出ないと反応もしないか。
薬品とかは冷凍保存とかしているものもあるでしょうし。温度が上がると変質とか危険になるものもある。
ああ、言いたいことは、企業の設備を維持するとか異常発生の恐れがあるなら、環境部門は出社しなければならないでしょうね。当然電気や水が止まった時の作業手順は整備しなければならない」
![]() 「電気関係は通電前には大点検しなければならないですね。ネズミが絶縁をかじるとか、フンとかゴミが溜まるとか、風とかで電線が切れたり垂れたりするだろうなあ〜
「電気関係は通電前には大点検しなければならないですね。ネズミが絶縁をかじるとか、フンとかゴミが溜まるとか、風とかで電線が切れたり垂れたりするだろうなあ〜
普段は毎日点検しているから大問題になる前に気づくけど」
![]() 「そうそう、現業系以外はリモートワークにしろと行政が言い出すかもしれないぞ」
「そうそう、現業系以外はリモートワークにしろと行政が言い出すかもしれないぞ」
![]() 「リモートワークですか、まだ会社の状況がそこまでの段階には至ってないでしょう。例えばこの本社の環境管理課がリモートワークで仕事ができますかね?」
「リモートワークですか、まだ会社の状況がそこまでの段階には至ってないでしょう。例えばこの本社の環境管理課がリモートワークで仕事ができますかね?」
![]() 「セキュリティが確実なら、事務作業はインターネットを経由して自宅でできるんじゃないかな」
「セキュリティが確実なら、事務作業はインターネットを経由して自宅でできるんじゃないかな」
![]() 「事務といっても紙の書類を見たり工場とやりとりしたりですから、どうですかねえ〜」
「事務といっても紙の書類を見たり工場とやりとりしたりですから、どうですかねえ〜」
![]() 「確かに……坂本さんの言うように条件整備が必要だね。資料類を電子化し、コミュニケーションには電話を止めてメールとか社内SNSのようなものでしなくちゃいけないね」
「確かに……坂本さんの言うように条件整備が必要だね。資料類を電子化し、コミュニケーションには電話を止めてメールとか社内SNSのようなものでしなくちゃいけないね」
![]() 「年配者にはハードルが高いねえ〜」
「年配者にはハードルが高いねえ〜」
![]() 「おいおい、坂本さんより私が年上だよ」
「おいおい、坂本さんより私が年上だよ」
翌日、山内と磯原が話している。
![]() 「先だって頼んだ、パンデミック発生時における緊急事態についての指針なり教範なりどうなっている?」
「先だって頼んだ、パンデミック発生時における緊急事態についての指針なり教範なりどうなっている?」
![]() 「はい、内部で打ち合わせて進めております。
「はい、内部で打ち合わせて進めております。
正直言って私達もそいうことに経験がなく、また設定条件が明確でありませんので、手順を具体的に決められません。ことにおいて検討すべき事項の羅列程度しかできないでしょう。
最初はその程度のものを提供して、工場はそれを参考にパンデミック発生時に緊急事態が起きた時の注意事項を作っておいてもらうつもりです」
![]() 「漠然としたものか?」
「漠然としたものか?」
![]() 「そうですね、パンデミックと限定しても、流行するものが何かで対応が全く変わるでしょう。
「そうですね、パンデミックと限定しても、流行するものが何かで対応が全く変わるでしょう。
例えば感染予防にするマスクとか手袋とか感染経路によって必要な保護具が違うでしょうし、行政が定める対策も異なると思います。あるいは最近はやっているジエットタオル
マスクにしてもどのような種類があるとか消毒方法などを列記しておいて、発生したものに応じてその選択肢や対応の概要を示すことだけでも役に立つかなと考えました。
ええと、話は変わりますが、工場では本社が工場へのサービスレベルを下げるのではないかと疑心暗鬼となっています。工場は自立して主体的に行動すべきとは思いますが、本社の工場へのサービスレベルは下げないと明言すべきと考えます」
![]() 「そのパンデミック発生時の指針なるものはいつまでに仕上がる?」
「そのパンデミック発生時の指針なるものはいつまでに仕上がる?」
![]() 「まずは出来上がったドラフトを見ていただき、山内さんのご意見を頂かないと見当がつきません」
「まずは出来上がったドラフトを見ていただき、山内さんのご意見を頂かないと見当がつきません」
![]() 「今、11月下旬になったところか……今月末までに仕上げよう。わしもできたところを見せてもらい、コメントするよ。お互いフィードバックを短くして早急に仕上げよう。
「今、11月下旬になったところか……今月末までに仕上げよう。わしもできたところを見せてもらい、コメントするよ。お互いフィードバックを短くして早急に仕上げよう。
そしてそれを工場に発信するときの発信文に、磯原君の言ったことを盛り込もう。あまり五月雨に文書を出すのはまずいからまとめたい」
![]() 「はい」
「はい」
![]() 「お前にひとつ聞きたいことがあった。ISO規格に事業継続マネジメントというのがあるそうだ。そいつはこういう目的に役に立つのか?」
「お前にひとつ聞きたいことがあった。ISO規格に事業継続マネジメントというのがあるそうだ。そいつはこういう目的に役に立つのか?」
![]() 「それは『ISO22301事業継続マネジメントシステム』ですね、略してBCMSと呼んでます。
「それは『ISO22301事業継続マネジメントシステム』ですね、略してBCMSと呼んでます。
役に立つのか否かとなると、立たないでしょう」
![]() 「ほう、磯原にしては珍しく否定的だな」
「ほう、磯原にしては珍しく否定的だな」
![]() 「ISO9001が品質を良くするに役に立つとか、ISO14001が環境を良くするに役に立つと思いますか?」
「ISO9001が品質を良くするに役に立つとか、ISO14001が環境を良くするに役に立つと思いますか?」
![]() 「まあ〜、直接的には関係ないな。いずれも手段を示すものではなく、システムが持つべきことを要求しているだけだ」
「まあ〜、直接的には関係ないな。いずれも手段を示すものではなく、システムが持つべきことを要求しているだけだ」
![]() 「そもそも規格のタイトルが『要求事項』ですからね。審査員も含めて多くの人が勘違いしてますが、ISOMS規格とはマネジメントシステムが備えなければならない条件を羅列しているだけです。どうすればその要求事項を満たすかは書いてありません。
「そもそも規格のタイトルが『要求事項』ですからね。審査員も含めて多くの人が勘違いしてますが、ISOMS規格とはマネジメントシステムが備えなければならない条件を羅列しているだけです。どうすればその要求事項を満たすかは書いてありません。
事業継続も同じですよ。課題を決定しろ、組織を作れ、必要な力量を決定しろだけです。それは審査員が審査するときのチェックリストにはなりますが、それを満たす仕組みを作る人の参考にはなりません」
![]() 「まあ、何を満たさなくちゃならないかの見出しは分かるわけだ」
「まあ、何を満たさなくちゃならないかの見出しは分かるわけだ」
![]() 「いやいや、もっと大事なことがあります。そしてそれについても多くの人が勘違いしています。ISO規格を作る人さえ間違っているように思います。
「いやいや、もっと大事なことがあります。そしてそれについても多くの人が勘違いしています。ISO規格を作る人さえ間違っているように思います。
それは、要求事項を満たせば大丈夫という保証がないことです。規格にある要求事項が十分条件かどうか、そして必要条件であるかも分からないのです」
![]() 「ああ〜なるほど、ISO14001のいずれの版だったかな、マネジメントシステムにはいろいろあると書いてあったな。ISO規格はそのひとつにすぎないって。
「ああ〜なるほど、ISO14001のいずれの版だったかな、マネジメントシステムにはいろいろあると書いてあったな。ISO規格はそのひとつにすぎないって。
そしてまたお前が言うように必要十分ではなく、当然ISO規格が完璧であるわけでもない。完璧なら規格改定はない。機械要素のISO規格は何十年も改定されてない。規格も物も枯れてスタンダードが確立しているからな。
どう考えてもISO規格は無力としか思えんな。さらに言えばその規格による認証もしかりと」
![]() 本日の愚考
本日の愚考
2024年元日に能登半島を中心に大地震が襲った。
私は思うのだが事業継続マネジメントシステムを認証している企業はこの地震のとき、認証していない企業といかなる差があったのだろうか?
現時点、日本でBCMSを認証している組織は86件だが
BCMSのISO規格は2012年制定されたが、その前身であるBS25999の認証は国内では2008年から始まっていた。認証した企業のいくつかは東日本大震災の洗礼を受けているわけだが、対応にいかほど効果があったのかという報告は見たことがない。
建屋の強度までは規格要求にないから、建屋が崩壊する確率は認証しても変わらない。道路の損壊や電気・水道などの社会インフラは認証企業と関係ない。組織の存在する地域が地震や台風によりダメージを受けたとき、認証企業は認証していない企業よりも事業継続できる確率が高まるだろうか(反語である)
品質向上ならISO9001でなく、ひたすら品質管理に努めたほうが効果はありそうだ。事業継続ならISO22301より、過去の事例を反映して対策を積み重ねていくのが正攻法に思える。
IBMが環境先進企業と呼ばれるようになったのは、地下水汚染や環境事故を起こしたら、愚直に是正処置をしてきたからだと本で読んだ
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 | ||
注2 | ||
注3 |
手を洗った後に、送風機で手の水を飛ばす装置の一般名はハンドドライヤーというそうだ。 ジェットタオル、エアータオルなどは商品名らしい。 | |
注4 | ||
注5 |
・「IBMの環境経営」山本和夫・国部克彦、東洋経済新報社、2001 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |