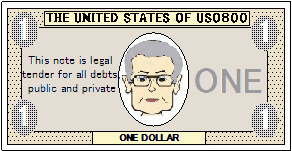*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
2020年10月
今日は環境管理課の定例ミーティングである。
課員が順次、過去1週間の業務報告をしているが、既に週報で知っていることなので頭に浮かぶ妄想を追っていた。
思い返すと自分がここに来てから4年半、上西前課長が辞めてからでも2年が経つ。あれ以来、磯原は課長代行をしているが、肩書から「代行」もとれず、後任課長も来ない。
本社勤務は一時的なものだ。いくらなんでも10年はいない。せいぜいあと2・3年だろう。磯原の心中はそろそろ元の工場に戻りたい。とはいえ娘のちなみも13歳になり、2年後は高校入試だ。娘も妻も千葉県で進学すると語っている。
やはり福島は田舎、千葉は都会である。よく千葉県は田舎と揶揄されるが、千葉市より西なら東京まで余裕の通勤・通学圏であり、また客観的に見て十分に都会である。ここに住んで本当の田舎に戻りたいという人はあまりいないだろう。
 午後からどころか夕方からディズニーランドに行ける場所は、娘にとっては十分に価値がある。
午後からどころか夕方からディズニーランドに行ける場所は、娘にとっては十分に価値がある。
現実に磯原は稲毛に住んでから、甥や姪が……本当は引率する磯原や妻の兄弟・姉妹が楽しみなのだろうが……ほとんど毎年ホテル代わりにされている。福島では友達と連れ添って行こうとしても簡単ではない。
娘と妻が本社勤務を望んでも、今後もいられるとは限らない。はてさてどうしたものか、いやどうなるものか……
そんなことを考えていると、誰かに呼ばれたような感じがして磯原はハッとした。
![]() 「磯原さん、ISO認証について、この場で課内に説明して了解を得ておきたいですが、よろしいですか?」
「磯原さん、ISO認証について、この場で課内に説明して了解を得ておきたいですが、よろしいですか?」
![]() 「私もそう思います。岡山さん、概要を説明して皆の意見を聞いてください」
「私もそう思います。岡山さん、概要を説明して皆の意見を聞いてください」
![]() 「ええと、みなさんご存じのように本社と支社はISO14001認証を受けております。一昨年は審査中にトラブルが起きて半年ほど認証が切れましたが、昨年に認証機関を替えて再度認証しました。
「ええと、みなさんご存じのように本社と支社はISO14001認証を受けております。一昨年は審査中にトラブルが起きて半年ほど認証が切れましたが、昨年に認証機関を替えて再度認証しました。
 |
||
 |
まだ日程は決まっていないのですが、来年の
それとは別に、社内でいろいろトラブルがありましてその原因を調査をするにつれ、ISO認証の有効性が疑問に思えてきました。そういった事情で今回の認証の有効期限をもって認証をやめようかと考えています」
![]() 「私はいつも話を聞いているから経緯はもちろん知っている。認証を止めることは賛成だ。
「私はいつも話を聞いているから経緯はもちろん知っている。認証を止めることは賛成だ。
しかし周りと良く調整して、問題ないようにしてほしいな」
![]() 「田中さんと同意見だ。工場や関連会社には、20世紀というと大昔と思うかもしれないが、本社は工場や関連会社に、ものすごく圧力をかけて認証させてきたという歴史がある。そういった経緯から、説明もなしに認証が不要だから本社は止めますとは言えない。
「田中さんと同意見だ。工場や関連会社には、20世紀というと大昔と思うかもしれないが、本社は工場や関連会社に、ものすごく圧力をかけて認証させてきたという歴史がある。そういった経緯から、説明もなしに認証が不要だから本社は止めますとは言えない。
工場や関連会社に理由をしっかり説明して、納得してもらわないとだめだ」
![]() 「社内的にはそうでしょうけど、社外的なことも考えてくださいよ。日■の環境経営度調査もあるし、工場は買い手からのグリーン調達もあるから、独断で止めるわけにはいかないでしょう。
「社内的にはそうでしょうけど、社外的なことも考えてくださいよ。日■の環境経営度調査もあるし、工場は買い手からのグリーン調達もあるから、独断で止めるわけにはいかないでしょう。
その辺をどう説明するのか、もちろんそういうことは検討済だと思うけど、相手が納得するのかどうか?」
![]() 「工場はそれぞれが要不要を考えて決めろとなると予想します。でも工場は勝手にしろとは言えないでしょう。当社としての考えを示してほしいですね。その理屈を皆が納得することが必要です。
「工場はそれぞれが要不要を考えて決めろとなると予想します。でも工場は勝手にしろとは言えないでしょう。当社としての考えを示してほしいですね。その理屈を皆が納得することが必要です。
例えばの話、本社が工場の認証も止めさせる、そしてその理由を本社が対外的に説明して、顧客の納得を得るとかしないとまずいでしょう」
![]() 「説明も内部だけで納めるのもあるし、外部の利害関係者を納得させるのもありそうですね。どこまでするのか」
「説明も内部だけで納めるのもあるし、外部の利害関係者を納得させるのもありそうですね。どこまでするのか」
![]() 「確かに止めるとなるとハードルが高いというのを実感しますね。だから認証を止められずズルズルと続けていく会社が多いのだろうと思う。
「確かに止めるとなるとハードルが高いというのを実感しますね。だから認証を止められずズルズルと続けていく会社が多いのだろうと思う。
| |||||
| |||||
私としては世の中の人を説得する必要はないと思う。認証辞退を納得させるというと、ISO認証制度に対する批判に思われそうだ。無駄な喧嘩しても一文にもならない。だから内部的に収めたほうが良いと思う。
環境経営度でISO認証を返上して採点が下がっても特に困ることもない。そもそも経営度の順位は、環境に対する施策よりも企業の業績反映のように思える。大体ランキング上位は有名企業ばかりで、環境経営がすばらしいというよりも、その逆に環境経営度の権威を受賞企業に裏書きしてもらおうってのが見え見えだ」
増子と坂本がぷっと吹き出す。🗣
![]() 「いや失礼。確かに過去より何かの賞を作ると、第1回の受賞者はトヨタ自動車に決まっている。優良企業を表彰するのではなく、優良企業に賞をもらってもらい、賞に箔をつけるとはハチャメチャだね。
「いや失礼。確かに過去より何かの賞を作ると、第1回の受賞者はトヨタ自動車に決まっている。優良企業を表彰するのではなく、優良企業に賞をもらってもらい、賞に箔をつけるとはハチャメチャだね。
日■の環境経営度も箔をつけるために、有名企業のそろい踏みか、アハハハ」
![]() 「そもそもランキングにどういう意味があるかと考えれば、経営者が気分を良くすることくらいしか意味がない。一般消費者がランキングを見て商品を選ぶとは思えないし、ランキングが上位でも環境事故を起こせば意味がない」
「そもそもランキングにどういう意味があるかと考えれば、経営者が気分を良くすることくらいしか意味がない。一般消費者がランキングを見て商品を選ぶとは思えないし、ランキングが上位でも環境事故を起こせば意味がない」
![]() 「それはISO認証も同じで、認証していても事故を起こせば意味がないですね。むしろマスコミいや消費者団体からは認証していないより叩かれたり、認証機関には裏切られたと砂をかけられたり」
「それはISO認証も同じで、認証していても事故を起こせば意味がないですね。むしろマスコミいや消費者団体からは認証していないより叩かれたり、認証機関には裏切られたと砂をかけられたり」
![]() 「見掛けだけで意味がないと……」
「見掛けだけで意味がないと……」
![]()
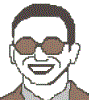 |
![]() 「本社・支社の認証返上だけなら、世の中は注目しないということですか?」
「本社・支社の認証返上だけなら、世の中は注目しないということですか?」
![]() 「そう思います。騒がれることはないでしょう」
「そう思います。騒がれることはないでしょう」
![]() 「磯原さん、意外ですね。正論をはいて天下を敵に回すのかと思っていましたよ」
「磯原さん、意外ですね。正論をはいて天下を敵に回すのかと思っていましたよ」
![]() 「うーん、私たちがISO認証制度に関わっているとか、認証制度の反対勢力ならそういうのもあるかもしれないけど、単に認証しているだけの立場ですから、もめることはないでしょう。静かに去るだけです」
「うーん、私たちがISO認証制度に関わっているとか、認証制度の反対勢力ならそういうのもあるかもしれないけど、単に認証しているだけの立場ですから、もめることはないでしょう。静かに去るだけです」
![]() 「分かりました。社内にいかに説明するかのストーリーをきれいに作ればよいと理解します。
「分かりました。社内にいかに説明するかのストーリーをきれいに作ればよいと理解します。
ええと決裁は役員会に上げるようなことじゃないですから、常務の了解を取ればよろしいですね」
![]() 「理由、経緯、メリット・デメリット、費用計算、内部の調整などを、A3で概要を一瞥できるようにしてほしい。完璧に仕上げないで骨組みができたら山内さんに今週くらいに話をしよう。
「理由、経緯、メリット・デメリット、費用計算、内部の調整などを、A3で概要を一瞥できるようにしてほしい。完璧に仕上げないで骨組みができたら山内さんに今週くらいに話をしよう。
山内さんからいろいろ指示あるだろうから、それを加筆修正して来週末に完成させて山内さんと常務に説明というところでお願いします」
![]() 「了解しました」
「了解しました」
・
・
・
・
![]() 「ええと、皆さんからの報告とか提案とかありますか?
「ええと、皆さんからの報告とか提案とかありますか?
ないようであれば私からお願いしたいことがあります。
ええと昨年から山内さんからの指示をみていてお気づきと思いますが、我々の部門である環境管理課の役割が減少しつつあることはご承知と思います」
![]() 「えっ、環境管理課の仕事は縮小しているのですか?」
「えっ、環境管理課の仕事は縮小しているのですか?」
![]() 「おいおい、気づかなかったのか? 『大きな本社・小さな工場』から、『小さな本社・大きな工場』という方向に動いているだろう。
「おいおい、気づかなかったのか? 『大きな本社・小さな工場』から、『小さな本社・大きな工場』という方向に動いているだろう。
昨年末に作った『非常事態下における緊急事態対応』というのは、工場が独立して動きなさいという意味だよ」
![]() 「ええっ!あれにはそういう意図があるのですか。どう読めばそうなるのですか?」
「ええっ!あれにはそういう意図があるのですか。どう読めばそうなるのですか?」
![]() 「もう5年くらい前になるかな、私が来る前のこと。本社に環境部というのがあった。部というくらいだから30人くらいいた。当然そこには環境にまつわる様々な機能があった。それを解体して、本来あるべき部署に分散したんです」
「もう5年くらい前になるかな、私が来る前のこと。本社に環境部というのがあった。部というくらいだから30人くらいいた。当然そこには環境にまつわる様々な機能があった。それを解体して、本来あるべき部署に分散したんです」
![]() 「あるべきとおっしゃると、それは間違っていたのですか?」
「あるべきとおっしゃると、それは間違っていたのですか?」
![]() 「間違っていたのではないと思います。環境部が設立されたのは、1997年経団連が環境自主行動計画というのを策定し公表した直後だったと聞く。なにしろ23年も前、私が高校生の頃だ。実際のところは分かりません。
「間違っていたのではないと思います。環境部が設立されたのは、1997年経団連が環境自主行動計画というのを策定し公表した直後だったと聞く。なにしろ23年も前、私が高校生の頃だ。実際のところは分かりません。
当時は会社の中で環境に関して、どんなことをしているか把握している人はいなかったんじゃないかな」
![]() 「いなかった、いなかった。私の覚えているのは、工場では公害防止は施設課、電気設備も施設課、植栽は総務部、廃棄物処理の半分は施設課で半分は総務部で、みんな別部署だった。土壌汚染とか地下水汚染の浄化作業なんて思いもしない時代だ。
「いなかった、いなかった。私の覚えているのは、工場では公害防止は施設課、電気設備も施設課、植栽は総務部、廃棄物処理の半分は施設課で半分は総務部で、みんな別部署だった。土壌汚染とか地下水汚染の浄化作業なんて思いもしない時代だ。
環境報告書もグリーン調達も環境配慮設計も存在せず、製品が廃棄物になったら市町村がしっかり処理しろと考えていた時代だ。製品が廃棄物になったのを作ったメーカーが責任を負うなんて逆立ちしても思わなかったね。
大きな声では言えないが、市だって廃棄物を野焼きしていた時代もあったんだよ。
だから経団連から環境活動をしっかりやろうといわれて、とにかく社内で環境に関係するものを集めて管理レベルを上げようという発想になったんだろうなあ〜」
![]() 「はぁ〜、そういう時代があったのですか」
「はぁ〜、そういう時代があったのですか」
![]() 「そんな昔じゃないのよ。マニフェスト票が産業廃棄物全体に義務化されたのは1998年からよ。廃棄物とお金を渡せば、後は知らないというのが普通だったの」
「そんな昔じゃないのよ。マニフェスト票が産業廃棄物全体に義務化されたのは1998年からよ。廃棄物とお金を渡せば、後は知らないというのが普通だったの」
![]() 「石川君はそんな時代があったと信じられないだろうが、私もこんな時代になるとは信じられなかったよ、アハハハ」
「石川君はそんな時代があったと信じられないだろうが、私もこんな時代になるとは信じられなかったよ、アハハハ」
![]() 「要するに環境のお仕事そのものを理解しておらず、とりあえず環境に関わるだろうというお仕事を集めたわけだ。そしてそれぞれについて世の中の動きを調べて、規制や社会に要求に応じた手順や基準を作り社内に展開したという流れでしょうか」
「要するに環境のお仕事そのものを理解しておらず、とりあえず環境に関わるだろうというお仕事を集めたわけだ。そしてそれぞれについて世の中の動きを調べて、規制や社会に要求に応じた手順や基準を作り社内に展開したという流れでしょうか」
![]() 「その理解で間違いない。私が40くらいのときだ。本社もそう動いたし、工場でも似たような仕事を集めて環境課というような名前の看板を挙げた」
「その理解で間違いない。私が40くらいのときだ。本社もそう動いたし、工場でも似たような仕事を集めて環境課というような名前の看板を挙げた」
![]() 「しかしそれから15年経った2010年頃、そういう仕組みはどうも違うんじゃないかと考えられたのですね」
「しかしそれから15年経った2010年頃、そういう仕組みはどうも違うんじゃないかと考えられたのですね」
![]() 「と言うと?」
「と言うと?」
![]() 「環境に関わるものを集めたものの、それらは無関係ってものが多かったのです。例えば省エネと廃棄物削減は関係ない。廃棄物を減らそうとすると電気を使うとか、廃棄物を減らすと電気も減るなんてことはない。環境配慮設計で廃棄物削減とリサイクル向上を目指すのと、工場の廃棄物処理は無関係です」
「環境に関わるものを集めたものの、それらは無関係ってものが多かったのです。例えば省エネと廃棄物削減は関係ない。廃棄物を減らそうとすると電気を使うとか、廃棄物を減らすと電気も減るなんてことはない。環境配慮設計で廃棄物削減とリサイクル向上を目指すのと、工場の廃棄物処理は無関係です」
![]() 「ちょっと待ってくださいよ、そうなりますか?
「ちょっと待ってくださいよ、そうなりますか?
例えば工場の廃棄物処理は製品リサイクルの参考になるでしょう」
![]() 「一般的な廃棄物処理としての知識にはなるでしょうけど、まあカテゴリーというか分野が全然違うわよね。
「一般的な廃棄物処理としての知識にはなるでしょうけど、まあカテゴリーというか分野が全然違うわよね。
 家電リサイクルなどは材質ごとに分けて小さく破砕してリサイクルルートに乗せるというシステムを作ることだから。
家電リサイクルなどは材質ごとに分けて小さく破砕してリサイクルルートに乗せるというシステムを作ることだから。
通常の廃棄物処理とは無害とか安定化させることじゃないのかな。もちろんリサイクルできればそれにこしたことはないけど、コストが合わなくちゃ永続できない」
![]() 「まあ、そういうことで無関係な機能を集めても、効果的な管理も運用もできないということが分かってきたということでしょう」
「まあ、そういうことで無関係な機能を集めても、効果的な管理も運用もできないということが分かってきたということでしょう」
![]() 「もちろん当初の狙いだった、環境に関わるさまざまな仕事の手順や基準を作ることは叶ったし、環境に関する処理技術などの知識が得られたというわけです。
「もちろん当初の狙いだった、環境に関わるさまざまな仕事の手順や基準を作ることは叶ったし、環境に関する処理技術などの知識が得られたというわけです。
そして大事なことですが、よく考えてみるとそれぞれの機能は本来属する部門があると気づいた。それで環境報告書担当は、新たにできたCSR部に移りCSR報告書に含まれた。省エネは生産術研究所に移って工場省エネとオフィス省エネの研究とコンサル事業をするようになった。
製品の環境設計や廃製品のリサイクルは、各製品の事業本部に移り研究することから、実際の製品に応用する実践部隊に変質した」
・
・
・
![]() 「あのう〜、非常に初歩的なことですが発言してよいですか?」
「あのう〜、非常に初歩的なことですが発言してよいですか?」
![]() 「課内ミーティングなんだから自由に発言してよ」
「課内ミーティングなんだから自由に発言してよ」
![]() 「よく環境マネジメントシステムって言いますよね。今のお話を聞くと、環境マネジメントシステムというのは、存在しないように思います。だって廃棄物と環境設計とグリーン調達はカテゴリーが違うだけでなく、それは過去からの企業の主要な要素である設備管理とか設計とか調達という機能に含まれます。
「よく環境マネジメントシステムって言いますよね。今のお話を聞くと、環境マネジメントシステムというのは、存在しないように思います。だって廃棄物と環境設計とグリーン調達はカテゴリーが違うだけでなく、それは過去からの企業の主要な要素である設備管理とか設計とか調達という機能に含まれます。
ということは、それぞれを集めてもシステムではない。単に環境に関係するというだけが共通した性質です。 じゃあ環境マネジメントシステムってなんですか?」
![]() 「超根源的な疑問を呈されちゃったよ、ハハハ」
「超根源的な疑問を呈されちゃったよ、ハハハ」
![]() 「岡山さんが茶化すってことは正解をご存じなんでしょう。教えてください」
「岡山さんが茶化すってことは正解をご存じなんでしょう。教えてください」
![]() 「正解かどうか、私の解釈です。
「正解かどうか、私の解釈です。
学問なんていうとおこがましいですが、議論をするときはまずは使う言葉を定義しなければなりません。曖昧を敵にしては神々の戦いもむなしいってのはアイザック・アシモフの小説ですが、議論する双方が議論で使う名詞も動詞も、同じ意味で使わなければ無意味です。
ということで私がISO審査対応をするようにと言われたとき、まずは規格を読みました。規格の頭に定義があり、そこで定義されていない言葉は通常の辞書の語義で使うとあります。
ここまで理解していただいたら、次に進みます。
環境マネジメントシステムの定義は『マネジメントシステムの一部で、環境側面をマネジメントし、順守義務を満たし、リスクおよび機会に取り組むために用いられるもの』です。
では『マネジメントシステム』はとなりますが『方針、目的及びその目的を達成するためのプロセスを確立するための、相互に関連する又は相互に作用する、組織の一連の要素』です。
これから環境マネジメントシステムが、いかなるものかお分かりになりますよね」
![]() 「えっ?」
「えっ?」
![]() 「石川さん、難しく考えることないのよ。マネジメントシステムというのは会社を動かす仕組みであり、相互に関連する渾然一体のものであるということがひとつ。環境マネジメントシステムとはその一部であり、環境に関わるものということです。
「石川さん、難しく考えることないのよ。マネジメントシステムというのは会社を動かす仕組みであり、相互に関連する渾然一体のものであるということがひとつ。環境マネジメントシステムとはその一部であり、環境に関わるものということです。
演繹されることとして、環境マネジメントシステムはシステムではない。環境マネジメントシステムに入ると取り上げられたもの同士が、相互に関連したり作用することがないものもあるということよ」
![]() 「ユミちゃんはすごい理解力ですね。脅威的なのは身長だけではなかったのですね」
「ユミちゃんはすごい理解力ですね。脅威的なのは身長だけではなかったのですね」
![]() 「馬鹿にしないでよ。私はあなたより年上で人生40云余年、社会勉強で論理学も権謀術数も習得したのです」
「馬鹿にしないでよ。私はあなたより年上で人生40云余年、社会勉強で論理学も権謀術数も習得したのです」
![]() 「柳田さんの話を聞いて分かりました。環境といわれているお仕事には、お互い無関係なものもあるということですね。だから環境部にまとめたのはある時期においては最適解かもしれないが、過渡期の存在にすぎないと……」
「柳田さんの話を聞いて分かりました。環境といわれているお仕事には、お互い無関係なものもあるということですね。だから環境部にまとめたのはある時期においては最適解かもしれないが、過渡期の存在にすぎないと……」
![]() 「環境先進企業に環境部はなく、CSR先進企業にCSR部はないという言葉を聞いたことがありますが、環境とかCSRとかが会社に浸透している会社なら、わざわざ環境部とかCSR部というのは要らないということか」
「環境先進企業に環境部はなく、CSR先進企業にCSR部はないという言葉を聞いたことがありますが、環境とかCSRとかが会社に浸透している会社なら、わざわざ環境部とかCSR部というのは要らないということか」
![]() 「しかし皆さんはすごいですねえ〜。そういうことをサッと理解してしまうのだから」
「しかし皆さんはすごいですねえ〜。そういうことをサッと理解してしまうのだから」
![]() 「学問において問題を提起することは、問題を解くことと同じく重要と言いますね。石川君はすごいよ」
「学問において問題を提起することは、問題を解くことと同じく重要と言いますね。石川君はすごいよ」
![]() 「いえ、岡山さんがサラッと言い、それを当たり前に理解する皆さんはもっとすごいです」
「いえ、岡山さんがサラッと言い、それを当たり前に理解する皆さんはもっとすごいです」
・
・
・
![]() 「話を戻しますが、田中さんの意見、つまり環境だといわれていた様々な仕事・機能は本来それを行うべき部門に再配分されたという意見は、私が考えていたことと同じです。
「話を戻しますが、田中さんの意見、つまり環境だといわれていた様々な仕事・機能は本来それを行うべき部門に再配分されたという意見は、私が考えていたことと同じです。
しかしまだ本来の部門に移っていないものもあるということです」
![]() 「ということは5年前の環境部解体が、不適切であったということですか?」
「ということは5年前の環境部解体が、不適切であったということですか?」
![]() 「不適切というか、引き取り手のない機能が残ってしまったということでしょう」
「不適切というか、引き取り手のない機能が残ってしまったということでしょう」
![]() 「どこも引き取らない廃棄物と、省エネ法対応の事務局、本社のISO事務局と工場のISO支援、それから公害防止が残ってしまい、それを環境管理課として残したんでしょ。
「どこも引き取らない廃棄物と、省エネ法対応の事務局、本社のISO事務局と工場のISO支援、それから公害防止が残ってしまい、それを環境管理課として残したんでしょ。
廃棄物をどこにもっていくかとなると、生産技術でもないし施設管理でも持て余しそうですね」
![]() 「磯原さんのお仕事は、そもそもは省エネだったのでしょう。だったら生産技術担当ですよね」
「磯原さんのお仕事は、そもそもは省エネだったのでしょう。だったら生産技術担当ですよね」
![]() 「省エネする技術とか指導ということならそうでしょうし、その部分はすでに生産技術研究所に移管されています。
「省エネする技術とか指導ということならそうでしょうし、その部分はすでに生産技術研究所に移管されています。
実を言えば私は本社に来るとき、省エネ法のエネルギー管理企画推進者……つまり山内さんのことですが……その手足をしてほしいと言われました。
要するに全社のエネルギー管理手順や削減計画を作り実行させフォローする、そういうことを山内さんの指示の下に私がするのが当初の計画でした。
ですから技術的というよりアドミニストレーションだったのです。それは生産技術研究所の仕事ではありません。環境担当役員の、法律ではエネルギー管理統括者である常務の仕事です」
注:アドミニストレーションとは統治、行政、管理などの意味で、会社ではマネジメント(管理)が適正に行われるように指導・統制をおこなう意味でつかわれる。
![]() 「ほう〜、磯原さんは環境管理課とは無縁だったのか」
「ほう〜、磯原さんは環境管理課とは無縁だったのか」
![]() 「ハイ、ただそうなると私は生産技術本部長室所属となりまして、人事の扱い上、平社員が役員室所属というのはないそうで、環境管理課兼役員室所属となったわけです。
「ハイ、ただそうなると私は生産技術本部長室所属となりまして、人事の扱い上、平社員が役員室所属というのはないそうで、環境管理課兼役員室所属となったわけです。
プロジェクトなどで平社員が役員室兼務するのは多々ありますからね」
![]() 「ええっ、磯原さんは役員室兼務だったの」
「ええっ、磯原さんは役員室兼務だったの」
注:「役員室」とは役員のいる部屋のことではない。社長、監査役、執行役などになると、その職務範囲は広くとても一人で対応できるものではない。それで役員の下に個々の職務を担当する人が付き、それぞれ専門分野を担当する。国会議員も一人では仕事ができないから、複数の秘書が付いているのと同じだ。秘書といっても小間使いではなく、様々な専門家たちである。役員室とは部より一つ上の組織である。
役員室の担当者は、普通は工場長クラスとか最低でも部長クラスである。
![]() 「そうですよ。ちゃんと組織表に書いてあるでしょう。
「そうですよ。ちゃんと組織表に書いてあるでしょう。
もっとも上西課長は最後まで磯原さんが兼務だったと気づかなかったようだわ」
![]() 「だけどそれなら環境管理課の雑用を何から何まですることはなかったのに。
「だけどそれなら環境管理課の雑用を何から何まですることはなかったのに。
上西課長がなんでもかんでも磯原さんに投げていたね。よく文句を言わずに仕事をしていたものだ」
![]() 「確かにそうですね。廃棄物以外に本社支社のISO事務局の仕事も残ったのですが人は減ってしまった。それで環境管理課所属になった私に回ってきました。その他、工場でいろいろ問題が起きると暇だと思われて私に回ってくるのがデフォになってしまいました」
「確かにそうですね。廃棄物以外に本社支社のISO事務局の仕事も残ったのですが人は減ってしまった。それで環境管理課所属になった私に回ってきました。その他、工場でいろいろ問題が起きると暇だと思われて私に回ってくるのがデフォになってしまいました」
![]() 「そして磯原さんは仕事が早いから重宝がられたのよ、上西課長にも山内さんにも。器用貧乏ですね、アハハ」
「そして磯原さんは仕事が早いから重宝がられたのよ、上西課長にも山内さんにも。器用貧乏ですね、アハハ」
![]() 「まあ、それはともかく、環境部解体から5年が経って再度環境課の見直しをしなければならない時期になったと思います。
「まあ、それはともかく、環境部解体から5年が経って再度環境課の見直しをしなければならない時期になったと思います。
それは上から言われたからでなく、私自身も環境管理課の職掌がどうあるべきか、積極的に言えば我々の存在意義をいかに示すか、改めて考える必要があると思います」
![]() 「確かにそうだ。もう2年になるが、坂本さん、岡山君、石川君と私がここに異動したのは、パワー不足ということだった。坂本さんと私は工場の指導、岡山君と石川君は工場の次期管理者候補として教育するということだったはずだ。
「確かにそうだ。もう2年になるが、坂本さん、岡山君、石川君と私がここに異動したのは、パワー不足ということだった。坂本さんと私は工場の指導、岡山君と石川君は工場の次期管理者候補として教育するということだったはずだ。
環境管理課の職掌が変わらなければ、坂本さんと私が引退したら工場の古手をまた引っ張る、岡山君と石川君は卒業して君たちより5歳くらい下の人を持ってきて本社の経験をさせて成長したら戻すというサイクルを繰り返すだけでも良いだろう。
だけど目の前の問題を解消できたなら、環境管理課の業務を見直しをする道もあるだろうね」
![]() 「今までの話は経緯というか前提条件のおさらいです。ということを前提に我々は何をすべきを考えておく必要があるということです」
「今までの話は経緯というか前提条件のおさらいです。ということを前提に我々は何をすべきを考えておく必要があるということです」
![]() 「何をすべきかというと?」
「何をすべきかというと?」
![]() 「周りに流されるだけではいやではありませんか? 取り巻く環境、会社の状況、己のコンピタンス、そういうものを考慮して自分は会社にどんな貢献ができるか、言い換えると自分をいかに高く売りこむかを考えるべきです」
「周りに流されるだけではいやではありませんか? 取り巻く環境、会社の状況、己のコンピタンス、そういうものを考慮して自分は会社にどんな貢献ができるか、言い換えると自分をいかに高く売りこむかを考えるべきです」
![]() 「なるほど、わしの立場で考えると、当初求められたタスクは果たしたが、単に老兵は引退するのではなく、わしの持つ経験を更に活用できないかということだな」
「なるほど、わしの立場で考えると、当初求められたタスクは果たしたが、単に老兵は引退するのではなく、わしの持つ経験を更に活用できないかということだな」
![]() 「私ならどういう選択肢があるのでしょう? 一刻も早く工場に戻って本社での経験を生かすということですか?」
「私ならどういう選択肢があるのでしょう? 一刻も早く工場に戻って本社での経験を生かすということですか?」
![]() 「まず石川さんの希望がどうかだろう。君を候補に選んだのは私だ。はじめは高崎工場は石川さんを出さないだろうと思っていた。君は工場で評価され将来を期待されていたからね。ところが予想に反して工場長も部長も石川さんの能力を買ってくれて、会社全体を相手に頑張ってほしいと言って送り出してくれた。
「まず石川さんの希望がどうかだろう。君を候補に選んだのは私だ。はじめは高崎工場は石川さんを出さないだろうと思っていた。君は工場で評価され将来を期待されていたからね。ところが予想に反して工場長も部長も石川さんの能力を買ってくれて、会社全体を相手に頑張ってほしいと言って送り出してくれた。
力量が向上したと考えて、元の工場に戻りたいならそれでも良いけど、全社の廃棄物行政に従事していきたい希望ならそういう売り込みもある。他の部署に行きたいと志望しなくても、自分がしたいことを企画して提案すれば自動的にその仕事をするようになるでしょう」
![]() 「良く分かりました。ただ今の私は日々そこまで考えていたわけではないので、これから考えたり勉強したりしていきます」
「良く分かりました。ただ今の私は日々そこまで考えていたわけではないので、これから考えたり勉強したりしていきます」
![]() 「いずれにしても、あと1年や1年半の時間はあるよ。
「いずれにしても、あと1年や1年半の時間はあるよ。
そういうわけで個人的にはいかに自分を高く売るかを考えるべきだし、環境管理課そのものも他に負けない技術とか知識とかで存在意義を示さないと消滅してしまうだろう」
![]() 「環境管理課はどこへ行くか……なくてもよいならなくなるのはしょうがないとも言えるね」
「環境管理課はどこへ行くか……なくてもよいならなくなるのはしょうがないとも言えるね」
![]() 「山内さんから聞いた話ですが、アメリカ海兵隊は独立戦争のときに作られたそうです。当時の海兵隊は漫画や映画で描かれた海賊の戦いと同じで、敵の軍艦に接舷して切り込むのが仕事だった。やがて海軍同士の戦いは大砲で撃ち合いが主となり、そんな戦いはなくなった。
「山内さんから聞いた話ですが、アメリカ海兵隊は独立戦争のときに作られたそうです。当時の海兵隊は漫画や映画で描かれた海賊の戦いと同じで、敵の軍艦に接舷して切り込むのが仕事だった。やがて海軍同士の戦いは大砲で撃ち合いが主となり、そんな戦いはなくなった。
じゃあ海兵隊はいらないのかとなったわけ。実際に廃止された時期もあった。その後、海賊退治や拿捕された人の解放とか、陸軍や海軍の狭間の仕事をして海兵隊の存在意義を示してきた。
第一次大戦の頃には、敵前上陸できることを目指してそれなりに認められた。
しかし第二次世界大戦後は敵前上陸など発生しないと考えられ、またその存在意義を失ったかと思えたが、海兵隊のみで作戦を行えるという独自性で生き残った。アメリカ海兵隊は戦闘機から爆撃機そしてヘリコプター、また戦車とか水陸両用強襲輸送車(水陸両用戦車)まで持っているからね。陸軍・海軍・空軍が必要な作戦を、海兵隊だけで遂行できる。
アメリカ海兵隊のように知恵を絞れば、環境管理課が生き残る道はあるでしょう。
例えば緊急事態対応のタスクフォースとかあるんじゃないかな。以前、熊本工場で漏洩事故が起きたとき、磯原さんが行って対応を指導した。岩手工場のときは田中さんが行って原因究明した。廃棄物の不法投棄問題では坂本さんと石川君が行って片をつけた。
そういうトラブルシューティングを専門にするのもありだろう」
![]() 「確かに存在意義を示すという点においてはありだね。ただいつまでもそういう仕事が存在しては困るわけだが」
「確かに存在意義を示すという点においてはありだね。ただいつまでもそういう仕事が存在しては困るわけだが」
![]() 「確かに当面ならともかく、ずっとそんな役目が必要なら会社がおかしいです」
「確かに当面ならともかく、ずっとそんな役目が必要なら会社がおかしいです」
![]() 「あのね、現代社会は変動が激しいの。恒久的な組織とかビジネスとかというものはないのよ。だから環境管理課の仕事を今見直しても、また数年後は見直すということになるでしょう。
「あのね、現代社会は変動が激しいの。恒久的な組織とかビジネスとかというものはないのよ。だから環境管理課の仕事を今見直しても、また数年後は見直すということになるでしょう。
1990年頃、アメリカのフォード社は『21世紀は車を作って売る会社ではない』と語ったわ。当時は作った車をレンタルするビジネスモデルを考えていたみたい。現実はフォード社は今金融機関になったわ」
![]() 「金融機関??」
「金融機関??」
![]() 「会社の経営に占める自動車ローンが大きいわよ。言い換えると製造業では生きていけなかったということかな」
「会社の経営に占める自動車ローンが大きいわよ。言い換えると製造業では生きていけなかったということかな」
![]() 「ホンダも車メーカーから飛行機メーカーだもんね」
「ホンダも車メーカーから飛行機メーカーだもんね」
![]() 「今は更に進んで有人のドローンを考えているのかもよ。有人のドローンというのはおかしいか」
「今は更に進んで有人のドローンを考えているのかもよ。有人のドローンというのはおかしいか」

![]() 「航空法ではドローンを『無人航空機』としているね」
「航空法ではドローンを『無人航空機』としているね」
![]() 「おっと、今この場で環境管理課の存続動向を決めるわけじゃない。現実はそういう動きをしていること、そして自分はどういう生き方を望むのか、そういうことを考えてほしい」
「おっと、今この場で環境管理課の存続動向を決めるわけじゃない。現実はそういう動きをしていること、そして自分はどういう生き方を望むのか、そういうことを考えてほしい」
![]() 「最終的には当社の環境管理体制は、どうあるべきかとなりますね」
「最終的には当社の環境管理体制は、どうあるべきかとなりますね」
![]() 「客観的に言えばそうだろうけど、主観的に言えば当社の環境管理体制をこうしたいということですか。あるいは自分は何をしたのか」
「客観的に言えばそうだろうけど、主観的に言えば当社の環境管理体制をこうしたいということですか。あるいは自分は何をしたのか」
・
・
・
・
ミーティングを終えて皆が立ち上がる。
![]() 「環境課のレーゾンデートルか〜、ISO認証などよりも重大な話だなあ〜」
「環境課のレーゾンデートルか〜、ISO認証などよりも重大な話だなあ〜」
![]() 「そういう言い方をISO関係者が聞いたら気を悪くしますよ」
「そういう言い方をISO関係者が聞いたら気を悪くしますよ」
![]() 「岡山君、まさか君は、環境管理課の存在意義よりもISO認証の意義のほうが重要だと……」
「岡山君、まさか君は、環境管理課の存在意義よりもISO認証の意義のほうが重要だと……」
![]() 「全然そんなこと思いませんよ。でも紳士は口にしないのです」
「全然そんなこと思いませんよ。でも紳士は口にしないのです」
![]() 「俺は紳士じゃないから、ISOなんて役に立たないって大声で言っちゃうぞ」
「俺は紳士じゃないから、ISOなんて役に立たないって大声で言っちゃうぞ」
![]() 「ハハハ、冗談ではなく本音なのがいいですね」
「ハハハ、冗談ではなく本音なのがいいですね」
![]() 本日の予定
本日の予定
どうでしょう、こんな調子でISO認証の将来と企業の環境管理体制の今後を考えておしまいということで幕を引きたいのですが……
おっと、まだ終わりませんよ。あと5回くらいかな
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |