*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
2023年6月になった。
新型コロナ流行は2023年5月に第2類から第5類になったために、感染者・数死者数とも日々の発表はなくなり、規制もなくなり暮らしは……表面上は……コロナ流行以前に戻った
本部長室の環境担当が田村さん、生産技術部長が小林さんに代わってから1年半が経った。ふたりとも一般常識はあるし、会社の組織もルールも理解しているし、名を売るとか過度な上昇志向もなく、部下が右往左往することはない。小林部長も当初のように俺が俺がという態度もおとなしくなった。
そういう意味では山内さんは純真無垢であったが、仕事のやり方は会社組織を無視して傍若無人だった。完璧な人はいないということか。
環境管理課長が磯原であるのは変わらない。そして庶務が柳田さんであるのも変わらない。二人ともそれなりの年になった。磯原は44歳、柳田は45歳である。
だが変化もある。
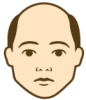 |
|
| 松村さん |
もっとも次にここから出ていくのは磯原に違いない。だから松村さんの定年まで磯原はここにいないだろう。
| 環境管理課の現在の座席配置図 | |||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||
余部さんは松村さんの後任になるだろう。彼も今では事故とか違反発生と聞くと、真っ先に飛び出していく。そんなことが毎年二三度はある。
とはいえこれからは緊急事態対応から、坂本さんのしている環境計画のフォローや工場や支社の環境全般の指導に移ってもらう。
坂本さんは傍から見ても体力は、本社に来た5年前に比べれば明らかに落ちている。寿命が延びたとか、今の老人は若いといっても、やはり65歳あたりが限度なのか。
岡山は1年前の春、工場排水からのリン高効率回収プロジェクトへの参加を乞われ研究所に異動した。その陰には、研究所にいった山内さんの思惑がありそうだ。
 |
|
| 岡山さん |
ところがあるとき工場で実験していて、工場の環境管理部門に居ついてしまったという彼の経歴を考えると、研究者であるのがベターだろう。磯原はゆくゆくその研究成果でドクターを取れと激励して送り出した。
 |
|
| 石川さん |
本人も納得、派遣していた高崎工場も納得、会社としても新しい取り組みの宣伝塔になる。
もちろん幸せな人ばかりではない。石川を工場に戻すという話が伝わったのか、岡山工場の福田から石川の後任に呼んでほしいとお願いされたが、彼は既に35歳だ。若手を育てるという目的から外れているとお断りした。
当時、磯原は福田を本社に呼ぶつもりだった。なぜか上西が福田を拒否したから石川になったのだが、人間はちょっとしたことで運命が変わってしまうものだ。今は、自分のいる場所で頑張れとしか言いようがない。
もちろん工場勤務が本社より下ではないとは言え、若い時に大局的に見る経験ができなかったのはやはり残念だろう。
 |
|
| 宇佐美さん |
廃棄物担当だった石川の後任として、名古屋工場から28歳の 宇佐美が来た。
前任の石川が本社に来たのが28歳、宇佐美も28歳だ。彼も石川が本社に来てからの活躍と、係長で工場に凱旋したのを見ているからやる気満々だ。
石川と違い、良い意味で社交的、如才ない男で積極的に本社各部門に顔と名前を売っている。本社を去るときは、環境部門でない営業とかかもしれない。それもまた吉。
そんなことで磯原は仕事と人員については安心している。突発的な事故発生や違反発覚は、この仕事ではつきものである。皆の意識が高く力量向上の努力があれば、憂いはない。
現在のメンバーが経験・知識・意欲の観点で、最高だというわけではないが、仕事のプライオリティを認識し、自分のやるべきことを粘り強く取り組んでくれるなら十分だ。それは彼らが次の職場でも私生活でも意味あることだろう。
|
| ||
今まで内外に課題とトラブルが多々あったこの職場を、改善してきたのは自分だという自負もある。人の入れ替え、教育、仕事の手順の明確化、指揮系統の見直し、ISO認証の返上などいろいろやってきた。
言い換えると磯原は次のステップに進まないといる場所がない。まあ、それまで1年や1年半の執行猶予はあるだろう。
課長席から皆を見回してそんなことを思う。
突然、柳田がさっと立ち上がり一礼する。彼女がそんな態度をとるとは、よほど偉い人でも来たのかと、ゆっくりと首を回してオフィスのドアの方を見る。
そこには相も変らぬバーコードの山内が、ニコニコして立っていた。磯原と目が合いスタスタと歩いてくる。
磯原も立ち上がり柳田と一緒に出迎え、会議室に案内する。
二人を会議室に入れると、柳田は消えた。
![]() 「わしが去って1年半か、変わらないようで変わったな」
「わしが去って1年半か、変わらないようで変わったな」
![]() 「そうですね、環境管理課の組織名は変わりませんが、メンバーは柳田さんと私以外はすべて入れ変わりました。ああ、山内さんは余部さんと入れ違いでしたっけ?」
「そうですね、環境管理課の組織名は変わりませんが、メンバーは柳田さんと私以外はすべて入れ変わりました。ああ、山内さんは余部さんと入れ違いでしたっけ?」
![]() 「岡山はわしが引っ張ったが、石川は高崎工場に戻したのか?」
「岡山はわしが引っ張ったが、石川は高崎工場に戻したのか?」
![]() 「ええ、彼も十分以上に成長してくれて工場で係長になりました」
「ええ、彼も十分以上に成長してくれて工場で係長になりました」
![]() 「環境管理課で人を育てるという制度の一期生としては十分な成果であるな。
「環境管理課で人を育てるという制度の一期生としては十分な成果であるな。
世は去り世は来たるか……坂本さんは来年は引退か?」
![]() 「ええ、定年延長というか高齢者雇用という観点からも実力があるという意味でも、もっといてほしかったのですが、彼も単身赴任が5年ですからね。夫婦でゆったり過ごしたかったのでしょう」
「ええ、定年延長というか高齢者雇用という観点からも実力があるという意味でも、もっといてほしかったのですが、彼も単身赴任が5年ですからね。夫婦でゆったり過ごしたかったのでしょう」
![]() 「そして磯原も今や大課長で悠々だな」
「そして磯原も今や大課長で悠々だな」
![]() 「実は行き詰ったって感じですね」
「実は行き詰ったって感じですね」
![]() 「おやまたどうしてかな?」
「おやまたどうしてかな?」
![]() 「良く知られていることですが、当社では工場長になるのは、開発系の出身か営業出身と決まっています。どう考えても施設管理とか資材部出身では事業を推進する旗頭としては不向きですからね」
「良く知られていることですが、当社では工場長になるのは、開発系の出身か営業出身と決まっています。どう考えても施設管理とか資材部出身では事業を推進する旗頭としては不向きですからね」
![]() 「そりゃそうだ。歴代社長だって開発系か営業系しかいない。どこの会社でも一般的だな。財務とか知財出の役員が社長になったなんてあまり聞かない。
「そりゃそうだ。歴代社長だって開発系か営業系しかいない。どこの会社でも一般的だな。財務とか知財出の役員が社長になったなんてあまり聞かない。
基本的に企業というのは拡大しなくちゃ存在できない。損失を少なくとか原価を安くではなく、売上を大きく規模を大きくしないと先はない」
![]() 「私もここは長いです。でもいくところがありません。工場に戻っても環境しか知らない人間に部長職は務まらないでしょう。工場では部長となると、いくつもの機能を管理しないとなりませんからね。
「私もここは長いです。でもいくところがありません。工場に戻っても環境しか知らない人間に部長職は務まらないでしょう。工場では部長となると、いくつもの機能を管理しないとなりませんからね。
本社にいても他の部署にいっても袋小路です。となると自分のキャリアをどうするかが私の課題です。
本社に来ずに工場にいたら、今頃は工場の課長になったかならないかで、現場でトランスの点検とか蛇退治とかして、楽しく過ごしていたと思いますよ」
| 🐍 |
注:工場でも電力会社でも、送電や変電施設の事故は、蛇を筆頭とする小動物が侵入したショートで起きたという報告が多い。その真偽は定かではない。
噂では事故に備えて、変電室に蛇の死体を常備しているとか?
![]() 「45歳で達観してしまったか。そりゃぜいたくな悩みだな。
「45歳で達観してしまったか。そりゃぜいたくな悩みだな。
仕事そのものの性質も変わったのだろう?」
![]() 「そうですね。来たときはISO認証もありましたが、それを返上するようになりました。社内ではほとんどが認証を返上しました。関連会社も非製造業も製造業もほとんどが返上しました。悩むところが建設業の許可を受けているところです。これも今年中くらいにははっきりさせたいと考えています。
「そうですね。来たときはISO認証もありましたが、それを返上するようになりました。社内ではほとんどが認証を返上しました。関連会社も非製造業も製造業もほとんどが返上しました。悩むところが建設業の許可を受けているところです。これも今年中くらいにははっきりさせたいと考えています。
また廃棄物にしても公害防止にしても、本社も工場も体制の見直し、遵法の確実化、改善などやってきたつもりです。ですがそれらが一巡して、事故も減ってきました。現状で安定すれば、もう居場所がありません。更なる改革は新しい人にやってほしいですね」
![]() 「確かにな、何事も体制を構築すると保守になり、時が経つと緩んでくる。そしたら人を変え組織を変えて、改革し改善を進めるという繰り返しになるのが一般的のようだ」
「確かにな、何事も体制を構築すると保守になり、時が経つと緩んでくる。そしたら人を変え組織を変えて、改革し改善を進めるという繰り返しになるのが一般的のようだ」
![]() 「それと収穫逓減の法則があります。どの工場でもいろいろ改善点が見つかると思います。投資をするなら手軽にできて効果があるものから取り掛かるでしょう。そして次善の改善、三善の改善と進んでいくにつれて、投資対効果はだんだんと下がります。
「それと収穫逓減の法則があります。どの工場でもいろいろ改善点が見つかると思います。投資をするなら手軽にできて効果があるものから取り掛かるでしょう。そして次善の改善、三善の改善と進んでいくにつれて、投資対効果はだんだんと下がります。
当社の場合、グループ全体で省エネの投資対効果の大きい順に手を打ってきていますが、もう何順もしていて落穂拾いをしている状況です。
今は補助金とか税制とか、燃料や電気代が少し変わっただけで変わってしまうという状態です。元々が乾いた洗濯物を絞っているようなものですからね。画期的技術が出ないと、更なる推進は難しい」
![]() 「まあ、それはどんな分野でも同じだ。だが諦めてはいかん。そういうときにブレークスルーは起きるというか起こさねばならんのだ。
「まあ、それはどんな分野でも同じだ。だが諦めてはいかん。そういうときにブレークスルーは起きるというか起こさねばならんのだ。
ところで今ISO14001はどうなったのか?」
![]() 「もう社内ではISO認証など頭にありません。正直言って昔そんなものがあったという認識です」
「もう社内ではISO認証など頭にありません。正直言って昔そんなものがあったという認識です」
![]() 「なるほど、なくなっても困らないか……
「なるほど、なくなっても困らないか……
というと今はISO第4世代になったのか?」
![]() 「おお、懐かしい言葉ですね。山内さんがいらした頃は、我々はISO第3世代なんて自称してましたね。
「おお、懐かしい言葉ですね。山内さんがいらした頃は、我々はISO第3世代なんて自称してましたね。
でもISOが付くのはISOを意識しているからであって、意識にないのですからポストISO世代ですかね?」
![]() 「なるほど、ISOの世代が変わったのではなく、ISOに無縁の世代か」
「なるほど、ISOの世代が変わったのではなく、ISOに無縁の世代か」
6月中旬、広報部から前年度のCSR報告書のドラフトができたので、サステナビリティ担当役員に確認してほしいと依頼があった。
今はCSR報告書は株主総会とも環境月間とも関わりない。まず基本はウェブサイトとなった。どうしても冊子が必要という場合用に、千部ほどハードコピーを作ってはいる。
ウェブサイトの文言やビジュアルは毎年7月頃全面的に見直し、数字のデータは四半期ごとに実績に書き換えている。
今回の依頼は文言修正の確認である。
今日は田村さんが生産技術部長と磯原を集めて、CSR報告書の環境パートの確認をしている。この仕事は生産技術部とか環境管理課のマターではないから、田村さんがふたりにアドバイスを頼んだということだ。
CSR報告書には、環境以外に安全衛生とか社会貢献などがあるから、そういったパートはそれぞれの担当役員に依頼がいき、田村さんと同じような役員スタッフが仕事をしているのだろう。
![]() 「しかしなんだなあ〜、私が来て2年経つが、何も改善していない。
「しかしなんだなあ〜、私が来て2年経つが、何も改善していない。
省エネも廃棄物も目標は昨年と変わらず。そして結果も業界申し合わせの1.5%を超えるのがやっと、事故や違反も未だゼロは未達成だ。
わしは労働安全を担当してきたが、毎年管理指標は上がっていくもんだ。
こんなことでいいのかね、磯原君、」
![]() 「目標値が昨年と変わらないというのは、努力していないということではありませんよ。労働安全と言いますと、主たる指標は度数率、強度率、千人率
「目標値が昨年と変わらないというのは、努力していないということではありませんよ。労働安全と言いますと、主たる指標は度数率、強度率、千人率
![]() 「ほう、そうかね?」
「ほう、そうかね?」
![]() 「例えば度数率ですが、これは対象年に発生した労働災害の死傷者数を延べ労働時間数で割ったものです。今年(2023)労働政策審議会は第14次労働災害防止計画
「例えば度数率ですが、これは対象年に発生した労働災害の死傷者数を延べ労働時間数で割ったものです。今年(2023)労働政策審議会は第14次労働災害防止計画
4年間で5%減ですから、年1.2%減になります。省エネは省エネ法で1%、業界申し合わせで1.5%ですから、労災の目標と変わりません」
![]() 「えっ、そうなの」
「えっ、そうなの」
![]() 「どの分野においても年1%というのは大変厳しいですよ。当然投資しないと改善はできません」
「どの分野においても年1%というのは大変厳しいですよ。当然投資しないと改善はできません」
![]() 「いやいや投資しなくても改善はできる。わしが工場にいたときは、意識向上で毎年省エネ1%とかしていたぞ」
「いやいや投資しなくても改善はできる。わしが工場にいたときは、意識向上で毎年省エネ1%とかしていたぞ」
![]() 「精神論としては立派と思いますが、本社でそんなこと言わないでくださいね。はっきり言って笑われます」
「精神論としては立派と思いますが、本社でそんなこと言わないでくださいね。はっきり言って笑われます」
![]() 「なんだと!」
「なんだと!」
![]() 「だって管理された職場というのは、5Mつまり、人、機械、方法、材料、管理をしっかりと定めて、それに基づいて仕事をさせます。そこからの逸脱を認めません。それは製造現場に限らず、事務所でも保守部門でも同じです。5Mのいずれかを変えなければ結果は変わらない、変わってはいけないのです。
「だって管理された職場というのは、5Mつまり、人、機械、方法、材料、管理をしっかりと定めて、それに基づいて仕事をさせます。そこからの逸脱を認めません。それは製造現場に限らず、事務所でも保守部門でも同じです。5Mのいずれかを変えなければ結果は変わらない、変わってはいけないのです。
意識向上で省エネができるとは、それまで意識が低かったから基準通り照明OFFしなかったとか、温度設定を怠ったとかとなりますよ」
![]() 「基準を守ってなかっただと! ならばどうして毎年省エネができたんだ?
「基準を守ってなかっただと! ならばどうして毎年省エネができたんだ?
5Mが変わらずとも、一生懸命仕事をしようとする意欲があれば成果は変わるはずだ」
注:多くの企業で「意識向上」とか「努力」による省エネを年1%位計画に織り込んでいる。ISO審査員はそれを咎めることなく、逆にそういう項目がないと盛り込めと指導する(違反だよ)。
もし「意識向上」とか「努力」によって省エネができるなら、その理屈を教えてほしい。
年1%とは小さくはない。というかとんでもない削減なんですよ。何しろ省エネ法での削減義務が年1%です。
意識向上だけで省エネできるなら万々歳だ。🙌
![]() 「小林部長、落ち着きなさいよ」
「小林部長、落ち着きなさいよ」
![]() 「製造なら刃物も被削材も変わらなければ、送りも切り込みも変えられません。排水処理だって設備が変わらなければ生物処理でも化学処理でも必要な時間は変わりません。
オフィスなら、照明も室温もOA機器のON/OFFも基準があります」
「製造なら刃物も被削材も変わらなければ、送りも切り込みも変えられません。排水処理だって設備が変わらなければ生物処理でも化学処理でも必要な時間は変わりません。
オフィスなら、照明も室温もOA機器のON/OFFも基準があります」
![]() 「じゃあ、どうして努力で改善できたんだ?」
「じゃあ、どうして努力で改善できたんだ?」
![]() 「私には分かりません……そうですね、昼休み前にはフィードレートをあげたり、定められた加工数より多く刃物交換をしなかったのでしょう。もしフィードレートをあげたなら形状許容差に入っているか、定められた基準より刃物交換が長ければ、仕上がりを確認しないといけませんね。
「私には分かりません……そうですね、昼休み前にはフィードレートをあげたり、定められた加工数より多く刃物交換をしなかったのでしょう。もしフィードレートをあげたなら形状許容差に入っているか、定められた基準より刃物交換が長ければ、仕上がりを確認しないといけませんね。
オフィスなら暑いのを我慢するとか、真っ暗な部屋で仕事をするとか……
あのですね、精神力だけ大和魂では勝てないのです」
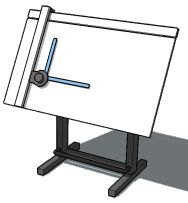
1960年代末は、オフィスにも設計居室にもエアコンなどなかった。ドラフターで図面を描いていると肘が汗まみれになり、描いた図面がベタベタになった。当時はそんなもんだと思っていた。
今、暑くても文句を言わずに仕事しろと言えば、アタオカとかパワハラとか言われるだろう。省エネ努力とは努力することでなく我慢することであったか?
![]() 「面白いことを言うね。すると君は人間の努力を認めないわけか?」
「面白いことを言うね。すると君は人間の努力を認めないわけか?」
![]() 「画期的なアイデアで金をかけずに改善できることもあるでしょう。
「画期的なアイデアで金をかけずに改善できることもあるでしょう。
しかしいずれにしても、改善するときは作業標準に示す5Mが見直されなければなりません。作業標準を変えずに作業方法を変えたら、それは会社規則違反です」
![]() 「ワケワカランね」
「ワケワカランね」
![]() 「小林部長、それは当たり前じゃないか。作業指示された方法に従わず早く作りましたというのを認めるのか?
「小林部長、それは当たり前じゃないか。作業指示された方法に従わず早く作りましたというのを認めるのか?
まずは提案を審査し、良ければ試行してQCDを検証して妥当なら作業標準を変えるのが筋だ。
先ほど君が言った、努力とか意欲で作業改善ができたなら、その中身を見たいね」
小林部長は口をヘの字にして黙った。
CSR報告書の検討が終わり磯原が会議室を出て行き、続いて小林部長が出ようとすると田村さんが呼び止めた。
![]() 「小林さん、あなたは磯原に何か思うところがあるのですか?」
「小林さん、あなたは磯原に何か思うところがあるのですか?」
本来なら敬語を使うのは目下の小林部長であり、田村氏が小林部長を君呼びしておかしくない。そこが田村氏と小林部長の違いなのだろう。
![]() 「そんなことは……いや、そうですね。正直言うと妬ましいのでしょう。私も昇進は早い方ですし、馬鹿ではないと思っていました。
「そんなことは……いや、そうですね。正直言うと妬ましいのでしょう。私も昇進は早い方ですし、馬鹿ではないと思っていました。
しかしトラブルが起きても、彼は困ったとか途方に暮れる状況にならないんですよ。私に相談するとか頼ってくることがない。
何事か起こって私が指示しようとすると、既に当面処置も恒久措置も手を打っているのです。それも私が指示しようとした方法でなく、それよりスマートな方法で」
![]() 「人により得手不得手は違うさ。小林さんには小林さんの得意がある。
「人により得手不得手は違うさ。小林さんには小林さんの得意がある。
ただ磯原のやり方をしっかりウォッチしておくのが良い」
![]() 「と言いますと?」
「と言いますと?」
![]() 「簡単だよ、奴の真似すればよいだけだ。
「簡単だよ、奴の真似すればよいだけだ。
君が感じるように磯原は大口を叩くように見えることもあり、とんでもなくおかしなことを言うように思えることもある。だが奴は根拠のないことは言わない。だから彼のやり方を学ぶことだ。
そして先ほど小林さんは努力でできると言ったが、客観的に考えて努力してもできないことはある。小林部長は発言に気を使った方が良い」
![]() 「努力だけでは改善はできないですか?」
「努力だけでは改善はできないですか?」
![]()
 「今は昔とは違う。科学技術も進んだし、価値観も変わった。スポーツで速く走るのも筋肉を付けるのも、根性とかトレーニングするだけでなく、休憩とか栄養とか更にはメンタルも考える時代だ。
「今は昔とは違う。科学技術も進んだし、価値観も変わった。スポーツで速く走るのも筋肉を付けるのも、根性とかトレーニングするだけでなく、休憩とか栄養とか更にはメンタルも考える時代だ。
部下を育てるのも、目標を与えて達成しろというだけでは、新人は辞めてしまう。人を育てるとは、できるように指導することであり、指導方法は確立されている。精神論と取られるような表現はすべきでない。
気を付けなければならないのは、21世紀になってパワハラが厳しく断罪されている。バブル時代なら当たり前だった、ガンバレ、俺についてこいなんてのは通用しない。手取り足取りとは言わないが、ステップを踏んで育てることができない人は通用しない時代だ」
![]() 「はあ〜、注意します」
「はあ〜、注意します」
・
・
・
・
小林が会議室を出てから田村はノートを開き、今日の打合せをまとめる。
いやCSR報告書の検討結果ではない。そんなものは磯原がそつなくまとめて、明日の始業前に田村にワークフローが届いているはずだ。田村は承認ボタンを押して広報部に送信すればおしまいだ。
今、田村がしているのは、小林部長の今後である。
小林部長もここにきて1年半、ご本人が言うほど生産技術部の改善は進まず、工場や関連会社に新しいサービスの提案もしていない。実を言って管理者を変えてほしいという声も人事や工場から聞いている。
それで本部長から、満2年になる今年10月が限度だから、どうするか考えてくれと田村にご下問があったのだ。
磯原の前任者のとき、周囲から使えないという非難ごうごうであったが、投手交代まで時間がかかり過ぎ問題を大きくしたらしい。
それで人事も専務も気にしている。
小林部長は相性が悪いのか、磯原をどうしても受け付けられないようだ。
田村から見れば、多少自己主張が強いところはあるが、表裏なく真面目に仕事をしている磯原に目くじら立てることもあるまい。むしろ小林部長が磯原に生産技術部の改革案を考えろと言えば、すぐさま良い案が出てくるだろうに……
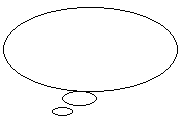 |
|
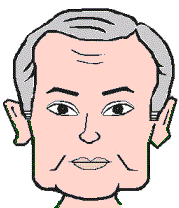 |
田村から見て磯原は、小林だけでなく田村を尊敬しているとは思えない。しかしルーティンワークをきれいにこなし、非常時に当たっては率先垂範で指揮を執り、しかも類似事故の再発防止まで手を打つなど、職責は十二分に果たしている。
上司への尊敬が足らんと文句を付けるほどのこともない。
対して小林はどうだろう?
過去2年、重大な決裁の間違いとか対応の漏れはなかったが、新しい計画もなく取り立ててスバラシイ成果もない。
平社員じゃないんだ、本社の部長あるいは工場長の地位としては期待外れだ。このまま生産技術部長を務めるには、力不足と言われても仕方ない。更に磯原のように積極的に動く部下を、評価せず活用していない。
小林部長は磯原を今年の秋に閑職に異動させる気だ。もっともそれには人事が難色を示すだろうし、小林に倍返しがくるはずだ。そのときは田村も責任を問われるだろう。
そう思うと田村は苦笑いする。
![]() 本日言いたいこと
本日言いたいこと
改善はしなければならない……とは誰でも知っている。
しかし改善はただではできない……と認識している人は少なく、古臭い管理職には更に少ない。

タンスターフル(Tanstaafl)という言葉がある。「ただの昼飯はない(There ain't no such things as a free lunch)」という英文の頭文字をつないだアクロニム(頭字語)である
昼飯でさえタダでないなら、お金が儲かる改善がタダってことはない。
改善は投資額の従属関数だ。会社が省エネに投資をすれば省エネは進む。しかし省エネすれば良いわけではなく、何事も投資対効果だ。何年で回収できるのか、いやそもそも回収できるのか考えなければならない。もちろん回収できなくても投資することもあり、儲かるのが分かっていても社是としてしないこともある。それは経営判断だ。
事故防止や違反防止も……方針であり、投資です。
昔々「生産第一、品質第二、安全第三」を方針としていた製鉄会社
方針を変えただけなら、何も変わらないと思うかもしれない。
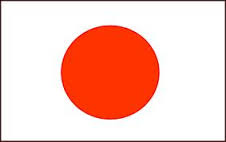
|
|  |
注1:旗の順序は左から、国旗、社旗、安全旗の順序だそうです。
注2:OBAQってなんだとお思いになりますか?
「おばQ」でございます。それがなにか?
方針を変えるとは、壁に貼る文言を変えることではない。安全第一とは投資の際に安全を優先することであり、設備に異常が見つかれば即座に生産停止を決定できることだ。それゆえ方針は成就する。
その工場では災害が減り、そして品質も上がり、最終的に生産も上がった。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 | ||
注2 | ||
注3 | ||
注4 |
「tanstaafl」の初出は何か調べた。私はハインラインの小説「月は無慈悲な夜の女王(1966)」と思っていたら、その歴史はそんな最近ではなかった。1938年の新聞記事だとあった。 Who Said TANSTAAFL First? | |
注5 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |



