*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
説明会の翌々日である。
生産技術本部で説明会の反省会を持った。メンバーは田村さん、磯原課長、そして広報部の広瀬課長である。広報部では前日に部内反省会をしていて、そこで出された意見を持ってきたという。

小林部長も顔を出したい雰囲気だったが、田村さんが「これは包括的な打ち合わせだから、公害関係の小林部長は出なくても大丈夫だ」とそれとなく断ってしまった。
磯原は小林部長の部下でもあるが、同時に全社の環境を見ている田村さんの部下だからということだろう。
本音は小林部長が、いつも磯原を批判ばかりして煩わしいからだろう。いや批判ならまだしも、反対のための反対意見を述べるだけだから、批判さえる本人だけでなく周りの人を嫌な気分にさせるから仕方ない。
![]() 「いやあ〜、あの説明会は広報に役に立ったかどうかはともかく、私自身にとってISO認証とか環境管理についてとても勉強になったよ」
「いやあ〜、あの説明会は広報に役に立ったかどうかはともかく、私自身にとってISO認証とか環境管理についてとても勉強になったよ」
![]() 「おや、どんなことですか?」
「おや、どんなことですか?」
![]() 「まず磯原君が作ってくれたQ&Aが完璧だった。広瀬さんの方で想定質問を考えてくれたよね。普通、想定問答というと質問と1対1で対応した模範解答だろうけど、磯原君の作ってくれたものは少し違った」
「まず磯原君が作ってくれたQ&Aが完璧だった。広瀬さんの方で想定質問を考えてくれたよね。普通、想定問答というと質問と1対1で対応した模範解答だろうけど、磯原君の作ってくれたものは少し違った」
![]() 「ほう、どんなものだったのですか?」
「ほう、どんなものだったのですか?」
![]() 「ISO規格と認証制度の関係、規格の問題、認証制度の問題、過去のトラブル、取り巻く人たちからISOはどうみられているかという実態、そういったことがA3で1枚物にまとめられていた。
「ISO規格と認証制度の関係、規格の問題、認証制度の問題、過去のトラブル、取り巻く人たちからISOはどうみられているかという実態、そういったことがA3で1枚物にまとめられていた。
もちろんその図を見ただけでは何も分からないが、図を指しながら原因からトラブルに至る因果関係とか、実際のトラブルの具体例などを教えてもらうと、なぜ問題が起きるのか、例えば規格の理解、事実誤認、コミュニケーションエラー、それた複合とか実に良く分かった。
そして広報部の作った想定質問がどこにあたるかということ、立場によって問題の認識が異なること、そういうものだった。説明会まで時間があるばその図を見ていた。すると想定質問に対する回答が思い浮かんでくる」
![]() 「ほう、ほう、それはぜひとも頂きたいですね」
「ほう、ほう、それはぜひとも頂きたいですね」
![]() 「そんな大層なものではありませんよ。正直申しまして田村さんは、ISOの繁文縟礼、審査でのコミュニケーション不足、審査員の力量不足などを実感していないと思いました。ですから1対1の想定問答では、通り一遍の回答になってしまうと思いました。
「そんな大層なものではありませんよ。正直申しまして田村さんは、ISOの繁文縟礼、審査でのコミュニケーション不足、審査員の力量不足などを実感していないと思いました。ですから1対1の想定問答では、通り一遍の回答になってしまうと思いました。
監査には回答がYESかNOとなるクローズドクエスチョンと、回答は何事かを説明しなければならないオープンクエスチョンがあります。いろいろ情報を収集するにはオープンクエスチョンがベターと言われています。
でもクローズドクエスチョンで問われても、起承転結とか取り巻く環境が分かるように回答したほうが、理解が深まり、YES/NOの回答よりも、質疑をより効果的で意味のあるものにできるはずです。
そのためには想定質問への回答を示すのではなく、その周辺も知っておいた方が良いと考えました。
とはいえ、一夜漬けに近い状況ですから包括的なことは無理です。なるべく簡単に質問の周辺を理解してもらえるようにと思ったのです」
![]() 「確か説明会での最初の質問は『それは自己宣言ですね』だったと思う。1対1の回答なら『NO』で終わりですけど、それでは応答が続かず説明会はお葬式のようになってしまっただろう。
「確か説明会での最初の質問は『それは自己宣言ですね』だったと思う。1対1の回答なら『NO』で終わりですけど、それでは応答が続かず説明会はお葬式のようになってしまっただろう。
そういう直接的な回答でなく、そもそも我々は認証に拘っていないのだと言いたかったのです。
ともかくあれを頭に入れておけば、想定質問だけでなくどの切り口での質問でも回答できると感じた。実際に私は回答を考えて発言していたのではなく、図を思い出しながら相手の知りたいことを説明しようとした」
![]() 「確かに今回聴衆者は少なかったですけど、田村さんの回答が質問に答えるだけでなく、なぜ卒ISOを目指したのか良く分かました。そのせいもあって質問は活発でしたね。
「確かに今回聴衆者は少なかったですけど、田村さんの回答が質問に答えるだけでなく、なぜ卒ISOを目指したのか良く分かました。そのせいもあって質問は活発でしたね。
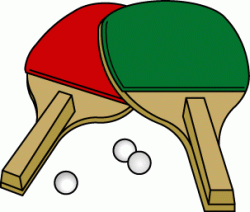 |
|
| テニスでも卓球でも、ラリーが続かないと面白くない。 |
10年以上前、環境報告書が珍しかった頃でも、あれほど質問がありませんでした。特に環境報告書/CSR報告書が一般的になってからは、省エネの数字とかに質問はあっても、環境活動とかISO認証について深く切り込んだものってなかったですね。
だって会社によっては環境活動の文章が1年前、2年前と変わらないなんて多々ありますからね。使っている写真が全く同じなんて見かけると、手抜きというかいかに安く作ろうとしているかが見えます」
![]() 「いや、まさしくそうだ。『自己宣言ですね』に対して『NO』ならラリーは終わりだ。
「いや、まさしくそうだ。『自己宣言ですね』に対して『NO』ならラリーは終わりだ。
ちょっと気になったのだけど、質問者は広瀬さんの仕込みじゃないんだろう?」
![]() 「実を言って広告を出している雑誌社の人に、質問する人がいなければ手を上げてほしいと頼んでいたけど出番がなかったわ」
「実を言って広告を出している雑誌社の人に、質問する人がいなければ手を上げてほしいと頼んでいたけど出番がなかったわ」
![]() 「それじゃ人数はともかく説明会は成功だったね」
「それじゃ人数はともかく説明会は成功だったね」
![]() 「ところが良かったとばかり言ってられないのよ。説明会の報道を見たり人づてに聞いたりしたからでしょうけど、説明会に来なかった新聞社とテレビ局から取材の話がいくつも来ているの。二度手間だわ」
「ところが良かったとばかり言ってられないのよ。説明会の報道を見たり人づてに聞いたりしたからでしょうけど、説明会に来なかった新聞社とテレビ局から取材の話がいくつも来ているの。二度手間だわ」
![]() 「いやいや、それは結構な話ですね。もっともそこは広報部で対応してくださいね。私どもは手が回りません」
「いやいや、それは結構な話ですね。もっともそこは広報部で対応してくださいね。私どもは手が回りません」
![]() 「ええっと、話を戻して、本日の議題は二つあると思います。ひとつは説明会の反省ですが、もうひとつはCSR報告書にISO認証返上を入れたこと、更に認証返上がどう受け取られたの総括です。
「ええっと、話を戻して、本日の議題は二つあると思います。ひとつは説明会の反省ですが、もうひとつはCSR報告書にISO認証返上を入れたこと、更に認証返上がどう受け取られたの総括です。
そこから行きませんか?」
![]() 「では認証返上を報告書に入れたことからいきましょう。
「では認証返上を報告書に入れたことからいきましょう。
広報部は大成功だった考えています。部長は他社も含めてCSR報告書は年度が違っても数字しか変わってないという評判を払拭したと喜んでいました。
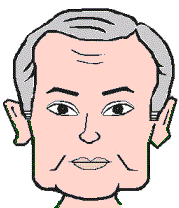 |
  |
  |
 |  |
しかし時代が違うせいか、ウチの若手はISO認証そのものをアプリオリに感じていて、返上の意味を理解してませんでしたね。
それでも説明会のあとに不参加だったマスコミから取材の依頼がいくつもあって、認証返上は大きな出来事だと認識したようです」
![]() 「実は私も、認証返上がネガティブな評価がされると懸念してたのですが、田村さんの説明のおかげで最終的に好意的な反応でうれしかったです」
「実は私も、認証返上がネガティブな評価がされると懸念してたのですが、田村さんの説明のおかげで最終的に好意的な反応でうれしかったです」
![]() 「ええと名前は忘れたが大学院生が最初TBT協定なんて言い出して、何を言ってるのかと思いましたよ。企業の本質と言うか、目的を分かってないんじゃないかな」
「ええと名前は忘れたが大学院生が最初TBT協定なんて言い出して、何を言ってるのかと思いましたよ。企業の本質と言うか、目的を分かってないんじゃないかな」
![]() 「2年ほど前、環境管理課のメンバーがISO認証について議論したことをまとめて『ISO認証の問題についての考察』という論文を当社の技報に載せたのです
「2年ほど前、環境管理課のメンバーがISO認証について議論したことをまとめて『ISO認証の問題についての考察』という論文を当社の技報に載せたのです
技報は市販していますから、同業他社や大学では定期購読してます。それを読んだ彼女のいる○○大学から、認証返上について講演を依頼されたことがあります」
![]() 「ほう、なるほど、」
「ほう、なるほど、」
![]() 「説明会の質問者は……清野さんと言いましたね……そのとき修士課程でした。今回は博士課程と自己紹介してましたね。彼女は勤め先のH電気でISO事務局をしていましたね。
「説明会の質問者は……清野さんと言いましたね……そのとき修士課程でした。今回は博士課程と自己紹介してましたね。彼女は勤め先のH電気でISO事務局をしていましたね。
ともかく彼女は会社でISO事務局所属らしく、大変認証制度に関心があるようです」
![]() 「なるほど、そうでしたか。それで彼女が報告会に来たわけですね。
「なるほど、そうでしたか。それで彼女が報告会に来たわけですね。
しかし単なる学生ならともかく、仕事をしているならISO認証と実務のプライオリティを分かってないとは、いささか心配だな」
![]() 「H電気は大会社だから、そういう人も生きていけるのよ」
「H電気は大会社だから、そういう人も生きていけるのよ」
![]() 「大会社に限らず、ISO事務局をしている人はそういう病に罹りやすいのです」
「大会社に限らず、ISO事務局をしている人はそういう病に罹りやすいのです」
![]() 「病か、アハハハ、ところでそのISO事務局とは何かね?」
「病か、アハハハ、ところでそのISO事務局とは何かね?」
![]() 「ISO認証とは私にとって、例えば排ガス測定を自社ではできないから測定会社に頼むような、一時的に外注する単純な仕事のイメージです。
「ISO認証とは私にとって、例えば排ガス測定を自社ではできないから測定会社に頼むような、一時的に外注する単純な仕事のイメージです。
ところが多くの企業では、ISO認証をきわめて重要で困難なお仕事と考えていて、そのための部署を設けたり専任者を置いたりするところが多いのです。
なにしろISO認証とは、会社を良くするためのものらしいですから(笑)
ISO課というのはあまり聞きません。多くはISO事務局とか称していますね。我が社でも工場がISO認証していた時期は、多くの工場でISO事務局がありました
注:「専任」という言葉を使ったが、分野によっては定義が決まっているそうだ。
医療業務では「専従」とは「8割以上」、「専任」は「5割以上」その業務に従事している者。労働組合の場合は「専任」はなく、「専従」は会社の仕事をしないことだ。
国語辞典で「専任」は「かけもちでなく、その仕事だけすること」だから、まあ許してほしい。
![]() 「ISO事務局の人たちは、自分たちが会社を良くするとか社員を指導すると誇り高く、まあわけの分からない理屈をこねていましたね。彼らの理屈は高尚すぎて、常人には理解できませんでした。
「ISO事務局の人たちは、自分たちが会社を良くするとか社員を指導すると誇り高く、まあわけの分からない理屈をこねていましたね。彼らの理屈は高尚すぎて、常人には理解できませんでした。
もっとも我が社では、私がISO事務局を全部なくしちゃいましたけど」
田村さんは目を白黒させている。磯原が語るISO認証企業や審査の実態を知らないからだろう。
![]() 「ハハハ、田村さんはご存じないかもしれませんが、磯原さんは有無を言わさぬ
「ハハハ、田村さんはご存じないかもしれませんが、磯原さんは有無を言わさぬ
ISO認証を止めてしまったとき、事務局だった人たちが気楽な仕事からまっとうな仕事に移ったから、だいぶ恨まれたでしょうけど」
![]() 「今回は小林部長に恨まれたようです。工場のISO事務局は私の査定をしませんが、小林部長は第一査定者ですから、真面目な話、今年の夏のボーナスは厳しいでしょうね」
「今回は小林部長に恨まれたようです。工場のISO事務局は私の査定をしませんが、小林部長は第一査定者ですから、真面目な話、今年の夏のボーナスは厳しいでしょうね」
![]() 「磯原さん、現状認識が甘すぎですよ。査定が悪いどころか、噂では10月の人事異動で磯原さんはどこかに飛ばされるようです」
「磯原さん、現状認識が甘すぎですよ。査定が悪いどころか、噂では10月の人事異動で磯原さんはどこかに飛ばされるようです」
![]() 「なにかあるとは思ってましたけど、そんな噂ですか。志半ばで斃れるのはいささか無念ですね」
「なにかあるとは思ってましたけど、そんな噂ですか。志半ばで斃れるのはいささか無念ですね」
![]() 「安心してくれ、君は本部長室兼務だから簡単にはいかないよ」
「安心してくれ、君は本部長室兼務だから簡単にはいかないよ」
![]() 「そう言えば、説明会のとき大分前に執行役だった三ツ谷さんが来ていたわ。年配の人に聞いたら小林部長が入社したときの課長だったそうです。説明会の後、小林部長とお話していましたね。
「そう言えば、説明会のとき大分前に執行役だった三ツ谷さんが来ていたわ。年配の人に聞いたら小林部長が入社したときの課長だったそうです。説明会の後、小林部長とお話していましたね。
以前、三ツ谷さんがウチがISO認証返上したのを怒って、小林課長に認証を継続するよう指示していたとか聞きましたけど」
![]() 「説明会が終わってから三ツ谷さんが私のところに挨拶に来た。話をしたけどISO認証返上を決定したことを褒めていた。
「説明会が終わってから三ツ谷さんが私のところに挨拶に来た。話をしたけどISO認証返上を決定したことを褒めていた。
特に私が語った公害からISOまで四半世紀、ISOから現在まで四半世紀経ったと聞いて、ISOを脱却するのは当然だと賛同を示していたね」
![]() 「へえ〜、すると三ツ谷さんがISO認証返上に気を悪くしていたというのは、どういうことかしら?」
「へえ〜、すると三ツ谷さんがISO認証返上に気を悪くしていたというのは、どういうことかしら?」
![]() 「そんな雰囲気はなかったね」
「そんな雰囲気はなかったね」
![]() 「三ツ谷さんとはどんな方なのですか?」
「三ツ谷さんとはどんな方なのですか?」
![]() 「私が入社したときの環境部長で、その後 執行役になった方よ。
「私が入社したときの環境部長で、その後 執行役になった方よ。
当時はISO14001が制定されて、我が社で認証の旗を振っていた。その後いっときですが、ISO認証機関の品質環境センターの社長もしていたはず。我が社の執行役兼務で非常勤でしたけど」
![]() 「なるほどイメージはつかめました。ご本人が言ったかどうかはともかく、経歴からは認証返上を許さんと言っても納得できます。
「なるほどイメージはつかめました。ご本人が言ったかどうかはともかく、経歴からは認証返上を許さんと言っても納得できます。
とはいえ田村さんがご本人と話されてそうでないとおっしゃるなら……」
![]() 「最近、有名人の写真を無断使用して、投資詐欺の宣伝に使ったというニュースがあったね。同じように、有名な人とか偉い人が言ったなんてのは、デマが多いから信用しちゃいけない。ひょっとして小林部長はデマを信じてピエロを演じたのかな」
「最近、有名人の写真を無断使用して、投資詐欺の宣伝に使ったというニュースがあったね。同じように、有名な人とか偉い人が言ったなんてのは、デマが多いから信用しちゃいけない。ひょっとして小林部長はデマを信じてピエロを演じたのかな」
なにか皆さん説明会が成功して気が抜けたからか、真面目な議論をしませんね。
・
・
・
・
![]() 「説明会の結果しなければならないこともいろいろあるだろう。これからの予定は?」
「説明会の結果しなければならないこともいろいろあるだろう。これからの予定は?」
![]() 「CSR報告書に載せた『卒ISO』を簡単に説明するものを作ってTVCMを打つつもりです。
「CSR報告書に載せた『卒ISO』を簡単に説明するものを作ってTVCMを打つつもりです。
せっかくマスコミが関心を持ってくれたのですから、有効に使わないと」
![]() 「認証不要と言い切ると、認証制度側から苦情とか、公に反論とかありませんかね」
「認証不要と言い切ると、認証制度側から苦情とか、公に反論とかありませんかね」
![]() 「『卒ISO』でなく独自のEMSであるとしましょうか。そうすればイチャモンつかないでしょう」
「『卒ISO』でなく独自のEMSであるとしましょうか。そうすればイチャモンつかないでしょう」
![]() 「K〇Sも初期はISOに似た名称でイチャモンがあったと聞きます。ISOが付かなければ大丈夫でしょう」
「K〇Sも初期はISOに似た名称でイチャモンがあったと聞きます。ISOが付かなければ大丈夫でしょう」
![]() 「先ほど広瀬課長が言った、説明会に来なかったマスコミの取材対応もあるのでしょう」
「先ほど広瀬課長が言った、説明会に来なかったマスコミの取材対応もあるのでしょう」
![]() 「そうそう、先ほどは田村さんがつれないこと語っていましたけど、インタビューには田村さんと磯原さんが必須ですからね」
「そうそう、先ほどは田村さんがつれないこと語っていましたけど、インタビューには田村さんと磯原さんが必須ですからね」
![]() 「具体的なことはともかく、一般論としてどんなスタンスで対応すべきですか?」
「具体的なことはともかく、一般論としてどんなスタンスで対応すべきですか?」
![]() 「現状認識ですが……環境優良企業と言われている会社は、ISO登場前から環境優良企業と言われていました。そしてISO認証したことで環境優良企業になったという話は聞いたことがありません」
「現状認識ですが……環境優良企業と言われている会社は、ISO登場前から環境優良企業と言われていました。そしてISO認証したことで環境優良企業になったという話は聞いたことがありません」
![]() 「なになに、それはまた聞き捨てなりませんね」
「なになに、それはまた聞き捨てなりませんね」
![]() 「そして環境優良企業と言われる会社の多くは、過去に公害や土壌汚染を起こしたりしているのが多い。そうでなくても、同業者あるいは近隣にそういう事故を起こした企業があるケースですね。
「そして環境優良企業と言われる会社の多くは、過去に公害や土壌汚染を起こしたりしているのが多い。そうでなくても、同業者あるいは近隣にそういう事故を起こした企業があるケースですね。
つまり環境優良企業と言うのは、環境事故が重大問題だと他より早く認識していたのです。自らが問題を深く理解しているから、その反省の上に環境配慮をしているのだと思います」
![]() 「事故を起こさないと環境優良企業になれないの?」
「事故を起こさないと環境優良企業になれないの?」
![]() 「事故は必須ではありません。耳を澄まして環境事故の情報を早めにキャッチし、事故の原因やその対応をしたのかを調査する、そして己はミスをしないように努めることです。
「事故は必須ではありません。耳を澄まして環境事故の情報を早めにキャッチし、事故の原因やその対応をしたのかを調査する、そして己はミスをしないように努めることです。
IT企業はどこも土壌汚染に関して脛に傷を持っています。だからこそ環境配慮をしているし、購入する部品についても含有化学物質だけでなく、製造過程でどのような化学物質を使うかまで調査していたのです」
![]() 「有機塩素系と揮発系だな、ハイテク公害とかIT公害と呼ばれた」
「有機塩素系と揮発系だな、ハイテク公害とかIT公害と呼ばれた」
![]() 「そうです。シリコンバレーでは1980年頃から問題になりました。つまり今、環境優良企業と呼ばれる企業は1980年代から対応してきたわけです。
「そうです。シリコンバレーでは1980年頃から問題になりました。つまり今、環境優良企業と呼ばれる企業は1980年代から対応してきたわけです。
失敗は誰にでもある。しかしその失敗を二度としない決意と実行が肝で、徹底できた企業が環境優良企業と言われるのです」
![]() 「なるほどなるほど、でも事故を起こさなくても環境優良企業にはなれるでしょう」
「なるほどなるほど、でも事故を起こさなくても環境優良企業にはなれるでしょう」
![]() 「現実には我が社も含めてほとんどの会社が、土壌汚染、地下水汚染を起こしています。しかし問題を起こしても、すべてがしっかりと是正をするわけじゃありません。そういうことを公にして再発防止に努めた企業が、環境優良企業となったのです」
「現実には我が社も含めてほとんどの会社が、土壌汚染、地下水汚染を起こしています。しかし問題を起こしても、すべてがしっかりと是正をするわけじゃありません。そういうことを公にして再発防止に努めた企業が、環境優良企業となったのです」
注:土壌汚染や地下水汚染の多くは、法規制ができる前に起きている。法規制前の汚染は違法ではない。また汚染が工場敷地外まで広がっていない、あるいは土地は売却しければ除染は義務でもない。
だから地下水汚染があっても手を打っていないところは多々ある。
ところでISO14001認証が始まってすぐに、過去に土壌汚染や地下水汚染を起こしていることが判明した認証組織を認証停止とか取り消しするのが多発した
何を論じても私は認証無価値論者らしい。
![]() 「多くの企業は土壌汚染、地下水汚染を起こしても、環境法規制を犯しても、しっかり是正しないから環境優良企業ではないということだな。
「多くの企業は土壌汚染、地下水汚染を起こしても、環境法規制を犯しても、しっかり是正しないから環境優良企業ではないということだな。
なんだっけかな? 悪いことをしたら、それを広報してしっかりと是正したほうが、評価が高くなるという法則があったようだが」
![]() 「劇場版ジャイアン効果
「劇場版ジャイアン効果
翌週である。環境管理課の定例会議だ。
このところ重大事件は起きていない。年々歳々、事故や違反が減っているのは事実だ。
それを磯原の活躍のおかげとは言わない。過去よりここで働いた佐久間さん、田中さん、坂本さんたちの活躍、そして山内さんの采配の賜物だと磯原は思う。彼らはスラッシュ電機の環境管理の中興の祖であり最高のメンバーだった。
いや現時点のメンバーを常に歴代最高のメンバーとしなければならない。常に今を過去最高に維持するのが、自分の使命だと身を引き締める。
![]() 「先週は当社のCSR報告書の説明会がありました。このメンバーで聴講された方はいなかったですね。柳田さんはサクラ集めご苦労様でした」
「先週は当社のCSR報告書の説明会がありました。このメンバーで聴講された方はいなかったですね。柳田さんはサクラ集めご苦労様でした」
![]() 「今はもう環境報告書/CSR報告書なんてニュースにならず、マスコミは取材に来ないんだろうね」
「今はもう環境報告書/CSR報告書なんてニュースにならず、マスコミは取材に来ないんだろうね」
![]() 「そうなのよ、社内でも面白いイベントなら行くって人が多いけど、報告書の説明会なんて眠くなるだけですもん。
「そうなのよ、社内でも面白いイベントなら行くって人が多いけど、報告書の説明会なんて眠くなるだけですもん。
ウチの課の皆さんに声をかけたけど、誰も出てくれなかったわ。
磯原さん、ロジスティックス部の落合さんと品質保証部の松尾さんが出てくれたから、お礼を言っておいてくださいね」
![]() 「分かりました。この会議が終わったら、先方の部長とご本人にお礼を言っておきます。
「分かりました。この会議が終わったら、先方の部長とご本人にお礼を言っておきます。
 環境管理課はCSR報告書と関わっていますから、次回からは聴講するようにしてください。
環境管理課はCSR報告書と関わっていますから、次回からは聴講するようにしてください。
宇佐美さんなんてためになると思いますよ。それに他部門の人と知り合う機会ですしね」
![]() 「柳田さんから声をかけられましたが、私のようなものが行って良いものか迷いました」
「柳田さんから声をかけられましたが、私のようなものが行って良いものか迷いました」
![]() 「私も外部の方のための報告会に社員が行ってはまずいかなと躊躇しまして…」
「私も外部の方のための報告会に社員が行ってはまずいかなと躊躇しまして…」
![]() 「本来は社外の人に向けての説明会なのですが、案内を出したマスコミも学生も来ないのですよ。それでサクラです、サクラ。枯れ木も山の賑わいってやつよ」
「本来は社外の人に向けての説明会なのですが、案内を出したマスコミも学生も来ないのですよ。それでサクラです、サクラ。枯れ木も山の賑わいってやつよ」
![]() 「枯れ木でも良いなら私のお仕事だな」
「枯れ木でも良いなら私のお仕事だな」
![]() 「今年のCSR報告書では我が社がISO認証を返上したことをとりあげましたので、報告会ではその経緯の説明がメインでした。
「今年のCSR報告書では我が社がISO認証を返上したことをとりあげましたので、報告会ではその経緯の説明がメインでした。
マスコミは1社しか来なかったですが、それでも学生とか雑誌社の方から、いろいろ質問が出て盛り上がりました」
![]() 「反響はどうでした? 肯定的なのか否定的か?」
「反響はどうでした? 肯定的なのか否定的か?」
![]() 「質問は否定的な感じで始まったのですが、田村さんが経緯を説明して最終的には認証返上したことを好意的に受け止めてくれたと思います。
「質問は否定的な感じで始まったのですが、田村さんが経緯を説明して最終的には認証返上したことを好意的に受け止めてくれたと思います。
広報部の話では、報告会に来なかったマスコミが噂を聞いて、今後取材に期待と連絡があったとのことです」
![]() 「ISO認証を続けるのと返上するのと何が違うのですか」
「ISO認証を続けるのと返上するのと何が違うのですか」
![]() 「今の人は認証とは何かを知らんのだね。
「今の人は認証とは何かを知らんのだね。
磯原君、これから環境管理を担当する新人には、ISO認証とはいかなるものかを教育する必要があるぞ。あと10年もして、全く知らない人たちにISO認証すると問題が解決するなんてカルトが流行るといけない」
![]() 「アハハハ、ISOがカルトとは良かった」
「アハハハ、ISOがカルトとは良かった」
![]() 「いやいや、案外そうかもしれんよ」
「いやいや、案外そうかもしれんよ」
注:カルトとは元々は「崇拝」「礼拝」を意味し、学術用語としてカリスマ的指導者を中心とする小規模で熱狂的な会員の集まりをいう。
日常語としては「特定の人や物に対する見当違いの過剰な称賛(Definitions from Oxford Languages)」を意味する。
![]() 本日の憤り
本日の憤り
会社で生きていくには、特許を取る、売上を上げる、生産性を上げる、安く作る、といった仕事の成果より、一緒に飲む、ゴルフに行く、カラオケに行くという人間関係というかコミュニケーションが重要なようです。
「課長島耕作」なんて、社内政治だけで昇進していく古臭く恥ずかしい話です。
ISO認証でも、2000年代には、審査を円滑に進めるには審査員と良好(?)なコミュニケーションをとりなさいとか、ISO事務局が社内で言ってもダメなら、審査員に不適合を出してもらいなさいと審査員が書いた本がありました。
自ら改めることができないで外力を頼るとは、恥ずかしくないのか? 何よりも会社のシステムを無視する行為は、ISO規格と相いれない!
そんなことを勧めるのがISO審査なのか?
そんなバカどもがISO認証を貶めたんだ。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
ISO14001認証が始まってから、法違反でない土壌汚染や地下水汚染でISO認証が停止とか取り消しになった事例は数多ある。 1998 M電器の地下水汚染 2001 A社の地下水汚染 2001 Nガラスの地下水汚染 2001 C社の地下水汚染 2002 F電工の土壌汚染 その他多数 | |
注2 |
「劇場版ジャイアン効果」とは、テレビの「どらえもん」では悪役ばかりしているジャイアンが、映画では友情に厚く頼れる力持ちを演じるので、その格差からとても立派に見えること。 ほぼ同じ意味でハロ(halo・後光)効果とも言われる。 仏像などを後ろから光を当てると、一層厳かに見えることかららしい。 | |
注3 |
「ゲイン・ロス効果」とは一貫して評価されるよりも、評価が逆転したほうが人に与える影響が大きいというれっきとした学説である。 悪い人が良く見えることがゲイン効果、良い人が一転悪く見えるのがロス効果という。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |