*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
社会人大学院生の清野が、スラッシュ電機のISO認証返上についてヒアリングに来た。早速質問が始まったが、清野がISO認証を研究していると言いながら、あまりにもISO認証の仕組みや実情を知らないので一旦終わることになった。再開はないだろうけど。
だがまだ1時間も経っていない。田村がせっかく来たのだから、少し話をしましょうという。磯原は、早く帰ってもらえばよいのに余計なことを……と思ったが、もちろん口には出せない。
広瀬課長はそれじゃ失礼しますねと、素早く消えてしまった。あの人は調子が良い。田村さん一人にはしておけない。磯原は残るしかない。
![]() 「お時間ありがとうございます。右も左も知らない私です。よろしくご教示願います。
「お時間ありがとうございます。右も左も知らない私です。よろしくご教示願います。
早速ですがISO認証制度の存在意義は何ですか教えてください」
![]() 「ISO認証の効用と存在意義は別ものでしょうね。実際に意味がなくても、世間がすばらしいと言えば価値がある。使用価値と交換価値かな。
「ISO認証の効用と存在意義は別ものでしょうね。実際に意味がなくても、世間がすばらしいと言えば価値がある。使用価値と交換価値かな。
新設の文芸の賞は、出す団体じゃなくてもらう人によって価値が決まる」
![]() 「田村さん、口をはさんでよいですか?」
「田村さん、口をはさんでよいですか?」
![]() 「いいとも、どうせ雑談だ」
「いいとも、どうせ雑談だ」
![]()
 「経済関連の賞が作られると、第一回は必ずトヨタに与えると言われます。そして本当は賞を与えるのではなく、賞を受け取ってもらうことで新設の賞の価値を上げると言われます」
「経済関連の賞が作られると、第一回は必ずトヨタに与えると言われます。そして本当は賞を与えるのではなく、賞を受け取ってもらうことで新設の賞の価値を上げると言われます」
![]() 「確かにそういう話を聞くね。新設のスポーツ大会でも有名選手に参加してもらうと、レベルの高い競技会とみなされる、となると文芸に限らずなにごとでも同じか」
「確かにそういう話を聞くね。新設のスポーツ大会でも有名選手に参加してもらうと、レベルの高い競技会とみなされる、となると文芸に限らずなにごとでも同じか」
![]() 「ええと……それがどういう関係があるのですか?」
「ええと……それがどういう関係があるのですか?」
![]() 「関係があるのか・ないのか、そこは人の受け取り方次第ですね。ISO認証ではどうですかね?」
「関係があるのか・ないのか、そこは人の受け取り方次第ですね。ISO認証ではどうですかね?」
![]() 「ああ、ISO認証の比喩ですか? 確かにISO認証をしたのはQMSでもEMSでも、当初は大企業、有名企業でした
「ああ、ISO認証の比喩ですか? 確かにISO認証をしたのはQMSでもEMSでも、当初は大企業、有名企業でした
認証企業はみな大企業、有名企業だから、認証すれば大企業になれる有名企業になれると思ったということでしょうか?」
![]()
 |  |
![]() 「それは疑似相関とか見せかけの相関と呼ばれるものですね」
「それは疑似相関とか見せかけの相関と呼ばれるものですね」
![]() 「そうそう、無関係なものが関係ありそうに思えることもあるし、因果を逆に受け取ることもある。猛暑の年はアイスクリームが売れるというが、アイスクリームが売れても猛暑にはならない」
「そうそう、無関係なものが関係ありそうに思えることもあるし、因果を逆に受け取ることもある。猛暑の年はアイスクリームが売れるというが、アイスクリームが売れても猛暑にはならない」
![]() 「なるほど、私のように事実関係を知らない人は、周りの人が言うことがそれなりだとそれを真実と思ってしまうのですね」
「なるほど、私のように事実関係を知らない人は、周りの人が言うことがそれなりだとそれを真実と思ってしまうのですね」
![]() 「そう卑下することはない。物理の原理と違い、ISO認証のような人間が作った仕組みは解釈次第ということもあるからね、何ごとも一概には言えないよ」
「そう卑下することはない。物理の原理と違い、ISO認証のような人間が作った仕組みは解釈次第ということもあるからね、何ごとも一概には言えないよ」
・
・
・
・
![]() 「御社ではISO審査によって悪影響があったという話がありましたね。具体的にはどんな問題がありましたか。話してよろしければお聞かせください」
「御社ではISO審査によって悪影響があったという話がありましたね。具体的にはどんな問題がありましたか。話してよろしければお聞かせください」
![]() 「私が環境に来る前の話だね。磯原君、どんなことがありましたか?」
「私が環境に来る前の話だね。磯原君、どんなことがありましたか?」
![]() 「問題があったというか、審査で問題を起こしてくれました。清野さんを信じて本当のところをお話ししましょう。
「問題があったというか、審査で問題を起こしてくれました。清野さんを信じて本当のところをお話ししましょう。
例えば環境目標です。弊社はISO認証のために、省エネをしているわけではありません。まず費用削減が目的ですし、法規制もあります。だから省エネをするわけです。
省エネ法では使用エネルギーが大きな事業所や企業は省エネ義務があり、数値も決められています。法では1%です。更に業界団体でも削減目標を立てています。弊社が加盟している団体では1.5%です。
ところで省エネというのは根性とかファイトで、できるものではありません」
![]() 「でも社員の意識向上とか注意すればできることもあるでしょう」
「でも社員の意識向上とか注意すればできることもあるでしょう」
![]() 「うーん、そう語る人が多いですね。企業とは……いや科学的管理法
「うーん、そう語る人が多いですね。企業とは……いや科学的管理法
![]() 「まあ、御社ではそんなにがんじがらめに管理しているの!」
「まあ、御社ではそんなにがんじがらめに管理しているの!」
![]() 「じゃあ、御社はこの仕事をやってくれ。方法は自分で考えろというのですか?
「じゃあ、御社はこの仕事をやってくれ。方法は自分で考えろというのですか?
そんな方法で仕事している会社は今どきありませんよ。御社では標準作業や標準時間
あのね、清野さん、設備も基準も何も変えずに、省エネしろと言ったら、パワハラどころか労働基準法違反ですよ。分かりますか?
清野さんはISO事務局というから、
![]() 「工場ではことごとく標準作業を決めているが、オフィスで業務の手順を明確にしているのは下位の業務だけだろうな」
「工場ではことごとく標準作業を決めているが、オフィスで業務の手順を明確にしているのは下位の業務だけだろうな」
![]() 「ええと、省エネや廃棄物などについての標準作業は、事務作業においてもマニュアルは整備されています。特に省エネについていえばビル管理会社が、照度基準や消灯基準を決めています。照明のON/OFF基準、空調の操作や設定はルールがあり、原則としてルールからの逸脱は認めません。もちろん最低限は法規制があります
「ええと、省エネや廃棄物などについての標準作業は、事務作業においてもマニュアルは整備されています。特に省エネについていえばビル管理会社が、照度基準や消灯基準を決めています。照明のON/OFF基準、空調の操作や設定はルールがあり、原則としてルールからの逸脱は認めません。もちろん最低限は法規制があります
もしルールを見直したほうが良ければ、新しいルールを決めてそれを遵守することになります。ここまでよろしいですか?」
![]() 「それはそうですが、工夫するとか努力するという余地はないのかしら?」
「それはそうですが、工夫するとか努力するという余地はないのかしら?」
![]() 「その場合はルールを見直すことになります。もちろん改定前に試行するでしょう」
「その場合はルールを見直すことになります。もちろん改定前に試行するでしょう」
![]() 「そういうがんじがらめでないとダメなのですか?」
「そういうがんじがらめでないとダメなのですか?」
![]() 「あることを成す方法がいくつか考えられるとき、一番良い方法、つまり安全に、品質が良く、速くなどの観点で、最善の方法を選ぶことはセオリーです。
「あることを成す方法がいくつか考えられるとき、一番良い方法、つまり安全に、品質が良く、速くなどの観点で、最善の方法を選ぶことはセオリーです。
例えば観光バスがA地点からB地点まで行くとしましょう。マイカーでの観光なら、ルートは気分次第だろうし、お子さんがぐずれば臨機応変にお土産屋に寄ったりする。

でも安全第一で乗り心地重視、更にタイムスケジュールが決まっている観光バスはそうはいかない。標準の運航ルートは決めてあるはずで、運転手が変わってもルートは同じです。
もちろん環境条件によって変わります。例えば道路工事、交通事故、渋滞など環境条件が変われば、次善のルートを選ぶことになる。
これを命令とか強制と受け取るかもしれないけど、責任の所在をはっきりさせ労働者を保護することでもある」
![]() 「磯原君の話を聞くとまさに…なんだね…ものすごく考えているのがわかる。そして君はそれを分かりやすく説明することにたけている。感心する」
「磯原君の話を聞くとまさに…なんだね…ものすごく考えているのがわかる。そして君はそれを分かりやすく説明することにたけている。感心する」
![]() 「お褒めいただき、ありがとうございます。私が口だけでなく実行できていれば、さらに良いのですが」
「お褒めいただき、ありがとうございます。私が口だけでなく実行できていれば、さらに良いのですが」
![]() 「磯原さん、おっしゃることが分かりました。私の理解が足りませんでした」
「磯原さん、おっしゃることが分かりました。私の理解が足りませんでした」
![]() 「それは良かった。では次に進みますね。
「それは良かった。では次に進みますね。
省エネに限らず改善をするにはリソースが必要です。リソースというと『人、もの、金』を思い浮かべますが、それだけでなく時間や情報やアイデアもあります。
根性だけで、できるものではありません。
それともうひとつ困難さのご理解をいただきたい。省エネ1%とは1年分の改善です。これは大変困難なことです。
清野さんのお宅で年に使う電力量、電気代じゃありませんよ、kWhのことです。これを過去数年調べてみてください。よほどのことがなければ変化はありません。
親戚の人が泊まりに来たり新しい家電が増えれば多くなるし、旅行に行ったり省エネ家電に更新すれば減るでしょう。
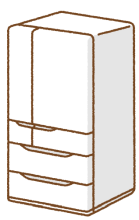 私の知識では、家電で最も大きな省エネを達成したのは、冷蔵庫ではないかと思います。冷蔵庫は1970年頃から広まりましたが、時とともに容積は大きくなりましたが消費電力は削減される一方です。特に冷蔵庫は24時間稼働ですから効果は大きいですね。
私の知識では、家電で最も大きな省エネを達成したのは、冷蔵庫ではないかと思います。冷蔵庫は1970年頃から広まりましたが、時とともに容積は大きくなりましたが消費電力は削減される一方です。特に冷蔵庫は24時間稼働ですから効果は大きいですね。
でも消費電力が1割減少した冷蔵庫に更新して15年間使うとして、年あたり0.7%の改善でしかありません。まして家庭で使う電力量の0.7%でなく、冷蔵庫の消費電力の0.7%です。
テレビもパソコンも液晶になったとき消費電力が50%も減ったそうです。耐用年数7年として、年7%削減です。でもそれ以降は液晶テレビから液晶テレビに更新しても省エネはできないでしょう
このように家庭で考えても、年1%削減というのはとても厳しいのです。家庭の電気使用量を毎年1%下げようとしてできると思いますか。
清野さんのご家庭で月どれくらい使っていますか?」
![]() 「我が家では両親と3人家族で、月350kWh
「我が家では両親と3人家族で、月350kWh
![]() 「1970年、私が子供の頃は家の電気使用量は120キロくらいだったなあ〜。あの頃の3倍か。あの頃に戻れば省エネはすぐに達成できそうだな」
「1970年、私が子供の頃は家の電気使用量は120キロくらいだったなあ〜。あの頃の3倍か。あの頃に戻れば省エネはすぐに達成できそうだな」
![]() 「豊かな生活をするために日本人は働いてきたんじゃないですか。それを否定したら社会が成り立ちません。
「豊かな生活をするために日本人は働いてきたんじゃないですか。それを否定したら社会が成り立ちません。
3人で350なら日本の平均です。じゃあそれを、来年は3.5kWh減らすアイデアがありますか?」
![]() 「例えば廊下とか外灯とか使用時以外点灯しない、用が済んだら速やかに消すとしたらどれくらい減りますかね?」
「例えば廊下とか外灯とか使用時以外点灯しない、用が済んだら速やかに消すとしたらどれくらい減りますかね?」
![]() 「廊下使っているのが白熱電球40W相当という電球型LEDランプとすると、消費電力は5Wくらいです。
「廊下使っているのが白熱電球40W相当という電球型LEDランプとすると、消費電力は5Wくらいです。
 外灯も似たようなものとして、毎日10分削減として月25Whですから350kWhの0.01%です。清野さんのお宅で使う電力の1万分の1ですね。1%どころか0.01%削減では全然足りません」
外灯も似たようなものとして、毎日10分削減として月25Whですから350kWhの0.01%です。清野さんのお宅で使う電力の1万分の1ですね。1%どころか0.01%削減では全然足りません」
![]() 「その前提条件だが、廊下や外灯を10分もつけているかね。我が家では帰宅したとき、玄関の外灯は人感センサーで3分くらいだし、廊下は玄関から居間まで歩く間だから1分も点けてないよ」
「その前提条件だが、廊下や外灯を10分もつけているかね。我が家では帰宅したとき、玄関の外灯は人感センサーで3分くらいだし、廊下は玄関から居間まで歩く間だから1分も点けてないよ」
![]() 「照明の節約ではたいしたことないですね。ではテレビを観る時間を減らします」
「照明の節約ではたいしたことないですね。ではテレビを観る時間を減らします」
![]() 「お宅のテレビは何インチでしょう?」
「お宅のテレビは何インチでしょう?」
![]() 「43インチだと思います」
「43インチだと思います」
![]() 「43インチですと4Kで110Wくらいですね。テレビだけで月3.5kWh減らそうとすると……毎日今までより1時間6分観る時間を減らせば可能ですね」
「43インチですと4Kで110Wくらいですね。テレビだけで月3.5kWh減らそうとすると……毎日今までより1時間6分観る時間を減らせば可能ですね」
![]() 「それじゃ、1%削減なんて楽勝じゃない?」
「それじゃ、1%削減なんて楽勝じゃない?」
![]() 「おいおい、テレビを観る時間が1時間も減って大丈夫かい?」
「おいおい、テレビを観る時間が1時間も減って大丈夫かい?」
![]() 「清野さんのお宅では、3年間はテレビを見るのを短くするだけで省エネできますね。でも今年の削減はできたとして、来年は今年より毎日テレビを見る時間を更に1時間6分短くしなければなりません。それができますか?
「清野さんのお宅では、3年間はテレビを見るのを短くするだけで省エネできますね。でも今年の削減はできたとして、来年は今年より毎日テレビを見る時間を更に1時間6分短くしなければなりません。それができますか?
日本の統計
![]() 「3年経ったらテレビが観られない。それは暮らしが変わるといってもよい。いやいや、見たいテレビを観なくなることを省エネといえるかね。たこ足配当ならぬたこ足節電だろう。
「3年経ったらテレビが観られない。それは暮らしが変わるといってもよい。いやいや、見たいテレビを観なくなることを省エネといえるかね。たこ足配当ならぬたこ足節電だろう。
それに4年目はどうするんだ」
![]() 「私もそう思います。そして3.5kWhの電気代は概ね月110円
「私もそう思います。そして3.5kWhの電気代は概ね月110円
清野さんのお宅で年間省エネ1%は、はっきり言って不可能じゃないかな?
分かってほしいのは、工夫とか注意する程度では省エネができないということです。
確実に省エネをするなら現状のままで節約するのではなく、建物の断熱改善、ライフスタイルを見直す、趣味を変えるなど必要でしょう」
![]() 「おっしゃることは分かりました。毎年1%削減は大変なことなのですね」
「おっしゃることは分かりました。毎年1%削減は大変なことなのですね」
![]() 「大変ですよ。もちろん省エネ法は、毎年一律に削減しろとは言っていません。設備更新した年に3%下がれば、その後2年間は減らなくてもOKです。
「大変ですよ。もちろん省エネ法は、毎年一律に削減しろとは言っていません。設備更新した年に3%下がれば、その後2年間は減らなくてもOKです。
とはいえ設備更新はただじゃありませんから、それを回収しなければなりません。電気代だけでは回収は難しいですよね。設備の耐用年数などを総合的に考えないと投資効率は出ません。まずは認許のハンコがもらえませんね」
![]() 「そのへんになると磯原君の恨み節に聞こえるなあ〜」
「そのへんになると磯原君の恨み節に聞こえるなあ〜」
![]() 「企業において省エネも大事ですが、新しいビジネスへの展開とか古い事業からの撤退など、経営全般を考えてお金を使いますからそれはしかたありません。
「企業において省エネも大事ですが、新しいビジネスへの展開とか古い事業からの撤退など、経営全般を考えてお金を使いますからそれはしかたありません。
それはともかく、私の言いたいことは年率1%削減というのは、ものすごく厳しいということです。さて努力とか意識付けという手段で、毎年1%の削減ができますか?」
![]() 「できません」
「できません」
![]() 「同意が得られたので、本題に入ります。
「同意が得られたので、本題に入ります。
これは弊社で実際にあったことです。
ISO審査で弊社の工場が年率1.5%削減の省エネ計画を出すと、審査員は目標が低すぎる。あとコンマ5上積みしなさいというのです。
そう言われて清野ISO事務局員は、どのように対応しますか?」
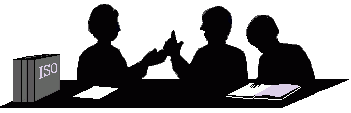
![]() 「元の計画がしっかりした根拠で策定されていたなら、それ以上は無理ですとしか言いようがありません」
「元の計画がしっかりした根拠で策定されていたなら、それ以上は無理ですとしか言いようがありません」
![]() 「でも審査員が目標値を上げないなら不適合にすると言えば?」
「でも審査員が目標値を上げないなら不適合にすると言えば?」
![]() 「そんなこと言うのかい?」
「そんなこと言うのかい?」
![]() 「その通りの発言はしていませんでした。ただ『このままでは審査を進められない』と語った録音があります」
「その通りの発言はしていませんでした。ただ『このままでは審査を進められない』と語った録音があります」
![]() 「まあ、お宅は審査の録音がOKなのですか?」
「まあ、お宅は審査の録音がOKなのですか?」

![]() 「今どきみんなスマホを持っているし、ボイスレコーダーもボールペンタイプとか腕時計とか、身分証のネックストラップタイプとかありますからね。ひょっとして誰かのレコーダーのスイッチが入ってしまったのでしょう」
「今どきみんなスマホを持っているし、ボイスレコーダーもボールペンタイプとか腕時計とか、身分証のネックストラップタイプとかありますからね。ひょっとして誰かのレコーダーのスイッチが入ってしまったのでしょう」
![]() 「事故ならしょうがないな」
「事故ならしょうがないな」
![]() 「あら、まあ、それで?」
「あら、まあ、それで?」
![]() 「結論を言えば、その工場は審査員に押し切られたのです。
「結論を言えば、その工場は審査員に押し切られたのです。
しかしそういうことはすぐばれます。弊社ではISO審査の結果を本社に報告することにしています。その報告と全社環境計画の実績報告、経済産業局への省エネ報告、これらを照らし合わせれば齟齬は見つかります」
![]() 「ほう〜、それでどうなりましたか?」
「ほう〜、それでどうなりましたか?」
![]() 「実はこの件は田村さんの前任者である山内さんと私が工場に乗り込みました(第8話)。調査したところ、ISO審査で省エネ計画を変更しただけでなく、不正な予算流用が発覚しました。結果としてものすごい処分になりました。
「実はこの件は田村さんの前任者である山内さんと私が工場に乗り込みました(第8話)。調査したところ、ISO審査で省エネ計画を変更しただけでなく、不正な予算流用が発覚しました。結果としてものすごい処分になりました。
外の人には言えないことですが、既に7年も経ちましたから……業務監査で見逃した執行役監査部長が辞任、工場長と部長が解任で関連会社に出向、関係者は減俸の処分になりました」
![]() 「あっ、それってあれか? 監査部長の件か」
「あっ、それってあれか? 監査部長の件か」
![]() 「もちろん社内だけでは済みません。認証機関に対して重大な違反
「もちろん社内だけでは済みません。認証機関に対して重大な違反
社内の処分のレベルに合わせたなら、認証機関を鞍替えすべきでしたね。当時はまだ対外的には甘い……いや弱気だったと反省します」
![]() 「いや十分にやったと思うぞ。もしどこかの工場でおかしなことがあると発覚して、私が担当したとして、それほど厳しいことができるかといえば、できないだろうね」
「いや十分にやったと思うぞ。もしどこかの工場でおかしなことがあると発覚して、私が担当したとして、それほど厳しいことができるかといえば、できないだろうね」
![]() 「この処分は大川専務主導で社長も入って決定されたことで、私のような下々は関わっていませんよ」
「この処分は大川専務主導で社長も入って決定されたことで、私のような下々は関わっていませんよ」
![]() 「まあ、そうだろうけど。ともかくウチがまっとうな会社だと知ってうれしいよ。
「まあ、そうだろうけど。ともかくウチがまっとうな会社だと知ってうれしいよ。
清野さん、お恥ずかしいところをお見せしました。口外しないでください」
![]() 「あっ、もちろんです。お約束します。
「あっ、もちろんです。お約束します。
しかしそれほど真剣に審査を受けていることに驚きました。私はその場を凌げばよいと思っていました」
![]() 「ISO審査を重要視しているというより、私どもは会社の仕事を重要視しているのです。
「ISO審査を重要視しているというより、私どもは会社の仕事を重要視しているのです。
ISO審査に高い金を払っているわけです。多少の審査ミスはあっても目をつぶります。しかし審査員好みに弊社の仕組みや目標をいじることは許しがたい行為です。審査を受ける企業は審査員のおもちゃではないのです。
真剣に検討して策定した弊社の環境計画を、何も知らない外部の者に目標が低いと言われることはありません。年1%削減目標がいかほどの困難かを知らずに、努力とか意識向上で上積みしろと言う審査員は、事前に拒否しないとなりませんね。
まあ、そんなわけで認証を止めたわけです。
おっと、方針に関しては意見を述べないように、それ以前から認証機関に申し入れてあります。経営者が決めた方針を、審査員風情に意見されたくありません。
外資系の老舗認証機関は、経営者の方針が徹底されているかを審査する。方針の内容は審査の外だと語っています。イギリスではそれが当たり前だそうです」
![]() 「すごい……磯原さんは私に対して厳しいことを言いますが、認証機関にも審査員にも厳しいのですね」
「すごい……磯原さんは私に対して厳しいことを言いますが、認証機関にも審査員にも厳しいのですね」
![]() 「誤解してほしくないのですが……私どもは無茶苦茶なことを言っているのではありません。
「誤解してほしくないのですが……私どもは無茶苦茶なことを言っているのではありません。
ISO17021以前はガイド66でしたが、それに基づいたしっかりした審査をしてほしいと言っているのです。不適合をOKしろと言っているのではありません。
実際に工場のISO審査で不適合を見逃した認証機関を呼んで、見逃さないようしっかり審査しろと要求したこともあります。
規格要求にない審査員特有とか認証機関独自の要求事項はお断り、法律はしっかり勉強してくること、親切心、改善提案などは無用だと言っているだけです」
・
・
・
・
![]() 「ISO関係者が話すのを聞いて、おかしいなと感じる言葉はたくさんあります。そういうことを耳にすると、この人はISO規格とかマネジメントシステムというものを、全く理解してないとしか思えません」
「ISO関係者が話すのを聞いて、おかしいなと感じる言葉はたくさんあります。そういうことを耳にすると、この人はISO規格とかマネジメントシステムというものを、全く理解してないとしか思えません」
![]() 「ほう、どんなことですか?」
「ほう、どんなことですか?」
![]() 「環境マネジメントシステムという言葉を、無造作に使う人が多すぎます。それもISOに無縁な人でなく、認証機関の社長とか雑誌などに登場するような人たちがです」
「環境マネジメントシステムという言葉を、無造作に使う人が多すぎます。それもISOに無縁な人でなく、認証機関の社長とか雑誌などに登場するような人たちがです」
![]() 「具体的にはどんなことでしょうか?」
「具体的にはどんなことでしょうか?」
![]() 「よく聞くのは『マネジメントシステムを構築する』とか『マネジメントシステムを導入する
「よく聞くのは『マネジメントシステムを構築する』とか『マネジメントシステムを導入する
![]() 「ええと……私もそういう言い方をしますよ」
「ええと……私もそういう言い方をしますよ」
![]() 「そうですか、それならぜひ教えてください。マネジメントシステムを構築するとは、どんなことでしょう?」
「そうですか、それならぜひ教えてください。マネジメントシステムを構築するとは、どんなことでしょう?」
![]() 「会社の仕組みがISO規格を満たすように見直すことかと思います」
「会社の仕組みがISO規格を満たすように見直すことかと思います」
![]() 「言葉の意味は、一般の人が共有する範囲で使うべきだと思います。またISO規格で定義されている語句は、その定義に基づいて使うのは当然です」
「言葉の意味は、一般の人が共有する範囲で使うべきだと思います。またISO規格で定義されている語句は、その定義に基づいて使うのは当然です」
![]() 「ですからマネジメントシステムを構築するというのは、おかしくないと思います」
「ですからマネジメントシステムを構築するというのは、おかしくないと思います」
![]() 「マネジメントシステムとは『方針、目的及びその目的を達成するためのプロセスを確立するための、相互に関連する又は相互に作用する、組織の一連の要素(ISO14001:2015 定義3.1.1)』とあります。
「マネジメントシステムとは『方針、目的及びその目的を達成するためのプロセスを確立するための、相互に関連する又は相互に作用する、組織の一連の要素(ISO14001:2015 定義3.1.1)』とあります。
およそ組織が存在すれば、その運営のためマネジメントシステムは自然発生します。もちろん多くの法人格を持たない組織のマネジメントシステムは、文書化されず不文律の場合も多いし、不完全なものも多い。しかしマネジメントシステムを持たない人の集まりは組織ではありません」
![]() 「ですが組織とは体制とかルールがあるものばかりではないかもしれません」
「ですが組織とは体制とかルールがあるものばかりではないかもしれません」
![]() 「それは組織の定義を外れます。国語辞典で組織とは『ある目的を目指し、幾つかの物とか何人かの人とかで形作られる、秩序のある全体』とありますし、英英辞典でorganizationとは『an organized body of people with a particular purpose, especially a business, society, association,(企業、社会、協会など、特定の目的を持つ組織化された人々の集団)』となります」
「それは組織の定義を外れます。国語辞典で組織とは『ある目的を目指し、幾つかの物とか何人かの人とかで形作られる、秩序のある全体』とありますし、英英辞典でorganizationとは『an organized body of people with a particular purpose, especially a business, society, association,(企業、社会、協会など、特定の目的を持つ組織化された人々の集団)』となります」
![]() 「なるほど、すべての組織はマネジメントシステムを持つから、マネジメントシステムを構築するというのは意味不明と……
「なるほど、すべての組織はマネジメントシステムを持つから、マネジメントシステムを構築するというのは意味不明と……
確かに昔、春闘なんて流行っていた時代は、組合本部から工場に、オルグなんてやってきたもんだ」
![]() 「オルグってなんですか?」
「オルグってなんですか?」
![]() 「多くの企業の労働組合はユニオンショップになっている。今の人はユニオンショップとかオープンショップなんて知らないかな?(クローズドショップは日本にはない)
「多くの企業の労働組合はユニオンショップになっている。今の人はユニオンショップとかオープンショップなんて知らないかな?(クローズドショップは日本にはない)
とにかく入社したら、労働組合に入らないとならないという労使の協定だ。
とはいえ組合員のほとんどは組合員の意識なんてない。春闘はテレビの中、自分たちは無縁と思っている人が多いだろう。
 だって組合と会社の交渉で決まるというより、経団連とかのレベルで方向は決まってしますからね。ハチマキしてこぶしを振り上げる気にはならない。
だって組合と会社の交渉で決まるというより、経団連とかのレベルで方向は決まってしますからね。ハチマキしてこぶしを振り上げる気にはならない。
そこで春闘に入る前に組合本部から工場や支社に出かけて行って、組合の要求の周知とか活動への参加意識付けをするイベントだね。アハハハ、誰もオルグなんて本気にしてなかったけど」
![]() 「なるほど、そうすると意識付けが薄い組織なら、システム構築をする必要があるということですか?」
「なるほど、そうすると意識付けが薄い組織なら、システム構築をする必要があるということですか?」
![]() 「いやいや、労働組合の組織体系はしっかりしているよ。組合は法律で定める仕組みを文書で定めないと法人格は認められない(労働組合法11条他)。
「いやいや、労働組合の組織体系はしっかりしているよ。組合は法律で定める仕組みを文書で定めないと法人格は認められない(労働組合法11条他)。
ただ組合員の意識が希薄だから、組合活動がアクティブになるときは全員参加を目指して周知徹底をするということだね。
システムを構築するとは、文書を作るとか組織体系を作ることでしょう。労働組合の組織はしかと存在しているわけで、オルグがシステム構築にあたるはずはない」
![]() 「正直言って難しいことを知らないと、話すこともできませんね」
「正直言って難しいことを知らないと、話すこともできませんね」
![]() 「そんなことはない。私はISO規格など無知だが、マネジメントシステムを構築すると聞くと、どうも変だなとは思ったよ。まさか新会社を作るわけじゃないでしょう。
「そんなことはない。私はISO規格など無知だが、マネジメントシステムを構築すると聞くと、どうも変だなとは思ったよ。まさか新会社を作るわけじゃないでしょう。
磯原君、『環境マネジメントシステムを導入する』というのもおかしいのか?」
![]() 「そもそもISO規格はシステムの形を決めているものではなく、システムが具備しなければならない要求事項を決めているだけです。ですからISO規格で定める環境マネジメントシステムは一様ではないというか、決まった形は存在しません。決まった形のないものを導入することはできません」
「そもそもISO規格はシステムの形を決めているものではなく、システムが具備しなければならない要求事項を決めているだけです。ですからISO規格で定める環境マネジメントシステムは一様ではないというか、決まった形は存在しません。決まった形のないものを導入することはできません」
![]() 「はあ〜、」
「はあ〜、」
・
・
・
・
![]() 「話をしているとどんどんさかのぼってしまうのですが……ISO認証に関わっている人はISO14001が最高というか唯一の環境マネジメントシステムと思っているようです」
「話をしているとどんどんさかのぼってしまうのですが……ISO認証に関わっている人はISO14001が最高というか唯一の環境マネジメントシステムと思っているようです」
![]() 「あらそうじゃないですか。簡易EMSは、ISO14001から要求事項をおろぬいたものと理解しています」
「あらそうじゃないですか。簡易EMSは、ISO14001から要求事項をおろぬいたものと理解しています」
![]() 「エコアクション21は環境報告書があったりするし、エコステージは改善活動の面もあるから、そうとばかりは言えないけど、確かに簡易EMSはISOより安易なものと見られていますね。
「エコアクション21は環境報告書があったりするし、エコステージは改善活動の面もあるから、そうとばかりは言えないけど、確かに簡易EMSはISOより安易なものと見られていますね。
でも世の中には環境マネジメントシステム規格と呼ばれるものはたくさんある。欧州ではEMAS
そしてISO発祥前からすべての企業は環境マネジメントシステムを備えていたわけだ。廃棄物の処理ルール、エネルギー管理のルールなど。
それは法律を守りその会社に見合ったシステムであり、その会社にとって最高のマネジメントシステムだったのではないでしょうか。
しかし現実を見れば、ISOに合わせて会社のルールを作るところは多いと思いますね。だからシステム構築という言葉を使う人が多いのかもしれない」
![]() 「御社では規格に合わせてルールを見直しましたのでしょう?」
「御社では規格に合わせてルールを見直しましたのでしょう?」
![]() 「私どもは基本的に社内規則を変えませんでした。従来からの会社規則が、ISO規格を満たしていることを説明したのです」
「私どもは基本的に社内規則を変えませんでした。従来からの会社規則が、ISO規格を満たしていることを説明したのです」
![]() 「なるほど、言っていることはよく分かる」
「なるほど、言っていることはよく分かる」
![]() 「そんなアプローチでよいのですか?」
「そんなアプローチでよいのですか?」
![]() 「今はなくなってしまいましたが、ISO14001の1996年版でも2004年版でも、序文に『既存のマネジメントシステムの要素を適応させることも可能である』という文言がありました。
「今はなくなってしまいましたが、ISO14001の1996年版でも2004年版でも、序文に『既存のマネジメントシステムの要素を適応させることも可能である』という文言がありました。
原文は『It is possible for an organization to adapt its existing management system in order to establish an environmental management system』です。
私は本来の趣旨は『この要求事項を組織のマネジメントシステムに組み込まなくてはならない』ではないかと考えるのです」
![]() 「磯原君の言っていることはよく分かる。ISO9001が登場する前から、B2Bでは品質保証協定を結ぶことは普通のことだった。客先の要求を満たすのに、会社規則で不足なときは従来の手順に必要なことを追加したのだ。
「磯原君の言っていることはよく分かる。ISO9001が登場する前から、B2Bでは品質保証協定を結ぶことは普通のことだった。客先の要求を満たすのに、会社規則で不足なときは従来の手順に必要なことを追加したのだ。
多くの会社がISO用の文書を作っているように、従来の文書とは別に〇〇社用の文書など作ったことはない。
ISO規格とか審査と言っても、客先より上位とか権限があるわけではない。現行で規格を満たしていることを説明するのが第一段階であり、客先が納得しないなら必要最小限を従来の手順に盛り込むだけだ」
 |
||
![]() 「はあ〜、お二人のお話を聞いてもピンときません」
「はあ〜、お二人のお話を聞いてもピンときません」
![]() 「じゃあ分かりやすいお話をしましょう。日本には半世紀も前から工場の環境管理をしっかりしなさいという法律があります。それを実践してくれればISO14001など不要だったのです」
「じゃあ分かりやすいお話をしましょう。日本には半世紀も前から工場の環境管理をしっかりしなさいという法律があります。それを実践してくれればISO14001など不要だったのです」
![]() 「はて、そんなしゃれたものがあったのかな?」
「はて、そんなしゃれたものがあったのかな?」
![]() 「公害防止防止組織法ですよ
「公害防止防止組織法ですよ
ISO14001をすばらしいなんて飛びつく前に、現実の法律をしっかり守って運用することが最優先であり有効であることは間違いありません」
![]() 「えっと、その法律は工場が対象で、オフィスとか学校には適用されませんね」
「えっと、その法律は工場が対象で、オフィスとか学校には適用されませんね」
![]() 「そうです。確かにデパートとか学校が対象外ですが、それは廃棄物処理法とか省エネ法で間に合うからですよ。いずれにしても日本の法律をひたすら守ることが最善のアプローチだと思いますね」
「そうです。確かにデパートとか学校が対象外ですが、それは廃棄物処理法とか省エネ法で間に合うからですよ。いずれにしても日本の法律をひたすら守ることが最善のアプローチだと思いますね」
![]() 「でもそれって省エネもないし、製品の環境規制も対象外よね」
「でもそれって省エネもないし、製品の環境規制も対象外よね」
![]() 「いえいえ、省エネ法には工場省エネとかビル省エネだけでなく、製品省エネもありますし、リサイクル法では回収・再資源化の決まりがある。スーパーのレジ袋規制のありますよ。消防法もあり毒劇物法もある。
「いえいえ、省エネ法には工場省エネとかビル省エネだけでなく、製品省エネもありますし、リサイクル法では回収・再資源化の決まりがある。スーパーのレジ袋規制のありますよ。消防法もあり毒劇物法もある。
法律は所管官庁がありますから、ひとまとめにならないのは仕方ありません。とはいえ環境基本法が最上位の法律ですから、体系としてはきれいにまとまっているのです。
総合的に見ればわざわざISO14001なんて手を出すことはなかったのです。
もちろん日本の場合ですよ。公害防止法が整備されていない国なら、ISO14001の存在意義があるのかもしれません。
ISO50001というのがありますね。エネルギーマネジメントの規格です。あんなものより省エネ法のほうがはるかに良くできています。法律で間に合うならISO規格は不要で認証も不要です。そのせいかどうかISO50001の認証件数は日本ではゼロですがね」
![]() 「そういう観点からもISO規格と認証の価値を、考えなければならないわけか」
「そういう観点からもISO規格と認証の価値を、考えなければならないわけか」
![]() 「ISO14001認証しようとどこでも苦労するのは、環境側面の決定と法規制の調査です。そんな無駄なことをするまでもなく、既に環境側面を知っているし、該当法規制も把握している会社が9割でしょう。環境側面を決めようと、パソコンを叩いて数字のつじつま合わせをするなんて、時間の無駄、電気代の無駄、働く意欲の喪失です。
「ISO14001認証しようとどこでも苦労するのは、環境側面の決定と法規制の調査です。そんな無駄なことをするまでもなく、既に環境側面を知っているし、該当法規制も把握している会社が9割でしょう。環境側面を決めようと、パソコンを叩いて数字のつじつま合わせをするなんて、時間の無駄、電気代の無駄、働く意欲の喪失です。
なぜ無駄なことをするのかといえば、審査員を納得させるためでしかありません。
そんな無駄なことより、実のある行動をすべきです。
ISO規格を作った人たちは、国内法が整備されていない国の人なのか、公害防止に関わったことがない人なのか、どうしようもないですね」
![]() 「ISO14001認証ブームは壮大な狂騒曲だったわけか」
「ISO14001認証ブームは壮大な狂騒曲だったわけか」
![]() 「経緯はともかく、振り返ってみればそうとしか思えません。
「経緯はともかく、振り返ってみればそうとしか思えません。
環境マネジメントシステムと呼ぶかどうかはともかく、日本の法律は環境管理体制を求めているわけです。法律を泥臭く守るという活動に、ひたすらまい進すれば良かったのです。私はそう思います」
・
・
・
・
![]() 「磯原さんはISO規格を一字一句しっかりと読んでいるのですね」
「磯原さんはISO規格を一字一句しっかりと読んでいるのですね」
![]() 「もちろんしっかりと読んでいるつもりです。それもJIS訳だけでなく英語原文も読んでいます。でも分からないことはいろいろあります」
「もちろんしっかりと読んでいるつもりです。それもJIS訳だけでなく英語原文も読んでいます。でも分からないことはいろいろあります」
![]() 「規格におかしいところでもあるのかい?」
「規格におかしいところでもあるのかい?」
![]() 「間違っているというか、納得できないことはありますね。
「間違っているというか、納得できないことはありますね。
例を挙げると序文に『環境マネジメントを組織の事業プロセス、戦略的な方向性及び意思決定に統合し』というフレーズがあります。英文も同じです。
これっておかしくないですか?」
![]() 「おかしくないかと問われても、私は全く分かりません」
「おかしくないかと問われても、私は全く分かりません」
![]() 「なんか定義と矛盾するような気がするね」
「なんか定義と矛盾するような気がするね」
![]() 「私もそう思います。定義では『環境マネジメントシステムはマネジメントシステムの一部(定義3.1.2)』だと定めています。
「私もそう思います。定義では『環境マネジメントシステムはマネジメントシステムの一部(定義3.1.2)』だと定めています。
では『環境マネジメントを事業プロセスに統合する』という発想は矛盾していませんか?」
![]() 「環境マネジメントと環境マネジメントシステムは対応するのだろうか?
「環境マネジメントと環境マネジメントシステムは対応するのだろうか?
また事業プロセスは組織のマネジメントシステムに含まれるのか?」
![]() 「ISO規格はドラフトを作った後、全世界に公開してレビューを求めます。
「ISO規格はドラフトを作った後、全世界に公開してレビューを求めます。
だから間違いがないとは思いますが、あの文章には納得できません。あそこばかりでもないですが」
![]() 「どうあれ虚心坦懐に、一休さんのどちて坊やのように考えるとおかしいね」
「どうあれ虚心坦懐に、一休さんのどちて坊やのように考えるとおかしいね」
![]() 「皆さんはISO規格の権威を認めず、認証の権威も認めないようですね」
「皆さんはISO規格の権威を認めず、認証の権威も認めないようですね」
![]() 「あのね、清野さん、法律でも条約でも、誤読されやすい文章を書くのが悪いのですよ。
「あのね、清野さん、法律でも条約でも、誤読されやすい文章を書くのが悪いのですよ。
日本では法律の解釈を決めるのは法律を作った国会ではなく、裁判所です。裁判官が理解したことが法の定めであるということです。
法律作成に関わった議員や官僚が『この文章の意図はそうじゃない』と言うならば、それはちゃんとした文章が書けなかった、己の力不足であるということ以外の何ものでもありません。
ISO規格も制定されたのちは、作成者の手を離れ一人歩きするのです。
法律でも規格でも、他人が読んでなんぼなのです」
![]() 「ISO規格だってたびたび改定されているわけで、崇め奉るようなものじゃないでしょう。『環境目標と目的がふたつないとダメだ』と講釈を騙っていたT審査員は2015年改定で目標だけになったとき反省したんでしょうか?
「ISO規格だってたびたび改定されているわけで、崇め奉るようなものじゃないでしょう。『環境目標と目的がふたつないとダメだ』と講釈を騙っていたT審査員は2015年改定で目標だけになったとき反省したんでしょうか?
私は責任を取れと言いたいですね。だって当時の規格を読み直しても、二つないとダメとは読めません。ISO9001とISO14001のobjectiveの意味が違うという発想もおかしいし…
それに当社とISOMS規格を比べれば、当社がなくなるよりISOMS規格が消滅するほうが早そうです。権威なんてありませんよ」
![]() 「うわー、それほどの自信をお持ちというわけね」
「うわー、それほどの自信をお持ちというわけね」
![]() 「自信じゃありません。現実の事業活動に携わっているからこそのスタンスです。
「自信じゃありません。現実の事業活動に携わっているからこそのスタンスです。
ハッキリ言って、ISO規格を優先するのか、経営上のことを優先するのかとなれば、ISO規格を切り捨てる一択です」
![]() 「まさしくその通りだ。私たちは、事業をしている。おままごとではない。
「まさしくその通りだ。私たちは、事業をしている。おままごとではない。
ちょっとした不注意とか見逃しで、大きな問題が起きるかもしれず、最悪倒産とか個人的には背任などの罪になるかもしれない。そうなるまいといろいろするのだが、力不足もあるし情報がなくて手が打てないこともある」
![]() 「だから審査員はル−ル通りの審査をして余計なことをしてもらいたくない。余計なことをしてくれるなと願うだけですよ。
「だから審査員はル−ル通りの審査をして余計なことをしてもらいたくない。余計なことをしてくれるなと願うだけですよ。
安易に計画を0.5%上積みしろなんて言ってほしくない。まずご自宅の電気使用量を金をかけず改善意欲と創意工夫で削減してからにしてほしい」
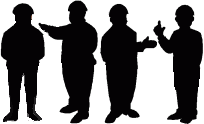
![]() 「しかしそんなことあれば、すぐに認証機関に異議申し立てすればいいじゃないか」
「しかしそんなことあれば、すぐに認証機関に異議申し立てすればいいじゃないか」
![]() 「今ならそうですね。でも21世紀初めまでは、審査員と会社側は対等じゃありませんでした。だから悲喜劇が多々起きたのですよ。
「今ならそうですね。でも21世紀初めまでは、審査員と会社側は対等じゃありませんでした。だから悲喜劇が多々起きたのですよ。
それに上司はかっこいいところを見せようと、審査員の無理なおねだりをハイハイと聞いてしまうのです。
山内さんも田村さんも、そういう腰抜けじゃなくて幸いです」
![]() 「はあ〜、皆さんと私ではISO以前に、仕事に向かう考え方、真剣さがまったく違うのですね。
「はあ〜、皆さんと私ではISO以前に、仕事に向かう考え方、真剣さがまったく違うのですね。
みなさんは事業を背負っている。私は単にISO審査という
ISO事務局なんて無用なお仕事だから気楽にいられるのでしょうか?」
・
・
・
・
話し合っていると、広報の広瀬課長がまた顔を出した。
![]() 「話が弾んでいるようね。あと30分くらいで終業時刻なの。
「話が弾んでいるようね。あと30分くらいで終業時刻なの。
 みなさん、この後、地下でちょっといかがですか? 清野さんもこれから会社に戻ってお仕事ってことはないでしょう?」
みなさん、この後、地下でちょっといかがですか? 清野さんもこれから会社に戻ってお仕事ってことはないでしょう?」
![]() 「おお、それはいいね。地下の居酒屋は、チェーン店でなく酒も肴もなかなかだよ」
「おお、それはいいね。地下の居酒屋は、チェーン店でなく酒も肴もなかなかだよ」
![]() 「はい、ありがたく」
「はい、ありがたく」
磯原は、心中考える。6時半頃まで付き合うか……それから机上を片付けてメールボックスを空にしてとなると、娘の顔は見られないな〜、やれやれと思うのである。
転勤してきたとき小学生だった娘も今は高校1年だ。最近は話をすることも少ない。夕食も一緒にするのは週末くらいだ。
ISOより会社、会社より家族だと磯原は思う。思っても思うようにはいかないのも浮世、
| 9歳のちなみ | 16歳のちなみ | |
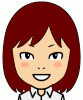 | 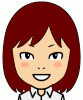 |
|
![]() 本日の主張
本日の主張
なぜこんなことをグダグダ書くのかって?
私は小説を書いているのではありません。ISO審査がいかなるものか、いかなる価値があるのか、そういうことを世に問いたいのです。
言いたいことは切りも限りもありませんが、ここらへんで「ポストISO編」を終えて次に進みましょう。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
ISO14001の登録順は1位から 東芝、日立、富士通、レゾナック(旧社名:日立化成)、パナソニック、富士電機、トヨタ、新日鉄、三菱電機、東芝メディカル、ルネサスエレクトロニクス(旧社名:ルネサステクノロジー)(全社でなく事業所1か所のものも含む) 優良大企業のそろい踏みであった。ISO14001はEUへの輸出とは無関係だから、その企業の環境イメージ増進のためだったのだろうか? | |
注2 |
科学的管理法とはアメリカのフレドリック・テイラーが20世紀初めに考案した、労働効率を上げるために労働者を管理する方法を言う。1960年頃日本でも広く取り入れるようになった。現代はそのままの形ではなく、業務の変化もあり活用の場において多様になっている。 日本に広めた上野陽一は「能率の父」と称され、彼が設立したのが産業能率大学である。 | |
注3 |
標準時ではない。標準時とは地球上の地域における時刻をいう。地域のことを等時帯といい、グリニッジ標準時より9時間進んだものとしている。 標準時間とは通常「工程管理における標準時間」をいい、「標準的な習熟度の作業者が標準の作業手順、方法、作業条件のもとで作業を行った場合の所要時間に、余裕を加えた時間」をいい、職場の時間管理の根拠とされる。 | |
注4 |
労働安全衛生法 事務所衛生基準規則 喚起、温度、照度、振動騒音、清潔などの基準が決めてある。 | |
注5 | ||
注6 | ||
注7 | ||
注8 |
基本料金とかあるからまったく電気を使わなくても電気代はただにはならない。また200Vとか深夜など契約条件によって一律には決まらない。 | |
注9 |
ISO17021に「不適合にするには証拠と根拠が必要」とあるから、これは明確に異議申し立ての対象となる。ISO審査においても罪刑法定主義と証拠裁判主義は正義である。 知る限り「審査員が目標が低いと考えれば不適合」なんて言うふざけたルールはない。 | |
注10 |
一例「ISOマネジメントシステムが一番わかる」日本品質保証機構、技術評論社、2021 この本の中に「構築する」や「導入する」が書かれている。 この本に限らず、書店に並んでいるISO解説本の多くに「構築する」「導入する」の記述があることに留意。 | |
注11 |
EMAS(Eco-Management and Audit Scheme)で、日本語には環境管理監査制度と訳すようだ。EC欧州委員会(European Commission)が設けた公の制度であり、国際規格であるISO14001を利用した民間のISO認証の仕組みとは別格である。 ISO14001が作られるよりはるか前の1993年にEMAS規則(EUの法律のようなもの)として定められ、1996年にISO14001が作られてからシステム部分はこれと共通化されたが、パフォーマンスが加わっている。2009年に制度が変わり、EU圏内だけでなく海外の国もEMASの認証が受けられるようになった。 *参考:EMASウェブサイト | |
注12 |
正式名は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」である。定められた設備や工程を持つ工場では公害防止の組織を作り、国家資格保有者が該当業務の指揮・管理をしなければならないことを定めたもの。 省エネについては省エネ法、正式名「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」で組織体制、有資格者などを決めている。 同様なものとして「消防法」は危険物の管理体制と有資格者を、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では廃棄物の管理・処理を定めている。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |