*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
清野の所属するISO事務局は、CSR部に属するが課でも係でもなく、単にISO事務局と呼ばれ部長の下に直接ぶらさがっている。
ISO事務局には専任者が3名いる。ずいぶん多いようにも思えるが、認証組織の対象範囲は本社を始め支社10数か所、営業所30数拠点、営業系関連会社など対象人員は1万人にもなるから、それくらい必要だろうと思っている。
事務局の責任者は50代後半の天野で、リーダーと呼ばれているが管理職ではない。リーダー以外の専任者は、30代の倉田、そして20代後半の清野である。
兼務者は本社に10数人、各支社には一人で合計30人ほどいる。10数年も前、認証したときは、兼務者も実際にISO認証の仕事をしていた。しかしISO審査がルーティン業務となった今、兼務者が顔を合わせるのは年度初めと審査前の会議くらいになっている。
唯一本社の営業部門にいる50代半ばの水島さんは、毎週末に事務局に顔を出している。水島さんは役職定年で課長を解任されてからろくな仕事をしていないから、暇つぶしに来ているのだと天野さんは言う。
| 専任者 | 兼務者 | ||||
リーダー 天野 | 倉田 | 清野 | 水島 | その他… | |
 |  |  |  |
||
清野がスラッシュ電機を訪問してから1週間が経つ。訪問後、清野は考え事をすることが多くなった。職場でも口数が少なく、周りの人が気にかけている。
今日は金曜日で水島さんが顔を出す日だ。いやそんなことは決まっていないが、週末には必ずと言ってよいほど顔を出す。
今朝、天野さんに、清野からみなさんにスラッシュ電機訪問の話をしたいと伝えた。
審査員に言われるままのISOでなく、自分たちが考えて会社に寄与することをしたいなと清野は思った。皆がどう思うかは分からないが、スラッシュ電機の深い考え、そして自分が受けた感動を、事務局のメンバーに伝えたいと思ったのだ。
16時過ぎ、いつものように水島さんが来ると、天野さんが打ち合わせをするから会議室に集まれと声をかけてくれた。
![]() 「何か通達でもありましたか?」
「何か通達でもありましたか?」
「いや、そうじゃありません。先日、清野さんがスラッシュ電機さんを訪問しましたので、その報告だそうです」
![]() 「へえー、どういう要件でお邪魔したのですか?」
「へえー、どういう要件でお邪魔したのですか?」
![]() 「それじゃ、スラッシュ電機訪問のお話をします」
「それじゃ、スラッシュ電機訪問のお話をします」
清野はA4数枚を綴じたものを皆に配る。
![]() 「私が○○大学の大学院の学生ということはご存じと思います。天野さんを始め皆さんには、いつも私の通学にご協力いただきありがとうございます。
「私が○○大学の大学院の学生ということはご存じと思います。天野さんを始め皆さんには、いつも私の通学にご協力いただきありがとうございます。
ひと月くらい前ですがスラッシュ電機の今年のCSR報告書が発行されました。最近は環境報告書とかCSR報告書発行などもはやニュースにもならず、マスコミや取引先などに配って終わりなのですが、スラッシュ電機では今年は説明会をするという案内がありました。
当社の広報部にも案内が来ていました。当社ではわざわざ聞きに行くまでもないという判断で、誰も説明会には参加しませんでした」
「ああ、知っているよ。なんだか今年はスラッシュ電機でISO14001認証返上が完了したから、それを特集したとあったね」
![]() 「10年前まではISO14001認証ブームだったけど、最近は認証返上が多くなってきたね。
「10年前まではISO14001認証ブームだったけど、最近は認証返上が多くなってきたね。
とはいえ大企業の認証返上はあまり聞いたことがない。スラッシュ電機も苦しくて、費用削減かな。アハハハ」
![]() 「実を言いまして、2年前に大学でスラッシュ電機の環境担当部門の方を呼んで、講演をしてもらったことがあります(第147話)。案内が来たのはそのつながりでしょう。
「実を言いまして、2年前に大学でスラッシュ電機の環境担当部門の方を呼んで、講演をしてもらったことがあります(第147話)。案内が来たのはそのつながりでしょう。
私は大学院でISO認証を研究しているので説明会に参加したのです。
ISO認証は2009年をピークに減少しています。今ではピーク時の6割まで認証件数が減っています。だから認証返上の流行りに乗ったわけではなく、様々な要件があり認証返上をしたという説明でした」
![]() 「うわー、そんなに減っているの! それほどとは知らなかったなあ〜」
「うわー、そんなに減っているの! それほどとは知らなかったなあ〜」
![]() 「認証返上について説明された方は田村さんという年配の方で、偉い人らしいです。とにかく環境管理に詳しくてマスコミから質問されると、資料も見ずに誰に相談することもなく、ご本人の言葉で詳しく説明されていました」
「認証返上について説明された方は田村さんという年配の方で、偉い人らしいです。とにかく環境管理に詳しくてマスコミから質問されると、資料も見ずに誰に相談することもなく、ご本人の言葉で詳しく説明されていました」
![]() 「部下が渡した資料を読むだけのウチの広報部長とは違うか、アハハハ」
「部下が渡した資料を読むだけのウチの広報部長とは違うか、アハハハ」
![]() 「田村さんの話を聞いて、論文を書くのに役立つ情報が得られるだろうと、スラッシュ電機の広報部にインタビューのお願いをしました。
「田村さんの話を聞いて、論文を書くのに役立つ情報が得られるだろうと、スラッシュ電機の広報部にインタビューのお願いをしました。
そしたら説明会でお話をされた田村氏……彼は環境担当役員のスタッフだそうです……それから環境管理課の課長の磯原氏とセッティングしてくれました。それが先々週のことでした。
私は認証返上の経緯とかメリット・デメリットなどを質問しようとしていたのですが、話が始まるとすぐに、論文を書くレベルではないと言われてしまいました」
「どういうことですか?」
![]() 「インタビューで早速いくつか質問したのですが、そのような質問をするようでは私の知識が全く乏しいと言われました。それでヒアリングから私の教育の場になってしまいました。
「インタビューで早速いくつか質問したのですが、そのような質問をするようでは私の知識が全く乏しいと言われました。それでヒアリングから私の教育の場になってしまいました。
ISO審査のルールは何に決まっていて、どんなことを決めているか、から始まりました。
それから現行のISO審査での問題を具体的に説明があり、そういったことを改善しないと認証の効果はないと言います。
私が調査して改善提案しようと考えていたことなど、既に検討して認証返上がその解であるというニュアンスでした。
ひとつの事例ですが、ISO審査で省エネが目標を0.5%上げろと審査員に言われたことをどう考えるかという話がありました。実を言ってそういう質問はウチでもありました。……というか、毎年のように発生しています。
私は0.5%の上積みなら創意工夫でできるのではないかと言ったところ、私の家庭で年1%削減ができるかどうか考えろと言われてしまいました」
![]() 「年1%は省エネ法の削減目標ですね。当社のどこの工場でも投資なんてしなくても1%くらいの計画はパッと出してくるよ。難しくないと思えるけど」
「年1%は省エネ法の削減目標ですね。当社のどこの工場でも投資なんてしなくても1%くらいの計画はパッと出してくるよ。難しくないと思えるけど」
![]() 「おいおい、倉田君、君の家庭で金をかけずに年1%の削減ができると思うか? 思うならやってみたまえ。工場だって投資なしに1%削減がパッとできるはずはない。そんなことができるなら、既にやっているはずじゃないか?
「おいおい、倉田君、君の家庭で金をかけずに年1%の削減ができると思うか? 思うならやってみたまえ。工場だって投資なしに1%削減がパッとできるはずはない。そんなことができるなら、既にやっているはずじゃないか?
言い換えると金をかけずに創意工夫でできるものは、10年前、20年前に実施済なんだよ。
だから現在、あと0.5%なんて言われると、工場の連中はあちこちから金をかき集め、鉛筆をなめてなんとかつじつまを合わせているのだろう。
私は10年前までFA
もし君ができると思うなら、君の家庭で金をかけずに何ができるか考えてみたまえ。テレビを観ない、エアコンを付けない、お風呂は冷める前に次々に入るとか、暖房は安衛法の事務所規則以下
![]() 「そんなに難しいのですか。でも当社は省エネ法より厳しい業界団体のガイドライン1.5%の計画ですよね。どこの工場でも軽々とできてるじゃないですか」
「そんなに難しいのですか。でも当社は省エネ法より厳しい業界団体のガイドライン1.5%の計画ですよね。どこの工場でも軽々とできてるじゃないですか」
![]() 「ウーム、倉田君が現実を知らないというのは良く分かったよ」
「ウーム、倉田君が現実を知らないというのは良く分かったよ」
![]() 「いや1%なら意識向上とか改善努力で十分できると思いますよ」
「いや1%なら意識向上とか改善努力で十分できると思いますよ」
![]()
 「実は私も同じことを言いました。向こうの磯原課長という人が具体的に説明してくれましたが、1%削減するにはテレビを観る時間を毎日1時間短くすることが必要だそうです。
「実は私も同じことを言いました。向こうの磯原課長という人が具体的に説明してくれましたが、1%削減するにはテレビを観る時間を毎日1時間短くすることが必要だそうです。
でも、それで終わりではないのです。2年目は更に1時間観る時間を短くしなければなりません。日本の家庭でテレビを観る平均は1日3時間だそうで、3年目はテレビを観られなくなり、4年目からは削減できません。
4年目は洗濯機を使うのを止めれば良いと笑われたわ」
![]() 「笑ったのはともかく、その人の言うことに間違いはない」
「笑ったのはともかく、その人の言うことに間違いはない」
![]() 「その磯原氏は事細かに数字を挙げて、いかに1%削減が困難かを私に認識させました。1%削減するには相当暮らしを変えなくてはなりません。少なくても意識向上とか改善努力では無理です」
「その磯原氏は事細かに数字を挙げて、いかに1%削減が困難かを私に認識させました。1%削減するには相当暮らしを変えなくてはなりません。少なくても意識向上とか改善努力では無理です」
![]() 「家庭の電力使用量は終戦後、直線的に増加してきた。1970年頃、私や天野さんが子供の頃だな、当時はひと月の電気使用量は120kWhくらいだったと思う
「家庭の電力使用量は終戦後、直線的に増加してきた。1970年頃、私や天野さんが子供の頃だな、当時はひと月の電気使用量は120kWhくらいだったと思う
それが2000年頃には300kWhになった。子供も減り核家族化になり世帯員数は1970年の3.45人から2.49人まで3割も減ったのにだ
大型冷蔵庫、自動洗濯機、エアコン、まあ豊かになり便利になるということはそういうことだろうね」
「まったくだ。省エネをしようというのは納得する。しかし正直言って冷蔵庫も掃除機も手放す気はないね。もちろんテレビもステレオもエアコンもパソコンもマッサージ機もだ」
![]() 「おっと本題はそうではなく、磯原さんはISO審査では目標値の見直しを勧めるのは、審査員の仕事を逸脱していると言います。そんなことも審査の問題というか、会社の事業の足を引っ張るだけで意味のない無駄だと言います」
「おっと本題はそうではなく、磯原さんはISO審査では目標値の見直しを勧めるのは、審査員の仕事を逸脱していると言います。そんなことも審査の問題というか、会社の事業の足を引っ張るだけで意味のない無駄だと言います」
「私も声に出したことはないけど、審査での問題をいろいろと感じている。
私たちが審査を受けるのがマンネリ化していると同じく、審査員も審査がマンネリ化しているのだろうね。言い換えると勉強していないということかな」
![]() 「ISO認証して10年も経てば、審査で要求事項を満たしていない問題は出ませんからね。
「ISO認証して10年も経てば、審査で要求事項を満たしていない問題は出ませんからね。
審査員の方々も多少は改善点を示すとか、改善のアドバイスするのが役目と考えているのでしょう。まあ雑談半分で他社事例などを聞くのは面白いし役に立つことはありますね」
![]() 「他社の話を聞くのは興味があるね」
「他社の話を聞くのは興味があるね」
![]() 「そうそう、それも大きな問題なのです。
「そうそう、それも大きな問題なのです。
他社の話をするというのは審査の規則に違反してますし、審査契約にある守秘義務に反する重大な違反とのこと。
なによりも私たちの会社のことを、他所に言って話していると思うとイラつきます。次回は苦情を申し立てましょう」
![]() 「あちゃ〜、言われてみればその通りだ」
「あちゃ〜、言われてみればその通りだ」
「今までは審査員は別格という扱いだったからね。でも確かに審査契約で守秘義務がある。過ぎてから苦情を言うより今年の審査前に、オープニングや審査中に他社事例を語ることを止めるよう要請しよう。
同時にウチのことを他社で語っていたかの調査を要請するよ。お願いではなく、契約違反と強く言うつもりだ」
![]() 「えええー、他社の事例を語ることって、そんな重大問題ですか!」
「えええー、他社の事例を語ることって、そんな重大問題ですか!」
![]() 「同業なら廃棄物量とかPRTR報告を見ただけで、その会社の実力が分かるんだよ。そんなことにも気が回らないのか」
「同業なら廃棄物量とかPRTR報告を見ただけで、その会社の実力が分かるんだよ。そんなことにも気が回らないのか」
![]() 「ともかくインタビューで聞く彼らの考えは、ISO認証していると、審査がものすごく負担になり、業務の足を引っ張るというのが第一でした。
「ともかくインタビューで聞く彼らの考えは、ISO認証していると、審査がものすごく負担になり、業務の足を引っ張るというのが第一でした。
また審査員が規格要求にないことを求める。そういうことが多々あると、例を挙げて説明を受けました。
例えば、ウチでも有益な側面がないと不適合と言われています。また環境側面それぞれに有益か有害かを明記しなければならないと言われました」
![]() 「えっ、環境側面に有益、有害はないの?」
「えっ、環境側面に有益、有害はないの?」
![]() 「まずISO規格にはそんな要求はありません。そもそも環境側面に有害も有益もないそうです。極め付きは環境側面に有害・有益があるというのは日本だけだと。
「まずISO規格にはそんな要求はありません。そもそも環境側面に有害も有益もないそうです。極め付きは環境側面に有害・有益があるというのは日本だけだと。
複数の外資系認証機関に問い合わせたメールも見せてもらいましたが、日本で活動している外資系認証機関で有益・有害はあると回答したところはゼロでした」
「ええっ!それは本当かい? ならば今年の審査前には認証機関を呼んで話し合いをしなくちゃならないな。
先ほどの件もあるから、別途問題点をまとめてほしい」
![]() 「その他のいろいろな問題についても、なぜ悪いのかの根拠と、具体的事例をあげて教えてもらいました。スラッシュ電機では、問題対策を審査員個人相手に説明するのでなく、認証機関に対して説明し、審査員に徹底するよう要請しているそうです。
「その他のいろいろな問題についても、なぜ悪いのかの根拠と、具体的事例をあげて教えてもらいました。スラッシュ電機では、問題対策を審査員個人相手に説明するのでなく、認証機関に対して説明し、審査員に徹底するよう要請しているそうです。
また工場の目標や計画への注文が多くて、省エネ投資も単にその工場の省エネだけでなくグループ全体の設備更新や新規事業など経営全般を考慮しているのに、その工場の環境投資が少ないと言われて審査でトラブルがあったそうです」
![]() 「省エネ法は何年か前に大きく変わって、事業所単独でなく企業全体あるいはグループ全体で考えるようになったからね。
「省エネ法は何年か前に大きく変わって、事業所単独でなく企業全体あるいはグループ全体で考えるようになったからね。
とはいえ審査員としては審査している工場の、省エネとか改善を求めたいだろう。審査員にとって認証範囲外で改善が進んでも、認証している工場に改善がなければ認証効果がでないからね。
審査員は審査報告として、認証を認めるとか認証継続して良いか否かを報告するわけだけど、そのときあまり改善が進んでいないと、判定委員会などでいちゃもんがつくかもしれないね。審査員としては自分が審査したところでは大きな成果を出してほしいのだろう」
![]() 「認証機関も費用削減で、今どき判定委員会を開いているところはないだろうけどね」
「認証機関も費用削減で、今どき判定委員会を開いているところはないだろうけどね」
注:審査員が審査した企業が認証できるとかダメとか決定できるわけではない。認証機関として判断するステップを設けなければならないことになっている。(参照ISO17021-1:2015 9.5.1)
認証事業が始まった頃は、判定委員会の委員には学識経験者とか企業の立場の委員を置くのが流行ったが、認証ビジネスはあっという間にコスト競争となり外部の委員は消え、その後更に省力化が進み、判定委員会ではなく決裁者がOK/NGを判定するところが増えた。21世紀初めのことである。
私の知り合いが某認証機関の判定委員会の委員をしていたが、弁当のレベルがだんだんと落ちてきたと笑っていたのは2003年頃だった。その後すぐに、判定委員会がなくなったよと語っていた。
「工場単位で認証するのは良いけど、ISO14001のアネックスで『上位組織の意向を適用してもよい(ISO14001:2015 Annex A.4.4 最終段落)』とあるが現実には『上位組織の意向に従う』しかない。
工場の戦略や投資は工場単独で決定できるわけでなく、本社あるいは事業本部などの上位機関が決定する。なにしろ法的にも投資家対応でも、責任は工場ではなく法人だからね。
法律的には全社あるいは企業グループとして法で定める省エネをしていれば問題はないだろうが、審査している工場で省エネが進まないと、目標を上げろと一言いいたくはなるだろう」
![]() 「そりゃ法律とISO認証を天秤にかければ、ISOのほうが軽いよね。
「そりゃ法律とISO認証を天秤にかければ、ISOのほうが軽いよね。
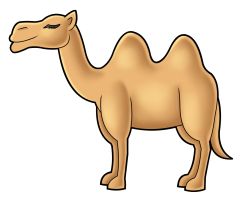
投資をしなくちゃ改善はできない。目標を上げろと言えば改善が進むならこの世は楽だ」
![]() 「まあ、そういうことを、いろいろ教えてもらいました。
「まあ、そういうことを、いろいろ教えてもらいました。
そうそうISO審査の最中に、審査員が暴行事件を起こしたこともあったそうです」
![]() 「ああ、それ聞いたことがある。1年位前かな業界団体の会合があったとき、スラッシュ電機の元大阪支社にいたという奴が笑いながら言ってたねえ〜」
「ああ、それ聞いたことがある。1年位前かな業界団体の会合があったとき、スラッシュ電機の元大阪支社にいたという奴が笑いながら言ってたねえ〜」
![]() 「それは興味がありますね。ぜひ聞かせてくださいよ」
「それは興味がありますね。ぜひ聞かせてくださいよ」
![]() 「他言するなと言われているけど関係ないよね、もう5年前のことらしい(第93話)。スラッシュ電機もウチと同じように、本社と支社を一体でISO14001認証している。毎年抜き取りで審査するわけだが、そのときは大阪支社の番だったらしい。
「他言するなと言われているけど関係ないよね、もう5年前のことらしい(第93話)。スラッシュ電機もウチと同じように、本社と支社を一体でISO14001認証している。毎年抜き取りで審査するわけだが、そのときは大阪支社の番だったらしい。
 |  |
審査員が支社の倉庫に行くと、アルバイトに来ていた女子高生たちがいて、その子らにスラッシュ電機の環境方針を知っているかって聞いた。
短期間のアルバイトで知りませんと回答されると、方針を知らないことに怒り狂って作業していた品物をあたりにぶちまけたそうだ。
ちょうど倉庫で工事をしていた大工が暴れる審査員を抑えようしたら、審査員が大工を殴って怪我をさせたという」
![]() 「そりゃ……とんでもないことを」
「そりゃ……とんでもないことを」
「雇用者責任があるのでしょうから、認証機関も大変だったでしょうね」
![]() 「結果としては示談成立で起訴猶予になったと言っていた。
「結果としては示談成立で起訴猶予になったと言っていた。
ともかくその結果、認証機関を変えてしまったそうだ」
![]() 「あれ? 認証を返上したのではなく鞍替えしたのですか?」
「あれ? 認証を返上したのではなく鞍替えしたのですか?」
![]() 「その暴行事件の時には認証機関を変えたのよ。その後変えた認証機関で審査を受けたのです。しかしトラブルはなかったけれど、認証機関を変えても審査で得るものはないと判断して、本社と支社は認証返上してしまった。
「その暴行事件の時には認証機関を変えたのよ。その後変えた認証機関で審査を受けたのです。しかしトラブルはなかったけれど、認証機関を変えても審査で得るものはないと判断して、本社と支社は認証返上してしまった。
その後、工場と関連会社に対して、事業上必要でないなら認証を止めるよう指示を出したそうです。そしてスラッシュ電機の全事業所がISO14001の認証を止めたのが昨年で、その概要をCSR報告書に載せたのが今年というわけ。
おっと、どんどん話がそれてきました。話を戻します。
そういう経緯を聞いて私もいろいろ考えました。
ウチも本社と支社がISO14001を認証して15年くらいになります。私は認証してから入社ですが、毎回審査で感じているのはマンネリ化していることです。
そして先日、スラッシュ電機を訪問して分かったのは、私たちもISO認証で得るものはほとんどない。単なるイベントだということです。
 そして審査費用はせいぜい300とか350万だけど、審査対応の人件費などを考えると2000万ではきかないほどお金がかかっていることです。
そして審査費用はせいぜい300とか350万だけど、審査対応の人件費などを考えると2000万ではきかないほどお金がかかっていることです。
また審査では規格適合と言っても、その価値がいかほどあるのか分かりません。遵法を点検してくれるわけでなく、会社で違法や事故が発覚すると、認証機関は騙されたというだけです。企業がだましていたわけじゃないと思いますね。単に企業も過失で気づかず、審査でも見逃しただけでしょう。
大金を払って余計悪者にされるなら、審査を頼まないほうがマシじゃありませんか。
そこまでいかなくても、審査で得るものは何もないのは間違いありません。
いろいろアドバイスとか他社の事例を聞かされますが、9割は既に検討していることですし、目標を高く持てと言われても私たちが省エネ目標を立てるわけではありません。全社のエネルギー使用状況、設備更新などを考えて投資を決めてるわけです。
まして本社や支社はテナントですから、照明器具一つとっても自分たちが対策できるわけではありません。ありていに言えばビル管理会社の計画に従っているだけです。
あげくに情報をバラされて、情報漏洩の共犯にさせられては冤罪事件です。
つまり……」
「つまり?」
![]() 「私たちのしているISO審査って、おままごとじゃないかって気づいたんです。
「私たちのしているISO審査って、おままごとじゃないかって気づいたんです。
スラッシュ電機が何もかも素晴らしいと思ったわけではありません。でも、彼らはISO審査で見逃して、後に社内の監査などで問題を見つけると、認証機関を呼んでしっかり審査をしろと苦情を言っているのです。
単に審査がしゃんしゃんと終わればよいと考えているわけじゃありません。常に真剣勝負をしているのです。
私たちもそれくらい真面目にISOに取り組むべきだろうと思いました」
![]() 「確かになあ〜、さっき天野さんが審査を受けるのがマンネリ化していると同じく、審査員も審査がマンネリ化していると言いましたが、現状の審査は台本を読んでいるような芝居ですよね」
「確かになあ〜、さっき天野さんが審査を受けるのがマンネリ化していると同じく、審査員も審査がマンネリ化していると言いましたが、現状の審査は台本を読んでいるような芝居ですよね」
「最近じゃ審査代行、更新代行ってのもあるそうじゃないか。我々が認証しようとしていた時期は、コンサルは新規認証だけで食っていけたんだろうが、今は新規はほとんどない。認証維持、認証更新を代わってあげましょうという代行業だ。
そんな代行業者が対面では、審査員も張り合いがないだろう」
![]() 「審査するほうもされるほうも同じコンサル会社かもしれんぞ、アハハハ」
「審査するほうもされるほうも同じコンサル会社かもしれんぞ、アハハハ」
![]() 「水島さんが考えるあるべき審査は、どのようなものですか?」
「水島さんが考えるあるべき審査は、どのようなものですか?」
![]() 「飾らない、嘘をつかない、ありのままだね」
「飾らない、嘘をつかない、ありのままだね」
![]() 「当社は、嘘なんてついたことありませんよ」
「当社は、嘘なんてついたことありませんよ」
![]() 「ほう〜、内部監査で是正完了していないのが、今までないってのは本当かね?
「ほう〜、内部監査で是正完了していないのが、今までないってのは本当かね?
省エネ計画は経産局に届けているのと、ISO審査で見せているのが違うのを知っているだろう。
環境教育なんてのが必要なのか否か定かではないが、当社では全員にさせている。
ウチの部で環境教育をした日に出張だった奴が受講済みになっていた。不思議なこともあるものだ」
![]() 「まあ、多少は飾っているかもしれませんね」
「まあ、多少は飾っているかもしれませんね」
![]() 「スラッシュ電機でも、数年前のこと経産局に出している数字と、本社に出している数字と、ISOで見せている数字が違うと発覚したそうです」
「スラッシュ電機でも、数年前のこと経産局に出している数字と、本社に出している数字と、ISOで見せている数字が違うと発覚したそうです」
![]() 「どこでもそんなものかね。それで、どうしたのかな、黙認か」
「どこでもそんなものかね。それで、どうしたのかな、黙認か」
![]() 「業務監査で見つけて黙認したので執行役監査部長は辞任、工場長と担当部長は役職解任で関連会社に出向、課長以下は減俸だったそうです」
「業務監査で見つけて黙認したので執行役監査部長は辞任、工場長と担当部長は役職解任で関連会社に出向、課長以下は減俸だったそうです」
天野と水島は顔を見合わせた。
二人とも驚いている。
![]() 「ほう〜、やるもんだねえ。
「ほう〜、やるもんだねえ。
信賞必罰ここにあり、さすがとしか言いようがない。それくらい真剣だから認証機関にも言いたい放題なんだろうな
「しかしちょっとやりすぎじゃないのかな」
![]() 「ウチでそんな処分したら、私まで……」
「ウチでそんな処分したら、私まで……」
![]() 「いや、おかしくないと思うぞ。さっきも清野さんは審査で不適合を見逃したら認証機関を呼んで是正を要求したとか言ったが、そういう真剣さが我々にはない。倉田君は審査員が不適合を見逃したらハッピーくらいに思っているんだろう。
「いや、おかしくないと思うぞ。さっきも清野さんは審査で不適合を見逃したら認証機関を呼んで是正を要求したとか言ったが、そういう真剣さが我々にはない。倉田君は審査員が不適合を見逃したらハッピーくらいに思っているんだろう。
彼らの真剣さを見習わねばならない。
倉田君、そういう仕事が本当の仕事だよ。ウチのISO審査はおままごと、お遊びなんだ」
![]() 「ここは営業の第一線じゃありません。開発に追われているわけでもない。余裕をもって仕事をしましょうよ」
「ここは営業の第一線じゃありません。開発に追われているわけでもない。余裕をもって仕事をしましょうよ」
![]() 「余裕を持つのは結構だが、是正完了していないのを是正済というのは虚偽の説明だ。ISOなんてどうでもいいが、厳密にいえばそれは背任とまではいかずとも業務上過失で懲戒だぞ」
「余裕を持つのは結構だが、是正完了していないのを是正済というのは虚偽の説明だ。ISOなんてどうでもいいが、厳密にいえばそれは背任とまではいかずとも業務上過失で懲戒だぞ」
「水島さんの考えも分かる。とはいえ、今まで審査でトラブルを起こさないことを第一にしてきたわけだ。真剣勝負をしようという発想ではなかったと思う。
どんな審査対応を上が望んでいるかを確認してから、ということでよろしいでしょう」
![]() 「そうですよ。ISO事務局なんて問題を起こさなくちゃいいんです」
「そうですよ。ISO事務局なんて問題を起こさなくちゃいいんです」
![]() 「もちろん上の考え次第ではある。でも真に会社に役に立つものであるべきだよね。おままごとでは悲しいじゃないか。
「もちろん上の考え次第ではある。でも真に会社に役に立つものであるべきだよね。おままごとでは悲しいじゃないか。
日々正念場って言葉知ってるか?
私は今、陰では老害なんて言われているけど、君の年には日々正念場と頑張っていたつもりだ。台本のある営業とか、おままごと営業とかしたことはない。
何よりも営業に台本があったら楽でいいねえ〜」
「まあまあ、水島さんとはこのISO認証の時からの付き合いじゃないですか。どうせISO認証もあと長いことはないですよ。このまま形だけを続けて、終わりを待ってもよろしいでしょう」
![]() 「そうかなあ〜、十何年前、本社・支社の認証活動をしたとき、天野さんと他社に先駆けてISO認証して会社の名を上げようと頑張ったじゃないですか。あのときの熱気をもう一度って思いませんか?」
「そうかなあ〜、十何年前、本社・支社の認証活動をしたとき、天野さんと他社に先駆けてISO認証して会社の名を上げようと頑張ったじゃないですか。あのときの熱気をもう一度って思いませんか?」
清野の報告会がなぜか、どんどんとずれていきそうです。とはいえ清野がこまごま説明する前に、水島氏と天野氏は清野の気持ちというか趣旨を理解してしまったようです。
なにせ認証した時から携わっていた彼らは、ISO第一世代なのですから。
先輩たちの作り上げた仕組みの意図を理解せず、形だけを踏襲する第二世代である倉田氏、そしてその矛盾に気付いたものの第三世代になれるのか清野氏、さて三つの世代の葛藤の行方は……
![]() 本日 思い出したこと
本日 思い出したこと
第165話で田村氏と磯原が清野氏に「そんなことを知らないとは、論文を書く以前だ」と言いました。考えればひどい言いようです。少し反省しました。
実は私は同じことを言われたことがあります。
12年ほど前、私が引退する前に、アイソス誌やその他の雑誌にたびたび登場する有名な審査員にメールを出した。
メールの趣旨は審査での問題を取り上げて、改善しなければ審査の品質が上がらないことを論じ、協力してほしいという趣旨だった。
返信が来た。
私の本文の前に1行だけ書かれてあった。
「何も知らないくせに大層なことを語るな」
まあ、彼に比べれば私は無名な一会社員である。そして私を思いあがった若者と思ったようだ。彼より若いのは確かだが、私も還暦を過ぎていたのだが。
しかしISO審査の現実は私のほうが知っていたようだ。彼は今は審査員もコンサルも引退しているが、現状を見て、私を貶すことができるだろうか?
認証件数が当時の半分に減った現状をどう思っているのか、是非ともお聞きしたいものだ。減るには理由があるはずで、彼はそれを理解しているだろうか?
あるいは彼は自分が現役の時金儲けができれば、後は野となれ山となれ、認証制度が消滅しても気にしないのかもしれない。その原因がご本人にあろうとも。
彼に次の成句を贈ります。
「心ここにあらざれば
 | 彼はまさに節穴審査員だな |
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
FAとはファクトリーオートメーション(Factory Automation)の略で、生産工程の自動化を図るシステムの総称 | |
注2 |
機械設備や電気機器で省エネになるものは「省エネ機器」と呼ぶが、省エネを図るための測定器やセンサーの類は省エネを進めるためのツールであり「省エネ支援機器」と呼ばれる。 | |
注3 |
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則では雇用した人たちを働かせる室温は、18〜28℃になるように努めなければならないとなっている。2021年までは17〜28℃であった。 家庭の室温を規制したものはない⇒室温が寒くても暑くても罰則がない。国は20〜28℃を推奨している。 | |
注4 | ||
注5 | ||
四書とは、儒教の経典である、大学・中庸・論語・孟子(もうし)の四つの書物をいう。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |