*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
天野たちがまとめ星部長に提案したISO認証の改善案は、部長に差し戻しにされた。ダメというのではなく、もう少しに検討を深めよということだ。
天野はいつものメンバーで討論した結果、とりあえずアンケート集計結果をアンケートしてくれた人たちに報告し、意見を募集した。万事公論に決すべきである。
1週間と期限を切ったが、本社内と支社から50件近い意見、改善案が送られてきた。それを皆で見て、改善方向の再検討である。
|
|
|
 |
|
| 星執行役 |
![]() 「まず、何を目指すかを考え直すべきかなと思います」
「まず、何を目指すかを考え直すべきかなと思います」
「何を目指すか?……どういうことでしょう」
![]() 「私たちはスラッシュ電機の改善策を見ていますから、どうしてもそれに合わせたというか、対抗するものと考えてしまいます。
「私たちはスラッシュ電機の改善策を見ていますから、どうしてもそれに合わせたというか、対抗するものと考えてしまいます。
スラッシュ電機は審査でどんな問題があったのか、会社側からみてどの問題を解決すべきかという観点で対策を決め、それを実現する方法を選択したと思います。
私たちの問題は、スラッシュ電機の問題とは違うのではないでしょうか。あるいは会社の体制がスラッシュ電機のレベルまで行ってないかもしれない。
となると目指すものはスラッシュ電機とは違うことになります」
![]() 「スラッシュ電機とウチの問題が、異なることもないと思う。審査員が誤った判断をしていたというのは共通だよね。有益な環境側面が必要と言われたのも、環境目的は3年以上も、スラッシュ電機でもウチでも同じだ。
「スラッシュ電機とウチの問題が、異なることもないと思う。審査員が誤った判断をしていたというのは共通だよね。有益な環境側面が必要と言われたのも、環境目的は3年以上も、スラッシュ電機でもウチでも同じだ。
となると審査での問題はほぼ同じだ」
![]() 「そうですね。しかしそれに対する認識は異なっていたと思います。有益な環境側面が必要とは、多くの工場で審査のたびに言われていました。しかし対応が違います。
「そうですね。しかしそれに対する認識は異なっていたと思います。有益な環境側面が必要とは、多くの工場で審査のたびに言われていました。しかし対応が違います。
スラッシュ電機では会社側と審査人が喧々諤々の議論を交わしていた。そして有益な環境側面があるという考えで資料作りをすると手間暇がかかるだけでなく、スラッシュ電機の環境管理が悪くなってしまうという認識を、社内で共有していたと思います。
それに反して当社では審査員が要求するならことはすべて正しいと受け取り、特段異議も唱えず言われた通りにしていた。
その結果、手間暇がかかっていたわけだけど、それが問題だという認識はなかったわけです。ISO審査とはこういうものと認識していたわけです。
寝る子は起すなではありませんが、現在問題になっていないことを対策するのではなく、今当社の社内で問題と認識されていることを解決すべきではないでしょうか」
![]() 「確かに当社では、会社の目標と工場の目標が違っても、大騒ぎになっていないからな」
「確かに当社では、会社の目標と工場の目標が違っても、大騒ぎになっていないからな」
![]() 「でもそれってまずいわけでしょう、対策が必要です」
「でもそれってまずいわけでしょう、対策が必要です」
![]() 「ルール違反だからダメと、一概に言えないと思うのですよ。今当社の人たちが問題だと認識していることを改善しないで、皆が気付かないことの対策をしても、社内の賛同を得られないと思います」
「ルール違反だからダメと、一概に言えないと思うのですよ。今当社の人たちが問題だと認識していることを改善しないで、皆が気付かないことの対策をしても、社内の賛同を得られないと思います」
![]() 「それじゃウチで問題になっているものって何ですか?」
「それじゃウチで問題になっているものって何ですか?」
![]() 「私たちが、なぜISO認証を見直そうと思ったかを振り返れば分かると思います」
「私たちが、なぜISO認証を見直そうと思ったかを振り返れば分かると思います」
![]() 「見直そうとしたきっかけは、清野さんがスラッシュ電機のCSR報告書の説明会に行ったことですね」
「見直そうとしたきっかけは、清野さんがスラッシュ電機のCSR報告書の説明会に行ったことですね」
「確かにスラッシュ電機の説明会を聞いて清野さんが当社でも問題があると感じたわけだ。でも、その問題はスラッシュ電機と当社は同じだったのだろうか?」
![]() 「同じものもあったと思いますし、違うのもありました。
「同じものもあったと思いますし、違うのもありました。
ただスラッシュ電機の話を聞くまでは、是正策が認証返上とまでは思い浮かびませんでした。
私が最初に気づいたことは、審査とは審査員の要望を受査企業が実現することではないということでした。審査員の思いを実現するのではなく、規格要求と現実の比較をしてもらい、規格要求を実現することです。
具体的には、目標を上積みするとか有益な環境側面とか、規格要求にない余計な仕事は止めたいと思いました」
![]() 「ということは清野さんの要求水準は低いわけですね」
「ということは清野さんの要求水準は低いわけですね」
![]() 「低いと言われるとその通りです。でも私たちの実力に応じたものと思えば、それでよろしいのではないですか。
「低いと言われるとその通りです。でも私たちの実力に応じたものと思えば、それでよろしいのではないですか。
省エネの目標を高くしろと言われて、実力以上の目標を立てて未達では意味がありません。
あるいはスラッシュ電機の方が余裕がない、損益も費用もきめ細かに管理されている状態だから、我々のようにおおらかと言うかどんぶり勘定ではやっていけないのかもしれません。
スラッシュ電機では環境活動もまじめだから、未達があれば売上とか安全と同じく厳しく評価され計画未達の責任が問われるのかもしれません。
当社の場合、ISO関係は重要じゃない、みそっかすなんです。
だから審査員に計画を高くしろと言われて目標を見直した結果、計画未達になっても問題だとなりません。だからまともな是正処置をとりません。どちらがあるべき姿かはともかく、そういう違いがあるのです」
注:疑問である。2002年頃出会った審査員(複数)は「目標は高いほうが良い。未達になっても構わない」と語った。
そう語ったのは一人二人ではなかったから、認証機関か指導的立場の審査員が、そういう指導をしていたと思われる。
清野が語るような、いい加減な目標とフォローがないのでは管理不十分だろう。案外そういう企業出身者が目標は高いほうが良いと言い出したのかもしれない。
まっとうな計画なら、目標に合わせたリソースを投じ達成するのが当たり前だ。目標を高くして未達でもよいというなら、それは計画でなく妄想に過ぎない。
となると思うのだが……
PDCAがしっかりしている会社はISO認証など不要であり、PDCAをしっかりしていない会社はISO認証など無駄である。
「ということはISO認証は○○である」
問:上記の○○に適切な言葉を入れよ(笑)
![]() 「なるほど、いろいろな観点で向うとこっちは違うわけだ。
「なるほど、いろいろな観点で向うとこっちは違うわけだ。
となると我々は、審査では規格の誤った解説とか、余計なアドバイスとかは要りませんと言えば良いことか」
![]() 「そうですね。環境管理とはどうあるべきかと突き詰めると、究極的には認証は無用ということに至るかもしれません。私たちの感じていたのはそこではなく、審査員の要求が規格を逸脱しないなら満足ではないかしら」
「そうですね。環境管理とはどうあるべきかと突き詰めると、究極的には認証は無用ということに至るかもしれません。私たちの感じていたのはそこではなく、審査員の要求が規格を逸脱しないなら満足ではないかしら」
![]() 「なんだか倉田君の言うように、スラッシュ電機に比べると見劣りするね」
「なんだか倉田君の言うように、スラッシュ電機に比べると見劣りするね」
![]() 「スラッシュ電機では、現状の問題を解決しようとトライアルをした結果、認証する必要がないと分かったのだと思います。
「スラッシュ電機では、現状の問題を解決しようとトライアルをした結果、認証する必要がないと分かったのだと思います。
私たちは現状では手間暇ばかりかかって成果がないと思っていたけど、私たちのISO規格の理解もままならず、ISO規格から離れるとか、ISO審査なしに改善する高みには至っていないのです」
![]() 「それでいいのかなあ〜」
「それでいいのかなあ〜」
![]() 「仮にスラッシュ電機と同じレベルで是正をするとして、そのときみんなの理解が得られるか、成果を出せるかと考えると、事務局だけが空回りしてしまうかように思います。そして結局ゴールにたどり着けないかと。
「仮にスラッシュ電機と同じレベルで是正をするとして、そのときみんなの理解が得られるか、成果を出せるかと考えると、事務局だけが空回りしてしまうかように思います。そして結局ゴールにたどり着けないかと。
スラッシュ電機のCSR報告書説明会で、大川専務と言う方がISO認証の『守破離』の『離』の段階に来たと語っていました。
|
|||
「おお、習い事とか武道でいう『守破離』だね。そう言われるとその通りだ。
それなら明らかな規格の誤解釈だけを改めさせ、その具現化の方法は審査員の独断でなく受査企業に任せてほしいということだね」
![]() 「そう、それです。いってみれば規格を正しく理解して、審査は審査のルールを守って行ってもらうこと」
「そう、それです。いってみれば規格を正しく理解して、審査は審査のルールを守って行ってもらうこと」
「行ってみれば当たり前のことでしかない。とはいえ、そこまでレベルアップさせるのも大変だね。認証機関が受査企業を指導するというのはよく聞くけど、受査企業が認証機関を指導するというのは聞いたことがないね。
今まで審査を受けてきた感じでは、話し合いになるかどうか……」
![]() 「清田さんのと言うか、我々のと言うか、認証機関に対する要求は非常に低い。この条件で向うが折れなければ認証機関を鞍替えということになりますか」
「清田さんのと言うか、我々のと言うか、認証機関に対する要求は非常に低い。この条件で向うが折れなければ認証機関を鞍替えということになりますか」
「長年おかしな考えで審査していたわけで、話をしても前進がないように思えるが、とりあえず話し合いはしなければならないね。
流れとしては、第一に我々は何を目指すかであり、それからその実現案となるわけで、具体的なことはおいおいと考えていくことにしよう」
![]() 「そういう意味では、わざわざスラッシュ電機にお話を伺いに行くことは、必要なさそうですね」
「そういう意味では、わざわざスラッシュ電機にお話を伺いに行くことは、必要なさそうですね」
![]() 「ISO規格で審査員から言われて、おかしいと感じたことの適否を確認することはあるな。かれらならズバッと回答してくれるだろう」
「ISO規格で審査員から言われて、おかしいと感じたことの適否を確認することはあるな。かれらならズバッと回答してくれるだろう」
「一から教えてくれでは恥だから、一応問題と思われることについてはその解釈と対応策を考えていくことは必要だね。
いくつくらいありそうかな?」
![]() 「工場や支社の人たちが問題にしたものは30もないでしょう。20くらいですか」
「工場や支社の人たちが問題にしたものは30もないでしょう。20くらいですか」
![]() 「それを品質環境センターにぶつけても、彼らは我々と話し合うのは初めてだから、スラッシュ電機と同じ解釈にしてほしいと言っても通用しないだろうな
「それを品質環境センターにぶつけても、彼らは我々と話し合うのは初めてだから、スラッシュ電機と同じ解釈にしてほしいと言っても通用しないだろうな
そこを詰めるのも一仕事か?」
「スラッシュ電機はそういうことを何度もしてきたんだ。我々も労を嫌ってはいけない」
![]() 「さっきの話に戻るけど、ごねるなら鞍替えしますと言うしかないね。もう義理は果たしただろう
年季奉公だって3年が普通だよ
「さっきの話に戻るけど、ごねるなら鞍替えしますと言うしかないね。もう義理は果たしただろう
年季奉公だって3年が普通だよ
「ウチは20年審査を依頼してきたから、とっくに年季は明けたか? 実際には出向者とかいるから簡単ではないけどね」
![]() 「スラッシュ電機はそういう問題も、一つ一つ潰していったのだろうね」
「スラッシュ電機はそういう問題も、一つ一つ潰していったのだろうね」
1週間ほどで過去に審査の際に審査員が説明した規格解釈でおかしいと思われるところを摘出し、事務局でまっとうと思われる規格の意図を考えた。それで終わりにしてもよかったが、星部長がスラッシュ電機に相談に行けと言ったことを踏まえると訪問したという実績も残しておかねばと、天野はご教示願いたい旨のメールを入れた。
田村氏と星部長は既に話をしていたようで、すんなりと進んだ。
予定していた質問を終えて雑談ベースの質疑になる。
数日後、天野は清野と倉田の三人でスラッシュ電機を訪ねた。先方は田村氏と環境管理課長と言う磯原氏が対応してくれた。
品質環境センター特有の誤解釈について、正しい意味についてすり合わせを行った。
田村氏、磯原課長とも気さくで教えてやるという意識もなく、困ったもの同士助け合おうという雰囲気である。
![]() 「いろいろお聞きしたいことがあります。御社の環境マニュアルはどれくらいのボリュームですか?」
「いろいろお聞きしたいことがあります。御社の環境マニュアルはどれくらいのボリュームですか?」
![]() 「30ページくらいはありましたか。なるべく簡単にしようと思っていましたが、認証機関の要求が細かくてめんどくさかったですね。もちろん認証を止めた今はありません」
「30ページくらいはありましたか。なるべく簡単にしようと思っていましたが、認証機関の要求が細かくてめんどくさかったですね。もちろん認証を止めた今はありません」
![]() 「ISO認証を返上しても、環境マニュアルは新人の教育研修に必要ではないのですか?」
「ISO認証を返上しても、環境マニュアルは新人の教育研修に必要ではないのですか?」
![]() 「えっ! 環境マニュアルを勉強用ですか……そういう発想は初めて聞きました。品質マニュアルにしても環境マニュアルにしても、認証機関が作ってほしいというから作っているにすぎません」
「えっ! 環境マニュアルを勉強用ですか……そういう発想は初めて聞きました。品質マニュアルにしても環境マニュアルにしても、認証機関が作ってほしいというから作っているにすぎません」
![]() 「2015年改定でISO規格にマニュアル作成要求はなくなりましたが、会社としてはあったほうが便利で役に立ちますよね」
「2015年改定でISO規格にマニュアル作成要求はなくなりましたが、会社としてはあったほうが便利で役に立ちますよね」
![]() 「おっしゃる意味が分かりません。環境マニュアルがどんな役に立つのか? 作るだけ時間の無駄でしょう」
「おっしゃる意味が分かりません。環境マニュアルがどんな役に立つのか? 作るだけ時間の無駄でしょう」
![]() 「マニュアルはISO規格に沿って記述されているから、審査の際に審査側、会社側の両方が持っていれば迷うことなく進みますけど」
「マニュアルはISO規格に沿って記述されているから、審査の際に審査側、会社側の両方が持っていれば迷うことなく進みますけど」
![]() 「どうも御社とは考えが異なるようです。弊社では環境マニュアルは認証機関が欲しいというから作っているという認識しかなく、審査の時に我々は見もしません。
「どうも御社とは考えが異なるようです。弊社では環境マニュアルは認証機関が欲しいというから作っているという認識しかなく、審査の時に我々は見もしません。
私たちにとってマニュアルは文書ではなく広報資料、チラシみたいなものです。嘘は書きませんが、文書番号はなく発行管理もしません」
![]() 「話が理解できないのですが、磯原君、どういうことですか?
「話が理解できないのですが、磯原君、どういうことですか?
![]() 「環境マニュアルは勉強になるし、審査に役に立つというのですが、どうでしょうねえ〜」
「環境マニュアルは勉強になるし、審査に役に立つというのですが、どうでしょうねえ〜」
「具体例を挙げますと規格要求では、環境方針を文書化するとか社内に伝達するとかありますね。そういう質問があればマニュアルを見て回答すれば楽だという話です」
![]() 「弊社には環境方針なるものがないのです。ですから出発点からして違いますね」
「弊社には環境方針なるものがないのです。ですから出発点からして違いますね」
![]() 「方針がないというと……?」
「方針がないというと……?」
![]() 「ないわけじゃないです。環境方針なるひとつのものがないということです。
「ないわけじゃないです。環境方針なるひとつのものがないということです。
弊社では、社長の年頭の挨拶、年度初めの方針説明などを合わせて社長方針としております」
![]() 「それで審査はOKですか?」
「それで審査はOKですか?」
![]() 「不適合にはなりませんでした。過去の話ですが」
「不適合にはなりませんでした。過去の話ですが」
![]() 「それで適合なんてありえない」
「それで適合なんてありえない」
「倉田君、ちょっとストップ。今日は本題に限定しよう」
・
・
・
・
![]() 「御社ではISO認証のとりまとめや指導は、磯原さんの環境管理課が担当になっているのですか?」
「御社ではISO認証のとりまとめや指導は、磯原さんの環境管理課が担当になっているのですか?」
![]() 「環境管理課の職掌は昔からの環境管理、すなわち大気・水質・騒音/振動の公害防止、電気や重油のエネルギー管理、そして廃棄物管理を担当することになっているのです。
「環境管理課の職掌は昔からの環境管理、すなわち大気・水質・騒音/振動の公害防止、電気や重油のエネルギー管理、そして廃棄物管理を担当することになっているのです。
弊社ではISO14001担当の部署がありませんので、工場や関連会社でISO認証絡みで困りごとがあると、社内電話帳から環境管理課ならISO担当だろうと見当をつけて電話してくるのです。
私は元、工場で電気設備の管理をしていただけで、省エネくらいしか関係なかったのです。とはいえ本社と言うのは工場や関連会社の上前を撥ねて暮らしているわけで、無下にするわけにはいきません。
放っとくわけにいきませんから勉強しました。
まあISOの問題は多々ありましたし今も皆無ではありません。スラッシュ電機本体では認証返上しましたが、関連会社では今も認証しているところはたくさんあります。
問題の根本は審査員の不勉強と、会社の人が審査員は間違えないと誤解しているからです。
まあそういうことをしていると驚くこともあります。
スラッシュ電機の審査において、審査員の解釈を論破されるとそれ以降、規格通り正しく審査するようになりましたが、関連会社に行くと、以前の間違えた考え方で審査しているのですよ。
自分の規格の理解を見直したのでなく、客が文句を言うところだけ客に合わせたのですかね?」
注:私の実体験である。某認証機関が私の勤め先で寝ぼけたことを語っていたので「そりゃおかしいですよ」説明して正しい解釈を教えた。するとその認証機関は審査員が変わっても、その後、私の勤め先では私が教えた解釈で審査をした。
だが他の会社に行けば、その後もずっと間違えた解釈で審査をしていた。よほど間違えた解釈が好きだったのか? それとも考えを変えると、死んじゃうのか?
磯原課長はそんな例を挙げて、おかしいねと笑う。本来ならスラッシュ電機で論破されたなら、その認証機関はすべての審査員に正しい理解を周知徹底し、すべての審査員がどこの審査でも正しい解釈で行うべきだろう。
![]() 「それと環境目的が3年以上というのは1996年版とか2004年版ならともかく、2015年版では環境目的と言う言葉そのものがなくなったのにどうしてですかねえ」
「それと環境目的が3年以上というのは1996年版とか2004年版ならともかく、2015年版では環境目的と言う言葉そのものがなくなったのにどうしてですかねえ」
![]() 「私も不思議に思います。そもそも2015年版の本文では目的(objectives)という言葉が出てこないのに、定義3.2.5で『目標(objective)』しかない英語原文と違って『目的,目標(objective)』とあるのはなぞとしか言いようがありません。アハハハ」
「私も不思議に思います。そもそも2015年版の本文では目的(objectives)という言葉が出てこないのに、定義3.2.5で『目標(objective)』しかない英語原文と違って『目的,目標(objective)』とあるのはなぞとしか言いようがありません。アハハハ」
注:JISQ14001で『目的』が2回あるが、いずれも『purpose』であり『objective』ではない。
規格に登場しない語の定義を定めるのはマカ不思議である😧
![]() 「我々の知らないこと、知らせたくないことがあるのかな?
「我々の知らないこと、知らせたくないことがあるのかな?
ところで認証機関が独自の規格解釈しても即批判する気はないけど、認定機関の要望だとか指導と言うのは汚いよね」
![]() 「どんなことでしょうか?」
「どんなことでしょうか?」
![]() 「1996年版のとき、通勤の環境影響を評価していないとダメだと言われた。1996年の規格では『組織が管理でき、かつ影響が乗ずると思われる環境側面を特定する手順……』を確立しとある。
「1996年版のとき、通勤の環境影響を評価していないとダメだと言われた。1996年の規格では『組織が管理でき、かつ影響が乗ずると思われる環境側面を特定する手順……』を確立しとある。
2000年頃、審査員が審査で『
私の先輩が本当かな?と思ってUKASにEメールを送ったわけです。すると返事がきました。
『UKASは規格解釈を決めることはしない。アドバイスであるが、規格では組織が管理でき、かつ影響が乗ずると思われるなら環境側面を特定しなければならないとある。影響を与えることができると考えたら、通勤の環境側面も該否を特定しなければならないだろう』
つまり規格要求通りしなさいと言うだけだ。
自分が言いたいことを権威者とか権限のある機関が言っているというのは詐欺ですよ。犯罪です。
有益な環境側面も審査員が『JABが言った』と語ったのを聞いたことがある。まさかJABがそんなことを言うはずがない。問い合わせていないけど、誰かがJABの虎の威を借りたんだろうなあ〜
注:2024年現在、堀江貴文氏とか前沢友作氏などが投資の広告に顔を載せているのを見たことがある。実はまったく無関係で、写真を無断で使われたと騒ぎになっている。
まさに虎の威を借りる狐である。
実を言って、私は堀江氏たちの広告は本物だと思っていた。
![]() それから環境側面は評価して決めなくてはならないって騙る審査員が多いよね。JIS訳では『評価』なんて語っていない。1996年版、2004年版、そして2015年版ともね、
それから環境側面は評価して決めなくてはならないって騙る審査員が多いよね。JIS訳では『評価』なんて語っていない。1996年版、2004年版、そして2015年版ともね、
2015年版を言えば『決定』で、評価というじゃない。『評価』と『決定』じゃ大違い。日本語の辞書を引いてもダメですよ。基の英文で使われている単語の意味を考える必要があります。
規格で使われるひとつの英単語は、常に日本語では同じ言葉に訳されるというのが原則です。『評価』と訳されている原語は『evaluate』だから『to judge how good, useful, or successful something』つまりそれが『いかほど良いか、有効か、うまくいくかを判定』しなくちゃならないことになる。実際にはこの文章は『決定』だ。決定も国語辞典を引いてもしょうがない。『決定』は『determine』だから『はっきりさせる』くらいのイメージじゃないのかな。
小さな違いだけど、その厳密さと手間は大違いでしょう。
嘘つくならもっとうまくしないとね、ばれると恥です」
![]() 「そういうのは悪質な誘導は多いのですか?」
「そういうのは悪質な誘導は多いのですか?」
![]() 「多いと思いますよ。とはいえ証拠なるものは審査で審査員が語ることをしっかりと記録しておくしかない。規格にないことを審査では『shall』だと語っているのは多いからね。
「多いと思いますよ。とはいえ証拠なるものは審査で審査員が語ることをしっかりと記録しておくしかない。規格にないことを審査では『shall』だと語っているのは多いからね。
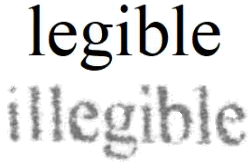 |
|
|
「分かりにくい文章」は芳しく ないというのは理解するが、そ の判断が微妙だから、規格要求 にするには不適だろう。 |
有名なものに『明瞭な文章』を『わかりやすい文章』と主張するのは多い。
なにが発端かと思っていたけど、某認証機関の社長たちが書いた本の中でその間違いを解説していたのを見つけた。間違うなと解説したのでなく、その本ではlegibleをしっかり間違えて解説している。
書籍に書くと10年も20年も残るから恥ずかしい」
![]() 「磯原さんは長年ISO担当をしていたのですか?」
「磯原さんは長年ISO担当をしていたのですか?」
![]() 「長くはないですね、本社に転勤してからなので6年です」
「長くはないですね、本社に転勤してからなので6年です」
「私はISO9001も14001も日本で最初にチャレンジした一人ですよ」
![]() 「それはすごいですね。弊社ではそういう人たちをISO第一世代、彼らが作ったしくみを継承した人たちを第二世代、そして今綻びかけているのを直そうとする人たちを第三世代と呼んでいます」
「それはすごいですね。弊社ではそういう人たちをISO第一世代、彼らが作ったしくみを継承した人たちを第二世代、そして今綻びかけているのを直そうとする人たちを第三世代と呼んでいます」
![]() 「じゃあ私は第二世代ですよ」
「じゃあ私は第二世代ですよ」
![]() 「実は当社の第二世代は、第一世代が作った仕組みを金科玉条として、見直しをしてはいけないと思っている人が多いのです。それで良いイメージはありません。
「実は当社の第二世代は、第一世代が作った仕組みを金科玉条として、見直しをしてはいけないと思っている人が多いのです。それで良いイメージはありません。
どんな仕組みも時代が変われば、見直しをしなければならないのは自明です。触らぬ神に祟りなしという逃げ腰はいけませんね。
おっと、それは弊社の話です。御社では世代が変わろうと常にチャレンジ精神で見直しを重ねていることと思います」
「倉田君はズバリその第二世代のようだね。なにかあると変えてはいけないという」
![]() 「私はそんなことありませんよ」
「私はそんなことありませんよ」
「それは良かった、じゃあ今回の改革を君が引っ張っていってくれると期待するよ」
![]() 「えっ」
「えっ」
![]() 「実は弊社ではもう第3世代の次の第4世代が登場しています」
「実は弊社ではもう第3世代の次の第4世代が登場しています」
「ほう〜、それはいかなるものですか?」
![]() 「ISO認証を返上してしまうというか、ISOMSよりも会社のMSを大事にする発想ですね」
「ISO認証を返上してしまうというか、ISOMSよりも会社のMSを大事にする発想ですね」
「おっしゃること良く分かります。
私の最後のご奉公はISO第4世代を育成することかな」
![]() 「別に育成することもありませんよ。私は常に現状に不満を持っていろいろしてきました。その結果、先ほどの第一世代からお前は第4世代だと言われました。世代は育てなくても、自然発生するのです」
「別に育成することもありませんよ。私は常に現状に不満を持っていろいろしてきました。その結果、先ほどの第一世代からお前は第4世代だと言われました。世代は育てなくても、自然発生するのです」
![]() 「この磯原君は宮本武蔵のような人で『万事において我に師匠なし
「この磯原君は宮本武蔵のような人で『万事において我に師匠なし
もちろん『我以外皆我師』というのも、これまた武蔵流です」
![]() 「田村さんは冗談が得意ですから。私はそれほど人間ができていません。
「田村さんは冗談が得意ですから。私はそれほど人間ができていません。
ただ仕事に誠実でありたいと思っています。良い仕事をしたい。ルールを守りたい。それを妨げるのは排除しなければなりませんね。
無駄なことを増やそうとするISO審査は是正させる。会社のトップ方針に従わないことを要求するのは止めてもらう。常にそう考えています」
![]() 「磯原さんの行動原理は、一本筋が通っていて、決して変わらないのですね」
「磯原さんの行動原理は、一本筋が通っていて、決して変わらないのですね」
![]() 「時代は変わりました。同僚とシンクロして仲良く働くのではなく、個人個人が、会社の方針に基づき、最高のパフォーマンスを出す、そういう時代ですよ。
「時代は変わりました。同僚とシンクロして仲良く働くのではなく、個人個人が、会社の方針に基づき、最高のパフォーマンスを出す、そういう時代ですよ。
そういう人が自由に動けるようにするのが私の役割です」
「我々の上司も田村さんのような方で幸運です。我々も磯原さんに負けないような個人のスキルアップと働く意欲を持たねばなりません」
・
・
・
・
![]() 「H電気さんがどういう方向で見直しをするのかは分かりませんが、ひとこと申し上げれば弊社の真似はしないことです」
「H電気さんがどういう方向で見直しをするのかは分かりませんが、ひとこと申し上げれば弊社の真似はしないことです」
「とおっしゃいますと?」
![]() 「まずお断りしておきます。我々が一般論としてベストであるわけではない。自分たちにとってもベストではないでしょう。
「まずお断りしておきます。我々が一般論としてベストであるわけではない。自分たちにとってもベストではないでしょう。
どの会社でもISO認証について困っていることがある。費用もかかる、手間もかかる。審査員の独断・独善もある。現状を改善するにはどうするかとなると、それぞれが困っていることを解決するしかありません。弊社には弊社の問題があり、御社には御社の問題があり、それはイコールではありません。
そしてまた各社には固有の制約条件があり、その条件下で解決しなければなりません。
現実には100点満点などなく、妥協することになる。
いくつも問題があれば、半分解決できれば良しとすることもある。
だから最適解は会社によって決まります。
それも我々が決めるのではありません。その環境下においては必然的に落としどころが決まってしまうということです」
「それは我々も同じ見解です」
![]() 「そこまで理解されているなら、できることをやるだけです」
「そこまで理解されているなら、できることをやるだけです」
![]() 本日 予想する苦情
本日 予想する苦情
タイトルが「![]() 清野の挑戦」とあるけど、「
清野の挑戦」とあるけど、「天野の挑戦」ではないかと言ってはいけない。
なんとかしようと思っていたのだが、なかなかうまくつながらないのだ。
しかし上手いことを思いついた。
「清野の(始めた)挑戦」の(始めた)を略したと思ってください。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
年季奉公という言葉は、ビルテナントの場合は特別な意味で使われる。新しいビルの入居者が埋まらないときに、ビルを建てた建設会社に多少店賃を割り引いて3年とか5年とか期限を切って入ってもらうことを言う。その対象範囲には建設関係はもちろん、エレベーター会社とか什器を納めたところ、その他 通常の取引先や下請け会社も義理で入居する場合もある。 年季が開けるとほとんどの店子は出ていくのも常のこと | |
注2 |
宮本武蔵の書いた「五輪書」の中にある言葉 驚くことはない、私もISO規格の読み方など習ったことはない。すべて試行錯誤。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |