*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
H電気のISO事務局のメンバーは作業を進めている。来週、審査を依頼している品質環境センターに行って、打ち合わせの予定だ。
そこで正しい規格解釈で審査してほしいということ、余計なアドバイスをしないでほしいということ、そういったことを要求する予定だ。
|
|
|
 |
だが2023年の現実は、今なお「有益な環境側面」が存在し、環境実施計画の目標が「3年以上」と語るのにはどういうことなのか、清野には分らない。
もっとも隣の席でおなじくパソコンを叩いている倉田の横顔を見ると、それをおかしいと思っていないのは明らかだ。考えることを止めたのか、気が付かないのか、聖書に書かれたことすべてを、事実と信じるキリスト教原理主義者のようだ。
そういや、1990年代半ば、いそいそフォーラムにISO原理主義者ってのがいたな(笑)
認証機関への要望はほぼまとまった。
規格を素直に読めば要求にないものを要求だとしていた事項。いわゆる横出し上乗せである
認証機関独自の要求を定めるなら、それを文書にして事前に審査を受ける企業に周知しなければならないし、その旨を審査契約に「ISO○○規格によって」だけでなく「ISO○○規格及び○○認証機関の定める要求によって」と記載しなければ、民法の契約違反になるのは明白だ。
注:ISO審査において、該当する認証規格以外の要求事項を追加することは禁止されていない。
卑近な例では認定機関のロゴマークの扱いや認証の表記についてなどがある。複合審査もあるし、MS審査と同時に製品検査を行うこともありうる。
いずれにしても審査契約で審査基準の同意がなければならない。
無断で認証機関あるいは審査員独自の要求をすることは、ドラえもんのジャイアンのように自分勝手のやりたい放題であるが、法的に見れば理論武装をしておらず単なるでたらめである。
・
・
・
・
倉田が清野に話しかけてきた。この人仕事に飽きてきたなと清野は心中思う。
![]() 「あのね、ISO審査員とか認証機関に今我々がまとめているようなことを、お願いしたら気を悪くしないですかね?」
「あのね、ISO審査員とか認証機関に今我々がまとめているようなことを、お願いしたら気を悪くしないですかね?」
![]() 「えっ、どうして?」
「えっ、どうして?」
![]() 「だって向うは会社を良くしようとしているわけですよね。それを不要とかルールではと言うのは失礼かなと」
「だって向うは会社を良くしようとしているわけですよね。それを不要とかルールではと言うのは失礼かなと」
![]() 「うーん、まず審査とは指導ではないですよね」
「うーん、まず審査とは指導ではないですよね」
![]() 「指導ではない? そうなの?」
「指導ではない? そうなの?」
![]() 「倉田さん、しっかりしてくださいよ。ISO審査は教育とか指導ではなく、裁判とか試験のようなものですよ。ISO規格の要求事項を満たしているか調べて、OK・NGを判定することです」
「倉田さん、しっかりしてくださいよ。ISO審査は教育とか指導ではなく、裁判とか試験のようなものですよ。ISO規格の要求事項を満たしているか調べて、OK・NGを判定することです」
![]() 「でもそれじゃ『改善したほうが良い』とか『すべきだ』というのはどうしてだい?」
「でもそれじゃ『改善したほうが良い』とか『すべきだ』というのはどうしてだい?」
![]() 「そういう発言そのものが、間違っているのでしょう。
「そういう発言そのものが、間違っているのでしょう。
もっとも正確に言えばISO17021-1で改善の機会を示すことだけはOKのはず」
![]() 「そうなの?
「そうなの?
いや、そうだとすると今までの審査で、目標が低いとか改善しなさいと言われていたのは全部間違いだったの?」
![]() 「質問でなく、指導や提案を語る審査員は間違いなのです。そしてそういう審査員の間違いを見逃していた私たちも間違っていたのでしょう」
「質問でなく、指導や提案を語る審査員は間違いなのです。そしてそういう審査員の間違いを見逃していた私たちも間違っていたのでしょう」
![]() 「そうすると過去のISO審査での応答集を作り、審査員の考え通りしようとしたことは全部無意味だったの?」
「そうすると過去のISO審査での応答集を作り、審査員の考え通りしようとしたことは全部無意味だったの?」
![]() 「たぶんそうだと思います」
「たぶんそうだと思います」
![]() 「ショックだぁ〜。足元が崩れるようだ」
「ショックだぁ〜。足元が崩れるようだ」
![]() 「倉田さん、まだどうなるか分かりません。
「倉田さん、まだどうなるか分かりません。
認証機関に行って私たちの要望を話しても、向こうは私たちを門前払いするかもしれません」
![]() 「私は10年ほどISO事務局をしてきて、立派な仕事だと思っていたけど、本当はあまり重要な仕事じゃなかったのかなあ〜」
「私は10年ほどISO事務局をしてきて、立派な仕事だと思っていたけど、本当はあまり重要な仕事じゃなかったのかなあ〜」
数日後、倉田と清野は品質環境センターを訪問した。
訪問前に、天野リーダーからは次のようなことを言われた。
「絶対にこちらの要求を通すなんて構えていくことはない。軽くジャブをかます感じで、我々もレベルが上がってきたから審査では規格とのコンペアをしっかりお願いしたいというニュアンスで交渉してきてほしい。
今回は顔合わせ、次で
そしてお願いだが、我々から見ておかしい要求事項はいかなる意味があったのかを、それとなく聞いてきてほしい」
遠くまで行くなら途中、決心を新たにとなるのだろうが、山手線で数駅だから気合を入れる前に敵地についてしまう。
途中の電車で倉田は弱気になったのか、交渉は清田がメインで話してほしいという。清田もこのところ倉田がファイトのない仕事をしていたから、ハイと答えた。
アポイントを取っていたので無人受付のインターホンで営業の鈴木部長にお会いしたと伝えると、すぐに男性ふたりが現れて応接室の一つに案内された。
| 堀川参事 |  |
 |
清野 | ||||||
| 鈴木取締役 |  |
倉田 | |||||||
名刺交換である。60前後の人が営業部長で取締役という肩書の鈴木さん、50前後が技術部参事という堀川さんである。
こういう会社では部長とか参事なんて職制とか権限とはリンクしていないのだろうなと、清野は名刺を押し頂きながら思う。技術部って何を設計するのだろう? これも謎だなと思う。
おっと倉田も清野も肩書はもちろんない。
「御社は今年12月に維持審査の予定となっております。まだ9月ですから、まだまだ時間があります。今日はどのようなお話でしょうか?」
![]() 「私どもも御社の認証を得て20年になります。今までは御社の指導を受けていると感じております。今後の審査について私どもの希望を述べまして、それに対応していただきたいという要請です」
「私どもも御社の認証を得て20年になります。今までは御社の指導を受けていると感じております。今後の審査について私どもの希望を述べまして、それに対応していただきたいという要請です」
「あのですね、ISO審査は指導ではありません。外交辞令であっても指導を受けたなどと言われますと、差しさわりがあります。誤解を招く恐れのある表現は止めていただきたいです。ご理解いただきたいと思います」
![]() 「あら、そうでしたか。昨年もそうですが御社の審査員は皆さん、指導するとか、アドバイスですと語っておられますので、意識して指導されていると思っていました」
「あら、そうでしたか。昨年もそうですが御社の審査員は皆さん、指導するとか、アドバイスですと語っておられますので、意識して指導されていると思っていました」
「おおっ、審査員がそう語っていますか。あってはならないことです。
おっしゃるように過去にはあったかもしれませんが、今後は口が滑っておかしなことを言わないよう徹底いたします」
![]() 「指導とかアドバイスと言っても、鈴木取締役さんのイメージと私のイメージが同じかどうか分かりませんので、今申しました今後は指導はいりませんという事例を説明いたします」
「指導とかアドバイスと言っても、鈴木取締役さんのイメージと私のイメージが同じかどうか分かりませんので、今申しました今後は指導はいりませんという事例を説明いたします」
清野は過去に審査で説明を受けた、おかしな規格解釈をリストしたA4数ページの綴じた物を二人に渡す。
![]() 「私どもも20年経ちまして少しは進歩したと思いますので、今後このような説明は不要です。以後アドバイスはいりません」
「私どもも20年経ちまして少しは進歩したと思いますので、今後このような説明は不要です。以後アドバイスはいりません」
鈴木と堀川はだまって首を縦に振った。
![]() 「それから今までに御社の審査員の方から、適合・不適合を出され、あるいは問題としてアドバイスをいただいたもののリストです。
「それから今までに御社の審査員の方から、適合・不適合を出され、あるいは問題としてアドバイスをいただいたもののリストです。
実は、その後、業界のISOの研究会などで他社の意見をお聞きしたものに、我々の考察を右端に記載しております」
「すごい数ですね」
![]() 「リストしましたものは複数の認証を受けた企業や、少数ではありますが他の認証機関に問い合わせて確認しておりますので、弊社の希望は妥当と思います。
「リストしましたものは複数の認証を受けた企業や、少数ではありますが他の認証機関に問い合わせて確認しておりますので、弊社の希望は妥当と思います。
これらについては今後、御社で適合の判定をしていただきたいと思います。
例えば2015年改定以前は、環境実施計画の目的の期間は3年以上必要と審査で言われておりました。改めて規格を呼んでもその根拠が見つかりません。
過去に目的が3年以内であるという不適合はたくさん出されていますが、それは過去より適合であったのではないかと思われます」
「まあ、規格解釈も時とともに変化しますからね」
![]() 「しかしながら他社での審査結果を見れば、ここ2・3年で解釈が変わったとは思えません。過去より適合であったのではないでしょうか」
「しかしながら他社での審査結果を見れば、ここ2・3年で解釈が変わったとは思えません。過去より適合であったのではないでしょうか」
![]() 「計画が目的用と目標用のふたつとは、どういうことですか?」
「計画が目的用と目標用のふたつとは、どういうことですか?」
![]() 「2015年改定前は、環境実施計画は目的のものと目標のもの二つが必要と言われておりました。過去に計画が目的対応と目標対応のふたつないものは不適合とされています」
「2015年改定前は、環境実施計画は目的のものと目標のもの二つが必要と言われておりました。過去に計画が目的対応と目標対応のふたつないものは不適合とされています」
![]() 「えっ」
「えっ」
「2015年改定では目標はなくなり目的だけになりましたので、現在は不適合が起きなくなりました。そういった問題は過去のものとご理解ください」
![]() 「ちょっとお聞きしたいのですが、目的・目標の計画がふたつないとして、不適合を頂いたのは直近で一昨年の2021年でした。2021年は大幅改定があった2015年より最近ですね。
「ちょっとお聞きしたいのですが、目的・目標の計画がふたつないとして、不適合を頂いたのは直近で一昨年の2021年でした。2021年は大幅改定があった2015年より最近ですね。
いつ・どんな理由で判断基準が変わったのでしょうか?」
鈴木は歯を食いしばったような表情から一転してにこやかに作り笑いをして、
「ISO規格の理解も日々変化していますから、変わることもありますよ」
![]() 「規格解釈が変わることはあるかと思いますが、一夜にして判断基準が変わるとかあるのでしょうか。
「規格解釈が変わることはあるかと思いますが、一夜にして判断基準が変わるとかあるのでしょうか。
それよりも、変わったことを客先つまり私どもに通知しないとは、おかしいですよね。
最低限そのときは認証を受けている企業に対して、その旨を広報しなければならないでしょう」
「おっしゃる通りですが、実際には手が回りません」
![]() 「過去に何度も不適合と言われて、今お宅に伺って判断基準を見直してほしいとお願いすると、既にその解釈は変わっているとは、おかしくありませんか?
「過去に何度も不適合と言われて、今お宅に伺って判断基準を見直してほしいとお願いすると、既にその解釈は変わっているとは、おかしくありませんか?
もし本日この場に来ていなければ、年末に行う審査では旧来の判断基準で審査されたのではありませんか」
「そのようなことはありません」
![]() 「それでしたら、もし本日私どもがお邪魔していなければ、御社の計画が一つで良いという解釈の変更は、いつ私どもに伝達する予定だったのでしょうか?
「それでしたら、もし本日私どもがお邪魔していなければ、御社の計画が一つで良いという解釈の変更は、いつ私どもに伝達する予定だったのでしょうか?
顧客に通知する計画書に進捗実績を記入したものがありますか? そういうものを見せてもらいたいですね。
そしてこの雰囲気ではそれ以外にも解釈が変わったものがありそうです」
「おかしいと言われればおかしいですが、現実には対応できないところもあり、後追いになっているということです」
![]() 「清野さん、とりあえず解釈については了解されたことを確認しましょう。解釈の変遷については別問題としてはどうですか?」
「清野さん、とりあえず解釈については了解されたことを確認しましょう。解釈の変遷については別問題としてはどうですか?」
![]() 「倉田から提案がありましたが、とりあえずお渡しした資料に記載した各項目について是非を回答していただけますか」
「倉田から提案がありましたが、とりあえずお渡しした資料に記載した各項目について是非を回答していただけますか」
鈴木と堀川は、紙を眺めていたが顔を上げる。
![]() 「鈴木部長、よろしいのではないですか」
「鈴木部長、よろしいのではないですか」
「ここに書かれた25件については、すべて適合とみなすこととします」
![]() 「結構です。それじゃ同じものを2枚改めてお渡ししますから、両方に日付とサインをいただけますか。とりあえずそのご了解が得られたら、本日お宅を訪問した目的は達成です」
「結構です。それじゃ同じものを2枚改めてお渡ししますから、両方に日付とサインをいただけますか。とりあえずそのご了解が得られたら、本日お宅を訪問した目的は達成です」
「それはよかったです」
鈴木は日付とサインをして1枚を清野に手渡す。
![]() 「それではお話を戻しますが、規格解釈はときとともに変わるが、それを御社から見て顧客である審査を依頼している企業には連絡はできないということでしたね」
「それではお話を戻しますが、規格解釈はときとともに変わるが、それを御社から見て顧客である審査を依頼している企業には連絡はできないということでしたね」
「いえ、できないわけではなく、すべてに対して適時な対応は難しいかと」
![]() 「実を申しましてスラッシュ電機さんを訪問して、ここにリストされた疑問点について審査でどのように判定されているのかと問いました。すべて過去より適合判定を受けていたとのことです。
「実を申しましてスラッシュ電機さんを訪問して、ここにリストされた疑問点について審査でどのように判定されているのかと問いました。すべて過去より適合判定を受けていたとのことです。
数か月の話ではなく何年も前とのことでした。
ということは、
「とんでもありません。さようなことはございません」
![]() 「御社との審査契約書では『ISO14001/JISQ14001および関連する審査規格に基づいて審査を行い、適合の場合認証する」と記述してありますね?
「御社との審査契約書では『ISO14001/JISQ14001および関連する審査規格に基づいて審査を行い、適合の場合認証する」と記述してありますね?
「確かにそういう文言です」
![]() 「ISO14001に書いてない要求事項で不適合を出すのは、民法の契約不履行
「ISO14001に書いてない要求事項で不適合を出すのは、民法の契約不履行
「ISO審査での問題を民事訴訟で争うということですか?」
![]() 「契約違反なら他の方法がありません。
「契約違反なら他の方法がありません。
商取引の問題、納期、品質、コストについて裁判で争うことは珍しくありません。審査契約とは審査というサービス提供の契約です。通常の商取引と何の違いもない」
「ISO審査で民事訴訟なんて聞いたことがない」
注:私が知る限り認証において民事訴訟になったのは、ISO認証していた某大手商社が所有していた土地に、地下水汚染が発覚したので認証停止しようとして、それに対して商社側が……という事例だけだ。
2000年から2010年に地下水汚染が発覚して認証停止とか認証辞退が多発した。
ISO認証は遵法を保証しないし、地下水汚染は違法でさえない。だから地下水汚染が発覚しても、法律的にもISO審査契約的上からも、停止も辞退も必要ないと考える。
多くの企業は評判が悪くなると判断して潔く(それとも争う価値がないと考えたか)辞退したが、契約を基にすれば認証停止されたら訴訟になってもおかしくない。
私がISO9001審査員の研修を受けたとき、審査途中で作業指導した結果、損害が発生して賠償請求の裁判が起こされたことがあると習った。
詳細は教えてくれなかったが審査で訴訟が起きたのは皆無ではないようだ。
![]() 「審査基準を『ISO14001と関連する審査規格』で契約しておいて、それ以外の理由を持ち出して不適合とするのは契約違反でしょ。そんな無茶が通用するかどうか裁判所に判断してもらうしかありません」
「審査基準を『ISO14001と関連する審査規格』で契約しておいて、それ以外の理由を持ち出して不適合とするのは契約違反でしょ。そんな無茶が通用するかどうか裁判所に判断してもらうしかありません」
「そんなあなた……」
![]() 「私どもはその覚悟があります。
「私どもはその覚悟があります。
ええと…もうひとつ、そのリストに記載が漏れてしまったのですが、有益な環境側面をどのようにお考えでしょうか?」
鈴木は堀川の顔を見る。裁判の話で二人とも相当ショックを受けたようだ。
お互い気まずそうな顔で見合わせたまま、しばし言葉を発しない。
「普通の企業は有害な環境側面を忘れることはありませんが、有益な環境側面を取り上げるのを忘れるところが多いのです。それで忘れてはいけないということから、有益な環境側面を取り上げるようにわざわざ解説しているのです」
![]() 「なるほど、しかし不思議ですね。先ほどのお話では指導やアドバイスはいけないということでしたが、有益な環境側面を忘れるなと注意喚起することはOKなのですか?」
「なるほど、しかし不思議ですね。先ほどのお話では指導やアドバイスはいけないということでしたが、有益な環境側面を忘れるなと注意喚起することはOKなのですか?」
「まあ具体的に対策を指導するわけではないのでよろしいかと」
![]() 「弊社の審査において環境側面すべてに有益・有害の区分をしていないとして、不適合をいただいたこともありますが、それも指導の範疇でしょうか。
「弊社の審査において環境側面すべてに有益・有害の区分をしていないとして、不適合をいただいたこともありますが、それも指導の範疇でしょうか。
指導して従わなければ不適合にするとは、新たな要求事項の追加ですよね?
企業側から見れば不適合というのは不合格ですから、非常に重大と受け止めます」
「まあそれも注意喚起ということで」
![]() 「注意喚起した結果従わないなら、規格要求にないことで不適合にすることは妥当なのですか?
「注意喚起した結果従わないなら、規格要求にないことで不適合にすることは妥当なのですか?
つまり有益、有害の区分を表示しないと不適合なのかです」
「難しいですね。お宅様は問題だという認識ですね。
それと御社はその件を異議申し立てしていませんね。ISO認証制度の正しい手順は、認証機関に異議申し立てすることです」
![]() 「まず弊社では審査時点で、有益な環境影響、有害な環境影響を生じる環境側面を把握していたつもりです。ですから注意喚起を受ける状況ではなかったと認識しています。
「まず弊社では審査時点で、有益な環境影響、有害な環境影響を生じる環境側面を把握していたつもりです。ですから注意喚起を受ける状況ではなかったと認識しています。
そのリストに規格要求にない有益、有害の区分の記載がないから指摘事項とされたことに異議申し立てはしてないのですが、その場で審査員に抗議しても相手されなかったということです。詳細な記録として速記録があります」
「積極的な指導であったとご理解いただけますか?」
![]() 「問題は指導なのか、不適合なのかということですね。その場では修正しないと審査を進めないと言われました。それは強要
「問題は指導なのか、不適合なのかということですね。その場では修正しないと審査を進めないと言われました。それは強要
「まあ、勇み足であったのでしょう。しかしその経緯を犯罪にしたいのですか」
![]() 「犯罪にする・しないではありません。どちらにしても民事訴訟ですから、御社が敗訴になれば損害賠償の話になるだけです。私どもは上司、会社に対して正しい仕事をしていたという証明になります。
「犯罪にする・しないではありません。どちらにしても民事訴訟ですから、御社が敗訴になれば損害賠償の話になるだけです。私どもは上司、会社に対して正しい仕事をしていたという証明になります。
そもかく私どもは審査員が不適合にしたことに納得できません。ですから最終的には、裁判で決着つけるしかないと思うのです。
そもそも論になりますが、ISO14001では指導的立場の〇田先生が『環境側面には有益も有害もない』とあちこちで講演されたのは2008年です。御社では理屈的に有害な環境側面とか有益な環境側面があると考えているのですか?」
![]() 「有害な環境影響を出すのが有害な環境側面で、有益な環境影響を出すのが有益な環境側面です」
「有害な環境影響を出すのが有害な環境側面で、有益な環境影響を出すのが有益な環境側面です」
| 良く聞かされる理屈だが、そもそも環境側面の定義を読み直すと、環境側面から多種多様な環境影響が出るわけで、有益だけ、有害だけとは考えられない。 | ||
![]() 「ご冗談をおっしゃる。
「ご冗談をおっしゃる。
ひとつの環境側面から良い環境影響も出ますし、悪い環境影響も出ますよ。もし悪い環境影響しか出ない環境側面なら、人はそれを利用するはずがありません」
![]() 「ほうー、有害な環境側面で、有益な環境影響を出すものがありますか?」
「ほうー、有害な環境側面で、有益な環境影響を出すものがありますか?」
![]() 「有害な環境影響を出す環境側面のティピカルなものと言えば、電力の使用、廃棄物、毒物でしょうか。
「有害な環境影響を出す環境側面のティピカルなものと言えば、電力の使用、廃棄物、毒物でしょうか。
電力の使用による有益な環境影響は、照明であり空調であり動力です。まさかそれを有害な環境影響とは言わないでしょう。
私たちは、石油を掘り出し、電力を作り、配電までの悪影響より、電気利用の効用が大きいから使うのです。
 廃棄物は文字通り、使われた何かの寿命が来たり、あるいは梱包材なら用途を果たしたものです。つまり何ものかが社会や人類に貢献した結果です。
廃棄物は文字通り、使われた何かの寿命が来たり、あるいは梱包材なら用途を果たしたものです。つまり何ものかが社会や人類に貢献した結果です。
毒物といえば青酸カリが思い浮かびますが、メッキするには……」
注:堀川が「有益な環境側面」という表現と使い、清野が「有益な環境影響を出す側面」と表現していることに気付いてほしい。
![]() 「分かりました、分かりました。おっしゃること十二分に理解しました。目から鱗です。しかもそんな簡単なことをなぜ気が付かなかったのか慙愧です」
「分かりました、分かりました。おっしゃること十二分に理解しました。目から鱗です。しかもそんな簡単なことをなぜ気が付かなかったのか慙愧です」
![]() 「ご理解いただきありがとうございます。
「ご理解いただきありがとうございます。
一つの環境側面をまとめて有益とか有害と単純化せずに、複式簿記のように貸方・借方の左右を厳密に記述したら、いかに有益が大きいかが分かるでしょう。
とにかくすべての環境側面は有益な環境影響も有害な環境影響も出入りしているのです。そして総合すると人類に役立つからこそ、人々が利用しているのです。
となると有益な環境側面というものをあると考えることは間違いですね。私たちが取り扱う環境側面はすべて有益な環境影響を持っている。しかし有害な環境影響もあるから、しっかりと管理しなければならないというだけです。
有益な環境側面には、もっと不思議がございます。有益な環境側面というのはうつろうものなのですか?」
注:「うつろう」とは 1.移動する 2.心変わりする 3.移り変わるもの 4.衰えていくもの
要するにアンステイブルだ。
![]() 「うつろうとは?」
「うつろうとは?」
![]() 「2008年洞爺湖サミットがありました。当時、白熱電球を蛍光灯電球に変えようなんて運動がありましたね。審査員の方が有益な環境側面として蛍光灯電球を例に挙げて説明していました。
「2008年洞爺湖サミットがありました。当時、白熱電球を蛍光灯電球に変えようなんて運動がありましたね。審査員の方が有益な環境側面として蛍光灯電球を例に挙げて説明していました。
最近審査に来られた方は蛍光灯電球を有害な環境側面の例に、LED電球を有益な環境側面の例に解説していました。
不思議ですね、有害な環境影響を出すのが有害な環境側面なら、蛍光灯電球は昔から有害な環境側面ではないのですか?
それとも10年前は電球型蛍光灯は有益な環境影響だけを出していたのですが、10年後の今はなぜか有害な環境影響ばかりになったのでしょうか?
あるいは時と場合によって有益が有害に変わるほど、有益な環境側面という考えはいい加減なものですか?」
| 白熱電球 | 電球型蛍光灯 | LED電球 | ||
 |  |  |  |  |
| 俺は最初から、 | 今は悪者、悲しい |
あなたは間違えたのではなく環境側面というものを理解していない
「また難題ですな、堀川さん、説明して」
![]() 「うーん」
「うーん」
![]() 「過去から有益な環境側面と言われたものは、そもそも環境側面じゃなかったのです。
「過去から有益な環境側面と言われたものは、そもそも環境側面じゃなかったのです。
省エネ工事は良い環境側面だというのは語義からしてハチャメチャです。
通常の工事からの廃棄物は有害な環境側面だが、省エネ工事から発生する廃棄物は有益な環境側面だなんて珍説も審査でお聞きしました。
バカバカしいと思いませんか」
![]() 「えっと、清野さんは何を言いたのでしょう?」
「えっと、清野さんは何を言いたのでしょう?」
![]() 「有益な環境側面も有害な環境側面もないということです。そして更に大きな問題は、審査員が環境側面の概念を理解していないことです。
「有益な環境側面も有害な環境側面もないということです。そして更に大きな問題は、審査員が環境側面の概念を理解していないことです。
しかし私どもでは過去の審査で、御社から有益な環境側面を取り上げていないと不適合、また有益と有害を区別していないと不適合、いろいろと頂きました。
そういった不適合を出された顛末を、御社に説明していただきたいです。
弊社の汚名返上のために、そして御社の名誉挽回のためでもあるわ」
「えっ、この場でですか?」
![]() 「いえいえ、これは大きな問題ですから口頭では困ります。弊社としましても、過去に何度も不適合を出されておりますから、これに関して御社として
「いえいえ、これは大きな問題ですから口頭では困ります。弊社としましても、過去に何度も不適合を出されておりますから、これに関して御社として
注:「顛末書」とは仕事上のトラブル・不始末・不祥事などが発生した場合に、発生日時、経緯などを説明し、問題が起きた原因、現在の対処状況や再発防止策などを報告する文書。
「始末書」とは、仕事上のトラブル・不始末、又無断欠勤や遅刻など就業規則違反をしたときに、謝罪・反省を表す文書。
私は始末書は一度だけだが、顛末書は何度か書かされた。いや、それはどうでも良い。
「それは……簡単には受けられませんね」
![]() 「これは私 担当者としての要請ではありません。企業として不適合を出されたということは、弊社の環境マネジメントシステムに不足があったという重大な問題です。それが解釈の変化で適合になるなら、その経緯そして過去に問題とされたことについて説明を受ける権利があります。
「これは私 担当者としての要請ではありません。企業として不適合を出されたということは、弊社の環境マネジメントシステムに不足があったという重大な問題です。それが解釈の変化で適合になるなら、その経緯そして過去に問題とされたことについて説明を受ける権利があります。
鈴木取締役が税務署から脱税と追求された後に勘違いでしたと放免されたとしましょう。無実で良かったと納得しますか。しっかりと経緯について説明を求めるでしょう。拘束された被害補償も必要です。
私どもは御社の審査において度重なる不適合を出されております。後で問題でなかったと言われても、過去の多数の不適合がなくなるわけでもなく、必要ない是正処置に投じた工数や費用が元に戻るわけではありません。御社の正式な弁明を求めるのは当然です」
「内部で検討させてもらいます」
![]() 「私どもは極めて大きな問題としてとらえております。よろしくお願いします。
「私どもは極めて大きな問題としてとらえております。よろしくお願いします。
その他、過去の審査で有益な環境側面がないという不適合、有益・有害を区別していないという不適合、種々の有益な環境側面に関わる不適合も頂いております。
それらについても同様の顛末の報告をお願いします。
話を戻しますが、先ほど鈴木部長さんのサインをいただいた件については、今後の審査で不適合にならないということの保証をいただきました。
それだけでなく、あのリストにある項目についても過去においてはなぜ不適合だったのか、今現在適合なのはなぜかの顛末をまとめて、有益な環境側面と共に報告いただきます」
「それは弊社の会社名で出すのですよね」
![]() 「もちろんです。私どもは過去より幾度も不適合をいただき、その理解と対応に苦慮してきました。そのために莫大な費用も時間もかけております。
「もちろんです。私どもは過去より幾度も不適合をいただき、その理解と対応に苦慮してきました。そのために莫大な費用も時間もかけております。
過去に不適合であるという根拠、今は適合である根拠、なぜ判断が変わったのかの経緯、そして判断が変わったときなぜ客先に通知しなかったのかという事情を不適合を出した側に報告を求めます。
実を言いまして、御社の審査所見報告書において、ISO17021-1で要求する証拠と根拠の記載が不完全なものが極めて多い。それはそのまま審査所見報告書そのものがISO17021-1に反しています」
注:ISO17021-1は2015年発行で、物語の時点で存在している。それ以前は枝番がなかったはず。
倉田はびっくりした顔で清田を眺めている。倉田より清田は5・6歳若いのにすごいなと思う。最近までこんな風じゃなかったのに……
「おっしゃる通りですね。我々にとって大問題であることは、御社にとっても大問題であることは理解します。我々には説明責任があります。
趣旨は承りました。すぐにはできませんので時間を……1週間ほどいただきたいと思います」
![]() 「結構です、それでお願いします」
「結構です、それでお願いします」
清野は打ち合わせたこと、顛末書の提出期限などを簡単に議事録にして鈴木取締役のサインをもらう。
逃がしてなるものか! 幸運の女神は前髪しかないのだ。
鈴木と堀川は小さな応接室を出てエレベーターのドアまで見送る。
エレベーターが下がるのを見て、さっきまでの応接室に戻ると、二人ともドサッと椅子に腰を下ろす。
![]() 「いやあ〜、小娘のくせに強かだねえ〜」
「いやあ〜、小娘のくせに強かだねえ〜」
「彼女の話を聞くのはつらいよ。語ることが事実だからね。しかもその責任は間違いなく当社にある。
堀川さんはISO認証とどれくらい関わったか存じませんが、まともな人なら怒り出すような審査が行われていた事実があります」
![]() 「そりゃ、本当ですか?」
「そりゃ、本当ですか?」
「規格をどう読んだらそういう解釈になるのかとか、誰が見てもおかしい判断が行われていた。
認証機関の団体もあるし、他の認証機関とはいろいろと交流があります。酒が入ったとき他の認証機関の取締役から『お宅は認証機関の恥部だ』と言われたことがある」
![]() 「それは……また……」
「それは……また……」
 |
|
| ヤレヤレ、疲れたなあ〜 |
「審査員が法律も知らずに危険物保管所が法に違反していると不適合にして、あとで企業から『消防署に問い合わせた結果、全く問題ないことを確認したので是正しません。不適合を削除してください』と言ってきたことがある」
![]() 「不適合を取り消したんですか?」
「不適合を取り消したんですか?」
「それがまたその審査員が当時の取締役でアホで頑固だったから取り消さないんだ。結局うやむやにした。ウチが是正完了していないのを見逃した形だ」
![]() 「目的が3年とか言ってましたね。あれは何ですか?」
「目的が3年とか言ってましたね。あれは何ですか?」
「まさに恥ずべきことだよ。規格では環境改善の計画を立てなければならないとあるが、その達成期限が3年以上でなければならないそうだ」
![]() 「何か根拠があったのですか?」
「何か根拠があったのですか?」
「思い当たるのは省エネ法の削減義務は『省エネ計画は中長期的に見て年平均1%以上改善(工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する事業者の判断基準)』とあるので、そこからかという気がする」
![]() 「でもISO規格の文言は中長期もありませんね」
「でもISO規格の文言は中長期もありませんね」
「となるとワカランネ、私より一世代前の幹部の妄想だろうよ」
![]() 「有益な環境側面ってなんですか? 実は私は今まで理解できなかった。先ほどあの女性の説明を聞いて納得しましたが、あれが真実でもないのでしょう」
「有益な環境側面ってなんですか? 実は私は今まで理解できなかった。先ほどあの女性の説明を聞いて納得しましたが、あれが真実でもないのでしょう」
「有益な環境側面なんて、ISO規格をしっかり読んだ人は発想しないだろう。
言い出しっぺは、かのSさんだろう。
ISO規格の定義を踏まえて理屈を考えたのではなく、キャッチフレーズになって意識高い系に流行すると思いついた程度じゃないかな。
実際にISO関係者にさえ疑問を持たれず流行し、もう元は取っただろう。
前の社長がSさんを信奉していてさ。向うは小さな認証機関だから問題になってもどうにでもなるだろう。だけど、こちらは一応大手と呼ばれる規模だから問題が顕在化すれば大変だ。
結局残ったのは、ISO14001の価値を貶めたというだけじゃないのかね」
鈴木は部屋を出て行ったが、すぐにトレイに紙コップのコーヒーふたつと灰皿を載せて戻ってきた。
  |
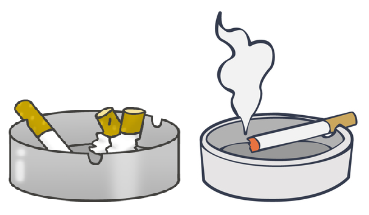 |
  |
 |
![]() 「このビルは全館禁煙と聞きましたが……」
「このビルは全館禁煙と聞きましたが……」
「勘弁してよ。何度もタバコを止めたけど、客先から苦情が来る度に吸い始めたよ。
こんなことは初めてじゃない。スラッシュ電機がウチに苦情を言ってきたことがある。もう6年位前かなあ〜(第17話)
今日みたいな感じじゃなくて、怒鳴りこんできたという感じだった」
![]() 「同じような問題でしたか?」
「同じような問題でしたか?」
「問題そのものは同じじゃないけど、規格解釈がおかしいという点では同じだ。あのときウチの審査員の行状を総ざらいして、完全に対策してしまえば良かったな
![]() 「客先から苦情を言われたなら、なぜ規格解釈をまっとうにして瑕疵をなくそうとしなかったのですか?」
「客先から苦情を言われたなら、なぜ規格解釈をまっとうにして瑕疵をなくそうとしなかったのですか?」
「当時は社長を始め、創立時からの取締役もいたし、とにかく根拠のない自信のある人ばかりで他の認証機関がどう解釈しようと気にしない人が多かった。
堀川さんから見れば私は年寄りだろうけど、私より五つも十も上の大御所が自分勝手なことをしていた。客の言い分がまっとうと思えても、自分が正しいと言ってたからね。自分は偉いつもりでも、世間では通用しないよ。
幸いスラッシュ電機もH電気も業界設立のウチに依頼してくれるからまだ良いが、当たり前の企業なら鞍替えしてしまうよ。
あのときもスラッシュ電機は不満だったようだが、転注には至らなかった。それで上のほうも慢心したんだろうね。何を言っても業界会員はウチに仕事を出すと、
彼らは外に出て仕事を取ることもせず、他社がどんな審査をしているかも気にせず、脳内お花畑だったんだろうね。
いつもイギリスにISO審査の研修に行って苦労したとか、自慢話ばかりされたよ」
![]() 「鈴木さんだって、その6年前ですか、問題点を片付けることができたじゃないですか。
「鈴木さんだって、その6年前ですか、問題点を片付けることができたじゃないですか。
今まで棚上げしといて後始末を私に任せるとは……」
「言われればその通りだ。だが、あのときはスラッシュ電機の……名前を忘れたが、そいつが理路整然と説明し、誰もが納得するように思えた。
|
|
|
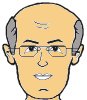 |
|
| 朱鷺元取締役 |
しかし皆が納得して改革しようとなったのを、当時の技術部長の朱鷺さんが話をひっくり返しちゃうんだ。あのとき朱鷺さんの頭を押さつけて『yes』と言わせていれば、大火になる前に火を消せたはずだ。
だが知っているようにここの指揮系統は社長がトップじゃない。株主各社が出向者を査定もするし監督もしている。朱鷺さんの会社からきている連中は朱鷺さんの話しか聞かない。社長は朱鷺さんを解任できない。雑居所帯の宿命だ。
ともかく誰かが過去の負債を処理しなくちゃならない。
私はここに来てからもう8年もやってきたよ。卒業させてくれよ」
![]() 「しかし未だに間違いが再生産されているとは」
「しかし未だに間違いが再生産されているとは」
「正直言ってここ10年間、古い考えを消すように努めてきたつもりだ。だけど今も残る古狸やその薫陶を受けた化石どもが3年目的、環境側面は数値計算とか、馬鹿の一つ覚えで……今日の清野氏の話を聞けば、現時点でも好き勝手な話をしているんだろうな
 千丈の堤も蟻の一穴より崩れるというけど、ウチでは身内がせっせと穴を掘っているから
千丈の堤も蟻の一穴より崩れるというけど、ウチでは身内がせっせと穴を掘っているから
今は企業側のレベルが上がっているから、議論しても我々は勝ち目がない、というか正論には勝てない。
今までごまかしを重ねてきたのを、一回リセットしないと」
![]() 「そのスラッシュ電機の担当者が詳しいなら、一度会ってお話を聞きたいですね」
「そのスラッシュ電機の担当者が詳しいなら、一度会ってお話を聞きたいですね」
「アハハハ、スラッシュ電機かあ〜、その後、ウチの審査員が審査中に大事件を起こして、大日本認証に鞍替えされちゃったよ。
ところが鞍替えして2年も経たない内に、スラッシュ電機は認証を返上してしまった」
![]() 「ほう、それはまた?」
「ほう、それはまた?」
「大金を払って審査を受ける価値がないとさ、今では認証機関より審査を受けるほうがレベルが高いようだ」
第一世代、第二世代そして第三世代の葛藤は認証機関内にも根強く……
客観的に見れば鈴木の気持ちも堀川の気持ちも分かる。
だけど認証機関はビジネスをしているのだ。考えるべきは、まず顧客満足だろう、そしてなによりも正義はどこか、そして認証機関が醸した企業の名誉と損失の回復だろう。
審査の理不尽で恨み骨髄に徹した、私のような人間もいることを忘れてはいけない。
何事においても、間違えを認め謝罪しまっとうな道を歩むしか救いはない。
![]() 本日の言葉
本日の言葉
「ISO七不思議」なんて言っても、実際の不思議は百も二百もある。
ここでは一つだけ挙げる。
審査で受査企業のルール及び運用がISO規格の要求事項を満たしていないと、「不適合」となりCAR(corrective action requirement)が出される。有罪である。
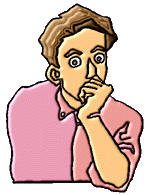
だが審査員がルールを破っても、判断を誤っても、誰も「不適合」と叫ばないし、CARが出されることもない。
それをおかしいと思わないか?
私の経験だが、異議申し立てをしようと手続きを聞こうと電話したら、「お話は分かりました、手続きなど不要です。しっかりと是正いたします」と電話を切られた。
そうじゃないんだよ。こちらは公式に異議申し立てをしたいんだよ……記録に残るように
![]() 本日 もう一つの不思議
本日 もう一つの不思議
ダラダラと書いていて、後で文字数を数えたら13,500字である。
いよいよ、ボケが進んだようだ。
早く寝よう
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
環境でいう「横出し上乗せ」とは、公害防止法令(国レベルの法律・施行令・省規則)で規制していないことを、条例(県や市町村の規制)で追加することをいう。 横出しとは法令で規制されていない物質を規制対象に追加すること、上乗せとは規制値を法令より厳しくすること。法令で規制されているものを緩くすることは許されない。なお横出しや上乗せができることは法令で決まっている。 | |
注2 |
契約不履行にはいろいろある。 ・履行遅滞とは債務の履行が遅れること。支払遅れ、納期遅れなど。 ・履行不能とは債務の履行ができないこと。農産物を売る契約をしたら凶作でものができなかったとか。 ・不完全履行とは履行はされているものの、一部の内容・状態が不完全であること。 審査契約の内容とおり行わないのは、当然契約条件を満たしていないので不完全履行になります。 じゃあ履行した一部のみ支払うのかとなると、審査基準を守っていないから履行不能ですかね? いずれにしても民法412条〜413条の2で定めてあります。 契約通り履行しない場合は、「履行の強制」もあり「不履行による損害賠償」もあります。 契約書に記載以外の審査基準を持ち出した場合は、無駄な是正をしたロスを請求することも可能のようです。 | |
注3 |
脅迫、強要、恐喝とあるがどう違うのか? 恐喝・脅迫は脅すことが目的で、恐喝が罪が重く、脅迫は罪が軽い。強要は「義務のないことをさせたり権利の行使を妨害」すること。 法の定義に照らせば、規格要求以外のことをしないと、認証を得られない/継続できないと思わせることは「強要」に当たることは間違いない。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |