*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
9月末、清野が認証機関である品質環境センターに相談というか要請というか、訪問して2週間が過ぎた。打ち合わせの時の回答期限である。
期限通りに連絡が来るとは思っていなかったが、予想外に約束を守って連絡はきた。
品質環境センターの鈴木取締役からで、文面は要請のあった顛末書をまとめた。郵送ではなく説明に上がりたい。御社の環境担当役員に直接説明申し上げたいので、コーディネートしてほしいということである。
| 執行役社長 | ||
| 星執行役 CSR部 部長 |
||
| CSR部 若宮次長 |
||
| ISO事務局 天野リーダー |
||
| 清野担当 |
清野から天野リーダーへ、天野リーダーから若宮次長、そして星執行役と報告が上がる。
その日の夕方には星執行役の秘書から、4日後の16時から定時までという返事が来た。その旨、品質環境センターの鈴木取締役に回答する。数分もかからず鈴木取締役から承知したこと、2名が伺う旨返信が来た。
その日のうちに、清野は天野リーダーと相談してロビー階の小会議室を確保した。
また、天野リーダーの指示で出席者は星執行役、若宮次長、天野リーダー、そして倉田、清野とする。出席者には開催通知と、品質環境センターへの提出資料、打合せ議事録、及び清野の考えた落とし所の案を添えて電子データで送る。
翌日朝、星執行役から清野宛にメールが入っていた。内容は、品質環境センターが来る前に内部で打ち合わせをする。時刻は来訪前の15時から1時間とするとのことである。昨日のメールは秘書がスケジュールを見て半自動的に回答をしたものらしい。
清野は若宮、天野、倉田の都合を確認する。倉田は出席の可否ではなく自分はこの仕事をする力がないから出席しないという返事が来た。これは清田が決められることではない。清田が思うことを付記して天野リーダーに転送する。
天野から倉田への回答は数分後に出され、そのCCは清野にも来た。
清田はそれを読んで、いささかギョッとした。仕事とはしたいことをするのではなく、命令されたことをすることだと認識させられたからだ。天野のメールには自分の仕事をよく認識してほしいが、できないならしかたがない。そして「(倉田の)欠席を認める」ではなく「(倉田への)出席指示を取り消す」であったからだ。
さて、予約していたロビー階の小会議室の予約表を見ると16時までは既に他の予約が入っている。小会議室は5室あるので他を見ると、14時から定時まで空いている部屋があるのでそこに予約を移す。
改めて出席者に対して部屋の変更と事前打ち合わせをするので15時から開催の旨の通知を送る。
ロビー階の喫茶店に当該小会議室に15時と16時にコーヒーを出すように注文を入れる。茶請けは不要だろう。
これで一段落か。
おっと、参加者に電子データを送ったのを見ない人もいるだろうと、当日持参しない人のためにプリントアウトしておく。
だらだらと書いたものだと思われるでしょう。実際その通りです。
自分が主催して会議をすることは、スケジュールや内容の内部調整、配布する資料の作成・コピー、会議室の確保、コーヒーやお茶の手配など、多岐にわたり結構大変です。
役員ともなれば秘書に「○○さん、こういうことで頼むよ」で済むでしょうけど、課長級以下ならすべて自分の手足を動かさないとならない。
そんな風景を表したかっただけです。
私自身、全社の担当者を集めて教育しようとか、環境課長を集めて法改正の説明会をするとか、そんなことはたびたびしましたが、
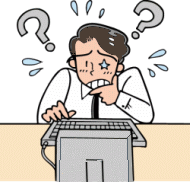
|
地方の工場の人で、東京に出張したことがないなんて人は珍しくない。交通便利で値段手ごろなビジネスホテルを案内するなど気配りも大事だ。
小説やテレビドラマで日常業務を描くなんてめったにありません。ドラマでは毎回事件が起きる警官だって、救急患者が運ばれる医師だって、現実はドラマチックなことは全体の数パーセントでしょう。ほとんどは定例会議、費用処理、勤怠処理、上司の代理で会議に出るとか灰色で塗りつぶされた日常で埋められているはずです。
当日15時、事前打ち合わせである。
さすが星執行役から指定されたからか、遅刻者はいない。全員が定刻前に集合する。コーヒーが配られると星執行役が口を開く。
![]() 「清野さんからもらった報告だと、今日向こうは顛末書をもってくるとある。
「清野さんからもらった報告だと、今日向こうは顛末書をもってくるとある。
どんな回答を持ってくるだろう。場合によっては決裂もあると思うが……
清野さんはどんな提案を持ってくると予想している?」
![]() 「ハイ、まず過去の判定が現実ではそぐわないということ、今後は私どもが要請した判断基準で行うこと、このふたつについては確約するだろうと思います。
「ハイ、まず過去の判定が現実ではそぐわないということ、今後は私どもが要請した判断基準で行うこと、このふたつについては確約するだろうと思います。
ただ過去に下した判定については過去のことだとして、変更も間違いも認めないとするか、あるいは間違いを認めても対策は過去に訴求しないという要求をすると思います」
![]() 「なるほど、冷静な判断だね。
「なるほど、冷静な判断だね。
若宮さん、天野さんはどうでしょうか?」
![]() 「私はISO審査の対面となったことはなく、また審査の結果について交渉したこともありません。ただ脇から見ていた限りでは、環境側面の決定方法について、愚にもつかないやり取りを聞いておりました。担当部署では無意味な神学論争で、時間も気力も体力も使い果たしたと思います。
「私はISO審査の対面となったことはなく、また審査の結果について交渉したこともありません。ただ脇から見ていた限りでは、環境側面の決定方法について、愚にもつかないやり取りを聞いておりました。担当部署では無意味な神学論争で、時間も気力も体力も使い果たしたと思います。
そういうのをなかったことにはできないと思います」
![]() 「なるほど、どうしたらよいか?」
「なるほど、どうしたらよいか?」
![]() 「謝罪文を一筆書いて出してもらうことが必要です。
「謝罪文を一筆書いて出してもらうことが必要です。
![]() 「天野さんはどうかね?」
「天野さんはどうかね?」
「正直言ってロスとなった損失を返せとか言っても無理でしょう。補償を取ろうとしてもろくな資産はありません。ウチはあそこの1割株主ですから経営状況は把握しています。
今後、ISO認証の重みはどんどん軽くなっていくとは思いますが、無視できるものでもない。ですから非公開を前提にしてでも、過去の審査は間違っていたと記したものは必要かと思います」
![]() 「基本的に天野さんも若宮さんと同じということで良いね。
「基本的に天野さんも若宮さんと同じということで良いね。
一筆書かせるといっても文章の内容次第だが、我々が強要罪を問われるかもしれない。
そこのところは『過去の審査では判定が間違えていた』という事実だけは書かせるようにしたい。
ところで向こうが全く非を認めないと言ったらどうするか?」
![]() 「ISO審査なんて言っても社会一般から見たら、単なる役務提供の契約です。品質が悪いとか納期が遅れたら、発注先を変えるのが鉄則です。こちらの要望に応えないならほかの認証機関にすることです。
「ISO審査なんて言っても社会一般から見たら、単なる役務提供の契約です。品質が悪いとか納期が遅れたら、発注先を変えるのが鉄則です。こちらの要望に応えないならほかの認証機関にすることです。
聞くところによると認証機関って日本で何十もあるそうですよ」
「先ほども言いましたがウチはあそこの1割株主です。出向者も10数人いますから、簡単にはできません」
![]() 「天野さん、仮に子会社が作っているものが性能が悪い、当社と無関係な企業のものは性能が良いなら、良いほうを調達することはおかしくないよ」
「天野さん、仮に子会社が作っているものが性能が悪い、当社と無関係な企業のものは性能が良いなら、良いほうを調達することはおかしくないよ」
![]() 「そういうものは多々あるね。よそが技術があり子会社が同じものを作れないなら、外から買わざるを得ない。
「そういうものは多々あるね。よそが技術があり子会社が同じものを作れないなら、外から買わざるを得ない。
それはおかしくない」
![]() 「あの、発言してもよろしいですか?」
「あの、発言してもよろしいですか?」
![]() 「問題ない、というか意見があって発言しないのは問題だ」
「問題ない、というか意見があって発言しないのは問題だ」
![]() 「今回の問題をいろいろ調べてきたわけですが、結局ISO認証とはブランドイメージでしかないというのが結論でした。実質的な効果、客が選択する際に考慮事項にあるわけでもなく、認証していないところより高く売れるわけではなく、単にイメージとして何か良さそうというだけです。
「今回の問題をいろいろ調べてきたわけですが、結局ISO認証とはブランドイメージでしかないというのが結論でした。実質的な効果、客が選択する際に考慮事項にあるわけでもなく、認証していないところより高く売れるわけではなく、単にイメージとして何か良さそうというだけです。
もし品質環境センターが非を認めなかったら、若宮次長のおっしゃる転注ではなく、認証を止めるという選択もあると考えます。
もちろん本社・支社に限るか、工場も含めるかは検討しなければなりません」
![]() 「なるほど、天野さん、認証を止めるということの検討もしたのですか?」
「なるほど、天野さん、認証を止めるということの検討もしたのですか?」
「最初の説明のとき申し上げましたが(169話)、社内アンケート結果では、認証が必要という回答をしてきた工場や支社はありませんでした。もちろん認証返上を決定する前に、再度確認を取ることは必要かと思います」
![]() 「スラッシュ電機が
「スラッシュ電機が
![]() 「真似したのではなくいろいろ調べた結果は、スラッシュ電機と同じルートを辿っていたか。検討した甲斐はあったということだ」
「真似したのではなくいろいろ調べた結果は、スラッシュ電機と同じルートを辿っていたか。検討した甲斐はあったということだ」
星執行役は時計を見る。
![]() 「まだ20分しか経過していないが、我々の対応策はあらかた決まったようだ。
「まだ20分しか経過していないが、我々の対応策はあらかた決まったようだ。
私の考えを述べる。
ひとつ、過去の判定ミスについて間違えたという事実を先方が認めること
この過去の審査判定の間違いのリストを今回の議事録に含めること
ひとつ、自今以降今回双方が確認したことに基づき審査では判定すること
ひとつ、過去に起きた問題については二度と起こさないように努め、再発した場合は即刻転注することもある
以上のことを議事録に記載する。議事録には先方の取締役のサインをもらう。代表取締役ならなお良しだが
そんなところで手を打たないか」
![]() 「天野さんと私の語ったことと同じですね。異議ありません。
「天野さんと私の語ったことと同じですね。異議ありません。
天野さんもよろしいかな」
天野がうなずく
![]() 「それじゃそういうことでと」
「それじゃそういうことでと」
「向こうが本日の会合で妥結するかどうか、分かりませんよ」
![]() 「ほう? 清田さんのメールを見ると取締役が来るようだが」
「ほう? 清田さんのメールを見ると取締役が来るようだが」
「鈴木取締役が来るのは間違いありません。ですが向こうは1割株主が10社あるのです。各社代表の取締役がいるわけで、一取締役に決裁権があるわけではありません。
じゃあ社長はと言えば、社長も決裁権限を持っているわけでもありません。決定は株主各社から来ている社長も含めた取締役10人の合議です」
![]() 「しまった、私は出向者を確認していなかった。今ウチから行っている取締役は誰だい?」
「しまった、私は出向者を確認していなかった。今ウチから行っている取締役は誰だい?」
「大木さんです。6年ほど前、当時あった環境部の部長をされていていました。
私からは先日の打ち合わせ後に、大木さん宛てに状況を報告しておきました。大木さんから返事がきまして、あまり向こうのメンツをつぶすようなことはできないが、過去に問題になったことの判定については見直しさせるという言葉をいただいています」
![]() 「時系列としては天野さんのメールの後だと思いますが、大木さんから数日前に電話がありました。
「時系列としては天野さんのメールの後だと思いますが、大木さんから数日前に電話がありました。
そのときの話では向こうの非を追及しないという条件付きでしたが、根回しはしたということです」
![]() 「それはありがとう。まずは良かったが、非を追及しなければというのが気になるな。責任を負えとは言わなくても、先方が間違えた事実だけは明確にしたい。
「それはありがとう。まずは良かったが、非を追及しなければというのが気になるな。責任を負えとは言わなくても、先方が間違えた事実だけは明確にしたい。
とはいえ振り返れば、過去にはとんでもないことを言われても、こちらがそれを正しいと信じたのは事実だ。当時は判定に不満でも騙されたと考えていたわけじゃない。あとで気が付いたというだけだ。
となると過去は間違えたことだけはっきりさせて、過去の責任は不問でも、今後は絶対許さないというところで妥協してもおかしくないか」
「執行役のおっしゃることで問題ありません」
![]() 「了解した。もちろん、まだ相手が何を言ってくるかは分からない。
まだ打ち合わせまで20分ある。何か言いたいことがあるかな?」
「了解した。もちろん、まだ相手が何を言ってくるかは分からない。
まだ打ち合わせまで20分ある。何か言いたいことがあるかな?」
![]() 「私たちより先に同じようなトラブルがあり、認証機関と何年も審査基準というか判定基準を擦り合わせてきたスラッシュ電機を見ると、結局、ISO認証の価値はないと認証を返上してしまいました。
「私たちより先に同じようなトラブルがあり、認証機関と何年も審査基準というか判定基準を擦り合わせてきたスラッシュ電機を見ると、結局、ISO認証の価値はないと認証を返上してしまいました。
ウチが2年後に同じような道を辿るなら、今ここで認証返上すれば2年間のISO認証維持費用の3億くらい低減できることになります。
その選択は考えられませんか?」
![]() 「確かに……若宮さん、前回の打ち合わせのときISO26000とか言っていたな。あれに切り替えてしまうというのはどうなんだ?」
「確かに……若宮さん、前回の打ち合わせのときISO26000とか言っていたな。あれに切り替えてしまうというのはどうなんだ?」
![]() 「真面目にISO26000を考えているのですが、範疇が環境と品質だけじゃありません。対象範囲が多岐にわたりますので相当数の部門を集めて進め方を考えなければなりません」
「真面目にISO26000を考えているのですが、範疇が環境と品質だけじゃありません。対象範囲が多岐にわたりますので相当数の部門を集めて進め方を考えなければなりません」
![]() 「あのさ、杓子定規にすることもないと思うのよ。
今までの環境と品質はそのままとして、人権とか労働なんて既に人事がしていることをチョチョイと引用して今後拡大を目指しますって書きゃいいんじゃないか。もちろんサスティナビリティ報告書にさ。
詳細は次回を待てと
「あのさ、杓子定規にすることもないと思うのよ。
今までの環境と品質はそのままとして、人権とか労働なんて既に人事がしていることをチョチョイと引用して今後拡大を目指しますって書きゃいいんじゃないか。もちろんサスティナビリティ報告書にさ。
詳細は次回を待てと
まあ、いいや、それは今後の課題として、約束の時間まであと10分だ。もう来るだろう」
ちょうどその時、清野の社内用スマホが鳴動した。
電話に出ると品質環境センターとの客がお見えになりましたという受付からだった。
清野が出迎えに部屋を出る。
途中、ロビーの喫茶店に寄り、コーヒーカップの回収と新しいもののサービスを頼む。
清野が二人の男性を会議室に案内してくる。
双方立ち上がり名刺交換の儀式を執り行う。
![]() 「この度は、過去よりISO審査において多々明瞭でない判定を下したというご意見を賜りまして、徹底したとまでは言えませんが過去の審査報告書の点検を行いました。審査基準を満たしているのか、記載がISO17021を満たしているかなどの点検を行いました。
「この度は、過去よりISO審査において多々明瞭でない判定を下したというご意見を賜りまして、徹底したとまでは言えませんが過去の審査報告書の点検を行いました。審査基準を満たしているのか、記載がISO17021を満たしているかなどの点検を行いました。
特に弊社独特の要求と思われている環境目的の期限とか、環境側面の点数法などについては、社内で妥当性の検討を行いました。
ISO14001審査は1997年から始まりましたので、もう四半世紀となります。時代時代によって審査での審査員の説明の仕方、不適合とするもの、不適合とする根拠に変遷もあり揺らぎもあるのはやむをえません。
黎明期においては環境側面の定義も理解されている方も少なく、環境側面なのか環境影響なのか環境活動なのか、そういう意味合いもあいまいなままであったという事情は皆さんもご存じであろうと思います。
そういう状況において審査員が理屈通りでなく分かりやすく説明したことが、後に誤解され不適合判定がおかしいと思われたこともあるかと思います。
それはともあれ、過去は過去、今は今ですので、ISOMS規格の正しい理解、審査での不適合の立証を規格に基づいて行うことなど今後一層の徹底を図ります。
以上が包括ですが、まず過去に御社に出した不適合については是正しようがありません。過去の報告書を書き換えることは認定機関にも届けなければならず、御社が10年前の不適合を削除されても何の効果もなく、まずはそれについては対策を免除していただきたい。
自今以降の審査においては、御社からご提案されたように過去の判定の不備を含めて、ここで改めて審査基準判定基準を打ち合わせて決めることとしたいと思います。
そういうことでいかがかと考えます」
注:いったん発行した審査所見報告書を見直すことに認定機関に届けたり承認を得る必要があるのかどうか、私は知らない。
ただ認証機関に明らかな間違いとか審査判定の修正を求めたとき、そのように説明された。
あのときすぐにJABに行って相談すれば良かったと後悔している。ほんの数キロなの
私の仕事では内部監査報告書に明らかな判断ミスがあった場合、役員まで行ったものを修正しなければならなかった。当然と言えば当然だが、辛いことであった。
清野はよく聞けば、潮田の言葉には「間違えていた」とか「責任がある」という意味の言葉が全くないことに気付いた。他の人たちは気が付いたのか、それをどう思っているかと疑問を持つ。
だがその心配は無用であった。星執行役も若宮次長も天野も、長年会社にいて海千山千である。潮田社長の話をしっかりと聞いていた。
![]() 「社長がご提案された落としどころは、私どもが考えていたことと同様と思いました」
「社長がご提案された落としどころは、私どもが考えていたことと同様と思いました」
潮田社長がホッとした顔をする。
![]() 「しかしながら過去に出された不適合でも、社長がおっしゃった『そういう状況において審査員が理屈通りでなく分かりやすく説明したことが、後に誤解され不適合判定がおかしいと思われた』という表現には大きな違和感があります。
「しかしながら過去に出された不適合でも、社長がおっしゃった『そういう状況において審査員が理屈通りでなく分かりやすく説明したことが、後に誤解され不適合判定がおかしいと思われた』という表現には大きな違和感があります。
例えば『環境側面のリストに有益と有害の区別がない』という不適合がありました。環境側面に有害も有益もないということは明白です。そしてひとつの環境側面から有害な環境影響も有益な環境影響も出すものは普通にあります。
よって、有益な環境影響を持つ環境側面を忘れるなという意味で有益な環境側面という語句を使うことを非難するものではありませんが、環境側面は有益な環境側面と有害な環境側面に分けろという考え、そして区別を必須とするという要求は明らかな審査での誤りです。
すべては過ぎ去った過去だから対策が打てないのは理解します。しかし元々問題ではないと言われるのはいかがなものか。私どもは謝罪とか賠償を求めるものではない。しかし過去の審査の判定に見られる過ちは、過ちであると明確にしていただかないと我々は受け入れられない」
![]() 「確かに有益な環境側面という言葉はISO規格にはありません。しかし有益な環境側面と有害な環境側面に分けることはいけないのでしょうか?」
「確かに有益な環境側面という言葉はISO規格にはありません。しかし有益な環境側面と有害な環境側面に分けることはいけないのでしょうか?」
![]() 「論点が違います。私どもは『環境側面を有益とか有害と区別していないので不適合』という判定を受け入れられないということです」
「論点が違います。私どもは『環境側面を有益とか有害と区別していないので不適合』という判定を受け入れられないということです」
![]() 「えっ、鈴木さん、どこかおかしいか?」
「えっ、鈴木さん、どこかおかしいか?」
「社長、有益な環境側面というものは存在しません。こちら様がいうのは、有益な環境側面があるとしたことは妥協するということです。
ですが元々有益な環境側面はないし、もちろん有害な環境側面もない。ですから環境側面を有益と有害に区別することはできないということです。有益と有害を区別していないから不適合と判断したことは、間違いだと認めなさいということです」
![]() 「えっ、どうも理解できないが……」
「えっ、どうも理解できないが……」
「ええと皆さん済みません。ちょっと社長と打ち合わせさせてください」

鈴木取締役は潮田社長を捕まえて部屋を出て廊下で小さな声で話をしている。
![]() 「うーん、どうも規格を理解されていないようだ。清野さん、君ならこういう時どうするかね?」
「うーん、どうも規格を理解されていないようだ。清野さん、君ならこういう時どうするかね?」
![]() 「みなさんはお互い忙しい方々です。長引くようならいったん向こうさんの報告を止めて、弊方の考えを伝えてそれに対応してくれるなら改めて来いという形で解散したらいかがでしょう」
「みなさんはお互い忙しい方々です。長引くようならいったん向こうさんの報告を止めて、弊方の考えを伝えてそれに対応してくれるなら改めて来いという形で解散したらいかがでしょう」
![]() 「なかなかよろしい。それじゃ既に7分経過しているからあと5分でそういうことにしよう」
「なかなかよろしい。それじゃ既に7分経過しているからあと5分でそういうことにしよう」
・
・
・
・
5分経っても品質環境センターの潮田社長と鈴木取締役は会議室に戻ってこなかった。
清野はお二人を呼びに行って、星執行役が引導を渡した。
鈴木取締役はひとりひとりにお辞儀をして辞去した。潮田社長は、何が問題なのか最後まで分からなかったようだ。
・
・
・
・
客が帰ると星執行役は座りなおす。
![]() 「どうせ今日は定時まで拘束されるわけだったのだ。少し話に付き合え。
「どうせ今日は定時まで拘束されるわけだったのだ。少し話に付き合え。
天野さん、」
「はっ」
![]() 「あの社長の対応を見ていると、ISO規格を理解していないように思えるが、間違いないか?」
「あの社長の対応を見ていると、ISO規格を理解していないように思えるが、間違いないか?」
「おっしゃる通り、基本的なことも知らないようですね」
![]() 「有益な環境影響がないというのは正しいのですか? 私が元宣伝部にいたときISO審査を受けましたが『この部門では有益な環境側面はないのか?』と聞かれたのを覚えていますよ。
「有益な環境影響がないというのは正しいのですか? 私が元宣伝部にいたときISO審査を受けましたが『この部門では有益な環境側面はないのか?』と聞かれたのを覚えていますよ。
今も認証機関の社長がしっかり有益な環境側面というので心配になりました」
![]() 「有益な環境側面とはISO規格にありませんし、概念そのものが存在しません。
「有益な環境側面とはISO規格にありませんし、概念そのものが存在しません。
もちろんISO規格でなく一般的な用法として、何事かには有益な側面も有害な側面もあるという表現は国語としてまっとうでしょう」
![]() 「ひとつ有益な環境側面がないことを説明してくれや」
「ひとつ有益な環境側面がないことを説明してくれや」
![]() 「まず『環境側面』とは環境影響を引き起こす製品とか
「まず『環境側面』とは環境影響を引き起こす製品とか
なぜ環境側面という考えをしたのかですが、ISO14001では環境保全を意図しているわけですが、環境影響を管理することはできません。出てしまったばい煙や騒音を追いかけていくわけにはいきません。
ですから環境影響を出す環境側面を管理することによって、そこから発生する有害な環境影響を小さくあるいは有益な環境影響なら大きくしようとする考えです。
当社の工場では環境側面として、生産する製品、考え方としては個々の製品名でもよろしいでしょうし白物家電でまとめても全部電気製品としてもよろしいです。
またサービスとは家電の修理とかエレベーターのメンテナンスとか輸送です。活動とは工場で生産するには電気・水・重油などを使います。そういうものを環境側面と呼びます。
さて、電気を使うということを考えます。
まず電気を作るにはダムを作ったり原子力発電所を作ります。燃料としてウランやガスや石炭や石油を掘り出して、
 はるかかなたの大陸から日本に運んできます。
はるかかなたの大陸から日本に運んできます。
ウランや石油は発電に使えるように様々な処理をおこないます。その過程ではエネルギーも使うし廃棄物も出します。
そして発電するときも環境影響を出します。火力発電でしたらCO2を出しますし石炭を燃やすと含まれている放射性物質が大気に放散すると言われています。
送電でも環境影響はあります。送電線を張り巡らすのは自然破壊です。だから電気を使うことは悪い環境影響があると言われます」
![]() 「えええっと待ってくれよ。
「えええっと待ってくれよ。
電気を使うことは環境側面、これは間違いない。
電気から出る環境影響には掘削による自然破壊、輸送によるエネルギー消費、発電による資源の浪費、CO2発生、全部悪い環境影響だ!
どこも有益な環境影響がないじゃないか」
![]() 「そうでしょうか。電気を使うことによって人々が良い暮らしをし、工場では生産して製品を作る。この有益な環境影響が自然破壊、CO2発生など有害な環境影響より大きいから人々は電気を使うのです。
「そうでしょうか。電気を使うことによって人々が良い暮らしをし、工場では生産して製品を作る。この有益な環境影響が自然破壊、CO2発生など有害な環境影響より大きいから人々は電気を使うのです。
今、世界中で大騒ぎをしている地球温暖化を止めるために電気を使うのを止めるより、温暖化が進んでも電気を使ったほうが有益だと考えているから使い続けているわけでしょう。
そしてせめて影響の少ないものにしようと太陽光とか風力を使い始めている」
![]() 「おお、ものすごく分かりやすい説明だ。納得した」
「おお、ものすごく分かりやすい説明だ。納得した」
![]() 「わしも理解できたと思う。
「わしも理解できたと思う。
もう一つ分かったのは、あの潮田社長は、ISO14001でも重要なキーワ−ドであろう環境側面を、理解していないということだ」
![]() 「私もそう思います。
「私もそう思います。
環境側面をよく理解していないと、有益な環境側面というものを発想するようです。
有益な環境側面を広めたい審査員は審査でいろいろなものを例にして説明しました。省エネ活動を有益な環境側面と言った審査員は多いです。
洞爺湖サミットの頃、日本では白熱電球を蛍光灯電球に変える運動がありました。当時審査員は『白熱電球は有害な環境側面で蛍光灯電球は有益な環境側面』と言いました」
「確かに、そう言われたねえ〜」
![]() 「なるほど、そうすると有益な環境側面と有害な環境側面というのはあるのか?」
「なるほど、そうすると有益な環境側面と有害な環境側面というのはあるのか?」
![]() 「そりゃ、どこかが間違っている。清野さんどこがおかしいのか説明頼む」
「そりゃ、どこかが間違っている。清野さんどこがおかしいのか説明頼む」
![]() 「確かに白熱電球も蛍光灯電球も環境影響を引き起こす製品ですから環境側面です。そして白熱電球も蛍光灯電球も資源を使い電気を使い、そして熱、光、そして廃棄物を出すという環境側面です。
「確かに白熱電球も蛍光灯電球も環境影響を引き起こす製品ですから環境側面です。そして白熱電球も蛍光灯電球も資源を使い電気を使い、そして熱、光、そして廃棄物を出すという環境側面です。
違いは何かと言えば、電気から光への変換効率です」
![]() 「でも変換効率が高いなら比較として有益な環境側面と言っても良いのではないか?」
「でも変換効率が高いなら比較として有益な環境側面と言っても良いのではないか?」
![]() 「そうでしょうか。洞爺湖サミットから10年が経った現在、有益な環境側面があると考えている人たちは、蛍光灯電球は有害な環境側面、LED電球は有益な環境側面と語っています。同じ轍を踏んでおり間違いには変わりません」
「そうでしょうか。洞爺湖サミットから10年が経った現在、有益な環境側面があると考えている人たちは、蛍光灯電球は有害な環境側面、LED電球は有益な環境側面と語っています。同じ轍を踏んでおり間違いには変わりません」
![]() 「蛍光灯電球が有害とされたのは、水銀問題で水俣条約もあったね。
「蛍光灯電球が有害とされたのは、水銀問題で水俣条約もあったね。
ああ、清田さんの論を否定するのではなく、むしろ補強すると思うけど」
![]() 「蛍光灯電球はあるときは有益な環境側面であったが、技術の進歩によって有害な環境側面になったということ?」
「蛍光灯電球はあるときは有益な環境側面であったが、技術の進歩によって有害な環境側面になったということ?」
![]() 「そういう考えもあるかもしれませんが、相対的すぎます。科学技術では、もっと理屈でスパッと行きたいですね。
「そういう考えもあるかもしれませんが、相対的すぎます。科学技術では、もっと理屈でスパッと行きたいですね。
白熱電球も蛍光灯電球もLED電球も皆単なる環境側面であり、それぞれ有益な環境影響も有害な環境影響も出すと考えたらいかがでしょう。その違いは電気を光に変換するけど変換効率が違うだけです。
そしてもっと重要ですが、白熱電球はエネルギーを光に変換する能率が悪い。これは発光の理屈から言って仕方ありません。ですから蛍光灯電球やLED電球に比べて悪い環境影響が大きいと言われるかもしれません。
しかしクルマのウインカーや尾灯ではどうでしょうか? LEDランプは発熱量が少ないためにランプ周辺に付いた雪が溶けないという問題があり、白熱電球のものを単にLED電球に交換するのは危険です。
言いたいことは、有益だとか有害だというのは、人間の恣意的な価値観によって決まっているだけです。
そもそも環境側面とは環境影響を管理することはできないから、影響を出す元を管理しようという発想です。ですからそのとき経済的に採用できる最良の方法を使おうというのがISO14001の目指すところでした」
注:1996年版のISO14001の序文には「環境マネジメントシステムは、組織が適切なところでかつ経済的に実行可能なところで最良利用可能技術の適用に配慮すること」を目指せとある。
この考えはEVABAT(Economically Viable Application of Best Available Technology)と呼ばれ、ISO14001ではこの考え通じて施策を進めるべきとあった。
時代が変わると誰もがそんなアプローチを忘れ「環境を守れ」と念仏を唱えるだけになったようだ。
![]() 「環境側面が良いか悪いかなどは常に相対的です。白熱電球はそれ以前の灯油ランプとかロウソクよりはるかに良かったわけです。いずれにしても比較でしかない有効性を、有益な環境側面とか有害な環境側面と呼ぶのは大きな勘違いです」
「環境側面が良いか悪いかなどは常に相対的です。白熱電球はそれ以前の灯油ランプとかロウソクよりはるかに良かったわけです。いずれにしても比較でしかない有効性を、有益な環境側面とか有害な環境側面と呼ぶのは大きな勘違いです」
| 照明器具 | ロウソク | 灯油ランプ | 白熱電球 | 蛍光灯電球 | LED電球 |
| 形態 | 🕯 | 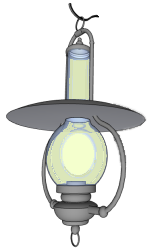 |  | 
| 
|
| エネルギー 変換効率 | 0.04% | 0.8% (注4) | 2% | 10% | 30% |
| 有益な環境影響 | 灯り | 灯り | 灯り 保温 | 灯り | 灯り |
| 有害な環境影響 | 煤による汚れ 健康被害 火災の危険 | 煤による汚れ 火災の危険 | 発熱 | 廃棄時の水銀 資源の浪費 | 資源の浪費 |
注1:変換効率の数値はWikipediaより
注2:発熱することは照明器具としてはエネルギー変換効率が低いとマイナスである。
LEDランプは熱を出さない(基板の発熱はある)ことは照明器として良いことであるが、冬季積雪のある地方では自動車のランプ周りに着雪しランプが見えなくなるマイナスがある。それは白熱電球と逆である。
注3:当然、ランプの寿命も考慮すべきことだ。
メーカーはLEDランプは10年間の長寿命と謳っているが、私自身の体験でも世間の評判もそれほど持たないようだ。
販売店では毎日8時間使用として、蛍光管の寿命を2〜4年、LED照明も4〜5年としている。これが実感される寿命だろう。
LED素子ではなく制御回路の問題とか人感センサーの故障と言われても、顧客にとっては動作しなくなった時が寿命である。
注4:石油のオープン状態での燃焼効率80%と仮定、燃焼での光エネルギー変換効率1%と仮定
![]() 「なるほどISO14001とは個々に拘わるとか表面的なことでなく、根本をしっかりとらえて考えなければならないということだ。
「なるほどISO14001とは個々に拘わるとか表面的なことでなく、根本をしっかりとらえて考えなければならないということだ。
LED電球が有益な環境側面と考えると思考停止してしまう。まずは使用目的に適しているか否か、変換効率の良否や使用済後の廃棄物が有害か否かということを考えて、この用途に何を使うべきかと考えれば一層の発展が期待できるというわけだ」
![]() 「不肖若宮も理解したしました。
「不肖若宮も理解したしました。
となりますと、品質環境センターの社長がああでは、ちょっと期待薄ですね」
「まあ鈴木取締役は理解していましたから、会社に戻ったら指導するでしょう」
![]() 「環境方針なんて皆軽視しているか知らんが、重要だと思うね。社長の思いを従業員に伝え、従業員はその意図を理解して仕事に励む。今の若い人が聞いたら笑うかもしれんが、これは時代とか世代とか関係なく世の中の
「環境方針なんて皆軽視しているか知らんが、重要だと思うね。社長の思いを従業員に伝え、従業員はその意図を理解して仕事に励む。今の若い人が聞いたら笑うかもしれんが、これは時代とか世代とか関係なく世の中の
そういうことはお題目とか理念ではなく、現実に効果があることだし、効果を出さなければならない。
社長が環境側面というISO14001の重要な概念を理解していなければ、その
![]() 「部長、ということは我々はどうすれば良いのですか?」
「部長、ということは我々はどうすれば良いのですか?」
![]() 「転注するのがよさそうだが、すぐにそうするわけにもいくまい。
「転注するのがよさそうだが、すぐにそうするわけにもいくまい。
![]() 「
「
お前はこんなことしたのかという質問ですか?
 一度もしたことありません。
一度もしたことありません。
私はいくつもの認証機関に、
「判断が間違ってるようです、再度検討してください」
「判断が間違っているぞ」なんて言いません。
「この規格解釈はおかしくありませんか?」
「字が読めないのか!」なんて言いません。
などなど、苦情を言いに行きました。
でもね、ほとんどが言い逃れ、雲隠れ、門前払いですよ、
もうね、お手上げでした。
![]() 本日のおさらい
本日のおさらい
一難去ってまた一難……ではありません。
H電気としては、お灸をすえてとりあえず現状維持、問題あれば転注ということですが、それって対策になっていません。単に先送りしただけです。
あれ、鈴木取締役のようですね、
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |