*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
私は認証機関、品質環境センターの潮田社長である。最近不愉快に思っていることがある。当社の審査に問題があると、営業部長の鈴木取締役から聞かされているからだ。
|
|
|
 |
|
| 潮田社長 |
当社の出資会社であり重要顧客であるH電気が、品質環境センターはISO14001審査で規格解釈を間違えているとか、要求事項にない不適合を出されたとか、あげくには不適合の記述に証拠と根拠が明確に記述していないなど、ふざけた言いがかりを付けてきたそうだ。
更に気にいらないことは、鈴木取締役がH電気の言い分に反感を持っていないことだ。むしろ彼は、先方の主張に賛同しているように感じる。
我が社、品質環境センターは30年近い歴史があり、日系大手の認証機関である。そんなところに何も知らない素人が、よくもふざけた言いがかりを付けてきたものだ。なんで鈴木取締役は、その場で論破して追い返さないのか私は不満である。
今日も鈴木取締役から話をしたいという。何を話すのか?
大会社ではないので、社長室などあるわけではない。学校の教室二つ分くらいのオフィスの一部をパーテーションで区切っているだけだ。脇には50センチ角くらいの小さな机と椅子がふたつあり、誰かが来たらそこで話すか、聞かれて困る話なら応接室で話すことになる。
鈴木取締役から応接室でと言われたので何事かと思った。
認証機関の応接室は、認証を受けたい企業とか審査の打ち合わせなどの訪問者と打ち合わせるところで、5・6人くらいしか入れない小さな部屋だが6室用意している。もちろん客ばかりでなく社内の少人数の打ち合わせにも使うわけだが、顧客との打ち合わせを優先しており、社内打ち合わせにはなるべく使うなと言っている。
鈴木取締役の話は応接室を使うほど、重要なのかどうなのか?
 |  | |
| 潮田社長 | 鈴木取締役 |
応接室の中で潮田社長と鈴木取締役が顔を突き合わせている。
![]() 「そのさ、彼らの言っていることは私から見れば全くおかしい。
「そのさ、彼らの言っていることは私から見れば全くおかしい。
鈴木さんは向こうの話を聞いてまっとうだと思えるのかい?」
「H電気から言われていることは、今までの審査で当社の審査員の判断は規格を理解していないと思われるものが多く、不適合でないものに不適合を出されていたのが多々あるということ。そして不適合について証拠と根拠を明記していないものが多いということ。
先方の出してきた資料を見る限り、それらは事実です」
![]() 「どうして事実とわかるの?」
「どうして事実とわかるの?」
「審査報告書は当社では10年保管にしています。ですから先方で問題とした審査報告書は、すぐに取り出して検証できます」
![]() 「つまり保管している過去10年間の審査報告書に不適合の判断の誤りや、不適合の証拠と根拠の記述が不備なものがいくつもあるということ?」
「つまり保管している過去10年間の審査報告書に不適合の判断の誤りや、不適合の証拠と根拠の記述が不備なものがいくつもあるということ?」
「そうです。そして書類は当社で保管しているだけでなく、顧客企業にも写を提出していますから、修正はできません」
![]() 「でも審査の判定なんて、後からでは分からないものが多いでしょう。現場の不具合はもちろん、書面の不具合にしても、報告書を読んでも状況は正確に分からず、どうとでもとれるでしょう。
「でも審査の判定なんて、後からでは分からないものが多いでしょう。現場の不具合はもちろん、書面の不具合にしても、報告書を読んでも状況は正確に分からず、どうとでもとれるでしょう。
もし何年か前の判定が間違えていたとしても、今更その判定の正否の検証なんてできないよ」
「現実にはそういうものはあります。ですが彼らはここ1・2年の不具合事例を取り上げていて、過去にもあったと言っています。そんな大昔の問題を掘り返しているわけではありません。
それよりも決定的なこととして、報告書の記載を読んで不適合が具体的に見えなければ、その報告書は出来が悪いのです。審査の問題どうこう以前に、報告書が不備と判断されます。
そしてまた彼らは文句を付けるだけではなく、他の認証機関の解釈も調べていますし、H電気以外での当社による他社の審査では解釈や判定が異なるという証拠を添えていることです。
ですから当社の一貫した見解とはいいがたいです。
更に向こうの論点は、当社の非を責めるのでなく、今後の審査において判断基準を擦り合わせたいと要請しているのです」
![]() 「あ〜、めんどくさい。そういうのは営業部長の鈴木さんが適当にあしらっておけばよいじゃないか」
「あ〜、めんどくさい。そういうのは営業部長の鈴木さんが適当にあしらっておけばよいじゃないか」
「H電気はグループ企業を含めると、当社の売り上げの3から4パーセントになる大手顧客ですよ。大事にしないと」

![]() 「H電気は顧客であると同時にウチの株主会社だよ。だから当社に依頼するのを止めるなんてできない。
「H電気は顧客であると同時にウチの株主会社だよ。だから当社に依頼するのを止めるなんてできない。
H電気から来ている取締役は大木さんだったね。彼に会社を黙らせるように言っておくよ」
「社長、そういう発想は間違いです。かってウチの1割株主だったスラッシュ電機が、ウチの審査員が問題を起こしたために、当社に審査を依頼するのを止めたという前例もあります
当社の審査の品質が良いと株主各社が理解してなければ、当社を推薦してくれるわけがありません。まして客から苦情を受けても無視するとか、あってはなりません」
![]() 「あー、分かった、分かった。
「あー、分かった、分かった。
それでどういう対応をしろというのですか? 謝罪すればよいの?」
「社長、発想が違うのですよ。彼らは過去の判定がおかしいと考えているものについて、当社の見解を聞きたいこと、そして彼らの考えを当社に聞いてほしいのです。
ですから当社が先方の要望に対応することは、こちらが彼らの要望をよく検討して、問題ないならそれを説明すること、問題であるなら今後は判定を見直す約束をすべきなのです」
![]() 「そんなこと営業の鈴木さんと審査部長の山田さんで話を付けたらよいじゃないの」
「そんなこと営業の鈴木さんと審査部長の山田さんで話を付けたらよいじゃないの」
「ご存じと思いますが審査部長が変わったのは今年4月でまだ半年経っていません。山田部長と話をしましたが、前任者である潮田社長が見解を決めてほしいと言います。なにしろ今起きた問題じゃなくて、社長が審査部長のときに起きたことですから。
それに審査員によって判定が異なるのでは、どのように教育指導してきたのか分からなければ手が打てません。
山田部長としては前部長が過去の審査報告書が適正だとするなら、それを通したいという見解です。責任転嫁ではなく、過去にそう決めたならそれなりの理由があるだろうということです。
もしすべてを私に任せてもらえるなら、私はH電気の言い分を100%採用して、審査員に周知徹底します。それでよろしいですか?」
![]() 「鈴木さんは彼らの言い分を正しいと思っているの? そこがひっかかる」
「鈴木さんは彼らの言い分を正しいと思っているの? そこがひっかかる」
「彼らは他の認証機関の見解を添付しています。それを考えれば大外れはありません。そして当社の審査員でもH電気以外ではH電気の意見通りの判定をしている人がいるのです。ただ審査部ではそういう人をH電気に回すと判断が過去と変わってしまうとして担当区域をしっかり分けています」
![]() 「うーん、そいじゃH電気が持ってきた事例を見せてよ」
「うーん、そいじゃH電気が持ってきた事例を見せてよ」
「とても大量ですが読みごたえはあります。これで一式です」
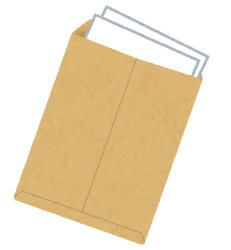
鈴木部長が潮田社長に渡したA4サイズの紙袋は、厚さ数センチはある。
潮田社長はそれを受け取ってかなり重さを感じた。1キロは優に超える。
![]() 「うわー、何ページあるの?」
「うわー、何ページあるの?」
「過去の報告書の抜粋、その判定が不適切とする考え、他の認証機関の見解、他の企業でその項番を審査した類似事例など1件で数ページありますからね。250ページくらいでしょう」
![]() 「分かった、一通り見せてもらうわ。明日、いや明後日に鈴木さんと打ち合わせしよう」
「分かった、一通り見せてもらうわ。明日、いや明後日に鈴木さんと打ち合わせしよう」
翌日である。潮田は鈴木取締役から借りたH電気からの「審査での疑義」と表題が付いた膨大な資料を読んでいる。鈴木取締役は250ページくらいと言ったが、潮田が数えたら320ページあった。
斜め読みしただけでも、まあ良くもこれほど調べたものだと感じる。そして取り上げている問題の多いこと。
- 「環境側面決定が点数法以外であるので不適合とされた」というものがある。

潮田はそれをみて、その文章の何が問題なのか分からない。
環境側面は評価しなければ良し悪しが分からないだろう。『特定するには詳細なライフサイクルアセスメントを要求しない』と付属書にあるが、ライフサイクルまではともかく、通常時の環境影響をしっかりと把握しなければいけない。それは定量化できるし、しなければ比較できない。
と考えると点数法以外の方法が思い浮かばない。潮田は10年以上前にここに出向したとき3代前の社長にそう習った。
- 「規格では所見報告書では不適合の根拠と証拠を明確に記述せよとあるが、どれを見ても明確に記載していない。
例えば次のような不適合の記載があった」
『調達先の環境調査票を5年間保管することにしているが、環境調査票を保管していない会社があった』

潮田は思う。文章を読めば根拠には『5年間保管すること』が該当するだろうし、証拠は『保管していない会社があった』ではないのか。バカバカしい
知らない人はいないだろうが、潮田社長の考えるレベルでは所見報告書の記載が不適合である。ISO17021-1の要求を満たすように不適合を記すなら、
「(被審査組織の)『グリーン調達規定』第25条では調達先の環境調査票を5年間保管することと定めているが、A社の2017年、B社の2018年調査票は(下線部は必要なので作者が情報を追記した)、本来ファイルしておくべきそれぞれの会社の調達先調査記録のファイルに綴じられていなかった」と証拠と根拠をトレーサブル(追跡できる)に記述しなければならない。
あなたの手元になる審査報告書の何割が、その要求を満たしているか、統計を取ると面白いだろう。
- 「オープニングミーティングで、審査員が社名を挙げて他社事例の説明をしている。これは守秘契約に反する」

一体何が悪いのか? 会社名を上げたのが悪いのか、別に犯罪じゃないだろう。
審査に行って他社の話をすると、参考になると喜ばれるものだ。問題じゃないじゃん。
- 「個々の環境側面に有益と有害の識別をしていないから不適合とあるが、不適合とする根拠がない」

まず環境側面には有益な環境側面と有害な環境側面があるのは自明のことだ。そして個々の環境側面が有益なものか有害なものかを理解していなければ、EMSが機能しないじゃないか!
こんな小学生でもわかることを根拠がないなんて、一体どこまでバカなんだ!
・
・
・
・
潮田社長は鈴木取締役から渡された講義資料の最初の10件を読んで呆れた。ISO14001の基本を知らずに審査が悪いと語るとは、まったく分かっていない連中だ。返答するにも、こちらは授業料をもらわないとならない。

潮田は資料を机の上にポンと放って、手を頭の後ろで組んで考える。
鈴木取締役ももっとしっかりしてくれないと困る。あの方は年功順なら社長になっていておかしくない。それが社長にならないのは、どこか足りないんだろう。
昼食後に話をしたいと潮田社長は鈴木取締役を応接室に呼んだ。
潮田社長はいささかお冠だ。
![]() 「鈴木さん、お借りした資料を最初の10件ほど読みましたが、呆れましたよ。
「鈴木さん、お借りした資料を最初の10件ほど読みましたが、呆れましたよ。
苦情というか言っていることが、屁理屈ばかりで論理がハチャメチャですね。
鈴木さんもあんな理屈が通っていない苦情など門前払いにしなくてはいかんでしょう」
「はあ、どんなものの論理がめちゃくちゃですか?」
![]() 「ええと、まず『環境側面決定が点数法以外であるので不適合とされた』というのがありますね」
「ええと、まず『環境側面決定が点数法以外であるので不適合とされた』というのがありますね」
「ハイ」
![]() 「こんなもの即、不適合にするのが当たり前ですよ」
「こんなもの即、不適合にするのが当たり前ですよ」
「社長、それはまずいですよ。ISO14001のどの版でも、点数法でやれなんて書いてありません。どうして点数法でないと不適合なのですか?
過去より点数法でなければ不適合という判定は間違いだとされてきたでしょう」
|
|
|
 |
|
| 潮田社長 |
![]() 「それは知っている。だが現実に点数法以外、公平で客観的な方法は聞いたことがない。結果としてウチでは点数法以外は不適合になっている。決して点数法だから不適合ではなく、著しい環境側面の決定方法が論理的でないという理由だったはずだ。
「それは知っている。だが現実に点数法以外、公平で客観的な方法は聞いたことがない。結果としてウチでは点数法以外は不適合になっている。決して点数法だから不適合ではなく、著しい環境側面の決定方法が論理的でないという理由だったはずだ。
ちょっと待てよ。H電気はここ10年新規登録した工場も事務所もなかったはずだ?
だから元から認証を受けているところは点数法だからこんな問題が起きるはずがない。点数法を止めたのかな?」
|
|
|
| 鈴木取締役 |
「そうです、そうです、良くご存じで。
研修所だったかな、そこが点数法でない著しい環境側面を決定する方法を、当社が認証している近所の会社から教えられて、簡単だからとその方法に切り替えたのです。
そういうわけでして、その研修所では近隣工場の著しい環境側面を決定する方法とその実際のものを添えて、何が悪いのか回答を求めています」
![]() 「完全に真似たのではなく、何か違っていて審査員は問題にしたのだろう?」
「完全に真似たのではなく、何か違っていて審査員は問題にしたのだろう?」
「いや全く同じでした。違ったのは審査員が違っただけ。
ですからなぜ別の会社を審査した時はOKで研修所はNGなのか、重大問題であるとしています」
![]() 「環境が違うとか方法だけ真似ていて、神髄を習っていないとか言えばいいじゃないか」
「環境が違うとか方法だけ真似ていて、神髄を習っていないとか言えばいいじゃないか」
「そんな信義に
![]() 「できるとも」
「できるとも」
「なら社長が説得してください」
![]() 「ああ、やってやるとも。
「ああ、やってやるとも。
それからさ、不適合の根拠と証拠を明確に記述せよとあるが、問題とされている事例はいずれも証拠も根拠も記載しているぞ。
例えば掲載されている事例で『排水測定の要領書で古いバージョンが使われていた。文書管理規定に反する』というのがある。ちゃんと根拠と証拠が書いてあるだろう」
「ISO17021-1では『9.4.5.3 不適合の所見は、特定の要求事項に対して記録されなければならない。また不適合の根拠となった客観的証拠を詳細に特定する、不適合の明確な記述を含めなければならない。』とあります。
排水測定の要領書というだけで、どの要領書なのか特定できますか? 文書の表題や文書番号は不要なのでしょうか?」
![]() 「報告書に書いてないんだから、現物見なくちゃ、分からんよ?」
「報告書に書いてないんだから、現物見なくちゃ、分からんよ?」
「報告書だけで不適合と判断できなければ、報告書の要件を満たしていません。
また古いバージョンとありますが、改定記号というかバージョンは何だったのでしょう?
バージョンの書き方は企業によって様々ですが、多くは初版は改定記号なしで、改定すると改定記号A、Bと進みますね。不適合としたもののバージョンは何で、正式なバージョンは何だったのでしょう?」
![]() 「そんなこと分からんでしょう」
「そんなこと分からんでしょう」
「報告書を読んだ人がその情報を得られなければ、その報告書は欠陥です。
もっとありますが、排水測定の要領書って言っても、いくつかの場所に配付されていると思います。どこにあった要領書でしょう? すべての場所の要領書のバージョンが違っていたのか、一か所だけ差し替えミスだったのか?」
![]() 「私は知らない。だけどそれがどうだっていうんだ?」
「私は知らない。だけどそれがどうだっていうんだ?」
「そういう記載がなければ、所見報告書としては欠陥です」
![]() 「審査員は皆そういう細かいことを事細かく書いているの?」
「審査員は皆そういう細かいことを事細かく書いているの?」
「当然です。そういうことを漏らさずに書けないと審査員研修を修了できません。
そして要件を満たさない報告書が来たら、判定委員会……今はなくなりましたから、報告書を審査する方はリジェクトしないと査読した人の力不足になります」
注:サラッと審査員研修を修了できないと書いたが、今はどうなんだろう?
1997年頃に私は審査員研修を3度受けたが、いずれもCARの書き方は丁寧に教えていた。
3度受けたのは本当で、3度合格した。どこかといえばグローバルテクノ、LMJ、JACOである。
不合格にならないのに何度も受けたのは、他の研修機関はどのように教えるのかと疑問を持ったからだ。
CEARあたりで承認審査員に雇ってもらえばよかった。
![]() 「そうなのか?」
「そうなのか?」
「向こうが問題としたものを、一個一個見ていくと、私にはすべて問題だと思えます」
![]() 「返事の期限はいつだ?」
「返事の期限はいつだ?」
「来週明けです。もちろんその日に結果報告するのではなく、その日にいつ説明に行くかを調整する予定です」
![]() 「分かった。いずれにしても当方の判定を変える気はない。そして先方の要求を受け入れる気もない。うまいこと言いくるめて何もしないつもりだ」
「分かった。いずれにしても当方の判定を変える気はない。そして先方の要求を受け入れる気もない。うまいこと言いくるめて何もしないつもりだ」
「社長は当社が何もしなくても相手が納得する説明ができるのですか?」
![]() 「ああ、大丈夫だ。私は一切こちらの責任にならないように説得してみせるよ。説明する論理は私が考えるから鈴木さんは同行してくれればよい。
「ああ、大丈夫だ。私は一切こちらの責任にならないように説得してみせるよ。説明する論理は私が考えるから鈴木さんは同行してくれればよい。
おっと、社長である私が説明に行くなら、向こうも環境担当役員くらいに出てもらわないと釣り合いが取れないだろう。先方には環境担当役員に出てほしいと言ってくれ」
注:常識で考えれば売上数十億の社長に、1兆円企業の執行役が会ってくれるはずがない。数十億の社長に会うのは部長級だろう。1兆円企業の工場の部長なら年数百億の生産を担当している。
ちなみにISO認証機関最大手のJQAの認証事業の売上は70億前後だ(総売で180億)。大手と言われても30億程度、中小に至っては年商数億の規模だ。
「承知しました。役員に臨席を求めるとなりますと、日時は向こうも社内の調整が必要と思います。
先方が都合の良い日時の回答を受けてとなりますね」
![]() 「ああ、そうしてください」
「ああ、そうしてください」
H電気を訪問して対応を説明する日となった。
受付で会社名を名乗ると、すぐに清野と名乗る若い女性が受付まで迎えに来た。
エレベーターで数階上がってひろい喫茶店のような雰囲気のロビーに出た。実際に一方の壁はズラッと喫茶店のようにコーヒーやらお茶請けを出すカウンターになっている。
たくさん並んでいるテーブルのいくつかで数人ずつの話し合いが行われている。その先にはドアが並んでいる。秘密でない打ち合わせがここで、秘密の打ち合わせは応接室か会議室で行われるのだろう。
女性はそのドアの一つを開けてどうぞと二人を中に案内する。
部屋の中には60前後の男性が2人と50前後と思われる男性の3人である。
名刺交換の後、潮田はこちらからさっさと話して片付けようと構想を練る。
早速、自分が考えてきたストーリーで表面的には不適際をお詫びして、これからしっかりやりますからよろしくねという説明をした……つもりであった。
 | 若宮次長 | |||||||
| 鈴木取締役 |  | 星執行役 | ||||||
| 潮田社長 |  | 天野リーダー | ||||||
 | 清野 |
潮田が一通り話をすると、星執行役が話し始めた。
潮田が話したようなことを向こうが期待していたとのことで、これはすぐに話がまとまると思ったが、だんだんと話がおかしくなる。
星執行役が明らかに規格の解釈を誤っているものがある。そういうものについて誤っていたということをまずハッキリ認めろというのだ。
潮田社長は星執行役を教育しようと話し始めると、星執行役が潮田が話すのを止めて、規格にはそもそも有益な環境側面はない、そうではあるが有益な環境側面という言葉を使うのは問題にしないという。しかし有益・有害を識別していないから不適合というのは断固拒否するという。
そこで鈴木取締役が潮田に話しかけて、向こうが有益な環境側面はないがそれはよしと譲歩しているのに、こちらが一方的に自分が正しいと主張すると逆襲を食らうという。
確かに規格に有益な環境側面という語句はない。だが世の中は環境側面というと有害なものばかりという認識があって、有益な環境側面を忘れがちだ。それを強調しているに過ぎない。
ここに至っても潮田の考えを理解せず、こちらの発言を自粛しようとは、頭がおかしいのではないか?
星執行役に説明すれば、有害な環境側面と有害な環境側面を識別する意味を理解し、過去の不適合は妥当だと納得するはずだ……
だがいくら説明しても星執行役は『環境側面を有益とか有害と区別していないので不適合』という判定を受け入れないという。そんな簡単なことを理解できないのか。困った。
そこでもう話がかみ合わず、歯車が砂をかんだように話し合いは進まない。
彼らは環境側面の意味というか定義を読んでいるのか?
訳が分からん??
私は納得しなかったが、鈴木取締役が一旦説明は中止して出直しますという。内輪で議論になってはまずいのは私も理解したので、そのまま帰社したが納得いかない。
会社に戻ると応接室に入って鈴木取締役を問い詰める。
![]() 「私は『環境側面を有益とか有害と区別していないので不適合という判定』がなぜ悪いのか分からんね」
「私は『環境側面を有益とか有害と区別していないので不適合という判定』がなぜ悪いのか分からんね」
「大変言いにくいですが、社長が勘違いしているのです。
それじゃISO17021-1の要求で説明しましょう。
『不適合の所見は、特定の要求事項に対して記録しなければならない。また、不適合の根拠となった客観的証拠を詳細に特定する』でしたね」
該当箇所の英語原文は、
9.4.5.3 A finding of nonconformity shall be recorded against a specific requirement, and shall contain a clear statement of the nonconformity, identifying in detail the objective evidence on which the nonconformity is based.
英文ではワンセンテンスがJIS訳では二つの文章に分けられているが、そのほうが意味が通じるようにも思えず?
「不適合としたことは『環境側面を有益とか有害と区別していない』ことです。

本論と関係ない余計なことですが大事なことですから申し上げておきますと、根拠だけでなく証拠も具体的に記載していません。
本来なら例えば『○○部署の環境側面一覧表』と書くべきでしょうが、報告書には書いていません。審査員は現物つまり環境側面一覧表のタイトルも文書番号も記録しなかったようです」
![]() 「鈴木さんは、そういうことを書かないとダメと思っているのですか?」
「鈴木さんは、そういうことを書かないとダメと思っているのですか?」
「もちろんです。監査とか審査では性善説を取らないのです。徹底的に証拠を固め、確固たる根拠で相手のミスを断定するのです。論理的に逃げ道がないようにするのは相手を追い詰めるためでなく、真実を明らかにするためです。
審査員が証拠・根拠を確実にせずに、企業側が『審査報告に書かれた事実はありません』と返したらどうしますか?」
![]() 「
「
「それもありかもしれません。でも当日ならともかく、数日経ったら忘れちゃいませんか。
1年後の審査で、自分が、あるいは他の人が是正確認するのに、『去年問題になった文書』を持って来いというのでしょうか? 笑われますよ。
報告書に文書番号とかバージョンが書いてあれば、それを含めて先方が内容を確認してサインしたことになるのです。そこまで記述されていれば、企業側はそんな文書知らないとは言えません。
相手が逃げも隠れもできないように、証拠と根拠を記述するのが必要条件です……と国際規格で定めているわけです」
注:所見報告書に受査組織の責任者(元は管理責任者がサインしろと言われた)がサインしているわけで、そこに書かれたことを知らなかったとは言えない。
なお、ISOとか言っても、単に民民の契約であるから、双方がサインするとき条件を付けても構わない。
「事実は認めるが不適合とは認めない」ならその旨明記してサインすればよい。その後どうなるかだが、無条件に不適合にはできないだろう。秘め事ならどうにでもなるだろうが、白日の下に晒されればそれなりに……
今回のH電気が過去の不適合をまとめて是正を図るというのは、今後に向けてであり、過去に遡及してというのは理屈から無理気味である。だって過去にときは受査組織の責任者がサインしているから。
とはいえ、法律だって遡及法が全面的に禁止されているわけではない。国民の利益になる場合とか災害時の措置などは普通に遡及法が施行される。ISO審査が間違いであれば遡及して救済が行われても異常ではない。(参議院法制局 経過措置と遡及適用)
何年たってもやはりそれはおかしいとなれば、今後の審査においては判定を改めてもらうというのはまっとうな要求である。
双方が過去の報告書を持っているわけで、受査組織は自社の所見報告書の社外広報を禁じらているわけでない。過去より不適合を出されたものも含めて、社外広報していた受査組織もある。認証しましたと広報するより、所見報告書も合わせて広報したほうが透明性が高いと評価されるだろう。
認証機関は自社のミスを広報されたらダメージだから、しっかりした審査、しっかりした所見報告書を書かないといけないということだろう。なにしろお金を取っているのだから当然だね。
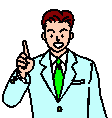
一事不再議、一事不再理という原則もあるが、同時に誤審をなくすために三審制があり、更に冤罪を防ぐために再審制もある。
ISO審査の判定も受査側を含めて公開で議論する仕組みにすべきだろう。
![]() 「分かった。とりあえずそれはおいておこう。その事例では向こうも証拠があったことは肯定している」
「分かった。とりあえずそれはおいておこう。その事例では向こうも証拠があったことは肯定している」
「では不適合である根拠に進みます。根拠の要件はISO17021-1で次のように書かれています。
『特定の要求事項に対して記録しなければならない(A finding of nonconformity shall be recorded against a specific requirement)』
要するに不適合にした根拠はどのrequirementつまりshallを満たしていないかを、明記しなければなりません。ここでは『環境側面を有益とか有害と区別していない』という事実でしたが、それはISO14001のどの要求事項に当たりますか?
直接的に『環境側面は有益と有害を識別する』という要求はありません。環境側面の項にはshallが5つありますが、そのどれが該当しますか?」
注:「specific」は通常「特定の」「特定された」と訳されるが、元々の意味は「具体的にこれだと指し示すこと」だ。
ここでは「該当する要求事項に記録せよ」だから、どのrequirement(shall)かを明記しなければならない。
![]() 「確かに有益と有害を区別しろというshallはない。しかし最初のshallでは『それに伴う環境影響を決定しなければならない』とあるから、有益・有害を示さなければ不充足だろう」
「確かに有益と有害を区別しろというshallはない。しかし最初のshallでは『それに伴う環境影響を決定しなければならない』とあるから、有益・有害を示さなければ不充足だろう」
「ここでは環境影響を決定するですから、騒音とか、熱などのイメージでしょう。それを有益・有害に分ける必要があるとは読めません。付属書でもそのようなことは書いてありません」
![]() 「鈴木さんはどうしても有益な環境側面はないというのですか?」
「鈴木さんはどうしても有益な環境側面はないというのですか?」
「一般的な日本語表現としてはあるでしょう。でもISO規格の定義に基づけば『ない』ことは間違いありません。
それにISO14001の重鎮である〇田さんが『有益な環境側面はない』と講演で語っているのですから議論の余地はありません」
・
・
・
・
![]() 「話を変える。点数法で環境側面を特定するというのもダメなのか?」
「話を変える。点数法で環境側面を特定するというのもダメなのか?」
「点数法で環境側面を特定する方法がダメではありません」
![]() 「それを聞いて安心した」
「それを聞いて安心した」
「しかし点数法以外をダメにすることは正当化できません」
![]() 「う〜ん、……しかし私には点数法以外で環境側面や著しい環境側面を決定する方法が思いつかない」
「う〜ん、……しかし私には点数法以外で環境側面や著しい環境側面を決定する方法が思いつかない」
「点数法以外の環境側面の決定方式は、外資系認証機関では普通です。知りたいなら問い合わせれば教えてくれますよ」
![]() 「いや……いいよ」
「いや……いいよ」
「環境側面や著しい環境側面を決定するとありますが、ここで『決定』とは意思で決める(decide)ことではありません。『determine』とは必然的に決まってしまうことです」
![]() 「決まってしまうとは、どういうこと?」
「決まってしまうとは、どういうこと?」
「お昼にカレーを食べるかそばを食べるかは、自分の意思で決められる『決定』です。
 農産物が豊作になるか凶作になるかは、人間ではなく天候や降水量が決定する、それが『determine』です。
農産物が豊作になるか凶作になるかは、人間ではなく天候や降水量が決定する、それが『determine』です。
あるいは火事が起きて調査した結果、火災原因が決定されるのが『determine』です。そこに人の恣意は関わりません。
著しい環境側面を決定するとは環境影響が大きいものを決めることですが、それは環境側面を決定する人によって変わるものではありません。科学的あるいは論理的に決定されるのです」
![]() 「だが決定した環境側面は、誰が見ても著しいものでなければならないぞ」
「だが決定した環境側面は、誰が見ても著しいものでなければならないぞ」
「社長、冷静になって考えてください。
点数法で環境側面を決定するって、真に数字で計算して決めているのですか? そうじゃないでしょう。これは著しい環境側面だと考えたものになるように、算式や数字を調整しているにすぎません。
点数法って何かを極める方法ではありません。自分が考えた結論を出す方法です。誰がやっても同じ結果になるのは、みなさん一応の知識を持っていて、何が重要なのか分かっているから、そうなるように調整するからです。
ですから点数法そもそもが、主客転倒なのです」
潮田は斜め45度を見上げて黙ってしまった。
数分後、鈴木は何も語らず部屋を出てしまった。
そして思う。自分もこの会社に長居して老後を無駄にしまった。バカバカしいことを止めて、人生を楽しまないといかんなあ〜と窓の外を見て思う。
すべてはここから始まったなんて言い回しがある。
清野が大学院で論文を書くのに悩み。ネタがないかとスラッシュ電機を訪ねたことから、少しずつISO認証の実態に疑問を感じた。そして改善しようと同僚を動かした。清野の話を聞いた天野リーダーは、最後のご奉公にISO認証のスタンスを見直そうと考えるようになった。そして若宮次長や星執行役にISO認証に関心を持たせたと、だんだんと動きが大きくなってきた。
 今、清野は自分が北京のチョウになった思いだ。
今、清野は自分が北京のチョウになった思いだ。
結果がどうあれ、そもそもは自分がおかしいと思ったことをおかしいと言い、こうあるべきだと考えたことを発言したに過ぎない。民主主義の原点は自己主張だろう。自己主張できない人に民主主義は無用である。いや民主主義は自己主張できない人が無用なのかもしれない。
政治が関わるのかと疑問かもしれない。政治とは政治思想とか国家を治めることではなく、利害関係を調整し不満を小さく満足の総和を大きくすることである。ならば国家も会社も家庭も関係ないし、政治家であろうと一般人であろうと、部下がなくても部下をいても関係なく、人は皆、政治に関り、対人間関係そして対組織関係をトラブルなく、トラブルがあれば解消に努めているわけだ。すべての人は政治力を持つべきだ。
清野の発言が皆を幸せにしたのかどうか、それは現時点だけなのか、将来そうなるのか、継続的なのか、そんなことは分からない。
![]() 本日の心境
本日の心境
ふとし様
あなた様からちょうど2年前に「次の物語を待ってます」というメールを頂きました。
それをきっかけに小説もどき「ISO第三世代」を書き始め、それから満2年もグダグダと紡いでまいりました。250ページの文庫本にすると18冊くらいになります。
「居眠り磐音」の51巻にはかないませんが、ISO小説では稀な長編です(えっ、私以外書いてないですって!)
まあ言いたいことも言ったし、もうマンネリかなと思い、時代も現実に追いついて終わりでよろしいかという気持ちです。
パッと終わりますというのもなんですので、これから数回、主たる登場人物のその後を書いてサヨウナラしようと思います。
原案者のご意見、できたら同意を求めます
ふとし様!
スマン、パソコンを新しくして過去のメールを保存していないのでメールから連絡できません。
これを見てください……と言っても無駄か?
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
ふとし様からお便りを頂きました(24.06.20)
ふとしです。ご無沙汰しております。 しばらくバタバタしておりまして、ようやく落ち着いたところです。 お話は毎回楽しく読ませていただいております。 「ISO第3世代」の世界でも悪が滅びつつあるようで安心しました。 楽しいお話を書いて頂き、感謝感激雨あられでございます。 後日談の方も楽しみにしております。 蛇足 こちらもメール環境が変わり履歴やアドレス等が訳わかめな状況です・・ |
呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン! ふとし大魔王登場 早速のご返事、ありがとうございます。 そいじゃ原案者のご了承を得て、まとめますのでよろしく。 次に何したらよろしいでしょうか? なにしろ浪人の身、貧乏人退屈男をしておりますので、なにかせねば暇が増すばかり |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |