*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
ISO 3Gとは
今回は元本社生産技術部の部長をしていた小林と、もう一人のお話である。
小林氏は2021年10月に本社の生産技術部長に就任して(第155話)、2年後の2023年10月に関連会社に出向となった。
通常、本社の生産技術部長となれば、次はどこかとなると、どうだろう?
本社の生産技術部長とは工場長と同格だ。成果を出せばより上に行くわけで、即執行役になるのは無理としても本部長は大有りだろうし、関連会社に出向となっても次期社長候補とか、業界団体への出向にしても名も実もある所に行くはずだ。
大して重要でもない関連会社に出向で、しかも社長候補でないなら、あまり能がないとみなされたと思われても仕方ない。
出向してひと月が過ぎた11月である。
出向した会社は電気設備工事業である。業務を具体的に言えば、工場やビルの受配電設備の据付やメンテナンスを業としており、本州だけだが事業所が5カ所あり約800人の従業員がいる。決して小さな会社ではない。

昔は送電線工事がメインだったが、日本も高度成長期が終わり送電線の整備が一段落してからは、新規の工事はほとんどない。またメンテナンスといっても新規建設に比べれば仕事量は微々たるものだ。
ところで最近は2019年の台風による千葉県での送電網の被害が大きかったことや、再エネの増加などもあり、政界や産業界でも電力網の再整備が必要という声もある
着任して社長から指示されたことは、現場作業の生産性向上を推進してくれとのことだ。製造業はもちろん、最近ではサービス業でも生産性向上が進んでいる。昨日まで夢だと思っていたことが、AIやITのと技術の進歩でできるようになってきた。

ファミレスだってウェイター・ウェイトレスが客から注文を聞いて伝票に書くなんてところはない。少し前はテーブルに置かれたタブレットで注文したが、今は客が自分のスマホで入力するのがメジャーである。すべては省力化、費用削減である。
現場で人手による電気設備の設置や配線を自動化、無人化はともかく、可能な限り工夫改善して省力化、生産性向上を図るのは当然である。
特に作業者の高齢化、若い人が嫌う重労働、町から離れた僻地での長期間の仕事など労働条件の改善は時代の要請である。
それを聞いて小林は途方に暮れる。社長の意図は分かるが、どのように進めたらよいのか小林には見当もつかない。
出向先の会社の商圏というか仕事をする地域はほぼ本州全域であり、工事は建物の中、屋外、高所作業、地下配管、都会もあるし山奥もある。
そんなふうに作業環境も作業内容もバラエティに富む仕事で、かつ工事が終われば次に移るという非定型、非定常の仕事において、生産性向上とはどういうアプローチをしたら良いものか。
小林が工場で生産技術というお仕事で、工場の課長、部長を勤めて本社の生産技術部長という生産技術畑において、双六のあがりまで行きついたのは事実だ。
しかし小林が作業改善に従事してそれを極めたわけではない。正直言って、少量生産とか手作業における生産性向上などやったことがない。
じゃあ小林は何をしてきたかといえば、1980年代から自動機やNCマシンを単独で使うのでなく、それらをつないで自動ライン化するFA(ファクトリーオートメーション)化がどんどん進んだ。小林は製造現場のFA化を図ってきたことが主たる業績である。
もちろん自分は全体の構想とか専門メーカーと交渉などをしてきたが、具体的な仕様決めとか機器間のインターフェース設計などは部下がしていた。自分はロボットのティーチングをしたこともなくPLCをいじったこともない。作業服を汚したことがないというのが自慢だった。それを自慢する発想もどうかと思う。
もちろん小林自身が頭を使わず、異動前にいた本社生産技術部に作業依頼を出す手もある。しかし何も考えずに改善してくださいというのでは、小林の存在異議が問われる。
実際にそういう依頼をしてくる本体の工場はなかったが、関連会社からは「ITを使った改善をしてください」というような、5W1Hが欠けた他力本願の依頼が来たことはある。
そんなメールを見ると小林は、こんな依頼が来たぞと部長席で大きな声で読み上げてアハハハと笑った。いつもそれに部下のお追従笑いが少し続いた。
自分の古巣にそんな依頼をしたら、後任部長に笑われるだろうし、部下たちは大声で笑うだろう。小林部長は他人の無能をあげつらっていたが実際には本人もできないじゃないかと、陰口どころか大声で笑われるに違いない。想像すると、いや想像するのは止めよう。
着任してからひと月と少々経ったが、まだ何も成果を出していない。今までしてきたことは近隣の工事現場を歩き、そこの責任者や作業者に話を聞いているだけだ。
ふた月前、出向を言われたとき、小林は人事担当といろいろ話をした。
まず自分は入社以来、生産技術部署に所属していたが、自動機を専門にしていた。だからFA関係を製造販売しているとか、社内でFAを進めている関連会社はないかと尋ねた。即座に希望通りの会社はないと言われた。
それで出向先で今までしたことがない作業改善を担当しても成果を出す自信がないと言うと、人事担当は笑いながら、「そんな心配はいらないですよ。小林さんは生産技術のプロですから、今まで経験したことを小出しにするだけで十分通用し尊敬されますよ」という。
そんなことはないと小林は言ったが、人事担当は平均より若くして本社の生産技術部長に登ってきた小林を有能な人物と確信していて、小林の語ることを冗談か謙遜と思って相手にしなかった。
学校で成績の良い人は優秀だと思われてエリートコースを歩く。入社して5年も経てば二人や三人部下を付けてもらえる。そういう部下も優秀だから「こんなことをしたい」と言えば、気を利かせて細かいことはやってくれシャンシャンと物事が進む。それを本人も周りの人も、その人の実力と思ってしまう。
だけど一人でやれと言われると、簡単な仕事もできないんだよね。私はそういう悲劇(喜劇?)を多々見てきた。
一般ピーポーである私はエリート(もどきか?)をいつも下から見上げていたが、9割は最後までエリート人生を全うできずどこかでこけた。そういうのを見ると快哉……いやそんなことはない。
現場歩きも、もうひと月している。今まで見た中でなにかひとつでも成果を見せないと……小林は追い詰められている。
某日、電材屋がセールスに来た。
資材部長が「電材屋が挨拶に来たので一緒に話を聞きませんか」と小林を誘ったので、これも勉強の機会と同席した。
工事では多量の資材を使う。しかしその資材の手配はさまざまだ。建物の場合はもちろんのこと大きな工事はゼネコンの下になるので、設置する機械や材料は顧客や元請が指定することが多く、中には客先や元請から支給されることもある。
そういうわけで工事のボリュームに比べて調達する電材はそれほど多くない。
| 電材屋の 営業マン |  |  |  | 資材部長 |
 | 小林 |
やってきた電材屋の営業は、40代半ばの男性だった。客先の訪問ノルマを消化しに来たような、あまり熱心でない感じだ。実際に購入する金額はほとんど毎年同じ程度であり、顔を出そうと出すまいと変わることはないのだろう。
小林はどこも大変だなあ〜という思いで、資材部長との話を脇で聞いていた。
世間話、業界動向、最近起きた電気工事の事故やその影響、そんな前振りの後、仕事の話になるが、前述したように調達する資材も限られているし、調達先を自由に決定できるわけではない。
営業マンもそれを知っているから30分もしないで話は種切れだ。
資材部長がそろそろ切り上げようとしていると、営業マンが小林に声をかけてきた。
![]() 「こちらが新任の小林部長さんですね。お名前は伺っております。今後よろしくお願いします」
「こちらが新任の小林部長さんですね。お名前は伺っております。今後よろしくお願いします」
だいぶ遅くなったが名刺交換をする。
資材部長は立ち上がり「お先失礼」と言って部屋を出ていく。小林と違い暇ではない。
小林は営業マンの名刺を受け取ってその資材部長の後を追おうとすると、営業マンが話を始める。
![]() 「そう邪険にしないでください。中小企業では管理者は各部門をローテーションするのが普通で、今どんな職務であっても、いつか小林部長さんも資材部長に就くことは間違いありません。これからお付き合いすることも多いでしょう」
「そう邪険にしないでください。中小企業では管理者は各部門をローテーションするのが普通で、今どんな職務であっても、いつか小林部長さんも資材部長に就くことは間違いありません。これからお付き合いすることも多いでしょう」
![]() 「そういうものですか」
「そういうものですか」
![]() 「小林部長さんは本社から出向されたと聞いておりますが、どこにいらしたのですか?」
「小林部長さんは本社から出向されたと聞いておりますが、どこにいらしたのですか?」
![]() 「生産技術部におりました。まだここに来てひと月少々です」
「生産技術部におりました。まだここに来てひと月少々です」
![]() 「生産技術部長さんでしたか。じゃあ前任者は江本部長ですね」
「生産技術部長さんでしたか。じゃあ前任者は江本部長ですね」
![]() 「そうそう、もっとも江本さんに会ったのは2回きりだ。江本さんも昔ならとうに役職定年だっただろうけど、高齢者等の雇用の安定化云々法によってスラッシュ電機の定年も伸び、役職定年も伸びてあの方は運が良かった。
「そうそう、もっとも江本さんに会ったのは2回きりだ。江本さんも昔ならとうに役職定年だっただろうけど、高齢者等の雇用の安定化云々法によってスラッシュ電機の定年も伸び、役職定年も伸びてあの方は運が良かった。
ところで生産技術部の顔ぶれにお詳しいようですが、上西さんも本社からの出向ですか?」
![]() 「奇遇ですね。私も元生産技術部で環境管理課の課長をしておりました」
「奇遇ですね。私も元生産技術部で環境管理課の課長をしておりました」
![]() 「ほう、何年前でしょうか?」
「ほう、何年前でしょうか?」
![]() 「私は2018年出向ですから、もう5年になります。もっとも私は生産技術部には8か月しかおりませんでした。
「私は2018年出向ですから、もう5年になります。もっとも私は生産技術部には8か月しかおりませんでした。
小林さんはいつからですか?」
![]() 「2021年10月から今年2023年9月までのちょうど2年間です。上西さんが出てから3年後に着任ということになりますね。
「2021年10月から今年2023年9月までのちょうど2年間です。上西さんが出てから3年後に着任ということになりますね。
しかし上西さんは8か月とはイレギュラーに短かったですね……なにかトラブルに巻き込まれたとか?」
![]() 「トラブルではありません、イジメでしたね」
「トラブルではありません、イジメでしたね」
![]() 「ほう、イジメ、環境管理課……ひょっとしてイジメたのは磯原課長かな?」
「ほう、イジメ、環境管理課……ひょっとしてイジメたのは磯原課長かな?」
![]() 「へえ〜、磯原は課長になったのですか!、驚きです。
「へえ〜、磯原は課長になったのですか!、驚きです。
小林部長もご存じと思いますが、磯原は仕事をしないのです。そのわりになんでも理屈っぽく説明するので、当時の部長や本部長室も磯原を信じていましたね」
![]() 「本部長室というと田村さんの前任者は……山内という人だったかな?」
「本部長室というと田村さんの前任者は……山内という人だったかな?」
![]() 「そうそう、山内です。山内と磯原のふたりは私が本社に来る前からいて、会社の環境行政を牛耳っていました。それに意見するとすべて否定されてしまいました。
「そうそう、山内です。山内と磯原のふたりは私が本社に来る前からいて、会社の環境行政を牛耳っていました。それに意見するとすべて否定されてしまいました。
小林さんの時は山内さんがいないから楽だったでしょう」
![]() 「山内さんを知らないのでなんともいえないけどね、ただ私が環境管理に口をはさむと、磯原課長は独裁者のようになにごとも拒否する男だったね」
「山内さんを知らないのでなんともいえないけどね、ただ私が環境管理に口をはさむと、磯原課長は独裁者のようになにごとも拒否する男だったね」
![]()
|
|
|
 |
|
| 磯原課長 |
工場で事故や違反が起きると、行く前から何が悪いと断定して、その証拠を見つけようとしかしません。もっと周りをよく見て考えないと」
![]() 「私は自動機が専門だったが、工場では生産技術部長が環境管理を見ているところが多く、私も環境には素人ではないと思っていた。
「私は自動機が専門だったが、工場では生産技術部長が環境管理を見ているところが多く、私も環境には素人ではないと思っていた。
本社に来て生産技術部長になって環境管理について指示とか意見すると、素人は黙っていろという感じだったね」
![]() 「それも私のときと同じです。工場で事故とか違反が起きて私が出張しようとすると、専門家でないと役に立たないと言って、現場から嘱託になったロートル連中を派遣するのです。課長の指示に従わず、部下が出張命令をするのです。呆れました。
「それも私のときと同じです。工場で事故とか違反が起きて私が出張しようとすると、専門家でないと役に立たないと言って、現場から嘱託になったロートル連中を派遣するのです。課長の指示に従わず、部下が出張命令をするのです。呆れました。
なによりも工場長とか行政との対応を、課長でなく嘱託者に任せてよいのかと疑問を持ちました。しかし磯原は課長の私が指示しても動かないのです」
![]() 「職権で命令しても動かないのですか?」
「職権で命令しても動かないのですか?」
![]() 「今は違うかも知りませんが、当時、磯原は環境管理課所属であると共に本部長室所属でもありました。
「今は違うかも知りませんが、当時、磯原は環境管理課所属であると共に本部長室所属でもありました。
ですから課長命令をしても、本部長室兼務だからと命令を聞かないのです。まあ職制のあいまいというかねじれみたいな状況でした」
![]() 「ああ〜、それは今も変わっていない。兼務を盾に私が命令しても言うことを聞かなかったね。
「ああ〜、それは今も変わっていない。兼務を盾に私が命令しても言うことを聞かなかったね。
上西さんは人事に相談したのかい?」
![]() 「磯原の人事の評価はとても高かったですね。本部長室から都合の良い話が伝わっていたのか、人事と親しくしていたのかは分かりません。
「磯原の人事の評価はとても高かったですね。本部長室から都合の良い話が伝わっていたのか、人事と親しくしていたのかは分かりません。
私が人事に磯原が指示命令に従わず困っていると言ってもスルーされました」
![]() 「そうだったのか。私も人事に磯原の異動を伺い出たのだが、その結果はじき出されたのは私の方だった。思い返すとあれは私に対するイジメだったのだろう」
「そうだったのか。私も人事に磯原の異動を伺い出たのだが、その結果はじき出されたのは私の方だった。思い返すとあれは私に対するイジメだったのだろう」
![]() 「お互いクジ運が悪いですね」
「お互いクジ運が悪いですね」
![]() 「まあ、私の努力不足もある。人事もそうだが広く広報や総務などに顔を売っておくとか、普段から他部門のお手伝いをしていると、磯原の肩を持つのだろう」
「まあ、私の努力不足もある。人事もそうだが広く広報や総務などに顔を売っておくとか、普段から他部門のお手伝いをしていると、磯原の肩を持つのだろう」
![]() 「確かにそうですね。となると私も困ったとき味方がいなかったのは、人助けをしてなかったということですかね?」
「確かにそうですね。となると私も困ったとき味方がいなかったのは、人助けをしてなかったということですかね?」
![]() 「積極的に仕事に向かい合うということもあるかもしれない。新しい仕事に就いたとき、その仕事についていかほど勉強するかということもある。
「積極的に仕事に向かい合うということもあるかもしれない。新しい仕事に就いたとき、その仕事についていかほど勉強するかということもある。
私がここにきてひと月半、仕事の勉強をいかほどしたかというと、大学受験ほど真面目にはしていない。
親会社で守備範囲がしっかりと決められていれば、仕事はできるだろう。
だけど子会社に出れば専門分野だけでなく、労務管理とか手形とか現場作業までを理解していないと客先で話もできない。
先ほど上西さんは中小企業ではローテーションするのが普通とおっしゃったね。
そういう意味では一つのカテゴリーのプロフェッショナルだけでなく、ゼネラリストでもあるように勉強しなければならないね。まあ、そんなことを考えている真っただ中ですが」
小林は上西と話しながら、自分は努力が足りないと感じた。本社の生産技術部長に要請して、工事現場巡りも今度から生産技術部の支援を得て行うようにしよう。知らなければ知るように努力しなければならない。
なるべく費用支払が発生しないように上手いストーリーを考えねばならないな。
上西は電気工事会社を出ると、東銀座の駅から都営浅草線で日本橋方向に向かった。浅草近辺には中規模の建築会社が相当数あるのだ。来たついでに取引のある会社に顔を出していこうと思う。
地下鉄に乗ると本社の環境管理課にいたときのことをいろいろ思い出す。
|
|
|
 |
|
| 磯原課長 |
小林部長には磯原が独裁的、独断専行といろいろ悪く言ったが、自分の内心では自分が悪かったことは分かっている。
磯原が上西に出張に行くなと言ったのは事実だが、上西より田中や坂本のほうが専門家であるのは間違いない。山内さんにしても、何度も上西に仕事の仕方、仕事に向かう姿勢など注意された。それらはイジメではなかったろう。上西が真面目に仕事しなかったからだと今は分かっている。
人事だって嘘の情報で上西に辛く当たったわけでもない。すべては己の不徳の致すところだ。
でもまあ、いいじゃないか。
多少は合理化して責任を擦り付けたって罪じゃないだろう。自分も少しは反省したし、自分も一生懸命やったと自分に思わせてもいいじゃないか。
そんなことを思っているともう浅草だ。
本社では使えないと、関連会社に出されて営業マンになったが、何とかやっているのだから、今が一番良かったと思うしかない。
小林は応接室を出て自分の席に戻る。
3メートルほど離れた横並びの席に先ほどまで一緒だった資材部長が座っている。
![]() 「小林さん、さっきの営業マンはお知り合いでしたか?」
「小林さん、さっきの営業マンはお知り合いでしたか?」
![]() 「いや面識はありません。私が元いた職場に私より数年前にいたそうです。
「いや面識はありません。私が元いた職場に私より数年前にいたそうです。
それでね資材部長、彼が言うにはこういう会社では管理職はローテーションするから私が資材部長になることもあるでしょうといって、いろいろとそんな関係の話をしてくれました」
![]() 「確かにローテーションはしますね。やはり小規模の会社ですし、幹部は会社の仕事全般について知っておくことは必要です。
「確かにローテーションはしますね。やはり小規模の会社ですし、幹部は会社の仕事全般について知っておくことは必要です。
そういう意味では今日、私が小林さんに声をかけたのは正解でしたね」
![]() 「ありがとうございます。勉強になりましたし、今迷っている社長のご指示についてもいろいろな方法があると気づきました」
「ありがとうございます。勉強になりましたし、今迷っている社長のご指示についてもいろいろな方法があると気づきました」
![]() 「それは良かった。またなにかあったら声を掛けますよ」
「それは良かった。またなにかあったら声を掛けますよ」
![]() 「よろしくお願いいたします」
「よろしくお願いいたします」
小林は給茶室の冷蔵庫から、自分が買い置いている紅茶のペットボトルを持ってきて一口飲む。
小林は思う。今日会った上西は8か月しか生産技術部にいなかったという。いくら能無しでも普通は1年はいるだろう。よほどのことでなければ、あり得ないことだ。たぶん職務怠慢とかで大きなミスをしたのだろう。
懲戒処分を受けたなら元の職場にいたとは言えないだろうから、横領とか情報漏洩など罪になることではなかったのだろう。
磯原をだいぶ悪役にしていた。私も磯原とは意見が対立することが多かった。今振り返るとなんで自分はあんなに磯原とぶつかったのだろう。坊主憎けりゃ袈裟まで憎いような感じで文句ばかり付けていたように思う。
磯原が環境管理のメンバーをしっかりと管理していたから妬んだのだろうか? CSR報告書説明会のとき、ISO認証を返上したのはまずいと意見したが、なにも20年も昔にISO認証の推進をした三ツ谷さんに不義理だからと反対することもなかった。10年ひと昔、20年経てば価値観が反転してもおかしくない。
あげくに説明会の後、三ツ谷さんに会って話をしたら、三ツ谷さんは時代が変わったのだから認証返上したことはすばらしいと語っていた(第160話)。
三ツ谷さんの話を聞いて、自分は何をしていたのかと力が抜けてしまった。
| 上西に会う前 |
頭も心も真っ白だあ〜 影も薄いぞお | ||
 |  |  |
|
|
このかなしみは 何やらん? | |||
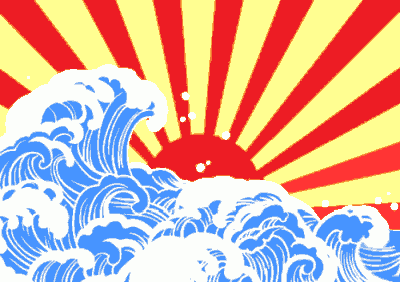 | 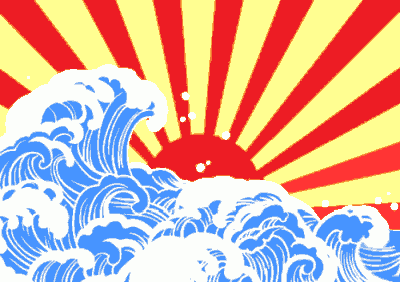 | 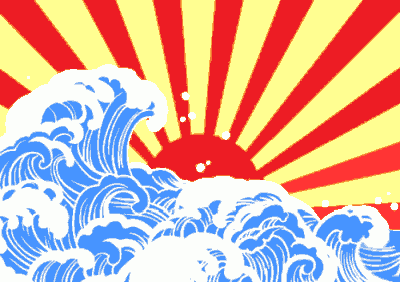 | |
 |
|||
|
バリバリいくぞ | |||
|
上の絵をどのようにして書いたか、分かった方に1万 | |||
結局は磯原が部長である自分に頼らず、堂々と仕事を進めていくのが気に入らなかったのだろう。彼の目指すところが間違っていなければ「がんばれよ」と声をかけるだけで良かったのだ。
|
|
|
 |
|
| 小林部長 |
だが翻って考えてみよう。生産技術部長なんて師団長のようなもので、参謀が持ってくる企画や相談に応じればよい。
なにもマウントを取る必要もなく自分が前線に立つこともない。管理者なのだから手足を動かすことではなく、人を動かせばよかったのだ。仕事が順調に進んでいればそれで良いのだ。
まっ、自分が未熟だったということに間違いない。
とはいえ、生産技術部長でオシマイというのは惜しかっただろうか? 案外そうではないかもしれない。
上に行けばそれに応じた成果を出さねばならない。ますます責任は重くなり、自分の決定は多くの人、多額の金に影響する。
今はどうかと考えれば、作業改善をしろという指示だ。自分は作業改善などしたことはないが、誰に頼めばよいかは知っている。彼らは手間賃を取って依頼された仕事をするために存在している。そして成果を出さなければ、こちらは払わない。仕事を依頼することは恥でもない。
ここに来たのは最良だったかもしれないな。
![]() 本日の教え諭し
本日の教え諭し
間違えたことを心から反省する人間がいかほどいるだろうか?
皆が皆、日々反省し向上に努めれば、還暦の頃には聖人君子ばかりになっているはずだ。
現実はそうではない。その証拠は古希を過ぎても反省せず失敗ばかりしている私がいる。
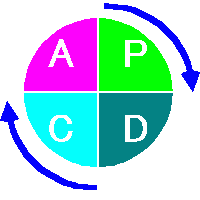
ISOの仕組みはPDCAと、計画、実行、反省、改善の繰り返しのはずだが、ISO認証企業が反省して改善に努めているようには見えないのも証拠のひとつだろう。
今回は短いお話でしたが、一番苦労したのは、過去に書いたことと矛盾のないように、過去のお話を読み直したことです。何時間もかかりました。アホラシ
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |