注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:文中「私」とは、作者である私、おばQのことではなく、このお話の主人公である「
キックオフをしてから1週間、猪越課長と私はISO認証に関わる部門を巡回して、説明会をしている。
関係する部門は全体の8割くらいになる。部ごとにまとめて行っているが2週間はかかる。
| 購買部 |
今日は購買部である。
購買部というと校内の売店の意味もあるが、製造業で部品や材料を調達する部門のことも言う。会社によっては資材部とか調達部なんて名称のところもある。
| 購買課 山本担当 | ||
| 外注課 大野課長 |
各部門に行くと、まずは3段組の表のコピーを配り説明をする。
A3用紙で10数ページになる3段組を渡すと、どこでも「ウェー」と言う声が返ってくる。そこをなだめて、各項目の要求事項を話して、お宅はどんなことか関わるか確認しましょうと言って、簡単なことから説明を始める。
話しているうちに理解が進むと共にいろいろと話が広がっていけば成功だが、時間がかかることこの上ない。
![]() 「ウチは文書管理なんて関係ないですよ」
「ウチは文書管理なんて関係ないですよ」
![]() 「総務課と技術管理課以外の方はそうおっしゃいますが、どの部門も文書管理に関わっているのです。
「総務課と技術管理課以外の方はそうおっしゃいますが、どの部門も文書管理に関わっているのです。
例えば急な仕様変更などあると、購買では取引先に図面をFAXで送ることもあるでしょう。その後、正式に図面変更される。そういったとき、当面の処理、正式改定の処理、それをどういう手順で行っているのか、間違いの起きないようにしているのか、ルールは決めていますか?
その手順を発注先まで通知しているでしょうか?」
![]() 「まあ、そう言われると、文書化されたルールはありませんね。口頭でしていますが確かに危ないですね」
「まあ、そう言われると、文書化されたルールはありませんね。口頭でしていますが確かに危ないですね」
![]() 「大野課長さんの方でも加工外注の図面の差し替えもあるでしょう」
「大野課長さんの方でも加工外注の図面の差し替えもあるでしょう」
![]() 「確かにありますね、……山本君、緊急時の図面の取り扱いは、部材も役務も同じだろう。君が手順を規定に盛り込んでくれよ、頼むぜ」
「確かにありますね、……山本君、緊急時の図面の取り扱いは、部材も役務も同じだろう。君が手順を規定に盛り込んでくれよ、頼むぜ」
![]() 「それから大野課長さんのところは計測器を外注先に貸与していますが、つい最近校正時期になっても持ってこないという問題がありましたね」
「それから大野課長さんのところは計測器を外注先に貸与していますが、つい最近校正時期になっても持ってこないという問題がありましたね」
![]() 「おっしゃる通り、大変申し訳ない。あれについては校正時期には製造現場が休日出勤しないよう出荷と計測器管理室と調整して日程計画を立てるよう見直しました。
「おっしゃる通り、大変申し訳ない。あれについては校正時期には製造現場が休日出勤しないよう出荷と計測器管理室と調整して日程計画を立てるよう見直しました。
校正する部門は休出になりますが、まあ、それはお願いしたい」
![]() 「それは購買部の手順として文書にしたのでしょうか?」
「それは購買部の手順として文書にしたのでしょうか?」
![]() 「いや〜、実を言って紙に書いて私がハンコを押して、関係部門と外注先16社に配ったのですよ」
「いや〜、実を言って紙に書いて私がハンコを押して、関係部門と外注先16社に配ったのですよ」
![]() 「手順はお考えになられたのでしょうが、その決まりが一過性でなく継続的に守られるかとなると心細いですね」
「手順はお考えになられたのでしょうが、その決まりが一過性でなく継続的に守られるかとなると心細いですね」
![]() 「そうなんですよ、難しいのは社内へは規定を直せば命令したことになりますが、外注先には規定は配布してませんから、どうするんでしょうねえ〜」
「そうなんですよ、難しいのは社内へは規定を直せば命令したことになりますが、外注先には規定は配布してませんから、どうするんでしょうねえ〜」
![]() 「外注先と取引基本契約書を結んでいますね。その中に書き込んでしまっても良いでしょうし、あるいは添付資料として配布すれば理屈は通りますね」
「外注先と取引基本契約書を結んでいますね。その中に書き込んでしまっても良いでしょうし、あるいは添付資料として配布すれば理屈は通りますね」
![]() 「ああ、そういう手があるか。そう言われるとその通りですね。山本君、悪いがそれも規定に盛り込んでくれないか」
「ああ、そういう手があるか。そう言われるとその通りですね。山本君、悪いがそれも規定に盛り込んでくれないか」
![]() 「大野課長、それって別の規定ですよ。勘弁してくださいよ」
「大野課長、それって別の規定ですよ。勘弁してくださいよ」
注:昔学校で「江戸時代は重病以外は医者に行ってはいけない」なんて、お触れがあったと教えられ、民百姓はひどい暮らしをしていたと聞かされた。
 田中圭一という筑波大の先生が書いた本に、当時 佐渡島では、暇な老人が医者に通って本当の病人が困っていた。医者が老人のサロンというのは昔からなのだ。
田中圭一という筑波大の先生が書いた本に、当時 佐渡島では、暇な老人が医者に通って本当の病人が困っていた。医者が老人のサロンというのは昔からなのだ。
それで皆が話し合い「病気の人しか行ってはいけない」という決まりを作った。
しかしその場限りでなく継続的にそして強制力を持たせるに、当時天領だった佐渡島の代官のところに行って、その村の約束を法律つまり幕府の法度にしてもらったという。
そして百姓はその掟に従って仲良く暮らしたという。めでたし、めでたし
ところが後の世ではそういう経緯を知らず、文章だけ読んで幕府はこのように細かく厳しい政策で百姓を縛ったのだと考えられてしまったという。
このケースは結果が思いもよらないことになったが、村人たちの考えはまったくISO的である。誉めて遣わす。
cf.「百姓の江戸時代」、田中圭一、筑摩書房、2000
| 営業部 |
営業部である。
ここは認証が必要と言い出した部門なので、部長自ら説明会(というほどのことはないが)に顔を出している。
二木さんは昨年までイギリス駐在だった。今回のISO審査では通訳をしてもらう。
| 営業課 二木 |
■ ■ | 営業部 三木部長 |
| 業務課 関口課長 |
注:
![]() 「二木さんには大役をお願いして申し訳ありません。私も佐川もジスイズアペンレベルなので」
「二木さんには大役をお願いして申し訳ありません。私も佐川もジスイズアペンレベルなので」
![]() 「商売の話なら自信がありますが、ISO用語となるとさっぱりですから、バックアップ頼みます。既に佐川さんからはISO審査用語の英和対語表なるものを頂いております。80語くらいありましたっけ、
「商売の話なら自信がありますが、ISO用語となるとさっぱりですから、バックアップ頼みます。既に佐川さんからはISO審査用語の英和対語表なるものを頂いております。80語くらいありましたっけ、
対語表にあるのは規格関連だけですので、実際の審査では標準偏差とか公差とか、いろいろな技術用語も出てくるでしょうねえ〜」
![]() 「もちろんバックアップしますよ」
「もちろんバックアップしますよ」
![]() 「まあ、あれだ。手に負えなくちゃ技術者に筆談してもらおう。英語が話せなくても皆英語の読み書きはできるだろう」
「まあ、あれだ。手に負えなくちゃ技術者に筆談してもらおう。英語が話せなくても皆英語の読み書きはできるだろう」
![]() 「営業の一番は契約内容の確認ですね」
「営業の一番は契約内容の確認ですね」
![]() 「契約内容と言われても、契約書は専門の翻訳を頼んでいますし、日英の弁護士にも見てもらっていますから、問題になるようなことはないと思いますが」
「契約内容と言われても、契約書は専門の翻訳を頼んでいますし、日英の弁護士にも見てもらっていますから、問題になるようなことはないと思いますが」
![]() 「ここでいう契約内容の確認とは、契約の確認であって契約書の確認ではありません。支払口座とか賠償責任とかではないのです。
「ここでいう契約内容の確認とは、契約の確認であって契約書の確認ではありません。支払口座とか賠償責任とかではないのです。
注文を受けたら、それを受注して良いかを検討することです。具体的には製品名、納期、送り先、価格もあるでしょう。注文を受けるたびにそういうことは内部で確認しますよね。納めることができないものを受注はずはないです。
そういう検討をことをしなさいという要求です」
![]() 「なんだ、そんなことだったのか。実を言って契約書はすべて本社の事業本部が保管しているので、ISO審査のときは借りてこようかという話をしていたんだ」
「なんだ、そんなことだったのか。実を言って契約書はすべて本社の事業本部が保管しているので、ISO審査のときは借りてこようかという話をしていたんだ」
![]() 「そういうことはすることはありません。ただ、ISO規格では受注時に確認した記録を保管せよとあります。それは審査のときに見ますよということです」
「そういうことはすることはありません。ただ、ISO規格では受注時に確認した記録を保管せよとあります。それは審査のときに見ますよということです」
![]() 「部長、輸出の場合は都度注文書が来て、それを受注するか否かの稟議というか確認書を関係部門回しますから、それで十分じゃないですかね?」
「部長、輸出の場合は都度注文書が来て、それを受注するか否かの稟議というか確認書を関係部門回しますから、それで十分じゃないですかね?」
![]() 「関係部門がハンコ押すだけじゃダメなんじゃないか? 検討したとか確認した証拠が欲しいんじゃないか?」
「関係部門がハンコ押すだけじゃダメなんじゃないか? 検討したとか確認した証拠が欲しいんじゃないか?」
![]() 「伺い書の中に、納期とかコストとか項目があり、それぞれに確認した部門の長が日付印を押しますのでよろしいでしょう」
「伺い書の中に、納期とかコストとか項目があり、それぞれに確認した部門の長が日付印を押しますのでよろしいでしょう」
![]() 「あい分かった」
「あい分かった」
![]() 「私から質問です。業務課は倉庫の管理とか、運送会社に出荷の手配をしてトラックに積み込むときの立ち合いです。我々が品質に関わるとは思えないのです」
「私から質問です。業務課は倉庫の管理とか、運送会社に出荷の手配をしてトラックに積み込むときの立ち合いです。我々が品質に関わるとは思えないのです」
![]() 「お配りした資料の4.15を見てほしいのですが……『取り扱い、保管、包装、保存及び引き渡し』という項目があります。これは設計し製造しただけでは品質は確実ではないということです。お客さんに手渡すまでがメーカーの責任です」
「お配りした資料の4.15を見てほしいのですが……『取り扱い、保管、包装、保存及び引き渡し』という項目があります。これは設計し製造しただけでは品質は確実ではないということです。お客さんに手渡すまでがメーカーの責任です」
![]() 「おうちに帰るまでが遠足ですってやつだな」
「おうちに帰るまでが遠足ですってやつだな」

![]() 「そうです、そうです。
「そうです、そうです。
例えば製品をトラックに載せているときに、雨が降ってきたらどうするのか、業者が荷扱い中に段ボール箱を落としたらどうするのか、そんなことをルールに決めてありますか?」
![]() 「責任区分は定めています。フォークで載せたら、それ以降は運送会社です」
「責任区分は定めています。フォークで載せたら、それ以降は運送会社です」
![]() 「落下した製品の良否確認は、どうするのでしょう?」
「落下した製品の良否確認は、どうするのでしょう?」
![]() 「ダメージが大きければ製造部に検品と修理依頼をします。それから正規の検査工程を通り倉戻しになります」
「ダメージが大きければ製造部に検品と修理依頼をします。それから正規の検査工程を通り倉戻しになります」
![]() 「お宅の規則に決めているのですか?」
「お宅の規則に決めているのですか?」
![]() 「概ねは決めてますが、まあ実際は現場で外観を見てOK/NGを決めて、ダメージの小さなものは梱包箱の交換で、ダメージの大きなものだけを戻すとか……まあ判定は曖昧ですね」
「概ねは決めてますが、まあ実際は現場で外観を見てOK/NGを決めて、ダメージの小さなものは梱包箱の交換で、ダメージの大きなものだけを戻すとか……まあ判定は曖昧ですね」
![]() 「今申しましたのは一例です。お宅の業務全体を眺めるといろいろあると思います。
「今申しましたのは一例です。お宅の業務全体を眺めるといろいろあると思います。
例えば最近多いゲリラ豪雨、倉庫を借りるときの調査項目に水害を考慮するとか。輸出では害虫などが梱包に入っていると大変なことになります。
風が吹けば桶屋のように、考えすぎることはありませんが、気づいていないリスクがあるかもしれません。
今日は説明会ですが、審査までに何度か打ち合わせを重ねますし内部監査もします。これから、そういった検討を進めルールを考えてください。
先ほどの例なら、ダメージのレベルを決めていて、合否判定をし、要確認のものは製造部に検品・修理依頼をするとか手順を決めておいてください。
ISOというものは口頭の約束とか紙に書いただけではダメなので、ちゃんとした規定とか課の文書が必要です。
そして社外に対しては公式な形の書面を渡すという形にしてください」
![]() 「わかりました。まずは関係者で、どんな事例があるのかから調べて、対応手順を考えます」
「わかりました。まずは関係者で、どんな事例があるのかから調べて、対応手順を考えます」
![]() 「関口課長、そういった物理的なダメージもあるだろうし、雨に濡れたとか保管中の湿気とか、輸送中の低温も考えてくれよ」
「関口課長、そういった物理的なダメージもあるだろうし、雨に濡れたとか保管中の湿気とか、輸送中の低温も考えてくれよ」
![]() 「承知しました」
「承知しました」
品質保証課 |
各部門の支援も重要だが、そればかりでなく品質保証課の本来の仕事もおろそかにはできない。すべてがISO認証に関わるから手抜きはできない。
品質保証課が担当の規定のワープロ起こしは山下さんが頑張ってあらましは終わったが、引き続き内容の見直しに入っている。
計測器管理室の方は、校正漏れを4月末までにゼロにするよう浜本さんには頼んでいる。とはいえ私がそうなるように筋道をつけたから、怠けていなければ達成できるはずだ。
校正記録を紙ベースではしょうがないので、猪越課長に言ってパソコンを入れて校正期限はエクセルで校正記録は電子データで管理することにした。
信頼性試験の方は猪越課長にお任せだ。正直設計や品管との取り合いとかは過去からの経緯で奇々怪々で手に負えない。
ISO認証のお仕事もある。
既に部門の打ち合わせを終えて、業務の見直しに入った部門からは、毎日何度も問い合わせ、悩み事相談の電話が来る。
そうそう猪越課長から内部品質監査体制を作れと言われている。
全社の品質を含む業務監査は以前からあった。しかし工場独自の内部品質監査というものはなかった。今までの顧客との品質保証協定で品質監査を求められているときは、都度それ対応の規定を作って、その顧客と取引のある期間だけ監査をしていたようだ。
内部品質監査を作って定常的に行えばよいと思うかもしれないが、品質保証協定では顧客ごとに要求が
だから顧客対応でお茶を濁すのが最善だったのだろう。
入社して20余年、現場あがりで管理職までなったにしても、まったく品質監査と無縁だった私が、内部品質監査規定を作れと言われて、翌日10数ページの規定、教育訓練から心得まで含むものを提出するとはお釈迦様でも想像もしなかっただろう。
しかし翌朝、私が猪越課長に「内部品質監査規定(案)」提出すると、彼は当然のように受け取り中を見もせず「規定制定・改定伺」に日付印を押す。
![]() 「課長、中を見なくて良いのですか? 1ページ以外白紙かもしれませんよ」
「課長、中を見なくて良いのですか? 1ページ以外白紙かもしれませんよ」
![]() 「アハハハ」
「アハハハ」
規定が承認されれば、後は規程通り監査員を教育して実施するのみだ。
これから後は各課に一人候補者を出してもらい、教え込む。私は30年前から数百人は教育してきた経験がある。慣れた仕事である。
| 総務部 |
今日は総務部である。
総務部でISO認証と関係するのは、総務課と人事課だ。
総務課は文書管理だけと思っていたが、清掃もあり、ゴミの収集もある。実際の清掃は外部の業者に委託しているわけだが、その実施手順、基準、仕上がりの確認などしている。
家庭用電子機器、早い話がゲーム機とか小型オーディオ機器の製造ラインは清潔、清浄が必要だから、工場内の清掃もそれなりにしなければならない。
| 総務課 児玉課長 | ||
| 人事課 桧山課長 |
人事課で関わるのは教育・訓練だ。新人研修とか昇格試験などは、ISOの教育・訓練には該当しない。しかし業務に関する各種資格受験や外部講習などは人事が手続きをするから、その体制、手順書、記録などがISO審査で該当する。
工場で必要な有資格者、特定の技能者の届け出は総務の仕事だ。
総務部でISO認証に無関係な仕事と言えば、経理課と福利厚生それにガードマンくらいかもしれない。
| 技術部 |
やっと最後の設計部門まできた。これで部門の説明会が一旦完了する。
製造部や施設管理とかいろいろな部門も、もちろん説明会をしております。省略したことでご了解ください。
| 構造設計課 下田課長 | ||
| 回路設計課 小川課長 |
設計部門は仕様を提示されてからの開発設計という流れは決まっているわけだが、種々の議事録がそろっていないとか、設計検証でのハンコがおかしいとかというのは数多ある。
おかしいというのは課長と係長のハンコの日付の順が前後していたり、課長のところに係長が代印を押しているが、その日付の日は課長が在籍、係長が出張していたりする。
お宅だってそんなのゴロゴロあるでしょう。
技構課長 24.08.29 下田 |
そういやあ、半年前の日付の押印に、監査員が触ったら
過去のものは手が打てないが、現時点からのものはしっかりしようと動いている。
打ち合わせの議事録はコピー黒板のものを使っているが、退色してしまうので必ず感熱紙にコピーしたものを議事録とする。
議事録の要件を満たさないもの、出席者記載忘れとか、ひどいものは議題さえ書き漏らしているものもあり、ホワイトボードに直接、議題、日付、出席者、などをマジックで書いてしまい、ホワイトボードを書くときは、まずそこに必要なことを書く習慣付けを始めた。
![]() 「ISO規格の要求事項というのはshallがある文章です。
「ISO規格の要求事項というのはshallがある文章です。
Shall establish documented procedures(文書を定め)とは、工場の規定とか課の文書で手順を決めておくことが必要です。
手順とは5W1Hがあることですよ。普通の文章には主語がないのが多いけど、手順書なるものは主語がないと不備ですからね。
Shall be recorded(記録する)とは、結果が書かれた何ものかが存在することです。議事録、帳票、報告書、日報、何でもよいけど、それが規定とか課の規則などで、その書面の名称を書いて、それに記録して保管することを決めておくことが必要です」
![]() 「ええとこの3段組の表をみると、『○○規定にある』と書いてあるが、既にその要求事項については○○規定で満たすから問題ないということなのか?」
「ええとこの3段組の表をみると、『○○規定にある』と書いてあるが、既にその要求事項については○○規定で満たすから問題ないということなのか?」
![]() 「文章を読む限り充足かと思いますが、皆さんが説明するときそれだけでは足りず、他の文書などを引用することになれば、お宅でその文書もこの表に盛り込んでほしいですね」
「文章を読む限り充足かと思いますが、皆さんが説明するときそれだけでは足りず、他の文書などを引用することになれば、お宅でその文書もこの表に盛り込んでほしいですね」
![]() 「佐川さん、ひょっとしてこの表は内部監査にも使えそうですね?」
「佐川さん、ひょっとしてこの表は内部監査にも使えそうですね?」
![]() 「そうです。実はこの表は、審査の準備のためのものであり、内部監査のときは監査員も使えるし、監査を受けるほうでも使えるし、本番の審査でも使えるあんちょこです」
「そうです。実はこの表は、審査の準備のためのものであり、内部監査のときは監査員も使えるし、監査を受けるほうでも使えるし、本番の審査でも使えるあんちょこです」
![]() 「おいおい、そんな万能のツールなのかい?」
「おいおい、そんな万能のツールなのかい?」
![]() 「これから何度も皆さんと打ち合わせることがあるでしょう。
「これから何度も皆さんと打ち合わせることがあるでしょう。
最初の今回は3段組を配布して、その部門がどれに該当するのをよく考えてほしいと言い、2回目は検討した結果、該当する業務を把握したか、該否が分からない仕事はないか、などを確認し、3回目は該当する仕事の手順はあるか、ないのはどうするか、4回目は実施した記録はあるのかと点検することになります。それって、そのまま内部監査ですね。
例えば『規格では□□を○○するとありますが、□□を決めた文書はどれですか? ○○の記録はどれですか?』と質問されるわけです。
それに回答するには該当規定という列に書かれた文書を見せて要求事項の説明の列に書いてあることを読めばよいわけです。
私が書いたのは概要ですから、皆さんが自分用にその規定の何ページにあるかとか、書いておけば該当箇所をパッと出せるようになります。
記録は関連文書・記録の列に書かれた帳票とか報告書を、引っ張り出して見せることになります」
注:「そんな内部監査なら会社をよくする効果はない!」なんておっしゃるか?
君はISO規格を読んでいるのか?
ISOMS規格では内部監査で会社を良くしようという意図はない。
初版では内部監査は「品質活動が計画された取り決めに従っているかどうかを検証するため、及び品質システムの有効性を検証するため(ISO9001:1987 4.17)」とあり、
2015年版でも「品質マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために(ISO9001:2015 9.2.1)」とある。
会社を良くするか否かは、その情報を使う
![]() 「ということはISO対応の準備とはこの縦の列を埋めておいて、審査のときはその文書や記録を見せれば良いわけか、簡単だな」
「ということはISO対応の準備とはこの縦の列を埋めておいて、審査のときはその文書や記録を見せれば良いわけか、簡単だな」
![]() 「だが開発とすると、開発した機種すべてに、規定で決めた記録がないとまずいことになる。あるのかね?」
「だが開発とすると、開発した機種すべてに、規定で決めた記録がないとまずいことになる。あるのかね?」
![]() 「点検するのはこれからですが、会議をしないとか議事録を残さなかったものありますが、半分は揃っているだろうと思います」
「点検するのはこれからですが、会議をしないとか議事録を残さなかったものありますが、半分は揃っているだろうと思います」
![]() 「過去からのもの全てが、揃っていなければならないわけではありません。
「過去からのもの全てが、揃っていなければならないわけではありません。
審査日から過去3か月分が揃っていなければならないことになります」
![]() 「7月上旬に審査というと、4月上旬からの記録があればよいということかい?」
「7月上旬に審査というと、4月上旬からの記録があればよいということかい?」
![]() 「正確に言えば、それ以前の文書や記録は規格要求を満たしていなくても審査の対象外ということです。ともかく規格を満たした規則とか記録は、これから先からとなります」
「正確に言えば、それ以前の文書や記録は規格要求を満たしていなくても審査の対象外ということです。ともかく規格を満たした規則とか記録は、これから先からとなります」
![]() 「なんだ、それじゃ簡単じゃないか」
「なんだ、それじゃ簡単じゃないか」
![]() 「だから今から3月末までに、現行の規定が十分か、記録、つまり議事録や帳票が抜けていないかを調べてほしいのです。
「だから今から3月末までに、現行の規定が十分か、記録、つまり議事録や帳票が抜けていないかを調べてほしいのです。
様式に漏れがないか、記載すべきところを埋めてないものがないかですね、そう言ったものってあると思いますよ」
![]() 「話は戻るけど、内部監査の教育もしなくちゃならないだろう?」
「話は戻るけど、内部監査の教育もしなくちゃならないだろう?」
![]() 「ISO規格と規定、文書、記録の関連は理解できたと思いますが、監査には聞き方のコツもありますし、監査報告書の書き方もありますし、文章のパターンもあります。
「ISO規格と規定、文書、記録の関連は理解できたと思いますが、監査には聞き方のコツもありますし、監査報告書の書き方もありますし、文章のパターンもあります。
そういったことを、まあ2時間くらい座学で説明して、実際の内部監査をしたりされたり、すればすぐに習熟すると思います
私は今みなさんにこの表の説明をしていますが、同時に議事録書いています。議事録は他の部門がQ&Aとして参考になると思うからで、いずれ配付なりするつもりです。
それと同時に、このやりとりを内部監査の記録の様式でもまとめています。
現時点では文書もまだ改定していませんし、記録の抜けもあるでしょう。ですが漏れがあったことに気付いた、決めていてもしていなかったということを監査報告にまとめて置けば、内部監査を何度も実施して、その度に質が向上してきたと分かるようにしたいです。
そして審査前の最終の内部監査を行って、不具合がなくなればPDCAが回っていることの裏付けになります」
![]() 「なるほど、説明会イコール内部監査ということか。そういう工夫でどんどん実績を積み上げると……
「なるほど、説明会イコール内部監査ということか。そういう工夫でどんどん実績を積み上げると……
ずるいとも思えるが、そういうアプローチこそ、有効で効率的なのだろうな」
![]() 「ハハハ、今回で構造設計課と回路設計課のふたつの課の第1回内部監査が終了ですよ。設計ではあと技術管理課がありますが、暇なとき向うの課長と担当者と会って話をしてきます」
「ハハハ、今回で構造設計課と回路設計課のふたつの課の第1回内部監査が終了ですよ。設計ではあと技術管理課がありますが、暇なとき向うの課長と担当者と会って話をしてきます」
![]() 「雑談をして内部監査を行うとはさすが達人だ。佐川君とは例の電波暗室(第5話)のとき初めて会ったが、只者ではないと思ったよ」
「雑談をして内部監査を行うとはさすが達人だ。佐川君とは例の電波暗室(第5話)のとき初めて会ったが、只者ではないと思ったよ」
品質保証課 |
各部門説明会を一巡して私は猪越課長と話をする。
![]() 「今回実施したことをまとめて、各部門と工場長に送りましょう」
「今回実施したことをまとめて、各部門と工場長に送りましょう」

![]() 「まだ全然進捗がないのだから、送付しても意味がないんじゃないか?」
「まだ全然進捗がないのだから、送付しても意味がないんじゃないか?」
![]() 「いやいや、スタートした時の状態を知らないと、これからの進歩が分かりませんよ。
「いやいや、スタートした時の状態を知らないと、これからの進歩が分かりませんよ。
各部門には全部門の問題となったことをまとめて送りましょう」
![]() 「そう言うなら、初回だけやってみようか」
「そう言うなら、初回だけやってみようか」
・
・
・
・
各部門の説明会のまとめを受け取ったいろいろな反応である。
工場長室である。
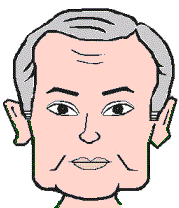 ほう、説明会の報告と言っても説明会ではなく現状の問題把握の指導だ、ある意味、内部監査なのだな。これを継続的に行って、監査に慣れさせ、また順次リファインを重ねるということか。
ほう、説明会の報告と言っても説明会ではなく現状の問題把握の指導だ、ある意味、内部監査なのだな。これを継続的に行って、監査に慣れさせ、また順次リファインを重ねるということか。
いろいろな問題点を指摘して現状を認識させる、佐川というのがなかなかテクニックがある。
こういう形で問題を摘出していけば半年後のISO審査は問題ないように思える。
よしよし、当面この2人に活動を任せよう。
購買部である。
![]() 「おーい、山本君、先日のISOの説明会のまとめなるものがきたぞ」
「おーい、山本君、先日のISOの説明会のまとめなるものがきたぞ」
![]() 「私にも来ました。お読みになりましたか?」
「私にも来ました。お読みになりましたか?」
![]() 「うん、他部門に比べるとウチは対象となるものが少ないから楽なようだな」
「うん、他部門に比べるとウチは対象となるものが少ないから楽なようだな」
![]() 「当社が決めたことを社外に通知してやらせるというのが、業務課にもありましたね。どんな文書で行うのか話し合ってみます」
「当社が決めたことを社外に通知してやらせるというのが、業務課にもありましたね。どんな文書で行うのか話し合ってみます」
![]() 「それがいい、当社から出す文書は同じくしたほうが何かと良いだろう。三人寄ればというから、皆で上手い方法を考えてくれ」
「それがいい、当社から出す文書は同じくしたほうが何かと良いだろう。三人寄ればというから、皆で上手い方法を考えてくれ」
営業部である。
![]() 「先日の説明会のまとめを読んで何か感じたか?」
「先日の説明会のまとめを読んで何か感じたか?」
![]() 「私はあれを内部監査の練習だと思いました」
「私はあれを内部監査の練習だと思いました」
![]() 「内部監査? 業務監査なんてあんな調子じゃなくて、刑事が取り調べるような感じだよ」
「内部監査? 業務監査なんてあんな調子じゃなくて、刑事が取り調べるような感じだよ」
![]() 「いえいえ、雑談の中で必要な情報を集めるのが内部監査と思っています。イギリスから来る審査員がどういう語りをするか分かりませんが、私なら佐川さんのような雰囲気にしたいですね」
「いえいえ、雑談の中で必要な情報を集めるのが内部監査と思っています。イギリスから来る審査員がどういう語りをするか分かりませんが、私なら佐川さんのような雰囲気にしたいですね」
![]() 「なるほど悪いところを指摘するのでなく、気づかせるか
「なるほど悪いところを指摘するのでなく、気づかせるか
しかし彼も初回だからマイルドにしたということはないのかね?」
![]() 「それはあるでしょうね。でもぶった切るぞという雰囲気でなく、談話のように監査を進めた方がお互い気分が良いですよね」
「それはあるでしょうね。でもぶった切るぞという雰囲気でなく、談話のように監査を進めた方がお互い気分が良いですよね」
品質保証課 |
数日後の品質保証課である。
![]() 「各部門の説明会のまとめを送っただろう、あれを読んでの反響を聞いたか?」
「各部門の説明会のまとめを送っただろう、あれを読んでの反響を聞いたか?」
![]() 「積極的に聞いてはいませんが、立ち話的には聞きました。
「積極的に聞いてはいませんが、立ち話的には聞きました。
技術の下田課長からは他部門の状況が分かってためになったと言われました。総務課長からは文書管理だけでなく、清掃についても教育訓練とか関わると知った。外注業者にどう伝えるか考えていると言われました」
![]() 「どう答えたのかい?」
「どう答えたのかい?」
![]() 「社内のルールを社外に伝えるというケースは少なくなかったですね。購買でも緊急な改定時のとりあつかいとか、業務でも製品の落下などの際の取り扱い方法もありました。そういうケースはやはり横通しして考えることも良いかなと」
「社内のルールを社外に伝えるというケースは少なくなかったですね。購買でも緊急な改定時のとりあつかいとか、業務でも製品の落下などの際の取り扱い方法もありました。そういうケースはやはり横通しして考えることも良いかなと」
![]() 「品質保証課が音頭を取ってなにかするということ?」
「品質保証課が音頭を取ってなにかするということ?」
![]() 「いえいえ、子どもじゃあるまいし、それは各部門が考えることでしょう。その意味でも全部門の応答を書いたまとめを全部門に送っているのですから」
「いえいえ、子どもじゃあるまいし、それは各部門が考えることでしょう。その意味でも全部門の応答を書いたまとめを全部門に送っているのですから」
![]() 「なるほど、獅子は子を谷に落とすか。這い上がれないのは助けてやれよ。
「なるほど、獅子は子を谷に落とすか。這い上がれないのは助けてやれよ。
工場長から返信が来ている。
簡単に言えば、しっかりやっているようだ。当面口を出さないから好きにやってみろ。困ったことがあれば言ってこいとのことだ」
工場長室 |
2月も下旬となった頃、猪越と佐川が工場長室に呼ばれた。
何事かが起きたのか?
![]() 「やぁ、忙しいところすまん。キックオフのとき本社の當山というのが騒いだな」
「やぁ、忙しいところすまん。キックオフのとき本社の當山というのが騒いだな」
![]() 「はい、本社指導の売り込みでしたね」
「はい、本社指導の売り込みでしたね」
![]() 「ISO認証活動している工場に聞いてみたが、評判悪いね」
「ISO認証活動している工場に聞いてみたが、評判悪いね」
![]() 「私もそのように聞いています」
「私もそのように聞いています」
![]() 「副工場長の尾関さんが當山を気に入っていて、指導を依頼しようと言うんだが、どうしようか?」
「副工場長の尾関さんが當山を気に入っていて、指導を依頼しようと言うんだが、どうしようか?」
![]() 「金額が安いなら頼むのもありかと思いますが、1人1日15万も取ります。
「金額が安いなら頼むのもありかと思いますが、1人1日15万も取ります。
驚くことに、キックオフのとき2人来ましたので、既に30万の請求書が来ています」
![]() 「あの日、何か指導を受けたのか?」
「あの日、何か指導を受けたのか?」
![]() 「ウチの認証までの計画表を見て素晴らしいと言って持って帰りました」
「ウチの認証までの計画表を見て素晴らしいと言って持って帰りました」
![]() 「ああ、そういうレベルね。
「ああ、そういうレベルね。
おっと、まさかその30万も払うつもりはないのだろう?」
![]() 「こういうことは政治的な話かと思いまして、月末に経理と相談しようと思っていました」
「こういうことは政治的な話かと思いまして、月末に経理と相談しようと思っていました」
![]() 「いくら社内のやりとりだけと言っても、しっかりと本社共通費で引かれるから払うわけにはいかんな。その請求書をわしに送れ」
「いくら社内のやりとりだけと言っても、しっかりと本社共通費で引かれるから払うわけにはいかんな。その請求書をわしに送れ」
![]() 「30万で終わりではありません。これから認証するまで毎月2人2日としても
「30万で終わりではありません。これから認証するまで毎月2人2日としても
 500万近い金を払うことになります。
500万近い金を払うことになります。
千葉工場では効果がないと指導を断って以降、実際に人は来ていませんが、毎月指導料として60万の請求が来ているそうです」
![]() 「そりゃ理屈が合わん。社内犯罪じゃないか。
「そりゃ理屈が合わん。社内犯罪じゃないか。
しかし……呆れたね。それほどデタラメをしているのか?」
![]() 「工場長、ここは本社の支援を受けずに、認証を進めるべきと考えます。
「工場長、ここは本社の支援を受けずに、認証を進めるべきと考えます。
認証できる自信はあります」
![]() 「先行している工場はいつ審査を受けるのかな?」
「先行している工場はいつ審査を受けるのかな?」
![]() 「兵庫工場が一番早く4月です。そのとき私と佐川が見学する予定です。最悪の場合でも、そのときから支援を求めるか否かを考える余裕はあります。
「兵庫工場が一番早く4月です。そのとき私と佐川が見学する予定です。最悪の場合でも、そのときから支援を求めるか否かを考える余裕はあります。
しかし工場長もおっしゃったように、なによりも本社の指導が役に立つのかどうか怪しいです」
![]() 「君たちだけで、大丈夫だな?」
「君たちだけで、大丈夫だな?」
![]() 「大丈夫です」
「大丈夫です」
![]() 「よし、この話は断ることにする。じゃあ、ISO認証頑張ってくれ」
「よし、この話は断ることにする。じゃあ、ISO認証頑張ってくれ」
![]() 「必ず期日までに達成します」
「必ず期日までに達成します」
品質保証課 |
品質保証課に戻ってきた。
![]() 「工場長と副工場長の見解が正反対のようだな」
「工場長と副工場長の見解が正反対のようだな」
![]() 「職制から言って、工場長が決裁すれば決まりでしょう?」
「職制から言って、工場長が決裁すれば決まりでしょう?」
![]() 「いろいろあってそうもいかないよ。偉くなればなったで、派閥のボスの取締役がどうなるかで一派の未来が替わるからね。
「いろいろあってそうもいかないよ。偉くなればなったで、派閥のボスの取締役がどうなるかで一派の未来が替わるからね。
副工場長は田村さんを追い落として、工場長になりたいだろうし」
![]() 「私には無縁の話ですね」
「私には無縁の話ですね」
![]() 「君にとって無縁じゃない。尾関副工場長が工場長になったら君にとっては地獄だろう。彼は君を懲戒解雇したくてたまらないようだ。懲戒解雇になると履歴書にも書くから、良いところには就職できないよ。
「君にとって無縁じゃない。尾関副工場長が工場長になったら君にとっては地獄だろう。彼は君を懲戒解雇したくてたまらないようだ。懲戒解雇になると履歴書にも書くから、良いところには就職できないよ。
何か君は恨まれるようなことをしたんじゃないのか?」
![]() 「思い当たるのがたくさんありすぎます。彼が転勤してきたのは、一昨年の9月だったと思います。
「思い当たるのがたくさんありすぎます。彼が転勤してきたのは、一昨年の9月だったと思います。
その直後の残業時間に、塗装ロボットのティーチングをしていたのです。なにしろ古い機械でダイレクトティーチングしかできません。塗装のブースは格子で囲っていて人が入れないようにしているのです。私と作業者一名で作業していたら、出入り口から入ろうとガタガタやってたんです。
危険だから入るなと言ったのが感情を害したようです。それが初対面でした。
それ以来、私の顔をみると必ずいちゃもんを付けてきます。最近は私に関係ないことでも叱られています」
注:ロボットはプログラムで動かすのも、手でアームを動かして動きを覚えさえるダイレクトティーチングもある。1990年頃は、ダイレクトティーチングの塗装ロボットなど年代物というわけではなかった。
あっ、今でもありますか!
![]() 「どんな経緯か知らないけど、わざわざ副工場長がロボットの囲いに入ることもなさそうだな。
「どんな経緯か知らないけど、わざわざ副工場長がロボットの囲いに入ることもなさそうだな。
でもそんなことで課長解任というのもないだろう?」
![]() 「うーん、私は空気が読めないのですよ。法を守っても会社じゃ通用しないこともあるのかと」
「うーん、私は空気が読めないのですよ。法を守っても会社じゃ通用しないこともあるのかと」
![]() 「そんな会社なら辞めちゃえばいいんだ」
「そんな会社なら辞めちゃえばいいんだ」
![]() 「私に能があればできますが、そうじゃないもので」
「私に能があればできますが、そうじゃないもので」
その夜の残業時に、尾関副工場長が猪越課長のところにやって来た。
これはあれですよ、當山に依頼しろという話ですか?
![]() 「おい、猪越、ISO認証支援の件、本社に依頼を出したか?」
「おい、猪越、ISO認証支援の件、本社に依頼を出したか?」
![]() 「工場長から支援が必要かと問われましたので、工場のメンバーで十分認証できると答えました」
「工場長から支援が必要かと問われましたので、工場のメンバーで十分認証できると答えました」
![]() 「本当にお前たちだけでできるのか?」
「本当にお前たちだけでできるのか?」
![]() 「上司は部下を信じていただきたいと思います」
「上司は部下を信じていただきたいと思います」
![]() 「わしは當山から、工場だけでは認証できないと聞いている。
「わしは當山から、工場だけでは認証できないと聞いている。
お前たちが努力すれば認証できるなんて考えているのは、當山から見ると甘いとしか思えないそうだ」
![]() 「ちょっと待ってください。當山さんたちは、指導と言えることをしていません。訪問した工場で入手した資料を、他の工場に提供しているだけです。
「ちょっと待ってください。當山さんたちは、指導と言えることをしていません。訪問した工場で入手した資料を、他の工場に提供しているだけです。
そして指導を受けている三カ所の工場では、當山さんの指導は、役に立たないどころか害があって迷惑だと言ってます。
千葉工場は正式に指導は無用と断りました」
![]() 「そんな話は聞いてないな」
「そんな話は聞いてないな」
![]() 「聞いてなくても事実です。
「聞いてなくても事実です。
それに金額がべらぼうです。當山さんたちが来ると、指導しても・しなくても、1日1人15万も請求するのです。
先日のキックオフでは、呼びもしないのに向こうからやってきて、しかも若手を連れてきて2人分30万の請求が来ています。あの日、何の指導も受けていません。ウチの資料を持って帰っただけです。
月に2回も来るそうなので、認証するまで420万も払うことになります。420万稼ぐには、工場の生産高を6,000万くらい増やさないとならんのです。そんな無駄な費用を費やすのは間違いではないですか」
![]() 「他の工場は支払っているのか?」
「他の工場は支払っているのか?」
![]() 「払っています。嫌や嫌やながらですけど。
「払っています。嫌や嫌やながらですけど。
どこもまともな指導をしないのに大金を払うのはおかしいと、指導してもらうのを止めたいと言っています。
千葉工場は正式に指導依頼を取り消したそうです。ところがそれ以降、指導に行ってないのに、今でも毎月60万の請求書が来ているそうです」
![]() 「うーん、それはおかしいな。當山はしっかりした奴だと思っていたが……
「うーん、それはおかしいな。當山はしっかりした奴だと思っていたが……
とにかく本社に指導依頼を出すように」
![]() 「工場長と調整してください。私は工場長から依頼しないと命じられています」
「工場長と調整してください。私は工場長から依頼しないと命じられています」
猪越課長は去っていく副工場長の後姿を見つめて、何を考えているか分からない人だと思う。
![]() 本日の暴露話
本日の暴露話
認証活動を書こうとすると、認証計画を立て、実際にするスケジュール表を作る必要があると思い至った。
それでキックオフとか内部監査の各部門のスケジュール表、予備審査、本審査などのイベントを1993年のカレンダーを眺めて決めて、WBSとガントチャートをしっかりと作った。
 規定1本作るのに何時間かかるのか、100本規定があると審査準備中に何回、何本くらい改定が発生するかとかは、頭に入っているが、それをバーチャルであっても進めていくのはかなり頭を使う。先に書いたときと日が経ってから書いたときで、規定の本数が替わったりしてはまずい。
規定1本作るのに何時間かかるのか、100本規定があると審査準備中に何回、何本くらい改定が発生するかとかは、頭に入っているが、それをバーチャルであっても進めていくのはかなり頭を使う。先に書いたときと日が経ってから書いたときで、規定の本数が替わったりしてはまずい。
いっそのこと、架空の工場が認証を受けるときのバーチャル認証準備セット、計画だけでなく、必要な規定類、様式、帳票一式を作って売りだしたらと、商売を考えてしまった
そういえばもう20年も前だが、ISO14001対応のすべての規定の雛形(電子データのCD付)なんてのを1万いくらで売っていた。立ち読みしただけで、こりゃ使い物にならないと見切った。
また登場人物の顔と名前、年齢の一覧表も作った。こんなことをするのは、過去の小説を書いたときもしなかった。
そこまでするのかと、自分自身、呆れてしまう。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |