注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
「時は金なり」というが、今の佐川や山口にとって「時は命なり」であった。もちろんそれは比喩表現であり、会社員としての忠誠とか仕事への献身という観点だ。
一番早く予備審査を受ける工場は、それまで出勤日が17日くらいしかない。1日10時間仕事するとして170時間、1時間は0.6%に当たる。ゆっくり考えることもできない。走りながら考えなければならない。
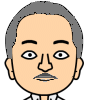 |
||
ISO14001認証は名誉とかカッコよさだが、当時のISO9001認証は事業が継続するかダメかという重大さだった。
もし未達なら会社の売り上げは数百億失われ、責任者は首にならないまでも評価が相当下がり、昇進の可能性は消えるに違いない。
江本部長は執行役員になるのがパー、野上課長は部長になるのがペケとか……
注:アップしてからハッと気が付いて調べたら、執行役員制度とはSONYが1997年に導入したのが最初だそうです。
このお話は今1993年ですから矛盾ですが、まあ〜、笑って見逃してください。
兵庫工場と長野工場のISO認証を達成を使命とされた佐川は、野上課長と一緒に帰ろうとした山口を捕まえて打ち合わせに入った。
まず今晩中に長野まで行って泊ろうと提案した。夕方の東北新幹線でいけば深夜長野に着く。駅前のビジネスホテルを取ってホテルには夜中に入ると連絡してほしい。そうすれば明日、始業時から長野工場で仕事にかかれる。
なお、北陸新幹線は1997年に長野まで長野新幹線として開通したので、1993年にはもちろんない。
いささか強引な佐川の話を聞いて、山口はさすがと思う。當山とは2年間一緒に仕事をしてきたが、
 出張の行きも帰りも余裕をもって計画して、夜討ち朝駆けなどしたことがなかった。その結果、兵庫工場で仕事する時間は、一泊二日で半日だけなんてことになった。
出張の行きも帰りも余裕をもって計画して、夜討ち朝駆けなどしたことがなかった。その結果、兵庫工場で仕事する時間は、一泊二日で半日だけなんてことになった。
感心するとともに、これはひょっとして認証できるかもしれないという気がした。山口自身、心の中ではもう計画通りのISO認証は無理と思っていたのだ。
それから約30分、佐川は明日 長野工場でやるべきことを山口と打ち合わせた。
佐川の希望は工場の見学、現状の進捗説明を受ける、どこでも良いが数部門 内部監査をしたいという。
![]() 「希望は伝えますが、先方の状況を知らない佐川さんが内部監査できますか?」
「希望は伝えますが、先方の状況を知らない佐川さんが内部監査できますか?」
![]() 「できるさ、作業の進捗を見るには内部監査が一番だからね」
「できるさ、作業の進捗を見るには内部監査が一番だからね」
![]() 「内部監査をすれば問題ばかりで話にならないと思いますよ」
「内部監査をすれば問題ばかりで話にならないと思いますよ」
![]() 「それで良いのさ、悪いところを見つけ出して次回までに直してもらう。それを予備審まで4週間あるから、みっつの工場を巡回しても4回転できる」
「それで良いのさ、悪いところを見つけ出して次回までに直してもらう。それを予備審まで4週間あるから、みっつの工場を巡回しても4回転できる」
![]() 「今までの當山さんの方法と全く違いますね」
「今までの當山さんの方法と全く違いますね」
![]() 「何をしなければならないか、現状をよく認識することが認証活動を推進する唯一の方法だ。それすなわち内部監査だよ。心配召されるな」
「何をしなければならないか、現状をよく認識することが認証活動を推進する唯一の方法だ。それすなわち内部監査だよ。心配召されるな」
![]() 「ただ、そうしますと、佐川さんを最近ISO認証開始した工場からの見学者という位置づけではおかしいですね」
「ただ、そうしますと、佐川さんを最近ISO認証開始した工場からの見学者という位置づけではおかしいですね」
![]() 「そうだね、それなら本社でこれから工場のISO認証支援をすることになったと紹介してほしい。當山さんの後任となったでも良い」
「そうだね、それなら本社でこれから工場のISO認証支援をすることになったと紹介してほしい。當山さんの後任となったでも良い」
![]() 「そうなると佐川さんは、もう逃げられませんよ」
「そうなると佐川さんは、もう逃げられませんよ」
![]() 「野上課長が来た時から、そうなるのは分かっていた。だから私としては、逃げるのではなく飛び込むしかなかった。チャレンジの機会と思うしかない。
「野上課長が来た時から、そうなるのは分かっていた。だから私としては、逃げるのではなく飛び込むしかなかった。チャレンジの機会と思うしかない。
長野工場を見たら兵庫工場にも行かなくてはならない。明後日、いや明々後日の朝からにしようか、ISO認証指導に行くと連絡してほしい」
![]() 「
「
![]() 「時間がない。やり方は長野と同じく行きたいが、明日の様子を見て調整しよう」
「時間がない。やり方は長野と同じく行きたいが、明日の様子を見て調整しよう」
![]() 「明日の予定は?」
「明日の予定は?」
![]() 「午前中は工場視察といくつかの部門を内部監査したい。午後からは向うの困りごと相談と質問を受けよう。できれば全部門の内部監査をしたいところだ」
「午前中は工場視察といくつかの部門を内部監査したい。午後からは向うの困りごと相談と質問を受けよう。できれば全部門の内部監査をしたいところだ」
![]() 「了解しました。その旨連絡しておきます」
「了解しました。その旨連絡しておきます」
![]() 「よし、作戦開始だ。山口さんは一旦本社に帰って、出張の準備をしてほしい。私は携帯電話を借りていきます。山口さんも携帯を用意しておいてください」
「よし、作戦開始だ。山口さんは一旦本社に帰って、出張の準備をしてほしい。私は携帯電話を借りていきます。山口さんも携帯を用意しておいてください」
![]() 「あっ、私は携帯電話を貸与されています」
「あっ、私は携帯電話を貸与されています」

注:1990年代初め、携帯電話は普及途上
高校生が携帯電話やPHSを持つようになったのは2000年以降だろう。それまではポケベルが最先端で、好きな人に「114106」なんて打っていたのだ。
緒形 拳主演の「ポケベルが鳴らなくて」なんてTVドラマが流れたのは、まさにこのお話の年、1993年であった。
翌朝、ビジネスホテルの狭いロビーで顔を合わせた佐川と山口は、黙って頷きあって長野工場に出陣した。
長野駅から数キロ離れた工業団地に長野工場はあった。従業員900名ほど、この地域では大きな工場である。製品は小型の歯車関係のユニットで、ギヤードモーターなどだ。
顧客企業の製品が、欧州へ輸出されておりISO9001認証が要求された。
山口は何度も来ているらしく、守衛所で入場の手続きをすると、佐川を工場の奥の方の事務所に案内する。
既に連絡がついていて、品質保証課の新沢課長と池神さんが待っていた。佐川は以前池神さんに電話でISO認証について問い合わせたことがある(第12話)。
池神さん |
新沢課長 |
 佐川 |
 山口さん |
「當山さんが退職されたって聞きました。長野工場は来月22日に予備審査です。これからどのような対応をするのか非常に懸念しております」
![]() 「いろいろご迷惑をおかけしておりまして大変申し訳ありません。まず本社の対応を説明したいと思います。
「いろいろご迷惑をおかけしておりまして大変申し訳ありません。まず本社の対応を説明したいと思います。
當山はご存じと思いますが、就業規則違反で諭旨解雇となりました」
「あのISOの資料でお金を取ったことですか?」
![]() 「そうです。それについては別途、職制を通じて本社から長野工場の方に事情説明とお詫び、また被害者への補償の話があると思いますので、ここでは省かせていただきます。
「そうです。それについては別途、職制を通じて本社から長野工場の方に事情説明とお詫び、また被害者への補償の話があると思いますので、ここでは省かせていただきます。
當山の後任として、この佐川さんがISO認証の指導に当たりますので、本日は挨拶と状況確認に参った次第です」
「格式ばった話はどうでも良いですが、予備審が二十数日後なんですよ💢
本社はどのように責任を取るのですか?」
![]() 「お気持ちは良く分かります。責任を取るというのは二つの意味があると思います。罪を負うという意味もありますが、計画を達成する意味もあります。
「お気持ちは良く分かります。責任を取るというのは二つの意味があると思います。罪を負うという意味もありますが、計画を達成する意味もあります。
私は後者の実現のために来たつもりです」
「そりゃカッコイイ話ですが、嘘偽りなしにできるのですか?」
![]() 「本日は、それを調べたい。頑張ればできる範囲なら私も頑張りますし、皆さんにも協力してもらいたい」
「本日は、それを調べたい。頑張ればできる範囲なら私も頑張りますし、皆さんにも協力してもらいたい」
「當山さんの指導がいい加減だったのは、明らかです。この数か月してきたことは、彼の指示に従ってやってはやり直しの繰り返しで、少しも前進がありません」
![]() 「過去については申し訳ないとしか言いようがありません。とりあえず現状を見せていただき、何をどうするかを考えたいと思います」
「過去については申し訳ないとしか言いようがありません。とりあえず現状を見せていただき、何をどうするかを考えたいと思います」
「池神さん、現場を一通り案内してきてくれるかな。1時間で戻ってきてほしい。
山口さんからの依頼された通り、1時間後に製造課長と技術課長、購買課長、総務課長を集めておく。
佐川さんがおっしゃるように予定通り認証が達成できるなら、最大限に協力というか努力したいと思う」
「内部監査なんて、まだ何も形になっていないのに、そんなことしても無駄ですよ」
「それはまた考えよう。それじゃ池神さん、工場を案内してください」
池神さんは憤懣やるかたない様子だが、なんとか文句を言いうのをこらえて二人を工場に案内する。
工場は機械加工職場と、ギアボックスの組み立てなどの職場の二つに分かれる。
従来からの汎用機をうまく組み合わせて半自動化ラインにしている。管理項目は一般的な機械加工と機械組み立てというところだ。
切削油の焦げる匂いが佐川には心地よい。
工場を巡回して戻ると、指名した課長4名と新沢課長が待っていた。
みな不服そうな顔をしている。
佐川 | 山口 | ||
 |  吉村購買課長 吉村購買課長 |
||
 |  大林総務課長 大林総務課長 |
||
新沢品証課長 | 池神品証課員 | ||
![]() 「初めまして、佐川と申します。福島工場でISO認証の担当をしておりましたが、昨日、突然、全社のISO9001認証の指導役を承りました。
「初めまして、佐川と申します。福島工場でISO認証の担当をしておりましたが、昨日、突然、全社のISO9001認証の指導役を承りました。
この仕事に就いたからには、冗談抜きに予備審を問題なし本審査も問題なしで認証を得るつもりでおります。最大限頑張りますから、ご協力願います」
![]() 「佐川さん? 立場と気持ちは分かりますが、本当に大丈夫ですか?」
「佐川さん? 立場と気持ちは分かりますが、本当に大丈夫ですか?」
![]() 「本気です。信用してくださいと言っても信用できないと思います。それで本日はここに課長が4名いらっしゃいますので、4つの課の内部監査をしたいと思います。
「本気です。信用してくださいと言っても信用できないと思います。それで本日はここに課長が4名いらっしゃいますので、4つの課の内部監査をしたいと思います。
それをすれば私はこちらがどれほどできているかを確認できますし、皆さんも長野工場の仕上がり具合を実感できて審査でパスするか否か感じられるかと思います」
![]() 「内部監査をするって、我々は過去何カ月も右往左往しただけで、まだ何もしてませんよ!」
「内部監査をするって、我々は過去何カ月も右往左往しただけで、まだ何もしてませんよ!」
![]() 「そうおっしゃらず、しばし付き合ってください。
「そうおっしゃらず、しばし付き合ってください。
まずは資料を渡します」
![]() 「當山さんの資料と同じじゃ困るよ、アハハハ」
「當山さんの資料と同じじゃ困るよ、アハハハ」
佐川は新沢、池神を加えた6名に福島工場の三段組を配る。
受け取った人たちは興味深くざっと眺め、自分の関わりそうなところを探してじっくりと読む。
数分時間をおいて佐川が話し始めた。
![]() 「少しは興味を持っていただけましたか。それではこれについて話をしたいと思います。
「少しは興味を持っていただけましたか。それではこれについて話をしたいと思います。
これは福島工場で作ったものです。一番左の列はISO規格の本文、その次の列の要求事項の解説です。ここまでは長野工場も同じです。その次の工場の規定類は皆さんがここの規定を探して書き込んで長野工場用の三段組を作らないとなりません」
![]() 「こんな資料の作り方もあるのか」
「こんな資料の作り方もあるのか」
![]() 「法律を理解しようとすると、こういう対照表を作るのが一般的だね。三段組という言葉もそこからだろう」
「法律を理解しようとすると、こういう対照表を作るのが一般的だね。三段組という言葉もそこからだろう」
![]() 「どの部門がどの要求事項に関わるか、何をするのか、関係する文書や記録の固有名詞がビジブルだ」
「どの部門がどの要求事項に関わるか、何をするのか、関係する文書や記録の固有名詞がビジブルだ」
![]() 「わざわざ作らなくても、規格要求がどんなものかと、何をしなければいけないかが分かれば、このままでも有効じゃないのか?」
「わざわざ作らなくても、規格要求がどんなものかと、何をしなければいけないかが分かれば、このままでも有効じゃないのか?」
![]() 「そうではありますが、どの部門が担当しているかは、工場によって取り合いが異なります。一目で規格要求と該当する規定、該当部門とそこがすることを、対照できるのがメリットなのです」
「そうではありますが、どの部門が担当しているかは、工場によって取り合いが異なります。一目で規格要求と該当する規定、該当部門とそこがすることを、対照できるのがメリットなのです」
注:「取り合い」とは建築関係では接合部あるいは接合部の処理を言うが、会社の仕事では文字通り仕事の分担、境界を言う。ここまでは○○課、ここからは○○課という塩梅だ。
![]() 「なるほど、なぜ本社はこういうまとめ方を始めに教えなかったのですか?」
「なるほど、なぜ本社はこういうまとめ方を始めに教えなかったのですか?」
![]() 「大変申し訳ありません。私どもの力不足としか言いようがありません。福島工場は本社の指導を受けず、外部講習会にも行かず、ひたすら規格を読んでアプローチを考えたと聞きます」
「大変申し訳ありません。私どもの力不足としか言いようがありません。福島工場は本社の指導を受けず、外部講習会にも行かず、ひたすら規格を読んでアプローチを考えたと聞きます」
![]() 「しかし作る手間が大変だな。今から取り掛かっても手遅れかな」
「しかし作る手間が大変だな。今から取り掛かっても手遅れかな」
![]() 「申し訳ありませんが、後ろ向きのことは取り合えずおいといて、前向きのことだけ考えましょう。
「申し訳ありませんが、後ろ向きのことは取り合えずおいといて、前向きのことだけ考えましょう。
この資料を三段組と呼んでいます。もちろん作らなくても認証には関係ありません。必須ではないが役に立ちます。
これから話を進めると、いかに役に立つを実感するでしょう。
それじゃ内部監査の練習です。職制の順序から総務課から行ってみましょう」
![]() 「えっ、もう始めるの。しかも私からですか? どういう進め方になるでしょう?」
「えっ、もう始めるの。しかも私からですか? どういう進め方になるでしょう?」
![]() 「一応、ISO審査の方法は調べました。それに倣っていきます。では質問を始めます。
「一応、ISO審査の方法は調べました。それに倣っていきます。では質問を始めます。
本チャンの審査のつもりで回答願います。質問が分からないときは分からないと言ってください。私が言い方を変えたり質問を変えます。
審査員の質問が理解できなくても審査でマイナスにはなりません。
では、
総務課が、ISO規格要求事項に関わるのは、文書管理、教育訓練、方針の周知といったところですか?」
![]() 「教育訓練というのは規格を読みますと……ええとこの三段組では今まで當山さんに教えらえたのと違い、一般的な社内教育や社内の昇格試験とは関係ないようです。そうなりますと総務課は文書管理と方針の周知だけでしょうか?」
「教育訓練というのは規格を読みますと……ええとこの三段組では今まで當山さんに教えらえたのと違い、一般的な社内教育や社内の昇格試験とは関係ないようです。そうなりますと総務課は文書管理と方針の周知だけでしょうか?」
![]() 「おっしゃる通り、ISO規格の教育訓練とは仕事についての技術・技能ですので、社内の資格別教育とか社内の資格試験ではありません。
「おっしゃる通り、ISO規格の教育訓練とは仕事についての技術・技能ですので、社内の資格別教育とか社内の資格試験ではありません。
お宅は品質マニュアルを作りましたか?」
「規格対応で作ってはあるのですが、この三段組を見て、こりゃ違うぞと思うところが何カ所もあります。ということで全面書き換えになりますね」
![]() 「そうですか。それは大変でしたね。
「そうですか。それは大変でしたね。
でも、この三段組の右側の縦軸二つをまとめるとマニュアルの記述になるのです」
「えっ、そうなの!
それではすぐにウチ用の三段組を作らないといかんな」
![]() 「そんなに時間はかからないでしょう。
「そんなに時間はかからないでしょう。
それに、いろいろな用途に使えるでしょうしマニュアルの文章にも流用が聞きますから」
「マニュアルを書くのにどれくらいかかりますかね。来週くらいにはマニュアルを出さないとならないのです」
![]() 「三段組をしっかり作れば一日あれば十分でしょう。
「三段組をしっかり作れば一日あれば十分でしょう。
すみません、本題に戻ります。
それでは大林課長さん、質問に入ります。
文書管理とは規定の発行や改定の際の取り扱いのことです。工場の規定を新規制定や改定したとき、工場内にはどのように周知しますか?」
![]() 「規定を新設や改定するとき、新規制定・改定されたというカバーレターを付けて規定のコピーを配布先に送付します。
「規定を新設や改定するとき、新規制定・改定されたというカバーレターを付けて規定のコピーを配布先に送付します。
ええと、規定のファイルは各課に配布されているわけではありません。常時使われるものではありませんので、例えば総務部なら総務課、人事課、経理課と課が三つありますが、規定集は1部だけです。
購買部も1部ですね。製造部になると製造部の事務所と製造課の事務所が二箇所あるので三部になります。現在工場全体で14部だったと思います。
配付されると規定集を置いている部署の庶務担当がその事務所内に朝礼とか回覧で周知しますが、総務部全課に周知しているかとなるとしていないかと思います」
![]() 「なるほど。
「なるほど。
規定集が全部の課に配布されていないとなると、必要な部署、例えば配布されていない現場の係事務所とか計測器管理室とかで、孫コピーつまり規定集をコピーして使っているということはありませんか?」
![]() 「いや〜、実はそう言うことがありました。ウチとしては発行部数を増やしたくない、使う方もめったに見るものではない。
「いや〜、実はそう言うことがありました。ウチとしては発行部数を増やしたくない、使う方もめったに見るものではない。
しかしいざ必要な時、別の建屋まで行くのは嫌だといろいろ事情が重なって、そういうことが行われています。
まだそれで問題が起きたことはないですが、いつかは問題が起きるでしょうね」
![]() 「脇から失礼します。現時点問題が起きていなければ良いのか、問題が起きる可能性があればダメなのか、どうなんでしょう?」
「脇から失礼します。現時点問題が起きていなければ良いのか、問題が起きる可能性があればダメなのか、どうなんでしょう?」
![]() 「規格では『すべての部門において、適切な文書の適正な版が利用できること(ISO9001:1987 4.5)』とありますから、仕組みとしてすべての部門が使えることが条件ですね。
「規格では『すべての部門において、適切な文書の適正な版が利用できること(ISO9001:1987 4.5)』とありますから、仕組みとしてすべての部門が使えることが条件ですね。
この『使えること』というのは、別の部屋でも良いのか、別の建物に置いてあっても良いのか疑問を持つでしょうけど、同じ部屋なら良いと考えればよろしいです。言い換えると別の部屋、別の建屋ではNGです」
![]() 「総務部は一つの部屋だから1冊で良いということですな?」
「総務部は一つの部屋だから1冊で良いということですな?」
![]() 「そうなります。但し、もし給食とか清掃などを総務が管理していて、その部署でも工場規定を参照することがあるなら、そこにも配布しないとならないことになります」
「そうなります。但し、もし給食とか清掃などを総務が管理していて、その部署でも工場規定を参照することがあるなら、そこにも配布しないとならないことになります」
![]() 「総務部では執務規定という課内の文書を作っております。給食の日常業務や清掃の方法や外注するときの手順なども執務規定に定めています。執務規定は給食には給食の執務規定、清掃には清掃の執務規定を配布しています。
「総務部では執務規定という課内の文書を作っております。給食の日常業務や清掃の方法や外注するときの手順なども執務規定に定めています。執務規定は給食には給食の執務規定、清掃には清掃の執務規定を配布しています。
それでよろしいのですか?」
![]() 「それで結構です。もちろんその執務規定も孫コピーはダメですからね。
「それで結構です。もちろんその執務規定も孫コピーはダメですからね。
先ほどのことに戻りますが、万が一、孫コピーが存在すれば有無を言わさずアウトになります。
他の部門も注意してください。総務は発行の管理はしなければなりませんが、それを受け取った部門で孫コピーしていれば、その部門の責任ですからね」
![]() 「分かりました。全部門に調査をかけて孫コピーを廃棄させます。どうしても必要なら正規に配布することにします」
「分かりました。全部門に調査をかけて孫コピーを廃棄させます。どうしても必要なら正規に配布することにします」
![]() 「うちもあぶないなあ〜、それにさ、JIS規格とか無造作にコピーしているけど、あれも著作権侵害だよね」
「うちもあぶないなあ〜、それにさ、JIS規格とか無造作にコピーしているけど、あれも著作権侵害だよね」
「JISZ9901をコピーしている人は結構いるんじゃないか。審査日前に一斉点検して……いや審査場に持ち込むなと徹底しよう」
注:ISO9001を最初に翻訳規格としてJISに制定したとき、「Q(管理システム)」という区分がなく「Z(その他)」の区分でJISZ9901として制定された。
なぜJISZ9001としなかったのかは今となると闇の中です。
![]() 「おっと、ISO規格で審査対象となる文書は、三段組で引用している規定だけです。
「おっと、ISO規格で審査対象となる文書は、三段組で引用している規定だけです。
ですから給食とか清掃は例えとして挙げただけです。もちろんISOに無関係でも問題が起きては困りますから、孫コピーは禁止したいですね」
「規定といっても、すべての規定をすべての部門で使うわけではないです。部門によっては、必要な規定のみ配布することでどうなんでしょう」
![]() 「必要な部門に必要な規定を配布することは問題ありません。現実に人事管理に関する規定は配布先を限定していますね。
「必要な部門に必要な規定を配布することは問題ありません。現実に人事管理に関する規定は配布先を限定していますね。
それは工場で決めればよいことです。ISO規格は『すべての部門において、適切な文書の適正な版が利用できる(4.4.1a)』ですから、現場で経理とか購買の規定はいらないかもしれません。
どの規定をどこに配布するかは、大林課長さんが決めればよろしいです。もちろん一部配布することや配布先を、文書管理規定に記載されてないといけません。
しかし総務部がそういう細かい管理ができるのか、どうでしょう」
![]() 「了解しました。費用と手間を考えて決めましょう」
「了解しました。費用と手間を考えて決めましょう」
![]() 「次の質問ですが、改定があったときの差し替えはどのように行いますか?」
「次の質問ですが、改定があったときの差し替えはどのように行いますか?」
![]() 「配付している部門に、改定後の規定と規定改定のカバーレターを付けて配布します。受け取った部門は差し替え後に、差し替えたこと、古い規定は破いて廃棄したことを記して返送します。返送されたものは、差し替えた証拠として総務が保管します。
「配付している部門に、改定後の規定と規定改定のカバーレターを付けて配布します。受け取った部門は差し替え後に、差し替えたこと、古い規定は破いて廃棄したことを記して返送します。返送されたものは、差し替えた証拠として総務が保管します。
その取扱いはカバーレターに書いてあります。カバーレターの様式は文書管理規定の付図としています」
![]() 「差し替えらえた古いバージョンはどのようにするのでしょう?」
「差し替えらえた古いバージョンはどのようにするのでしょう?」
![]() 「各部門で破いて燃えるゴミに入れます。工場の規定ですから機密保持を気にするようなものはありません。間違って使われるのを防げばよいと考えています」
「各部門で破いて燃えるゴミに入れます。工場の規定ですから機密保持を気にするようなものはありません。間違って使われるのを防げばよいと考えています」
![]() 「良く分かりました。
「良く分かりました。
ええと、今回は内部監査というより状況調査なので課長さんたちの言葉を信じていますが、実際の内部監査やISO審査ではすべてそれを定めている規定を開いて、書かれている場所を指さして説明しなければなりません。
手ぶらで説明するのはダメです。それは忘れないでください。
実際の審査ですと、審査員は審査する部門の規定をパラパラ見て、いくつかの規定の名称、バージョン……改定何版かですね、それをいくつか控えておいて、あとで総務部の原本と参照して間違いがないかをチェックします」
![]() 「おお、それでは審査前に規定集全部のバージョンを調べておかないといけませんね」
「おお、それでは審査前に規定集全部のバージョンを調べておかないといけませんね」
![]() 「そうです。よろしくお願いします。特に審査日直前となると、各部門があわてて規定を改定をするのが常ですから、審査前夜に実施しないと確実じゃありません。
「そうです。よろしくお願いします。特に審査日直前となると、各部門があわてて規定を改定をするのが常ですから、審査前夜に実施しないと確実じゃありません。
1冊ずつするのは能率的じゃありませんから、工場のすべての規定集を集めて、一冊にひとり付けて、目次から各規程まで掛け声かけてやるといいですよ。
総務課長さんには、方針の周知徹底のことも聞かないとなりません。
長野工場の品質方針は、どのような形で従業員に知らしめているのでしょう?」
![]() 「それについてはですね、自信があるのですよ、アハハハ
「それについてはですね、自信があるのですよ、アハハハ
この工業団地には既にISO認証したところがありまして、相談に行きました。そこでは胸に取り付ける名札のサイズの紙に方針を印刷して名札の裏側に差し込んでおくという方法でした。ウチもその方法を今年の正月から実施しております。
審査員に方針を聞かれたらカードを見せれば良いのです」
![]() 「その方法を聞いて、ISOも簡単だなと思ったよ、アハハ」
「その方法を聞いて、ISOも簡単だなと思ったよ、アハハ」
![]() 「ええとISOの要求は『この方針が組織のすべての階層で理解され、実施され、維持されることを確実にする(ISO9001:1987 4.1.1)』とあります。
「ええとISOの要求は『この方針が組織のすべての階層で理解され、実施され、維持されることを確実にする(ISO9001:1987 4.1.1)』とあります。
方針を印刷したカードを配ると理解されるのですか?」
![]() 「それは……理解されるとは言えませんね。方針カードを持っていても読んだかどうか分かりませんし、理解したかになると……」
「それは……理解されるとは言えませんね。方針カードを持っていても読んだかどうか分かりませんし、理解したかになると……」
![]() 「私が審査員なら、カードを見せられても理解したとは受け取りませんね」
「私が審査員なら、カードを見せられても理解したとは受け取りませんね」
![]() 「そう言われるとそうですが……となると、どんな方法が?」
「そう言われるとそうですが……となると、どんな方法が?」
![]() 「まず方針を理解するという意味ですが、おたくの品質方針を実は知らないのですが、いくつか項目があっても、一人の人がすべてに関わっているということはないでしょう。
「まず方針を理解するという意味ですが、おたくの品質方針を実は知らないのですが、いくつか項目があっても、一人の人がすべてに関わっているということはないでしょう。
ですから方針を理解するといっても、階層や職務によってレベルとか内容が異なると思います」
![]() 「『火の用心』のようなイメージですな?」
「『火の用心』のようなイメージですな?」
![]() 「その通りです。工場長が『火の用心』と言ったとして、管理職も部下も『火の用心』と唱和しても意味がありません。職階によって具体化して伝えないとならないのです。ですから方針を理解しているかと言っても、購買の課長と製造のパートの人の理解は異なるはずです」
「その通りです。工場長が『火の用心』と言ったとして、管理職も部下も『火の用心』と唱和しても意味がありません。職階によって具体化して伝えないとならないのです。ですから方針を理解しているかと言っても、購買の課長と製造のパートの人の理解は異なるはずです」
![]() 「方針の周知とはそう言うことだったのか」
「方針の周知とはそう言うことだったのか」
![]() 「お尋ねになったその会社では、審査員がまあしょうがないと思ってOKしたのかもしれませんね。
「お尋ねになったその会社では、審査員がまあしょうがないと思ってOKしたのかもしれませんね。
高田課長さんは製造課でしたね。高田課長さんが今年は現場の不良を半減しようと考えたとき、課員全員が毎朝『1993年の不良を0.5%する』と唱和したらうれしいですか?」
![]() 「ハハハ。少しもありがたくないですね」
「ハハハ。少しもありがたくないですね」
![]()
| |||||||||||||||||||||||||
それを受けて現場のリーダーは育成すべき人をローテーションさせることを考える、作業者は自分の技能を高め確認するために今年は1級技能士をと挑戦するかもしれない、パートの人は日常異常を発見したらすぐに監督者に知らせようと思うかもしれない。
そういうことが方針の周知徹底ですよ」
![]() 「品質方針と、部や課の年度目標とは意味が違うのではないかな?」
「品質方針と、部や課の年度目標とは意味が違うのではないかな?」
![]() 「おっしゃる通り違います。違うというのは片や基本精神であり、片やそれを展開したものだからです。それらは同じではないですが、整合していなければなりません。
「おっしゃる通り違います。違うというのは片や基本精神であり、片やそれを展開したものだからです。それらは同じではないですが、整合していなければなりません。
ISO規格では、品質方針を実施せよとあります。部長方針は工場の方針を展開したものであり、課長方針は部長方針を展開しているはずです。そうでなければ一体だれが品質方針を実現するのですか?
だから品質方針の目指すところを実現するために、各員が何をするのかを理解しなければならない。
早い話が工場長の方針を暗記するより、課長方針を聞いて自分が何をするのかを理解してほしいのです」
![]() 「なるほど、それが火の用心か、火の用心のために、何をすべきかが問題なのだな」
「なるほど、それが火の用心か、火の用心のために、何をすべきかが問題なのだな」
「そういう理解でISO審査がOKになるのですか? 品質方針を暗記しているほうがパスするような気がします」
注:1993年審査に来たイギリス人の審査員は「紙に書かれた品質方針を知っていても、日々何をするのか知らなければ意味がない」と(英語で)語った。ISO9001認証が始まった当時は、そういう考えをしていた審査員が多い。
実際の審査ではラインのパートの人やオフィスで「あなたは日々どんなことに留意しているか?」とか「今年、あなたが改善しようとしているのは何ですか?」という質問をして、その返答が品質方針にマッチしているかを確認した。
「方針を言ってください」という愚かな質問をした人はいなかったようだ。
それに比べて、方針カードの携帯を確認する審査は楽だろう 😛
ISO14001時代になると、審査員が劣化したようで、環境方針を暗記しろとか方針カードを持っていれば良いと、バカなことを主張する審査員が多くなった。
環境方針を暗記したり無用なカードを作るより、省エネ、省資源活動に精を出してくれた方が地球のためだ。
![]() 「確かにそういう審査員もいるでしょうね。でもそうなったら議論して規格を読んで聞かせましょう。
「確かにそういう審査員もいるでしょうね。でもそうなったら議論して規格を読んで聞かせましょう。
私も立ち会いますから、もめたら参加しますよ。
ええと、ここまで内部監査の練習をしてきて、何か気付いたことがありますか?」
皆顔を見合わせる。
なにもアイデアが浮かばないようだ。
![]() 「この三段組を見てほしいのですが、私は単純に規格要求の項目の右側の何をしなければならないかが書いてある升目を読んでいるだけです。
「この三段組を見てほしいのですが、私は単純に規格要求の項目の右側の何をしなければならないかが書いてある升目を読んでいるだけです。
そして皆さんの回答は、その右側の升目に書いてあることだと気付いてほしいのです」
![]() 「えっ、ということは、この三段組があれば……」
「えっ、ということは、この三段組があれば……」
「そういうことか!」
![]() 「ISOの審査はISO規格要求事項を満たしていることの確認ですから、要求事項以外を審査しません。ですから規格で『定める』『確実にする』『しなければならない』とあることをしっかりとする、それ以外はしなくて良いのです。
「ISOの審査はISO規格要求事項を満たしていることの確認ですから、要求事項以外を審査しません。ですから規格で『定める』『確実にする』『しなければならない』とあることをしっかりとする、それ以外はしなくて良いのです。
なお、規格で『定める』とあるのは規定で定めること、また『確実にする』とあるのは記録を残すことです。そう理解してください」
![]() 「そういう意味だとは知りませんでした。山口君も言わなかったな」
「そういう意味だとは知りませんでした。山口君も言わなかったな」
![]() 「私も知りませんでした。申し訳ありません」
「私も知りませんでした。申し訳ありません」
![]() 「それからISO審査では徹底されているかをしっかり見ます。規定改定の差し替えミスとか、日常点検がちゃんと埋まっているかとか、押印は決裁者のハンコであるかとか」
「それからISO審査では徹底されているかをしっかり見ます。規定改定の差し替えミスとか、日常点検がちゃんと埋まっているかとか、押印は決裁者のハンコであるかとか」
![]() 「そういうことは日々仕事をしている人でないと気が付きませんね。おっと、佐川さんも製造課長だったそうですね」
「そういうことは日々仕事をしている人でないと気が付きませんね。おっと、佐川さんも製造課長だったそうですね」
![]() 「首になりましたけど」
「首になりましたけど」
![]() 「福島工場の偉いさんは見る目がないのです。長野工場にいらっしゃい」
「福島工場の偉いさんは見る目がないのです。長野工場にいらっしゃい」
![]() 「高田課長、止めてくださいよ。やっとのことで本社に来てもらったのですから」
「高田課長、止めてくださいよ。やっとのことで本社に来てもらったのですから」
![]() 「冗談抜きに、このような人がISO認証の指導をすべきだ」
「冗談抜きに、このような人がISO認証の指導をすべきだ」
その後、駆け足であったが、技術課、購買課、製造課の内部監査の
![]() 「最初に佐川さんは内部監査をすると、どこまでできているか感じられるとおっしゃった。確かに良く分かりました。
「最初に佐川さんは内部監査をすると、どこまでできているか感じられるとおっしゃった。確かに良く分かりました。
身びいきかもしれませんが、ウチのできは決して悪くないと思います。というか元々工場の規定がしっかりしていて、業務においてそれを守っていたのではないかな」
「私も同じく思いました。ISO規格に合わせてというよりも、現状を見せてISO規格を満たしていることを説明するという方向が正しいように思います」
![]() 「おっしゃる通りです。新沢課長は顧客による品質監査を何度も経験されたと思います。ISO規格だって特別なものでなく顧客要求の一つにすぎません。
「おっしゃる通りです。新沢課長は顧客による品質監査を何度も経験されたと思います。ISO規格だって特別なものでなく顧客要求の一つにすぎません。
顧客対応で当社の仕組みを作るとか、変えるなんて発想がおかしいです。当社の仕組みは確固たるものである、客がいろいろ要求してきたら、当社のルールが既にそれを満たしていると説明するスタンスです」
![]() 「とは言うものの、実際には議事録を作っていなかったり、ハンコがないとか、代印をした人が代行権限がなかったりと……叩けば埃だらけですけど、アハハハ」
「とは言うものの、実際には議事録を作っていなかったり、ハンコがないとか、代印をした人が代行権限がなかったりと……叩けば埃だらけですけど、アハハハ」
![]() 「まあ、それはすこしずつ改善していってほしいです。
「まあ、それはすこしずつ改善していってほしいです。
ええと、これからのことになりますが、品質保証課で三段組を全部を埋めるのは大変ですから、各部署にそれぞれ関連する項番に印をつけて電子データを配布して、埋めてもらうというのが良いかと思います。
ひとつの課が関わるのは、せいぜい項番ふたつとか多くて三つでしょう。そこの規格の文章はせいぜい30行くらい。そこだけしっかり読んで、自分の課が関わることを書き込むというなら二日もあれば十分です。
そして該当する規定が大丈夫か確認する、そこで決めている議事録とか帳票とか報告書とかあるのか、決裁はどうか、保管はどうか、そういうことを確認すればISO審査対応としての文書の確認はおしまいです」
「おっしゃること分かります。できるかどうかはともかく、今やらねばならないことはそれですね。池神さん、今日中に今言われたことをやって、明日、各部門を集めて実行を頼もう」
![]() 「これだけやればISO審査対応はおしまいですか?」
「これだけやればISO審査対応はおしまいですか?」
![]() 「そう甘くはありませんよ。もう一つ現場があります。
「そう甘くはありませんよ。もう一つ現場があります。
例えば、ルールでラインの接地抵抗の定期点検・測定そして基準を決めているなら、その通り接地抵抗を測定しているか、記録があるか、定められた基準を満たしているか、そういうことがチェックされます。
あるいは指名業務なら指名された人が仕事しているかもあるでしょう。
温度・湿度の記録表が現場にあれば、日々のチェックがされているとか、計測器の精度・校正状況など、異常がないか、要資格作業は有資格者が行っているか、そういうのを点検しておかなければなりません」
![]() 「高田課長、そういったことはどうですか?」
「高田課長、そういったことはどうですか?」
![]() 「まだそこまでしていません。これからしっかりと点検します。いや点検をしているかどうかを点検します」
「まだそこまでしていません。これからしっかりと点検します。いや点検をしているかどうかを点検します」
「篠原課長、お宅の議事録や設計図面の照査や兼任の実施者はルール通りですか?」
![]() 「まだ20日あります。いろいろあって大変ですが、とりあえず文書関係は三段組をお願いしますよ。
「まだ20日あります。いろいろあって大変ですが、とりあえず文書関係は三段組をお願いしますよ。
ええと、今14時ですね。
山口さんとここに来るとき、長野で今日一杯と明日の昼過ぎまで各課の内部監査の練習をして、夕方、兵庫工場まで移動、明後日 朝から兵庫工場で、ここでやったことと同じことをしようと考えていました。
新沢さんの方でもう私どもがいなくても大丈夫というなら、本日夕方から兵庫に移動しようと思いますが、どうでしょう?」
「今日はそちらから教えられましたが、こちらでは疑問カ所が多々あります。それで一問一答という形で教えていただけないですか」
![]() 「だいぶありますか?」
「だいぶありますか?」
「できれば各課順々に来てもらって、それぞれの疑問点や対策案について相談してもらうという形で進めたいですが?」
![]() 「よろしいですよ。お願いですが、そういう疑問は他の工場でもあると思います。それでお宅がQ&Aを書かれるなら、コピーを頂けますか。
「よろしいですよ。お願いですが、そういう疑問は他の工場でもあると思います。それでお宅がQ&Aを書かれるなら、コピーを頂けますか。
差しさわりがあるなら部門を消して、他の工場に配布したいです」
「それはよろしいです。もちろん他の工場のQ&Aも頂けるのでしょうから」
その後、新沢課長が関係部門を順番に呼んで、疑問や相談を佐川が始めた。
そして今日、内部監査の練習をしなかった部門は、明日の朝から15時まですることとした。
明日16時に長野を立つと21時には西明石に着く。ホテルに泊まって明後日、朝から兵庫工場で今日と同じことをしようと考える。
山口にその旨伝えると、彼は了解してホテル手配と兵庫工場と調整すると返答した。
山口は会議室から品質保証課に戻って、切符の手配、ホテルの確保、兵庫工場との調整を行った。當山氏のときから、そういった庶務事項は山口に丸投げだった。
自分自身、旧帝大のマスターでそんなことをするのに山口は不満だったが、佐川のためならと思うと苦にならないものだ。
・
・
一段落すると山口は本社の野上課長に電話をする。
![]() 「おお、山口君か、今日一日の成果はどうだ?
「おお、山口君か、今日一日の成果はどうだ?
佐川君は口だけ男か、まともなのか?」
![]() 「佐川さんは本物です。長野工場の人は佐川さんの力量を認めました。指導は真摯に受け止めています。
「佐川さんは本物です。長野工場の人は佐川さんの力量を認めました。指導は真摯に受け止めています。
ただ時間的に間に合うかどうかは心配です。せめて半月早く彼を引き込めたら十分間に合ったと思います」
![]() 「そうか、不適合ゼロは難しいだろうが、なんとか数件の是正で認証できるよう頑張ってくれ。明日また途中報告を頼む」
「そうか、不適合ゼロは難しいだろうが、なんとか数件の是正で認証できるよう頑張ってくれ。明日また途中報告を頼む」
![]() 本日、持たれるだろう疑問
本日、持たれるだろう疑問
おばQはそんなことをしたのかと、
残念ながら、当時は情報源もなく強風にあおられた落葉のように、彷徨っておりました。
佐川先生が怖いものなしの傍若無人できるのは、30年間のチートがあるからです。
私がこうすればうまく行くと自分の考えを持てたのは、3箇所くらい認証してからでしたね。4回目はもう飽きましたけど。
幸いISO14001はすぐに登場しました。この小説でISO14001の登場は40話くらいでしょうか?
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
1990年頃からのデータが見つからなかった。2000年頃は既に高校生が持つものになっていて、携帯登場時の状況が見えない。 ・日本銀行 企業物価指数「携帯電話機の価格の推移」 ・携帯電話普及の背景要因に関する考察 |
外資社員様からお便りを頂きました(24.09.12)
おばQさま 1993年は、老人には少し前のように感じますが、描くのは大変なのですね。今だと当然な事が無い。 前回のお話でも勘違いしたのが少額訴訟で、当時は無かったのでした。 長野オリンピックは1998年だから、新幹線は高崎―長野間は無い。 信越線の特急で、碓氷峠を越えてゆく。山越え用に電気機関車をつなぐから、横川で特急も停車して、釜飯を買っていたのでした。 長野から明石までのルートだと、長野から松本へ出て飛行機(東亜国内のYS-11?)で伊丹へというルートも想定できますが、当時の空路となると皆目判らないから、やはり新幹線移動ですね。 ISOの指導 佐川は未来記憶と経験があるから、頼もしく長野工場を監査し指導してゆく。 大活躍ですし、工場関係者の本社への不信感も拭われて何よりです。 当時の通信事情:パソ通を思い出しました。ノートPCに、アナログモデム(PCカード)を差し込んで、電話のモジュラーを繋ぎ変えて「ピーヒャララ」と音がする。 1200bpsくらい出ればバンザイ、下手すると300bps ホテルの電話がモジュラージャックになっていないとモデムを繋げないので、音響カブラーなんてものも存在しました。 灰色のISDN対応の公衆電話があると、高速通信(1200-4800bps)出来て感動していた。 だから添付ファイルを送る場合は、kB程度で無いと無理。 500kBを越えるファイル送信の場合は、数十分かかったような気がします。 当然の、その間は電話代がかかるから、出張精算で、何で電話代が、こんなに高いのだと叱られた事もありました。 NIFTYなどを利用すると、各地にポートがあるのでローカル電話でつなげられるから電話代が助かった記憶があります。 細かい話は出てこないけれど、出張の多い佐川も、パソ通をやっていたのでしょうね。 これからも楽しみにしております。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 釜飯、スイッチバック思い出します。あの峠を何度通ったことかと、思い返すとあまりいい思い出はありません。改修とかお詫び出張とか(笑) この30年間でもいろいろなことが変わりました。賃金は裁量なんちゃらというので、時間外は付きませんとかなりました。 私の住んでいた郡山市の住宅地も下水道が来て水洗便所になりました。それまでは汲み取りだったのです。もっとも20年前に千葉に引っ越してきてから、習志野市、千葉市、市川市、船橋市を2年ごとに引っ越しましたが、市街地はともかく駅から2キロも離れると下水道が来たのは21世紀も10年以上過ぎてからです。驚くばかりです。 あと30年経ったらどうなりますかね? 私は見られそうないので残念です。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |