注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
佐川は山口のアドバイスに従い、千葉駅で降りた。夜8時少し前だった。駅前でビジネスホテルを探す。
駅から歩いてすぐに全国チェーンのビジネスホテルを見つけたので、特段こだわりもないのでそこ入る。チェーン店なら当たりはずれはないだろう。
| ||||
フロントで分厚い時刻表を借りて、明日の電車を調べる。千葉工場は8:30始業だから、佐倉まで18分で工場までタクシーで15分、それなら千葉発7:40あたりで良いだろう。
佐川はそんなことをしていて、スマホとはものすごいものなのだなと実感する。目的地と到着時刻を入れれば、いくつかのルートと交通機関と出発時刻を示してくれる。
1990年代は出張の時は、時刻表の必要なところを、数ページコピーしたものだ。そして出張途中で予定が変わると、みどりの窓口とかホテルで改めて時刻表を見て検討しなければならない。
電車の予約と変更が携帯電話でできるようになったのは、2010年頃だった。あれで電車に間に合わないと焦ることはなくなった。世の中は間違いなく進歩していると思う。
風呂から上がるとノートパソコンを取り出し、メールを開く。誰からもメールは来てない。
実施したこと、明日の予定をまとめて野上課長、猪越課長、山口さんにメールを送る。内容は長野工場は順調。もちろん内部監査で不適合はあったが、今の時期なら十分な進捗である。

時計を見ると10時だ。まだ洋子は起きているだろう。携帯電話は借りているが公私混同はいかんとホテルの電話でかける。
当時携帯電話の通話料は1分300〜400円もした。固定電話間の東京と福島では1分90円くらいだった。2024年の今は全国一律1分10円弱だ。
洋子には、いろいろ事情があって今千葉にいる。木曜日の夜には帰ると伝える。
さて、明日のことを思い煩っても仕方ない。少しでも時間を活用しようと金曜日予定している内部監査員教育の資料を作る。
内部監査の目的、何をするのか、成果物は何か、監査は進化しなければならないこと、そんなことを3ページほど書く。
それからテクニック的なこととして、要求事項の意味、確認方法、チェックリストはいかにあるべきか、それから実践になるわけだが、場慣れにはロールプレイだ。ロールプレイの台本を考えるか。
監査報告書のまとめ方と書き方も教えなければならない。その基本は、罪刑法定主義と証拠裁判主義の徹底だ。
罪刑法定主義とは犯罪と刑罰について、あらかじめ法律で規定しなければならないという原則。
平たく言うと、どんなことをしたときは罪になるか、その行為をしたときの罪の重さを法で決めておくこと。
どことは言わないが外国人でも国民でも、政府が気に入らないと逮捕して、何年も拘束するのは近代国家、法治国家ではない。また同じ犯罪でも、裁判官や行政官の気分で罪の重さが違うのはいけない。
証拠裁判主義とは犯罪は証拠によって立証されないとならないという原則。拷問による自白、タレコミだけでは有罪にできない。
このふたつは裁判に限らず、論理的な議論においては必須要件であり、ISO審査においてもこの二つの原則は当然であり、審査と認証の規格であるISO17021に明記されている。
ISO17021-1:2015
9.4.5.3 不適合の所見は、特定の要求事項に対して記録しなければならない。また、不適合の根拠となった客観的証拠を詳細に特定する、不適合の明確な記述を含めなければならない。不適合については、証拠が正確で、その不適合が理解できるものであることを確実にするために、依頼者と協議しなければならない
読んで字のごとく、どのshallを満たしていないかを記さねばならない。つまり「規格に不適合です」だけではISO17021への不適合であり、「このshall(要求事項)に不適合です」と言わないとダメなのだ。
そして不適合の根拠となった証拠は「詳細に特定」しなければならない。「詳細に特定」とは後で
「規定に汚れがあって文字が読めないものがあった」ではダメで、「○○工場に置かれていた規定集に綴じられていた、規定(文書番号XXXXとXXXX)が汚れていて読めない」と書いておけば、報告書を読んだ人が事実か否か、証拠を検証することができる。
根拠と証拠、これが明白でなければ監査も審査も価値はない。
こんな話を書くと「つまらねえ〜」と思う人もいるかもしれない。
だが「ISO審査が公正で客観的」であるためには、する方もされる方も、これをしっかりと理解する必要がある。
さもないと、
そういうことのないように、曖昧を排除しスキをなくさなければならない。
といっても難しいわけではない。不適合を証拠と根拠でしっかり記述するよりも、現実の審査や監査では困難なことがある。
私の経験で審査での最大の問題は、審査員が規格を理解しておらずいくら説明しても理解できないこと、審査員が規格にない要求事項を言い出したときいかに穏やかに断るか……それらが最大の問題であった。
そんなことを思い出すと、お金を出して審査を依頼したのに、なんでそこまで気を使わなければならないのかとため息が出る。
まあ、悪人を処断するのも渡世の義理。
そんなことをまとめていると、もう真夜中を過ぎている。
明日も頑張ろう!
翌火曜日、予定した電車で佐倉駅に行き、タクシーで工業団地まで行く。
工場の守衛所で品質保証課を尋ねると、女性ガードマン(ガードウーマン?)が簡単な地図を書いてくれた。奥の方の建物だ。その建物の入り口から入ると事務所のカウンターがあるから、そこで聞けという。
不親切ではなく、レイアウトがかなり込み入っているらしい。
お礼を言って歩き出す。
注:「女性ガードマン」なのか「ガードウーマン」なのか、真面目に迷った。ChatGPTに助けを求めると、
 日本なら「女性ガードマン」の方が通りが良いとでた。「ガードウーマン」は語としては正しいが一般的ではないとある。
日本なら「女性ガードマン」の方が通りが良いとでた。「ガードウーマン」は語としては正しいが一般的ではないとある。
更に、世の中は男女を示さない語に移りつつある(例:看護婦→看護師)ので「セキュリティスタッフ」が良いとある。
だが、日本で「セキュリティスタッフ」は警備員として使われるほか、救急救命士などにも使われているようで、これまた一般的ではない。よって、上記の『女性ガードマン(ガードウーマン?)』という表記にしてみた。
教えられたカウンターで、近くの人に品質保証課を訪ねてきたというと、案内してくれた。
品質保証課の看板の下にある机の島に行って、一番偉そうな人に声をかける。
![]() 「本社から来ました佐川と申します」
「本社から来ました佐川と申します」
![]() 「あっ、お待ちしていました。私が課長の林です。以前一度、佐川さんから電話をいただきましたね(第3話)。
「あっ、お待ちしていました。私が課長の林です。以前一度、佐川さんから電話をいただきましたね(第3話)。
この度はいろいろとご迷惑をおかけします」
![]() 「はっ、迷惑とおっしゃっても、何が迷惑なのか分かりませんが?」
「はっ、迷惑とおっしゃっても、何が迷惑なのか分かりませんが?」
![]() 「ちょっとここではまずいので会議室でお話ししましょう。
「ちょっとここではまずいので会議室でお話ししましょう。
オーイ、桜井さんを呼んでくれ」
 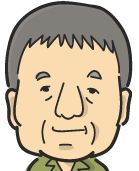 | |
| ★林課長 | 桜井さん★ |
数分後、定年間近と思える男性が入ってきた。
それぞれ自己紹介して全員着席する。
何かどんよりとした雰囲気だ。なんだろう?
![]() 「まずご挨拶と本日訪問しました目的ですが……今までは當山さんがISO認証の指導をしていましたが、退職されましたので先週から私が後任になりました。
「まずご挨拶と本日訪問しました目的ですが……今までは當山さんがISO認証の指導をしていましたが、退職されましたので先週から私が後任になりました。
千葉工場は以前、本社の指導を辞退されたと聞きましたが、昨日、野上課長へ再度支援をお願いしたそうですね。
日程的にはかなり厳しいと思われますが、現在の進捗状況を確認して、どのように進めるかを相談のために参りました」
![]() 「実は……その、ちょっと問題がありましてね。
「実は……その、ちょっと問題がありましてね。
単純に支援をお願いするだけでなく、ご相談することがあるのですよ」
![]() 「課長、全部話しちゃうのですか?」
「課長、全部話しちゃうのですか?」
![]() 「これからのこともあるし、そうしようと思う」
「これからのこともあるし、そうしようと思う」
![]() 「でもそうすると佐川さんに責任を負わせることになりますよ」
「でもそうすると佐川さんに責任を負わせることになりますよ」
![]() 「何か深刻そうな話ですね。話を聞いた感じでものを言いますが、誰かが違法な行為をした場合、
「何か深刻そうな話ですね。話を聞いた感じでものを言いますが、誰かが違法な行為をした場合、
 |
桜井さんがおっしゃったように、私は素人ですしそういった部門の者ではないので聞きたくないですね」
佐川は林課長の話を聞いているうちに30年前の事件を思い出した。あのときも當山さんが退職したのちに、千葉工場の問題があらわになったのだ。
この問題は當山さんとは関係ないのだが……當山さんでは頼りない、問題だと思ったから外部の人を頼ったから起きたことではある。
30年も前のことをおぼろげながらでも覚えているとは、70歳になっても、まだボケてはいないようだ。
![]() 「まあISO認証の指導という意味では無関係ではないのですが」
「まあISO認証の指導という意味では無関係ではないのですが」
![]() 「想像で当ててみましょうか、
「想像で当ててみましょうか、
一度、本社の指導が要らないと断ったということは、誰か、例えば外部のISOコンサルの指導を受けられる状況になったわけですね。
そして再び本社の支援を要請したことは、その指導を受けられなくなったからではないでしょうか。そしてその原因は、なにか非合法とは言いませんが、問題がある相手であったとか、情報入手がまっとうな手段でなかったとか……」
![]() 「ストップ、ストップ。おっしゃる通りです。佐川さん、あなたは超能力者ですか!
「ストップ、ストップ。おっしゃる通りです。佐川さん、あなたは超能力者ですか!
やはり隠すのは最悪なんだな〜。
桜井さん、ウチにコンプライアンス部門なんてないよな。まずは部長に話すか、それとも人事に相談しようか?」
![]() 「まず職制に沿って、部長に話すのがスジでしょう」
「まず職制に沿って、部長に話すのがスジでしょう」
![]() 「今、部長いるかな、ちょっと行ってくるわ」
「今、部長いるかな、ちょっと行ってくるわ」
![]() 「お供しましょうか?」
「お供しましょうか?」
![]() 「いや、大丈夫だ。私の仕事だ」
「いや、大丈夫だ。私の仕事だ」
林課長は会議室の電話でどこかにかけ、少し話して受話器を置き、部屋を出て行った。
![]() 「桜井さん、先ほど語ったのはまったくの想像ですが、真相はどうなんですか?」
「桜井さん、先ほど語ったのはまったくの想像ですが、真相はどうなんですか?」
![]() 「いや、おっしゃった通りですよ。長野工場の新沢課長も兵庫工場の大木課長も、佐川さんを頭の回転が速い人だと言ってましたが、速いだけでなく鋭いで人ですね」
「いや、おっしゃった通りですよ。長野工場の新沢課長も兵庫工場の大木課長も、佐川さんを頭の回転が速い人だと言ってましたが、速いだけでなく鋭いで人ですね」
![]() 「詳しく、」
「詳しく、」
![]() 「千葉工場ではISO認証に向かって活動中で、予備審査が5月12日、本審査が6月30日の予定も既に決まっています。
「千葉工場ではISO認証に向かって活動中で、予備審査が5月12日、本審査が6月30日の予定も既に決まっています。
昨年下期から、本社の當山さんの指導を受けて作業を進めていたのですが、當山さんも初心者のようで、話すことがしょっちゅう変わるのです。それでやり直しが何度も続き、我々も思い悩んでいました。
それと當山さんの指導料がとんでもなく高額だったことも問題でした。
昨年12月頃かな、ISO事務局の藤本さんがISOコンサルを見つけてきたのです」
![]() 「ほう、もうISOコンサルが登場したのですか?」
「ほう、もうISOコンサルが登場したのですか?」
![]() 「と、おっしゃると?」
「と、おっしゃると?」
![]() 「私はISO認証した企業が数百社くらいになったとき、そこでISO認証に関わった人たちが独立したり認証した企業が新しいビジネスとして始めたりして、ISOコンサルという仕事が発生すると考えていました。
「私はISO認証した企業が数百社くらいになったとき、そこでISO認証に関わった人たちが独立したり認証した企業が新しいビジネスとして始めたりして、ISOコンサルという仕事が発生すると考えていました。
しかし認証企業が数十社もない時点で、ISOコンサルをしている人がいるのかと疑問に思いました。仮に数十社とすると、メインでISO認証した人は数十人しかいないわけです。
その人たちが外に出て活躍するには、まだ時間がかかると思いましたので」
![]() 「うわー、そういうことを考えていましたか。読みが深いですね。
「うわー、そういうことを考えていましたか。読みが深いですね。
佐川さん。その通りなのですよ」
![]() 「その通りとおっしゃいますと?」
「その通りとおっしゃいますと?」
![]() 「當山さんが信頼できないので、我々も近隣の工場でISO認証に向かって活動している会社とか、知り合いでISOに詳しい人とかを探しておりました。
「當山さんが信頼できないので、我々も近隣の工場でISO認証に向かって活動している会社とか、知り合いでISOに詳しい人とかを探しておりました。
藤本さんが見つけてきたコンサルは、ISOコンサルを自称していましたが、実はこの近くの凸凹機械に勤めていました。ISOコンサルは兼業というよりも小遣い稼ぎだったようです。
自称コンサルは、実はその会社のISO認証に関わっていたのは事実ですが、中心人物ではなくその他大勢の一人らしいのです。
そして凸凹機械も、まだ審査を受けていません。ただ我々より1年ほど早くから準備をしてきてそうとう形が整っているという話です。
その自称コンサルは社内資料を持ち出して、ウチに売っていたということが発覚したのです。つまりISOコンサルを自称していた人は窃盗と情報漏洩の罪、そして我々は故買です」

注:
当然犯罪です。罪名は盗品等譲受け罪
![]() 「故買とは盗品と知って買うことでしょう。皆さんが盗品と知らなかったら……」
「故買とは盗品と知って買うことでしょう。皆さんが盗品と知らなかったら……」
![]() 「藤本さんは初めからその事実を知っていたか、知らなかったかは分かりません。
「藤本さんは初めからその事実を知っていたか、知らなかったかは分かりません。
ともかく、その凸凹機械では、横領事件として告発したようです。
『ようです』というのは、マスコミ報道されるほどの事件ではないですし、まだ噂になって1週間くらいで詳しいことが分かりません。
私どもにその凸凹機械から話があったわけでもなく、疑心暗鬼、遅疑逡巡でして」
![]() 「昨日、本社に指導を要請したというのは、その自称コンサルが今後コンサルできないと言ってきたからですか?」
「昨日、本社に指導を要請したというのは、その自称コンサルが今後コンサルできないと言ってきたからですか?」
![]() 「実はこの2週間、彼から連絡がないのです。自称コンサルを紹介した藤本さんが心配して彼の家に行ったところ、どこに行ったのか分からず、あちこち聞き歩いて、彼が凸凹機械に勤めていて、凸凹機械が彼を告発したと噂を聞いた次第です。
「実はこの2週間、彼から連絡がないのです。自称コンサルを紹介した藤本さんが心配して彼の家に行ったところ、どこに行ったのか分からず、あちこち聞き歩いて、彼が凸凹機械に勤めていて、凸凹機械が彼を告発したと噂を聞いた次第です。
問題は二つあります。ひとつは他社の情報を買ったことが犯罪になるのかどうか。
もうひとつはここのISO認証が指導者がいないと、どうしたら良いか分からないことです。
後者については林課長が兵庫や長野にそれとなく相談したところ、當山さんの後任が頼りになりそうだと……失礼……聞いたもので、再度本社に支援を要請したという経緯です」
![]() 「状況は分かりました。問題はふたつですか。
「状況は分かりました。問題はふたつですか。
まず故買だったのか、善意の第三者だったのかという問題。コンサルと信じていたと言えるなら、罪じゃないですから警察に話しておくべきでしょうね。
ただそうであっても、凸凹機械との会社対会社の交渉は必要でしょうね。こちらが受け取ったものが横領したものなら、現物は返さないとならないでしょう。ただ今回こちらが得たものは、物というより情報ですから、現物を返すより情報料でしょうからいかほどになるか?
もちろんこちらが盗品と知っていたとすれば、どうなるのか分かりません。藤本さんですか、その方が最初から企業秘密と知っていれば刑事事件でしょう。
ふたつめは予備審査まで、もうひと月半ないわけですが、今の出来上がり状況次第では予備審査に入れるか入れないか、それは見せてもらいたいです。
藤本さんという方は、今、会社に来ているのですか?」
![]() 「はい、この工場ではISO認証は極めて重要でして、ISO推進グループという部署ではないですがプロジェクトのような位置づけで、ちゃんとした部屋をもらっているのです。建屋が違うので歩いて数分です」
「はい、この工場ではISO認証は極めて重要でして、ISO推進グループという部署ではないですがプロジェクトのような位置づけで、ちゃんとした部屋をもらっているのです。建屋が違うので歩いて数分です」
注:この当時、ISO認証が飾りになるなんて考えた会社はない。ビジネス上必須だから認証に向けて活動していたに過ぎない。言い方を変えると、認証しないと輸出から撤退するかかが得るレベルのことだった。
桜井さんと待っていたが、なかなか林課長が戻ってくる気配はない。それで凸凹機械から入手したという資料類を、見せてもらうことにした。
桜井さんはそればかりでなく、千葉工場の品質マニュアルのドラフトも持ってきてくれた。
そして桜井さんは一旦仕事に戻ると言って、佐川一人を会議室において行ってしまった。
佐川はこれ幸いと資料を眺める。決して無駄な仕事じゃないと思う。
凸凹機械から入手した資料というのは、ISO規格紹介の一般的なものから、第三者認証の仕組み、認証までにすること、スケジュールなどで、どこかの講習会で配布されたものを再コピーしたもののようだ。この時代はコピーを数回繰り返すとかなり不鮮明になる。21世紀はそれほど気にならないが何が改善されたのだろ
印刷された資料を注意してみても文中にもヘッダー/フッターにも凸凹機械社名の記載もなく、そう思わせる記述もない。
 |
|
 |
ひょっとしてどこかの講習会で配ったものを、出典を隠してコピーして、凸凹機械内で使用してた可能性もある。
講習会でもらった配布資料をコピーすることは著作権侵害に当たるだろうが、それをお金を払って入手することが故買になるかといえば、そうはならないような気がする。売る方が罪になっても、買う方は善意の第三者ではなかろうか?
それと話は違うが、凸凹機械も実際に審査を受けていないのだが、このような対応で大丈夫なのかと疑問を感じる。
ひとつは品質マニュアルである。表紙に凸凹機械と社名は書いてないが、品質方針のところに社名があるからドラフトなのだろう。そこに書いてある文章がISO規格そのままなのだ。
例えば契約内容の見直しだが、ISO規格、ISO9001:1987では
ISO9001:1987 4.3 契約内容の見直し
供給者は、契約内容を見直しするために、及びこれらの活動を調整するための手順を確立し、維持する。
供給者は、各契約内容を見直しして、次の事項を確実にする。
となっている。
それに対して、入手したマニュアルは

ISO9001:1987 4.3 契約内容の見直し
凸凹機械(株)は、契約内容を見直しするために、及びこれらの活動を調整するための手順を確立し、維持します。
凸凹機械(株)は、各契約内容を見直しして、次の事項を確実にします。
まさに🦜オウム返しである。まあこの方法が絶対ダメとは言えない。1995年から1998年頃、ISOコンサルに指導を受けた中小企業の品質マニュアルに多く見られたものである。
しかしながらマニュアルに要求されるのは、規格で要求することはしますと答えるだけではなく、どのように実現するかの概要と手順書が参照できることを記さねばならない。
1987年版ではそこは不明確であったが、第三者認証が広まるにつれて1994年版、2000年版とマニュアルについての要求は具体的ではないが、書き加えられた。
それは、次のようなものを品質マニュアルに書けということである。
- 規格が要求する文書化された手順
手順を書き込むか、手順を定めた文書が辿れること - 規格が要求する記録の具体的な事項
- もちろん品質方針や品質目標なども盛り込む必要があった。
ということは「○○します」というだけでなく、「○○をする概要を記すほか、その具体的なことは当社の文書○○規定で定めています」と参照文書がトレースできるよう書かねばならない。
佐川はハッとして、千葉工場の品質マニュアルのドラフトを開く。
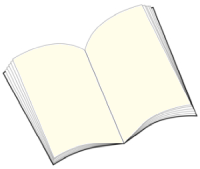 おお!、まさしく凸凹機械から入手した品質マニュアルと同じく「○○します」のオンパレードだ。そして参照すべき社内文書(つまり規則や規定)の記載がない。
おお!、まさしく凸凹機械から入手した品質マニュアルと同じく「○○します」のオンパレードだ。そして参照すべき社内文書(つまり規則や規定)の記載がない。
當山さんの指導にも呆れるが、この自称コンサルにも呆れる。千葉工場も千葉工場だ、よくもこんなものに騙されて大金を払ったものだ。
そう思うのは自分が30年のアドバンテージがあるからだろうか? いや、少し常識があれば気づくと思うのだが。
凸凹機械が審査を受けてどうなるかは興味がある。もしこれで審査をパスするなら、その認証機関はマニュアルなどどうでもよいに違いない。その認証機関も問題だな!
注:当時有効だったの「ISO10011-1 品質システム監査の指針」では、その5.1.3で事前の文書チェックで「品質システムが要求事項を満たすには不適当であると分かったならば、このような懸念が解消して依頼者、監査員、更にできれば被監査者までが納得するまで、それ以上の資源を監査に使わないほうがよい」としている。
これはつまりマニュアルチェックで問題があれば審査を行わないことを示す。
自称コンサルと契約したときに払ったお金が40万と聞いて驚いた。しかし當山さんか山口さんが1日来ると15万、半年間毎月二人が二日ずつ来ていたら、360万も払うことになる。それに比べれば非常に安い。
藤本さんに会ったことはないが、ISO認証を進めようとしたら、當山さんからISOコンサルに切り替えたいと思う気持ちは分かる。もっともそれがまともなISOコンサルなら良いけれど……ババを引いたようだ。
なかなか林課長が戻ってこないし、誰もやってこない。一度、品質保証課に行って林課長が戻って来たかと確認したが、部長のところに行ったきり未だ戻ってないという。どうしたものかと思いつつ、会議室に戻り資料を読んでいた。
佐川が会議室に一人になって2時間ほど経ち、もうすぐお昼だ、はてどうしようと思った頃に、林課長が桜井さんを連れて現れた。
千葉工場 林課長  |  |
|
千葉工場 桜井さん 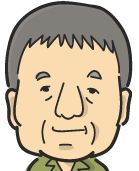 |
![]() 「だいぶ時間がかかりましたね。どういう結論になりましたか?」
「だいぶ時間がかかりましたね。どういう結論になりましたか?」
![]() 「事は思っていたより大事になりました。凸凹機械は従業員500名の中堅企業で、ウチはまあ大会社なので、交渉すればなんとかなりそうです……当社は変なことにならないようにと、本社のコンプライアンス部門が凸凹機械と正式な話し合いをするとのことです。
「事は思っていたより大事になりました。凸凹機械は従業員500名の中堅企業で、ウチはまあ大会社なので、交渉すればなんとかなりそうです……当社は変なことにならないようにと、本社のコンプライアンス部門が凸凹機械と正式な話し合いをするとのことです。
これから、と言っても今日明日に先方に申し入れするそうです。弁護士と相談して理論武装していくらしいです。
なお、コンサルから提供されたものが、横領というか情報漏洩したとは知らなかったとは主張するそうです。
今、藤本君から経緯の聞き取りをしています。まさか盗品だったと知ってたなんてことはないと思いたい」
![]() 「千葉工場のISO認証指導はいかがいたしましょう?
「千葉工場のISO認証指導はいかがいたしましょう?
正直言いまして私も多忙ですので、もし千葉工場が当面私を受け入れるどころでない、あるいは認証のスケジュールを見直すとかなら、私は今晩中に兵庫工場に移動して、明日朝から内部監査などをしたいのです」
林課長はどうしたら良いのか決めかねるようだ。
![]() 「佐川さん、午前中私どもの資料をご覧になっての、感想を教えてもらえませんか?
「佐川さん、午前中私どもの資料をご覧になっての、感想を教えてもらえませんか?
トラブルはあっても認証の活動はしなければなりません。今までの活動が間違っていない、マニュアルなどが良いというならうれしいです」
![]() 「資料を読んだだけで説明を受けてないので詳細は分かりませんが、マニュアルは見直したほうが良いかと思います。あとはマニュアルを支える規定や記録が、いかほどそろっているかは、実態を調べないと何とも言えませんね。
「資料を読んだだけで説明を受けてないので詳細は分かりませんが、マニュアルは見直したほうが良いかと思います。あとはマニュアルを支える規定や記録が、いかほどそろっているかは、実態を調べないと何とも言えませんね。
なによりも、認証機関がマニュアルにどんなことを要求しているかの確認もしないとなりません」
![]() 「なるほど、説明を受けないと分からないと……」
「なるほど、説明を受けないと分からないと……」
![]() 「すみませんが、午後一まで待ってくれますか。工場内で打ち合わせをしますので」
「すみませんが、午後一まで待ってくれますか。工場内で打ち合わせをしますので」
![]() 本日の見通し
本日の見通し
こういうことは経験したのかと問われますか?
このような話は何度か聞きましたが、さすがに刑事事件になった話は聞いたことありません。
30年も前は情報漏洩などあまり気を使わなかったこともあります。ノウハウの価値など評価しなかったのもありますね。
この事件は、佐川さんが上手く裁いてくれるでしょう。たぶん
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
英語原文は下記の通り。基本的に英文を読むべし。 A finding of nonconformity shall be recorded against a specific requirement, and shall contain a clear statement of the nonconformity, identifying in detail the objective evidence on which the nonconformity is based. Nonconformities shall be discussed with the client to ensure that the evidence is accurate and that the nonconformities are understood. The auditor however shall refrain from suggesting the cause of nonconformities or their solution. | ||
刑法256条 第1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 第2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 | ||
実は知らなかったので調べた。 実際に技術の進歩でいろいろと改善されているという。 ・アナログコピー機からデジタルコピー機への進化:データ保管もデジタル ・解像度の向上:私が15000円で買った安物でも1200dpiだ。 ・画像処理技術の進化:明るさ、コントラスト、色相などの調整 ・トナー/インクの向上:コピー後の退色したりかすれたりせず、コピー時の陰影が変化しにくい |
外資社員様からお便りを頂きました(24.09.26)
おばQさま、千葉工場 驚きの展開ですね。 コンサルだと思ったら「不正に入手した情報」の疑いとは。 会社としての対応はお書きのように警察への届け出も必要ですが、法務を入れて「委託したコンサルは御社社内資料を持ち出して、ウチに売っていた疑いあり。 当該コンサルは行方不明で警察には届け出済。当該資料が御社のものの場合には返却の用意あり。」という感じで内容証明でも送るしかないですね。 それにしても、余計な仕事が増えた千葉工場の関係者お気の毒。 >こういうことは経験したのかと問われますか? 仕事をしていると、巻き込まれでも、何かしらありますよね。 分野は違いますが、米国でのビジネスで90年代に、私も似たような問題を体験しています。当時は、情報を盗まれたで、随分と訴訟がおきておりました。 米国のベンチャーに、とある日本の会社の事業部が出資、人も送って支援。 あえなく倒産、またはどこかに身売り。 すると出資元の会社を、情報の不正利用で訴える。 米国や日本の大きな会社は、どこかの事業部で、出資した会社と同じような製品を作っている。実態は分離されているから、そんな情報の利用なんて不要だけれど、訴える側からすれば立証するのはお前だ。 当時のカルフォルニア州法では、大きな会社とベンチャーとの係争だと、小さい会社が有利。特に陪審員には技術の事なんて知らないから、大きな会社が悪いというバイアスは簡単にかかります。訴える側は勝てば儲けものの非対称な訴訟で、訴えられた側は弁護士費用だけでもすごい出費。たぶん弁護士事務所が、そんなビジネスを考えたのでしょうね。かくて日本企業に限らず、米国の大手も、同様な訴訟で訴えられました。 以降は、情報の受け取りの管理については、非常に厳しくなったと思います。 やっぱり現場でしっかりと仕事された経験があるから、お話にしても参考になります。 これからも楽しみにしております。 |
外資社員様 毎度ご指導ありがとうございます。 私の場合、外資社員様のような大きな会社さんで大きな問題を経験したことはありません。 会社の物を持ち出すとか、売るとか、そういうのは素人が見ても犯罪だとなりますが、新しい技術とか方法なんてのは物でなく情報なのです。そういったものは身に着いたものなら副業で教えるのは良いのか悪なのか、となると微妙だと思います。 講習会で聞いてきたことを、孫講習をするのは良いのか悪いのかも分かりません。配布資料をコピーして配るのでなく、自分が配布資料と同様の物を作成したなら著作権は作成者にあるはずです。 と考えるとなかなか難しいです。 ところで先行きはますます泥沼に入りそうです。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |