注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
1993年4月21日である。何かの記念日ではない。兵庫工場の予備審査の前日である。
本社からは山口と佐川が来ている。佐川も二度目の人生ではまだISO審査なるものに立ち会ったことがないので興味津々である。もちろん兵庫工場の面々は、みな深刻なほど真剣だ。
佐川と山口は午前中に工場に入ったが、今更指導することも点検することもなく、なにか質問とか困ったことがあったら、声をかけてくださいと言って品質保証課にいる。
今更なにもすることがないのであるが、のどかな話をしてはいけないような雰囲気である。
・
・
・
暇かと思っていたが、そうでもないようだ。次々に相談者がやって来る。
トップバッターは同じ課の、小林さんと庶務の女性だ。
|
|
|
![]() 「課長、オープニングの出席者はどうしますか?
「課長、オープニングの出席者はどうしますか?
それに式次第もありますが……」
![]() 「オイオイ、今頃考えるのか。とっくに工場に周知しているとばかり思っていた。
「オイオイ、今頃考えるのか。とっくに工場に周知しているとばかり思っていた。
普通の客と同じだよ。審査員は1名だよね?
まず守衛所に来てもらったら、総務の応接室に入ってもらう。そしたらお茶だな。
おっと、私に来所したことを電話してほしい。いろいろあるだろうから携帯電話を持っていてくれ」
![]() 「サヨちゃん、案内とお茶出しは、総務でやってくれるのかな?」
「サヨちゃん、案内とお茶出しは、総務でやってくれるのかな?」
![]() 「案内は守衛所でしてくれると思いますが、確認しておきます。応接室も確保しておきます。
「案内は守衛所でしてくれると思いますが、確認しておきます。応接室も確保しておきます。
お茶は総務ではしてくれないですね。私が行って用意します」
![]() 「それじゃ、来るのが9時と言われているから、10分前までに守衛所に行って待っていてくれないかな。サヨちゃんが応接に案内して、お茶を出すまでしてほしい」
「それじゃ、来るのが9時と言われているから、10分前までに守衛所に行って待っていてくれないかな。サヨちゃんが応接に案内して、お茶を出すまでしてほしい」
 注:つまらないことだが、1990年頃は会社で会議というと、決まってお茶だった。ホットコーヒーとかアイスコーヒーとかいう発想がなかった。
注:つまらないことだが、1990年頃は会社で会議というと、決まってお茶だった。ホットコーヒーとかアイスコーヒーとかいう発想がなかった。
一般家庭で飲むコーヒーはインスタントで不味かったからか、コーヒーを飲む習慣がなかったからか、年配者は飲まなかったからか、どうしてだろう?
![]() 「分かりました」
「分かりました」
![]() 「君から連絡があったら私が工場長と入り、挨拶と名刺交換する」
「君から連絡があったら私が工場長と入り、挨拶と名刺交換する」
![]() 「それじゃお茶は4名と……」
「それじゃお茶は4名と……」
![]() 「こちらからのお願いですが、今回、我々は本社から指導や見学ではなく立ち合いとして来ているわけで、陪席したい。
「こちらからのお願いですが、今回、我々は本社から指導や見学ではなく立ち合いとして来ているわけで、陪席したい。
そのとき本社からISO審査の視察に来ていると紹介してほしい。我々も名刺交換します」
![]() 「それじゃお茶は6名ですね」
「それじゃお茶は6名ですね」
![]() 「オープニングミーティングはどこでするのでしょうか?」
「オープニングミーティングはどこでするのでしょうか?」
![]() 「それもか!
「それもか!
出席者は部長4名と審査を受ける課長に出てもらう。無関係な課長は出ない。
その人数が入れる部屋を確保してください。
心配になって来たけど、工場長の予定は抑えているだろう?」
![]() 「大丈夫です。工場長の予定は、総務課の秘書の方に予約済です。
「大丈夫です。工場長の予定は、総務課の秘書の方に予約済です。
認証機関から、工場長には、オープニングミーティング、経営者インタビュー、クロージングミーティングに出てほしいと言われています」
| 大木品質保証課長 管理責任者 |
![]() 「机に氏名を書く席札を作りますか?」
「机に氏名を書く席札を作りますか?」
![]() 「作ろう。全部じゃない、課長はいらないな。審査員、工場長、部長それに私だけで良い」
「作ろう。全部じゃない、課長はいらないな。審査員、工場長、部長それに私だけで良い」
![]() 「はい、それで作ります」
「はい、それで作ります」
![]() 「工場長に事前に何かありますか?」
「工場長に事前に何かありますか?」
![]() 「経営者インタビューは工場長が好きに語ってくれてよいですよ。工場長クラスなら皆さんこういった場は慣れているでしょう。それに経営者が語ることに不適合を出せませんよ。
「経営者インタビューは工場長が好きに語ってくれてよいですよ。工場長クラスなら皆さんこういった場は慣れているでしょう。それに経営者が語ることに不適合を出せませんよ。
経営者インタビューが終われば、まずは工場巡回です。一人なら何人もついて歩くことはないでしょう。大木課長が案内して、現場の課長が待機していれば良い。巡回ルートは決めているね。
製造部門だけでなく、倉庫、営業、設計などのオフィスも含む。見せたくないところは案内しなければ良い。それと認証範囲以外は見せないこと。まともな審査員なら、認証範囲外は見ないと言います。
小林さんが忙しいなら、誰かひとりついて会話をメモっとくと良い。良い悪いとか、コメントがあれば、巡回中でも関係部門に伝えること」
注:現場巡回は審査のために行うものだから、審査範囲を見るのが当然だ。イギリスから来た審査員とか認証が始まった当初は、認証範囲であることを必ず確認した。余計なところを見て情報漏洩とか言われるのを嫌ったようだ。
逆に当時は審査時間を短くしようと、遠回りしたり余計なところを見せたりしようとしたが、ことごとく拒否された。審査員も真剣だったようだ。
ISO14001時代になると、興味があるから認証範囲外でも見たいなんていう審査員が現れた。いろいろである。
![]() 「私がついてメモを取ります」
「私がついてメモを取ります」
![]() 「事務所に誰もいないとまずいから、サヨちゃんの代わりに電話番を頼んでおいてね」
「事務所に誰もいないとまずいから、サヨちゃんの代わりに電話番を頼んでおいてね」
![]() 「現場巡回をしたら、一旦休憩をして、次は書面審査になる。時間割に従って審査対象部門を回る。
「現場巡回をしたら、一旦休憩をして、次は書面審査になる。時間割に従って審査対象部門を回る。
対象部門は打ち合わせ場の確保、課長と対応する人1名から3名くらい出ること」
![]() 「ここはすべての部門の事務所がワンルームでしょう。移動することなく、同じ会議室でしようと思います」
「ここはすべての部門の事務所がワンルームでしょう。移動することなく、同じ会議室でしようと思います」
![]() 「それで良いですよ。動かないほうがいい、ボロが出ないからね。
「それで良いですよ。動かないほうがいい、ボロが出ないからね。
必要な書類を持ち込むこと。
1時間半に10分くらい休憩とるようにして、お茶を出してください」
![]() 「必要な書類ってどこからどこまでですか?」
「必要な書類ってどこからどこまでですか?」
![]() 「三段組に出てくる文書と記録だよ。規定集は予め二三冊会議室に置いといたほうが良いね。審査員が一冊、説明者が一冊、説明者が見つけるのが遅いときは、後で規定集の該当箇所をを開いて説明者に渡すとかした方がスムーズにいく。
「三段組に出てくる文書と記録だよ。規定集は予め二三冊会議室に置いといたほうが良いね。審査員が一冊、説明者が一冊、説明者が見つけるのが遅いときは、後で規定集の該当箇所をを開いて説明者に渡すとかした方がスムーズにいく。
持ち込む文書も記録も1枚物を見せるのではなく、必ずファイルごと見せるように。
全部の部門が終われば審査員がまとめに入る。その部屋で良いでしょう。審査員だけにして、何かあったら小林さんに連絡してもらう。
多分、コピーとか頼まれるから」
![]() 「審査が終わった時点でお茶を出して、そのとき私に電話してもらうように話します」
「審査が終わった時点でお茶を出して、そのとき私に電話してもらうように話します」
![]() 「その辺は向こうからスケジュール表が来ています」
「その辺は向こうからスケジュール表が来ています」
![]() 「クロージングの前に、向うから審査結果を言われる。こちらはそれを見て同意するかどうか検討し回答するのだけど、管理責任者だけで良いか、工場長の了解が要るならそこにも工場長が参加してほしい。あっ、それはこちら側だけの内部の打ち合わせです」
「クロージングの前に、向うから審査結果を言われる。こちらはそれを見て同意するかどうか検討し回答するのだけど、管理責任者だけで良いか、工場長の了解が要るならそこにも工場長が参加してほしい。あっ、それはこちら側だけの内部の打ち合わせです」
![]() 「それはお茶なんていりませんよね」
「それはお茶なんていりませんよね」
![]() 「いりません。審査員がひとりでまとめをするときと、昼食時にお茶を出してください。」
「いりません。審査員がひとりでまとめをするときと、昼食時にお茶を出してください。」
![]() 「そうそう、お昼はどうしますか?」
「そうそう、お昼はどうしますか?」
![]() 「オイオイ、それもまだ手配してないの?」
「オイオイ、それもまだ手配してないの?」
![]() 「小林さんも、会社員として客が来た時の対応くらい、事前に検討しておいてよ」
「小林さんも、会社員として客が来た時の対応くらい、事前に検討しておいてよ」
![]() 「サヨちゃんも気付いていたなら、早くに言ってくれよ。小林君はそういうことは、からっきしなのを知っているだろう」
「サヨちゃんも気付いていたなら、早くに言ってくれよ。小林君はそういうことは、からっきしなのを知っているだろう」
品証課のコントを聞きながら、佐川は不安を感じつ。ISO云々でなく、仕事の基本をしっかりしてくれ。
・
・
・
小林さんの対応が終わると、見計らったように樋口人事課長が品質保証課の島(机の塊)にやってきた。
![]() 「樋口さん、どうかしたの?」
「樋口さん、どうかしたの?」
![]() 「経理で規定集の点検をしたら、ページの抜けや綴じられた規定のバージョンが古いなど、いくつも問題があった」
「経理で規定集の点検をしたら、ページの抜けや綴じられた規定のバージョンが古いなど、いくつも問題があった」
![]() 「経理はISO審査に関係ないよ。それに文書管理は総務課じゃないか。人事課長様が慌てるところじゃないだろう」
「経理はISO審査に関係ないよ。それに文書管理は総務課じゃないか。人事課長様が慌てるところじゃないだろう」
![]() 「いやいや、総務課長は今その規定集の原本を点検したりで、てんやわんやです。
「いやいや、総務課長は今その規定集の原本を点検したりで、てんやわんやです。
それで隣にいた私も、座ってられない雰囲気で、対策を請け負ってしまいました」
![]() 「なるほど、経理だけの問題じゃないということか、規定集を見直してもらうしかないでしょう」
「なるほど、経理だけの問題じゃないということか、規定集を見直してもらうしかないでしょう」
![]() 「規定集は工場全体で10数部配付していますから、点検はシステマチックにせんといかんでしょう。品証から声をかけてもらえないかな」
「規定集は工場全体で10数部配付していますから、点検はシステマチックにせんといかんでしょう。品証から声をかけてもらえないかな」
![]() 「点検ってどうするのかな?」
「点検ってどうするのかな?」
佐川はそのやり取りを聞いて、よくあることだと思いつつ、自分も何もせずここにいては申し訳ない。片肌脱ぐかと立ち上がる。
![]() 「それじゃ私がお手伝いします。工場の規定の配布先に、庶務担当がファイルを持って集まれと言ってくれますか」
「それじゃ私がお手伝いします。工場の規定の配布先に、庶務担当がファイルを持って集まれと言ってくれますか」
![]() 「配布先も分からないんだ」
「配布先も分からないんだ」
![]() 「大丈夫ですよ、それじゃ総務課に行きますか」
「大丈夫ですよ、それじゃ総務課に行きますか」
総務課と言っても歩いて50歩だ。
![]() 「規定集の見直しは本社の佐川さんが手伝ってくれるそうだ」
「規定集の見直しは本社の佐川さんが手伝ってくれるそうだ」
![]() 「えっ、やってもらえるの、ありがたいわ」
「えっ、やってもらえるの、ありがたいわ」
![]() 「いえいえ、手順を説明するだけですよ。
「いえいえ、手順を説明するだけですよ。
ええと配布先に、規定集をもって総務に集まれって声をかけてください」
![]() 「人を集めて点検させるの?」
「人を集めて点検させるの?」
![]() 「それしかありません。1時間もあれば終わると思いますよ」
「それしかありません。1時間もあれば終わると思いますよ」
![]() 「配付部数は16部なのですが、ISO審査対象は8部門です。それだけでいいですかね?」
「配付部数は16部なのですが、ISO審査対象は8部門です。それだけでいいですかね?」
![]() 「点検しないものを絶対に審査の場に持ち込まなければ良いですが、徹底出来ますか?」
「点検しないものを絶対に審査の場に持ち込まなければ良いですが、徹底出来ますか?」
![]() 「確かに審査員が規定集を見ているとき、こちら側も規定を見るという状況もあるでしょう。そうなると、使っていない部門から規定集を借りてくるでしょうね」
「確かに審査員が規定集を見ているとき、こちら側も規定を見るという状況もあるでしょう。そうなると、使っていない部門から規定集を借りてくるでしょうね」
![]() 「あとあと問題が起きると困るから、全部集めよう」
「あとあと問題が起きると困るから、全部集めよう」

彼女が電話で関係部門に声をかけている間に、佐川は樋口課長に会議室の確保を頼んだ。
10数分後、16人の庶務担当が規定集のファイルを持って集合した。
1990年代初期は、イントラネットに規定を掲載したり、勤怠や給食の手続きをしたりするところはない。なにしろ事務系の社員全員に、パソコンが行き渡らない時代だから。
イントラネットに社内電話帳や規定集を掲載したり、オンラインで種々の手続きをしたりするようになるのは、Windows95が登場してからだろう。
各部門から規定集を持って来るとチェックを始める。
![]() 「ええとある部門で規定集に、古いバージョンが綴じられているのが見つかりました。それで点検を行いますのでご協力願います。
「ええとある部門で規定集に、古いバージョンが綴じられているのが見つかりました。それで点検を行いますのでご協力願います。
まずは机にならんでお座りください。
 | 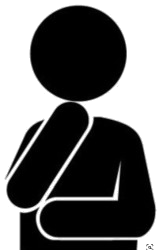 | 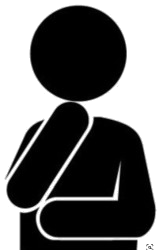 | 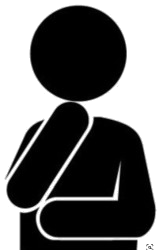 | 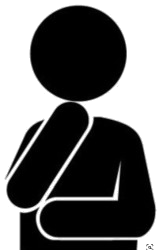 | 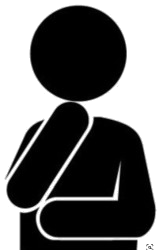 |
まず規定の目次のバージョンを言いますから、合っているかどうか確認してください。
次に綴じられた規定のタイトルとページ数、バージョンを言いますから、その通りかの確認、全ページをめくって書き込みやアンダーラインなどがないかを確認します。
異常があればその時点で手を挙げてください。ポストイットを貼ります。
総務の方、渋谷さんですか、ポストイットを皆さんに配ってください。
見つかるたびに必要カ所をコピーして差し替えると大変だから、後でまとめてコピーしましょう。
ではいきますよ、目次のページは1993年4月13日付けです。みな大丈夫かな?」
即座にふたりの手が挙がった。
![]() 「おふた方の目次が違いますか? いつのでしょう?」
「おふた方の目次が違いますか? いつのでしょう?」
![]() 「1992年10月です」
「1992年10月です」
![]() 「1993年4月1日です」
「1993年4月1日です」
![]() 「じゃあ、二人とも目次のページにポストイットを貼ってください。綴じてからも見えるように、ページよりはみ出すように貼ってね。
「じゃあ、二人とも目次のページにポストイットを貼ってください。綴じてからも見えるように、ページよりはみ出すように貼ってね。
次いきますよ。
トップは工場職制規定、規定番号0001のバージョンはFです。ページ数は5ページ、両面コピーですから3枚です」
![]() 「私のところ、バージョンがEよ、それに書き込みがあるわ! しかもボールペンよ、嫌になっちゃうわね」
「私のところ、バージョンがEよ、それに書き込みがあるわ! しかもボールペンよ、嫌になっちゃうわね」
![]() 「私のところは4ページまでで、5ページがありません」
「私のところは4ページまでで、5ページがありません」
ドンドンと声が上がる。佐川は驚いた。それほど文書管理が悪いのか。
これは問題だな。
![]() 「佐川さん、もう手順は分かりました。後は私がやりましょう」
「佐川さん、もう手順は分かりました。後は私がやりましょう」
![]() 「規定の数は、全部で280本だったと思います。頭の30本くらい点検して、問題が多ければ、もう点検を止めて全部コピーして総入れ替えした方が早そうですね」
「規定の数は、全部で280本だったと思います。頭の30本くらい点検して、問題が多ければ、もう点検を止めて全部コピーして総入れ替えした方が早そうですね」
注:ご存じと思うが、法律とか規定は「
![]() 「全部で16,000枚くらいコピーすることになりますか。お金はともかく時間的にはどうですかね」
「全部で16,000枚くらいコピーすることになりますか。お金はともかく時間的にはどうですかね」
![]() 「コピーだけなら1時間かかりません。発行印もプリントしますし、とじ穴も自動ですから。手がかかるのはファイルに綴じるだけですね。部分的に差し替えるよりまるごと差し替えた方が速いです。16冊やっても10分もかかりません」
「コピーだけなら1時間かかりません。発行印もプリントしますし、とじ穴も自動ですから。手がかかるのはファイルに綴じるだけですね。部分的に差し替えるよりまるごと差し替えた方が速いです。16冊やっても10分もかかりません」
樋口課長が更に数件の規定を読み上げると、度々手が挙がる。
![]() 「こりゃもうダメだね。チェックするのを止めて、規定全部を入れ替えよう。
「こりゃもうダメだね。チェックするのを止めて、規定全部を入れ替えよう。
渋谷さん、規定全部を入れ替える手配をしてください」
![]() 「承知しました。
「承知しました。
じゃあ、みなさん規定集を置いてお帰りください。中身を新しくします。2時間後に引き取りに来てください」
庶務担当がドッと去っていき、姦しかった会議室が一瞬で静寂になる。
![]() 「樋口課長さん、決断ありがとうございます。
「樋口課長さん、決断ありがとうございます。
しかし文書管理には問題がありそうですね」
![]() 「改定の度に差し替えましたという返信を、もらっているのですが……皆、真面目に仕事していないのかな」
「改定の度に差し替えましたという返信を、もらっているのですが……皆、真面目に仕事していないのかな」
![]() 「目次のページから合わないとは呆れましたよ。
「目次のページから合わないとは呆れましたよ。
それに書き込みはまずいよね」
![]() 「どうもありがとうございました。直ぐにコピーします」
「どうもありがとうございました。直ぐにコピーします」
![]() 「佐川さんのおかげですね。チマチマしていたら間に合いませんでした」
「佐川さんのおかげですね。チマチマしていたら間に合いませんでした」
![]() 「つまらないようですが、規定集でバージョン違いとか書き込みがあれば即アウトでしょう。良かったですよ」
「つまらないようですが、規定集でバージョン違いとか書き込みがあれば即アウトでしょう。良かったですよ」
注:バージョン違いが見つかっても即アウトということはない。しかし多数あれば偶発でなく必然であり、それはシステムの問題だから不適合になる。
偶発による不具合発生をなくすには、また別のアプローチが必要だ。例えば規定集をイントラにアップするとかだ。
樋口課長と別れて佐川が品質保証の事務所に戻ると、大木課長の隣に大谷営業課長と女性が座っている。佐川を見ると大谷営業課長が立ち上がり佐川に話しかけた。
![]() 「議事録原本にコピー黒板の感熱紙を綴じているのですが、まずいですかね」
「議事録原本にコピー黒板の感熱紙を綴じているのですが、まずいですかね」
|
|
|
![]() 「感熱紙でダメかということは、変色して読めなくなるということですね。
「感熱紙でダメかということは、変色して読めなくなるということですね。
それは保管期間次第でしょう。毎週の打合議事録はホワイトボードのコピーで、月のまとめを別の報告書にするなら、OKと思います。それを正規な議事録として長期間残すなら感熱紙はまずいですね。4.16記録の『読みやすく』に反します。善し悪し以前に、役に立たないんじゃだめでしょう」
![]() 「綴じられているのが、けっこう多いのですが、ワープロ起こししないとまずいですか?」
「綴じられているのが、けっこう多いのですが、ワープロ起こししないとまずいですか?」
![]() 「感熱紙をPPCにコピーして感熱紙の方を捨てて、コピーしたものに日付印を押せば良いでしょう。
「感熱紙をPPCにコピーして感熱紙の方を捨てて、コピーしたものに日付印を押せば良いでしょう。
ただ今となると日付印の日付が問題だなあ〜」
![]() 「その時の日付に合わせて日付印を押せば良いでしょう」
「その時の日付に合わせて日付印を押せば良いでしょう」
![]() 「明日の審査までにスタンプが乾かないでしょう。手で触れたら問題ですね」
「明日の審査までにスタンプが乾かないでしょう。手で触れたら問題ですね」
![]() 「感熱紙で文句を言われるか、乾いてないハンコで文句を言われるかの、究極の選択ですか」
「感熱紙で文句を言われるか、乾いてないハンコで文句を言われるかの、究極の選択ですか」
![]() 「スタンプ押したあとテッシュを当てればいいんですよ。余分なインクが吸われて乾燥します」
「スタンプ押したあとテッシュを当てればいいんですよ。余分なインクが吸われて乾燥します」
![]() 「そうか、じゃあ頼んだよ。このファイルに入っている感熱紙の議事録と記録を全部コピーして、コピーしたものに私の日付印を押してほしい。日付は感熱紙に書いてある日付に合わせてね。
「そうか、じゃあ頼んだよ。このファイルに入っている感熱紙の議事録と記録を全部コピーして、コピーしたものに私の日付印を押してほしい。日付は感熱紙に書いてある日付に合わせてね。
今日は課長になったつもりで仕事してください」
![]() 「えええ〜、何件あるんですか〜、100枚もあったら死にま〜す」
「えええ〜、何件あるんですか〜、100枚もあったら死にま〜す」
夕方になり喧騒も静まった。しかし定時を過ぎても灯りは消えない。これから夜になってからも、突発的に問題が発覚するだろう。
品質保証の大木課長、小林さん、本社の佐川と山口さんがコーヒーを飲んで雑談をしている。品質保証の大木課長はもう十分頑張ったから、問題が出たらそのときと腹を決めたようだ。
  |
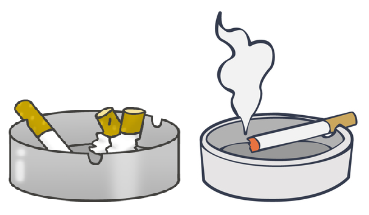 |
  |
 |
1993年当時は、分煙とか禁煙という発想はない。
タバコを吸うことがデフォルトの時代である。
佐川はタバコを吸わないが、世の中こんなものだと悟っている。
![]() 「審査前というとこんなものですか?」
「審査前というとこんなものですか?」
佐川は前世では何百回も審査を受けた。いずれも悲喜交々であった。だが自分が体験したとは言えない。現時点、ISO審査を体験した人は日本ではごくわずかだ。つじつまが合わない。
![]() 「人間ですからミスをするのは当たり前です。こんなものでしょう。
「人間ですからミスをするのは当たり前です。こんなものでしょう。
私はISO審査の経験はありませんが、重要な審査を受けるときは、そりゃ気を使います。例えば電取とかULですね」
![]() 「電取とかULでしたら私も何度も受けました。そう思うと初めてではないですな」
「電取とかULでしたら私も何度も受けました。そう思うと初めてではないですな」
・
・
・
・
のどかな話をしていると、そこへ人事課長が顔色を変えて登場。
![]() 「ちょっと相談なんだけど、」
「ちょっと相談なんだけど、」
![]() 「どうしましたか?」
「どうしましたか?」
![]() 「前年度末に、保管しているさまざまな記録の整理整頓をしました。
「前年度末に、保管しているさまざまな記録の整理整頓をしました。
記録にもいろいろありまして、永久保管もありますし、10年、5年とあります。社内のルールで3年間の記録は、すぐに取り出せるようにと決まっています。
それで年度末の掃除のとき、保管場所がないので4年より前の記録を、製品を保管している隣町の運送会社の倉庫に運んだのです。まあ車で行けば片道30分、探して持ってくると往復2時間というところです。
今日、ウチの者が規格を読んで『即座に検索できる方法によって保管する』とあるから、不味いのではないかと言い出しまして、 いかがなものでしょう?」
![]() 「なるほど、JIS訳は『即座に』とありますね。
「なるほど、JIS訳は『即座に』とありますね。
日本語で即座というと、どれくらいでしょうか?」
![]() 「日本語で即座なら、その場ですぐの意味ですから、数分でしょうか?」
「日本語で即座なら、その場ですぐの意味ですから、数分でしょうか?」
実は佐川は前世において最初の審査のときイギリスから来た審査員に、
だがそのときの回答を聞いた話として、この場で説明することはまずいだろう。自分が考えたことにして言わないと……
![]() 「英語を読むと they are readily retrievableの個所ですね。
「英語を読むと they are readily retrievableの個所ですね。
Retrievableは『取り戻せる』とか『取得できる』という意味ですが、問題はreadilyですね。ReadilyはReadyの副詞形で『すぐに』という意味もありますが『容易く』という意味もあります。
JIS訳は『即座に取得できる』ではなく『即座に検索できる』ですからね。その意味で良いと思います」
英語原文は下記の通り(ISO9001:1987 4.16)
Quality records shall be stored and maintained in such a way that they are readily retrievable in facilities that provide a suitable environmental to minimize deterioration or damage and to prevent loss.
「they are readily retrievable」の意味が「即座に検索できる」「即座に手に入る」あるいは「容易く検索できる」「容易く手に入る」のいずれなのか、私は分からない。
ただ1993年にイギリス人に審査を受けた際に、私が下手な英語で聞いたら「どこにあるかがはっきりしていれば良い」と言われた。爾来、私はそれを信じている。
ちなみに、
Copilot「必要なときにすぐにアクセスできる、または取り出せる状態にあること」
ChatGTP「それらは容易に取り出せる、または簡単に取り出せる状態にあるという意味」
Google翻訳「簡単に取り出せる」
いずれの翻訳でも上記4つともOKのように思える。
![]() 「え〜と、違いが分かりませんが」
「え〜と、違いが分かりませんが」
![]() 「規格は『即座に記録を見られること』ではなく、『即座にどこにあるのか検索できること』を要求しているのです」
「規格は『即座に記録を見られること』ではなく、『即座にどこにあるのか検索できること』を要求しているのです」
![]() 「佐川さん、具体的にはどういう状況なら良いのですか?」
「佐川さん、具体的にはどういう状況なら良いのですか?」
![]() 「文章のままですよ。倉庫に保管するときに、どの種類の記録の何年物はどこに保管しているかを記帳していて、『必要なときは迷わず取り出せます』と言えば良いのです。奥にあって取り出すのに何日かかってもOKです」
「文章のままですよ。倉庫に保管するときに、どの種類の記録の何年物はどこに保管しているかを記帳していて、『必要なときは迷わず取り出せます』と言えば良いのです。奥にあって取り出すのに何日かかってもOKです」
![]() 「必要な場合は……『すぐに取り出せる』のではなく、『迷いなく取り出せる』……うーん、そういうことで良いのですか?」
「必要な場合は……『すぐに取り出せる』のではなく、『迷いなく取り出せる』……うーん、そういうことで良いのですか?」
![]() 「それってJIS訳の『即座に検索できる』そのままです。
「それってJIS訳の『即座に検索できる』そのままです。
英語のニュアンスは私には分かりませんが、和訳が都合良ければ、それでいきましょう、アハハハ」
樋口課長はキツネにつままれたような感じだが、佐川が問題ないというなら問題ないと思うことにした。
お礼を言って樋口課長は自席に戻っていく。
彼も今晩は、品質マニュアルと人事課の文書をめくって夜遅くまでいるのだろう。ご苦労なことだ。
・
・
・
・
と思っているとまた営業の大谷課長がやって来る。
![]() 「大谷課長、また悩み事ですか?」
「大谷課長、また悩み事ですか?」
![]() 「そうです。でも大木さんは悩みがないようですね。明日の被告席は大木さんですよ」
「そうです。でも大木さんは悩みがないようですね。明日の被告席は大木さんですよ」
![]() 「大丈夫、佐川さんという鉄腕弁護士がついていますから」
「大丈夫、佐川さんという鉄腕弁護士がついていますから」
![]() 「私は見学者ですから、審査員の対応はできませんよ。
「私は見学者ですから、審査員の対応はできませんよ。
審査員の規格解釈がおかしいときは質問したいですが、許されるかどうかは分かりません」
![]() 「ええっ、そうなの! 私は佐川さんがバックアップしてくれると思っていたよ」
「ええっ、そうなの! 私は佐川さんがバックアップしてくれると思っていたよ」
![]() 「大木さんは大丈夫でしょう。私の悩みを聞いてほしい。
「大木さんは大丈夫でしょう。私の悩みを聞いてほしい。
あのね、ウチの製品といっても顧客から見れば部品です。それで相手の生産計画が変わると、納入先とか納期とかジャンジャン変わるわけですよ。
もちろんそれが無理なときとか、費用が変わるようなときは交渉しますけど」
![]() 「実際のやり取りはどのようにしているのですか?」
「実際のやり取りはどのようにしているのですか?」
![]() 「実を言って問題はですね、ほとんどが文書の記録がないのですよ。まあ9割方はお金にも日程にも関わりないというか問題はないのですが、電話です、電話。
「実を言って問題はですね、ほとんどが文書の記録がないのですよ。まあ9割方はお金にも日程にも関わりないというか問題はないのですが、電話です、電話。
まず客先から変更連絡を受けつけた人間は、社内通知アテハツですな、それを書いて関係部門に伝えます……当たり前ですが運送屋の手配もあり、倉庫には日々の出荷に関わりますから、文書で通知が必要です。それは社内的に残ります。
ですが、客先から変更があったという証拠は電話しかありません。もちろん後で水掛け論になると困りますので、こちらはいつ誰から変更通知があったかと記録して、それを客先に変更の確認と了解したことの返事をする形で発信します。
ですから契約の見直しといっても、向うからの変更指示がないのです。客観的に見るとこちらが勝手に、納期とか納入先を変えて客先に通知しているように見えるかもしれません」
![]() 「今までミスがあったということはありますか?」
「今までミスがあったということはありますか?」
![]() 「こちらからの確認で伝達ミスが発覚したことはありますが、客先で生産ストップなどの問題発生までは至っていません」
「こちらからの確認で伝達ミスが発覚したことはありますが、客先で生産ストップなどの問題発生までは至っていません」
![]() 「とりあえず現状是認するしかないでしょう。当方が客先から変更を受けた記録、相手方の氏名、日時、指示内容を記録して残す、回答したときは発信文を残すことをルール化していますか?」
「とりあえず現状是認するしかないでしょう。当方が客先から変更を受けた記録、相手方の氏名、日時、指示内容を記録して残す、回答したときは発信文を残すことをルール化していますか?」
![]() 「それは我々の防衛のためにルールにしています。
「それは我々の防衛のためにルールにしています。
電子メールが一般化すれば、向こうが発起したことの記録は残るのですがね」
![]() 「あと数年するとそうなりますよ」
「あと数年するとそうなりますよ」
そういうやりとりは、1990年頃にはけっこうあった。
その後、製造業は社内にとどまらず会社の垣根を越えて、サプライチェーンの上流から下流まで電子的に情報がつながって運営されるようになった。
電子メールもネットもない時代、そんな方法で仕事していたのかと思うとぞっとする。よくもまあトラブルが少なかったものだ(ないとは言わない)。
私のリアルの審査前はこんな風だったのかという質問ですか?
1995年頃まではまさしくこんなもので、審査前日は徹夜でした。
でも何度か審査を受けると、慣れてきて大いに手抜きするようになり、審査でトラブルが起きても動じなくなりました。
しかしISO14001の時代(1997年以降)になると、審査員たちはオリジナリティな要求事項を
それを、罪刑法定主義と言いましたね。
大事なことです、覚えましょう。
その要求事項はどこに書いてあるかと聞いても「規格に書いてないことを根拠に不適合は出せない」ということさえ知らない審査員がいたのですから、これには参った、www
引退した今だから笑えるけど、当時は天誅を下したかった。いや、斬殺はいかん、呪い殺したい。これなら不能犯で罪にならない。
そういえば(遠い目)今でも有益な環境側面を騙る審査員はいるのでしょうか?
![]() 本日の振り返り
本日の振り返り
 まず故郷出身の西田敏行の冥福を祈りまして、一曲
まず故郷出身の西田敏行の冥福を祈りまして、一曲
もしも〜、ピアノが弾けたなら〜、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだろう〜♪
私の場合、もしも〜、英語が得意なら〜、もっといろいろできたのに〜♪と思います。
現実は高校を出てから、英語どころか微分も積分もまったく縁のない仕事で、40過ぎて就いた仕事がISO認証のお仕事。当時、和訳されたISO9001もなく、高校時代の英和辞典を引っ張り出して訳しました。あのときの自分をほめたい。
まあ、そんな私に英語を使う仕事をさせたとは、
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |
