注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
4月28日水曜日、長野工場の予備審査となった。
そんなことまで真似ることはないと思いつつ、ご苦労様と言って、ふたりは環境管理課で待つことにする。
・
・
・
環境管理課では新沢課長が、ひとり腕を組んで座っている。
![]() 「おはようございます。緊張していますか?」
「おはようございます。緊張していますか?」
「そうなのよ、兵庫工場が順調すぎたので、工場長始め皆さんの期待が大きくなってしまってね、今朝は部長から『兵庫に負けるな』と言われたよ、参ったね
![]() 「勝つも負けるもないですし、それに認証機関も違うのでしょ
「勝つも負けるもないですし、それに認証機関も違うのでしょ
「そう、兵庫は日系の元検査機関だし、ウチはイギリス系の●R社だからね」
![]() 「イギリス系って言うと審査員はイギリス人で言葉は英語ですか?」
「イギリス系って言うと審査員はイギリス人で言葉は英語ですか?」
「いや、審査員は日本人です。審査員は以前、船級検査とかしていたとかで、その後ISO審査員になろうとイギリスで修業をしたと聞きます。
ウチは認証機関探しでは最も早く1年以上前にスタートした。当時は審査を受け付けるところといえば、英国系しかなかったからね。
兵庫が審査契約したのはウチよりずっと遅かった。認証機関の選択が、審査の方法とかに違いが出るのかどうか気になります」
![]() 「審査基準が同じなのですから、変わりはないはずです。私の想像ですが、イギリスはISO9001以前からBS5750で審査してきた歴史がありますから、審査方法が成熟していると思いますよ、審査員が日本人であっても」
「審査基準が同じなのですから、変わりはないはずです。私の想像ですが、イギリスはISO9001以前からBS5750で審査してきた歴史がありますから、審査方法が成熟していると思いますよ、審査員が日本人であっても」
「そう聞くと安心しますが、ええと……と時計を見る……まだ始業前か、そろそろ来ても良い頃だ」
![]() 「来れば池神さんから連絡があるでしょう。私どもも朝の挨拶に参加させてもらいます」
「来れば池神さんから連絡があるでしょう。私どもも朝の挨拶に参加させてもらいます」
「それは伺っております。連絡が来たら部長と一緒に総務の応接室に参りましょう」
・
・
・
それから数分もせずに連絡があり、4人は総務の応接室に行く。
例によって名刺交換して、挨拶と軽くジャブの応酬をして、時間が来るとオープニングミーティングの場に移る。
・
・
・
中ほどの大きさの会議室に、応接室から来た人の他に、審査に関係する部長、課長そしてその部門で応対する者が十数名座っている。
席札とかお茶出しとか、会議や来客の扱いは兵庫工場からの情報だけでなく、担当者が慣れているというかレベルが高いのだろう、問題なく用意されていた。
佐川は式進行が順調に進むのを見て、ISO審査も意味のない行事になりそうだなと思う。まあ、それで良いなら特段異議もない。
 製造部長 製造部長 |
|||
| 藤原審査員 |  | 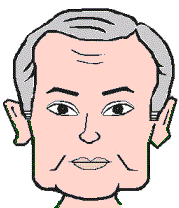 長野工場長 長野工場長 |
|
 本社 佐川 本社 佐川 |
|||
 本社 山口 本社 山口 |
注:ctlキーを押しならがドラッグしても、フル3Dモードは開きません。
オープニングミーティングも、決まりきったことの説明だけで10分もかからない。
経営層インタビューも、人の出入りがなくそのまま進む。ISO認証をしようとした経緯、認証の成果として何を求めているか、これまた決まりきったことばかりだ。
この時代はISO認証して会社を良くしようなんて語る人はいない。認証は欧州への輸出の必要条件だから、しなければならないというだけだ。要求があるからしなければならないと話すことを、恥ずかしいなんて思う気持ちもない。
当たり前だ、ULの認定をなぜ受けるのですかと聞かれて、会社を良くするためと答えたら、その経営者はバカかと思われるだけだ。アメリカで売るためにUL認定が必要だからだ。UL認定が要らないならULを受ける会社はないだろう。
ISO認証も商売をするために必要だからだ。
注:実を言って1990年頃、会社が素晴らしいとアッピールするために、必要がないのにULの認定を受けた会社を知っている。UL認定は会社がしっかりしていると示す良い方法なのだろうか?
だがいつしか経営者のリップサービスなのか「会社を良くするためにISO認証を考えた」なんて訳の分からないことを言う人が現れ、それが当たり前になってしまった。商売のためというのは恥ずかしいことなのか?
経営者インタビューを終えると、工場巡回である。これまた池神氏は書記とか用意していて抜かりはない。兵庫工場の小林さんは池神さんを見習わなければならない。
いや、準備周到な池神さんが、行き当たりばったりでもそれなりに仕事を捌いている小林さんを見習うべきなのか、悩むところだ。
長野工場は機械加工が多く、電子機器組み立ての兵庫工場とは大違いだ。だが工場の性質に応じて、働く人の意識も変わるし、清掃もするし、用具もそろえる。長野工場は決して汚れているという印象はない。
現役時代、私は下請けに指導によく行っていた。いろいろな業種があり、機械加工、木工などの会社は、工場は汚れるという前提で考えている。だから切粉が散らばないようにしているし、掃除用具を用意し、常に清掃をする。反対に電子機器の組み立て工場は、汚れないという意識が強い。
| 🦋 |
ある下請け会社はウォークマンタイプのカセットプレーヤーを組み立てていたが、掃除なんてめったにしなかったようだ。
冬なのに大きなガの死骸が壁際に落ちていた。それを見て何か月も掃除をしていないと思った。従業員もそういう風景を気にしない。たまげた。
工場内は床や機械だけでなく、法で定める表示板も、古いが薄汚れたという感じもない。立派な管理状態だろう。
1時間少々で工場巡回を終えて戻る。
休憩後から審査開始だ。
 | 💥 |  |
青コーナーは管理責任者の
![]() 「製造部長さんは管理責任者となっていますが、どういう仕事をされていますか?」
「製造部長さんは管理責任者となっていますが、どういう仕事をされていますか?」
![]() 「正直言って管理責任者とは、ISO規格にある役目で、元からあるわけではありません。普通の会社で、規格に書かれた職務を一人が担うということはないですね。
「正直言って管理責任者とは、ISO規格にある役目で、元からあるわけではありません。普通の会社で、規格に書かれた職務を一人が担うということはないですね。
もちろん規格に書いてある仕事は、企業では当然存在しますから、誰かがしているわけです。だけど特定の一人の役目かと言われば違いますね。というか、規格で書いている管理責任者の役割は、ひとりで負えるものではありません。
例えば組織を決め責任・権限を与えるとありますが、当社のようになればどのような部署を置くか、そこは何をするかというのは、工場に限らず全社的にほぼ決まっているわけです。工場ごとに、どんな部門が置くかを考えるわけありません。総務、営業、購買、設計、製造、工場管理などは工場が違っても変えようないですね。組織の目的が決まれば、法規制を含めた周囲環境によって、決めるというより決まってしまうわけですよ。
となると管理責任者が規格にあるように、いろいろ考えて実行することはない。
組織だけでなく、文書管理だって、工場設立時から当たり前のこととして文書管理の仕組みを設けている。それはISOなんて無関係に必要だから行っているわけです。
それは購買も同じ、営業しかり、設計の仕組み手順しかり、教育しかり。
是正処置を考えれば、品質の是正処置のルールというものはなく、安全でも労務管理でもお金でも、すべての是正処置のルールは一つしかありませんね。企業で働いたことがあればご理解いただけるでしょう。
今後ISO認証が広まれば、規格に合わせて、品質の教育、品質の是正処置、品質の文書という形にする会社もでるでしょう。でもそれは間違いだし、企業としては下の下だ。
それは当社だけでなく、普遍的、一般的です。となるとISO規格というものは、当たり前のことをやれと、言っているようにしか思えない。
もちろんそういう仕組みというか制度が、ない企業もあると思いますよ。誕生したばかりとか小規模なところですね。ですが大半は設立時から存在しているわけです。
ですから管理責任者の仕事を新たに作る人という見方ではなく、従来からそういう仕事をしている人を示すべきですね。ですから規格で定める管理責任者の役目を、ひとりが担当しているわけではないと考えるべきですね。
そういう趣旨はISO9000の序文に書いてあるようですが、本文にはありません。どうなんでしょうなあ〜、ハハハ」
注:上記の発言のISO9000は最近作られた「ISO9000:2015品質マネジメントシステムー基本及び用語」ではなく「ISO9000:1987 品質管理及び品質保証の規格―選択及び使用の指針」である。
池神氏はギョッとした顔をしているが、新沢課長は面白そうに部長の語るのを聞いている。
![]() 「おっしゃるようにISO9000では、組織を作るというよりも、顧客満足を満たすには、組織を補強しなければならないことが必要である旨が書いてありますね。そしてそれをする者を管理責任者としています。
「おっしゃるようにISO9000では、組織を作るというよりも、顧客満足を満たすには、組織を補強しなければならないことが必要である旨が書いてありますね。そしてそれをする者を管理責任者としています。
それとJIS訳もおかいしのですよ。Management representativeが、どうして管理責任者になるのですか? 管理責任者なら単純にmanagerでしょうね。
representativeとは代表権を持つとは限りませんが、会社を代表して仕事に当たる人間ですよ。ここでは品質担当役員とでも訳すのが適切かと思います。そして本文に書かれている仕事をする人なら、そうとうの権限を持つことになります。
それに管理責任者の仕事はおっしゃる通りです。書かれた仕事を1人でしている会社もあるでしょうし、複数の人が担っている会社もあるでしょう。実際はいろいろですが、審査においては品質担当役員がいてくれた方が、相手が一人で済むのでありがたいです」
![]() 「見解が一致して良かったです。ということで品質マニュアル上、製造部長である私が管理責任者と記してありますが、実際にはこの工場の複数の人が役割分担しているとご理解ください。もちろん審査においては私が代表して受け答えします」
「見解が一致して良かったです。ということで品質マニュアル上、製造部長である私が管理責任者と記してありますが、実際にはこの工場の複数の人が役割分担しているとご理解ください。もちろん審査においては私が代表して受け答えします」
![]() 「了解しました」
「了解しました」
兵庫工場では各部門の事務所がすべてワンフロアーに集まっていたが、長野工場はいくつもの建屋があり、それぞれの各職場に事務所が分散している。それで書面審査は、審査員が各事務所をお邪魔する一般的な形だ。
普通なら審査は、審査員に対応する管理職とアシスタントの2人くらいで受けるものだが、今回は初めてのことでありバックアップ要員がいるから、10数人入れるような大きさの部屋で、審査員と受ける人が座るテーブルがあり、その後方に観客数人がいるという感じだ。
![]() 「品質マニュアルによると業務課のお仕事は、営業の受注を受けて、生産計画の作成をすること、完成品の保管と出荷とありますね。もちろんその過程において生産進捗を監視して異常があれば対応をすると……」
「品質マニュアルによると業務課のお仕事は、営業の受注を受けて、生産計画の作成をすること、完成品の保管と出荷とありますね。もちろんその過程において生産進捗を監視して異常があれば対応をすると……」
![]() 「ハイ、そうです」
「ハイ、そうです」
![]() 「営業の受注が過大とかで生産計画が立たないなんてことはないのですか?」
「営業の受注が過大とかで生産計画が立たないなんてことはないのですか?」
![]() 「営業の規定○○をご覧ください。受注に当たっては、業務課、購買部門に調達品と製造能力の確認を取って受注の可否を検討するとあります。営業でも確認されるでしょうけど、受注時は複数部門で対応できるか確認します。
「営業の規定○○をご覧ください。受注に当たっては、業務課、購買部門に調達品と製造能力の確認を取って受注の可否を検討するとあります。営業でも確認されるでしょうけど、受注時は複数部門で対応できるか確認します。
ですから受注するものは、生産可能なものだけとなります」
![]() 「売り上げの達成のために、無理をすることはありませんか?」
「売り上げの達成のために、無理をすることはありませんか?」
![]() 「ありません」
「ありません」
![]() 「そうですか。
「そうですか。
本題と離れますが、規定では『業務課、購買部門』とありますが、一方は業務課と具体的に部署名を記述しているのに、他方は購買部門と漠然としているのはどうしてですか?」
![]() 「業務課も営業課も営業部です。そしてこの営業の規定は営業部が作成しますし、営業部はこの規定で仕事をします。ですから営業活動内部の責任を曖昧にせず、明記しているわけです。
「業務課も営業課も営業部です。そしてこの営業の規定は営業部が作成しますし、営業部はこの規定で仕事をします。ですから営業活動内部の責任を曖昧にせず、明記しているわけです。
他方、部品や材料の調達は購買部のお仕事で、その役割分担を営業所管の規定で、明記するのは不適当と考えているわけです。露骨なことを言えば、購買部門の職制変更があれば、営業所管の規定を改定しなければならなくなります。そのとき担当部署がどう変わるのかは、購買部でなければ分かりません。
同様に購買部の規定では、自部門の職制名は明記しているはずです。その反面、購買が発注するトリガは営業課からの通知ではなく、営業部からの通知となっているはずです」
![]() 「なるほど、規定において部門名の記載方法にはしっかり理由があるわけですね。
「なるほど、規定において部門名の記載方法にはしっかり理由があるわけですね。
そうしますと業務課は営業の出荷計画を基に生産計画を立てるわけですか?」
![]() 「業務課の一存ではできませんから、製造部や購買部の確認はします」
「業務課の一存ではできませんから、製造部や購買部の確認はします」
![]() 「あれっ、先ほどは『業務課、購買部門と製造部門の確認を取って受注の可否を検討する』とありましたね。既に購買部門とか製造部門の確認を取っているわけでしょう?」
「あれっ、先ほどは『業務課、購買部門と製造部門の確認を取って受注の可否を検討する』とありましたね。既に購買部門とか製造部門の確認を取っているわけでしょう?」
![]() 「状況は常時変わります。調達も業者の状況も交通機関の状況も変わります。製造でも設備の故障や電力供給など状況は変わります。また営業としても顧客要求により、生産順序も注文数も変わります。常にそういう情報を得て日程計画を調整するのが業務課です。
「状況は常時変わります。調達も業者の状況も交通機関の状況も変わります。製造でも設備の故障や電力供給など状況は変わります。また営業としても顧客要求により、生産順序も注文数も変わります。常にそういう情報を得て日程計画を調整するのが業務課です。
当然、変化が大きくて対応できないときは注文を断るとか、逆に失注ということになります」
![]() 「そうしますと、当初の各部門の検討は無意味となるわけですね」
「そうしますと、当初の各部門の検討は無意味となるわけですね」
![]() 「無意味ではないでしょう。受注のときその可否を検討し、生産のときに日程を検討するというだけです。
「無意味ではないでしょう。受注のときその可否を検討し、生産のときに日程を検討するというだけです。
世の中変化つきものです。天変地異はともかく、列車の遅れ、停電、近くに火災が起きて避難したため業務が止まるなんて当たり前です。
ですから客先都合、当社都合、上流の都合、それらを受けて常時、内部で対応策の検討、顧客との調整、その結果の行動となるわけです。
ええと……ISO規格では契約内容の見直しとか言いましたっけ?」
![]() 「なるほど、しっかりとISO規格を体現されていると……」
「なるほど、しっかりとISO規格を体現されていると……」
![]() 「ご冗談を、そういう動きは昔から当然のことですよ」
「ご冗談を、そういう動きは昔から当然のことですよ」
![]() 「なるほど、質問を変えます。
製品保管の期間はいかほどですか?」
「なるほど、質問を変えます。
製品保管の期間はいかほどですか?」
![]() 「理想を言えば、部品や材料も仕掛も完成品在庫も持ちたくない、完成即出荷が希望です。しかし現実には、顧客要求もあり製造設備の能力もあり、前倒しに分割生産するとか、細長く流すこともありますから完成品在庫はあります」
「理想を言えば、部品や材料も仕掛も完成品在庫も持ちたくない、完成即出荷が希望です。しかし現実には、顧客要求もあり製造設備の能力もあり、前倒しに分割生産するとか、細長く流すこともありますから完成品在庫はあります」
![]() 「保管時の環境条件は定めてありますか?」
「保管時の環境条件は定めてありますか?」
![]() 「わしばかり話していてもつまらないだろう、須田君説明してくれや」
「わしばかり話していてもつまらないだろう、須田君説明してくれや」
![]() 「技術部でが『製品保管輸送仕様書』というのを定めていていまして、そこで定められた保管基準を維持することになります」
「技術部でが『製品保管輸送仕様書』というのを定めていていまして、そこで定められた保管基準を維持することになります」
![]() 「技術が仕様書を作り発行していると……それはいかなるルールで業務管理課の倉庫の維持管理につながるわけですか?」
「技術が仕様書を作り発行していると……それはいかなるルールで業務管理課の倉庫の維持管理につながるわけですか?」
![]() 「ええと、ご質問は、その仕様書が、社内の指示文書としての有効性、強制力という意味と理解しますが、それでよろしいですか?」
「ええと、ご質問は、その仕様書が、社内の指示文書としての有効性、強制力という意味と理解しますが、それでよろしいですか?」
![]() 「それで間違いありません」
「それで間違いありません」
![]() 「『製品の保管及び輸送に関する規定』というものがあり、その中で製品の保管や輸送においては、技術が制定した『製品保管輸送仕様書』にの定めるところによると記述されています」
「『製品の保管及び輸送に関する規定』というものがあり、その中で製品の保管や輸送においては、技術が制定した『製品保管輸送仕様書』にの定めるところによると記述されています」
 |
須田が審査員の前に規定集を広げて、該当箇所を指さす。
![]() 「なるほど、ではその仕様書ではどんなことを定めていますか?
「なるほど、ではその仕様書ではどんなことを定めていますか?
温度、湿度、衝撃などですか……
先ほど輸出という話がありましたが、御社の責任はどこまでですか?」
![]() 「それは我々のところでは分からんな。我々の担当は客先指定の場所に納入するまでだ。
「それは我々のところでは分からんな。我々の担当は客先指定の場所に納入するまでだ。
その先まで契約しているかは営業でないと分かりませんな」
![]() 「ISO9001の『4.15.5引き渡し』では『契約上要求されている場合には、納入先への引き渡しまで継続する』とありますので、目的地が外国ならそこまでの運搬中も含むと考えられますね」
「ISO9001の『4.15.5引き渡し』では『契約上要求されている場合には、納入先への引き渡しまで継続する』とありますので、目的地が外国ならそこまでの運搬中も含むと考えられますね」
![]() 「納入先の引き渡しとあるなら、我々の納入先は国内ですが」
「納入先の引き渡しとあるなら、我々の納入先は国内ですが」
![]() 「ああ、これは翻訳が悪いのですが、原文はThis protection shall be extended to include delivery to destination.ですから、正しくは『目的地までの配送も含む』の意味です」
「ああ、これは翻訳が悪いのですが、原文はThis protection shall be extended to include delivery to destination.ですから、正しくは『目的地までの配送も含む』の意味です」
注:30年前の昔、審査員から上記のことを言われた。その場はそのまま進んでしまって不適合にもならなかったが、今思い出して(私の記憶力はすごいのだ)英文を読み返すと、どうとでも取れそうだ。納入先でなく目的地であるのは間違いない。
でも自社または自社が管理しない輸送する区間についても、保証する契約はあるのかな? 特殊な保護をする物ならありそうだ。
![]() 「それは契約を見てもらうしかないですね。いずれにしても会社の規定ではこの部門の業務は顧客指定場所への搬入までが担当です」
「それは契約を見てもらうしかないですね。いずれにしても会社の規定ではこの部門の業務は顧客指定場所への搬入までが担当です」
少し前、佐川から呼ばれて須田がのところに行き、佐川から小さな声で話を聞いて席に戻る。
![]() 「営業に契約条件を問い合わせしました。当社の契約はすべて指定された納入場所で、運送会社のトラックの車上渡しで、そこまでの運送が対象です」
「営業に契約条件を問い合わせしました。当社の契約はすべて指定された納入場所で、運送会社のトラックの車上渡しで、そこまでの運送が対象です」
注:「車上渡し」とは、トラックの荷台から、受取人が荷物を下ろす納品方法を指す。
![]() 「了解しました。契約書は営業で見せてもらいます」
「了解しました。契約書は営業で見せてもらいます」
午後一は、製造課である。
対面は高田課長である。
![]() 「文書管理についてお聞きします。文書管理と言っても、工場の規定だけではありませんね。製造部門で作る文書には、どのようなものがありますか?」
「文書管理についてお聞きします。文書管理と言っても、工場の規定だけではありませんね。製造部門で作る文書には、どのようなものがありますか?」
![]() 「製造部門で作る文書ですか……工作仕様書、作業指示書、工具補修要領書、工程図、塗り見本、仕上げ見本、そんなところでしょうか。
「製造部門で作る文書ですか……工作仕様書、作業指示書、工具補修要領書、工程図、塗り見本、仕上げ見本、そんなところでしょうか。
おっと、塗り見本や仕上げ見本は製造課で作りますが、技術部で承認してそこで登録・採番・発行されます」
![]() 「仕上げ見本とか塗り見本というのも文書なのですか?」
「仕上げ見本とか塗り見本というのも文書なのですか?」
![]() 「ISO規格でいう文書とは一般語の文書でなく、決裁を受けて制定され、強制力を持ち、バージョンがあり、発行管理されるものと考えています。ですから紙に書かれたものだけでなく、傷の見本も文書に当たるでしょう」
「ISO規格でいう文書とは一般語の文書でなく、決裁を受けて制定され、強制力を持ち、バージョンがあり、発行管理されるものと考えています。ですから紙に書かれたものだけでなく、傷の見本も文書に当たるでしょう」
![]() 「なるほど、一般的な現場作業の5W1Hを定めたものは、先ほど挙げたどれに当たりますか? 規格ではwork instructionとありますね」
「なるほど、一般的な現場作業の5W1Hを定めたものは、先ほど挙げたどれに当たりますか? 規格ではwork instructionとありますね」
![]() 「作業指示書と呼んでいます。規定の『製造部門の指示書規定』というもので分類や名称を定めています」
「作業指示書と呼んでいます。規定の『製造部門の指示書規定』というもので分類や名称を定めています」
![]() 「作成や発行管理について決めていますか?」
「作成や発行管理について決めていますか?」
![]() 「この『製造部門の指示書規定』の中で、作成と運用という項番で定めています。実務をするのはウチの文書管理担当です」
「この『製造部門の指示書規定』の中で、作成と運用という項番で定めています。実務をするのはウチの文書管理担当です」
![]() 「工場の規定で定めているのは、大まかな枠組みです。作業指示書の具体的なルールは、課の執務規定で決めています。執務規定とは工場の規定で定めている文書体系で、課内の手順を決めたものです。法律と省令の関係のようなものです」
「工場の規定で定めているのは、大まかな枠組みです。作業指示書の具体的なルールは、課の執務規定で決めています。執務規定とは工場の規定で定めている文書体系で、課内の手順を決めたものです。法律と省令の関係のようなものです」
![]() 「なるほど、文書管理については課のレベルまでしっかりしているのですね。
「なるほど、文書管理については課のレベルまでしっかりしているのですね。
具体的な運用についてはどうなのでしょう?」
![]() 「作成者に制限はなく誰でもよいです。決裁は製造課長、コピーや発行管理は庶務担当つまり私で、配布も差替えも廃棄も私が行います。
「作成者に制限はなく誰でもよいです。決裁は製造課長、コピーや発行管理は庶務担当つまり私で、配布も差替えも廃棄も私が行います。
新機種が出るときは、100枚から200枚も新規作成となるので大変です」
![]() 「これを見ると決裁は課長となっていますが、高田課長さんは100枚から200枚も中身を見て押印しているのでしょうか?」
「これを見ると決裁は課長となっていますが、高田課長さんは100枚から200枚も中身を見て押印しているのでしょうか?」
![]() 「切削加工からプレス、塗装、印刷、組立、梱包と多岐にわたりますし、枚数が枚数ですから、内容チェックとか図面との照合ははっきり言ってできませんね。
「切削加工からプレス、塗装、印刷、組立、梱包と多岐にわたりますし、枚数が枚数ですから、内容チェックとか図面との照合ははっきり言ってできませんね。
もちろん作成者以外のものがチェックしておりまして、照査欄にサインしています。私は照査印があれば承認しています」
![]() 「それなら照査者が決裁するのと同じですか?」
「それなら照査者が決裁するのと同じですか?」
![]() 「まず課長決裁は課の執務規定で決めたのではなく、工場の規定で定めてあります。
「まず課長決裁は課の執務規定で決めたのではなく、工場の規定で定めてあります。
私としては、作業指示書に問題があった場合、課長の責任であることを明示するために、課長が承認印を押していると認識しています」
![]() 「なるほど、分かりました。
「なるほど、分かりました。
発行された作業指示書の内容を見直すべし、改定すべきという現場の意見はあるのでしょうか?」
![]() 「もうたくさんありますよ。当社でも、いわゆる改善活動を行っておりますので、新機種が出たときは、第1ロット後に非常にたくさんの改善提案が出てきます」
「もうたくさんありますよ。当社でも、いわゆる改善活動を行っておりますので、新機種が出たときは、第1ロット後に非常にたくさんの改善提案が出てきます」
![]() 「そういう場合はどのように運用するのでしょう?」
「そういう場合はどのように運用するのでしょう?」
![]() 「まずどのようにして作業指示書が作られるかという話からしましょう。
「まずどのようにして作業指示書が作られるかという話からしましょう。
新機種導入のフローは、まず工程設計ですね。工程を検討し工程図にまとめ、ジグ、刃物、金型、塗料、副資材などを手配し、それを具体的に作業指示書に展開することになります。
工程設計が妥当かどうかの検証は、新機種導入前に試作を重ね、最終的に量産試作と呼ぶ100台かそれ以上を正規なラインで流します。
まあそういうことで品質的には確認されますが、生産性の問題は量産で判明するものはあります。また作業指示書の表現の見直しが求められることもあります。
そんなわけで発行後の対応が生じます。
改定方法ですが、基本的には作業指示書を改定するまでは作業は変えません。変更するときは製造条件変更記録を残し、切り替え時点と台数を記録します」
![]() 「本日生産していたのは○○型でしたね。○○型の製造条件記録を見せてください」
「本日生産していたのは○○型でしたね。○○型の製造条件記録を見せてください」
庶務の横山さんが後ろに置いたパイプファイルの一つを取り、審査員の前に置く。
![]() 「これが○○型の記録です。量産初期には、ものすごい数の変更がありますね。
「これが○○型の記録です。量産初期には、ものすごい数の変更がありますね。
描いた絵が分かりにくいから視点を変えたほうが良いとか、文章が分かりにくいから言い回しを変えろというのも多いです」
![]() 「なるほど、改善活動が盛んですね。何ロットか生産すれば変更は落ち着きますか?」
「なるほど、改善活動が盛んですね。何ロットか生産すれば変更は落ち着きますか?」
![]() 「改善とか不具合の見直しは終息しますが、図面改定とか部品の特採は生産終了まで散発的に発生しますね。それと指名業務の工程は人が変わると記録します」
「改善とか不具合の見直しは終息しますが、図面改定とか部品の特採は生産終了まで散発的に発生しますね。それと指名業務の工程は人が変わると記録します」
![]() 「図面改定も記録するのですか?」
「図面改定も記録するのですか?」
![]() 「製造条件記録は作業指示書の変更だけ記録するのではありません。製造条件を記録するわけです。
「製造条件記録は作業指示書の変更だけ記録するのではありません。製造条件を記録するわけです。
現実には製造条件だけでなく、特採品を使ったとか、図面改定の切り替えも区別せず、すべて製造条件記録に残します」
・
・
・
![]() 「ええと、質問は以上で終わりです。
「ええと、質問は以上で終わりです。
今までお話を聞いた中で、どうかなと思うものが、いくつかありましたので……
まず改善提案の中で『文章が分かりにくい』というのがありましたが、それは『4.16 読みやすく』に反するのではないかと思いますが、いかがなものでしょう?」
![]() 「作業指示書の文章に読みにくいものがあることですか。まあ分かりやすい文章の方が、分かりにくい文章よりは良いでしょうな。
「作業指示書の文章に読みにくいものがあることですか。まあ分かりやすい文章の方が、分かりにくい文章よりは良いでしょうな。
ですが、それはISO規格で問題になるほどのことなのでしょうか?」
![]() 「規格では『読みやすく』とありますね」
「規格では『読みやすく』とありますね」
![]() 「読みやすくねえ〜、」
「読みやすくねえ〜、」
横山さんが後ろからつつかれるのを感じて振り向くと、佐川は小さく手招きする。
すぐさま佐川のところに来て話を聞いて席に戻る。
![]() 「ええと、ISO規格では『読みやすく』という言葉があるのは、『4.16記録』です。文書の項番で読みやすくという要求はありません」
「ええと、ISO規格では『読みやすく』という言葉があるのは、『4.16記録』です。文書の項番で読みやすくという要求はありません」
![]() 「えっ、そうだったかな?」
「えっ、そうだったかな?」
![]() 「それから『読みやすく』の原文は『legible』で、辞書を引くと明瞭という意味で、文章が読みやすいということでなく、文字は明瞭で読み間違いしないようにです」
「それから『読みやすく』の原文は『legible』で、辞書を引くと明瞭という意味で、文章が読みやすいということでなく、文字は明瞭で読み間違いしないようにです」
注:「読みやすく」を「分かりやすく」と間違える人がいるのか? と思うかもしれない。
だが現実は間違えなかった審査員がいるのかと思うほどいた。某認証機関の社長と審査員研修機関の講師をしている人が書いた本でもズバリこれを間違えている。
この本は10年前だから、ISO認証が始まって20年くらい経ったときの発行である。
![]() 「ああ、確かに文書管理の項番にはないな。
「ああ、確かに文書管理の項番にはないな。
えっと、それから読みやすくではなく明瞭であることと……うわー、確かにそうだ。これは翻訳が分かりやすくないなあ〜
ご説明良く分かりました。今の提案を取り消します」
![]() 「ISO規格でどうこうでなく、分かりにくいなら改善をしたほうが良い。しかし分かりにくいとは主観的で客観的に判断できるのだろうか?」
「ISO規格でどうこうでなく、分かりにくいなら改善をしたほうが良い。しかし分かりにくいとは主観的で客観的に判断できるのだろうか?」
![]() 「本社の佐川さんはアイデアがありますか?」
「本社の佐川さんはアイデアがありますか?」
突然、藤原審査員が佐川を見て声をかけてきた。
先ほど横山さんにアドバイスしたのを恨みに思ったか?
![]() 「この場合、文書の文章や絵が分かりにくいのですから、『4.5.1文書の承認及び発行』の『文書の発行に先立ち、適切性を審査する』を根拠にして、審査のチェック項目とすべきと審査報告に記述されたらいかがですか。
「この場合、文書の文章や絵が分かりにくいのですから、『4.5.1文書の承認及び発行』の『文書の発行に先立ち、適切性を審査する』を根拠にして、審査のチェック項目とすべきと審査報告に記述されたらいかがですか。
ただ先ほど高田課長が言いましたように、絵でも文章でも、分かりやすい分かりにくいは主観的なものですから、不適合というよりも、例えば決裁前に監督者とか作業者に確認を取るべきという提案ではいかがでしょう。
案外こういうものは気分的なこともありますから、そういう根回しにより解決するかもしれません」
![]() 「さすが佐川さんだねえ〜、次回から試行してみよう」
「さすが佐川さんだねえ〜、次回から試行してみよう」
![]() 「では気づきとしてそのようにコメントしましょう。
「では気づきとしてそのようにコメントしましょう。
ええと別件ですが、作業指示書の発行管理はお聞きしました。しかし原本の保管は製造課の事務所のファイル棚にあります。誰でもそれをコピーしたり抜き取ったりできるようなので、無断コピーあるいは無断で修正するという事態は起きないでしょうか?
規格には明確ではないですが『文書及びデータを管理する手順を設定し維持する』とありますから、正式ルート以外の文書の書き換えなどを防止する必要があります」
![]() 「そう言われると反論しようないな。性善説でできている仕組みだから」
「そう言われると反論しようないな。性善説でできている仕組みだから」

![]() 「確かにコピー室の図庫は、担当者がいないときは施錠しますね。
「確かにコピー室の図庫は、担当者がいないときは施錠しますね。
ウチのキャビネットはガラス戸付きでカギもありますから、毎日始業時に引き戸のカギを開けて終業時にカギをかけましょうか?」
![]() 「それは簡単だけど安易すぎないか?
「それは簡単だけど安易すぎないか?
それに作業指示書を作成している部門は、ウチだけでなく他にもいくつも部門があるので、それぞれ条件が違うしね」
横山さんが長引きそうだと思い、佐川の意見を聞こうと振り向くと佐川が手招きする。
ササっと佐川の傍に行く。
そして話を聞くと戻って高田に伝言する。
![]() 「今のお話は工場内でも複数部門が関りますので検討いたします。
「今のお話は工場内でも複数部門が関りますので検討いたします。
ええと、本審査は5月ですが連休もあり、是正処置が間に合いそうありませんが、そこはどうしましょうか?」
![]() 「本審査のときに、是正中ということで説明いただければよいと思います」
「本審査のときに、是正中ということで説明いただければよいと思います」
![]() 「了解しました」
「了解しました」
・
・
・
クロージングミーティングでは、製造部の文書管理の安全対策と営業の顧客との電話での交渉の際の記録が、軽微な指摘事項とされた。
![]() 製造部長(管理責任者)と
製造部長(管理責任者)と新沢課長は了解して予備審は終了した。
新沢課長が門まで見送りするというと、藤原審査員はひとりで帰れますと言って断った。
1人で工場内を歩かせるわけにはいかないので、佐川がアテンドと言って守衛所まで同行する。
佐川が守衛所でタクシーを頼むと、30分くらいかかるという。市街地から離れた工業団地だから仕方がない。
守衛所の脇に、従業員に外部の人が面会に来たとき話せる休憩所のような場所がある。ガードマンがそこで待っていてくださいという。
佐川も一緒に中に入り座って待つ。
藤原氏が佐川に話しかけてくる。
![]() 「だいぶ黒子のアドバイスがあったようでしたが」
「だいぶ黒子のアドバイスがあったようでしたが」
![]() 「大変失礼しました。彼らも良く知っているのですが、緊張して頭が回らないようでしたので、少しアドバイスをしました」
「大変失礼しました。彼らも良く知っているのですが、緊張して頭が回らないようでしたので、少しアドバイスをしました」
![]() 「佐川さんは本社から認証指導に来ているとのことですが、ISOに関してどのような経験があるのでしょう?」
「佐川さんは本社から認証指導に来ているとのことですが、ISOに関してどのような経験があるのでしょう?」
![]() 「全くありません。ただ規格の対訳本をひたすら読みました。そして規格をよく理解するには和文ではダメと感じました。
「全くありません。ただ規格の対訳本をひたすら読みました。そして規格をよく理解するには和文ではダメと感じました。
藤原さんはイギリスで審査をされていたとのこと、和訳をどう思いますか?
引き渡しの項番では翻訳が悪いとおっしゃっていましたね」
![]() 「はい、引き渡しはおかしいなとおもっておりました……しかしlegibleには参りました。見逃しです。
「はい、引き渡しはおかしいなとおもっておりました……しかしlegibleには参りました。見逃しです。
和訳の『読みやすく』とあるのを、分かりやすくと頭に入っていました。Legibleなら真っ先に不鮮明が頭に浮かびます」
![]() 「私はそればかりでなく、方針などの言葉も日本語の方針というよりも、より具体的で日常の判断や行動基準のイメージを持ちました。
「私はそればかりでなく、方針などの言葉も日本語の方針というよりも、より具体的で日常の判断や行動基準のイメージを持ちました。
英文の単語に一致する日本語の単語がない場合、無理やり一語に替えるのでなく、節とか句にして表現する方が間違いないでしょうね」
注:英語でも日本語でも、句とは主語と動詞の構造がない複数の語のまとまりであり、節とは主語と動詞の構造がある語のまとまりをいう。
![]() 「なるほど……」
「なるほど……」
そのとき、ガードマンが「タクシーが来ましたよ」と呼びに来た。
![]() 「佐川さん、いろいろご教示、ありがとうございました。一層の研鑽に努めます」
「佐川さん、いろいろご教示、ありがとうございました。一層の研鑽に努めます」
品質保証課に戻ると、関係者が集まって反省会をしている。
佐川が戻ると新沢課長が来て、お礼を言う。
「兵庫と違い2件不適合があったけど、先日予備審を受けたこの工業団地の他の会社では、本審査に進むには一層の努力と言われたそうで、そこに比べれば段違いです」
![]() 「部長とか上の方から、兵庫と比べて言われるかもしれませんが、気にすることはないですよ。本審ではまた違った結果になるかもしれませんし。
「部長とか上の方から、兵庫と比べて言われるかもしれませんが、気にすることはないですよ。本審ではまた違った結果になるかもしれませんし。
今回は大成功ですよ」
「そうですよ、課長。當山さんが来ていたときは見通し真っ暗でしたから」
「當山さんか〜、言われて思い出した。もうすっかり忘れていたよ」
製造部長が部屋に入ってきた。
![]() 「おー、みんな、よくやった、よくやった。
「おー、みんな、よくやった、よくやった。
予想以上だったよ。工場長も喜んでいた。
おい、新沢課長、今日の夜は健保会館に関係者を集めて打ち上げだ」
![]() 本日の予告
本日の予告
世の中、良いことばかりではありません。
人生は楽しいことより苦しいことのほうが多いと、仏陀が語っています。
特待生より落ちこぼれは多く、宝くじは当選よりもハズレが多いのです。
幸せより不幸せが多く、良いことが続けば、悪いことはもっと続きます。
![]() 本日のオマケ
本日のオマケ
そんなに低姿勢な審査員がいるものか💢とおっしゃいますか?
そうです、私も会ったことがありません、キリッ
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |