注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
1993年6月7日(月)、佐川と山口は、前の週に兵庫工場を審査した認証機関を訪問して懸案を片付けて、その日は午後の新幹線で一旦帰る。翌8日は平日で山口は本社でお仕事、佐川は自宅で療養だ。考えてみれば佐川は傷病欠勤中である。
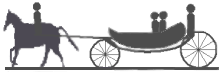 1993年の6月9日は皇太子(現今上陛下)結婚の儀が行われ祝日であった。
1993年の6月9日は皇太子(現今上陛下)結婚の儀が行われ祝日であった。
そして10日(木)から11日(金)が長野工場の本審査である。またトラブルがあると困るからと、佐川と山口さん二人が本審査に立ち会うことにした。
佐川は9日の午後に自宅を出て、夕方に早めに松本のホテルに入る。そもそも祝日に移動しても賃金は出ないから、いつホテルについてもお金も変わらない。
 |
|
|
張ですってwww |
と考えていて佐川はハッとした。まてよ、佐川は今傷病欠勤中だから、どうなるのだろう。出張旅費くらいは出るのだろうか? 庶務の福井さんに聞いてみよう
21世紀の今、小さなビジネスホテルで、食事を出すところは激減した。小さなビジネスホテルでも朝飯は一人前にとる。ならば外の定食屋の方が良いとする人が増えたからだ。もちろん定食屋が広まったこともある。だが20世紀はまだ小さなビジネスホテルでもレストランが付いていた。
佐川は大酒は飲まないが、晩酌はしていた。だが骨折治療中の飲酒はダメと言われた。アルコールは、カルシウムを溶かして排出してしまうので、骨のつながりが悪くなるそうだ。
ホテルの小さなレストランで、晩酌なしで夕飯を食べていると、山口がやって来た。彼とはホテルだけ決めて電車は自由としていたのだ。
![]() 「外は細かい雨が降っています。気が滅入りますね」
「外は細かい雨が降っています。気が滅入りますね」
![]() 「私が来たときはまだ降っていなかったけど、とうとう降り出したか。
「私が来たときはまだ降っていなかったけど、とうとう降り出したか。
明日も雨らしいね。どうなるかな」
![]() 「雨が降ると審査が変わるのですか?」
「雨が降ると審査が変わるのですか?」
![]() 「審査は変わらないだろうけど、天気が変われば条件が変わり、晴天では起こらない問題が顕在化するかもしれない」
「審査は変わらないだろうけど、天気が変われば条件が変わり、晴天では起こらない問題が顕在化するかもしれない」
![]() 「はあ〜、そうなんですか」
「はあ〜、そうなんですか」
山口は関心のない様子で相槌を打つ。
翌朝、朝飯を食べて外に出ると、弱い雨が降っている。佐川はバッグから折りたたみ傘を出してさす
![]() 「佐川さんは、いつも傘を持ち歩いているのですか?」
「佐川さんは、いつも傘を持ち歩いているのですか?」
![]() 「年中を出張していると、いつ雨に会うかもしれません。東京が晴でも、福岡は雨で札幌は雪とかね。いつもバッグに、折りたたみ傘を入れておくと良いですよ」
「年中を出張していると、いつ雨に会うかもしれません。東京が晴でも、福岡は雨で札幌は雪とかね。いつもバッグに、折りたたみ傘を入れておくと良いですよ」
![]() 「當山さんはいつもタクシー利用でしたから、雨が降っても気にしませんでした」
「當山さんはいつもタクシー利用でしたから、雨が降っても気にしませんでした」
![]() 「おやおや、タクシー利用基準なんて本社じゃ気にしないのかな。工場は高い本社費用を上納しているんだよ」
「おやおや、タクシー利用基準なんて本社じゃ気にしないのかな。工場は高い本社費用を上納しているんだよ」
注:本社費用(又は本社費)とは、工場や支店に直接関係ない費用のこと。本社の人たちの賃金やその他の費用、本社の賃貸料など。
俗に上納金と呼ばれる。工場から見ればうらやましい、いや恨めしい、いや税金かな。
![]() 「私もこれからはまず歩く、遠ければ公共交通機関を使うことにします。
「私もこれからはまず歩く、遠ければ公共交通機関を使うことにします。
佐川さんの折り畳み傘は小さいから、
・
・
・
佐川と山口は、始業30分前に工場に入る。
既に新沢課長も池神さんも準備完了、いざ出陣という風情で張り切っている。
「予備審で問題皆無だった兵庫工場で、先週の本審では不適合が複数出たと聞きまして、こりゃ本審はハードルが高いのかと覚悟していました。
ところが月曜日の昼に、指摘がすべて撤回されたと兵庫の小林君から知らせがありました。
それには佐川さんが活躍したと聞きましたよ」
![]() 「いや、単に審査員の勘違いを指摘しただけです」
「いや、単に審査員の勘違いを指摘しただけです」
「不適合がなくなったのは良いのですが、そのおかげで工場長も製造部長も『長野も負けずに無欠点でいけ』と檄を飛ばされて困りますよ」
「しっかり点検したつもりです。大丈夫と思いますが」
![]() 「予備審で不適合が二件ありましたね。それには対応しましたか?
「予備審で不適合が二件ありましたね。それには対応しましたか?
ええと、製造課の要領書の原紙の保管が誰でも触れるのがまずいということと、営業の顧客との電話連絡の記録がメモなので情報が網羅されていないものがあったということでしたね」
「営業の方はすぐさま顧客との電話連絡記録のフォーマット(様式)を決めて、それに書き込むようにしました。関連する規定も改定しています。確かに確認すべき事項の漏れがなくなったと評判です」
![]() 「製造課の方はどうしました?」
「製造課の方はどうしました?」
「部門によって事務所が、一部屋の部門もありますし、大きな部屋で島ひとつの部門もありまして、統一した方法はとれません。結局ルールは、定時後は外部の人が触れないような方法を取ることに決めました。
事務所が一部屋のところはドアに施錠する、単なるパーテーションのところはカギ付きの戸棚に保管します」
![]() 「あのう〜、形は大丈夫と思いますが、運用の方は大丈夫ですよね?
「あのう〜、形は大丈夫と思いますが、運用の方は大丈夫ですよね?
もちろん文書管理に限らずですが」
「運用と言いますと?」
![]() 「言葉そのままで、ルールがしっかり守られているかです。
「言葉そのままで、ルールがしっかり守られているかです。
作業要領書は生産中のものが掲示されているとか、そうそう、作業要領書に書き込みとか汚れて読めないとかはないでしょうね。文書管理は規定だけじゃないですから。作業要領書も文書です。
予備審と本審の違いは、荒く見るのと細かく見るの違いでなく、予備審は文書ができているかを見、本審査では運用がしっかりしているかを見るのです。
予備審で良くできていますねと言っても、要求事項が文書に展開されているという意味であって、しっかり運用されているかはチェックしていないのです。
ですから仏作って魂入れずなんてこと、ないようにお願いしますね」
「大丈夫と思いますが……」
「今更心配してもしょうがない。大丈夫と信じていきましょう」
話が一段落つくと、池神は審査員を出迎えると守衛所に行く。
予定の10分前に審査員がタクシーで来所、雨は朝より少し強くなった。待機していた池神が、来客用の傘を出して渡し、審査員二人を案内して事務所棟まで歩く。
審査員は予備審で来た藤原さんがリーダーで、もう一人清水さんという審査員だった。
 |   |
オープニングミーティングは予備審と同じ、経営者インタビューも同じく、特段どうこうはなかった。経営者インタビューで不適合を出すツワモノもいないだろう。
工場巡回も前回と同じコースである。ただ前回と違うのは、雨が降っていることと、しかもだんだんと強くなってきた。傘を何本も持った女性事務員が後を付いてきて、棟間の移動の際は皆に傘を配る。
テントハウスの前で、バンボディのトラックから荷下ろしをしていた。プラスチックのパレットに積んだ段ボール箱をフォークリフトが下ろして倉庫の中に運ぶのだが、トラックから庇までの間10mほど、段ボール箱の上に雨が降り注いでいる。
注:バンボディとは荷台が箱型になっているトラックのこと

清水審査員はフォークが下ろしたパレットに近づき、雨に濡れた上段の段ボール箱を手でなでる。
![]() 「段ボールがかなり濡れていますが、品質に問題はないのですか?」
「段ボールがかなり濡れていますが、品質に問題はないのですか?」
案内の新沢課長と立ち会っていた本田業務課長が、苦い顔をしている。
![]() 「正直言いまして分かりません。直ぐに上の段を開梱して確認します」
「正直言いまして分かりません。直ぐに上の段を開梱して確認します」
![]() 「雨が降ると、いつもこのような状況になるのですか?」
「雨が降ると、いつもこのような状況になるのですか?」
![]() 「いつもはテントハウスの
「いつもはテントハウスの
本日は倉庫内の補修工事をしていて、一部の荷物を庇の下に移動したので、トラックを庇の下に停められないのです」
![]() 「なるほど、めったに発生しないとしても、雨が降っているときはビニールシートをかぶせるとか対策を決めていないのですか?」
「なるほど、めったに発生しないとしても、雨が降っているときはビニールシートをかぶせるとか対策を決めていないのですか?」
![]() 「不勉強で存じません。調べてみます」
「不勉強で存じません。調べてみます」
・
・
・
審査員二人はこれ以降も、巡回中におかしなものを見つけるとあちこちで立ち止まり、いろいろ質問をする。
それを見て、佐川は役に立つ指摘をしてくれるだろうと思う。その結果、不適合が出るのはやむを得ないし、当然である。
結局、佐川ができるのはISO認証のために、何をしなければならないかを教えることとでしかない。
実際にやっていることがルールと違うか、ルールが不十分かを知らしめる(懲らしめる?)のは、仲間でなく外部の人でないと実効性がないのだ。
そういう意味で、この審査結果で不適合は10個くらい出るだろうが、良いことだと思う。
1時間の予定であった工場巡回が、審査員があちこちで立ち止まるため1時間半かかった。だが藤原リーダーは予定より遅れたことを気にしていないようだ。
これはつまり予備審査で、書面が規格を満たしていることを確認したから、現場で問題になったところを重点的に見るつもりだろう。
・
・
・
最初の部門は業務課であった。
| 藤原リーダー |  | 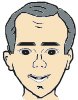 | 本田課長 | |
| 清水審査員 |  |  | 須田さん | |
![]() 「前回お邪魔したとき、書面はほとんど見て仕組みはしっかりできていることは確認しました。
「前回お邪魔したとき、書面はほとんど見て仕組みはしっかりできていることは確認しました。
それで本日は運用状況の確認を主と考えております。
ええとまず気になったのは、フォークリフトの荷下ろしから、テントハウスの倉庫までの運搬です。たまたま雨が降っておりまして、パレットに積まれた段ボールは、特に一番上はだいぶ濡れていました。
まず濡れることは問題ないのか、雨が降っているときの対応を決めているのか、その辺をご説明願います」
本田課長の顔が緊張でこわばっている。
須田は課長の顔を見て、自分が説明するしかないと覚悟したようだ。気が利く部下である。
![]() 「通常はあのように雨に降られて荷下ろしすることはありません。本日は工事中と雨が重なり異常であったことは残念です。
「通常はあのように雨に降られて荷下ろしすることはありません。本日は工事中と雨が重なり異常であったことは残念です。
手順書の作成が晴天時しか定めていなかったということが原因で、雨天や雪の場合などを追加したいと思います」
脇で本田課長がやっと息を吹き返したようで、首を何度も縦に振っている。
![]() 「天気もいろいろあり、雨や雪だけではないと思います。またフォークリフト作業ばかりでなく、例えば歩行するだけでも事故が起きるかもしれません」
「天気もいろいろあり、雨や雪だけではないと思います。またフォークリフト作業ばかりでなく、例えば歩行するだけでも事故が起きるかもしれません」
![]() 「と、おっしゃいますと?」
「と、おっしゃいますと?」
![]() 「異常をすべて想定していくことはできません。雨と雪とおっしゃいましたが、
「異常をすべて想定していくことはできません。雨と雪とおっしゃいましたが、
またフォークリフト作業についてだけでなく、庇の下に荷物を仮置きしたとき、万が一のときテントハウス内の人の避難は大丈夫なのかも考えなければなりません。
先ほど工場巡回したとき、私どもは傘を貸していただきましたが、見ていますとお宅の従業員の方々は、濡れまいと棟間を走っていました。雨が降っているとき走って、滑って転ばないか怪我の恐れはないのか、危険予知なども考慮すべきではないかと思います」
![]() 「おっしゃることは分かりますが、それは業務課のマターではなく、工場全体に関わることですね」
「おっしゃることは分かりますが、それは業務課のマターではなく、工場全体に関わることですね」
![]() 「私どもは製造課の審査をしているわけではありません。長野工場の審査をしております。製造課で出た問題を長野工場の問題と考えてほしいです」
「私どもは製造課の審査をしているわけではありません。長野工場の審査をしております。製造課で出た問題を長野工場の問題と考えてほしいです」
「はい、ご指摘はそのように受け止めて、対策するつもりです」
![]() 「審査とは規格に合わない事象があれば改善を求めるものですが、目の前の事象の改善に留まらず、その発生原因を突き止めて対策してほしい。
「審査とは規格に合わない事象があれば改善を求めるものですが、目の前の事象の改善に留まらず、その発生原因を突き止めて対策してほしい。
本日拝見した雨天時のトラックの積み下ろしは問題ですが、同時に雨天時の棟間移動も問題と思いました。すると問題はトラックの積み下ろしではなく、工場として雨天時の対応策をしっかり決めていないのかなという発想に至ります。
そうなると先ほど本田課長がおっしゃったように、業務課だけの問題ではありませんね。では工場として雨天時のルールをどうするかを、全体の枠組みの中で考えることになります。そして担当部門ごとにそれぞれをどうするのかを考える、対策を決める、実施するとなると思います」
「おっしゃること良く分かりました。そのように是正処置を行います」
![]() 「あっ、勘違いしてほしくないのですが、審査は指摘事項を提示するだけです。どのような対策をするか、どこまでするかはお宅が決めることです。
「あっ、勘違いしてほしくないのですが、審査は指摘事項を提示するだけです。どのような対策をするか、どこまでするかはお宅が決めることです。
ただ今回の問題はフォークリフトのみ記述すると、その対応だけと受け取られると思いましたので、様々な天気のとき、製品品質に関わることが他にもあるのではないかという意味で、雨天時の棟間移動を例に挙げました。
それと正確には、雨天時に走ることは安全の問題で、品質と関係ないと思われますので、ISO9001の審査で取り上げるのは筋違いというか余分なことでした。一応参考まで」
「ご教示ありがとうございます。よく理解しました」
午後はいくつかの部門を行い、初日の最後は製造課である。
| 藤原リーダー |  |  | 高田課長 | |
| 清水審査員 |  |  | 庶務の横山さん | |
![]() 「作業要領書を、作業者の前に吊るしているのは良いですね」
「作業要領書を、作業者の前に吊るしているのは良いですね」
![]() 「お褒め頂きありがとうございます。作業要領書の掲示については緒論ありますが、私はトヨタの大野耐一さんの本に感動し、すべての職場で眼前に掲示するように指示しております」
「お褒め頂きありがとうございます。作業要領書の掲示については緒論ありますが、私はトヨタの大野耐一さんの本に感動し、すべての職場で眼前に掲示するように指示しております」
![]() 「その作業要領書に、工場のキャンペーンのスタンプを押していますね」
「その作業要領書に、工場のキャンペーンのスタンプを押していますね」
![]() 「ハイ、現在、当工場では品質向上キャンペーンを行っており、『品質は1人1人が責任者』をスローガンとしております。それを徹底しようと、作業要領書すべての空白部分にスタンプを押しています」
「ハイ、現在、当工場では品質向上キャンペーンを行っており、『品質は1人1人が責任者』をスローガンとしております。それを徹底しようと、作業要領書すべての空白部分にスタンプを押しています」
![]() 「素晴らしいことだと思います。しかし押印の場所によっては、作業要領書の文字や絵の部分にスタンプの赤インクが重なり、読み取りにくいものが散見されます。あれはどうなのでしょう?」
「素晴らしいことだと思います。しかし押印の場所によっては、作業要領書の文字や絵の部分にスタンプの赤インクが重なり、読み取りにくいものが散見されます。あれはどうなのでしょう?」
![]() 「そのようなものがありましたか?
「そのようなものがありましたか?
横山さん、どうなんです?」
![]() 「なにしろ枚数が枚数ですから大勢で押しました。ずれもあるでしょうし、インクが撥ねたりして、多少は読みにくいものもあるかもしれませんね」
「なにしろ枚数が枚数ですから大勢で押しました。ずれもあるでしょうし、インクが撥ねたりして、多少は読みにくいものもあるかもしれませんね」
![]() 「まずかったかな?」
「まずかったかな?」
![]() 「課長は半年だけ、キャンペーン期間が過ぎて下期になったら、全部入れ替えるとおっしゃったじゃないですか」
「課長は半年だけ、キャンペーン期間が過ぎて下期になったら、全部入れ替えるとおっしゃったじゃないですか」
![]() 「そうだった、そうだった。下期までというとあと二月半か」
「そうだった、そうだった。下期までというとあと二月半か」
![]() 「それと予備審査のとき、藤原リーダーがヒアリングしたとき、御社では見本版も文書として管理するというお話をお聞きしたとのこと」
「それと予備審査のとき、藤原リーダーがヒアリングしたとき、御社では見本版も文書として管理するというお話をお聞きしたとのこと」
![]() 「はい、そうです」
「はい、そうです」
![]() 「塗装作業場にある
「塗装作業場にある
![]() 「いやあ〜、参ったな。
「いやあ〜、参ったな。
塗見本はですね、弊社が作成しますが、それを客先に送って承認印を頂くのですよ。そしてまた退色などを考慮して、有効期限を1年としております。
10カ月経過した時点で新しい塗見本を作り、客先に送付して承認を頂くわけですが、客先もすぐに処理せずに時間がかかるのです。有効期限までに帰ってこないと期限切れになってしまうのです。
それでやむなく新しい塗見本が帰ってくるまで、古いものを継続使用しているのです」
![]() 「なるほど、期限切れの塗見本があったのはそういうことですか。
「なるほど、期限切れの塗見本があったのはそういうことですか。
ええと、以上から考えて、文書管理として問題を提起します。
作業要領書にスローガンをスタンプすることは、規格4.5.1『適切な文書の適正な版が利用できる』に反して文字が判読できないものがあった。
また塗見本については同じく『適用するべきでない文書の利用を防ぐために、最新版の文書を明確にするように、台帳又はそれと同等の文書管理手順を確立する』を満たさないということでよろしいでしょうか」
![]() 「前者のスタンプについては、当方の検討不足であるということで納得します。
「前者のスタンプについては、当方の検討不足であるということで納得します。
しかし後者の塗見本については当社では対応できません」
![]() 「あのですね、審査では是正方法の提案はできません。ですから話半分に聞いてほしいのですが……
「あのですね、審査では是正方法の提案はできません。ですから話半分に聞いてほしいのですが……
まず塗見本の寿命が1年というのは根拠があるのか、もし1年半持つなら10か月後に作成し客先承認を待つ現状でも良いでしょうし、1年しかもたないなら、10か月後でなく半年後とかに作成するのもありでしょう。
でも1年持たないから半年後にサンプルを作成するというのも、理屈に合いませんね。
あるいは先方に有効期限を過ぎている場合、返送されるまでは古い塗見本を継続して使用することの了解を取るなどして、それをルールとするなどあると思います。
もちろん御社が改善策の妥当性・有効性を検討し、客先の了承が必要でしょう。
私どもは、作った決まりが妥当であるか、守られているかを拝見します」
![]() 「なるほど、現在の状況と条件を考慮して、対策を考えるということですね。
「なるほど、現在の状況と条件を考慮して、対策を考えるということですね。
了解しました。いずれにしても現状がまずいとは、私も現場も認識しているところです。ありがとうございます」
・
・
・
審査はまだまだ続く。
二人の審査員の指摘されたことはもっともなことばかりだ。また自分勝手な理屈も振り回さない。佐川はこのお二人はまっとうな審査員なのだろうと思った。
しかし、その思いは10分後に粉砕された。
今日最後の製造課の審査が終わり、皆立ち上がり片付けを始めざわつく。
新沢課長が、これから本日の指摘事項についての対策会議を招集しようと考えていると、藤原リーダーがニコニコ顔で傍に来る。
「ハイ、なにか?」
![]() 「今日の宴席はどこでしょうか?」
「今日の宴席はどこでしょうか?」
新沢は相手が何を言っているのか全然理解できなかった。日本語で話していたら突然ロシア語が飛んできたという感じだ。
ええと……この人たちは、これから宴会があると予定しているということかな……そう考えつくまで数秒かかった。
![]()
これは……まずいぞ、そんなこと考えもしなかった。
何とか手配しなければならない。自分は今夜に今日の指摘の対策と、明日審査を受ける部門への反映をしなければならない。だから出席はできない。場所はどうする?…それに費用は?、総務に話を付けないと……、それに出席者は集まるか……それに……
![]()
新沢はやっと立ち直った。
「ハイ、承知しております。ご覧のようにバタバタしておりますので、応接室で30分ほどお待ち願います」
・
・
・
それからの新沢の動きは、入社23年にして最高のパフォーマンスだったと自分自身思う。飛行機ならアフターバーナー、車ならオーバードライブで走り回り、説得しまわり、人を集めて何とか形にした。
 |  |  |  |
新沢の要請を受けた総務課長は、接待など今の時代めったにないが、そのめったにないとき使う料亭を予約し、総務部長は各部長に話をして今夜参加することを指示し、工場長にも出席をお願いする。
予算は……まあ、しょうがないと総務課長はため息をつく。今どき顧客や官の立入検査だって接待などしないぞ。そもそも初めから相手が断って来る。
30分後、初めは新沢課長は一縷の望みどころか諦めていたが、皆の努力によって、場所と料理と出席者とお金がそろい、審査員の要求への対応は完了した。

だが、総務部長も総務課長も新沢課長も、翌日の夕方に清水審査員が「今晩も昨日と同じところですか?」と聞いてくるとは想像もしなかった。
![]() 本日の反省
本日の反省
今回の審査場面は、なぜかまともな話になってしまい、審査員を茶化す暇がありませんでした。
当時の審査員はまともな審査はしましたが、当然のこととして、飲ませろ、食わせろ、○○させろと言っていたことを省くわけにはいきません。それが当時の現実です。
なお、これは外資系も国内認証機関も変わりません。もっとも外人の審査員が来たとき飲ませたことはなかったと思います。
蛇足ですが、タイにいたとき日本から来た審査員は、審査後にタイ観光と〇ルフをしたいと(以下略)
ただISO9001時代は宴席を求めることはしたが、規格解釈がおかしな人は少なかったのは事実である……少なかったのであって、いなかったわけではない。
ISO14001の時代になると、宴席もお土産も欲したが、より問題なのは規格を理解しておらず「俺がISO規格だ
正確に言えば「俺がISO規格だ」と言った人に会ったことはないが、「私の言うことは絶対だ」とか「私はISOTC委員より詳しい」と語った審査員には複数会った。
また「消防法は消防署より詳しい」とか「廃棄物処理法は県環境課より詳しい」という審査員ほど、間違い(ウソ)を語っていた。困ったことである。
あっ!あなたのことですよ。中〇さん、〇上さん、〇木さん。
彼らの言う通りしていたら、手が後ろに回るところだった。
彼らの言う通りしないと認証がもらえず、いう通りすると違法になる。まさにハムレット。当時は異議申し立てしようなんて知恵が回らなかった。
お土産問題、接待問題は、2003年に読売新聞がISO審査の際の饗応を問題とする記事
規格の理解不足問題……これは2009年以降、審査登録件数が減って認証機関が青くなるまで、改善は見られなかった。いやそれは規格の理解が深まったというよりも、煩く言うと認証辞退されるから控えただけかな?
![]()
これを読んで「ISOアルアルだな」なんて笑っている人がいるだろう。
同志よ!当時は笑い事じゃなかったんだよね(笑)
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
休暇や欠勤中に出張に行くことは通常ないが、緊急時において出張を命じることは可能である。 | ||
「俺がルールブックだ」とは1959年、プロ野球の二出川延明審判が判定に抗議されたときに発した言葉とされている。 二出川審判の表現はともかく、その判定はルールブック通りで間違いなかった。 「私はISOTC委員より詳しい」と自称したISO審査員の語ったことは「すべて間違い」だったのとは違う。 | ||
読売新聞 2003/4/22、某認証機関の審査員が審査に行った〇市から前沢牛の接待を受けた。 2003/8/14、某認証機関の取締役と審査員が、審査に行った〇町から饗応を受けた。 実際の記事は実名記載。いずれも続報がある。 ISO担当にとっては、そんなこと日常茶飯事で当たり前すぎることであった。 ご異議あれば ⇒こちらへ |
外資社員様からお便りを頂きました(24.12.12)
おばQさま 今回はまともな審査なのだと感心していたら、最後に来ましたね(笑) 空気を読まない私なら、ここで一言「審査機関の独立性」と三遍唱えてみます。 えぇ、それでもダメなら「記念写真撮りましょう、記録になりますから」 無駄な不適合出されて、無駄な工数使うよりは、接待で済むなら安いものだから、受け入れるのが当時の空気でしょうね。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。偉い人は実質はどうでも良くて、納期通り形ができれば良いと考えています。 ルールに則してどうなのか? 社会通念におかしくないのか? 無駄使いでないのか? 細かいかもしれませんが大事なことを見つめてないのです。 そんなら最初からコンプライアンス無視で「3せる」でやればいいのですよ。まあ、一寸の虫にも五分の魂、下っ端にも矜持ってもんがあります。 ともあれそういう摂待で済むならという発想が、認証機関や審査員を甘やかしてしまった、だからISO認証をダメにしてしまったということは大いにあると思います。 まあ、棺桶に片足入れたISO認証制度を私のように真面目に考えている人はいないでしょう。10年も前、大学院の修士論文でISO認証の信頼性なんてのを書いたら、先生がもうISOの時代じゃない、社会責任投資とかテーマにしろなんて言われてオシマイでしたから。そんなものなのでしょう。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |