注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
6月11日金曜日である。
朝ホテルで目が覚めて佐川の頭に浮かんだのは、今日、審査が終わった後の反省会(?)がもめて、今日は帰れないだろうということであった。
 というのは、昨日、審査はいくつもの部門で「指摘です」とは言われていないが、何件ものダメ出しを食らっているから、その内の何件かは不適合になるだろう、そして出された部門は、本社の……つまり佐川の指導が悪いからだと吊るし上げされるだろう。
というのは、昨日、審査はいくつもの部門で「指摘です」とは言われていないが、何件ものダメ出しを食らっているから、その内の何件かは不適合になるだろう、そして出された部門は、本社の……つまり佐川の指導が悪いからだと吊るし上げされるだろう。
まあ、問題があり原因が己自身にあって鬱憤をぶつける先がないとき、本社が受けるしかあるまい。
恨まれるのも賃金の内だ。
審査は午前中、残った部門の書面審査を終え、午後は審査員のまとめである。
3時には報告書案をまとめて、新沢課長に声をかけるという。
用意した小会議室に審査員二名がこもり、部屋に入ってから20分ほどはなにやら話声が聞こえたが、そのあとは静かになった。
 当時は書類というのは、外に出すものを除いて手書きが基本だ。いや手書きしかできない。だから1990年以前、事務職の人たちは、ペン習字とか事務用の文字・数字を書けるように練習したものだ。
当時は書類というのは、外に出すものを除いて手書きが基本だ。いや手書きしかできない。だから1990年以前、事務職の人たちは、ペン習字とか事務用の文字・数字を書けるように練習したものだ。
ISO審査のように、出張先で作成するのも手書きだ。当時の所見報告書は、幼稚園児かと思われるような稚拙な字もあり、達筆なものまでバラエティに富んでいた。
手書きだから報告書を作成すると言っても、キーボードを叩く音もしないしプリンターのチーカチャカチャ、チーという音もない。
審査所見報告書をワープロするようになったのは、1995年頃からだろう。
1990年代前半、パソコンはまだノートと呼ぶには厚みがあり重かった。年々ノートパソコンが小さく軽くなり、所見報告書を持参したパソコンでワープロするようになった。だがプリンターまで持ち歩く審査員は少なく、またパソコンを訪問先のLANにつなぐのはウイルスの危険性から拒否され、一旦eメールで認証企業の担当者に送り、それを担当者のパソコンからプリントアウトしてもらうなどしたものだ。
審査員まとめの時間、品質保証課のメンバーと佐川と山口は、隣の部屋でだべっている。審査員から何か要望があると対応するためだ。
 | ||||
 | ||||
![]() 「いやはや予想していたよりも、だいぶ数多く指摘を出されましたね」
「いやはや予想していたよりも、だいぶ数多く指摘を出されましたね」
![]() 「全部が不適合になるわけではありません。彼らも問題にしたものを取捨選択するでしょうし、同じ項番のものをまとめて問題提起するかもしれません。
「全部が不適合になるわけではありません。彼らも問題にしたものを取捨選択するでしょうし、同じ項番のものをまとめて問題提起するかもしれません。
現場や書類で見つけた現象を即不適合とするのは、低レベルな審査員です。その現象が何が不適合か……不適合とはISO規格のどのshallを満たしていないかということですが……それを考えてまとめるわけです」
![]() 「それは審査員が問題の原因を究明するということですか?」
「それは審査員が問題の原因を究明するということですか?」
![]() 「原因究明まではしません。それは企業がすることです。
「原因究明まではしません。それは企業がすることです。
例えば文書のバージョンが古かったというのもありましたね。その現象は『4.5.1a)活動を行うすべての部門において、適切な文書の適正な版が利用できる』に該当することを、示すまでが審査員の仕事です。
なぜ適切な文書の適正な版が利用できなかったのかの、原因を調べるのは会社です」
![]() 「ああ、そうか、分かりました。兵庫工場の不適合におかしいのがあったのは、shallがハッキリしていなかった。ええと不適合の根拠を示していないものがいくつもありましたね。
「ああ、そうか、分かりました。兵庫工場の不適合におかしいのがあったのは、shallがハッキリしていなかった。ええと不適合の根拠を示していないものがいくつもありましたね。
そうそう、審査員は不適合を出すとき、証拠と根拠を書かなければならないとISO10011にありましたね」
![]() 「兵庫工場のときは、言いがかりというか、誰が聞いてもそれはおかしいだろうというような指摘ばかりでした。それは審査員自身がどのshallに該当すると考えていないからですね。正確に言えばshallがないのに、審査員の思い込みで不適合にしている。
「兵庫工場のときは、言いがかりというか、誰が聞いてもそれはおかしいだろうというような指摘ばかりでした。それは審査員自身がどのshallに該当すると考えていないからですね。正確に言えばshallがないのに、審査員の思い込みで不適合にしている。
今回は、問題と言われたことは納得できます。それがそのまま不適合になるわけではないとは思いますが」
「確かに兵庫工場の不適合、従業員がマニュアルを読んでいないとか、規定集の配布数が少ないとか、正式な報告書の脇にコピー黒板のメモがファイルされているとか、規格要求事項にないことばかりだ。ケチ付けているとしか思えない」
「しかし有効期限の過ぎた
![]() 「でも課長が当面はそれで行くと決めたなら、良いのではないですか?」
「でも課長が当面はそれで行くと決めたなら、良いのではないですか?」
![]() 「ISOはある意味、形式を求めるから、それなら課長が『新しい塗見本ができるまでこの見本を使うことにする』と紙に書いてハンコを押して、塗見本に貼っておくとかしておけばOKでしょう。
「ISOはある意味、形式を求めるから、それなら課長が『新しい塗見本ができるまでこの見本を使うことにする』と紙に書いてハンコを押して、塗見本に貼っておくとかしておけばOKでしょう。
もちろん規定の方には『塗見本の再承認が遅れた場合は云々』と、そのルールというか手順を決めておく必要がありますよ。まあ緊急時には、そこまでしなくても良いとは思います」
注:佐川が「ISOは形式を求める」と述べたことに、若干補足する。
ISO規格とは「暗黙知を形式知とする」ことと同義である。そもそもISO規格とは、職人の頭の中にあることを、皆で共有して同じレベルの仕事をしましょうという考えだから、「形式的」に悪いという意味は全くない。標準化とはそういうものだ。
![]() 「ああ、そうすれば良いのですか」
「ああ、そうすれば良いのですか」
![]() 「ルールを杓子定規に守るのでなく、より良い方法を考えてそれをルールにするのです。そんなこと、ISO規格が登場する前から当たり前にしていたことです」
「ルールを杓子定規に守るのでなく、より良い方法を考えてそれをルールにするのです。そんなこと、ISO規格が登場する前から当たり前にしていたことです」
「トラックから降ろすとき搬入する部品が濡れると気づくというか、濡れたら大丈夫かと思う気持ちがなかったのですかねえ〜」
![]() 「確かにISOに関係なく、おかしいと思わないとおかしいですよね」
「確かにISOに関係なく、おかしいと思わないとおかしいですよね」
「とはいえ、不適合がたくさんあれば、品質保証課の責任だと言われるだろうな」
![]() 「私は、品質保証課は管理責任者の手足だと考えています。
「私は、品質保証課は管理責任者の手足だと考えています。
製造部長は予備審査(第34話)のとき、管理責任者の職務を熱く語っていたじゃないですか」
「おお!確かに、あのとき部長は、管理責任者の仕事はひとりの人がすることではなく、それぞれの仕事を担当している人たちがするのだと言っていましたね。そして管理責任者は、それを包括的に見て調整するのが役目という話でした」
「ああ、そんな話をしていたな。ということは塗見本の期限切れとか部品が雨で濡れたことは、品証の責任ではないと言えるのか?」
![]() 「それからISO規格にある要求事項も、いろいろありますから、品質保証担当でなく、品質管理担当というものもありますよね。体制や抽象的なものは品質保証の範疇でしょうけど、製品固有など即物的なことは品質管理の範疇ですよ」
「それからISO規格にある要求事項も、いろいろありますから、品質保証担当でなく、品質管理担当というものもありますよね。体制や抽象的なものは品質保証の範疇でしょうけど、製品固有など即物的なことは品質管理の範疇ですよ」
![]() 「理屈からはそうですが……それを見つけてくれないのは、品証の責任だと言われるのは見えていますね」
「理屈からはそうですが……それを見つけてくれないのは、品証の責任だと言われるのは見えていますね」
参考までに、
「品質管理」とはQuality controlの訳で「品管」と略し、「品質保証」とはQuality assuranceの訳で通常「品証」と略す。品質管理と品質保証は異なるもので、お互いに補完しあう関係にある。
昔(1990年以前)は「Quality management」を「広義の品質管理」と呼び、「Quality control」を「狭義の品質管理」と呼んでいた。「呼んでいた」とは私の思い込みではなく、当時のJIS用語でそう決めていた。
当時は広義の品質管理(今は品質マネジメントとか品質経営などと呼ぶ)は狭義の品質管理、品質保証、品質改善からなると言われる。
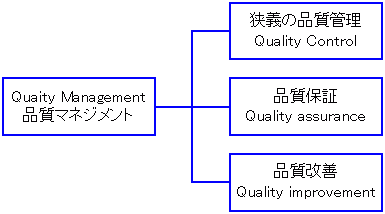
この図は1990年以前は品質管理の概念図として広く使われていたが、ISO9001登場後は使われなくなった。
なぜだろう?
品質管理は、「作り手側の視点」で不良品を出さないことで、主に製造過程を管理する。品質管理は中世欧州のギルド所属員が悪いものを出さないために始まり、産業革命をへて19世紀後半から大量生産の品質維持の方法論が確立されてきた。

「品質保証」とは「買い手側の視点」で、企画から使用時までの安心感、満足感の向上を図るもの。品質保証も昔から発想はあったが、現在の品質保証は第二次世界大戦で不発弾、不発爆弾を減らすために、完成までの全工程を管理する方法論として確立した。
「うまく行けば現場の成果、ダメなら品証の責任と、どっちに転んでも自分は悪くない」
![]() 「まあまあ、どんな不適合を出してくるのかまだ未定ですが、期限切れも雨に濡れたのも、新沢さんや池神さんに是正処置ができるわけないのは、はっきりしています。是正できるのは問題を起こした部門です。
「まあまあ、どんな不適合を出してくるのかまだ未定ですが、期限切れも雨に濡れたのも、新沢さんや池神さんに是正処置ができるわけないのは、はっきりしています。是正できるのは問題を起こした部門です。
品質保証課としては、内部監査で見逃したのはなぜかを考えること、そして各担当課が考えてきた是正処置案が、指摘されたこと、例えば濡れ防止に効果があるかを検証することでしょうね。
目の前の対策だけでなく、発生を防止するような前向きなものでないと困りますね。
本日、不適合となったことの是正処置を認証機関に提出して、検討不十分とか水平展開不足と差し戻しになれば、それは品質保証課の責任ですから」
 |  |  |  |
「内部監査で見逃した理由といえば、確かに現場はほとんど見ませんでしたね。作業要領書も塗見本も。本当なら作業者が要領書通りしているかを、チェックしなければならないだろうな。
次回の内部監査では現場をしっかり見なければなりませんね」
「我々がした内部監査は認証機関のした予備審査に当たるのだろう。つまり文書ができているかの点検だったんだ。
これからは運用をしっかり見るようにしようや。気にすることはない」
![]() 「今日何件、不適合にされるか知りませんが、佐川さんならうまいこと説明して、向うが出してくる不適合を撤回させられませんか?」
「今日何件、不適合にされるか知りませんが、佐川さんならうまいこと説明して、向うが出してくる不適合を撤回させられませんか?」
![]() 「ものによっては上手く説明すれば、撤回させられるものもあるだろうね。
「ものによっては上手く説明すれば、撤回させられるものもあるだろうね。
例えば塗見本の期限オーバーなら、客先との電話交渉の記録とかを見せて、期限延長となったことを朝礼で伝えていたが、塗見本に注記するのが漏れたとか説明すれば、相手は納得するかもしれない。
ただどうかなあ〜、兵庫工場の場合は、審査員が間違えたことを説得することだった。今回は審査員は間違えていない。
ルールに反していることを、はっきりと不適合とされたなら、反省して是正すべきだろう」
「私もそう思います。不適合の件数を減らしても意味がない。指摘事項とは、罰を食らうとかではない。不適切なところを示してもらって直すことです」
「不適合が出た部門からは、助けてくれという声が出されるでしょうけど」
「まあ、しかたない。それは覚悟しておこう」
・
・
・
丁度、話が一段落したとき、ノックされドアが開いた。
清水審査員が顔を出した。
![]() 「案ができましたので説明したいと思います。
「案ができましたので説明したいと思います。
メンバー集めと、このコピーを人数分お願いします」
「そいじゃ人を集めますから、10分ほどお待ちください」
新沢課長は管理責任者である製造部長と、書面審査で問題があった課長に集合をかける。
池神は受け取った紙を持ってコピー室に行ったようだ。
用意がそろうと審査結果の説明会兼調整が始まった。
![]() 「予備審と本審査を行いました。報告書案をまとめましたので、内容の確認をしていただき意見交換をしたいと思います」
「予備審と本審査を行いました。報告書案をまとめましたので、内容の確認をしていただき意見交換をしたいと思います」
不適合として提示されたのは4件であった。
|
長野工場の初回審査 不適合一覧
|
![]() 「以上です。
「以上です。
なお、予備審のときの指摘2件、製造部の文書管理の安全対策と営業の顧客との電話での交渉の際の記録については、是正を完了したことを確認しました。
皆さん関心を持たれている不適合案4件についてのご意見をお願いします」
![]() 「契約内容の品質記録に関しては、規定通りでないのは間違いないです。指摘に異議はありません」
「契約内容の品質記録に関しては、規定通りでないのは間違いないです。指摘に異議はありません」
![]() 「設計の妥当性確認とデザインレビューの記録ですが、規定では両方とも機種ごとにファイルすることになっています。デザインレビューの記録は機種を問わずデザインレビューの記録にファイルされているとありましたが、実際には、昨日ご覧になったひとりの担当者だけが、デザインレビューというファイルを作って、その者が担当した機種のみがまとめてファイルしていました。
「設計の妥当性確認とデザインレビューの記録ですが、規定では両方とも機種ごとにファイルすることになっています。デザインレビューの記録は機種を問わずデザインレビューの記録にファイルされているとありましたが、実際には、昨日ご覧になったひとりの担当者だけが、デザインレビューというファイルを作って、その者が担当した機種のみがまとめてファイルしていました。
そこはそのように書き直してください。
それで昨日、指摘を受けてから間違った方法でファイリングしていた担当者には注意して、規定に定める通りにファイリングを見直しました。
現時点は規定通り、すべて機種ごとファイルに直しました。
それでですね、つきましては不適合を勘弁してもらえないですかね? つまり削除してもらえませんかね」
![]() 「ファイリングを見直したとおっしゃいましたが、現物を拝見出来ますか?」
「ファイリングを見直したとおっしゃいましたが、現物を拝見出来ますか?」
 |
設計担当者が数冊のファイルを持って審査員のところに行く。清水審査員と藤原リーダーがパラパラ見てうなずく。
![]() 「是正までしたとみなしましょう。承知しました。不適合から削除します」
「是正までしたとみなしましょう。承知しました。不適合から削除します」
![]() 「よろしくお願いします」
「よろしくお願いします」
篠原課長はニコニコしている。
それを見た営業課長が手を挙げた。
![]() 「あれ、それってありですか?
「あれ、それってありですか?
実は私どもも指摘されてすぐにファイリングの見直しをして、関係者に規定を遵守するよう通知しているのです。営業の方も削除してもらえませんかね」
![]() 「よろしいでしょう。削除します」
「よろしいでしょう。削除します」
![]() 「ありがとうございます」
「ありがとうございます」
![]() 「文書管理と取扱いについての不適合を了解しました。
「文書管理と取扱いについての不適合を了解しました。
ひとつ質問ですが、作業要領書にスローガンを記載することはまずいのでしょうか?」
![]() 「まずご理解いただきたいこととして、審査員は、規格に合っていないものを問題提起するだけが仕事でして、システムについて相談を受けたり是正方法のアドバイスをしてはいけないルールです。
「まずご理解いただきたいこととして、審査員は、規格に合っていないものを問題提起するだけが仕事でして、システムについて相談を受けたり是正方法のアドバイスをしてはいけないルールです。
まあ、それは置いといて、スローガンを要領書に掲げることは悪いことではありません。ですからスローガンを書き込みたければ、最初から様式の一部として印刷してしまうか、後でスタンプを押印するなら、予めスタンプを押す空欄を設けておくとか、要するに本文や説明図が、見えなくならないようにすべきでしょうね」
![]() 「ああ、ありがとうございました」
「ああ、ありがとうございました」
「品質監査についてですが、今まではISO認証活動中でして、ここ2カ月で3回行っております。それで改めて是正のフォローアップは行っていませんが、不適合を見つけた次の内部監査時には前回のフォローをしています。書面審査の際に、その次に行った内部監査記録に記述していたのを、お見せしたと思います。
また内部監査ではアドバイスすることは不適なのは分かりますが、別途是正検討の会議とか議事録を作るまでなく、監査時には関係者が集まっているわけで、その場で是正策を打ち合わせたことも記録も盛り込んでいます。そのことも審査時に説明したつもりです。
監査、是正検討、是正の実施、是正確認という杓子定規の流れではありませんが、認証活動中の出来事としてご理解いただきたい」
![]() 「清水さんそういった説明はあったの?
「清水さんそういった説明はあったの?
じゃあ、OKでいいですか?
了解しました。これについては削除します。
ただ原則を述べますと、審査員であろうと内部監査員であろうと、同じ人が問題を指摘することと是正をすることは、コンフリクトが生じると心してください。あるいはコンフリクトに気付かず、ポジティブフィードバックが起きるおそれがあります。
覚えておいて欲しいのは、内部監査をした人と、不適合の是正確認をする人は違えることが必要です。内部監査とその是正処置も、常にその妥当性は監視されなければならないのです」
注:監査した人が是正の相談に乗ってはいけないというのは、よく言われることである。だが監査の不適合の是正処置を、監査した人が確認することが不適切なことは、私の経験から間違いない。
![]()
監査した人の判定が間違えていた場合はもちろんであるし、判定が間違いなくても、是正処置が監査した人の思いの方向に進むことは十分考えられる。特に法規制に関わることは重大だから、ダブルチェックの意味でも是正確認は人を変えて行うべきだ。
![]()
 悪の是正スパイラル |
それは都市伝説ではなく、私自身、その経験が2度ある。審査員よ、是正を指導してはいけないと言いたいが、指摘する人と是正確認をする人が同一では仕組として問題があるのだ。
「おっしゃる意味分かります。認証までは本社の協力を得てガムシャラにやってきたという状況でした。今後は手順を守って行えると思います」
![]() 「それじゃ皆、納得したか?
「それじゃ皆、納得したか?
おお、本社の佐川さん、山口さん、何かご意見ありませんか?」
![]() 「異議はありません。
「異議はありません。
ご指摘はすべて妥当で、長野工場の向上に役立つものと考えます」
![]() 「そうしますと指摘事項2件ということになりますか?
「そうしますと指摘事項2件ということになりますか?
じゃあ、藤原審査員さん、それでまとめてください。
クロージングミーティングは何時からになりますか?」
![]() 「修正に10分、それをお宅に確認してもらい管理責任者のサインをしていただいて、それを皆に配るためのコピーを頼むとして、何分くらいかかりますか?」
「修正に10分、それをお宅に確認してもらい管理責任者のサインをしていただいて、それを皆に配るためのコピーを頼むとして、何分くらいかかりますか?」
「20分あれば十分です」
![]() 「それじゃ、4時開始ということでいかがでしょうか?」
「それじゃ、4時開始ということでいかがでしょうか?」
・
・
・
クロージングミーティングの後に、清水審査員が新沢課長に「今晩も昨日と同じところですか?」と聞いてきた。
新沢課長は何のことか分からず数秒間フリーズした。そして昨日と同じとは宴席のことと気づき、すぐに手配しなければと思ったが、いや、もういいだろうと考え直した。
新沢課長はにっこりとして
「本日は私ども皆、仕事が溜まっておりまして、ちょっと無理です。半年後、おいでになったときに、また楽しくやりましょう」
清水審査員も気を悪くした風もなく、そいじゃまたと言って控室に戻っていった。
新沢はほっと息を吐いた。
半年に1回飲ませるくらいは、まあ、良いだろう。
なお、ISO9001の初期は、維持審査のインターバルは半年だった。数年後に1年間隔か半年間隔かを選択するようになり、ISO14001が登場した頃は、1年間隔がデフォとなった。
定時後は予想通り反省会である。長野工場の関係者と佐川と山口が集まる。
打ち上げでないのが良いのか悪いのか、真面目なのか不真面目なのか?

皆、ホッとしているのは事実だ。ISO9001認証はビジネス継続のためという大義があり、必死に頑張ってきたわけで、課題山積であったが、結果として納期を守り目的を達したのは間違いない。
とはいえ、皆、欲目はある。
![]() 「本社の支援が悪いんじゃないか?
「本社の支援が悪いんじゃないか?
要領書に押したスタンプがずれて文字が見えないなんてのは見つけてくれないと困るよ」
![]() 「文書管理を考えてみてください。
「文書管理を考えてみてください。
指摘されたのは仕組みの問題ではなく、運用の問題です。本社も品質保証課も仕組みの問題の指導はできますが、運用はその部門に頑張って欲しいのです」
![]() 「運用とは何だ?」
「運用とは何だ?」
![]() 「文字通り、日々の仕事です。
「文字通り、日々の仕事です。
例えば他の工場でもありましたが、今回も規定集の中に改定副番が古いのが入っていたという部門がありました。
改定副番Dまで進んでいる規定が、ある部門では副番Cが入っていたそうです」
注:
例:ゼロ戦11型(A6M2-a)、ゼロ戦21型(A6M2-b)……aやbが副番にあたる。
 |
|
| ゼロ戦32型(A6M3) これは型名が違う |
似たようなものに「枝番」があり、ISO17021-1、ISO17021-2というように、1つの文書を分割した場合などに付けられる記号をいう。
なお、「そえばん」でなく「ふくばん」と呼ぶ会社もある。副番と枝番の意味合いは、組織によって逆のこともあるようだ。
![]() 「言っている意味が分からないが」
「言っている意味が分からないが」
「予備審査のとき、すべての規定を新しくコピーして中身を入れ替えたのですが……予備審から本審までたった40日しか経っていません。その40日の間にも何度か規定改定があったそうです。そのときに差し替えのミスしたということです。
そういう日々の業務管理は、誰がしなければいけないのでしょうか?
それを本社の指導が悪いと言われても困るでしょう」
![]() 「でも指摘されたのは、規定集の差し替えのような運用ばかりではないでしょう?」
「でも指摘されたのは、規定集の差し替えのような運用ばかりではないでしょう?」
![]() 「いや、そうです。塗見本の有効期限が過ぎたのを、使っていたというのもありましたね。作業要領書に品質活動のスローガンをスタンプで押して、要領書の文字が読めないというものもありました。いずれも元からある長野工場の規定を読めばそういう事態は異常だと思うはずです。
「いや、そうです。塗見本の有効期限が過ぎたのを、使っていたというのもありましたね。作業要領書に品質活動のスローガンをスタンプで押して、要領書の文字が読めないというものもありました。いずれも元からある長野工場の規定を読めばそういう事態は異常だと思うはずです。
慣れてしまって、異常を異常と感じなくなっていたと思うのです」
![]() 「そういわれりゃ、設計のファイルの仕方が規定通りでないのを、本社のせいとは言えないな」
「そういわれりゃ、設計のファイルの仕方が規定通りでないのを、本社のせいとは言えないな」
![]() 「分かった、分かった。
「分かった、分かった。
本社の指導が悪かったわけじゃないということだな」
![]() 「今までは規定の改定差し替えミスを見つけても、大したことじゃないと考えていたのだろう。ISOの要求は高いわけじゃないけど、ルール逸脱を見逃さないことなんだ。
「今までは規定の改定差し替えミスを見つけても、大したことじゃないと考えていたのだろう。ISOの要求は高いわけじゃないけど、ルール逸脱を見逃さないことなんだ。
これからは日常管理を、しっかりするということが大事だ。
決裁は決められた人か、代印は委任されたものか、孫コピーはしてないか、当たり前のことでしかない。実を言って、それが大変なんだがな。
当たり前のことを当たり前にやる、それしかない」
![]() 本日の思い出・本日の決意
本日の思い出・本日の決意
 1993年、最初にISO9001認証したとき、缶ビールと乾きもので打ち上げをした。そのとき仲間といろいろ話したが、一人が次のようなことを語ったのを覚えている。
1993年、最初にISO9001認証したとき、缶ビールと乾きもので打ち上げをした。そのとき仲間といろいろ話したが、一人が次のようなことを語ったのを覚えている。
「10年後、ISOってなんだったんだろうって言ってるよね」
つまりISO認証など、一過性の流行、熱病みたいなものだと言ったのだ。
ISO9001の認証件数はその13年後の2006年後にピークとなり、それ以降、単調減少して、30年後の2024年には、ピークのちょうど半分になった。
流行が去って、ISO認証制度は何を残したのだろうか? 日本の、いや世界の品質保証はいかほど向上したのだろうか?
私はISO9001とか14001の流行が悪かったとは言わない。社内失業者だった私は、ISO認証のおかげで家族を養うことができた。ありがたいことだ。
だが不満はある。ISO認証に関わった人、特に審査側の人がもっと真面目に仕事をしたならば、今よりもっと興隆していただろうと思う。
証拠を出せ!
それを、待ってました!
ISO認証の信頼性が問われたとき、なぜそれを究明しなかったのか?
「信頼性向上のためのアクションプラン」はどうなったのか?
認定機関もJACBも計画を立てるのは得意なようだが、結果が大事。
それも計画したことはやりました、では困る。
大事なのは、あなたたちの大好きなアウトプットマターズ
結果として、信頼性は上がったのか、それは定量的に立証できるのか?
「マネジメントシステム規格認証制度の信頼性向上のための「アクションプラン(行動計画)」は2009年8月だった。
あれから15年、あの時生まれた赤ちゃんは2025年春、高校生になる。
アクションプランは野垂れ死にしたのか?
それとも実体のない
タイムスリップISOの中で、そういうことを書いていく予定だ。
乞うご期待
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
アウトプットマターズとは、2008年頃ISO業界で流行語大賞になった言葉だ(冗談だ)。当時はISO9001の認証が始まって15年、ISO14001認証が始まって10年経っていた。そして「ISO9001認証して良くなったのは文書管理だけ、ISO14001認証して良くなったのは環境意識だけ」なんて揶揄された。 そういう空気から、規格に適合するだけではまずい、成果が出なければならないのだという発想から、アウトプットマターズが必要と言われた……実際はもっともらしく美辞麗句を連ねて説明されていた。 だがISO認証するにはアウトプットマターズがなければならないという理屈もない。なぜならISO認証はパフォーマンスが上がることを保証していない。 2009年7月に発行されたISO/IAF共同コミュニケにおいて、ISO認証とは組織が規格を満たしていることを確認した以上のことを意味しないとある。 これらを踏まえると、ISO認証が組織のパフォーマンス向上をさせる/促す効果はないといえる。 さあ、困った。私が困ったわけではない。ISO業界が困ったのだ。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |