注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
今日はISO研究会である。佐川は未来プロジェクトに異動してから、めったに顔を出さなくなり、吉宗機械からは山口だけが毎回出席している。
規格発行から1年が過ぎISO14001の審査が進むにつれて、審査員の未熟やミスによるトラブルも減ってきた。そのためメンバーの関心が薄れたのか、月例の研究会は欠席が目立つようになってきた。
いよいよ、環境ISO研究会も任務完了かと思えてきた。
だが今回は出席者が多い。実は最近新たな問題が起きたのだ。いや、起きつつあるというべきか?
 吉本 吉本 | ||||
| 金子 |  須藤 須藤 |
|||
| 田中 |  山口 山口 |
|||
| 高橋 |  鈴木 鈴木 |
|||
| 小林 | ||||
![]() 「実は数か月前に私のところの関連会社で審査を受けて、特定した環境側面に有益か有害かの区分がないと言われた。審査員が言うには、不適合ではないが口頭で改善しろ……つまり有害・有益の記載を追加しろと言われたとのこと。
「実は数か月前に私のところの関連会社で審査を受けて、特定した環境側面に有益か有害かの区分がないと言われた。審査員が言うには、不適合ではないが口頭で改善しろ……つまり有害・有益の記載を追加しろと言われたとのこと。
その関連会社から、環境側面に有益とか有害とかあるのかと質問されて、そんなわけないと答えました。
ところがつい先週、高橋さんと須藤さん、そして中村さんからも、環境側面に有益なものがないと不適合になったという情報が入りました。
驚いて、当社の工場と関連会社に問い合わせたら、7カ所から『有益な環境側面があることが認証に必要』と言われたという報告がありました。
幸いと言うかなんというか、4カ所では環境側面に有益な環境影響や有害な環境影響が記載してあったので、OKになったという。
そして3カ所ではそういった記述がなかったため、不適合にされていた。
これをどう考えるかということが、本日の緊急課題です」
![]() 「ああ、我社でも言われたよ。だけど審査員によって有益・有害の識別が必要だという人と、いらないという人がいた。だからそんなことで、不適合を出されるとは思い至らなかったね」
「ああ、我社でも言われたよ。だけど審査員によって有益・有害の識別が必要だという人と、いらないという人がいた。だからそんなことで、不適合を出されるとは思い至らなかったね」
私が有益な環境側面という言葉を聞いたのは、2000年だったと思う。
他社の同業者(ISO担当)から電話があって、「最近、審査を受けたのだが、そのとき審査員から、有益な環境側面がないとこれからは不適合になると言われた」という。
![]()
詳細を聞いたが、審査員の言葉として環境側面には有益な環境側面と有害な環境側面に分かれるから、有害な環境側面だけでなく有益な環境側面も抽出することが必須であり、当然、環境側面に有害か有益かの識別をしなければならないと言われたという。
![]()
その話を聞いて呆れた。全く新しいアイデア?であることは認めるが、大きく間違っていることは確実だ。いったいどこのバカがそんなことを語っているのかと聞くと、雑誌などに寄稿している有名な審査員らしい。
またトラブルメーカーが現れたかと、私はガックリした。
![]() 「まず有益な環境側面と有害な環境側面があるというのは事実なのか、それを議論したい。
「まず有益な環境側面と有害な環境側面があるというのは事実なのか、それを議論したい。
それが有益・有害の環境側面があるなら、識別する義務があるのかどうかになる」
![]() 「規格を読む限り環境側面に有害・有益を識別せよという要求はないのは確実だ。
「規格を読む限り環境側面に有害・有益を識別せよという要求はないのは確実だ。
では環境側面に有害・有益と分けられるかどうかはどうだろう?」
![]() 「この世に人間が作ったものは、すべて人間社会にとって有益だから、存在しているのです。ですから存在するすべての環境側面から出る環境影響を合計すると、有益な環境影響が多いことは間違いありません」
「この世に人間が作ったものは、すべて人間社会にとって有益だから、存在しているのです。ですから存在するすべての環境側面から出る環境影響を合計すると、有益な環境影響が多いことは間違いありません」
![]() 「ちょっと待ってください。例えばPCBを考えてみましょう。PCBは著しい環境側面ですが、あれを有益な側面と言えますか?」
「ちょっと待ってください。例えばPCBを考えてみましょう。PCBは著しい環境側面ですが、あれを有益な側面と言えますか?」
![]() 「今、金子さんは『有益な側面』とおっしゃいましたが、この場合の『側面』は観点と言う意味と理解します。『有益な環境側面』があるかどうかはまだ議論していませんから」
「今、金子さんは『有益な側面』とおっしゃいましたが、この場合の『側面』は観点と言う意味と理解します。『有益な環境側面』があるかどうかはまだ議論していませんから」
![]() 「おっしゃるとおりです。『PCBの環境影響に有益なものがあるか』と訂正します」
「おっしゃるとおりです。『PCBの環境影響に有益なものがあるか』と訂正します」
![]() 「PCBの有害性は、1968年のカネミ油症事件
「PCBの有害性は、1968年のカネミ油症事件
油症事件ばかりではありませんが、その頃から世界的にPCB規制が行われるようになり、多くの国ではPCBの無害化処分が行われています」
![]() 「日本では全然処理してないの?」
「日本では全然処理してないの?」
![]() 「いえ一度焼却処理をしたことがあったはずです
「いえ一度焼却処理をしたことがあったはずです
爾来、30年間、使用者・保有者に、しっかり保管しておけと、ふざけたことです」
注:PCBが危険だとなり、製造、使用の禁止がされたが、使用中・保管中のPCBをどのように無害化処理するかは決まらず、使用者・所有者が適正に管理しろという規制が30年も続いた。
 | |
なんでこんなに時間がかかったのかと言えば、政治が悪いということなのだろうが、物事は単純ではない。
外国ではカネミ油症のようが事件がなく、大きな反対運動もなく、日本では濃度0.5ppm以上はPCB廃棄物としたのに対して、アメリカ・カナダは濃度が50ppm以上、スウェーデンは100ppm以上として、処理方法も高温焼却でOKとして、ドンドンと処理を進めた。
日本では微量でも危険だとか、燃やさない処理をしろなど反対運動があった。
![]() 「PCBの良いところって何なの?」
「PCBの良いところって何なの?」
![]() 「いろいろな用途に使われていたのは、メリットがたくさんあるからですよ。燃えない、電気絶縁が良い、熱で劣化しない、化学的に安定しているなどです。そのためトランスやコンデンサの絶縁油として最適、エレベーターのケーブルに混ぜれば柔軟性を与えかつ安定している。
「いろいろな用途に使われていたのは、メリットがたくさんあるからですよ。燃えない、電気絶縁が良い、熱で劣化しない、化学的に安定しているなどです。そのためトランスやコンデンサの絶縁油として最適、エレベーターのケーブルに混ぜれば柔軟性を与えかつ安定している。
人に口に入らなければ最高です。
まあ、それはおいといて・・・
PCBの危険性が知られていないとき、製品の原料から廃棄までのライフサイクルを通じてのベネフィット/ロスの和がプラスと評価されていたのです。
観点を変えましょう。今世に使われている様々な物質、道具、機械があります。そこに新しい物質、道具、機械などを送り出そうとしたとき、過去からあるものより費用対効果が良くなければ需要がないではありませんか。つまり世の中に存在するものは役に立つもの、有益なものだけです」
![]() 「ああっ、そういう考え方もあるか?
「ああっ、そういう考え方もあるか?
となると存在するものはすべて有害より有益な効果が大きいということになる。
いや、待てよ。そうすると環境側面はすべて有益なことになる」
![]() 「こういう話をするときりも限りないのですが、もう少し話すと、かっては垂れ流しで良かったものが時代と共に内部化・・・要するに製造者が負担することに移っています。ですからそういう観点から、ベネフィット/ロスの和をどの時点で考えるか、誰の負担とするかは一意的には決まりません。
「こういう話をするときりも限りないのですが、もう少し話すと、かっては垂れ流しで良かったものが時代と共に内部化・・・要するに製造者が負担することに移っています。ですからそういう観点から、ベネフィット/ロスの和をどの時点で考えるか、誰の負担とするかは一意的には決まりません。
それからいくら総合的に有益な環境影響が大きかろうと、有害な環境影響を少なくする、あるいは管理することは必須です。ISO的に言えば、環境影響を管理することはできないから、発生源である環境側面を管理しなければならないということです」
![]() 「ある時期は有益が大きくても、状況が変わる、例えば代替品の登場とか危険性が知られたとかあると、人の評価が有益から有害になるということか」
「ある時期は有益が大きくても、状況が変わる、例えば代替品の登場とか危険性が知られたとかあると、人の評価が有益から有害になるということか」
![]() 「そうです。もっともそんなことは、自然環境から見たら全く無意味でしょうね。環境影響が有害とか有益と言うのも、神学論争に思えます。
「そうです。もっともそんなことは、自然環境から見たら全く無意味でしょうね。環境影響が有害とか有益と言うのも、神学論争に思えます。
騒音を考えたとして、人間に害があるとか動物が子どもを産まなくなったとか言われます。しかしそんな結果が起きても、地球規模で考えれば誤差と言うか、さざ波みたいなものでしょう。
どこかの偉い人がガイヤ理論
だから地球のためとか、環境のためと言うのを禁じるべきです。いや、恥じなくちゃならない。人間そこまで傲慢になってはいけません。今の環境保護は、人間が暮らしやすい環境を維持するというのが本音ですよね。
私たちは、つつましく控えめであるべきです」
![]() 「ちょっと待ってください。
「ちょっと待ってください。
自然界に存在するもので、生態系に悪影響を与えるものはないよね。生態系に悪影響を与えるのはすべて人間が作ったものだ」
![]() 「須藤さん、冗談を言わないでくださいよ。いつからエセ環境保護者になったのですか。
「須藤さん、冗談を言わないでくださいよ。いつからエセ環境保護者になったのですか。
自然に存在して生態系に悪影響を与える、生物を殺すものって、たくさんありますよ。自然由来の重金属被害、ガスによる被害など枚挙にいとまがありません。
例えば川が重金属や酸性物質を溶かして動植物に被害を出すのがありますね。
| ||||||||||||||||||||||||||||
あるいは地中からラドンガスが発生している地域はたくさんあります
![]() 「山口さんがおっしゃることは、環境保護など無意味と言うことよ」
「山口さんがおっしゃることは、環境保護など無意味と言うことよ」
![]() 「正鵠をついてきますね。実際そうだと思います。
「正鵠をついてきますね。実際そうだと思います。
今、環境保護と言っているのは、人間保護なんです。動物愛護とか希少種の保護なんて嘘っぱちですよ。堂々と人間の暮らしやすい地球にすると言えば良いのですよ。
無意味かという問いに答えるなら、人間の暮らしにとっては立派に意味があります。動植物の保護というのは二次的でしょうね。
言っちゃうと、そもそも今、唱えられている環境保護は、白人至上主義なの。アフリカの人たち暮らし、アジアの生態系を考えているとは思えない。地球温暖化を止めろというのは、欧州が猛暑とか多雨になるから騒いでいるのです。アフリカが干ばつになっても環境保護を唱えません。
それと活動も彼らの価値観ですからね。真に環境保護かどうか分からない。
鯨を保護しようというなら、そもそもクジラを激減させたのは、
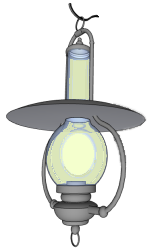 ヨーロッパ人が鯨油をランプ照明に使ったからです。
ヨーロッパ人が鯨油をランプ照明に使ったからです。
『白鯨』とか鯨取りのお話しでしょ。彼らが殺した鯨は日本人が今まで狩った数よりはるかに多いでしょう。
ペリーがなぜ日本に来たかご存じ? アメリカの捕鯨船の薪や水の補給基地が欲しかったから。開国を迫ったのはそのためです。
欧米の環境保護を真面目に考えるとバカバカしくなります。
『沈黙の春』を書いたレイチェル・カーソンが保護しようとしたのは、北アメリカ本来の自然ではなく、開拓された後の風景です。これは良く言われることです
![]() 「でも環境保護って言えば、シロクマを救え、捕鯨禁止とかいろいろあるじゃないですか。それって自然のためで、人間のためではないですよね?」
「でも環境保護って言えば、シロクマを救え、捕鯨禁止とかいろいろあるじゃないですか。それって自然のためで、人間のためではないですよね?」
![]() 「いえ、100%人間のためですよ」
「いえ、100%人間のためですよ」
![]() 「クジラを救うのは生態系の保全でしょう?」🐳
「クジラを救うのは生態系の保全でしょう?」🐳
![]() 「捕鯨禁止はホェールウォッチングが金になるからです。捕鯨をしないからクジラが増えすぎて、ペンギンが食べるオキアミを食べつくして、ペンギンが餓死しているそうですよ
「捕鯨禁止はホェールウォッチングが金になるからです。捕鯨をしないからクジラが増えすぎて、ペンギンが食べるオキアミを食べつくして、ペンギンが餓死しているそうですよ
クジラとペンギンを比較すると、ホェールウォッチングは金になるけどペンギンウォッチングは金にならないから。ペンギンなら新宿サンシャインでも葛西臨海公園でも見られますからね。
人間の健康を害するから天然痘撲滅とか、ポリオウイルス根絶、マラリア撲滅が自然保護なんですか? シロクマを救うなら天然痘やマラリアも救わないとおかしくありませんか?」
![]() 「まあ、まあ、山口さんも熱くならないで」
「まあ、まあ、山口さんも熱くならないで」
![]() 「環境側面に有害・有益を付けるなら、根源的な議論が必要と言いたかったのです。
「環境側面に有害・有益を付けるなら、根源的な議論が必要と言いたかったのです。
ISO14001の序文には人間社会の持続可能性を目指していますが、他の生物の持続可能性は書いてありません
![]() 「山口さんの主張はものごとの深淵を語っているのは分かりましたが、要約するとどうなりますか?」
「山口さんの主張はものごとの深淵を語っているのは分かりましたが、要約するとどうなりますか?」
![]() 「有益な環境側面などISO14001から逸脱した、世迷い事だということです」
「有益な環境側面などISO14001から逸脱した、世迷い事だということです」
![]() 「私もそう思います。山口さんはそれを理屈で証明できるのですね?」
「私もそう思います。山口さんはそれを理屈で証明できるのですね?」
![]() 「勿論です」
「勿論です」
![]() 「規格に書いてないからでしょう?」
「規格に書いてないからでしょう?」
![]() 「勿論それは第一義です。
「勿論それは第一義です。
でも世迷い事を論破するのは正論だけでは足りません。なにしろ相手は論理的な人たちでなく信者ですからね。
信心を変えさせるには論理的な話より、ショックを与える話とか物を見せなくては効果がありません。信じていたことが間違いだと気づかせないとダメなのです」
![]() 「そいじゃみんないろいろ言いたいだろうけど、まず山口さんが有益な環境側面がないということを説明してもらえますか?」
「そいじゃみんないろいろ言いたいだろうけど、まず山口さんが有益な環境側面がないということを説明してもらえますか?」
・
・
・
・
 山口はホワイトボードを転がして、皆が座っている机の脇まで持って来る。
山口はホワイトボードを転がして、皆が座っている机の脇まで持って来る。
それからスラスラと文字を書いていく。
具体論は次回を待て!
ここまで6,000字、ここで真面目に書き続けると15,000字くらい行ってしまう。
次回に気を持たせるのは、連続ドラマの鉄則と最近学んだ。
![]() 本日の小話
本日の小話
今回はなぜ日本で「有益な環境側面」が普及したのかという小話で締めます。
題しまして「流れ着いた先が有益な環境側面」であります。もちろん創作ですよ、
名前が似ているとか、〇〇先生とは△△さんのことだろうなんてコメントは禁止
では、始まり、始まり
某所で名のあるISO審査員でありコンサルもしている西東さんが、講演していた。
![]() 西東先生
西東先生
「皆さん、ISO14001は環境側面に始まり環境側面で終わると言っても過言ではありません。環境側面を把握することは極めて重要です。
環境側面を把握しなさいと申しますと、どこの会社でも必死に探しますね。
使用エネルギー、廃棄物、製品、公害関係などはまず忘れません。その他に事務用品、名刺の古紙配合率、ゼムクリップの使用数、PPC枚数、トナー使用量など、一生懸命に調べています。
しかし有害な環境影響をもたらすものは頭に浮かびますが、有益な環境影響をもたらすものはついつい漏れてしまうものです。
有益な環境影響をもたらすと言いますと、当然ですが製品もありますしサービスも有益な環境影響を私たちに与えてくれます」
![]() 会社員A
会社員A
「先生、有益な環境側面を忘れるなということですね?」
![]() 「いや有益な環境側面でなく有益な環境影響です」
「いや有益な環境側面でなく有益な環境影響です」
![]() 会社員A
会社員A
「分かりました、有益な環境側面を忘れるなと」
![]() 「いや・・・(違うけど、まあ、いいか)」
「いや・・・(違うけど、まあ、いいか)」
どこかの会社の一室
![]() 会社員A
会社員A
「この前、西東先生が環境側面を特定するとき、有益な環境側面を忘れるなと語った。それをきいてなるほどと思った」
![]() 会社員B
会社員B
「そうか、大事なことを教えてもらってありがとう。
それじゃ、ウチでは環境側面一覧表に有益か有害かの欄を作って、どちらかに〇印をつけることにしよう」
少し後、会社員Bの事業所の審査
![]() 審査員A
審査員A
「御社では有益な環境影響を忘れないように有益か有害かのチェックを入れていますが、有益な環境側面なんてありましたか?」
![]() 会社員B
会社員B
「実を言いまして西東先生が講演でお話しされたのですよ。
環境側面には有害と有益がある。有益な環境側面を忘れないようにって、
それで当社は環境側面一覧表に 有害・有益 の欄を追加してどちらに該当するかチェックをいれています。有益な環境側面がたくさんあるでしょう」
![]() 「ほう、西東先生が! (それじゃ有益な環境側面なんてないと言うとまずい、褒めておこう)」
「ほう、西東先生が! (それじゃ有益な環境側面なんてないと言うとまずい、褒めておこう)」
どこかの認証機関の一室
![]() 審査員B
審査員B
「西東先生、先生のおっしゃる有益な環境側面はスバラシイで発想ですね。どこに審査に行っても採用されています。もう有益な環境側面を忘れることはないでしょう」
![]() 西東先生
西東先生
「本当は有益な環境影響なのだが」
![]() 審査員B
審査員B
「正直言って環境側面と環境影響の関係なんて誰も理解してませんよ。有益な環境側面で良いのです。
それに環境影響より環境側面の方が言いやすいでしょう」
![]() 西東先生
西東先生
「そうだね」
(なんだか有益な環境側面ってとても良いアイデアだったようだ)
どこかの会社の審査である。
![]() 審査員C
審査員C
「御社では有益な環境側面というものを把握していないのですか?」
![]() 会社員C
会社員C
「有益な環境側面? そんなの規格にありましたっけ?」
![]() 審査員C
審査員C
「今はそれを把握しないとダメになりました。これは重大な不適合です」
![]() 会社員C
会社員C
「ええええーーー」
どこかの認証機関の一室
![]() 出版社の人
出版社の人
「西東先生のお書きになった『有益な環境側面の捉え方』ものすごく売れてますよ。もうこれが日本のISOのスタンダードです」
![]() 西東先生
西東先生
「ワハハハハ(ISO規格になくても、バカな連中が喜んでいるなら結構なことだ。ワシにもお金がザクザク)」
有益な環境側面を本に書いた、売れた、儲かった。
有益な環境側面について講演をすると人が集まった。
有益な環境側面の有無を見るだけで不適合を出せる。審査が楽だ
結果として
ISO14001に取り組む人はどんどん規格から外れて、全く別物の宗教の信者となり果てた。環境は少しも良くならず、有益な環境側面を書いた本は資源を浪費し、無駄な仕事が環境管理従事者の仕事を阻害し、ISO14001の意図である「遵法と汚染の予防」は遠くなるばかり。
そしてISO認証はバカバカしいものに堕ちた。
それが今である。めでたしめでたしと言うべきなのか?
いつか「会社をよくする審査」についても批判を書く。
「ISOは会社をよくする」と騙っている人たち、必読である。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
カネミ油症事件とは、1968年10月、西日本を中心に広く発生した食中毒事件である。カネミ倉庫社製の米ぬか油に熱媒体(熱を伝える流体)として使われていたかカネクロール(PCBの一種の商品名)が混入して、このPCBが吹き出物、色素沈着、目ヤニ、倦怠感、しびれ、食欲不振を起こした。そう被害者数は14,000人と言われる。 米ぬか油を摂取したことによる死亡者は公表されていない。 | |
| 注2 |
1970年代、製造メーカーであるカネボウがPCBの焼却処理をしたと読んだことがある。 | |
| 注3 |
イギリスの科学者ジェームズ・ラブロックによって唱えられた「地球全体をひとつの生命体ととらえて、すべての生物、非生物が相互に作用して地球環境を維持しているという考え方」 はっきり言って科学というより宗教としか思えない。 | |
| 注4 |
ラドンガスは花崗岩から発生する。花崗岩は酸性火成岩でシリコンが主成分で、ウランやトリウムといった元素が濃縮されている。ウラン238が崩壊することでラジウム226となりラドン222となる。 ラドンはガスだから地上に出てくるが、空気に対する比重は7.73と極めて重く、地表に滞留する。 | |
| 注5 |
「ラドンとは?家庭で発見されたこの危険なガスについて学ぶ」 | |
| 注6 |
「間違いだらけのエコ生活」、池田清彦、MdN新書、2020 | |
| 注7 |
「ペンギンが激減、クジラの増加も一因か」 | |
| 注8 |
持続可能の定義は確立したものはなく、環境と開発に関する世界委員会の1987年のブルントラント報告書で、持続可能な開発とは「将来の世代が彼らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発」とした。以降これが使われている。 将来の世代将来の世代も現在の世代も、人間以外とは思えない。もちろん「彼らのニーズ」には、人間の望む生態系の中の生物の生存も含まれるだろう。それは本来のというか現状の生態系とは違う、害虫や見た目の悪い生き物のいない世界ではないだろうか? |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |