��1�F���̕���̓t�B�N�V�����ł��B�o�ꂷ��l����c�͎̂��݂�����̂ƈ�؊W����܂���B
�A��ISO�K�i�̉��߂ƈ��p������@�ߖ��Ƃ��̓��e�͂��ׂĎ����ł��B
��2�F�^�C���X���b�vISO�Ƃ�
��3�F���̂��b�͉��N�ɂ��n�邽�߂ɁA������ɂ������ƔN�\�����܂����B
ISO��
2010�N���A�̑�Ȃ�ISO14001�̐鋳�t�ł��鎛�c ������́A�^���̍u����Łu�L�v�Ȋ����ʂ͂Ȃ��v�ƌ�����B����Ō��������͂����B���������ꂩ��15�N���o���������A�L�v�Ȋ����ʂƌ��ISO�W�҂͑��݂���
| �����搶 | |
 |
|
| �L�v�Ȋ��� �ʂ͂���̂� |
�Ђ���Ƃ��Đ^�ʖڂɍl���Ă���Ɏ������̂��Ƃ���A���x���Ⴍ�ċ~���͂Ȃ��B
���Ȃ݂ɃC�M���X�ł��A�����J�ł��A�u�L�v�Ȋ����ʁv�Ȃ�ďn��͎g���Ă��Ȃ��B�R���Ǝv���Ȃ�Google�f������ł�Chatgpt�f�ꂳ��ł������Ă݂āB�i�����ɂ�google-US����UK�����g�����Ɓj
�������L�[���[�h��Beneficial environmental aspects�Ƃ�Positive environmental aspects�Ƃ���̂���B
�q�b�g����̂�99%�����{�����B�p��������ɂ͂��邪�A����URL��ccTLD�́ujp�v�ł���
���₢��A���c���ے肵���̂�����A�킴�킴���ׂ�܂ł��Ȃ��B
��
��
��
��102�b�̑���
��ISO������Łu�L�v�Ȋ����ʁv�Ɋւ���v�����R���ɓo�ꂵ�A�L�Q�E�L�v�m�ɂ��Ȃ��ƕs�K���ƂȂ鎖�ԂƂȂ��Ă���Ɩ���N���ꂽ�B
 �����o�[���炢�낢��ӌ����o�����A�`�F�A�}���̓c������R���ɁA�܂��L�v�Ȋ����ʂ��K�v�Ƃ����咣���ԈႢ�ł��邱�Ƃ�������Ăق����Ƌ��߂�ꂽ�B
�����o�[���炢�낢��ӌ����o�����A�`�F�A�}���̓c������R���ɁA�܂��L�v�Ȋ����ʂ��K�v�Ƃ����咣���ԈႢ�ł��邱�Ƃ�������Ăق����Ƌ��߂�ꂽ�B
�R���̓z���C�g�{�[�h�̑O�ɗ����Đ������n�߂�B
![]() �u�܂����t�ɂ��Ăł����A�����ʂƊ��e���ɂ��čĊm�F���܂��傤�B
�u�܂����t�ɂ��Ăł����A�����ʂƊ��e���ɂ��čĊm�F���܂��傤�B
�����ʂ�
�u���Ƒ��݂ɉe��������A�g�D�̊����A���i���̓T�[�r�X�̗v�f
Element of an organization's activities, products or services that can interact with the environment.(ISO14001:1996 ��`3.3)�v�ƒ�`����Ă��܂��B
�܂����e����
�u�L�Q���L�v�����킸�A�S�̓I�ɖ��͕����I�ɑg�D�̊����A���i���̓T�[�r�X���琶����A���ɑ��邠����ω�
Any change to the environment, whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting from an organization's activities, products or services.(ISO14001:1996 ��`3.4)�v
�ƒ�`����Ă��܂��B
�����ł͂����肳���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B����͊����ʂƂ͌����ł���A���e���͌��ʂł��B�����������Ɋ����ʂ́w�g�D�̊����A���i���̓T�[�r�X�̗v�f�x�ł���܂��B
�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA���e���̌������ׂĂ������ʂł͂Ȃ��v
![]() �u���݂܂���A������Ɨ������E�E�E
�u���݂܂���A������Ɨ������E�E�E
�����ʂ͌����ł���ˁv
![]() �u��̓I�ɍH��ŏd�����g���Ă��āA�d���^���N����d���R��āA���ꂪ�����͐�ɗ������Ĕ_�Y���␅�Y���ɔ�Q���o�����Ƃ��܂��傤�B
�u��̓I�ɍH��ŏd�����g���Ă��āA�d���^���N����d���R��āA���ꂪ�����͐�ɗ������Ĕ_�Y���␅�Y���ɔ�Q���o�����Ƃ��܂��傤�B
���̂Ƃ����e���͎Y���␅�Y�������ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B���������̌����͉����H �ƌ����A�܂�����ǂ��Ă����A�d�����͐�ɗ����������ƁA�d�����^���N��z�ǂ���R�k�������ƁA�R�k���������Ƃ��Ă͔z�ǔj���A�^���N�̕��H�A����̌�肩������Ȃ��A����ɂ����̂ڂ�Ώd�����g�p���Ă������ƂƂ������܂��B
�����݂͂ȏd���ɂ��_�Y���␅�Y�����������������ƌ����܂��v
| �d���̎g�p | �d���^���N �d���z�� |
�z�ǔj�� �^���N���H ������ |
�d���̘R�k | �d���̉͐� ���� |
�_�Y���␅ �Y���̔�Q |
|||||
| �E�L�̌��� | �E�L�̌��� | �E�L�̌��� | �E�L�̌��� | |||||||
| ������ | ������ | ���e�� | ||||||||
![]() �u���������Ή����̂悤�ɁA���Ȃ肱���������邼�v
�u���������Ή����̂悤�ɁA���Ȃ肱���������邼�v
![]() �u�܂��A���Ƃ��b�ł�����B
�u�܂��A���Ƃ��b�ł�����B
���ׂČ����������Č��ʂ�����܂��B�����������ƂȂ���̂͂��ׂĊ����ʂł��傤���H
�d�����g�p���邱�ƁA�d���^���N��d���̔z�ǂ͊ԈႢ�Ȃ������ʂł��傤�B
�������z�ǂ̕��H�Ƃ��{�����̌P���Ƃ��͊����ʂł͂Ȃ��B����͊����ʂɑ���菇�쐬��P���ł���킯�ł��B
�܂��R�ꂽ�d���������͐�ɗ��������Ƃ��A�d���R��͊����ʂł͂���܂���B����͉����̒��ڂ̌�����������܂��A�����ɂ���Ă����炳�ꂽ�ł����Ċ����ʂł͂Ȃ��v
![]() �u������܂����B���̂ɂ��d���R��́w�g�D�̊����A���i���̓T�[�r�X�̗v�f�x�ɊY�����Ȃ��ƁB
�u������܂����B���̂ɂ��d���R��́w�g�D�̊����A���i���̓T�[�r�X�̗v�f�x�ɊY�����Ȃ��ƁB
���e���̌������ׂĂ������ʂł͂Ȃ��̂ł��ˁv
![]() �u�����Ċ��e���͊g���h���ɘa���邵���Ȃ��B�Ǘ��͂ł��Ȃ��B�����炻�̌����ł�������ʂ��Ǘ�����̂�ISO14001�̍l���ł�
�u�����Ċ��e���͊g���h���ɘa���邵���Ȃ��B�Ǘ��͂ł��Ȃ��B�����炻�̌����ł�������ʂ��Ǘ�����̂�ISO14001�̍l���ł�
�d���R�k�̑������Ƃ��āA�d���^���N��������ΏC���Ƃ��X�V�A�z�ǂȂ�_�����@�̌������A�^�]����Ȃ�菇�̌������A�S���҂̋���P���Ȃǂ���ł��傤���A�R�k�������Ƃ͊����ʂł͂���܂���B
�܂�������Ċm�F���Ă��������āA�ł͖{��ɓ���܂��B
�L�v�Ȋ����ʂƂ������t�́A�K�i�{���ɂ��A�A�l�b�N�X�ɂ��AISO14004�ɂ�����܂���B
�L�v�Ȋ��e���Ƃ������t�͋K�i�{���ɂ͂Ȃ��A��`�ɂ��邾���ł��B
�w���e���͗L�v�Ȃ��̂ƗL�Q�Ȃ��̂����� (ISO14001:1996 ��`3.4)�x�Ƃ���܂��B
���̕��͂���ł́A�����ʂ���L�Q�Ȋ��e�������A���邢�͗L�v�Ȋ��e�������o�Ȃ��̂��A����Ƃ��L�Q�ȉe�����L�v�ȉe�����o��̂��͓ǂݎ��܂���B
���̑O�ɁA�L�v�Ƃ��L�Q�Ƃ́A�N�̎��_�Ō��Ă̂��Ƃ��Ƃ����^�������܂��v
![]()
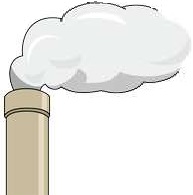 �u�L�v�Ƃ��L�Q���đ��ΓI�Ȃ��̂���Ȃ����ˁA��̓I�Ȃ��̂�ˁB
�u�L�v�Ƃ��L�Q���đ��ΓI�Ȃ��̂���Ȃ����ˁA��̓I�Ȃ��̂�ˁB
�Ⴆ�Δ��o�͒N�ɂƂ��Ă��L�Q�ł���B��ЂɂƂ��Ă��ߗZ���ɂƂ��Ă��A��ʎЉ�猩�Ă��v
![]() �u���o�͂Ƃ������A�Ζ��̎g�p�͗L�Q�Ȃ̂��L�v�Ȃ̂��l����Ƃǂ��ł��傤�H�v
�u���o�͂Ƃ������A�Ζ��̎g�p�͗L�Q�Ȃ̂��L�v�Ȃ̂��l����Ƃǂ��ł��傤�H�v
![]() �u�����̌@�ɂ����鎑���͊��A�g�p����CO2�����A�������f�����Ƃ��A�N�ɂƂ��Ă��������Ƃ����ˁv
�u�����̌@�ɂ����鎑���͊��A�g�p����CO2�����A�������f�����Ƃ��A�N�ɂƂ��Ă��������Ƃ����ˁv
![]() �u�����ł��傤���H 1960�N��܂ő����̍H��ł́A�ΒY�ŏ��C���������g�[�����肵�Ă��܂����B
�u�����ł��傤���H 1960�N��܂ő����̍H��ł́A�ΒY�ŏ��C���������g�[�����肵�Ă��܂����B
���ꂪ�A�����������ΒY���e�ՂŎg�p���֗��A���o���o�Ȃ��A�R�k���o�Ȃ�
���̌�A�X�ɏd������d�C�ւ̓]�����s��ꂽ�킯�ł��B�֗�������ł��B
�Ƃ������Ƃŏd�����L�Q�Ȃ��̂��Ƃ������z�͎��삪�����ł��v
![]() �u�������A�L�v���L�Q�Ƃ����͔̂�r�̖��Ȃ̂ł��ˁv
�u�������A�L�v���L�Q�Ƃ����͔̂�r�̖��Ȃ̂ł��ˁv
![]() �u���������������������悤�ɁA�w�N���猩�āx�Ƃ����ϓ_�ɂ����܂��B�ߗZ���Ȃ̂��A�l�ޑS�̂Ȃ̂��A�l�ԈȊO�̓��A�����猩�ĂƂ��A����ɂ���ĈقȂ�܂��v
�u���������������������悤�ɁA�w�N���猩�āx�Ƃ����ϓ_�ɂ����܂��B�ߗZ���Ȃ̂��A�l�ޑS�̂Ȃ̂��A�l�ԈȊO�̓��A�����猩�ĂƂ��A����ɂ���ĈقȂ�܂��v
![]() �u����͎��������Ă���B���A�n�����g���Ȃ�đ����ł��邯�ǁA����͌��ݒn���̔e���������Ă���l�Ԃ��猩�Ăł��傤�B�������D�݂̐������ɂƂ��ẮA������̊g��ł����烉�b�L�[�ł��傤�B���ɓ�m�̓��A�����k�サ�Ă���ƕ���Ă���v
�u����͎��������Ă���B���A�n�����g���Ȃ�đ����ł��邯�ǁA����͌��ݒn���̔e���������Ă���l�Ԃ��猩�Ăł��傤�B�������D�݂̐������ɂƂ��ẮA������̊g��ł����烉�b�L�[�ł��傤�B���ɓ�m�̓��A�����k�サ�Ă���ƕ���Ă���v

���F�q�A�������߂Ƃ���Q����ւ��邢�͔M�т̐A���̕s�@����(?)���悭����Ă���B���̂����T�\���Ȃǂ������ė���̂��낤�B
�������łȂ��A�C�ł��M�ы��̖k�オ����Ă���B
![]() �u�����������n����̐������̂قƂ�ǂ��߂�D�C�������ɂƂ��āA�_�f�̑��݂͒��d�v�ł��B�ł��_�f�̓V�A�m�o�N�e���A�����o�������̂ł����āA����ȑO�̌��C���������s�E�����킯���B
�u�����������n����̐������̂قƂ�ǂ��߂�D�C�������ɂƂ��āA�_�f�̑��݂͒��d�v�ł��B�ł��_�f�̓V�A�m�o�N�e���A�����o�������̂ł����āA����ȑO�̌��C���������s�E�����킯���B
�_�f�Z�x���Ⴍ�Ȃ����猙�C���������Ăєe��������Ƃ��������ŁA�n���ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��ǂ����Ƃł��ˁB�����łȂ��ƌ����Ȃ�A�V�A�m�o�N�e���A�����������Ƃ��A�K�C���Ȃ�_�l���Ȃɂ������͂��ł��v
���F���͊��ی�Ƃ��n���������x��l�������A�V�A�m�o�N�e���A���_�f������B���s�E�������ƂɎv������Ȃ��̂��s�v�c���B
���C���������n���̑�C��ς��悤�Ƃ����Ƃ��A�l�Ԃ͂���Ɛ키���낤�B���̐킢�͐��`�̐킢�Ȃ̂��H ����Ƃ����C�������Ƃ̐��������Ȃ̂��H
�����l����ƁA�K�C�����_�Ȃǂ��ق炵���ĕ����Ɋ����Ȃ��B
![]() �u�ƂȂ�ƗL�v�Ƃ��L�Q�Ƃ́A�ǂ��������ƂȂ�ł��傤�H�v
�u�ƂȂ�ƗL�v�Ƃ��L�Q�Ƃ́A�ǂ��������ƂȂ�ł��傤�H�v
![]() �u���V�ɂ͕������ȁv
�u���V�ɂ͕������ȁv
![]() �u�L�Q�̌���́wadverse�x�ʼnp�p���T�������ƁA
�u�L�Q�̌���́wadverse�x�ʼnp�p���T�������ƁA
�@�@�ړI����ʂɕs���Ƃ��}���I
�@�A���v��~���ɍR��
�@�B�D�܂����Ȃ�
�Ȃǂ��o�Ă��܂��B
���{��́w�L�Q�x�̈Ӗ�����Ȃ��A�D�܂����Ȃ��Ƌq�ϓI�Ƃ�������ςɎv���܂��B���l�ɗL�v�́wbeneficial�x�Łw���v��^����A�𗧂x�Ƃ����Ӗ��ł��B���R�A�N�ɖ𗧂������ł��ˁB
���͐l�Ԋ�Ǝ��܂����B
�K�i�̕��͂ł͒N�ɂƂ��āw�L�Q���L�v�x�������ĂȂ����ǁA�P��̈Ӗ�����͏������l���邢�͓ǂސl�A�v����l�Ԏ�̂ɍl���Ă���悤�Ɏv���܂��B�ł����炱���ɂ͐��Ԍn�ł͂Ȃ��u�l�Ԃ��邢�͐l�ԎЉ�v������ƍl����B
���R�Ƃ��āA���Ԍn���l����A������̂ɂƂ��ėL�v�Ȃ��̂͑��̂��̂ɂƂ��ėL�Q�Ƃ����͔̂��ɑ����B
�L�v�Ƃ��L�Q�Ƃ����̂́A�l�Ԃ����Ă͂��߂Đ��藧�T�O�ł��B���R�E�ɂƂ��ē�_���Y�f�������悤���A�I�]���w�������悤���A�C���ʂ��㏸���悤���A�ǂ��ł��������Ƃł͂���܂��B�I�]���w���̂��̂̓V�A�m�o�N�e���A����������̂ł��B
ISO14001�́w����Ɖ����̗\�h�x�ł��B�����璘���������ʂ��Ǘ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B����Ɉّ��͂Ȃ��B
�������Ȃ��H�Ƃ����A��͂�w��X�l�ނɂƂ��ėǂ����R���ێ����邱�Ƃ��ړI�x�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��v
![]() �u������̂ɗL�v�Ȃ��̂́A�ʂ̂��̂ɗL�Q�Ȃ��Ƃ�����Ƃ������Ⴂ�܂������ǁA������ƐM�����܂���B��̗�͂���܂����H�v
�u������̂ɗL�v�Ȃ��̂́A�ʂ̂��̂ɗL�Q�Ȃ��Ƃ�����Ƃ������Ⴂ�܂������ǁA������ƐM�����܂���B��̗�͂���܂����H�v
![]() �u�����ł��ˁE�E�E���q�͔��d�����v���`���Ă��������B�����Ƃ����Ă��P�ɔM�G�l���M�[��d�C�ɕς��邾���ł��B�M�����͍����ƒቷ�̍��Ō��܂�܂��B�ቷ�̕��͒Ⴂ�����ǂ��̂Ő��C�̐����g���܂��B
�u�����ł��ˁE�E�E���q�͔��d�����v���`���Ă��������B�����Ƃ����Ă��P�ɔM�G�l���M�[��d�C�ɕς��邾���ł��B�M�����͍����ƒቷ�̍��Ō��܂�܂��B�ቷ�̕��͒Ⴂ�����ǂ��̂Ő��C�̐����g���܂��B
��������ς���ƔM����C�ɕ��o���܂��B���̂��߉͐쐅��C���̐������Ǐ��I�ɏ㏸���܂��B�����̌����ł͂��̉��x�㏸��7���ȓ��Ƃ��Ă��܂����A7���͂��̂������傫��
 |
�T�P�ɂƂ��ėL�Q��������Ȃ����A�M�т̋��Ƃ��T���S�ɂƂ��Ă͗L�v�ƌ�����ł��傤�ˁv
![]() �u����͐l�ԂɂƂ��Čo�ϓI�ɗL�Q�Ƃ������Ƃ��v
�u����͐l�ԂɂƂ��Čo�ϓI�ɗL�Q�Ƃ������Ƃ��v
![]()
 �u�C�������オ��X�p���]�[�g�E�n���C�A���Y�̂悤�ȉ����łȂ��A���O�Ƀn���C�≫��̊C�����܂��ˁB��������ΗL�v�Ȋ����ʊԈႢ�Ȃ��A�A�n�n
�u�C�������オ��X�p���]�[�g�E�n���C�A���Y�̂悤�ȉ����łȂ��A���O�Ƀn���C�≫��̊C�����܂��ˁB��������ΗL�v�Ȋ����ʊԈႢ�Ȃ��A�A�n�n
���Ǝ҂Ɗό��q�ɂƂ��ẮA�L�v�ł��ˁB���Ǝ҂��猩��ΗL�Q�ł��傤���ǁv
�E
�E
�E
�E
![]() �u�ł͗L�v�Ȋ����ʂ�����ƌ���Ă���l�����́A�ǂ�Ȃ��̂�L�v�Ȋ����ʂƂ��Ă��邩�H
�u�ł͗L�v�Ȋ����ʂ�����ƌ���Ă���l�����́A�ǂ�Ȃ��̂�L�v�Ȋ����ʂƂ��Ă��邩�H
ISO�W�̏��ЁA���G���A�E�F�u�T�C�g�ŗᎦ����Ă������̂����Ă݂܂��傤�v
| �敪 | ���� |
|
�d���̘R�k �L�Q���w�����̎g�p �s�@���� �p���� ���i�E�ޗ��̗A�� |
|
| �L�v�Ȋ����� |
�C���o�[�^�E�G�A�R���̗p �p���i�̃��T�C�N���V�X�e���̍\�z ���B�����̒Z�k ���T�C�N���ނ̎g�p �ᑛ���E��U���̐ݔ��ւ̍X�V ��������A���ʔr��(�[���G�~�b�V������ڎw��) �O���[���w�����i(���ɔz���������[�J�[����w��) �ʂ����̗p ESG���� ����Q�Ԃւ̐�ւ��i�f�B�[�[���Ԕp�~�j ���z�����i�ɏd�_��u�����c�� ���M�d������u�����d���ւ̌��� |
���F��\��2025�N8��8����Google�Łu�L�v�Ȋ����ʁv�Ō������ăq�b�g�������ŁA�Ӗ��������������̂����グ���B
�L�v�Ȋ����ʂƂ�����ŁA
�Ⴆ�A�p���������ϑ���̏��@���m�F�i�@�̋`�����j�A�s�Ǎ팸�i�H�j�A�p�������荂���ł����T�C�N������i��j
![]() �u�I�C�I�C�A������Ƒ҂Ă�B�R������A���̕\�̓z���g�ł����H�v
�u�I�C�I�C�A������Ƒ҂Ă�B�R������A���̕\�̓z���g�ł����H�v
![]() �u�{���A�{���A�f�ʂł���v
�u�{���A�{���A�f�ʂł���v
![]() �u�܂��s�@�������L�Q�Ȋ����ʂƂ͈�����k�ł��傤�B�s�@�����͔ƍ߂ł���B�_�����n�`�����`��
�u�܂��s�@�������L�Q�Ȋ����ʂƂ͈�����k�ł��傤�B�s�@�����͔ƍ߂ł���B�_�����n�`�����`��
���蓾�Ȃ��Ǝv���܂����A�s�@�������������ʂɂ��Ă�����A���܂����H�v
![]() �u���������Ƃ��Ȃ��ȁB���������ɂ����A����͏�k���H �h�f�l
�u���������Ƃ��Ȃ��ȁB���������ɂ����A����͏�k���H �h�f�l
![]() �u����Ȃ�@������ĕs�@�������Ȃ��̂͗L�v�Ȋ����ʂ���A�p�������o���̂��L�v�Ȋ����ʂɂȂ��Ă��܂��v
�u����Ȃ�@������ĕs�@�������Ȃ��̂͗L�v�Ȋ����ʂ���A�p�������o���̂��L�v�Ȋ����ʂɂȂ��Ă��܂��v
![]() �u���i�A�����L�Q�Ȋ����ʂȂ�A��������ď���҂ɓn���ȂƂ������Ƃ��A�o�J�o�J�����v
�u���i�A�����L�Q�Ȋ����ʂȂ�A��������ď���҂ɓn���ȂƂ������Ƃ��A�o�J�o�J�����v
![]() �u�L�Q�Ȋ����ʂɂ����ꂽ���A�L�v�Ȋ����ʂɂ����ꂽ���B
�u�L�Q�Ȋ����ʂɂ����ꂽ���A�L�v�Ȋ����ʂɂ����ꂽ���B
�L�v�Ȋ����ʂƂ��Ă�����̂͂��ׂāA�����ʂł͂Ȃ������P�����ł͂Ȃ��̂��v
![]() �u�����ƁA�C���o�[�^�[�E�G�A�R���̗p�A���T�C�N���E�V�X�e���\�z�c�c���ׂĊ����ʂłȂ����P�������ˁv
�u�����ƁA�C���o�[�^�[�E�G�A�R���̗p�A���T�C�N���E�V�X�e���\�z�c�c���ׂĊ����ʂłȂ����P�������ˁv
![]() �u���P�����Ȃ�Ƃ������A���T�C�N���ނ̎g�p�Ȃ�āA�^�Ɋ��z���ɂȂ�̂������ׂ��傫���Ȃ邩������Ȃ�
�u���P�����Ȃ�Ƃ������A���T�C�N���ނ̎g�p�Ȃ�āA�^�Ɋ��z���ɂȂ�̂������ׂ��傫���Ȃ邩������Ȃ�
���̂Ƃ����삪�����ɓ����Ă����B
�����̋��ɂ������֎q�ɍ����ĊF�̘b���Ă���B

|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() �u���̃��T�C�N���ނ̎g�p�ɂ��Ă������ʂł͂Ȃ��ˁv
�u���̃��T�C�N���ނ̎g�p�ɂ��Ă������ʂł͂Ȃ��ˁv
![]() �u�O���[���w�����i�Ƃ�ESG�����Ȃ�A�L�v�Ȋ����ʂƌ����Ă悢������v
�u�O���[���w�����i�Ƃ�ESG�����Ȃ�A�L�v�Ȋ����ʂƌ����Ă悢������v
![]() �u�܂����̓�͊����ʂȂ̂ł��傤���H
�u�܂����̓�͊����ʂȂ̂ł��傤���H
�O���[���w���Ƃ͍w���ɂ����āA�]�����QCD(�i���E�R�X�g�E�[��)�̑���E(���z��)��D�荞��ōw�����邱�Ƃł��B
���B�Ƃ����@�\�͊����ʂł���ƌ�����ł��傤�B���������̕]����Ɋ��z�����v���X���邱�Ƃ������ʂ��ƌ����A�Ⴄ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���v
![]() �u�Ȃ�قǁA���B�͊����ʂ��A������Ƒ҂Ă�A�F����̂Ƃ���Œ��B�������������ʂɎ��グ�Ă���Ƃ���͂���܂����H�v
�u�Ȃ�قǁA���B�͊����ʂ��A������Ƒ҂Ă�A�F����̂Ƃ���Œ��B�������������ʂɎ��グ�Ă���Ƃ���͂���܂����H�v
![]() �u���[��A�E�`�ł͎��グ�Ă��Ȃ��ȁv
�u���[��A�E�`�ł͎��グ�Ă��Ȃ��ȁv
![]() �u���B�Ƃ����͎̂��ޒ��B���傾�����s�����̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�u���B�Ƃ����͎̂��ޒ��B���傾�����s�����̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�v���d�l�����߂��炻��������Ȃ��B�����璲�B�i�̎g�p�����߂�ߒ��ɂ����āA���z��������A�����ׂ���������Ƃ������Ƃ���Ȃ��ł����H
�v�������ʂƂ��Ă��Ȃ��Ƃ���͂Ȃ��ł��傤�B������v���傶��Ȃ��āA�v�Ƃ����@�\�������ʂł��傤�v
![]() �u�����������������邩������܂��A���͈Ⴄ�ϓ_�Ő��������Ǝv���B
�u�����������������邩������܂��A���͈Ⴄ�ϓ_�Ő��������Ǝv���B
�e�Ђ��O���[�����B�𐄐i����O���[�����B�Ƃ������t�͎g���Ȃ��Ȃ�܂��ˁB�����Ă��ꂪ
![]() �u�Ȃ�قǁA����������Ƃ��̒ʂ肾�B�O���[�����B�Ȃ�āA���ɊS�����܂����Ƃ��̈ꎞ�I�Ȃ��̂Ȃ̂��ˁv
�u�Ȃ�قǁA����������Ƃ��̒ʂ肾�B�O���[�����B�Ȃ�āA���ɊS�����܂����Ƃ��̈ꎞ�I�Ȃ��̂Ȃ̂��ˁv
![]() �uESG�����Ȃ�ԈႢ�Ȃ��L�v�Ȋ����ʂł���ˁv
�uESG�����Ȃ�ԈႢ�Ȃ��L�v�Ȋ����ʂł���ˁv
![]() �uESG�����ƂȂ�ƁA���z�����̂��̂����[�]���f�[�g�����낤�Ȃ��`�v
�uESG�����ƂȂ�ƁA���z�����̂��̂����[�]���f�[�g�����낤�Ȃ��`�v
![]() �u���삳��A�ǂ��ł��傤�AESG�����͗L�v�Ȋ����ʂƌ����܂����H�v
�u���삳��A�ǂ��ł��傤�AESG�����͗L�v�Ȋ����ʂƌ����܂����H�v
![]() �u�r���������o���čς݂܂���B���܂ɊF����̊���������ȂƎv���܂��āB
�u�r���������o���čς݂܂���B���܂ɊF����̊���������ȂƎv���܂��āB
������ESG�����ł����B���͕ی���ЂƂ��،���Ђ̌������Ƃ���w�̐搶�Ȃ��A�ǂ̂悤�Ȃ��̂�ESG�����ƌ�����̂��A���̕]�����ǂ����邩�A�����Ƃ̎^���������邩�Ȃ�Ă̂��������Ă���Ƃ���ł���
���̗\���ł����A����10�N�͊|���������ł��܂�L�܂�Ȃ��ł��傤�B���A���~���j�A���J���ڕW���������ŁA�̑���2000�N�ł��傤�B���̒���ESG���������グ����Ǝv���܂��B�ł��t�@���h�Ȃǂ���̓I�ɂȂ�̂�2010�N�ȍ~�ł��傤�ˁv
![]() �u���ꂶ��A2010�N������������͐L�т�Ƃ������ƁH�v
�u���ꂶ��A2010�N������������͐L�т�Ƃ������ƁH�v
![]() �u�L�т܂���B���͊��͗��s�ł�����B���������ƕt���Ύ�ł��傤�B2020�N���܂ł͔{�X�Q�[���ł��傤�B
�u�L�т܂���B���͊��͗��s�ł�����B���������ƕt���Ύ�ł��傤�B2020�N���܂ł͔{�X�Q�[���ł��傤�B
���������ɂ�������r�W�l�X�������āA�O���[���E�H�b�V��(���������̊��ی�Ƃ����Ӗ�)�ƌ�����悤�ɂȂ�܂��B���ɗǂ��Ƃ������ׂ�������Ə̂�����̂��^�ɂ����Ȃ̂�������܂��B�����đ��������������̊��ی�Ɣ������A���ʂƂ��Ċ��ی��ESG���������ɂȂ��Ă��܂��̂ł��v
![]() �u�܂��ɖ��������Ă����悤�ł��ˁv
�u�܂��ɖ��������Ă����悤�ł��ˁv
![]() �u���̏�̃e�[�}�ł���L�v�Ȋ����ʂ������ł����A���̒��Ŋ��z���Ƃ��A�����גጸ��搂��Ă�����̂̐^���͂ǂ��Ȃ̂��ƌ������Ɩʔ����ł��傤�ˁB
�u���̏�̃e�[�}�ł���L�v�Ȋ����ʂ������ł����A���̒��Ŋ��z���Ƃ��A�����גጸ��搂��Ă�����̂̐^���͂ǂ��Ȃ̂��ƌ������Ɩʔ����ł��傤�ˁB
���Ȃ肪���\�A���邢�͋�_�ƃo�����Ȃ��ł���
![]() �u���_�Ƃ���ESG�����̓|�V����̂ł����H�v
�u���_�Ƃ���ESG�����̓|�V����̂ł����H�v
![]() �u�����܂ł͂ǂ��ł����ˁA�������Ă͂₳���̂��ꎞ�ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��v
�u�����܂ł͂ǂ��ł����ˁA�������Ă͂₳���̂��ꎞ�ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��v
![]() �u���삳��̌����Ăł́A�L�v�Ȋ����ʂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����H�v
�u���삳��̌����Ăł́A�L�v�Ȋ����ʂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����H�v
![]() �u�ǂ�Ȋ����ʂ����āA�L�v�Ȋ��e�����L�Q�Ȋ��e���������Ă��܂��B���������ESG�����Ȃ�L�v�Ȋ��e�������Ȃ��Ǝv���Ă�������ł��傤�H�v
�u�ǂ�Ȋ����ʂ����āA�L�v�Ȋ��e�����L�Q�Ȋ��e���������Ă��܂��B���������ESG�����Ȃ�L�v�Ȋ��e�������Ȃ��Ǝv���Ă�������ł��傤�H�v
![]() �u�L�Q�Ȋ��e�����v�������Ȃ���v
�u�L�Q�Ȋ��e�����v�������Ȃ���v
![]() �u����z�����������Ƃ����Ă��A���ꂪ���`���Ɩ����ƁA�f��ł�����̂ł͂���܂���B
�u����z�����������Ƃ����Ă��A���ꂪ���`���Ɩ����ƁA�f��ł�����̂ł͂���܂���B
�Ⴆ�Đ��\�G�l���M�[�Ƃ��ĕ��͔��d�Ƃ����z�����d�����邱�Ƃ́A��K�͂Ȏ��R�j��ɂȂ�܂��B����͂��������s�v�ł��傤�B
���R�ۑS�ƌ����Ă��A���̎��R��ی삵�悤�Ƃ���̂��A�l���Ă݂�ΐ��`�Ȃǂ���܂���B���R�ۑS�ƌ����܂����A���R�Ƃ������i�͍]�ˎ���ɂ͂���܂���B�ߐ��̐l�Ԃ���������ɂ����܂���
���捻�u�́A�����Ă����Ƒ����ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���͑��������Ȃ��悤�ɏ������Ă��܂��B1950�N��͔_�n�����悤�Ƃ��Ă����̂ɂˁB���ɂ���̂����`�Ȃ̂��A���������`�Ȃ̂��A�ǂ����ł��傤���H
�����ɂȂ�̂����`�ł����H
���t�@���h�͂ǂ��ɓ���������ǂ��̂��Y�݂܂��ˁB���ۂɂ͗ǂ���Ǝv���ē����������Ƃɂ���āA����肪�N���ĉE����������̂ł͂Ȃ��ł����H
����͔���ł͂���܂����B
�C���^�[�l�b�g�̍v���Ől�̈ړ�����������������Ȃ����ǁAGoogle�����ł͏펞300��kW�A����3��̓d�͂�����Ă��܂��B���R�n�����g���̌��ł��ˁB
����قǂ̓d�͂������C���^�[�l�b�g�̑��݂��ǂ��l���܂����H
�����������Ƃ́A�����ɐ��������Ƃ��Ȃ��A�ԈႢ���Ȃ��Ǝv���܂��v
![]() �u�ł�Google�Ђ͂��̂��ׂĂ��A�Đ��\�G�l���M�[�Řd���Ă�����Ĕ��\������v
�u�ł�Google�Ђ͂��̂��ׂĂ��A�Đ��\�G�l���M�[�Řd���Ă�����Ĕ��\������v
![]() �u���d�Ԃ݂͂�ȂȂ����Ă��܂���B������čĐ��\�ȓd�C���A���ʂ̉Δ���苣���͂��ア�����t���Ă���Ӗ��ł����Ȃ��ł���
�u���d�Ԃ݂͂�ȂȂ����Ă��܂���B������čĐ��\�ȓd�C���A���ʂ̉Δ���苣���͂��ア�����t���Ă���Ӗ��ł����Ȃ��ł���
![]() �u�܂��܂��A��قǏ��т��������ȁA�O���[�����B�͂����ɋƖ��̒��Ɏ�荞�܂�āA���ʂȂ��Ƃ���Ȃ��Ȃ�Ƃ������b������܂����ˁB
�u�܂��܂��A��قǏ��т��������ȁA�O���[�����B�͂����ɋƖ��̒��Ɏ�荞�܂�āA���ʂȂ��Ƃ���Ȃ��Ȃ�Ƃ������b������܂����ˁB
ESG���������ʂ̓����̑I������̈�Ɏ�荞�܂�āAESG�����Ȃ�ČĂ�Ȃ��Ȃ�ł��傤�ˁv
![]() �u���Ⴀ�A���삳��͗L�v�Ȋ����ʂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����H�v
�u���Ⴀ�A���삳��͗L�v�Ȋ����ʂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����H�v
![]() �u���܂ł̘b�̗����m��܂���A�g���`���J���Ȃ��Ƃ��������炲�߂�Ȃ����B
�u���܂ł̘b�̗����m��܂���A�g���`���J���Ȃ��Ƃ��������炲�߂�Ȃ����B
���������L�v�Ȋ����ʂ������Ă���l�������A�v���`���Ă�����̂͂��낢��ł��B���m�Ȓ�`������܂���B
�ꕔ�̐l�����́A�L�v�Ȋ����ʂƗL�Q�Ȋ����ʂ������ƐM���Ă��܂��B���Ɍ��킹��Ƃ��ׂĂ̊����ʂ̊��e���͗L�v���L�Q������ƍl���Ă��܂��B���ׂĂ̊����ʂ͗L�v�ƗL�Q�̊��e�����o���Ă���A�L�v�Ȋ��e�����̂Ă������Ƃ������K�v�ł��邩��g���Ă���킯�ł��B
�ꕔ�̐l�����́A�L�Q�ƗL�v�̊��e���𑍍����ėL�v���傫����ΗL�v�Ȋ������Ƃ��Ă��܂��B���\���܂������A���ׂĂ̊����ʂ͗L�v�Ȋ��e���ƗL�Q�Ȋ��e���������A�L�v���傫������̗p���Ă���킯�ł��B�ł����炱�̘_���͈Ӗ����Ȃ��ƌ����܂��B
�����ЂƂA���ꂪ�命�����߂Ă��܂����A�����팸������L�v�Ȋ������ƍl���Ă���Ƃ������Ƃł��B
�����ISO14001����������ǂ߂Ƃ��������悤������܂���v
�p�`�p�`�Ɣ��肷�鉹������B���̕�������Ɠc����![]() ���肵�Ă���B
���肵�Ă���B
![]() �u���������삳��͌�肫���Ă܂��ˁB
�u���������삳��͌�肫���Ă܂��ˁB
�Ȃ��Ȃ����������Ȃ����̂ł���B
�b�͂��������ꂽ�ł��傤���ǁA�ŋ߁A�L�v�Ȋ����ʂ��K�v�Ƃ����R�����������Ă���̂ł��B���������F�̌Ղ̊�������Ă����Ƃ��́A����Ȕ��z���v�������܂���ł����B
���A���̃����o�[�̉�Ђ�֘A��ЂŁA����ɂ܂��g���u�����N���Ă��܂��B
�ǂ��������̂��ƁE�E�E�v
![]() �u��ԊȒP�ȕ��@�́A�L�v�Ȋ����ʂ��Ȃ��ƕs�K���Ƃ����F�؋@�ւ���A����ւ����邱�Ƃł��B
�u��ԊȒP�ȕ��@�́A�L�v�Ȋ����ʂ��Ȃ��ƕs�K���Ƃ����F�؋@�ւ���A����ւ����邱�Ƃł��B
�K���A�E�`�̋ƊE�c�̂̎Y�Ɗ��F�؋@�ւ͗L�v�Ȋ����ʂ�K�v�Ƃ��Ă��Ȃ��v
![]() �u���삳���������肢�ł��ˁB���������͍��삳�A�L�v�Ȋ����ʂ�����Ȃ�Č������狖���A�Ƌ����������炶��Ȃ��ł����v
�u���삳���������肢�ł��ˁB���������͍��삳�A�L�v�Ȋ����ʂ�����Ȃ�Č������狖���A�Ƌ����������炶��Ȃ��ł����v
![]() �u�����Ȃ�Č���Ȃ��ł��������B���ؒ��J�ɐ������܂�����v
�u�����Ȃ�Č���Ȃ��ł��������B���ؒ��J�ɐ������܂�����v
![]() �u�Y�Ɗ��F�؋@�ֈȊO�ł��A�O���n�̑����͗L�v�Ȋ����ʂ�����Ȃ�Č����Ă��Ȃ��B������ւ��邩�����A�����ɂ͏o���҂Ƃ��o�����Ă�����ŊȒP�ł͂Ȃ��v
�u�Y�Ɗ��F�؋@�ֈȊO�ł��A�O���n�̑����͗L�v�Ȋ����ʂ�����Ȃ�Č����Ă��Ȃ��B������ւ��邩�����A�����ɂ͏o���҂Ƃ��o�����Ă�����ŊȒP�ł͂Ȃ��v
![]() �u�L�v�Ȋ����ʂ�v�����Ȃ��F�؋@�ւ́w�L�v�Ȋ����ʂȂ�ĂȂ��x�ƌ����Ă��ꂽ�炢���̂Ɂv
�u�L�v�Ȋ����ʂ�v�����Ȃ��F�؋@�ւ́w�L�v�Ȋ����ʂȂ�ĂȂ��x�ƌ����Ă��ꂽ�炢���̂Ɂv
![]() �u�����͑�l�̎���Ȃ낤�B�m��ǁv
�u�����͑�l�̎���Ȃ낤�B�m��ǁv
![]() �u�^�����ɑΉ�����Ȃ�A�L�v�Ȋ����ʂ��Ȃ��ĕs�K���ƌ���ꂽ��A�ًc��\�����ĂāA�����Řb�������Ƃ�������Ĕ[�������邱�Ƃł��ˁv
�u�^�����ɑΉ�����Ȃ�A�L�v�Ȋ����ʂ��Ȃ��ĕs�K���ƌ���ꂽ��A�ًc��\�����ĂāA�����Řb�������Ƃ�������Ĕ[�������邱�Ƃł��ˁv
![]() �u�\���Ȃ��Ă������S��������R��������������A���ꂪ��ԍ���ȁv
�u�\���Ȃ��Ă������S��������R��������������A���ꂪ��ԍ���ȁv
![]() �u�����ɂ��Ă��郁���o�[�́A�F�Г��ł�ISO�̌��ЂƎv���Ă���̂ł��傤�B�撣��Ȃ����ȁv
�u�����ɂ��Ă��郁���o�[�́A�F�Г��ł�ISO�̌��ЂƎv���Ă���̂ł��傤�B�撣��Ȃ����ȁv
![]() �@�{���̂��f��
�@�{���̂��f��
���f�肵�Ă������A���͗L�v�Ȋ����ʂ�����ƌ�邱�Ƃ��ւ���Ƃ���������Ƃ����C�͂��炳��Ȃ��B���{�����@�͌��_�̎��R��ۏႵ�Ă���A������������Ă��邱�Ƃ͖����Ȏ����ł���B
���̃E�F�u�ł́AISO�ɂ��Č���Ă���̂ł����āA����ISO14001�Œ�`����u�����ʁv�ɂ����āA�L�v�ȑ��ʂ͂Ȃ����Ƃ��咣���Ă��邱�Ƃm�ɂ��Ă����B
�����āA�X�Ɂu�L�v�ȑ��ʂ�����v�Ǝ咣���Ă��A���͂���������Ĕ�����͂��Ȃ��B��w�̍u�`�̒��ŁA�u���ɂ����ėL�v�ȑ��ʂ��l�����ق����A��ƂɂƂ��Ă͗L�v�ł��낤�v�ƌ�邱�Ƃ͎��R�ł���B���̏ꍇ�A���ʂƂ������t�̒�`���肩�łȂ��̂ŁA���������Ɩ���N���鍪���͂Ȃ��B
�������AISO�R���̏�ɂ����āA�u�L�v�ȑ��ʂ��Ȃ��̂ŕs�K���ł���v�Ƃ��u���肳�ꂽ�����ʂ��L�v���L�Q����ʂ���Ă��Ȃ��̂ŕs�K���v�ȂǂƂ�����������ƁA���Ɍ������B���悤�Ȃ��̂͒f�łƂ��ċ������Ƃ��ł��Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ炻���ISO17021�ɔ����Ă��邵�A�R���_��ɂ������Ă��邩�炾�B
�܂����R���_�ɁA�u�R���ɓ������ĐR������ISO�K�i�Ɋ�Â����A�l�̎�ςɂ���ĐR�����s���܂��v�Ȃ�ď����Ă���F�؋@�ւ͂Ȃ����낤�B
���͗L�v�ȑ��ʂ�M����R������A���̌ٗp�҂ł���F�؋@�ւɑ��N�ɂ킽��ꂵ�߂��Ă����B
�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��v�ȂǂƁA�Q�ڂ������Ƃ������Ă͂����Ȃ��B
�Y���ȁA�L�v�ȑ��ʂ͗L�Q�Ȃ̂��B
| �����O�̘b | ���̘b���� | �ڎ� |
�Q�l����
���T�C�g�̉ߋ��̃R���e���c
�E�L�v�Ȋ����ʂ͕s�łł���
�E�L�v�ȑ��ʂ͗L�v�ł���
�E���R�ی���ĂȂɂ�A�L�v�Ȋ��e�����ĂȂɂ�
| ��1 |
7��8�����_�AGoogle�Łu�L�v�Ȋ����ʁv�Ō�������ƁA0.53�b��177�����q�b�g�����B | |
| ��2 |
�uccTLD�v�Ƃ́ACountry Code Top Level Domain�̗��ŁAURL�̖����̍��ʃg�b�v���x���h���C���̂��ƁB �A�����J�̓C���^�[�l�b�g���˂̍��Ȃ̂ŕt���Ȃ��̂��������Aus�ƌ��܂��Ă���B�B���{�Ȃǂ͕t���Ă��邪�A���{�W�▯�Ԋ�Ƃ͂��Ȃ��̂������B | |
| ��3 |
�������d���̎g�p������p�����͏o��B���o���o�O�t�B���^�[�ł�߂��邵�A�r�K�X�̒��a���u�ŗ��_�J���V�E���Ȃǂ̉��ނ��n�߉��D�����������B | |
| ��4 |
�k�C���̊C�����͉�15�`20���A�~3�`8�����炢�A����͉�28�`29���A�~20�����x�ł���B �����̂��̊C�͉���̊C���B | |
| ��5 |
�܂�����ISO���W�Ȃ����A�Ǒf�l�Ƃ́u�ǁv�͉����痈���̂��s�v�c�Ɏv�����B���W���Ƃ��p��Ȃǂ��炩�Ǝv������A����R���łȂ������ȓ��{��̐ړ����ŁA�u�ǐ^�v�u�Ǔc�Ɂv�u�Lj����v�Ƃ����悤�ɁA��������Ӗ������邻�����B ����ȕ��������Ă��Ă����ɂȂ���̂��B ���łɌ����A���̑O�ɂ���u���������ɂ����v�Ƃ́u�厖�Ȃ��Ƃ������������w�I�\���v�������ł��B | |
| ��6 |
���� ���═�c�M�F�Ȃǂ�20���I����A���T�C�N�����K�����������ׂ�������킯�ł͂Ȃ��Ǝ咣���Ă���B�Ȃ��A���̓�l�͌����̒��炵���B | |
| ��7 |
���͎��͖^�ی���Ђ�ESG�����̘_���������ăh�N�^�[�ɂȂ�A��w�����ɂȂ����l��m���Ă���B���≽�x����������Ƃ����邾�����B 2010�N����ESG�����Ȃ烏�V�ɕ����ƌ��ŕ�����Ă������A2020�N�ɂȂ�Ƒ�w�ł�ESG�����Ȃljߋ��̂��́B���g�������悤���B | |
| ��8 |
ESG�����̍Ő�����2020�N�O��ŁA2025�N�̍��A���s�͊��ɏI������B 2018�`2019�N�͉��Ă�ESG�������}�������B ������2020�N�R���i���s�ɂ�蕂�������̂ł͂Ȃ���Ƃ̎����\�����d�v�������B 2022�N�ȍ~�̓C���t���E���V�A�̓V�R�K�X������~�ȂǃG�l���M�[��@�A�E�N���C�i�푈�ɂ��G�l���M�[���S�ۏ�ȂNj����̉��l�ς̓������d�v�ƂȂ�AESG�����͎~�܂����B | |
| ��9 |
�l�ł��@�l�ł����ɗǂ��ƐM���č����d�C���͍̂D���ɂ���Ηǂ��B �����������̓d�C��̖��ׂ����Ăق����B�u�ăG�l���d���ۋ��v�Ƃ������ڂ�����A�d�C���11%���炢���Z����Ă���͂����B����͑��z�����d���Ă���ƒ�ւ̔z���邨���ł���B���̂��Ƃ͂Ȃ��A���z�����d�����Ă�ƒ�̐ݔ�����X���������Ă��邾�����B | |
| ��10 |
�u���R�Ƃ̋����Ƃ����E�\�v�A�����h��A�˓`�АV���A2009 |
����800�̖ڎ��ɖ߂�
�^�C���X���b�vISO�̖ڎ��ɖ߂�
     |
 �g�{
�g�{ �{��
�{�� �R��
�R�� ���
���