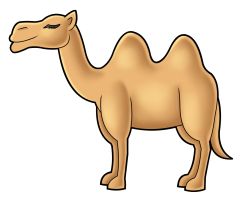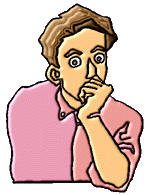注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
田中は4月末、連休前に、ISOの月刊誌「ISO認証」の編集長の押田に話を持ち掛けた。
ISO14001の審査で、規格要求事項ない要求を追加する審査員、認証機関が絶えない。
 |
|
| 田中です |
押田は「論理が通っていて誹謗中傷でなければ」掲載することはやぶさかではないと答えた。
但し、掲載されても世の中への影響力はあまりない、というか読者が本気で読んでいないのではないかという弱気な発言であった。
そして予定に入れるから5月末までに6,000字にまとめてほしい。社内で検討してOKなら6月末発売の7月号に掲載するという。
2月号に小林氏が寄稿(第100話)したときは9,000字という指定だったが、最近はコンテンツも盛りだくさんになり、3ページでなく2ページが定位置になったという。
ということで田中氏渾身の論説である。
なお「ISO認証」誌の連載カラム「俺にも言わせろ」は、トップバッター小林の後、他の人々の投稿を載せて回を重ねており、田中は第6回目になる。
|
俺にも言わせろ その6「有益とは何か」 ISO14001の審査が始まってから1年半が経ち、審査する側もされる側も、規格を理解し、審査の応答もすっかり慣れたように思う。しかし今でもそんな規格解釈で良いのかと、疑問に思うものも散見される。 今回はそれについて思うことを書く。ご意見、反論を期待する。 まず「環境」とは何か? ISO14001:1996では「環境」を「大気、水質、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの(定義3.2)」と定義している。 これを読むと人間関係も含むようで、それならセクハラ・パワハラも含むように思える そうなのだろうか? ISO14001:1996の定義の原文は Surroundings in which an organization operates, including air, water, natural resources, flora, fauna, humans, and their interrelation この文章を読んで、人間関係も含むと思えるか? 英英辞典を見ると、Environmentで人間関係を示す場合は、work environment(職場環境)とかpsychosocial environment(心理社会的環境)のように、形容詞を付けるのが普通だ。Environmentのみでは、人間同士の相互関係を意味せず、外部環境と人間の関りと解するようだ。 ISO 14001でいう環境は人間関係ではなく、自然環境を通じて人や社会に影響するものに限定されると考えるべきだろう。人間と人間の関係はこの文章の範囲外で、パワハラ・セクハラはISO14001の対象外だ。 こんなことを考えたのは、某審査員が「ISO14001は人間関係も良くしますよ」と語ったからだ。ISO14001認証企業でセクハラが起きれば、 そんなことを考えると、常識だとか、分かっていると、軽く流していたものでも、考え直す必要がありそうだ。 次に「有益」を考えてみよう。 定義3.4で「環境影響」とは「有害か有益を問わず(中略)環境に対するあらゆる変化」とある。 ここで「有害か有益かを問わず」とはどういう意味だろう? 有害とは何に対してなのか? どういう基準で有害となのか? 考えたことがありますか? 「そんなことは当たり前だ。有害とは環境に有害なことだ」とおっしゃる人は多いだろう。環境に有害とは、果たしてどういうことなのか? ISO14001を認証しようとすると、認証しようとする組織の環境側面を洗い出し、その重要性を評価して著しい環境側面とそうでないものに分ける作業がある。このとき環境影響が有益であっても有害であっても、閾値は組織が決めた基準以上のものを著しい環境側面とする。 多くの企業は有害な環境影響を、使用あるいはインプットとして重油使用・電気使用・水使用などを挙げ、排出(アウトプット)としては、排ガス・騒音・振動・排水、廃棄物などを挙げているだろう。 このとき有害とは何者が被害を受けているのか? 「自然環境」と答える人が大多数だと思う。だが、私はそうではなく「人間社会」だと考える。 そもそも地球は人間のために存在しているわけではない。 地球は約46億年前、宇宙を漂うガスやチリが集まり、太陽の誕生に伴って形成された微惑星が衝突・合体を繰り返して岩石の球体が誕生した。  原始的な地球は高温でマグマの海に覆われていたが、冷却するにつれて水蒸気が雨となり、約40億年前に海が形成された。
原始的な地球は高温でマグマの海に覆われていたが、冷却するにつれて水蒸気が雨となり、約40億年前に海が形成された。そして約38億年前には最初の生命が誕生したが、そのときの大気は水蒸気、二酸化炭素、窒素であった 地球は生物のためのものではないし、もちろん人間のための存在でもない。前述したように全くの自然現象で出来上がり、全くの偶然で生物が発生し、それが進化して人間は意識を持ち考えるようになったと再認識してほしい。 地球は私たちのためにあるのでもなく、私たちのものでもない。地球の環境に合わせて我々が進化したのであり、私たちが地球を壊そうと利用しようと、人間の勝手である。 そんなこと、分かり切ったことだというかもしれない。しかし私は意味のないことを書くつもりはない。こういうことをしっかり考えることは、とても重要だ。 ISO14001規格の要求を理解するには、その4,000字が一字一字どのような意味なのかを、しっかり理解しなければならない。規格の文章を、通常使われているニュアンスと思い漠然と読むだけでは、規格を理解することはできない。 なぜそういうことを語るのか、説明する。 有害な環境影響とは何かと考えたとき、多くの人は人間による自然環境への影響だと考えるだろう。 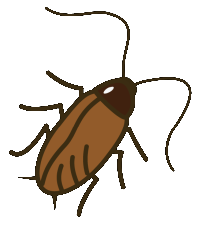 しかし地球という視点から見れば、人間の活動はゴキブリの活動と同じレベルだ。もちろん人間活動は、ゴキブリの数億倍、数兆倍の環境影響を地球に与えている。
しかし地球という視点から見れば、人間の活動はゴキブリの活動と同じレベルだ。もちろん人間活動は、ゴキブリの数億倍、数兆倍の環境影響を地球に与えている。しかし地球から見れば人間の活動がいかなるものであっても、微々たるものだ。 だって27億年前に地球の大気に酸素が現れ、最終的に20%も占めたことにより、嫌気性生物の多くは死滅した それによって地球が困ったこともない。いや長期的に見れば、いずれすべての生物は死に絶えるのだ。そうなっても地球は困らない。 じゃあ有害とは誰に対して害があるのか、有益とは誰に対して良い影響を与えるのか? そんなこと考えるまでない。影響を受けるのは人間だ。いやISO14001は人間が受ける影響しか考えていない。 序文には「持続可能」とか「環境保全」という言葉が頻出するが、すべて人間を主体に考えている。そもそも規格の意図は「遵法と汚染の予防」であり、それは人間が作ったルールを守れ、人間に害を与えるなということであり、人間中心主義なのである。 世の中考えるとおかしなことは多い。 人々は天然痘を撲滅してそれを偉大な成果と言った。天然痘による被害者をなくしたから。それは地球のためではなく、当然だが天然痘ウイルスのためでもない、人間のためだ。 人間はレッドデータブックなるものを作り、絶滅危惧種を保護しろと叫ぶのは誰のためなのか? 勿論、人間のためだ。 人は役に立つ生き物、見た目の良い生き物を救う。クジラを救うのは生態系保全とかではなく、ホェールウォッチングビジネスのためらしい。クジラ人口増加によってペンギンが飢餓になっても気にしない。 他方、人間が困る生き物を撲滅している。狂犬病を恐れてニホンオオカミを絶滅させた。その結果、食物連鎖の頂点が不在になり、 役に立つ生き物、見た目がかわいい生き物を保護し、人間に害のある生き物、見た目の悪い生物は保護しないと 見た目だけでなく、薬品の原料になるとか、見た目の良い生き物のためという場合もあるだろう、いずれにしても人間の  もちろん心の奥底からすべての生き物を尊び、人間が滅んでも生物が自然に生きることを望む人がいるかもしれない。それを実現しようとするなら鳩山由紀夫が語ったように、人間が滅ぶしかない。
もちろん心の奥底からすべての生き物を尊び、人間が滅んでも生物が自然に生きることを望む人がいるかもしれない。それを実現しようとするなら鳩山由紀夫が語ったように、人間が滅ぶしかない。それは一つの考えではあるが、ISO14001の目的ではないし、あなたも私も望むところではない。
だってあなた、危険な寄生虫やアフリカ睡眠病を人間に 地球上に登場した生物の99%以上が絶滅したと言われる。そしてまた種には寿命があり、すべての種は必ず絶滅するという説もある。あるいは進化して新しい種となる。 人間も動物だから、異種間の、また同種間の生存競争は避けられず、自然界の枠組みから逃れられない。
注:「
と考えると、有害な環境影響とは人間生存に不利益のある環境影響であり、有益な環境影響とは人間社会に利益をもたらすものなのだ。 そんなことは驚くことじゃなくて、皆、心の中では分かっている。それを上品に自然を守れと語る。本音は自分が暮らす環境を、自分が好むように維持したいのだ。 多くの企業が有害な環境影響としているものは、インプット(投入)として重油使用・電気使用・水使用など、アウトプット(排出)としては、排ガス・騒音・振動・排水、廃棄物を挙げている。 それらは暮らしに好ましくないから有害な環境影響かもしれないが、人間社会に必要であり、一概に有害だとは言えない。違いますか? 物を作るには資源(素材・部品・材料)を必要とし、製造にはエネルギーを使い、輸送にもエネルギーや梱包に資源を使う。あらゆる製品は必要だから作り使う。 ではそのために資源を使うことは有害なのか? それから有害、有益の境界は確固たるものでなく、状況、技術、知見などによって動いている。 かってフロンは不燃、無毒、安定して性能が良いという、三拍子そろった素晴らしいと評価され、「夢の化学物質」としてもてはやされた。その用途は、冷媒、エアゾールのガス、洗浄剤に使われた。ところが1974年オゾン層を破壊するとして、一夜にして有害物質となった。 今日、有益と評価しているものが、明日は有害とされることも十分ある
PCBは飛行機や軍事用途においては、一般用途で使用が禁じられてからも例外として使われていた。汚染の危険よりもその効用を考えると使う選択をしたのだ。劣化ウランも同じだろう。 ここまでの私の話をきいて、有害な環境影響は悪い、なくそうと単純には言えないと思うだろう。 資源を使うことが悪いならビジネスの拡大は悪いことになる。電気の使用も水の使用も悪いことになる。 昔は人間が作り出した環境影響は小さかったとおっしゃるか? そんなことはない。昔から人間の行為によって環境の改変は行われた。
もちろん規格を読めば、著しい環境側面を削減しろとか、なくせとは書いてない。しっかり管理せよとあるだけだ。 何と言っても、シアノバクテリアによる大気組成の改変に比べたら、核兵器であろうと地球温暖化であろうと、微々たるものだ。 話を変える。 世に怪しげなことを語る人はたくさんいる。 「ISO14001は会社を良くする」と語る人は多い。特にISOコンサルとか審査員が語る。審査件数を増やそうとしているとしか思えない。 しかしISO14001には「会社を良くする」とは書いてないし、それらしき要求事項もない。そもそもISO14001の意図は、「遵法と汚染の予防」である。平たく言えば「違反しない、事故を起こさない」ための仕組みである。 そもそも会社を良くするとは何だろう? 会社を良くするというなら、まず『良い会社』を定義しなければならない。 良い会社とはどういうものか?
「ISO認証は会社を良くする」と語る、ISOコンサル、認証機関は、どのように会社が良くなると考えているのか? 「会社を良くする」とは、何を良くするのか? その指標は何か?、まずそれをはっきりしてほしい。 次に、どういう理由でその指標が改善されるのか、理屈と証拠を示す必要がある。 ISO認証した企業はその指標が向上しているのか、その差は危険率何パーセントの検定で有意となったのか? それくらい説明してもらわないと信用ならん。 信用ならんとは、騙されませんよということだ。 「環境ISOは儲かる」 ISOコンサル、認証機関は「ISO14001はISO9001と違って、儲かります」と言う。 ISOコンサルを頼むと、開口一番、ほぼ全員がそう言うだろう。審査でも、経営者インタビューが始まると、審査員の多くがそう語る。 儲かるとは「利益が出る」あるいは「利益が増える」ということだ。彼らは、どういう理屈あるいは根拠でそういうのか? 不思議でなりません。 そもそもISO14001の意図は企業の損益改善ではない。何度も言うが「遵法と汚染の予防」、つまり違反をしない、事故を起こさないことだ。 どういう発想をすれば儲かるのか、いい加減なことを語らないで欲しい。 ISO14001のどのような活動が儲けにつながるのか、説明が欲しい。 PPC使用を10万枚削減したところで、認証の費用の1%にもならない 自分の売り物を貶してどうする! 私の望むことは、ISO認証機関やコンサルが認証を勧める際に、「環境ISOは品質ISOとは大きく違う。会社を良くし儲ける規格なのだ」などと仲人口を叩かず、真に規格の意図を伝えることだ。 それと同時に認証の意義を説明してほしい。 もっと大きな疑問がある。 審査に来る審査員のほとんどが「環境第一に考えてほしい」と語る。環境は何よりも優先するそうだ。  経営者インタビューを受ける工場長や社長は、「弊社は環境第一です」なんて、そんな怪しげなことに相槌を打つことはない。
経営者インタビューを受ける工場長や社長は、「弊社は環境第一です」なんて、そんな怪しげなことに相槌を打つことはない。むしろ環境第一とは何か? それは実行可能なのか? と問い返すべきだ。もし、利益より環境保全を優先するというなら、とっととお帰り願った方が良い。 よく「〇〇第一」という言い方がある。その発祥は、昔々、アメリカのUSスティール社ベツレヘム製鉄所である。そこでは事故が多く、スローガンを「安全第一、品質第二、生産第三」と決めたのが安全第一の起こりである だが現実の経営はそんなに単純ではない。利益第一でないのはもちろんであるが、経営は安全とか環境だけを考えれば済むわけではない。 「企業の目的は存続すること」と語ったのはドラッカーだ。存続するには利益を出さねばならないし、違法なことをしてはいけないし、従業員に辞められても困るし・・・そのためには良い品質の製品・サービスの提供、高い技術そして常なる革新、その結果として信頼性を得て企業ブランドの確立、事業推進に当たっては遵法・高い倫理の維持、環境だけでない社会的責任を全うすることが必須である。 「経営は環境第一」なんて簡単に言えるものではなく、すべて大事なのだ。 「環境第一」と語る人は、そういうことを知って言うのか、思い付きで語るのか、単なる言葉の綾なのか? ISO14001の審査では環境第一と言い、ISO9001の審査では品質第一と語るのか? 言いたいことは多々あり、今回は3部作の第1部のつもりだ。 なお、第2部は、有益な環境側面という考えはありえるのかを論じたい。 第3部は、過去からの管理とISO規格でいう環境側面との関係を論じたいと思っている。 もしこの評判が良ければ押田編集長から第2部も許可されるだろうから、ぜひ応援メールを編集部に送って欲しい。 |
![]() 本日の一言
本日の一言
私は言いたいことがたくさんある。それを小説の登場人物に託しているわけです。
でも公にするものを書こうとすると、どんどんと
まあ、言わないよりは少しでも言った方が、私自身のガス抜きにはなります。
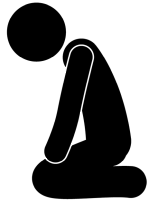 できるなら「ISOは会社を良くする」とか「ISOは儲かる」といったことを語っていた審査員たちを呼び集め、板の間に正座させて2時間ばかり問い詰めたいですね。
できるなら「ISOは会社を良くする」とか「ISOは儲かる」といったことを語っていた審査員たちを呼び集め、板の間に正座させて2時間ばかり問い詰めたいですね。
座禅のとき叩く
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
パワハラ・セクハラがこの物語の1998年に使われていたか、通用するのかと疑問があるかもしれません。 セクハラという語は1989年の男女機会均等法の改正論議で使われ始め1990年代は世の中一般で使われていました。 パワハラは2001年に岡田康子が「パワーハラスメント」と言い出して広まったと言われます。とはいえ単なる熟語ですから、それそういう言い方がなかったわけではありません。 | |
| 注2 |
・環境展望台 ・海の自然のなるほど ・田近研究室 | |
| 注3 |
好気性微生物は酸素を必要とし有機物を分解してエネルギーを得る。動物、魚類、植物などは好気性生物である。 他方、嫌気性生物とは、生育に酸素を必要としない生物で、ほとんどの嫌気性生物は細菌です。嫌気性生物は空気中で生きられず、ドブとか湖の湖底など酸素が乏しい場所に生育している。嫌気性生物は排水処理などで利用されている。 | |
| 注4 |
・「地球そして生命の誕生と進化」 | |
| 注5 |
・「地球と生命の誕生と進化ガイドブック」丸山茂徳、清水書院、2020 ・「生命と地球の歴史」丸山茂徳・磯崎行雄、岩波新書、1998 | |
| 注6 |
1998年ではないが21世紀になると、蛍光灯電球は非常に有益なものとされた。当然悪役は白熱電球だった。審査員は蛍光灯電球は素晴らしいと言えばオープニングミーティングは間に合ったのだ。良い時代だね それから10年もせずに、蛍光灯電球は悪役に堕ち、LED電球がヒーローになった。バカみたい。 | |
| 注7 |
ISO14001の効用を書いた論文に、PPC削減費用を挙げたものがCINIIに収録されていた。その論文を書いた人はドクターだった。恥ずかしいと思わないのだろうか? ISOなどを語らないで欲しい。 CINIIの収録論文は定期的に見直しがあるから、今もあるかどうかは知らない。 | |
| 注8 |
・「安全第一」には続きがあるのを知っていますか? |
外資社員様からお便りを頂きました(2025.08.28)
おばQさま 忙しさにも、暑さにも負けず、連載有難うございます。 本旨に全く関係ないツッコミ失礼します。(本旨は全面的に賛成で隙が無い) 「狂犬病を恐れてニホンオオカミを絶滅させた。その結果、食物連鎖の頂点が不在になり、カモシカ等の食害で森林が危機になっている。」 因果関係はその通りですが、森林の食害は鹿(二ホンジカ)が最大です。 当時は不明ですが、こちらに林野庁の記事があります。 https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/tyouju.html なぜ気になったかと言えば、私自身 山暮らしで鹿害にあっております。 一方でカモシカは個別に縄張りを持つが、鹿は縄張りが無く群れで自由に移動。 両方の生育地域が重なるとカモシカは駆逐されてしまいます。 記事の内容には、いつもながら感心して拝見しております。 これからもお元気でご活躍下さい。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 この件、裏を取らず思い込みで書いてしまいました。申し訳ありません。訂正いたします。 ただ調べますと、同じ林野庁でも統計データがいろいろです。別の資料では、 1位 シカ(ニホンジカ) 2位 イノシシ 3位 カラス 4位 熊 5位 サル 6位 アライグマ でネズミは選外です。 カモシカもネズミ並でした。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |