注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
「ISO認証」誌の「俺にも言わせろ」に田中が寄稿した「有益とは何か(第106話)」は、かなり評判になった。それで今まではお便りが、来ても数通だったのが急増している。
20世紀も末ともなれば、お便りはすべてeメールだ。発行部数1万弱の「ISO認証」誌でお便りが500件近く来たとは驚異なことだ。
かなり評判になったということは、そういう経験者が多く、そして疑問に感じたり、あるいは不満を持っている人が多いということだろう。
お便りを読むと、「ISO14001は会社を良くする」とか「会社が儲かる」と聞いた経営者が担当者をつかまえて、「会社を良くするのはISO担当者の役目だ」「なにがいかほど良くなるのか」というトンチンカンなことを問い、あげくに「会社が良くならないのは担当者の責任」と言われて、ノイローゼになった者もいた
ともかくISOコンサルが「ISOは儲かる」とか、審査員の「ISO14001は会社を良くする」という発言の影響は極めて大きい。
お便りを読めば読むほど、審査員よ!いい加減なことを言わないでくれという悲痛な声が聞こえる。
増子がまとめた結果は下表のようであった。
| 要旨 | 件数 | 備考 |
| 「儲かる」とか「良くなる」によくぞ反論してくれた | 240 | |
| そんなことより目の前の問題の対策を教えてほしい | 90 | |
| そんなこと考えることはない。審査員の言う通りすれば問題がない | 70 | |
| 筆者は間違っている。ISOは儲かるし、会社を良くするのだ | 30 | |
| その他 | 30 | |
| 意味不明 | 10 | 冷やかしなど★★★★ |
注:上表は調査したものではない。ISO認証の手伝いをしたときの、関係者の反応を基に作った。断じて捏造ではない。
まず、押田編集長は出版社にこれほどメールが来たことに驚いた。彼の今までの経験では、雑誌の記事ひとつにこれほど反響があったことはない。読者の多くは記事に同感しても反感を持っても、読み捨てて終わりが普通だ。
| ? | |
 |
|
| 押田編集長 |
そして増子のまとめた数値とコメントをみて、ISO認証は従業員にものすごいストレスを与えているものだと思う。それはISO規格の問題ではなく、認証制度でもなく、ISO規格やISO認証の実質を知らない人が、ISO認証に過大な期待を持つことによる弊害だと思う。
だが一番気になるのは反論である。「ある派」にはどのような考えがあるのだろう?
発信者には審査員もコンサルも企業の人もいるが、共通することがある。
せっかくISO14001を認証したなら会社が良くならなければならないという発想というか、強迫観念があるようだ。
それは考えるまでもなく「ISO認証すれば会社は良くなる」という発想と、同義というか等価ではないだろうか。
自分が思っていたことと正反対の意見には、なかなか論理だけでは納得できるものはない。だがわざわざ反論メールを送るということは、自分の立場ではそういう発想が妥当・適切だと思っていることは間違いなく、ひょっとして現実に効果を出しているのかもしれない。
ともかく同意も反論も、皆、まっとうに田中に向かい合っているのは好ましい。
押田編集長は以前、規格解釈が複数あるなら、闘論させたら面白いと言われたのを思い出した。それは吉宗機械の佐川課長だったか、いや、部下の増子だったかな?
なるほど、そういう企画もおもしろそうだ。
とはいえ・・・この決闘の挑戦を受けるものだろうか?
「ISO認証」誌に寄稿した人は、しっかり考えているだろうから、その発言を取り下げることはないだろう。だが、それに反論メールを寄こした人は、寄稿者ほど深く考えていないかもしれず、脊髄反射かもしれない。そしてメールの発言に証拠・根拠を持っていないかもしれない。
お互いが証拠に基づくか理屈を考えたものでなければ、討論してもシュプレヒコールの応酬とか駄々こねになってしまう。
・
・
・
・
押田は部屋から出て、雑居ビルのエレベーター脇にある自販機で熱い缶コーヒーを買い飲みながら自席に戻る。
 缶コーヒーを飲むと、まっとうなコーヒーを飲みたくなる。いつでもうまいコーヒーが飲める、佐川たち大会社の人たちがうらやましい。
缶コーヒーを飲むと、まっとうなコーヒーを飲みたくなる。いつでもうまいコーヒーが飲める、佐川たち大会社の人たちがうらやましい。
押田は佐川がロビーで客にコーヒーを出すたびに、カウンターで伝票に部門費のオーダーを記入しサインしているのを知らないのだ。もちろん予算オーバーになればお叱りが来る。
反論を寄せてくれた中で論理がまっとうな人に参加を求めたら何人来るだろう。1対1の闘論より、複数対複数ならチームメンバーが助け合い、打たれ強くそしてよどみなく進みそうだ。
2名対2名か、3名対3名か、そんなところだろう。片側5名もいて全員が発言したら収拾が付かない。3名対3名くらいなら、1名が沈黙しても2名対3名で論戦は進むだろう。
それと必ずしも勝ち負けをつける必要はないが、逆に完璧に勝ち負けが決まってしまったらどうなるか?
スポーツなら捲土重来となっておかしくないが、闘論で負けたらどうなのか? 氏名が雑誌に掲載されたら、後々、社内で肩身が狭いだろう。もしコンサルなら大いに仕事に支障がでる。
だが、素人と言っては悪いが、ISOTC委員でもない、審査員でもない、市井人が何を語っても正しいとは限らない。単に論理構築がまずかっただけと言い訳できる。もしISOTC委員などが討論で勝った方にいちゃもんを付けてくれるなら、雑誌としてはなお盛り上がることは間違いない。
掲載した内容が不適だと、雑誌が責任を問われることもないだろう……たぶん、
一応社長に相談しようか・・・
・
・
・
・
社長室というか、社長がいる小部屋である。
押田編集長が説明すると、間髪を入れず社長のコメントが返って来る。
![]() 「オイオイ、増子のまとめたものを読ませてもらったが、始まる前から勝敗が決まっているようだな。
「オイオイ、増子のまとめたものを読ませてもらったが、始まる前から勝敗が決まっているようだな。
討論する相手は一般人でなく審査員でないとだめだろう」
![]() 「吉宗機械の佐川課長が出てきたら、審査員でも負けますよ。現実に彼の指導を受けた連中が、不適合を出した認証機関に行って不適合を取り下げさせていますからね」
「吉宗機械の佐川課長が出てきたら、審査員でも負けますよ。現実に彼の指導を受けた連中が、不適合を出した認証機関に行って不適合を取り下げさせていますからね」
![]() 「それじゃ闘論する意味がない」
「それじゃ闘論する意味がない」
![]() 「確かにそうですが、今回の田中氏の記事は審査の間違いを指摘して、反論者はそれを間違いでないと反論しているわけです。見解が違うのですから討論する意味はあります」
「確かにそうですが、今回の田中氏の記事は審査の間違いを指摘して、反論者はそれを間違いでないと反論しているわけです。見解が違うのですから討論する意味はあります」
![]() 「風車に突っ込むドンキホーテだな。
「風車に突っ込むドンキホーテだな。
とはいえ『会社が儲かる』が認証機関の考えなら、それなりの理由か根拠はあるのだろうな?」
![]() 「思い当たるのは、認証ビジネスほど提供するサービスが同一という業種はないでしょうね。単に同一になってしまうというのではなく同一でないとならないルールであり仕組みなのです。
「思い当たるのは、認証ビジネスほど提供するサービスが同一という業種はないでしょうね。単に同一になってしまうというのではなく同一でないとならないルールであり仕組みなのです。

例えば税理士なら、税に関するサービスは同じでしょうけど、それに止まらず、最近ではISO認証のコンサルもしている人がいます。事業拡大か、あるいは顧客サービスですかね。
税理士の業務以外のサービスを、有償無償に関わらず顧客に提供しても法的に問題ありません。
でも審査員が審査で税理士の代わりはできませんね。能力的なことではありません。審査においてアドバイスしてはいけないってguide62に書いてあります
どこも同じサービスなら審査料金だけの競争になってしまいます。ですからISO審査において、どのように付加価値を付けるかが難関です。ならば審査で会社を良くするとかいう言い方になるのは仕方ないかもしれません」
![]() 「他社に差別化するには、儲かるとか会社を良くすると言わないとダメか?
「他社に差別化するには、儲かるとか会社を良くすると言わないとダメか?
そうではないだろう。会社を良くするという前に良い審査をするべきだろう」
![]() 「良い審査とは何ですか?」
「良い審査とは何ですか?」
![]() 「セオリー通りさ、ISOMS規格を自家薬籠のものとし、guide62に基づいて行う審査だろうね。もちろん審査員は冷静で礼儀正しいことだ」
「セオリー通りさ、ISOMS規格を自家薬籠のものとし、guide62に基づいて行う審査だろうね。もちろん審査員は冷静で礼儀正しいことだ」
![]() 「それって良い審査じゃなくて、当たり前のことですよね。
「それって良い審査じゃなくて、当たり前のことですよね。
ISOMS規格を理解せず、guide62を知らず、すぐに頭に血が上り、ビジネス敬語を使えないのでは審査員になれませんよ」
![]() 「現実に規格を理解せず、審査のルールを知らず、灰皿投げたり怒鳴ったり、相手には敬語を使わず、自分は先生と呼ばれないと返事をしないのがいるそうじゃないか、アハハハ」
「現実に規格を理解せず、審査のルールを知らず、灰皿投げたり怒鳴ったり、相手には敬語を使わず、自分は先生と呼ばれないと返事をしないのがいるそうじゃないか、アハハハ」
![]() 「まあ〜、そういう話も聞いています。最低レベルを担保するのが必須ですね」
「まあ〜、そういう話も聞いています。最低レベルを担保するのが必須ですね」
![]() 「おまえ、必須どころじゃなくて、そうでなければ審査員になれないはずだぞ。そうでないのが存在することは、仕組みに欠陥があるのだ。
「おまえ、必須どころじゃなくて、そうでなければ審査員になれないはずだぞ。そうでないのが存在することは、仕組みに欠陥があるのだ。
しかし手合い違いでも討論すると、ゴングが鳴った瞬間にノックアウトされたんじゃ試合になっても記事にはならんな。
ならば最初は自由討論させて、後でそれをうまくまとめるか。場合によっては一方が指導する形になっても仕方あるまい」
*
*
*
押田編集長は社長と話したことをまとめると、吉宗機械の佐川に会うアポイントをとる。
ということで数日後の吉宗機械のロビー階にある小会議室である。
訪問者は押田編集長、対応者は佐川と山口である。
![]() 「弊社のISO認証誌の7月号に、田中さんが有益と有害について書いたでしょう。大反響がありました。彼に同意の声も多かったですが、反論も多く喧々諤々です。
「弊社のISO認証誌の7月号に、田中さんが有益と有害について書いたでしょう。大反響がありました。彼に同意の声も多かったですが、反論も多く喧々諤々です。
社長の指示で、ISOは会社を良くするか、ISOは儲かるのかについて討論会をやることになりました」
![]() 「そりゃ過激ですね、でも面白そうだ、アハハハ」
「そりゃ過激ですね、でも面白そうだ、アハハハ」
![]() 「闘論の結果、勝ち負けがついても良いのでしょうか?」
「闘論の結果、勝ち負けがついても良いのでしょうか?」
![]() 「そこが問題なのですよ。それで社長は、ディベートのルールでやれと言います」
「そこが問題なのですよ。それで社長は、ディベートのルールでやれと言います」
![]() 「ディベートだって勝ち負けはありますよ
「ディベートだって勝ち負けはありますよ
![]() 「ウチの社長はなかなかのアイデアマンなのですよ。社長は、勝ち負けはテーマの正誤、真偽ではなく、ディベート技量の勝ち負けだと言います。
「ウチの社長はなかなかのアイデアマンなのですよ。社長は、勝ち負けはテーマの正誤、真偽ではなく、ディベート技量の勝ち負けだと言います。
更に『ISOは儲かる』とか『ISOは会社を良くする』の肯定側を、田中さんや山口さんにしてもらえば良いというのです」
![]() 「それじゃ・・・私が『ある』と主張するなら、その論理にボロがあっても、『ある派』はつっこまずに負けを選べば『あること』になってしまいますよ」
「それじゃ・・・私が『ある』と主張するなら、その論理にボロがあっても、『ある派』はつっこまずに負けを選べば『あること』になってしまいますよ」
![]() 「そうかあ〜、社長は、お互いに勝つために最善を尽くすはずだという発想なのですよ」
「そうかあ〜、社長は、お互いに勝つために最善を尽くすはずだという発想なのですよ」
![]() 「それならこうしたらどうでしょう。最初は我々が否定側に立ちます。たぶん『ある派』を否定にできます。相手が同意しなくても、ディベートなら審判を置くのでしょうから。
「それならこうしたらどうでしょう。最初は我々が否定側に立ちます。たぶん『ある派』を否定にできます。相手が同意しなくても、ディベートなら審判を置くのでしょうから。
その次のテーマで攻守交替して、我々が肯定側になります」
![]() 「そうすると、どうなりますか?」
「そうすると、どうなりますか?」
![]() 「一回目で負けたら、二回目は内容に関わらず勝つために最善を尽くすんじゃないですかね。肯定・否定に関わらず一勝一敗なら恨みっこなし、笑って終われますよ」
「一回目で負けたら、二回目は内容に関わらず勝つために最善を尽くすんじゃないですかね。肯定・否定に関わらず一勝一敗なら恨みっこなし、笑って終われますよ」
![]() 「なーるほど、納得しました。
「なーるほど、納得しました。
それからディベートには審判が必要ですが、佐川さんじゃ立ち位置が明白ですから、どなたか適任者がいませんかね?」
![]() 「立ち位置から大学の先生とかが、良いでしょうね。とはいえISOに関わりない論理的な先生が確保できるかどうか?」
「立ち位置から大学の先生とかが、良いでしょうね。とはいえISOに関わりない論理的な先生が確保できるかどうか?」
![]() 「大学の先生の中にはISO審査員をしているとか、審査員研修機関で講師をしている人もいますね。
「大学の先生の中にはISO審査員をしているとか、審査員研修機関で講師をしている人もいますね。
そういうISOに関係ある教授とかではダメなのですか?」
![]() 「そういう先生方は、ISO至上主義が多い。そうでなくても認証機関の幹部とかに知り合いが多いから、正論を語って火中の栗を拾うことをしないでしょう」
「そういう先生方は、ISO至上主義が多い。そうでなくても認証機関の幹部とかに知り合いが多いから、正論を語って火中の栗を拾うことをしないでしょう」
![]() 「勝敗の判定は主張の内容ではなくディベートとしての勝敗ですよね?」
「勝敗の判定は主張の内容ではなくディベートとしての勝敗ですよね?」
![]() 「そのつもりです。真の勝敗判定はISO誌の読者にお任せです。
「そのつもりです。真の勝敗判定はISO誌の読者にお任せです。
でも認証機関の幹部となると、自社の過去の審査結果を否定できず、また言葉尻を捕らえられるのも嫌うでしょう。ビジネスを考えると、審判の依頼を受けるかどうか」

![]() 「日系の認証機関ならそうかもしれませんが、外資系ならしがらみに気を使わないのと違いますか」
「日系の認証機関ならそうかもしれませんが、外資系ならしがらみに気を使わないのと違いますか」
![]() 「当てがありますか?」
「当てがありますか?」
![]() 「B〇〇社のハワードGMなら、喜んでやってくれると思いますよ。彼はISO認証が劣化するのを恐れていますから。
「B〇〇社のハワードGMなら、喜んでやってくれると思いますよ。彼はISO認証が劣化するのを恐れていますから。
彼はISO14001ができる前からBS7750の審査をしています。日本で権威とみなされているかはともかく、日本の審査員の誰よりも審査経験があり、日本語も流暢で話も上手い。
彼にいちゃもん付ける勇気がある審査員や認証機関はないでしょう」
![]() 「なるほど、彼とは二度ほど会ったことがあります。おっと一度はここの会議室でしたね。
「なるほど、彼とは二度ほど会ったことがあります。おっと一度はここの会議室でしたね。
謝礼はどれくらいになりますかね?」
![]() 「話してみないと分かりませんが、B〇〇社の宣伝にもなりますし、電車賃だけでOKするんじゃないですか?」
「話してみないと分かりませんが、B〇〇社の宣伝にもなりますし、電車賃だけでOKするんじゃないですか?」
![]() 「どうせやるなら学生時代のノリで、一泊泊まりで・・・そうですね、例えば弊社の保養施設で伊豆高原とか那須の温泉とかで、前日は攻守の打ち合わせと懇親会をして、翌日テーマ二つについてディベートの実施とかどうですか?」
「どうせやるなら学生時代のノリで、一泊泊まりで・・・そうですね、例えば弊社の保養施設で伊豆高原とか那須の温泉とかで、前日は攻守の打ち合わせと懇親会をして、翌日テーマ二つについてディベートの実施とかどうですか?」
![]() 「なるほど〜、『ある派』の方も数名になるでしょう。見知らぬ同士でしょうから、前日は打ち合わせもあるでしょうし、酒を飲んで親睦を深めるのは良いですね」
「なるほど〜、『ある派』の方も数名になるでしょう。見知らぬ同士でしょうから、前日は打ち合わせもあるでしょうし、酒を飲んで親睦を深めるのは良いですね」
![]() 「その手があったか、そこまでは考えなかったな。
「その手があったか、そこまでは考えなかったな。
確かに講演会とは違うから、チームでの準備が必要ですね。もちろん皆さん専門家だから問題の内容も主張に至る考えも共有しているでしょうけど、役割分担も作戦もありますね。
イベントとしていい感じですね」
![]() 「移動がありますから、皆が集まるのは昼過ぎでしょう。
「移動がありますから、皆が集まるのは昼過ぎでしょう。
午後一杯、挨拶、進め方、各チームの打ち合わせをして、夕刻以降は懇親会でどうです?」
![]() 「なるほど、なるほど、やはりここでお話を伺って良かったですわ」
「なるほど、なるほど、やはりここでお話を伺って良かったですわ」
その場ですぐ、佐川が広報部の広瀬課長に電話して、一枚加わらないかと声をかけた。広瀬課長がすぐに来て話に加わる。
 |
|
| 私を呼ばないなん てダメじゃない。 |
費用とすれば保養施設の利用と宴席だけだ。会社行事とすれば費用は安くできる。10数名としても20万はかからないだろう。
もちろん一応、形は協賛にしてもらう。当然雑誌にもその旨記載してもらう。
会社のメリットはISO認証するだけでなく、ISO認証の広報活動に貢献していると環境報告書などで使える。ISOの理解を深めるために身銭を切っているというのが良い。
もちろんそれ以外の費用は「ISO認証誌」持ちだ。押田も雑誌社が主宰者でないと筋が通らない。
*
*
*
押田は増子に指示して、反論を寄こした中で論理が通っていると思われる人を、8人ほどピックアップしてお誘いのメールを出してみた。打率5割でも4人はOKするだろう。4人全員が選手にならずとも、懇親会、準備作業、見学でも来た甲斐はあるだろうと決めつけた。いやテーマごとに選手を替えれば全員出場できる。
レフリーにはB〇〇社のハワードに依頼した。
押田がハワードに、イギリスでもディベートはしていますかと聞くと、ディベートの発祥はイギリスだと笑われた
ハワードの方は日程が決まれば、それに予定を合わせるという。
こちらも宣伝にもなるし、審判のパフォーマンス次第では認証機関の評価も上がると見積もったのだろう。
注:もちろん、イギリス人は自国を「イギリス」は言わない。ちゃんとしたときはユナイテッド・キングダムで、普通はグレート・ブリテンとかブリテンと言う。
しかしすごいね、ユナイテッド・キングダムは連合王国だし、グレート・ブリテンなら大英帝国だ。国号が「日本」なんてシンプル過ぎる。
韓国だって「大韓民国」と「大」が付き、北朝鮮は「朝鮮民主主義人民共和国」だ。民主主義とか共和国とは笑ってしまう。
いろいろとあったが最終的にディベートの作法に則りで開催することになった。
勝ち負けは主張の理論たてだけでなく、ディベートの力量も見るということだ。そのほうが角が立たないという逃げでもある。
*
*
*
ディベートは8月多くの企業が夏季休暇にする時期の始まりに設定した。いまどき会社の保養所を利用する社員などいない。利用者は引退したOBがほとんどで、宿泊料が安いから利用するのである。そして老齢の彼らは夏季連休は混むから旅行に出ない。要するにガラガラである。
*
*
*
結局、押田のお誘いに乗ったのは3名だけであった。夏季連休ではあるが月遅れ盆の時期だし、家族持ちは前々から予定があるのだろう。
押田編集長は、次回は余裕をもって募集せんといかんと反省する。次回があればだが
対するチームはリーダーが田中、鈴木は『俺にも言わせろ』のつながりで参加、そして山口である。
佐川はお手伝い要員で、選手から外れた。
*
*
*
初日、昼過ぎに保養所集合である。
アイスブレーキングの後に、ディベートのルールの説明、テーマそして肯定・否定の役割交代などを説明する。
| 主催:「ISO認証誌」 | 協賛:吉宗機械 |  増子 |  押田編集長 |   広瀬課長 |
Aチーム | Bチーム |
|
久保 |  田中 田中 |
|
夏井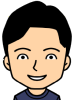 |  鈴木 鈴木 |
|
金沢 |  山口 山口 |
|
審判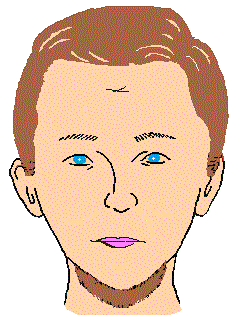 ハワード | 用務員 佐川 |
オリエンテーションの後は、それぞれのチームが別部屋で作戦会議、調査、グループ内の役割検討などを行う。ネットにつながるパソコンを各2台置いているから十分だろう。プリンタも各部屋に用意してある。
*
*
*
夜、懇親会である。
最初は宴会場という話もあったが、わずか12名では広すぎるということで、12畳くらいの洋室だ。今の時代、誰もが座るのは辛い。決してハワードのためではない。
伊豆半島は漁港
主宰者の押田編集長が今回のイベント開催の経緯と明日の健闘を期待すると話す。その後、乾杯の後、参加者の自己紹介などが続く。
田中の記事に対する反論から選抜された3名は次のとおりである。
 久保氏
久保氏
40代半ば、技術部にいたらしいが、年齢から第一線を外れ技術管理に移り少し腐っているようだ。ISO認証には文書管理が大きい位置を占めるので、ISOを足がかりに久保は社内への影響力を高めようという狙いが見える。
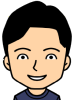 夏井氏
夏井氏
30歳半ば、品質管理にいたがISO認証のために品質保証部門が設置され、そこに移ったという。品質管理の手法やULの対応はベテランだが品質保証はあまり詳しくないようだ。BtoCのビジネスなら、品質保証部門がない会社も普通にある。
 金沢氏
金沢氏
20代後半、純真なのか不勉強なのか、審査員やコンサルの語ることを神の声と信じている。彼らの話を否定する田中を、完全におかしいと思っている。
こういう若者を見ると、品質保証という仕事は、いろいろな仕事を経験した人でないとまずいと感じる。
少し食べて腹が落ち着くと、動き回って歓談が始まる。
最初3名はハワードの周りに集まる。
![]() 「ハワードさんはイギリスで審査員をされていたのですか?」
「ハワードさんはイギリスで審査員をされていたのですか?」

![]() 「そうです。もちろん始めた時はISO規格などありません。イギリスの品質保証規格での審査でした」
「そうです。もちろん始めた時はISO規格などありません。イギリスの品質保証規格での審査でした」
![]() 「日本ではISO審査員とは尊敬される仕事ですが、イギリスではどうですか?」
「日本ではISO審査員とは尊敬される仕事ですが、イギリスではどうですか?」
![]() 「イギリスは銀行でもなんでもそうですが、大学を出なければならないというものではなく、実務で経験を積むものという考えがあります。
「イギリスは銀行でもなんでもそうですが、大学を出なければならないというものではなく、実務で経験を積むものという考えがあります。
審査員も学歴は高卒も多いですが、従事する人は実務経験を積み、それなりに自負はありますよ」
注:イギリスの大学進学率はネットを見ると様々だ。文科省の大学進学率の国際比較(2010)では63%となっており、House of Commons Libraryサイトでは35%前後である。
これは18歳時点の高等教育機関への進学率は35%であり、その後社会人として種々の高等教育機関(大学以外も含めて)で学んだ、学歴というか学業経験を持つ人が65%いるとのこと。
![]()
日本の場合、社会人になってから大学・大学院に行く人は数%とのこと。そのため、新卒時の学歴イコール最終的な学歴らしい。これが日本の教育というかライフスタイルの弱い点(悪い点)と言われているそうだ。
![]() 「私たちは日本語に訳された規格を読んでいます。英語の原文と違うニュアンスのところもありますか?」
「私たちは日本語に訳された規格を読んでいます。英語の原文と違うニュアンスのところもありますか?」
![]() 「ありますね。日本語でなく英文を読んで考えた方が良いです。
「ありますね。日本語でなく英文を読んで考えた方が良いです。
日本では中学から英語を習っていますし、難しい単語もありません。翻訳で逆に意味を難しくしている感じがします」
![]() 「例えば、どんなところでしょう?」
「例えば、どんなところでしょう?」
![]() 「ええと環境側面の原語はaspectで、これを日本語では側面と訳しています。しかし日本語の側面は、もともと物体の正面でない横方向を言います。
「ええと環境側面の原語はaspectで、これを日本語では側面と訳しています。しかし日本語の側面は、もともと物体の正面でない横方向を言います。
aspectにはそのような意味合いはなく、見た目、性質、機能、表情、態度、物事を調べる切り口とか方法という意味です」
注:「環境側面」とは何ぞやと、私はいろいろ調べた。
「側面」とは漢語ではあるが10世紀以前の文書には見られず、日本に入ってきたのは10世紀以降らしい。そしてその意味は、単に物体の横面という意味だった。
![]()
明治末期に西洋の文書を翻訳するとき「aspect」を「側面」と訳したのが始まりという。元々「側面」にそのような意味があったのではなく、側面に新しい意味を加えたのである。
故に「側面とは何だろう?」と考えるのは無駄の極みである。側面を忘れて、「aspect」を英英辞典ひたすらで調べるしかない。
![]() 「どう訳せばよかったのでしょう?」
「どう訳せばよかったのでしょう?」
![]() 「漢字熟語ではないですが『何ものかの環境に関すること』と訳せば良かったと思います」
「漢字熟語ではないですが『何ものかの環境に関すること』と訳せば良かったと思います」
![]() 「私は多くの人が、明日、ディベート相手の小林さんや田中さんもですが、環境側面を理解していないと思います。
「私は多くの人が、明日、ディベート相手の小林さんや田中さんもですが、環境側面を理解していないと思います。
彼らは過去から管理しているものが環境側面だと公言しています。それは大間違いです。
ISO14001は環境経営の規格であり、従来からの公害防止や省エネの考えでは、今後の持続可能は成り立たないと、新しい視点で考えないとなりません」
![]() 「それは明日の討論が楽しみです(こいつはバカだ)」
「それは明日の討論が楽しみです(こいつはバカだ)」
![]() 「審査で審査員が語ることには、ISO規格に書いてないことも多いのですが、それはどうなのでしょう?」
「審査で審査員が語ることには、ISO規格に書いてないことも多いのですが、それはどうなのでしょう?」
![]() 「規格を読んだだけでなく、それが意図しているのは何かを考えないとならない。いわゆる解釈だな」
「規格を読んだだけでなく、それが意図しているのは何かを考えないとならない。いわゆる解釈だな」
![]() 「解釈するということは、読む人が望むように読むことになりますね」
「解釈するということは、読む人が望むように読むことになりますね」
![]() 「ISO規格は単純です。解釈する必要はありません。書いてある通りです」
「ISO規格は単純です。解釈する必要はありません。書いてある通りです」
![]() 「そうはならないよ。法律だって論理解釈ってのがあるだろう。それと同じだ」
「そうはならないよ。法律だって論理解釈ってのがあるだろう。それと同じだ」
![]() 「ISO規格の理解は、文字解釈しかありません。
「ISO規格の理解は、文字解釈しかありません。
ISO9001のときから記録の要求にあるから、文書も同様に管理しなければならないという審査判定があったようです。それは間違いです。
規格というものは書いてあることはmustですが、文字に書いてないことは無関係です」
![]() 「そういう発想では会社を良くなりません」
「そういう発想では会社を良くなりません」
![]() 「おお、ディベート始まってしまいそうです。では審判は余計な発言は止めておきましょう(山口さんよ、明日はこいつを袋にしてくれ)」
「おお、ディベート始まってしまいそうです。では審判は余計な発言は止めておきましょう(山口さんよ、明日はこいつを袋にしてくれ)」
ひとつ離れた席で田中と山口が飲んでいた。
聞くともなしに久保の声が入ってきて、二人とも苦笑いをする。
この分では明日、久保氏の発言を全否定しても、自分が切られたことさえ理解しないだろう。狂信者には勝てないなとため息をつく。
少し離れたところで佐川は増子と飲んでいた。
![]() 「もうお仕事は慣れましたか?」
「もうお仕事は慣れましたか?」
![]() 「この仕事に就いて、8月でちょうど一年になります。登れど登れど頂は見えずですが、目の前の仕事を処理するのに迷うことはなくなりました。
「この仕事に就いて、8月でちょうど一年になります。登れど登れど頂は見えずですが、目の前の仕事を処理するのに迷うことはなくなりました。
とはいえ校正も校閲も素人で、今、夜間の校正の専門学校に通っています」
![]() 「ほう、増子さんは努力の人ですね」
「ほう、増子さんは努力の人ですね」
![]() 「いえ、就職した直後に佐川さんも入っている研究会の飲み会で(第90話)、いろいろ申しましたが、今は反省しています」
「いえ、就職した直後に佐川さんも入っている研究会の飲み会で(第90話)、いろいろ申しましたが、今は反省しています」
![]() 「反省など無用です。すべての体験は良い体験なのです。私もISO認証に携わり、数えきれないほど自分も認証したし、指導もしました。それは失敗の積み重ねですよ。
「反省など無用です。すべての体験は良い体験なのです。私もISO認証に携わり、数えきれないほど自分も認証したし、指導もしました。それは失敗の積み重ねですよ。
岡本真夜
![]() 本日の進歩?
本日の進歩?
本日の文字数は約8,000字でしょうか。今までなら物語が一段落つくまで16,000字とか書いていたと思います。最近は少し利口になって、読む人のことも考えて分割するようになりました。
1万6千字となると、普通に読んで、40分はかかります。始業前にはお忙しいでしょう。8,000字なら20分、それくらいなら妥協の範囲かと……いえいえ、上長が仕事しろと言い出すに十分な時間です。
これは進歩したどころか大いに反省せねば・・・
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
ISO認証活動で自殺したという事件は何度か新聞に載った。今現在「ISO+自殺」でGoogle検索すると2件ヒットするが、認証後の活動で自殺したという記事はない。 しかし私自身が関わった中で、「認証をしても何も良くならない」とノイローゼなのか鬱なのか休職してしまった人が一人、休職はしないものの鬱状態になり会社が懸念して異動させた人が一人いる。 | |
| 注2 |
この物語の1998年時点、まだguide66は発行されておらず、1996年制定のISO9001審査を定めたguide62がISO14001審査にも援用されていた。 guide66は1999年に制定された。その後、2006年にISO17021が制定されてguide62とguide66は廃止された。 正直言って、ISO17021の出来が悪くguide66が蘇って欲しい。 | |
| 注3 |
・ディベートルールディベートとは?定義とルール、実施の流れ、ディスカッションとの違いを解説 ・ディベートのルール | |
| 注4 |
広い意味の討論は紀元前5世紀の古代ギリシアで始まったと考えらていれる。 現代的なディベートは中世のオックスフォードやケンブリッジ大学で、「ディベーティング・ソサエティ(討論会)」が起源と言われている。 19世紀以降、アメリカで「競技ディベート」行われるようになった。 | |
| 注5 |
驚くことに三浦半島には漁港が37港もある。静岡県の指定漁港は48港だから、実に8割が伊豆半島に所在する。 ・静岡県 県内の漁港 | |
| 注6 |
岡本真夜のtomorrowは1995年、この物語は今、1998年、まだ人々に口ずさまれていた時代だ。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |