注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
食堂で全員そろって昼食をとる。どこにでもあるメニューだが、魚が美味い。
 食べながら雑談や午前中の話をしており、無言だった朝食と打って変わって和やかムードだ。朝食は勝負するぞ、勝つぞというかなりとんがった雰囲気だった。
食べながら雑談や午前中の話をしており、無言だった朝食と打って変わって和やかムードだ。朝食は勝負するぞ、勝つぞというかなりとんがった雰囲気だった。
今はもう勝敗はどうでもよくなったし、認証機関のボスやISO規格の理解で一歩先を行っている人たちに、少し勉強させてもらおうという気持ちだろう。
おっと、これは『会社良くなる派』の雰囲気であり、『会社良くならない派』は午前と変わらず長閑である。
食事後のコーヒーになると、ある派とない派の会話も出るようになった。
![]() 「田中さんたち三人は、どういう関係なのですか?」
「田中さんたち三人は、どういう関係なのですか?」
![]() 「佐川さんを含めて私たちは、〇〇業界団体の環境部の環境ISO研究会のメンバーなのです。ISO14001が制定されることに備えて1995年初めから勉強会をしてきました」
「佐川さんを含めて私たちは、〇〇業界団体の環境部の環境ISO研究会のメンバーなのです。ISO14001が制定されることに備えて1995年初めから勉強会をしてきました」
![]() 「佐川さんは非常にISO規格に明るいとお見受けしました。先ほどのハワードさんの話にも出てきましたが、工場や関連会社のISO認証の指導をしているとか」
「佐川さんは非常にISO規格に明るいとお見受けしました。先ほどのハワードさんの話にも出てきましたが、工場や関連会社のISO認証の指導をしているとか」
![]() 「指導はしてますが、特に詳しいわけではありません。私は現場上がりですし」
「指導はしてますが、特に詳しいわけではありません。私は現場上がりですし」
![]() 「久保さん、騙されてはいけませんよ。佐川さんは、ISO9001の認証が始まったときから審査員を指導していましたから」
「久保さん、騙されてはいけませんよ。佐川さんは、ISO9001の認証が始まったときから審査員を指導していましたから」
![]() 「はっ!、審査員を指導とはどういうことです」
「はっ!、審査員を指導とはどういうことです」
![]() 「いえいえ、常識的なことだけです。規格を読んでも深い意味は分かりませんし、久保さんとハワードさんの話にあったように、文字解釈か論理解釈かなど考えたこともありません」
「いえいえ、常識的なことだけです。規格を読んでも深い意味は分かりませんし、久保さんとハワードさんの話にあったように、文字解釈か論理解釈かなど考えたこともありません」

![]() 「ウソ、ウソ、私どもの環境ISO研究会で、ISO14001の解説を書籍にして発行しましたが、ほとんど佐川さんが作ったのです。詳しくないはずがありません」
「ウソ、ウソ、私どもの環境ISO研究会で、ISO14001の解説を書籍にして発行しましたが、ほとんど佐川さんが作ったのです。詳しくないはずがありません」
![]() 「えっ、皆さんが、あの認証指南本を書いたのですか?
「えっ、皆さんが、あの認証指南本を書いたのですか?
僕も買いました。非常に参考になりました。ただ、かなり強気で独断と思えるところもありましたね」
![]() 「産業環境認証機関の監修は受けているし、あそこに座っているハワードさん、彼はB〇〇社のトップです、にも見てもらっていますよ。内容は保証付きです」
「産業環境認証機関の監修は受けているし、あそこに座っているハワードさん、彼はB〇〇社のトップです、にも見てもらっていますよ。内容は保証付きです」
![]() 「そいじゃ、今日討論を挑んだのは、手合い違いでしたか」
「そいじゃ、今日討論を挑んだのは、手合い違いでしたか」
テーブルの反対側では、また別の組み合わせが話し合っている。
![]() 「午後の部ですが、テーマを『ISO14001は儲かるか』だったと思いますが、そうなるとまた定義とか細かいことでもめると思います。
「午後の部ですが、テーマを『ISO14001は儲かるか』だったと思いますが、そうなるとまた定義とか細かいことでもめると思います。
それでもっと分かりやすいもの、結論を出すのを目的とせず、皆が疑問に思っていることを語りあうようなものが良いと思います」
![]() 「具体的にどんなテーマが良いかアイデアありますか?」
「具体的にどんなテーマが良いかアイデアありますか?」
![]() 「午前中と同じ『ISOは会社を良くするか』でも良いです。ディベートの作法でなく、結論を出すという制約を外して、疑問を出すだけでも良し、語り合うだけでも勉強になると思うのです。
「午前中と同じ『ISOは会社を良くするか』でも良いです。ディベートの作法でなく、結論を出すという制約を外して、疑問を出すだけでも良し、語り合うだけでも勉強になると思うのです。
特に私は対等に議論などできず、教えを乞うレベルですから」
![]() 「提案があります。確かに『会社を良くする』と語る審査員やコンサルは多いです。ところが、この『良くする』があいまいです。午前中も定義で議論になりました。
「提案があります。確かに『会社を良くする』と語る審査員やコンサルは多いです。ところが、この『良くする』があいまいです。午前中も定義で議論になりました。
そこで提案ですが『ISO認証は会社に貢献するか』と言い換えたらどうでしょうか」
![]() 「私も発言。ISOとかISO規格というのは、今話題にしているのはISO14001で異議はないと思います。
「私も発言。ISOとかISO規格というのは、今話題にしているのはISO14001で異議はないと思います。
でもISO規格とISO認証は、似てますが全然違います。
しかもISO規格を活用して会社を良くしたい久保さんもいれば、ISO認証とは規格適合を証するものと理解している我々とは話がかみ合いません」
![]() 「そう、そう、まずそこからずれているね」
「そう、そう、まずそこからずれているね」

![]() 「そういうことになると、ISO14001の活用を議論するのか、ISO14001認証の効果を議論するかをはっきりさせなくてはなりません」
「そういうことになると、ISO14001の活用を議論するのか、ISO14001認証の効果を議論するかをはっきりさせなくてはなりません」
![]() 「その前にISO9001とISO14001の、本質というか性質の違いを考えるのもあります」
「その前にISO9001とISO14001の、本質というか性質の違いを考えるのもあります」
![]() 「ISO9001は取引のためであり、ISO14001は自分のためだからですか?」
「ISO9001は取引のためであり、ISO14001は自分のためだからですか?」
注:「ISO9001は取引のため」と聞いて「えっ、それなんのこと?」と思う人がいるかもしれない。
ISO9001が2000年改定で変質しておかしくなったが、そもそも「ISO9001は取引のため」なのである。現在だって「ISO9001認証」は商取引のためであるのは間違いない。
![]() 「あるいはISO9001は商取引で意味があり、ISO14001はESG投資とかCSRで意味があるのですか?」
「あるいはISO9001は商取引で意味があり、ISO14001はESG投資とかCSRで意味があるのですか?」
![]() 「う〜ん、分かりませんが、どこか大きく違うように思うのです。」
「う〜ん、分かりませんが、どこか大きく違うように思うのです。」
![]() 「いや非常に大事なことだ。とはいえ、あまり話題を広げては、半日ではまとまらない。
「いや非常に大事なことだ。とはいえ、あまり話題を広げては、半日ではまとまらない。
イメージが違うならそれをテーマにしても良いと思うけど・・・あるいは平易にISO14001に期待するものというのもありですね」
![]() 「ISO14001に期待するものと表現したら、理解にバラツキも出ない気がしますが」
「ISO14001に期待するものと表現したら、理解にバラツキも出ない気がしますが」
![]() 「いやいや、ISO14001に期待すると言っても、規格に期待するのですか、認証に期待するのですか?」
「いやいや、ISO14001に期待すると言っても、規格に期待するのですか、認証に期待するのですか?」
![]() 「一般人は認証しか頭にないでしょうね。自己宣言の存在も、規格を活用することも知らんでしょう」
「一般人は認証しか頭にないでしょうね。自己宣言の存在も、規格を活用することも知らんでしょう」
![]() 「増子さん、あなたの考えるISO14001に期待するものは何ですか?」
「増子さん、あなたの考えるISO14001に期待するものは何ですか?」
![]() 「そりゃ決まっています。今、多くの業種でISO14001の認証が始まっています。
「そりゃ決まっています。今、多くの業種でISO14001の認証が始まっています。
ISO9001なら輸出している製造業だけが対象・・・そうですねUL認定のようなもので、必要な会社だけのことで、それ以外の業種は無関係、それでオシマイです。
でもISO14001が登場したことで、すべての業種で環境管理レベルを客観的に示す指標ができたわけです。だからその認証を受けて、評判というか評価を上げようとしているわけです。
それにより弊社のような、ニッチなカテゴリーの市場も拡大すると期待しております」
![]() 「ハハハ、さすがISO雑誌を出版してる我が社の社員だ。まあ、そこまで言えば贔屓の引き倒しだろうけど。
「ハハハ、さすがISO雑誌を出版してる我が社の社員だ。まあ、そこまで言えば贔屓の引き倒しだろうけど。
山口さんはどう?」
![]() 「私がISO14001に期待するものは、はっきり言ってありません」
「私がISO14001に期待するものは、はっきり言ってありません」
![]()
![]()
![]() 「期待してない???」
「期待してない???」
![]() 「ISO14001の意図は『遵法と汚染の予防』です。平たく言えば、違反しない・事故を起こさないです。
「ISO14001の意図は『遵法と汚染の予防』です。平たく言えば、違反しない・事故を起こさないです。
日本においては公害、廃棄物、工場省エネ、製品省エネ、化学物質管理、いろいろな切り口で環境法が細かく制定されています。
イギリスは知りませんが、アメリカより環境法の整備は進んでいるでしょう。まあ1960年代に、公害列島なんて言われたことで、そうなったのでしょうけど」
注:環境法という法律はない。自然環境や生活環境の悪化を防止し、維持・改善する法律の総称である。公害防止、廃棄物、省エネ、自然保護などから成る。
![]() 「ですからISO14001以前から、環境管理は法令できめ細かく定められています。実際にISO14001が登場したとき、当社の公害対策の専門家たちは、そんなもの無用だと語っていました。
「ですからISO14001以前から、環境管理は法令できめ細かく定められています。実際にISO14001が登場したとき、当社の公害対策の専門家たちは、そんなもの無用だと語っていました。
現実にも環境側面なんていう新しいアイデアを持ち出して、結果として企業の仕事を増やしているだけです。
言い換えれば、ISO規格の専門語を取り払い、環境改善の活動状況、環境法規制の遵守状況、そのためのルールを監査すればISOの審査と同等以上です。ISO14001の方が守備範囲は狭いし、内容も曖昧です。
ただ絶対に日本の法律が守備していないこともあります。それは工場以外の組織における環境管理ですね。デパート、劇場、病院、アリーナなどですか。
騒音とか廃棄物処理などは現行の法律の対象です。しかし第3次産業の省エネ規制はありません。リサイクルや環境配慮の規制も未整備です。
そういった分野でも環境対応の管理が必要で審査・監査が必要ですが、そのためにはISO14001がなくても、現在ある環境関連法規を改正をすれば間に合うと思いますね」
![]() 「さすが企業で環境管理をしている人は、いろいろ考えているものだね」
「さすが企業で環境管理をしている人は、いろいろ考えているものだね」
![]() 「ISO14001は、法規制の上に自主的な活動を載せるイメージと思ったがね」
「ISO14001は、法規制の上に自主的な活動を載せるイメージと思ったがね」
![]() 「環境法が未整備の国ではそうでしょう。しかし日本は既に、他国が法規制の上に自主的な活動を載せたところまで法規制が整っていると言えるでしょう」
「環境法が未整備の国ではそうでしょう。しかし日本は既に、他国が法規制の上に自主的な活動を載せたところまで法規制が整っていると言えるでしょう」
![]() 「いや、驚きました。山口さんはISO規格の解釈を考えるだけでなく、ISO規格の存在意義、そしてそれに対する対応を考えてらっしゃる。
「いや、驚きました。山口さんはISO規格の解釈を考えるだけでなく、ISO規格の存在意義、そしてそれに対する対応を考えてらっしゃる。
山口さんはISO認証など不要と考えているわけですね?」
![]() 「正直言って認証が必要ないだけでなく、認証制度が必要なのか疑問です。
「正直言って認証が必要ないだけでなく、認証制度が必要なのか疑問です。
私は認証指導はISO9001から関わってきました。そこで経験したことは、会社の仕組みを知らない審査員が、自分の好みで会社の仕組みを改悪させる、おもちゃにすることでした。
それに比べれば酒を飲ませろとか、お土産を要求する方が可愛いものです。
私は会社の仕組みを悪くさせようとする審査員には断固戦います。そしてULのように認定が必須でないなら、わざわざISO認証などする必要がないと思っています」
![]() 「やれやれ、佐川さんだけじゃなく、山口さんも硬派ですね」
「やれやれ、佐川さんだけじゃなく、山口さんも硬派ですね」
![]() 「そいじゃ午後の部を始めましょうや」
「そいじゃ午後の部を始めましょうや」
*
*
*
会議室のテーブルを四角く組み合わせて、参加者全員12名が座る。
 | ||
![]() 「午前の部は競技ディベートの作法で行いましたが、お互い慣れていないためか、やりにくいように見えました。
「午前の部は競技ディベートの作法で行いましたが、お互い慣れていないためか、やりにくいように見えました。
それで午後の部はテーマは決めますが自由に発言してもらい、お互いに賛成・反論を自由に、どんどん言いたいこと言い合う方法で進めたいと思います。
雑誌の記事にするときは、それを編集してまとめたいと思います。
もちろん大声で言いたい放題では収拾つきませんので、まずは主催者、協賛者を除いて一巡してから司会が・・司会は私が務めます・・司会が指名した方が発言するということにしましょう。
特に結論を出すこともなく、勝ち負けもありません。
テーマは『ISO認証は会社に貢献するか』とします」
増子が立ち上がり、脇に置いたコピー黒板にテーマを手書きする。
![]() 「ではまずは久保さんから『ISO認証は会社に貢献するか・しないのか』自由意見を言ってください」
「ではまずは久保さんから『ISO認証は会社に貢献するか・しないのか』自由意見を言ってください」
![]() 「私が会社に入ってから25年になります。その間にさまざまな経営手法とか問題解決手法、改善手法が流行しました。
「私が会社に入ってから25年になります。その間にさまざまな経営手法とか問題解決手法、改善手法が流行しました。
思い出すままに言えば、入社当時はZD運動
その後にサークル活動(QCサークル)というものが流行りました。元々はZD運動の一環として始まりましたが、後にZD運動は消滅しQCサークルは残り、日本産業発展の素と言われてきましたが、ISOが登場してからは下火です。
技術部門でもVAなんて流行りました。
まあ細かいことはどうでもいいのですが、様々な手法が流行り、去っていきました。まさに『世は去り、世は来たる。しかし大地は永遠に変わらない(旧約 伝道の書1.4)』ですね。
それで良いと思うのです。少なくても新しい改善手法は、何かを会社に残していきました。ISOMS規格とその認証活動は何かを加えていくだろうと思います。
言い換えると、ISO認証のブームもせいぜいが25年、四半世紀だと思います。
以上です」
![]() 「ご意見、なかなか厳しいですね。ISO認証は見方によっていろいろな顔を持っています。企業から見れば、会社の仕組みの改善になるかもしれないという期待があるでしょう。
「ご意見、なかなか厳しいですね。ISO認証は見方によっていろいろな顔を持っています。企業から見れば、会社の仕組みの改善になるかもしれないという期待があるでしょう。
認証する側から見れば認証ビジネスと言われるように、新しいビジネスモデルです。露骨に言えば金儲けです。
ヨーロッパではISO9001が現れたとき、ホワイトカラーの失業対策と言われました。日本においては社内失業者対策かもしれない。
もちろんすべてのビジネスモデルは寿命があります。ISO9001認証件数は増加を続けていましたが、既に微分係数はゼロです。先に待つのは新規認証件数の増加の減少でその先は認証件数の減少です。
我々は、次なるビジネスを考えなければなりません」
![]() 「当社にとっても同じです。ISO規格の第三者認証制度の次は、高齢化社会の問題ですかね……
「当社にとっても同じです。ISO規格の第三者認証制度の次は、高齢化社会の問題ですかね……
それはともかく、それでは次は田中さんどうぞ」
![]() 「私にとってISO認証は、まさしく事業継続のためです。ヨーロッパは小さな国がたくさんありました。第二次世界大戦が終わり、超大国が世界を仕切るようになりました。政治・経済・軍事すべてにおいてヨーロッパの地盤沈下です。
「私にとってISO認証は、まさしく事業継続のためです。ヨーロッパは小さな国がたくさんありました。第二次世界大戦が終わり、超大国が世界を仕切るようになりました。政治・経済・軍事すべてにおいてヨーロッパの地盤沈下です。
ヨーロッパ諸国は二大超大国に第三極として加わり、世界を動かせる力を維持しようとしました」
| 名称 | 初期の加盟国 | 目的 | |
| EEC |
西ドイツ、ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オランダの6ヵ国 | アメリカ、ソ連に対抗できる経済圏の確立をめざして関税の統一、資本・労働力移動の自由化、農業政策の共通化などを目指した | |
| EC 欧州共同体 |
1967年 | 西ドイツ、ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、英国、アイルランド、デンマーク、ギリシャ、スペイン、ポルトガルの12ヵ国 | 国境のない単一市場をつくることを目的とし、商品取引の自由化のほか労働力取引の自由化を図った。 |
| EU 欧州連合 |
1993年 | ECに同じ。 但し西ドイツから統一ドイツに変わった。 |
国境のない単一市場をつくることを目的とし、商品取引の自由化だけでなく労働力取引の自由化や通貨の統一を図った。 |
![]() 「ヨーロッパの国家間の協力の程度は増す一方で、仕上げは1993年の欧州統合でした。来年、1999年は通貨も統合する予定です。
「ヨーロッパの国家間の協力の程度は増す一方で、仕上げは1993年の欧州統合でした。来年、1999年は通貨も統合する予定です。
ヨーロッパと言ってもすべてが工業国ではありません。世界的に見れば先進国ばかりですが、工業国あり、農業国あり、経済規模も人口も大小あります。
そのために域内の人モノの移動は自由にすると言ったものの、物を自由に動かせるのはISO9000s認証した工場が作った物に限るとしたのです。
その制約は域外からの輸入品にも適用されました。日本製品をEU諸国に輸出するなら製造工場はISO認証していないとならないのです。
私の勤務先は、以前から輸出していたものを、1993年以降も輸出するために、ISO認証が必要でした。
つまり『ISO認証は会社に貢献するか』という問には『ISO認証は会社<の事業>に貢献するか』と語句を追加すればYESなのですが、それって単純に輸入国の非関税障壁対応ですね。会社を良くするとは思えません。
そこは、久保さんと違います」
注:ISO9001規格登場時、これは非関税障壁ではないと力説していたが、規格がどうあれその使い方次第で非関税障壁になることは否定できない。欧州内の移動制限そのものが非関税障壁であることは間違いない。
![]() 「そういう人は多いでしょうね。言い換えるとそれ以外の理由で、ISO認証した方っていらっしゃいますか?」
「そういう人は多いでしょうね。言い換えるとそれ以外の理由で、ISO認証した方っていらっしゃいますか?」
![]() 「私は親会社から認証しろと言われて、いや上品に言えばそういう方針を出されたからです。認証したものの、それから5年、ありがたみはありません」
「私は親会社から認証しろと言われて、いや上品に言えばそういう方針を出されたからです。認証したものの、それから5年、ありがたみはありません」
![]() 「それじゃどうして、夏井さんは田中さんの『ISOは会社を良くしない』に反論したのですか?」
「それじゃどうして、夏井さんは田中さんの『ISOは会社を良くしない』に反論したのですか?」
![]() 「うーん、それを言われると弱いですね。親会社の方針に従っただけですから、ISO9001もISO14001も役に立っていません。というか無用なのです。とはいえエライサンがISO14001の認証を推進したので、もう止めましょうと言えません。
「うーん、それを言われると弱いですね。親会社の方針に従っただけですから、ISO9001もISO14001も役に立っていません。というか無用なのです。とはいえエライサンがISO14001の認証を推進したので、もう止めましょうと言えません。
今回も田中論文を否定しろと言われて……相済みません」
![]() 「すまじきものは宮仕えですか、まあ、心境は分かりますが・・・
「すまじきものは宮仕えですか、まあ、心境は分かりますが・・・
金沢さんはどうなのですか?」
![]() 「もう単純に認証指導に来たコンサルの先生も、審査に来た審査員も『ISOは会社を良くする』というので、それがアプリオリに頭に染みついてしまいました」
「もう単純に認証指導に来たコンサルの先生も、審査に来た審査員も『ISOは会社を良くする』というので、それがアプリオリに頭に染みついてしまいました」
![]() 「佐川さんは『ISO認証は会社に貢献するか』という問いにどう答えますかね?」
「佐川さんは『ISO認証は会社に貢献するか』という問いにどう答えますかね?」
![]() 「私はISOMS規格というものは、すべて品質保証規格だと考えています。ISO9001はズバリ品質保証の国際規格と称していました。
「私はISOMS規格というものは、すべて品質保証規格だと考えています。ISO9001はズバリ品質保証の国際規格と称していました。
私はISO担当する前は、BtoBの顧客からの品質保証要求の対応をしていました。顧客が品質保証要求を要求するから対応するのであって、そこに会社を良くするという考えはありません。
買い手は良いものを納めてほしいから品質保証要求をするわけで、納入先の会社を良くしたいわけではありません。それは同意いただけるでしょう。
当然こちらもISO9001を見て思ったのは、今までA社の品質保証、B社の品質保証・・とあったのに、更にISO9001という品質保証要求が増えたということでした」
![]() 「質問。ISO9001を認証すれば、BtoBの品質保証要求は、なくなったのではないですか?」
「質問。ISO9001を認証すれば、BtoBの品質保証要求は、なくなったのではないですか?」
![]() 「なくなりません。ハワードさんもご存じと思いますが、顧客対応の品質保証要求事項はISO9001のように骨組みだけ目次だけで中身がありません。
「なくなりません。ハワードさんもご存じと思いますが、顧客対応の品質保証要求事項はISO9001のように骨組みだけ目次だけで中身がありません。
二者間の品質保証要求なら、物のトレーサビリティなら、どの部品とどの組立品はトレーサビリティの対象と指示します。
計測器の校正も、単に国家標準からのトレーサビリティではなく、どの校正機関に頼めとか、校正間隔も先方の考えで1年とか半年とか具体的に指示されます。特殊工程も同じです。我々が決めるのではなく買い手が決めます。
ご存じと思いますが、ISO9001は修正(tailoring)を認めていました。でも第三者認証では修正すればISO9001から逸脱してしまいます。ですから修正はできません。
結局どうなったかというと、ISO9001を認証しても、従来からの品質保証要求は生きていて、買い手による品質監査も従来通り行うのが現実です」
![]() 「そういう会社が多いとは聞いています」
「そういう会社が多いとは聞いています」
![]() 「さてISO14001も品質保証規格であるわけですが……」
「さてISO14001も品質保証規格であるわけですが……」
![]() 「ちょっと待ってください。どうして環境マネジメントシステム規格が、品質保証の規格なのですか?」
「ちょっと待ってください。どうして環境マネジメントシステム規格が、品質保証の規格なのですか?」
![]() 「品質保証とは『製品又はサービスが、所与の品質要求を満たしていることの妥当な信頼感を与えるために必要なすべての計画的及び体系的活動(ISO8402:1994
「品質保証とは『製品又はサービスが、所与の品質要求を満たしていることの妥当な信頼感を与えるために必要なすべての計画的及び体系的活動(ISO8402:1994
ISO14001を読めば、環境管理についてなすべきことを網羅しています。
品質保証とは何かの活動・・・生産でも販売でも環境管理でも・・・管理する項目や手順を要求するものですから、それはISO14001もズバリ該当します。
ISO14001とは、企業の環境管理に品質保証を要求するものなのです」」
![]() 「はあ〜、そうなんだ・・・」
「はあ〜、そうなんだ・・・」
![]() 「佐川さんはISOMS規格を悟っているのですね」
「佐川さんはISOMS規格を悟っているのですね」
![]() 「冗談をおっしゃってはいけません。悟りを開いた人は仏陀しかいないという人もいます。ISOの悟りを開いた人はいないんじゃないですか。
「冗談をおっしゃってはいけません。悟りを開いた人は仏陀しかいないという人もいます。ISOの悟りを開いた人はいないんじゃないですか。
それはともかく、ISO14001を品質保証規格とみれば、すべてがはっきりと見えてきます。
これまでの私の話を聞いて『ISO認証は会社に貢献するか』は、もう答えが出てしまったでしょう」
![]() 「ハワードさんは分かったかもしれないけど、私は分からない。分かった人いるの?」
「ハワードさんは分かったかもしれないけど、私は分からない。分かった人いるの?」
![]() 「私も分かりません」
「私も分かりません」
![]() 「簡単な論理ですよ。私は、ISO9001が外部品質保証要求のひとつに過ぎないと申し上げた。それはよろしいですね。
「簡単な論理ですよ。私は、ISO9001が外部品質保証要求のひとつに過ぎないと申し上げた。それはよろしいですね。
多くの顧客が品質保証要求をしてきます。設計管理、工程管理、保管管理、出荷管理、それは顧客が損しないように迷惑を受けないようにするためです。
工場はそれに対してどう対応するか考えてみてください。
お気づきと思いますが、ISO9001対応とISO14001対応には多くの企業で違いがあります。
山口さん分かりますか?」
![]() 「いつも佐川さんのお話を聞いていますが、この問には自信がありません。
「いつも佐川さんのお話を聞いていますが、この問には自信がありません。
ISO9001のとき、以前から品質保証協定を結んでいた企業は、それと同じ対応をしました。どういうことかというと、過去よりある会社の規則・規定から要求に見合ったものを抽出してマニュアルを作りました。
他方、ISO14001のときは、過去の環境管理の規則・規定を無視して、新しくISO用の規定を作ったところが多かったように思います」
![]() 「ウチはおっしゃる通りでしたね」
「ウチはおっしゃる通りでしたね」
![]() 「当社もそうです」
「当社もそうです」
![]() 「品質保証要求は顧客の数だけあります。それに合わせて会社の仕組みを作る人はいません。作れるはずがありませんね。
「品質保証要求は顧客の数だけあります。それに合わせて会社の仕組みを作る人はいません。作れるはずがありませんね。
ISO規格だからと特別扱いして、それ用の規定類を作るのは、おかしいということです」
注:現実にはISO9001の品質マニュアルも、現実の会社規則を無視してバーチャルというか二重帳簿のシステムを作った会社は多い。
そういう方法を多くのコンサルが指導した。彼らは今後のことなど考えず、審査登録証をもらえば任務終了だから、そんないい加減なことを教えたのだろう。
そういう能無しコンサルは絶滅すべきとは思うが、あっしには関わりのないことだ。
![]() 「意味が分かりませんが?」
「意味が分かりませんが?」
![]() 「どの会社でも創立したときに、会社のルールを決めているはずです。定款だけで仕事はできませんからね。
「どの会社でも創立したときに、会社のルールを決めているはずです。定款だけで仕事はできませんからね。
システムとは何かといろいろ言われていますが、アメリカ軍では定義ははっきりしています。それは組織、機能、手順です。
組織といっても構成するのは、人ばかりでなく部品とかソフトでも良いのです。機能とは何を担当するかの役割分担、手順は作業の処理をどう進めるかです。簡単明瞭ですね。
会社のシステムがたくさんあるはずはありません。明文化されていようとされてなくても、有機的に組みあがったひとつしかない。
そのシステムで、設計、調達、製造、販売について、お金、人、物の動かし方を決めているはずです。
そのルールがたくさんの顧客からの品質保証要求を満たし、またISO9001が要求することを網羅しているはずです。
品質マニュアルとはISO規格要求をその会社ではどの規則が対応しているかを示す対照表にすぎません」
![]() 「えぇ、マニュアルが対照表・・・そ、そんな」
「えぇ、マニュアルが対照表・・・そ、そんな」
![]() 「ですからISO規格要求を満たすものを、会社のあるいは工場の規則集から探し出して、規格要求に対応するよう記述すればマニュアルは出来上がる。ISO9001認証は過去の顧客からの品質保証要求に更に1件追加になったにすぎませんからね。
「ですからISO規格要求を満たすものを、会社のあるいは工場の規則集から探し出して、規格要求に対応するよう記述すればマニュアルは出来上がる。ISO9001認証は過去の顧客からの品質保証要求に更に1件追加になったにすぎませんからね。
お話しはこれでおしまいです。
蛇足ですが、マニュアルをものすごいものとか、最上位の文書と考えている審査員もいますが、愚の骨頂です。
マニュアルは会社の規則の要約というか、会社規則から顧客要求に対応する部分を切り取り貼り付けたスクラップブックにすぎません」
久保、夏井、金沢の、えーという叫び声がする。
![]() 「ところがISO14001では、規格要求に見合った文書を新たに作る人が多かった。なぜなんでしょうね?
「ところがISO14001では、規格要求に見合った文書を新たに作る人が多かった。なぜなんでしょうね?
確かに環境側面とかは過去にはなかった。ISO14001で作った概念ですからね。イギリスのBS7750にもEnvironmental aspectなんてありませんでした
でも簡単に言えば法規制が関わる物や作業、危険な物や作業、損害が大きなものを、著しい環境側面と新たに呼ぶことをしたということに過ぎない。
じゃあ、元々それに見合ったことをしていなかったのか?
法律に関わるか、認可や届け出が必要か、有資格者が必要か、事故が起きたら大問題になるか、そういうことを調べることはしていたはずです」
![]() 「ウチでは、そういうプロセスが思い当たりません」
「ウチでは、そういうプロセスが思い当たりません」
![]() 「山口さん、どうですか?」
「山口さん、どうですか?」
![]() 「していました。どの会社でもしているはずです。
「していました。どの会社でもしているはずです。
例えば新しい化学物質を使うとか新設備を導入するとき、法に関わるか否か、資格者が必要か否か、届け出の要否などを調べるのは、労働安全衛生法で定められています。安衛の担当者はそういうことをしていると思います。新設備を導入するときは、販売先がそういうことを教えてくれます。手続まで手伝ってくれますよ。
その他、消防法や公害防止組織法でもそういう規制はあります」
![]() 「その通りです。
「その通りです。
ということを踏まえると、現在、届け出しているものや作業、資格者がいるものは著しい環境側面に間違いない・・そこまでよろしいですか?」
![]() 「待ってください。本当に法規制と規格要求は一対一になるのですかね?
「待ってください。本当に法規制と規格要求は一対一になるのですかね?
![]() 「一般解として正しいとは数学的に証明はできませんが、個々の事例を見るとその考えから逸脱するものはありませんでした。
「一般解として正しいとは数学的に証明はできませんが、個々の事例を見るとその考えから逸脱するものはありませんでした。
ともかく弊社ではそういう考え方でISO14001の認証をしています」
![]() 「吾々が作った認証指南本も、その方法を推奨しています」
「吾々が作った認証指南本も、その方法を推奨しています」
![]() 「ということは会社の仕組みを変えず、あるがままを見せて、ISO14001を認証したということですか?」
「ということは会社の仕組みを変えず、あるがままを見せて、ISO14001を認証したということですか?」
![]() 「もちろんです。先ほど山口さんが、審査員の趣味や好みで会社の仕組みを改悪させない、おもちゃにさせないと力説してましたね。私も同感です」
「もちろんです。先ほど山口さんが、審査員の趣味や好みで会社の仕組みを改悪させない、おもちゃにさせないと力説してましたね。私も同感です」
![]() 「驚きました。山口さんはすごいが、佐川さんはもっとすごい」
「驚きました。山口さんはすごいが、佐川さんはもっとすごい」
![]() 「すごくありません。誰でも考えれば、そこに行きつきます。月給をもらっているわけですから、会社に損をさせない仕事をしなくちゃいけません。
「すごくありません。誰でも考えれば、そこに行きつきます。月給をもらっているわけですから、会社に損をさせない仕事をしなくちゃいけません。
これを演繹すれば、環境側面をスコアリング法で決める方法はおままごとであることは明白です」
![]() 「おままごと! そんな・・」
「おままごと! そんな・・」
![]() 「皆さんの中で、著しい環境側面をスコアリング法で決めた方はいますか?」
「皆さんの中で、著しい環境側面をスコアリング法で決めた方はいますか?」
久保、夏井、金沢が手を挙げる。
![]() 「そのとき自分たちが重大だと思ったものが、大きな点数が成るように、調整したのではないですか?」
「そのとき自分たちが重大だと思ったものが、大きな点数が成るように、調整したのではないですか?」
久保、夏井、金沢の三名、頷く。
![]() 「それこそ、まさにおままごとの証拠です。皆さんは初めから著しい環境側面を知っていたのです。だから結論がそうなるように配点表を作った、それだけのことです。
「それこそ、まさにおままごとの証拠です。皆さんは初めから著しい環境側面を知っていたのです。だから結論がそうなるように配点表を作った、それだけのことです。
別に責めてはいません。私も複数の審査員研修機関のテキストを入手したり、受講した知人に質問して状況を把握しています。
審査員研修の講師ははっきり言っています。『自分が著しい環境側面だと思っているものが著しい環境側面になるよう配点を決めなさい』ってね、
その時点でスコアリング法がくだらないことが明らかです。
話を戻します。
与えられた問いに答えるには、もうワンステップ論理を進める必要があります。
元からある規則・規定から、要求事項に見合うものを抜き書きすれば、環境マニュアルが仕上がるのなら規則規定の改定は不要です。
ということは過去からの会社の仕組みは全く変わらない。何も変えずにISO認証できことの言い方を変えれば、『ISO認証は会社に貢献しない』となる。
この論理の連鎖に、ご異議、ご質問ありますか?」
全員がしばし沈黙した。
ISO認証とは、そんな簡単なことなのか?
今までしていたことは全くおかしなことだったのか?
![]() 「御社はそのようにしてISO認証したのですか?」
「御社はそのようにしてISO認証したのですか?」
![]() 「そうです。時間もないリソースもない、そういう状況で結果を出すには本音で勝負しかありません。
「そうです。時間もないリソースもない、そういう状況で結果を出すには本音で勝負しかありません。
当社もISO9001認証のときは、スタートがゴタゴタして遅れてしまいました。私に話が来たときは、既に予備審査までひと月と迫っていました
私のアイデアを信じて実行してくれた人たちのおかげですよ」
![]() 「予備審査のひと月前だって・・・・
「予備審査のひと月前だって・・・・
私はISO認証のプロだと思っていました。佐川さんの話を聞くと、自分が全くの初心者というか、何も知らない子供だったと自覚しました」
![]() 「いえいえ、会社が違えば条件も違います。みな苦労は同じですよ」
「いえいえ、会社が違えば条件も違います。みな苦労は同じですよ」
![]() 「佐川さん、過去よりルールで決めていたはずと言うが、どの会社も全く問題ないと言えるのかい?」
「佐川さん、過去よりルールで決めていたはずと言うが、どの会社も全く問題ないと言えるのかい?」
![]() 「おっしゃる通りです。どこも完璧はありません。
「おっしゃる通りです。どこも完璧はありません。
ルールで決裁者を決めていても、責任者不在時に代行権限のない人が決裁していたとか、法の手続きはしているが、手続することを明文化していなかったなど、いくつかありました。幸い法に反することや、事故の原因になりそうなことはありませんでした。
そういった処置をしたとか明文化したのが『ISO認証は会社に貢献する』ことなら、認証は会社に貢献すると言っても間違いではないでしょう。
アハハハ、失礼、思い出し笑いです。ISO14001の効果として、コピーが減ってPPC使用枚数が減ったという論文を書いていたドクターもいました。いくらなんでも認証費用に200万も払って、年間のPPC枚数を数万枚減らしたところで雀の涙、それをISO14001の効果だと言ったら、ISO14001が泣きますよ。
それにコピーが減ったのを、ISOの効果と言えるのかも疑問です」
注:A4のPPC1枚が以前は80銭くらいだったが、2025年は1円前後に値上がりしている。
オフィスの紙使用量調査はいろいろな機関がしているが。共通しているのは2000年以降、電子化が進み、使用量は減少傾向にあり、2020年には半減している。
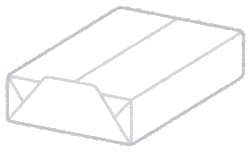
私はコピー減はISO認証の効果であると、記した報告を見たことがない。冷静に考えればISO認証とコピー枚数は無関係だ。
法を守るとかリスクに気付いたというのはISO認証と関連があるかもしれないが、コピー枚数は純粋に事務処理の仕組みの問題である。
もし趣味の会のコピーをしていたとか、ミスコピーが減った、あるいはワークフローシステムに代えたなら、ISO認証とは縁のない話だ。
2022年の平均的事務所では一人当たり年間2,000〜3,000枚(A4換算)で、紙使用量が多い業務で年間4000〜5000枚(同)と言われる。
なお、アメリカの調査では日本の2割増しらしい。
いずれにしても1,000人の工場でオフィスワーカーが400名として3,000枚/年とすれば400×3,000=120万枚であり、この1割を減らしても年12万円である。ISO認証でPPCが減ったとは語るな。
![]() 「佐川さん、御社には、そういう逸脱を見つける仕組みがなかったのですか?」
「佐川さん、御社には、そういう逸脱を見つける仕組みがなかったのですか?」
![]() 「いえ、ありました。どこの会社でも業務監査をしていると思います。弊社でも10年も前から、業務監査において環境に関しても点検していました。それに決裁の問題は、環境という視点でなくても見つけなければなりません。
「いえ、ありました。どこの会社でも業務監査をしていると思います。弊社でも10年も前から、業務監査において環境に関しても点検していました。それに決裁の問題は、環境という視点でなくても見つけなければなりません。
しかし監査員といっても工場の部長級が、他の工場に行って相互チェックするわけです。しかも環境の専門家でもなく、監査業務を習ったわけでもありません。せいぜい通り一遍の話をしてしっかりやっている、なんてことでお終いでした。
自分の工場が業務監査を受けるときは攻守逆転するわけで、あまり厳しいことも言えませんし、
もちろんそれでは困ります。そういったことで現在は、環境ばかりでなく、品質とか設計とか輸出管理などの業務監査の監査員の資格制度、また監査の方法、見逃しの責任を明確にして、監査員教育をしています」
![]() 「輸出管理とかになると、監査できる人が限られるでしょうね?」
「輸出管理とかになると、監査できる人が限られるでしょうね?」
![]() 「その辺になるとお答えできません」
「その辺になるとお答えできません」
![]() 「そうでしょうな。
「そうでしょうな。
ええと・・・なんか佐川さんが話すと、物事すべて白黒が決まってしまい、討論が終わってしまいますね」
![]() 「そのう〜、先ほどの、ひと月で予備審査を受けたという話ですが、それは本当ですよね?」
「そのう〜、先ほどの、ひと月で予備審査を受けたという話ですが、それは本当ですよね?」
![]() 「嘘偽りなく本当です。ついでに申し上げますと、工場はひとつではありません。4つの工場を同時並行して指導したのです。
「嘘偽りなく本当です。ついでに申し上げますと、工場はひとつではありません。4つの工場を同時並行して指導したのです。
しかもその4カ所は、兵庫県、長野県、千葉県、福島県と、どの工場間を移動するにも半日から1日かかるところでした。長野はまだ新幹線が走っていませんでしたし、神戸空港もありませんでした。
移動時間がかかるということは、指導する時間が短くなってしまいます。
あのときは私もアプレンティスとして佐川さんと同行しましたが、家に帰るのは週に1日だけで、毎日点々とホテル暮らしでした。
そのためばかりではないですが、私は結婚するのが半年遅れましたよ」
| 😄 | 😀 | 😁 | 😃 | 😄 | 😆 |
![]() 「4つの工場すべてが、一発で認証したのですか?」
「4つの工場すべてが、一発で認証したのですか?」
![]() 「もちろんです。不適合を出された工場もありましたが、佐川さんが認証機関に乗り込んで審査員の判断ミスと覆しました」
「もちろんです。不適合を出された工場もありましたが、佐川さんが認証機関に乗り込んで審査員の判断ミスと覆しました」
![]() 「まったくの偶然だが、あのとき私は神戸の街角で、その認証機関から帰る途中の佐川さんと山口さんに会ったね(第40話)。アハハハ」
「まったくの偶然だが、あのとき私は神戸の街角で、その認証機関から帰る途中の佐川さんと山口さんに会ったね(第40話)。アハハハ」
![]() 「すごいですね、我々のはるか遠くだ」
「すごいですね、我々のはるか遠くだ」
![]() 本日の疑問
本日の疑問
日本人は、ISO認証したら、会社を良くしようとか、儲けようと考えているようだ。
「そのためにISO認証した」と言われるかもしれないが、ISO認証する意味を考えてほしい。
だいぶ古いがISO/IAF共同コミュニケ
そこでは
「ISO9001の認証に期待される成果」として「定められた認証範囲について、認証を受けた品質マネジメントシステムがある組織は、顧客要求事項及び適用された法令・規制要求事項を満たした製品を一貫して提供し、更に、顧客満足の向上を目指す」
とある。
認証する意味はそれ以上でも以下でもない。会社を良くするとも儲かるとも書いてない。
ISO認証をしている元締めが「ISO認証とはこういうものだ」と明言しているのだ。ISO認証は、会社を良くすることや儲かるようにすることが目的でないことは間違ない。
もちろん結果としてそうなることもあるかもしれないが、それが目的ではないのだ。
おっと、そんなことコンサルも認証機関も知っているだろう
いい加減な仲人口を語るな!
仲人なら夫婦喧嘩とか離婚騒ぎになれば相談に乗るのに、コンサルも審査員も
■蛇足である。
「きめこむ」とはどういう言い回しなのだろうと興味を持った。
これは江戸時代の芝居で「〇役になり切って演じる」ことを「〇役を決め込んで演技する」と表現したことからだそうです。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
ZD運動とは1960年代製造業に流行った品質改善活動である。ZDはzero defects(無欠点)のことで、従業員全員が自分の仕事で誤りをしないようにするもの。 現実には精神論で終わったところが多かったようだ。 | |
| 注2 |
ISO9001の用語の定義は2000改定以前は、「ISO8402 品質−用語」で定めていた。 ISO9001:1994 3定義 「この規格では、ISO8402で規定する定義を適用する」 | |
| 注3 |
実を言って私は過去25年間、BS7750なんて名前しか知らずに生きてきた。この物語「タイムスリップISO」を書き始めるとき、BS7750の対訳本をアマゾンで買って何度も読んだ。120ページの本の定価は8,000円、買値は661円だった。 「環境管理・監査システム」日本規格協会編、日本規格協会、1994 | |
| 注4 |
IAF(国際認定フォーラム:International Accreditation Forum)とは、各国の認定機関が加盟する国際組織である。 役割は、すべての国の認定機関のレベルを合せ・向上を図り、どの認証機関の認証でも同じレベルとして国際的に通用することを推進することとなっている。 ホントのところは分からない。 | |
| 注5 |
・「ISO/IAF共同コミュニケ」ISO/IAF、2010、 「認定された ISO 9001認証に対して期待される成果」 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |