注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
ここ数年春は遅い。1999年も同じで開花宣言は3月末だ。当然気温も低く、中旬になっても最高気温15℃前後、最低気温5℃前後が続いている。
佐川はダウンを着て手袋をして通勤している。いくら福島県の生まれ育ちと言えど、5年も関東南部に住んでいれば、暖かい冬に慣れてしまう。
 佐川は今、環境部と未来プロジェクト兼務である。いつもは未来プロジェクト室に座っているが、ISO9001やISO14001審査でトラブル発生とヘルプコールが来ると、アシストするのが環境部員としての佐川の仕事である。
佐川は今、環境部と未来プロジェクト兼務である。いつもは未来プロジェクト室に座っているが、ISO9001やISO14001審査でトラブル発生とヘルプコールが来ると、アシストするのが環境部員としての佐川の仕事である。
10年前のように休日も休まずなんてことは今はなく、しっかり休日は休んでいる。もちろん暇ではないし、ISOだけでなく公害や廃棄物の相談に来る人も多い。
まあ、それだけ経験を積んで問題の対処方法が身に付いたということだろう。
来年度の目標は、自分なりに考えている。
環境部の仕事では、社内のISO14001認証が完了し、関連会社については既に柳田企画(第47話)の佐々木・片岡両氏に移管しようと考えている。
彼らも還暦過ぎたというから、二三年の内に引退するだろう。ゆくゆくは自分がその後釜に行くのかなと、ぼんやりと考えていた。
未来プロジェクトでも、今年、佐川は大きなイベントはないと見ている。
そして自分が知る出来事は、文書化してメンバーに周知している。あとはメンバーがその情報から問題の発生防止、他社に遅れない提案、あるいは新たなビジネスを考えてもらうことだ。いつまでも佐川に頼っていては困る
佐川は山口に、ISO認証指導の仕事がなくなった後は、どうするのかと聞いたことがある。
 |
|
| 山口 |
彼が言うにはISOではなく、社内の品質システムを真に改善していくことを考えているという。ということは、ISO規格でもISO認証でも、品質システムの改善はできないと認識しているのだろう。彼もISO認証に関わって6年、ベテランの域だ。
ある程度筋書きができたら、品質部長に売り込んで、新しい仕事を作り出したいという。
元々、本社にいる連中は「仕事を
そういう保守(保守的という意味ではない)の仕事に就いている人以外は、常に新しい技術や設備や管理手法を探していて、それをいかに活用して名をあげるかという欲望で、生きているように見える。
いや、そう言っては否定的だ。常に新しい技術やビジネスを咀嚼して社内展開するのを、自分の仕事と考えているようだ。
具体的には、ISO9001が登場すれば認証を指導し、その要求事項を会社のルールに織り込んでしまえば、次はISO14001、それが終わればまた新しい仕事を見つけるか、今の居場所でそれができなければ、他の部門に売り込み、受け入れてくれる職場で活動することになる。
そういう制度があるわけではなく、自分がしたいことをするために、周りを巻き込み動かすのだ。
それはチャレンジ精神溢れ独立独歩で素晴らしいとも言えるが、行き過ぎると當山のように私利私欲に走って、非合法のことまでするようになる
まあ、彼の場合は元々、タガがはずれていたのかもしれない。
|
|
|
 |
|
佐川も今年49歳になる。今までの6年間、ISO認証という新制度のおかげで飯を食ってきたが、それもそろそろ終りが見えてきた・・・いや見えているのは25年先を経験した佐川だけかもしれない。
第三者認証制度というものは鬼っ子のようなもので、元々は二者間の品質保証から脱皮して、第三者認証という新しい枠組みを提案したものだが、その結果は第三者認証の効果はなく、二者間の信頼も得られずに終わりそうだ。
それはともかくというか、それと大いに関連するのだが、佐川はどういう未来を拓いていくべきか、まだ確信がない。
今後、国策として定年が延長されるが、佐川のときはせいぜい嘱託で63までだろう。それでは新たな職務にチャレンジするには時間が足りない。
今考えているのはやはり環境であるが、ISOと離れて、環境遵法の向上を図ることが会社にとって喫緊の課題だろうとみている。それなら自分もそういう関連資格もスキルもあると思う。
方法としてはグループ企業の担当者教育と監査の制度を作り上げることだ。チャンスと言ってはまずいが、2000年頃から各企業において環境不祥事が頻発する。そういうことを踏まえて環境遵法向上プランを売り込めば採用される可能性は大きい。
今はISO14001の認証が始まって2年経ったところだが、すぐにISO14001は遵法にも事故防止にも、パフォーマンス改善効果がないと言われるようになる。
それはアプローチが違っても、山口の考えているものと相反するものではない。彼のプランと上手くマージできれば二人の力を合わせて成果を出せると思う。
グループ企業の認証指導をいつまでに柳田企画に移管できるのか、これは吉井部長と話をしないとならないな。
*
*
*
3月某日
佐川は吉井部長に面談したいと時間を取ってもらう。
ここは小会議室だ。
![]() 「佐川も、次に何をしようかと迷っているのか?」
「佐川も、次に何をしようかと迷っているのか?」
![]() 「さすがお見通しですね。ISO14001も柳田企画に移管しないと、あちらも仕事が先細りでしょうし、環境部もいつまでも実行部隊を持っているようではまずいでしょう」
「さすがお見通しですね。ISO14001も柳田企画に移管しないと、あちらも仕事が先細りでしょうし、環境部もいつまでも実行部隊を持っているようではまずいでしょう」
![]() 「お前と話をしていて、環境部も期限付きとか
「お前と話をしていて、環境部も期限付きとか
あれは何年前だろうな?」
![]() 「私もそう言ったのを覚えています。あれは環境部設立前でしたから・・・5年前になりますか」
「私もそう言ったのを覚えています。あれは環境部設立前でしたから・・・5年前になりますか」
![]() 「5年前か、時の経つのは早いものだ。
「5年前か、時の経つのは早いものだ。
あのとき佐川は、環境部が発展的解消と言っていたな。・・・CSR部になるとか。
今仕事として持っている公害防止、省エネ、廃棄物、フロン、PCB、環境レポート、ISO認証支援などがあるが、そういうのはこれからどうなるんだ?」
![]() 「どうなるのかというより、吉井部長がどうするのかでしょう」
「どうなるのかというより、吉井部長がどうするのかでしょう」
![]() 「ざっくばらんに言えば、社内の空気は、もう公害の時代じゃない、ISOも終わった、となると環境部はいらないという方向だな」
「ざっくばらんに言えば、社内の空気は、もう公害の時代じゃない、ISOも終わった、となると環境部はいらないという方向だな」
![]() 「それは世の中全体の流れですね。1990年代中ほどはどこでも環境部とか類似の名前の部署を作るのが流行でした。しかし今年か来年に潮流が変わります」
「それは世の中全体の流れですね。1990年代中ほどはどこでも環境部とか類似の名前の部署を作るのが流行でした。しかし今年か来年に潮流が変わります」
![]() 「それも佐川の予言か?」
「それも佐川の予言か?」
![]() 「そうです、絶対に外れません。
「そうです、絶対に外れません。
環境部がなくなっても、元に戻るわけではありません。ISOの関係というより、経団連の環境憲章
とにかく多くの企業では環境部を解体、または守備範囲を広げてCSR全般とかに改組していきます。
環境部設立前の元の体制に戻すところは少なく、公害防止や省エネは全社統括機能をなくし、工場にお任せが多いですね。
 環境設計とかグリーン調達は設計部門や調達部門の手順に織り込めば済むかもしれませんし、いずれにしても製品固有なところがありますから、それで良いのかもしれません。
環境設計とかグリーン調達は設計部門や調達部門の手順に織り込めば済むかもしれませんし、いずれにしても製品固有なところがありますから、それで良いのかもしれません。
環境報告書はCSR報告書となってCSR部門あるいは広報部がすればおしまいです。
問題は、公害防止、省エネ、廃棄物などは工場だけで対応できるのかということ。
またオゾン層保護のフロン規制は終わりましたが、新たな規制として、懸案だったPCB処理はこれから始まります。
更にEUは鉛規制を始めますし、それに続いて含有化学物質規制を始めるでしょう」
![]() 「今度、未来プロジェクト主催の説明会を開くと聞いた。その説明会だけで良いのか? 全社挙げて対応せにゃならんのではないか?」
「今度、未来プロジェクト主催の説明会を開くと聞いた。その説明会だけで良いのか? 全社挙げて対応せにゃならんのではないか?」
![]() 「おっしゃるように進めるつもりです。まずは皆さんに、EU対応の重要性を理解してもらわねばなりません」
「おっしゃるように進めるつもりです。まずは皆さんに、EU対応の重要性を理解してもらわねばなりません」
![]() 「そういう
「そういう
![]() 「確かに事業本部とか工場に放り投げて、自分達でやれというのは無理でしょうね。フロン問題と同じように、研究所、海外拠点まで含めた活動が必要です。
「確かに事業本部とか工場に放り投げて、自分達でやれというのは無理でしょうね。フロン問題と同じように、研究所、海外拠点まで含めた活動が必要です。
EUの規制ですから、当然欧州拠点には担当者を常駐させるとかの、対応が必要なレベルです。
環境部解体したとき、そういう課題をどこが統括するのかとなります」
![]() 「先ほどの公害防止とか廃棄物も、全社統括を置くべきじゃないのか?」
「先ほどの公害防止とか廃棄物も、全社統括を置くべきじゃないのか?」
![]() 「私もそう思います。公害防止といっても、単なる維持じゃありません。亜鉛はまもなく規制値がとても厳しくなり、それを遵守するには製造工程も含めて技術開発が必要になります
「私もそう思います。公害防止といっても、単なる維持じゃありません。亜鉛はまもなく規制値がとても厳しくなり、それを遵守するには製造工程も含めて技術開発が必要になります
これには排水処理の設備メーカー任せでなく、社内の行程の見直しが必要となります。まさにオゾン層保護のフロン見直しと同じレベルの活動です。
このように公害防止と言っても単なる保守ではなく、技術開発それも設計や製造そして研究所も巻き込んだ活動が必要となります。
ただ世の中はそう
![]() 「そういうことを考えているとは、本社に担当者を置く必要があると、お前はそれに自推するつもりか?」
「そういうことを考えているとは、本社に担当者を置く必要があると、お前はそれに自推するつもりか?」
![]() 「私の考えているのは違います」
「私の考えているのは違います」
![]() 「面倒くさいことは嫌いか?」
「面倒くさいことは嫌いか?」
![]() 「吉井さんの言葉では、私は身勝手で面倒から逃げているように聞こえます」
「吉井さんの言葉では、私は身勝手で面倒から逃げているように聞こえます」
![]() 「気にするな、言葉の綾だ」
「気にするな、言葉の綾だ」
![]() 「私は工場や関連会社の環境担当者育成と環境監査を制度化したいのです。
「私は工場や関連会社の環境担当者育成と環境監査を制度化したいのです。
2002年頃から全国的に環境での違反とか事故が目立って増えてきます。一流大手の企業、製鉄とか製紙会社とか、そういうところで大気汚染、水質事故、記録改ざん、面白いように違反や事故が連続します。
当社では問題発覚はなかったようですが、関連会社では違反がいくつも見つかります」
![]() 「それは・・・・・・どういう」
「それは・・・・・・どういう」
![]() 「先ほど吉井部長は公害、省エネ、廃棄物と言った業務の統括業務を、本社からなくすようなことをおっしゃった。
「先ほど吉井部長は公害、省エネ、廃棄物と言った業務の統括業務を、本社からなくすようなことをおっしゃった。
私は無駄排除や効率化に反対しませんが、なくせないものもあるわけです。
私はこれからのそういう業務の枠組みを、吉井部長と私で決めておきたいと思います。仕組みを整えて後任者が動けるようにしたい。
お互い、何年どころか4月以降、今の職にいるかどうか分かりませんからね
ISO14001の序文に『組織が法律上及び方針上の要求事項を満たし続けることを(中略)確実に効果的であるものにするためには、体系化されたマネジメントシステムの中で実施し、かつ全経営活動と統合したものにする必要がある』とあります。
ISOの文句もいいのがあるでしょう。実践すべきです」
![]() 「そこで言うシステムとはどういう意味だね?」
「そこで言うシステムとはどういう意味だね?」
![]() 「システムとはコンピューターとかインプット・プロセス・アウトプットなどではありません。
「システムとはコンピューターとかインプット・プロセス・アウトプットなどではありません。
簡単に言えば、組織・機能・手順です。
組織とは、数人ならともかく大人数になれば部・課・係とするようなことです。機能とはそれぞれの部署の仕事を決めることで、手順とはこの仕事はどのように処理するかを決めることです。
考えてみれば簡単なことです。
吉井さんと私がいる間に、起こりえることに対しての方法を決めておけば後任に役立つでしょう」
![]() 「システムってそういう意味だったのか。英語圏にいてもよく分からなかったな。わしは『特定の目的のために連携して機能する仕組み』と思っていた」
「システムってそういう意味だったのか。英語圏にいてもよく分からなかったな。わしは『特定の目的のために連携して機能する仕組み』と思っていた」
![]() 「それは定義というより、外から見た姿というか情景でしょうね」
「それは定義というより、外から見た姿というか情景でしょうね」
![]() 「勉強になった。
「勉強になった。
それについては、わしもお前と相談したかったのよ、どうするかな」
![]() 「先ほど言ったように吉井さんと私で環境部がどうなろうと、しっかりしたシステムというか体制を作っておきたかったのですが・・・・・・
「先ほど言ったように吉井さんと私で環境部がどうなろうと、しっかりしたシステムというか体制を作っておきたかったのですが・・・・・・
今、お話ししていると残る時間はあまりなさそうですね。
誰が見ても私は本社に長居したようです。満6年になりました。人事もどこかに移動させたいと考えているでしょう。
とはいえ、年齢や賃金を考えると、引き取り手もないでしょうしね。
さて、どうしますか。この問題を放って、私が異動するのも寝覚めが悪いですし・・・
![]() 「いやそう決まっているわけでもない。今、環境部をどうするかは検討中だ。
「いやそう決まっているわけでもない。今、環境部をどうするかは検討中だ。
だがお前個人の身の振り方は心配することはない。お前を欲しいと言っているところは片手ではきかない。
仕事とか待遇はいろいろだがな。
まずは産業環境認証機関が来て欲しいと言っている。どうだ、お前の好きなISO審査だ」
![]() 「ISO認証ビジネスも寿命があります。私の引退までは認証ビジネスは続くでしょうけど、
「ISO認証ビジネスも寿命があります。私の引退までは認証ビジネスは続くでしょうけど、
想像するに、認証機関に出向したらやらされるのは、認証ビジネスの次になるものを検討せよということになりそうです」
![]() 「先を見ているお前にはそれまで分かっちゃうか」
「先を見ているお前にはそれまで分かっちゃうか」
![]() 「これは予言の話ではなく、月々の増分を見ていれば誰でもわかります。とはいえ、まだ多くの人は気づかないでしょうね。
「これは予言の話ではなく、月々の増分を見ていれば誰でもわかります。とはいえ、まだ多くの人は気づかないでしょうね。
あと2年したら認証機関の経営者は青くなりますよ」
![]() 「それから柳田企画だな。ISO認証だけでなく作業改善とか業務改善をさせたいという話が来ている」
「それから柳田企画だな。ISO認証だけでなく作業改善とか業務改善をさせたいという話が来ている」
![]() 「環境部をなくすかどうかは、環境部の定義付けもあります。過去数年の継続を考えることはありません。
「環境部をなくすかどうかは、環境部の定義付けもあります。過去数年の継続を考えることはありません。
RoHSやREACHの情報収集と、それを関連部門に周知するだけでも、十分存在意義はあるでしょう。職制ではなくプロジェクトかもしれませんが。
可能なら部員をブリュッセルとかルクセンブルクに常駐させロビー活動する案もありますね。
担当業務をどうするか、守備範囲をどうするか、取り合いをどうするかで、環境部の仕事も人員も変わります」
![]() 「なるほど、考えればやることはいくらでもあるのだな」
「なるほど、考えればやることはいくらでもあるのだな」
![]() 「環境部を解散とか発展的解消と言い換えるにしても、その機能はなくせません。
「環境部を解散とか発展的解消と言い換えるにしても、その機能はなくせません。
当社から必要な業務を除いてしまったら、行く末は小さなことから大きな問題を起こすでしょう。まさに千丈の堤も蟻の一穴からです。
環境部があろうとなかろうと、公害防止とか省エネはしなければならないことです。先ほど言った外国の環境法規制を調べて各工場や関連会社に情報提供することも必要です」
*
*
*
3月某日
本社の中会議室に長机と折り畳み椅子を並べて50名ほど座っている。
今日は佐川が欧州の鉛規制、含有化学物質規制の話だ。これも未来プロジェクトのお仕事である。
佐川が演壇で語っている。
![]() 「欧州の鉛規制の話は1994年頃から出ていまして、みなさんも対策を検討中と思います。
「欧州の鉛規制の話は1994年頃から出ていまして、みなさんも対策を検討中と思います。
今日、私はこれからどうなるか未来のお話をします。
明日の話をすると、鬼が笑うと言いますが、私は予言者と呼ばれていて、今まで予言したことは一つも外していません。
疑うのは勝手ですがとりあえず最後までお聞きください。
今まで、欧州の鉛規制を鉛フリーと呼んでいましたが、これから形がまとまって有害物質規制になります。そして名称も2002年、EUの官報でRoHSと称されます。
RoHSも1回こっきりでなく、何度も改定され規制対象も広く規制も厳しくなっていきます。最初のRoHS、後にRoHS1と呼ばれますが2003年2月に採択されます。ちょうど今から4年後になります。
規制対象物質は、鉛だけでなく、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)を加えた6物質です。
RoHS1の対象は8つのカテゴリー、大型家庭用電気製品、小型家庭用電気製品、情報技術(IT)機器および電気通信機器、民生用電気/電子機器、照明機器、電気/電子工具、玩具/レジャー/スポーツ用品、自動販売機です。
・
・
・
・
RoHS2と呼ばれる改定は2011年採択、2013年発効となります。
RoHS2ではRoHS1に医療機器、監視/制御機器とすべての電気電子機器(EEE)が加わります。これにはケーブル、およびスペアパーツも含まれます。
それにCEマーク表示も必要になります。
RoHS3は2015年に発行され、対象物質に成形品の可塑剤として使われているフタル酸エステル類で、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、DEHP)、ベンジルブチルフタレート(BBP)、ジブチルフタレート(DBP)、ジイソブチルフタル酸エステル(DIBP)が加わります。
ベトナム戦争の頃からフタル酸エステルの人体への危険性は知られていましたが
この他にも小改定があると思いますが、そこまでは分かりません。
 | ||||
|
||||
それからREACHの話をします。こちらはまだ表面化していないと思います。
REACHとはRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals(化学物質の登録、評価、認可および制限)のアクロニム
2001年・・・・・・再来年ですね、欧州委員会の「将来の化学物質戦略に関する白書」で1トンを超える化学物質は「登録」、100トンを超える化学物質は「評価」、そして特定の懸念物質は「認可」を義務付ける制度が提案されます。
これを基に2003年10月に制度案が採択され、具体的な法は2007年に発効します。
これはRoHSと大きく違い、規制というよりも情報公開要求といえるでしょう。製品の含有物質すべて、筐体も電子回路も機構部品もすべて何をいかほど含んでいるかを把握しなければなりません。
そして消費者から要請があれば、45日以内に製品に含まれる物質に関する情報を提供する義務があるというものです」
・
・
・
・
実を言って、佐川が関係者を集めての説明は度々あり、今回が初めてではない。だから一度でも佐川の話を聞いた人は、その後の体験から佐川が語ることを事実と認識している。
もっとも佐川の知識はマスコミ報道レベルしか知らないことも認識されている。
それでもどんなことが起きるのか数年前に知ることができればその価値は大きい。鉛フリーの話は1993年頃から出ていて今大詰めだが、そういう情報を少しでも早く知っていれば対応に余裕が取れる。更にどんな方法で対応したのかも、概略だけでもありがたい。聞いている方だってプロなんだから。
質問が多数あった。
![]() 「MSDSの提供が法で義務になるのは再来年のはずだ。MSDSでさえ100%入手できない状態なのに、材料の含有物質の詳細を出させるなんてできるのか?」
「MSDSの提供が法で義務になるのは再来年のはずだ。MSDSでさえ100%入手できない状態なのに、材料の含有物質の詳細を出させるなんてできるのか?」
![]() 「とにかくやらなくちゃ欧州で売れなくなるのですから、全業界が大騒ぎになります。そしてEUの規制に合わせて動き出します。やがてEUで決めた制度が全世界に広まり、日本国内でも同様な制度が作られます。
「とにかくやらなくちゃ欧州で売れなくなるのですから、全業界が大騒ぎになります。そしてEUの規制に合わせて動き出します。やがてEUで決めた制度が全世界に広まり、日本国内でも同様な制度が作られます。
MSDSは国連の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に準拠させることになり、2012年から呼び名からマテリアルが抜けてSDSと変わります」
![]() 「これからのことだけど、日本人のことだからRoHSもREACHも間に合わせちゃうんでしょう?」
「これからのことだけど、日本人のことだからRoHSもREACHも間に合わせちゃうんでしょう?」
![]() 「もちろんです。EU内の企業よりも早いでしょう。
「もちろんです。EU内の企業よりも早いでしょう。
EU統合したときISO9001認証が必須となりましたが、日本がEUより早く対応した。
RoHSやREACHでも日本は負けませんよ」
![]() 「なるほど黒船が来ても恐れることはない、乗っ取ればいいんだ」
「なるほど黒船が来ても恐れることはない、乗っ取ればいいんだ」
*
*
*
3月末
小会議室である。経営企画室 中山取締役、人事部 下山次長、環境部 吉井部長がいる。
![]() 「世の中はCSRに流行が移り、もう環境の時代じゃないと言ったのは下山君だったよな」
「世の中はCSRに流行が移り、もう環境の時代じゃないと言ったのは下山君だったよな」
![]() 「言ったかもしれません」
「言ったかもしれません」
![]() 「確かに企業では環境部門の看板をかけ替えるところが多いが、大学は環境を冠する学部や学科を作るところが多いようだ。
「確かに企業では環境部門の看板をかけ替えるところが多いが、大学は環境を冠する学部や学科を作るところが多いようだ。
これって大学は時代に遅れているのかな?」
![]() 「大学と言っても多数あります。確かに環境を冠する学部を創設とか従来からある学部に環境を追加したりしているところは今もありますね。
「大学と言っても多数あります。確かに環境を冠する学部を創設とか従来からある学部に環境を追加したりしているところは今もありますね。
いずれにしても、我々は周りを気にすることはありません」
| 中山取締役 |  |
下山人事部次長 |
||
 | 吉井環境部部長 |
|||
![]() 「先だっての話は環境部の役目は終了したという前提でしたね。
「先だっての話は環境部の役目は終了したという前提でしたね。
実はあれからいろいろ考えましたて、環境部という名前はともかく、今、環境部が担当している業務放り出すわけにはいかないという結論になりました」
![]() 「公害防止などは過去になったと思います。吉井部長は今も心配ですか」
「公害防止などは過去になったと思います。吉井部長は今も心配ですか」
![]() 「元々、公害防止は生産技術部にありました。新設備導入時の支援、事故時の対策支援、そういう仕事はなくなりません」
「元々、公害防止は生産技術部にありました。新設備導入時の支援、事故時の対策支援、そういう仕事はなくなりません」
![]() 「じゃあ、環境部解体したら担当者を生産技術に戻しますか?」
「じゃあ、環境部解体したら担当者を生産技術に戻しますか?」
![]() 「いや、もういないんだ。環境部ができて二三年目にもう必要ないだろうと、担当者2名を工場に異動させた。
「いや、もういないんだ。環境部ができて二三年目にもう必要ないだろうと、担当者2名を工場に異動させた。
ところが、先だってのダイオキシン問題から、公害規制が見直しというか全般的に厳しい方向に改正される見込みだ」
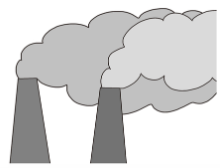
注:「所沢ダイオキシン事件」は、1999年2月テレビ朝日の「ニュースステーション」で報道された。
物語の1999年3月は、まさにマスコミも政府も各自治体も国民も、大騒ぎしている
![]() 「事故が起きてないなら良いのではないか?」
「事故が起きてないなら良いのではないか?」
![]() 「実は工場での事故というのは年に一二度起きているのです。昨年は佐川が兼務ですから、彼に工場に行ってもらいました」
「実は工場での事故というのは年に一二度起きているのです。昨年は佐川が兼務ですから、彼に工場に行ってもらいました」
![]() 「彼にできるなら、誰にでもできるでしょう。彼は公害防止なんて担当したことはないよ」
「彼にできるなら、誰にでもできるでしょう。彼は公害防止なんて担当したことはないよ」
![]() 「佐川は現場の作業者から課長までなりました。環境部門の経験はなくても、排水処理でも煤塵でも現場の経験者です。公害関係の資格も総なめです。
「佐川は現場の作業者から課長までなりました。環境部門の経験はなくても、排水処理でも煤塵でも現場の経験者です。公害関係の資格も総なめです。
それに彼の頭の良さと決断力、コミュニケーション能力、彼ほどのものはそういません。
問題が起きたら、彼一人派遣すれば安心していられます。
それは下山さんだってご存じじゃないですか?」
![]() 「奴は意外な特技があるものだ」
「奴は意外な特技があるものだ」
![]() 「現在の環境部の機能としては、公害防止、省エネ、廃棄物、フロン、化学物質管理、PCB、環境レポート、ISO認証支援などがあります。
「現在の環境部の機能としては、公害防止、省エネ、廃棄物、フロン、化学物質管理、PCB、環境レポート、ISO認証支援などがあります。
省エネもますます厳しくなるでしょう。昨年(1998)も改正がありましたが、2002年、2005年、2008年と改正が続きます。
それは佐川の予言ですがね」
![]() 「どこに行ってもどんなことでも佐川、佐川か。彼の予言は有用かもしれないが、彼に頼りすぎると、とんでもないことになるぞ」
「どこに行ってもどんなことでも佐川、佐川か。彼の予言は有用かもしれないが、彼に頼りすぎると、とんでもないことになるぞ」
![]() 「彼の能力を予言だけと捉えるのは間違いです。彼は予言などなくても能力があります。未来から戻る前に、高卒では真っ先に課長になっています。
「彼の能力を予言だけと捉えるのは間違いです。彼は予言などなくても能力があります。未来から戻る前に、高卒では真っ先に課長になっています。
本社に来てからも、ISO9001認証が大きく遅れていたのを、審査までひと月半というときに彼が挽回し認証したのはもはや伝説です。
それに環境部解体という発想も、佐川がいたから思いついたわけです。
数日前ですが、21世紀すぐにEUで化学物質規制が厳しくなると、佐川が説明会をしていましたが、ああいうのを見ていると、彼がいなくなったらどうしたらよいか悩みます」
![]() 「吉井部長の話は、環境部解体はできないということですか? それとも佐川がいればできるということですか?」
「吉井部長の話は、環境部解体はできないということですか? それとも佐川がいればできるということですか?」
![]() 「佐川に頼っている部分は大きいというのは事実です。もちろん彼に頼らない体制にする必要があります。
「佐川に頼っている部分は大きいというのは事実です。もちろん彼に頼らない体制にする必要があります。
その体制を確立する前に、環境部解体はできないと考えているということです。
公害とか省エネとかそれぞれの分野ごとに、専門家を育てれば大丈夫でしょう。しかしそれには、最低でも2年位必要です」
![]() 「今更そんなことを言うとは、今までの管理が問題だぞ」
「今更そんなことを言うとは、今までの管理が問題だぞ」
![]() 「その通りです。
「その通りです。
私も環境業務の経験がなかったもので、彼の立ち回りを見ていて、それを当たり前のレベルと思っていました。
未来プロジェクト兼務となってからも、ISO関係は彼が取り仕切っていたし、公害担当がいなくなっても彼が皆処理していました。
管理者として反省しています」
![]() 「環境担当者の多くが佐川以下と聞こえますね」
「環境担当者の多くが佐川以下と聞こえますね」
![]() 「そう言いました」
「そう言いました」
![]() 「ということは、環境部を廃するにしてもしなくても、佐川が必要か、彼を埋めるには数人投入が必要ということになる。
「ということは、環境部を廃するにしてもしなくても、佐川が必要か、彼を埋めるには数人投入が必要ということになる。
環境部が不要どころか補強が必要ということですよ。そんな話通りませんよ」
![]() 本日の反省と誓
本日の反省と誓
振り返ると、上品なお話しか書いていない。
実際の審査はこんなものじゃなかった。
先生と呼ばれないと返事せず、対応する人の声が小さいと聞こえないと怒鳴った。普通のことです。
灰皿が飛んだのは書いたが、飛ぶのは灰皿ばかりでなく、それ以外のものも飛んだ。
ファイルも飛んだし、罵声も飛んだ。それは書いていない。
ISO審査は上品なものではなかった。リアルというマンガ
まだ書いてない審査員の不祥事、不名誉、無様、不細工は数知れない。
書いてはいけないようなものは別として、軽いものは書いてみようか。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
1991年に制定した。その後、環境問題の変化に合わせて2〜4年で見直しを重ねている。 | |
| 注2 |
2006年に、亜鉛の排水基準はそれまでの5 mg/Lから2 mg/Lになった。 これは直ちには達成困難という理由で、いくつかの業種(10業種程度)には暫定排水基準が設定され、猶予措置がとられた。 | |
| 注3 |
ベトナム戦争で傷病兵の点滴のチューブにフタル酸エステルが可塑剤に入っていて、症状が急変して大問題になった。 | |
| 注4 |
アクロニム(acronym)とは英語で単語の頭文字をつないでひとつの単語として読むもの。 例:NATO(North Atlantic Treaty Organization)ナトーではなくネイトーと聞こえる。 NASA(National Aeronautics and Space Administration)ナサでなくナアサと聞こえる。 アルファベット通り読むのはイニシャリズムと呼ぶ。 例:FBI(Federal Bureau of Investigation)エフビーアイ CEO(Chief Executive Officer)シーイーオー | |
| 注5 |
「リアル」、井上雄彦、集英社、既刊16巻、1999〜 泣きたかったら読みましょう。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |
