注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1999年4月となった。
環境部の発展的解消(?)の話はなくなったようで、むしろ公害防止、省エネ、廃棄物に各1名と3名も増員している。
それを聞いて佐川はまっとうなことだと思う。環境保護とかCSRというのは

| |
| 吉井部長 |
異動の噂のあった吉井環境部長は、相変わらず環境部長の椅子に座っている。ただ彼は今まで事業所長級(工場長・支社長と同格)の資格だったが、今度新たに設けられた執行役員
ならば環境部の位置づけも、人事部や経理部と同じくワンランク上がったのかというと、そうではない。
大佐が中隊長をするようなアンバランスだが?
実を言って佐川にとっては偉い人が異動しようとあまり影響はない。今までだって、吉井部長と話すなど月に何度もなかった。佐川のレベルでは社内政治とは無縁だ。
おっと、佐川に異動の話はまったくなく、相も変わらず環境部と未来プロジェクト兼務である。
佐川の環境部のお仕事であるISO14001認証は順調であり、今年度中に柳田企画に移管してしまう。山口はそうなれば環境部から生産技術部に戻り、マネジメントシステムの見直しをしたいと言っていた。
ISOの見直しをするのかと聞くと、ISOとは関係なく、真に会社に役立つ仕組みを考えたいと言っていた。
ただ認証ビジネス界隈の話では、情報セキュリティのマネジメントシステム
そんなことを佐川が言うと、それは4年も先でしょう。それまでにQMSの大幅見直しをすると見得を切った。
佐川はISO14001を柳田企画に移行した後、しばらくは指導支援があるだろうが、ゆくゆくはISOと縁が切れるだろう。
未来プロジェクトでの仕事は、第一義にはこれから起きることの情報をまとめてプロジェクトメンバーに周知を図り、その活用方法のまとめ役である。
こちらも覚えている限りのものは書き出して、メンバーに周知している。
第二義には未来の知識を基にビジネスやリスク予防のアイデアを出すことだ。
いずれにしても新しい情報はないわけで、もうこの仕事は終わりだなと考えている。

| |
| 佐川 |
ところで、メンバーは佐川を除き6名いるが、皆、知り得た情報で何かしら蓄財をしているだろう。株価の日々の上がり下がりは分からないにしても、数か月単位の情報があれば、十分投資で稼げるはずだ。
それは会社の財産(情報)を盗んでいるような気もするが、ダメと言っても禁じる手段はなさそうだ。
佐川も
だから情報を提供した自分は該当しないと考えている。それはご都合主義だろうか?
さてそんなことで佐川は暇になったのかというと、実は新しい仕事が増えた。
| 環 境 部 | |
公害も廃棄物も省エネも、工場が
このためいろいろ支障があった。
例えば、廃棄物や使用水量など環境報告書用の数値は、毎年度首に各工場から報告してもらい、本社の環境報告書担当がまとめている。報告書担当のぼやくこと・・・
新設備導入を計画する際には、法規制やその設備の評価など、伝手もない田舎の工場では調べようもない。
職制改正があったとき、これでよいのかなと思ったが、しばしの間、大きな問題もなく時は過ぎた。
問題が起きたのはそれから1年経った1年前だ。当時はISO14001の認証も、要領を得たので、死ぬほど忙くもなくなった佐川に、吉井部長が面倒見てくれんかと対応を頼んだ。
佐川は「面倒を見てくれ」を、その業務を担当せよではなく「今顕在化したトラブルを解決してくれ」と理解した。
吉井部長は管理者としてまともな方だと思うが、同時に予告なしに担当を変えたり異動を命じたりするので「唐突の吉井」と呼ばれている。油断はできない。
問題は産業廃棄物を、分工場から本工場に県境をまたいで自社運搬していたことだった
現場にいたときは排水処理設備も廃棄物も日常の仕事だった。そんなことをしていたのを思い出して軽く引き受けた。
現地に行って顛末と善後策を行政に説明して、お小言を頂いて落着した。状況によるが、この程度で直罰はない。
だが工場対応のお仕事はそれひとつで済まなかった。問題が起きるたびに佐川に投げられる。しかも不思議と問題が続く。
更に問題と言えない工場からの相談に対応すると、なぜか相談が急増した。
 現地に行くものも月に数件はあるし、電話での相談は毎日のようにある。
現地に行くものも月に数件はあるし、電話での相談は毎日のようにある。
どんなものかというと、多種多様だ。
構内の配管が劣化して廃酸が公共河川に流出した、深夜の騒音測定値が協定超えた、マニフェスト票の重量が合わない、市の焼却炉までの運搬を構内外注に依頼しているがいつも乗車している社員が車に乗らずに運んだ
電話相談もあり、メールで来るものもあり、現地出張もありと、佐川は結構忙しくなった。メール処理だけでも毎日2〜3時間は取られるのだ。
佐川も最初は、環境部の中では工場の現場経験者は自分しかおらず、自分が手伝うのももっともだと思ったが、このような状況が恒常化すると、これはたまらない。未来プロジェクトにも迷惑をかけるようになる。
吉井部長に「業務が変わらないのに人を減らした付けが回った。対策しないと問題です」と報告はした。当然というべきか、なにも手を打つ様子もなく1年が過ぎた。
そういう経緯があって、やっと公害防止などの担当が配属されたというわけだ。
佐川は解放されたのではなく、3人の教育が新たな仕事に増えた。3人が一人前になるまで、今までの工場や関連会社からの相談対応もしなければならない。
一応3人とも工場での経験が2・3年あるというし、担当していたものの資格も持っている。さすがエネルギー管理士は年齢的に資格取得の要件
公害防止と言っても典型7公害といわれるように大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7種類あるわけだ。それに工場で排水処理していたにしても、大気汚染は知らないだろう。
まあ、地盤沈下は現代ではないだろうけど
廃棄物はカテゴリーとしてはひとつだが、非製造業も関わるから該当事業所はものすごい数になる。それに廃棄物は規制が複雑で問題だ。
省エネに至ってはひとりでできるものではない。できるのは改善活動のとりまとめとかテクノロジートランスファーくらいだろう。守備範囲がどこまでなのかだが・・・・・・
全体を一言で言えば、皆半人前、あと少しでその担当を一通り理解でき、全社と関連会社の指導監督には2年必要だろう。
だから教育するのは、初歩的なことや関係ないことはなしで、当社グループ保有設備の概要、関係する法規制のおさらい(縁のない法律は知る必要なし)、異常発生時の対処方法、そんな所だろうと佐川は思った。 実際はそれでも簡単ではないのだが・・・・
具体的な計画をどうしようかと考えていると、吉井部長から声がかかった。
*
*
*
![]() 「先日お前から聞いたが、あと2年ほどすると、いくつもの大手企業で環境法違反や環境事故が多発すると言ったな
「先日お前から聞いたが、あと2年ほどすると、いくつもの大手企業で環境法違反や環境事故が多発すると言ったな
注:2000年頃から環境事故や違反が増えたかという問いには、統計的には増えたとは言えない。
だが報道件数及びその論調から、環境事故や違反が増えたと認識されたことは間違いない。
その結果、社会的にその原因である企業の管理不十分、怠慢、違法行為が批判された。
とくに有名企業、大企業が多くマスコミから叩かれた。
![]() 「はい、2000年頃から多発しますね」
「はい、2000年頃から多発しますね」
![]() 「お前は前世では当時、既に退職していたから、この会社の状況は知らないと言った」
「お前は前世では当時、既に退職していたから、この会社の状況は知らないと言った」
![]() 「はい、そうです」
「はい、そうです」

![]() 「わしは環境部として、その問題が噴出しないように何をすれば良いか考えている。
「わしは環境部として、その問題が噴出しないように何をすれば良いか考えている。
それで、今すぐすべきこと、半年後にすべきこと、恒久的にすべきこと、そんなふうにお前の考えを教えてくれ」
![]() 「今すぐすることは、遵法点検に特化した環境監査の実施です。現状を知らなければ何もできません。
「今すぐすることは、遵法点検に特化した環境監査の実施です。現状を知らなければ何もできません。
できればそれを恒久的なものにしたいです」
![]() 「環境監査など定期的にしている業務監査の一環としてやっている。
「環境監査など定期的にしている業務監査の一環としてやっている。
環境だけでなく、品質、輸出管理などについて、各工場の部長級で相互監査しているぞ」
![]() 「あれは監査じゃありません。他工場ではどんなことをしているか、見学しているようなものです。
「あれは監査じゃありません。他工場ではどんなことをしているか、見学しているようなものです。
監査とはしっかり監査基準を決め、それへの適合・不適合を判定することです」
![]() 「よく分からん。お前の言う監査とは何だ?」
「よく分からん。お前の言う監査とは何だ?」
![]() 「監査とは、指導とか設備や作業を点検することではありません。
「監査とは、指導とか設備や作業を点検することではありません。
監査すべきことについて、それが適正になされているか否かを点検することです」
![]() 「監査すべきこととは何だ?」
「監査すべきこととは何だ?」
![]() 「監査とは監査員が好き勝手にするものではありません。
「監査とは監査員が好き勝手にするものではありません。
経営者あるいは監査責任者が、監査してほしいものの調査を命じるからするのです。まあ恒常的に行っている監査は、監査事項を会社規則で決めていることも多いですけどね。
監査すべきこととは経営上必要なことであり、その都度点検項目が変わります。
例えば他社で事故が起きたら、類似の設備に関わることでしょうし、法違反が起きれば遵法監査を命じると思います」
![]() 「ISO14001の内部監査では遵法点検としては不足か?」
「ISO14001の内部監査では遵法点検としては不足か?」
![]() 「ISO14001で要求している内部監査では、監査基準はISO規格と会社が決めた規則です
「ISO14001で要求している内部監査では、監査基準はISO規格と会社が決めた規則です
遵法を見るのが目的ではありません」
![]() 「ISOの内部監査は、その違反とか事故防止に役に立たないのか?」
「ISOの内部監査は、その違反とか事故防止に役に立たないのか?」
![]() 「うーん、役に立たないとは言いにくいですが・・・・・・規格要求と会社のルールが監査基準なら、ルールは決めたか、決めたことを文書にしたか、その通りしているか、記録はあるかを点検します。
「うーん、役に立たないとは言いにくいですが・・・・・・規格要求と会社のルールが監査基準なら、ルールは決めたか、決めたことを文書にしたか、その通りしているか、記録はあるかを点検します。
それに工場でISOの内部監査員になっている人たちは、環境技術も環境法規制も知りませんよ。
足りないものばかりです」
![]() 「何が足りないのだ?」
「何が足りないのだ?」
![]() 「今現在、法律を守っているか、事故や不具合が起きないようになっているかを点検していません」
「今現在、法律を守っているか、事故や不具合が起きないようになっているかを点検していません」
![]() 「業務監査でもそれを点検していないのか?」
「業務監査でもそれを点検していないのか?」
![]() 「先ほど吉井部長は、各工場の部長級が相互監査をしているとおっしゃった。
「先ほど吉井部長は、各工場の部長級が相互監査をしているとおっしゃった。
吉井部長が工場に行って工場の現場を歩き、法の届け出の記録をご覧になって、法を守っているか、設備の運転はまっとうかを見ていますか? 違反とか届が漏れているとか気がつきますか?」
![]() 「気が付かないな、いやそもそもチェックする項目さえ知らん」
「気が付かないな、いやそもそもチェックする項目さえ知らん」
![]() 「私が工場にいたとき、業務監査があり、環境のパートの対応をしました。私は環境部門ではありませんでしたが、自分の職場の毒劇物の管理とか排水処理施設などの運転をしていましたから。
「私が工場にいたとき、業務監査があり、環境のパートの対応をしました。私は環境部門ではありませんでしたが、自分の職場の毒劇物の管理とか排水処理施設などの運転をしていましたから。
当然、日々の記録とか有資格者の届、検認などの点検をするなら、私が説明しなければなりません。しかし記録を出せとか会社規則集を出せと言われませんでした。
聞くのは通り一遍の当たり障りのない事ばかりです。
監査の手法も知らず、法規制も知らずでは、遵法監査ができるわけありません」
![]() 「しかしISO審査だって内部監査だって、法の遵守は確認するだろう?」
「しかしISO審査だって内部監査だって、法の遵守は確認するだろう?」
![]() 「ISO審査は遵法確認ではないと明記されています
「ISO審査は遵法確認ではないと明記されています
またISOの内部監査でも法対応の手順は会社規則に定めてあるでしょうけど、もし違反が起きていても、会社規則に基づいて行政報告をして法に則り是正処置をすればルール通り仕事をしていることになり適合判定でしょうね
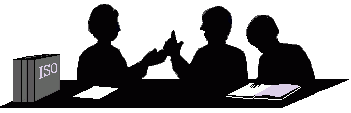
ISO審査では法の遵守を見ないことになっています。そしてもし認証している会社で違反や事故があれば、審査で嘘をつかれたとか、見せてもらえなかったというのが決まり文句です。
見ないことになっているなら、法違反があっても審査対象外と言って欲しいですね。こちらは違反をしても嘘はついていませんから」
![]() 「あまりそんなことを言うなよ。まあ報道を見るとそういう感じはするな
「あまりそんなことを言うなよ。まあ報道を見るとそういう感じはするな
法の遵守と言ってもたくさんあるよな、全項目を調べるのか?」
![]() 「それは監査方針と状況によりますね。
「それは監査方針と状況によりますね。
原則として監査では全数見るわけではありません。そもそもラインの管理者が、日々、全数確認しているはずです。
部下の行動と成果を点検する責任は管理職にあり、検印は点検した証拠です。
監査の目的次第ですが、一般的にはまっとうに管理され運用されていることを前提に行います。それゆえ抜取になります。
ISO14001の審査も内部監査もそういう方法ですね」
![]() 「ええと結論として、遵法点検に徹した環境監査をする必要があるのだな?」
「ええと結論として、遵法点検に徹した環境監査をする必要があるのだな?」
![]() 「吉井部長の要求を満たすにはそうなります」
「吉井部長の要求を満たすにはそうなります」
![]() 「・・・その遵法点検は抜取で良いのか?」
「・・・その遵法点検は抜取で良いのか?」
![]() 「監査にも全数も抜取もあります。それは監査項目の重要性と調査項目の状況によって選択されます。
「監査にも全数も抜取もあります。それは監査項目の重要性と調査項目の状況によって選択されます。
今回は事前情報がありませんから、
その監査の結果、問題だらけなら是正をしっかりフォローして、安心できるレベルまで持ち上げないとなりません。
監査して見つかった不具合を指導も是正の確認もせずに、再度、監査して悪い悪いと言っても詮のない話です」
ISO14001:1996の序文に「レビューと監査を行っただけでは、組織のパフォーマンスが法律上及び(会社の)方針上の要求事項を満たし続けることを保証するのに十分ではないかもしれない」とあり、だから「マネジメントシステムを構築する必要がある」と続く。
これは正しくは、「しっかり監査をし、レビューをしろ。それができたらマネジメントシステムもしっかりするのだ」と書くべきだったのだ。
本来ならISO規格はレベルが低かろうが当たり前のことを書くべきだった。しかし規格制定者が、レベルの低いことは書きたくなかったのか、そういう記述はない。だから誰も基礎をしっかり整えず、規格に書いてあることを形ばかりしたに過ぎない。
その結果は、ろくなことにならないのは自明だ。
![]() 「全数点検して遵守状況が安心できれば、あるいは是正完了した以降は、抜取で良いとなります。もちろん次回は前回監査以降が監査対象となりますから、点検するボリュームは大幅に少なくなります。
「全数点検して遵守状況が安心できれば、あるいは是正完了した以降は、抜取で良いとなります。もちろん次回は前回監査以降が監査対象となりますから、点検するボリュームは大幅に少なくなります。
ご注意を申し上げますが、監査は抜取検査のように統計的な理論付けがされていません。
検査のAQL(合格品質水準)は、顧客指定によるか、社内で決められるなら費用対コスト
しかし監査でのAQLは指定されていません。それで抜取方法も抜取数も、統計の理論的裏付けはありません。
統計的根拠なく適当に抜取って検査するのを、スポットチェックと言いましたっけ? そんなレベルです」
注:ラインの品質確認のために統計的手法ではなく、少数を抜き取って確認することを「スポットチェック」とか「チェック検査」などと現場で呼ぶ。
JIS規格で使われているかと調べたら、「スポットチェック」という語句を使っているJIS規格は3件あったが、「スポットチェック」の定義はされていなかった。
![]() 「それはISO審査でも同じだな?」
「それはISO審査でも同じだな?」
![]() 「そうです。ISO審査の規格
「そうです。ISO審査の規格
![]() 「ならISO認証した企業が不祥事を起こしても、認証機関はそれは理論上発生すると言っても良い。それなのに、なぜ嘘をつかれたというのかな?」
「ならISO認証した企業が不祥事を起こしても、認証機関はそれは理論上発生すると言っても良い。それなのに、なぜ嘘をつかれたというのかな?」
![]() 「それは理屈上ありえると言えば、今までISO認証すると品質が良くなるとか会社が良くなると言っていたのが、誇大広告だとバレるからではないのですかね?
「それは理屈上ありえると言えば、今までISO認証すると品質が良くなるとか会社が良くなると言っていたのが、誇大広告だとバレるからではないのですかね?
そこをごまかすためにまっとうな理屈なく暴走して、談合があればQMS認証取消し、品質問題があればEMS認証取り消しとエスカレートしたのでしょう。
某認証機関の取締役に、認証した企業でセクハラ問題
もうメチャクチャというかデタラメですよ、認証機関は社会におもねて漂うだけです。呆れました。
いつからISO認証は会社の品格審査になったのですか」
注:セクハラ云々の話は実話である(認証機関名と取締役の名は秘す)。
また某消費者団体の女性幹部は、ISO認証企業に騙されたと語っていた。
私はISO認証企業は品質が良いと推奨したり、本人は買うときにISO認証の有無を見ていたのかと聞いた。そういうことはしていないという。
じゃあ、今までISO認証なんて無視していたのではないですか?
何を騙されたのか、どんな被害を受けたのか、もう頭がまともとは思えない。
![]() 「なるほど、一度嘘をつくとごまかすほどに嘘が重なり、ドツボにはまる。
「なるほど、一度嘘をつくとごまかすほどに嘘が重なり、ドツボにはまる。
ところで監査で不適合があれば是正確認をするだろう。是正確認は監査した者がしなければならないのか?」
![]() 「そこはまたいろいろ考えがあります。ISO審査では審査した審査員が是正確認しますね。
「そこはまたいろいろ考えがあります。ISO審査では審査した審査員が是正確認しますね。
私は良くない方法だと思っています。
特に遵法監査ですと、最初の判断も是正確認も責任重大です。審査した人が間違えれば、是正確認を同じ人がしても間違いを検出できません。
ですから私は審査をした人以外が、是正確認をすべきと思います。監査と是正確認の実施者が変わればダブルチェックになりますから、信頼性は高くなります」
![]() 「うーん、なるほど。だがそれをするには一定レベル以上の人間が複数必要になる」
「うーん、なるほど。だがそれをするには一定レベル以上の人間が複数必要になる」
![]() 「そうです。でも遵法を確実にするためには監査だけでなく、工場の担当者のレベルアップをしなければならず、レベルが上がれば事故も違反も減る。それに環境監査の監査員として工場の担当者を活用できます」
「そうです。でも遵法を確実にするためには監査だけでなく、工場の担当者のレベルアップをしなければならず、レベルが上がれば事故も違反も減る。それに環境監査の監査員として工場の担当者を活用できます」
![]() 「そこまで考えているか」
「そこまで考えているか」
吉井部長はしばし沈思黙考する。
![]() 「今すぐ工場の遵法監査をしろと言えば、お前はできるか?」
「今すぐ工場の遵法監査をしろと言えば、お前はできるか?」

![]() 「力量的には勿論できます。ただ負荷的な意味では、いくつの工場を監査するかですね。
「力量的には勿論できます。ただ負荷的な意味では、いくつの工場を監査するかですね。
規模によりますが、ひとつの工場で最低3日、特定施設が多ければ1週間はかかるでしょう。二人でしても三日。
できるなら今度異動してきた3名を教育して、彼らにやらせたいところです」
![]() 「やってみないと分からないだろうが、お前は当社の環境遵法のレベルはいかほどと思う?」
「やってみないと分からないだろうが、お前は当社の環境遵法のレベルはいかほどと思う?」
![]() 「特定施設設置には大金がかかります。ですから本社が認可しないと予算が取れません。本社は金を出したくないですから穴が開くほど漏れがないか確認します。
「特定施設設置には大金がかかります。ですから本社が認可しないと予算が取れません。本社は金を出したくないですから穴が開くほど漏れがないか確認します。
それで届出漏れとか資格者がいないということはないでしょう。
ただ時が経てば、資格者の交代とか事業所長の異動の際の届け出漏れは発生するでしょうね」
![]() 「あっ、2年前、本社の環境保全課を廃止したから、それ以降、本社で二重チェックをしてないぞ」
「あっ、2年前、本社の環境保全課を廃止したから、それ以降、本社で二重チェックをしてないぞ」
![]() 「そうでしたね。あのとき何故と思いました。
「そうでしたね。あのとき何故と思いました。
あれから1年ですか、それでさまざまな不具合が現れてきたのでしょうね。やはり本社に工場の環境管理支援担当は必要ですね。
管理された状態を見て、手抜きすると足をすくわれます。多くの場合、管理者が汗をかいて頑張っているのは見えないものです」
![]() 「環境保全課を廃止した俺への嫌味か?
「環境保全課を廃止した俺への嫌味か?
まっ、それは真実ではあるな
メモ、メモと・・・・・・
排水とかばい煙の測定などは大丈夫か?」
![]() 「どうでしょう、規制を外れたとき、中には環境測定会社に頼んで、日付とか数字をいじってもらっているかもしれませんね」
「どうでしょう、規制を外れたとき、中には環境測定会社に頼んで、日付とか数字をいじってもらっているかもしれませんね」
注:環境計量士が虚偽の記載をするのは違反である。だが過去に報道されている。
![]() 「環境監査では誤解を招く、環境遵法監査と呼ぼう。
「環境監査では誤解を招く、環境遵法監査と呼ぼう。
環境遵法監査をすれば、違反や事故はなくなるか?」
![]() 「監査は遵法や事故防止の施策ではありません。不具合を見つけることです。
根本的な対策は設備のスペックの再検証と、不備な点があれば対策すること。その運用手順をしっかりと定めること。
「監査は遵法や事故防止の施策ではありません。不具合を見つけることです。
根本的な対策は設備のスペックの再検証と、不備な点があれば対策すること。その運用手順をしっかりと定めること。
多くの場合、製造や測定の設備や機器には作業標準を決めていますが、設備や建屋には保全標準をしっかり定めず、個人のスキルに依存していることが多いのです。
そして担当者には必要な資格を取らせよく訓練させること。
そのためにはお金をかけることです
いずれにしても現状把握と問題検出のために一度徹底した遵法監査をせねばなりません。恒久的にも定期的な実施は必要です。
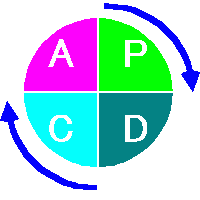 PDCAと言いますね。チェックは改善プロセスの重要な作業です」
PDCAと言いますね。チェックは改善プロセスの重要な作業です」
注:監査はPDCAのチェックである。アクションは経営者/管理者の仕事だ。
![]() 「今5月上旬か、やろうとすれば最速でいつ頃できる?」
「今5月上旬か、やろうとすれば最速でいつ頃できる?」
![]() 「いくつ工場の監査をするかですね。それと工事やオフィスも環境法と関わります。
「いくつ工場の監査をするかですね。それと工事やオフィスも環境法と関わります。
トライアルするなら製造業、支社、関連会社の販売会社、工事会社、倉庫、運送などいろいろな業種を監査したほうがよろしいでしょう」
![]() 「非製造業とかオフィスが、環境法と関係あるのか?」
「非製造業とかオフィスが、環境法と関係あるのか?」
![]() 「廃棄物はどこでも出ます。オフィスから出るプラスチックや金属は産業廃棄物になります。ホチキス、販促物、什器みな産廃です。
「廃棄物はどこでも出ます。オフィスから出るプラスチックや金属は産業廃棄物になります。ホチキス、販促物、什器みな産廃です。
それに今では省エネはすべての業種で義務ですしね」
![]() 「うーん、監査員を育成するとして何名必要だ」
「うーん、監査員を育成するとして何名必要だ」
![]() 「監査を何人でするかもあります。また監査専門の人を置くのか、本社と工場の環境担当者が組んでするのもありです。
「監査を何人でするかもあります。また監査専門の人を置くのか、本社と工場の環境担当者が組んでするのもありです。
監査に要する時間ですが・・・・・・私も素人じゃないと思いますが、一つの工場の監査をするとなると1週間はかかるでしょうね。
それより大事なのは監査の位置づけです。社内の監査は、会社規則で監査部がすることになっています。環境部が断りなしに始めて、越権行為と叱られても困ります。
ISOの品質監査とか環境監査は、監査の規則のものと違い経営者に報告されないので、監査部監査とは扱いが違うのです。みそっかすですね。
今吉井部長がお考えの環境遵法監査は、社長報告に値すると思いますので、監査部とトラブラないように、監査部と話を付けないとなりません」
![]() 「なるほど・・・・・・」とメモを取る。
「なるほど・・・・・・」とメモを取る。
![]() 「吉井部長が2年後を気にしているなら、今ひと月ふた月どうってこともないでしょう。私が例の3人を教えるのにふた月ください。
「吉井部長が2年後を気にしているなら、今ひと月ふた月どうってこともないでしょう。私が例の3人を教えるのにふた月ください。
吉井部長は監査部と調整してください。方法としては、例えば監査部の下請けとなって代行するという考えもあります」
![]() 「会社の機能としてはそれがまっとうかもしれんな。
「会社の機能としてはそれがまっとうかもしれんな。
よし、監査部との調整、実施対象、時期などはワシが考える。お前は例の3名の教育を頼む。
7月には仕事ができるようにもっていってくれ」
![]() 「承知しました・・・と言いたいのですが、未来プロジェクトの
「承知しました・・・と言いたいのですが、未来プロジェクトの![]() 佐山さんと話はしておいてください」
佐山さんと話はしておいてください」
![]() 「ちょっと待て、そもそも2000年頃に環境不祥事多発というのも予言だよな。いや、未来プロジェクトの成果であるわけだ。
「ちょっと待て、そもそも2000年頃に環境不祥事多発というのも予言だよな。いや、未来プロジェクトの成果であるわけだ。
お前が佐山さんに問題をあげて、未来プロジェクトが環境部に報告し、対策を依頼するのが筋だ。
そして環境部を未来プロジェクトのお前が支援するということになる」
![]() 「吉井部長の口が上手いのには、参りました。さすが『唐突の吉井』ですね」
「吉井部長の口が上手いのには、参りました。さすが『唐突の吉井』ですね」
![]() 「すぐやれ、佐山さんから話が来るのを待っている」
「すぐやれ、佐山さんから話が来るのを待っている」
![]() 本日のペンディング
本日のペンディング
上品じゃない話を書こうかと思ったのですが、モロに書けば差しさわりあるかと気になります。
それでしばし考慮中と・・・・・・
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
執行役員という名称は1997年にSONYが導入したのが始まりで、その後、多くの企業が採用を始めた。 執行役は会社法で定められた役員であるが、執行役員は法で定められた役員ではなく、企業が定めた従業員である上級管理職のことが多い。 | |
| 注2 |
ISO27001とはISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)のISO規格である。 ISMSの考えは情報をコンピュータにセーブし処理するのが広まった1980年頃から「情報システム安全対策実施事業所認定制度」が作られていた。 イギリスでは1995年にBS7799発行された。これはハード、ソフト、業種などによらず情報セキュリティに焦点をあてた規格であった。 BS7799を基に、情報セキュリティの国際規格が検討され、ISO/IEC27001が2005年に発行された。 日本では認証ビジネスが2000年頃から頭打ちとなり、QMS、EMSに続くものとしてISMSが期待されていた。 | |
| 注3 |
難しく考えると事前協議とかいろいろ疑問はあるが、単に不要物を集めて廃棄するかしないかを社内検討していると考えると、運んでいるものは廃棄物ではなく、問題でさえない。 | |
| 注4 |
排出する廃棄物を自社運搬できるのは排出者のみというのが元々の条文だった。これが排出者の管理下にあるなら産業廃棄物収集運搬の許可がなくてもできるとしたのは、小泉首相の行革で2005年である。それ以前は違法である。 ・環廃産発第 050325002 号 | |
| 注5 |
エネルギー管理士試験の受験資格は特にない。しかし試験合格しても実務経験がなければエネルギー管理士にはなれない。実務経験不足の人は、試験合格後に業務について経験を満たして審査を通れば、晴れて資格が取れる。 私の友人も試験は合格したけど法で定めた業務に就くことができず、資格が取れなかった。 蛇足であるが、公害防止管理者にも試験合格してもなれないのをご存じか? 公害防止管理者とは特定施設の責任者として届け出された者を言う。特定施設がなければ資格があっても公害防止管理者にはなれない。公害防止管理者試験とは公害防止管理者になるための資格試験である。 | |
| 注6 |
高度成長時期は工場が地下水を汲み上げたために地盤沈下が各所で起きた。そのために地下水利用の制限、河川水への切り替えが行われ、1980年以降は新たな問題は起きていない。 ただ一旦地盤沈下を起こしたところは回復していないところが多い。 | |
| 注7 |
この物語の中では、佐川は2000年頃から大企業の環境法違反、環境事故が多発すると語っているが、実際は2000年から急に発生したのではなく、1998年頃から地下水汚染や不法投棄の報道が増えている。 それは住民の環境意識(要するに生活環境が悪くなるとすぐに苦情を言う)の変化と、ISO認証企業が違反・事故を起こすとニュースバリューがあると思われたのだろう。 種々の環境指標 ・環境事故件数 総務省消防庁 石油コンビナート事故件数推移 この図からは2002年から増加していると言える。 ・水質事故件数 環境省 公共用水域における水質事故の発生状況 この図から水質事故は1998年頃から急増している。 ・公害苦情件数 総務省 公害苦情受付件数 大気汚染が1999年急増しているのはダイオキシン問題である。また騒音は工場ではなく生活騒音が主。 この図からは公害が増加しているとは見えない。 ・廃棄物 環境省 産業廃棄物の不法投棄等の状況 廃棄物不法投棄は1998年より不法投棄が急増し、2005年には沈静化した。 | |
| 注8 |
ISO14001も版によって記述は変わったが、中身は変わっていない。 ・1996年版: この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された取り決め ・2008年版:1996年版に同じ ・2015年版: 1)環境マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項 2)この規格の要求事項 | |
| 注9 |
ISO17021-1の審査計画一般で「マネジメントシステムの認証審査は、法令遵守の審査ではない」と明記されている。 この物語の時代はGuide66だったが、同文の記載があったように思う。忘れた。 | |
| 注10 |
認証した企業が不祥事を起こすと、認証機関側は申し合わせたように、審査で虚偽の説明を受けたという言い訳をした。 違反や事故を起こしたことは悪いことではあるが、その審査で本当に隠していたとか虚偽の説明をしたのかは、私は大いに疑問に思っている。虚偽の説明の証拠を見たことがない。 また、マスコミ報道の表現として「環境の国際規格ISO14001認証を取得した○○社」と書かれ、 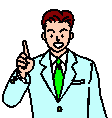 嘘をついて立派な称号を得たというニュアンスで報道された。
嘘をついて立派な称号を得たというニュアンスで報道された。審査は抜取であるから漏れることもあるわけで、そのことはISO17021にも順法を確認したわけではないと明記している。 抜取であるならAQLを定めて、それ以下なら審査は問題ないと言い切ってくれないと、認証の価値はない。 それなら違反、事故を起こさない企業を審査なしで認証すれば良いのだ。認証の意味を認証制度側は理解していないとしか思えない。 | |
| 注11 |
コストにはもちろん、失敗コスト、予防コストの他に営業的なものも含む。 | |
| 注12 |
ISO17021にもあるし、Guide66にもあった。 | |
| 注13 |
トヨタ・アメリカの社長が秘書をセクハラした問題が大きく報道されたのはこのお話しより7年ほど遅い。しかしこの頃から社内のセクハラ問題はいろいろ話題になり、談合や情報漏洩などでISO認証の停止や取り消しがあることから、我々企業でISO認証を担当していた者はセクハラがあってもQMS・EMSが取消になるだろうと思っていた。 |
外資社員様からお便りを頂きました(25.10.14)
おばQさま いつも更新有難うございます。 2話に共通して感じたのは、佐川の立派な点。 大きな功績をあげても、更に自分が出来る事をやっている点ですね。 その昔 Windowsのファイルシステムで、どうしても判らない事があって、1年がかりでやっとキーマンを見つけた事があります。 その人はWindows創設期のメンバーでMSキャンパス内に自分専用のコテージを持っていて、部屋には自転車が数台置いてあり、スポーツウエアを着ていました。 私の質問を聞くと「良く私が知っていると探し当てたね」と開口一番。 腹は立ったが、愛想良く聞きたい事を聞いて帰りました。 何が言いたいかと言えば、アメリカでも重要な仕事をした人は、その実績は頭に収めて会社には出さない。 その機密だけで仕事をせずに高給取って遊んで暮らしていられる。 日本でも「働かないオジサン」という管理職が問題になりましたが、こちらは先輩がそうだったから年功序列で自分の番だと、高給貰って働かない。 でもマイクロソフトも其の後凋落したし、日本の会社も落ち込んだ。 みんなが佐川みたいに考えられないから、そうなったのでしょう。 加えて言えば、佐川の活躍は吉井部長のような有能な上司に恵まれた点もあり。 ダメ上司は功績は自分のものにして自分では決断を避ける、問題があれば部下に押し付け、何も責任を取らない。 責任や判断を迅速に出来る上司が減ったのも、日本企業の凋落の原因でしょうかね? |
外資社員様、いつもご指導ありがとうございます。 書きたいことは多々あるのですが、手がまだ治らずキーボードを打つのが大変です。 これから佐川は、遵法体制を盤石な(?)ものとし、ISO認証を脱皮するという筋書きを考えているのですが、どうでしょう。 正直言ったもう第三者認証は叩く甲斐もないと思ってきました。 JQAのウェブサイトを見たら監査代行サービスなんて載ってました。 昔、下請けとか部品メーカーに品質監査に行ったものですが、それを代行するというものです。 ISO認証がない時代、当然、そういう品質監査代行業者がいたわけですが、30年経った結果、一回りしてそこに戻ったというか、お終いなのと呆れます。 あと数年経つとまた変わるでしょう。楽しみにウオッチします。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |