注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
第118話から続く
吉井部長から話を聞いた中山取締役は、数日後、人事の下山次長を呼ぶ。
![]() 「下山君、懸案になっていたと思うが・・・・・・未来プロジェクトのこれからについてだが、君はどういうビジョンを持っている?」
「下山君、懸案になっていたと思うが・・・・・・未来プロジェクトのこれからについてだが、君はどういうビジョンを持っている?」
![]() 「ビジョンですか、あまり先のことは考えていませんが、これから10年引っ張るわけにはいかないでしょう。せいぜいあと数年で幕引きですかね?」
「ビジョンですか、あまり先のことは考えていませんが、これから10年引っ張るわけにはいかないでしょう。せいぜいあと数年で幕引きですかね?」
![]() 「なぜ幕引き?」
「なぜ幕引き?」
![]() 「時間経過とともに、佐川の記憶も曖昧になるでしょう。それに彼は2023年までの記憶しかないと言います。ですから、あと5年、2005年過ぎたらもう気が抜けたビールかなと思います。
「時間経過とともに、佐川の記憶も曖昧になるでしょう。それに彼は2023年までの記憶しかないと言います。ですから、あと5年、2005年過ぎたらもう気が抜けたビールかなと思います。
もちろんそれ以降の未来の知識が役に立たないということではなく、それは今現在出してもらえば、今後2023年まで間に合うということです」
| 中山取締役 |  |
机だよ |
下山人事部次長 |
![]() 「ここ2年間半の、未来プロジェクトの成果を金額換算するとどれくらいかな?」
「ここ2年間半の、未来プロジェクトの成果を金額換算するとどれくらいかな?」
![]() 「プロ野球が優勝すると経済効果は何億円という算出の根拠はいい加減ですね
「プロ野球が優勝すると経済効果は何億円という算出の根拠はいい加減ですね
その成果は何十億・何百億という声もあり、大金であることは間違いありません。
とはいえ、その金額を佐川ひとりとか未来プロジェクトが、稼いだわけではありません。彼の予言を元にしていますが、多く人がどうすべきかを考え・対策計画を作り・実行した結果です。
まだ真偽は定かではありませんが、10年後に起きるという東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による原発の被害は20兆円以上
経団連主導で防潮堤改修と非常用発電の見直しを行った場合の見積もりが500億ですが、仮に防止できれば被害はゼロになるかもしれない。それをどう評価するかは難しいですね。
その成果は経団連や東電その他のおかげが99%でしょうね。未来プロジェクトの寄与は1%でしょうか、それでも2,000億ですか、大きいのは間違いない。
それに未来プロジェクトの運営費用も結構掛かっています。人件費もプロジェクトチーム7名だけでなく、実行部門の費用もあります。オフィスの家賃
出張旅費や会議費など合計すれば、年間の運営費用は1億超えるでしょう。もちろん今までの実績は、それをはるかに超えています。
有終の美を飾るというなら、しっかり成果を出しているときに、終了するのが良いのではないですか。
中山取締役は成果があれば継続するとお考えですか?」
![]() 「そりゃ益が百万、2百万ではしょうがないが、ビジネスだって利益率が一定以下になれば撤退する判断もあり、損益分岐点を超えているなら最後まで落穂拾いする判断もある。
「そりゃ益が百万、2百万ではしょうがないが、ビジネスだって利益率が一定以下になれば撤退する判断もあり、損益分岐点を超えているなら最後まで落穂拾いする判断もある。
ワシの知る限り最初の年は焼却炉で数十億、次の年は東アジア通貨危機で機会損失数百億の低減、総会屋問題ではブランドイメージの棄損を防いだ。
それ以降も、海外のテロ事件、事故などからの回避など、金額換算は難しいがプラスなのは間違いない。だからできるだけ引っ張りたいね。
考えてみろ、年10億も貢献している社員なんてまずないよ。神がかった研究者や営業マンくらいだろう」
![]() 「そう考えると、そうではありますね。とはいえ何も工夫をしないで良いわけではありません。
「そう考えると、そうではありますね。とはいえ何も工夫をしないで良いわけではありません。
過去2年間の運営を顧みて、未来プロジェクトの人件費削減、アイデア豊かなメンバーへの入れ替えも検討する余地はあります」
![]() 「それはあるね。誰が今まで施策立案に寄与したか勤務評定も必要だ。
「それはあるね。誰が今まで施策立案に寄与したか勤務評定も必要だ。
おっと、そういうことを![]() 佐山君はしているのかね?」
佐山君はしているのかね?」
![]() 「佐山さんは勤怠とか部門費は細かく見ているようですが、成果の評価はないですね。彼はルーチンワークとか、つじつま合わせが得意で、プロジェクトの意図を理解していないのかもしれません。そこが佐山さんの問題です」
「佐山さんは勤怠とか部門費は細かく見ているようですが、成果の評価はないですね。彼はルーチンワークとか、つじつま合わせが得意で、プロジェクトの意図を理解していないのかもしれません。そこが佐山さんの問題です」
![]() 「それで思い出したが、彼はプロジェクトの成果を具現化する努力が足りないとか、関係部門へのコミュニケーションが下手で問題だという苦情も聞いている。君はどう思う?」
「それで思い出したが、彼はプロジェクトの成果を具現化する努力が足りないとか、関係部門へのコミュニケーションが下手で問題だという苦情も聞いている。君はどう思う?」
![]() 「確かに私が担当していたときも、皆に計画を立てろ、進めろ部下をフォローするだけで、自らが他部門を巻き込んで進めることはしませんでしたね。実は東アジア通貨危機のとき、経理・財務に声をかけたのは私なんですよ。
「確かに私が担当していたときも、皆に計画を立てろ、進めろ部下をフォローするだけで、自らが他部門を巻き込んで進めることはしませんでしたね。実は東アジア通貨危機のとき、経理・財務に声をかけたのは私なんですよ。
彼は長年、工場の管理者(第51話)でしたから、決まりきったことは得意でも、新しいことへのチャレンジ精神に乏しいかもしれません。
佐山さんはプロジェクトマネジャーになって2年半、ひとつの部門にいるには十分な期間です。どうでしょう、異動してもおかしくありません」
![]() 「後任は、環境部の
「後任は、環境部の![]() 吉井君なんてどうかね?」
吉井君なんてどうかね?」
![]() 「吉井さんはアイデアマンですし管理者として有能です。でももう執行役員ですからね。プロジェクトマネジャーでは手合い違い(偉すぎる)でしょう。
「吉井さんはアイデアマンですし管理者として有能です。でももう執行役員ですからね。プロジェクトマネジャーでは手合い違い(偉すぎる)でしょう。
兼務にしても、どちらも重要部署ですから、実質的に代理者・・・たぶん佐川でしょうが、マネジャー業務をさせることになりますね。
それでしたら、それこそ![]() 佐川をマネジャーにしても良いと思います」
佐川をマネジャーにしても良いと思います」
![]() 「佐川はダメだ」
「佐川はダメだ」
![]() 「はっ、佐川は、資格的にも年齢的にも性格も問題なく、おかしくないですが・・・」
「はっ、佐川は、資格的にも年齢的にも性格も問題なく、おかしくないですが・・・」
![]() 「奴はアイデアを出せばよく、その分の処遇はしている。マネジメントもできるだろうが、彼に期待するものとは違う。余計なことをさせてアウトプットが減っては損だ。
「奴はアイデアを出せばよく、その分の処遇はしている。マネジメントもできるだろうが、彼に期待するものとは違う。余計なことをさせてアウトプットが減っては損だ。
佐川はプロジェクトの庶務仕事もしている。ワークフローや書類を見ると、作成は皆、佐川になっている。佐山君はアテハツ一つ書けないのか?
佐山は佐川を買い殺しにする気か、それはいかんだろう」
![]() 「プロジェクトで序列が彼の次となると
「プロジェクトで序列が彼の次となると![]() 伊達は佐川と同じく課長経験ありで48歳です。ただ当社には、プロジェクトマネジャーには部長級以上という、暗黙のルールがありますが」
伊達は佐川と同じく課長経験ありで48歳です。ただ当社には、プロジェクトマネジャーには部長級以上という、暗黙のルールがありますが」
![]() 「いまどき意味のないルールだ。活動を盛り上げてくれるならそいつでかまわん。2年任せて様子を見よう、いやその伊達ではなく未来プロジェクトの先行きをだ」
「いまどき意味のないルールだ。活動を盛り上げてくれるならそいつでかまわん。2年任せて様子を見よう、いやその伊達ではなく未来プロジェクトの先行きをだ」
![]() 「了解しました。佐山さんは?」
「了解しました。佐山さんは?」
![]() 「関連会社で、それなりの仕事を見繕ってやれ、年齢も年齢だし、出向命令が出ておかしくない」
「関連会社で、それなりの仕事を見繕ってやれ、年齢も年齢だし、出向命令が出ておかしくない」
![]() 「承知しました。他部門との調整の必要はありませんから、6月1日付で本人と懇談します」
「承知しました。他部門との調整の必要はありませんから、6月1日付で本人と懇談します」
注:平均寿命、定年、年金支給は大きな関係がある。このお話は現時点1999年である。当時はまだ定年延長は大問題ではない。当時、厚生年金は60歳から支給だったから、定年後も長く働くという意識はなかった。
20世紀末は、60歳まで勤めて、嘱託で2年働くというのが世間相場だった。
役職に就いている人は、50代半ばで関連会社に出向して、その後転籍して62歳頃、関連会社の定年というのが大半だった。
| 年代 | 平均寿命(男) | 定年 | 年金 | 社会問題 |
| 1970 | 69.3 | 55 | 60 | 年金と定年のバランスがとれていた |
| 1980 | 73.4 | 55⇒60 | 60 | 年金財政の不安も出始める |
| 1990 | 75.9 | 60 | 60 | 定年60歳が義務化。一応バランス状態 |
| 2000 | 77.7 | 60 | 65 | 「再雇用」「継続雇用」という仕組みが確立 |
| 2010 | 79.6 | ⇒65 | 65 | 高齢化社会の急進 |
・平均寿命推移
・厚労省資料支給開始年齢について
平均寿命が10歳延びて、年金支給開始が5年伸びでは、つじつまが合わないのは自明だ。
吉井部長のささやきでこうなったのではないだろう。佐山が今まで未来プロジェクトのミーティングや対外的な会議でイニシャチィブをとらず、消極的だったのが中山取締役の気に入らなかったのだ。
下山も佐山更迭に異議はない。だが佐山がアグレッシブに仕事をしないのに気づいても、中山取締役から言われるまで何もしなかった。自分はまだまだ未熟だと反省する。
実を言えば、中山取締役だって佐山の手抜き仕事に気が付いていたわけではなかった。吉井部長から言われたことが真実かどうか、下山次長に鎌をかけて聞いたに過ぎない。結果は吉井部長は正しかったようだ。
これで吉井部長の要望も反映したし、下山次長に注意喚起もした、ヨシヨシ
昔、私が勤めていた工場で工場長は何代も変わったが、最年少で工場長になったYさんという方がいた。何百人もいるから私など話す機会はなかったが、噂はいろいろ聞いた。ひとつはミスを二度すると飛ばされるというもの。実際に設計チョンボして、遠くの営業所などに異動になった人が何人もいたから、嘘ではないだろう。
その後、私が転職して数年後、全く関係ない場所で偶然お会いしたことがある。
向うは私を知らないだろうが、私は覚えていたから「お久しぶりです」と挨拶した。すると私の名前を憶えていた。工場長が話したこともない下っ端の顔と名前を知っていたことに、正直、感激した。
・
・
・
・
1999年6月1日
人事異動が発表された。プロジェクトマネジャーが佐山から伊達に代わり、![]() 相馬が抜けて財務部の
相馬が抜けて財務部の![]() 野村課長が兼務になった。
野村課長が兼務になった。
佐山は出身地の県にある工場で、清掃や駐車場管理をしている40人ほどの関連会社に出向である。本社の重要なプロジェクトマネジャーから工場所属の関連会社の責任者では月からスッポンだが、佐山は重責から逃れて正直言ってホッとしていた。
転任の挨拶回りで、良い仕事に就けたと複数の人から思われたようだ。東京で単身赴任を2年半していたから、これからは故郷で悠々自適がうらやましいと、挨拶回りで多くの人から言われた。
佐山は満足して本社を去っていった。

| |
| 伊達です |
プロジェクトは明確な目的がある。それをプロフェッショナル達が達するために動きやすい環境作り、抵抗勢力との交渉、問題に突き当たったとき助っ人を探すことがマネジャーの仕事と考えている。
自分がそうであるように、プロジェクトにはこれを踏み台に立身出世しようなんてのはいない。みな面白いから、チャレンジしたいからいるのだ。ならばそういう連中を気分よく働かせて目的を達成すればいいのだ。
もちろん自分は早いのが取り得のバカバカしい発言で、議論を活発にさせるのは今までと同じだ。
それから佐川と一日じっくり話して、これからの20年の未来史をしっかり文書化し、そこでおきる大小のイベント(事故・災害・政変等)を明確にしていく。
毎年、佐川が翌年の出来事を示しているが、小出ししていては長期的な対応ができないものもあり、毎年その年の重要課題を考えるより、5年スパンくらいで考えるようにしたい。

| |
| 課長だって! |
佐川にとっては何も変わらない。対外的には元から課長の名刺だったし、工場に行けば課長の名刺の有無より、問題を解決してくれる人は尊敬され、そうでない當山(第12話)のような人は、もう来るなと言われるだけだ。
注:佐川は工場で課長だったが、本社の課長は工場の部長級である。つまり大出世である。
尾関副工場長にイジメられていたときはもうお先真っ暗で辞めようと思っていたものだ。まさに起死回生、いや捲土重来かな?
ただラインにしっかり組み込まれると、未来プロジェクトの方をどうするかとなり、上司である吉井部長、中山取締役、伊達プロジェクトマネジャーと話をして、環境部に常駐、未来プロジェクトはミーティングのみ参加することにした。
*
*
*
佐川の最初の仕事は、工場管理課の守備範囲の取り合いをはっきりさせることだ。
職制・職務規則に「〇〇課は〇〇をする」と書いてあっても、職務の取り合いというのは地図に境界線を引いたようなものではない。
例えば「省エネの推進」とあっても、エネルギー使用量のデータ収集、省エネ法のとりまとめ・届け出もある、ボイラーや電気設備の省エネ技術、省エネ機器の検討、省エネのための操業方法の検討、設備投資計画、などいろいろある。
例えば、今まで省エネ法のとりまとめは生産技術本部部長室で、電気設備・ボイラー更新などは生産技術部で、研究所は工場から省エネ設備の有効性などの評価をしている。用水の使用量や廃棄物排出量は誰も把握していない。
そして指揮系統としては工場と関連会社は事業本部の下にあり、本社部門が勝手に工場に指示命令できるわけではない。 それが現実だ。
佐川は、研究本部、生産技術本部、生産技術部、各事業本部と打ち合わせを繰り返し、境界を確定した。
水使用量、エネルギー使用量、廃棄物排出量は環境部が行う
省エネ機器の研究や投資計画は生産技術部、その評価や研究は個別依頼を受けて研究所とした。
省エネ法の届のまとめは生産技術本部に環境部が報告する。
このように決めた。
今までどうしていたのかという疑問を持つかもしれない。
会社も行政も同じだが、元々すべてを網羅した機能を持っていない。必要になったら対応するのが現実だ。
吉宗機械でも「工場の環境業務を統括する部門」はなかった。なくても間に合えば作らない。必要だと工場管理課が作られたなら、そこがどんな仕事をするのか明確(文章)にする必要があり、似たような仕事をしている部門と調整が必要になる。
会社規則を新たに作るとき、過去の規則との重複や矛盾は徹底的に調べるが、新しい部署を作るとき、他部門の業務との重複や矛盾はあまり調整しないように感じる。
工場管理課にはそれ以外というかメインの仕事として、工場とグループ企業の環境管理の指導支援、事故・違反時の工場支援と全社展開のお仕事がある。
具体的には、ISO14001認証の支援、審査でのトラブル発生時の対応がある。
これも複雑怪奇になる。環境施設そのものは生産技術担当であり、行政対応は事業所であり、広報は広報部・・・
まあ、それも関係部門とコミュニケーションを取ってやっていくわけだ。
佐々淳行氏の「連合赤軍あさま山荘事件
前述したものの対応は佐川と山口が昨年までしていたわけで、今年から佐川が環境部に常在すれば対応は問題ない。
そして今年度からの環境遵法監査である。新人の育成は早急にしなければならない。
*
*
*
監査には監査のテクニックがあり、監査するものについての知識と経験が必要であり、そもそも監査向きの性格であってほしい。
もちろん世の中は、望ましい人などめったにいないと決まっている。
今回異動してきた3名は工場では環境部門にいたわけだ。佐々木と大谷はISO14001の内部監査員だったという。特に佐々木は、認証機関が行っているISO14001審査員研修を受講していると自慢していた。
とはいえ、その程度のことは全く意味のないことであり、そもそも審査員研修の講師でさえ真の監査ができるのかはなはだ疑問である。
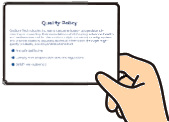
これは言いがかりではない。100人ほどの審査員に審査を受けたり審査を見学したが、なるほどと思った審査員は10人いるかいないかだ。
「方針カードを持っているから方針の周知はOK」なんて判断しているようじゃ・・・・・・
環境マネジメントシステム監査をするには、どんな資質、力量、知識が必要か・・・悩むことはない。ISO19011に書いてある。
注:ISO19011を知りたくば、日本規格協会の「ISO19011対訳本
*
*
*
とはいえ対訳本を読めばOKではない。テクニックを身に着けるいは実践もあるし、役割に徹する演技力も必要もだ。なによりも目ざとさとか好奇心も必要だ。
とはいえ、環境遵法監査をするには、環境法令を自家薬籠のものとしていないとできないということはない。
そもそも環境省の官僚だってそんな人いませんよ。元、環境省に出向していた人から聞いた話だが、自分が担当している法律なら、法律、施行令、施行規則(名称多々あり)そして出した通達はそらんじているだろうけど、担当外の法律は一般人並みという。
そして監査する場所の所在地、設備、周囲環境などにより、規制を受ける法律はかなり限定される。
法律は2105本
もちろん環境の名がつかない消防法や毒劇物法もあるが、普通の事業所なら関わる法律は50〜70本だろう。
更に関わる法律でも、その事業所が関わることは何カ所かあるだけだ。第一条から付則まで読むことはない。
*
*
*
今日は小会議室で佐川の講義である。
受講者は、新人3人の他に山口もいる。
 |
|||
|
![]() 「監査とは経営者とか監査責任者から、どこそこに行って監査基準はこれこれでしてこいと言われてするものです。
「監査とは経営者とか監査責任者から、どこそこに行って監査基準はこれこれでしてこいと言われてするものです。
多くの場合、何を重点にするとか、こういう理由があって監査をするということは示されます。それが監査方針ですね。
監査員は作業者です。自分の意思で動くわけでもなく監査基準を決めることもありません。そしてまた結果から何をするかを決めることでもありません。現地調査の正しい報告、それが仕事です。
監査の仕事とは、指示された項目について、監査基準と比較して適合しているか、不適合(適合していない)かの証拠を調べ、その証拠と、監査基準の何に適・不適かを記録して報告します。
監査には多様なものがあり、その方法も状況や目的に応じて変化するでしょうけど、簡単に言えばそれだけのことです」
![]() 「ISOの内部監査とはだいぶ違いますね」
「ISOの内部監査とはだいぶ違いますね」
![]() 「ほう、全く同じと思います。どこが違いますか?」
「ほう、全く同じと思います。どこが違いますか?」
![]() 「ISO14001の内部監査の監査基準は、ISO14001に決まっていますから、変えようがありません」
「ISO14001の内部監査の監査基準は、ISO14001に決まっていますから、変えようがありません」
![]() 「それは考えようじゃないですかね。そもそもISO規格で内部監査しているとは思えませんけど」
「それは考えようじゃないですかね。そもそもISO規格で内部監査しているとは思えませんけど」
![]() 「私が内部監査をするとき、いつもISO規格だけしか使いませんよ」
「私が内部監査をするとき、いつもISO規格だけしか使いませんよ」
![]() 「ええと佐々木さんはどこの工場だっけ?」
「ええと佐々木さんはどこの工場だっけ?」
![]() 「宮城工場です」
「宮城工場です」
![]() 「山口さん、宮城工場はあなたが指導したの?」
「山口さん、宮城工場はあなたが指導したの?」
![]() 「認証の指導は行きましたが、ISO9001の経験があるから環境監査の指導は不要と言われました」
「認証の指導は行きましたが、ISO9001の経験があるから環境監査の指導は不要と言われました」
![]() 「そうか、佐々木さんは3段組という言葉を聞いたことありますか?」
「そうか、佐々木さんは3段組という言葉を聞いたことありますか?」
![]() 「ISO事務局の人たちがいつも持って歩いていました。私は監査には無関係だと思っていました」
「ISO事務局の人たちがいつも持って歩いていました。私は監査には無関係だと思っていました」
![]() 「佐々木さんはどんな風に監査していたの? 例えば『マネジメントシステム文書』の項番の質問をしてみて」
「佐々木さんはどんな風に監査していたの? 例えば『マネジメントシステム文書』の項番の質問をしてみて」
![]() 「私は規格を暗記していますよ。文書にはshallがみっつありますが、しなければならないことはたくさんあります。
「私は規格を暗記していますよ。文書にはshallがみっつありますが、しなければならないことはたくさんあります。
最初の要求は『マネジメントシステムの核となる要素およびそれらの相互作用を記述する』です。
内部監査では要求事項の通りに質問します。具体的には『マネジメントシステムの核となる要素およびそれらの相互作用を記述していますか?』と聞きます」
![]() 「すごいねえ〜(こりゃ、手に負えないわ😞)」
「すごいねえ〜(こりゃ、手に負えないわ😞)」
![]() 「すごいでしょう。審査に来た審査員からすぐにもISO審査員としてやっていけると誉められました」
「すごいでしょう。審査に来た審査員からすぐにもISO審査員としてやっていけると誉められました」
![]() 「山口さん、宮城工場の内部監査に立ち会ったことはないの?」
「山口さん、宮城工場の内部監査に立ち会ったことはないの?」
![]() 「ありません。こんなふうにしていたのですか。驚きました」
「ありません。こんなふうにしていたのですか。驚きました」
![]() 「その質問を聞いた方は、どのような回答をされたのでしょう?」
「その質問を聞いた方は、どのような回答をされたのでしょう?」
![]() 「それが・・・・・・レスポンスが悪くて・・・期待する回答が来ないのですよ。失礼ながら、山口さんの指導が悪かったのではないですか」
「それが・・・・・・レスポンスが悪くて・・・期待する回答が来ないのですよ。失礼ながら、山口さんの指導が悪かったのではないですか」
![]() 「佐々木さんに内部監査を教えてくれた方は、どういう人ですか? ISO9001の監査をしていたとか?」
「佐々木さんに内部監査を教えてくれた方は、どういう人ですか? ISO9001の監査をしていたとか?」
![]() 「いや、審査員研修機関の『ISO14001審査員研修』に参加しました。そこでISO審査員になる研修を受けました」
「いや、審査員研修機関の『ISO14001審査員研修』に参加しました。そこでISO審査員になる研修を受けました」
![]() 「その研修では規格文言通りに質問する方法を教えたのですか?」
「その研修では規格文言通りに質問する方法を教えたのですか?」
![]() 「はい、そうです」
「はい、そうです」
![]() 「審査とか監査の質問方法は、大きく分けて二つのアプローチがあります。今、佐々木さんが、おっしゃったのは項番順審査というものです。もう一つの方法は習いませんでしたか?」
「審査とか監査の質問方法は、大きく分けて二つのアプローチがあります。今、佐々木さんが、おっしゃったのは項番順審査というものです。もう一つの方法は習いませんでしたか?」
![]() 「別の方法もあるような話はされました。でもこの方法が質問に対応する回答を得られるから良いと習いました。
「別の方法もあるような話はされました。でもこの方法が質問に対応する回答を得られるから良いと習いました。
別の方法は習っていません」
![]() 「正直言って、項番順審査は初心者向けというか、第一回目の監査なら使うかもしれないという方法です。
「正直言って、項番順審査は初心者向けというか、第一回目の監査なら使うかもしれないという方法です。
我々が行う監査には不向きだと思います」
![]() 「審査員研修機関が教えているのは、間違いだということですか?」
「審査員研修機関が教えているのは、間違いだということですか?」
![]() 「間違いとは言わないよ。ただ、我々には不向きだ。
「間違いとは言わないよ。ただ、我々には不向きだ。
佐々木さんは、内部監査してレスポンスが悪く期待した回答が得られなかったと言った。
じゃあ、期待する回答が得られるように、質問する方法はないだろうか?」
![]() 「私は環境部門にいましたが、内部監査員をしたことはありません。その代わり内部監査は何度も受けました。
「私は環境部門にいましたが、内部監査員をしたことはありません。その代わり内部監査は何度も受けました。
あっ、私は大分工場で認証の指導には山口さんが来ました。そして内部監査のときも山口さんが一緒に回りましたね」
![]() 「あのときお会いしましたね」
「あのときお会いしましたね」
![]() 「大分の内部監査員はそのような質問はしなかったですね」
「大分の内部監査員はそのような質問はしなかったですね」
![]() 「Shallは必ず質問しなくてはなりませんよ」
「Shallは必ず質問しなくてはなりませんよ」
![]() 「いや、佐々木君の言った『マネジメントシステムの核となる要素およびそれらの相互作用』なんて難しい言葉も使わなかったし、そもそも質問が抽象的で私が聞いても意味が分からないよ」
「いや、佐々木君の言った『マネジメントシステムの核となる要素およびそれらの相互作用』なんて難しい言葉も使わなかったし、そもそも質問が抽象的で私が聞いても意味が分からないよ」
![]() 「それにYESと答えられないとISO審査に合格しないよ。大分工場はよく合格しましたね」
「それにYESと答えられないとISO審査に合格しないよ。大分工場はよく合格しましたね」
![]() 本日は時間切れ
本日は時間切れ
原理主義者のような佐々木君を、納得させることができるでしょうか?
 実際にこういうおかしな考えに染まった人は、会社にも審査員にもいるんですよ。そして一度感染すると、二度と回復しない恐ろしい病気です。
実際にこういうおかしな考えに染まった人は、会社にも審査員にもいるんですよ。そして一度感染すると、二度と回復しない恐ろしい病気です。
佐々木君を救うことはできるでしょうか?
この病気の審査員に当たると、そのまま審査を続けては会社の損害、指導するのは会社の損害、不適合を出されて認証機関に文句言いに行くのも会社の損害、まさに八方ふさがり。
悪病は追い払わねばなりません。
ダラダラと書いてきて、さあ、遵法監査に入ろうと思ったら時間切れではなく、もう9,000字をオーバーしてました。
本日はこれまで、次回に続く
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
ニュースなどで聞く「経済効果」とは、イベントや事業によって「どれだけお金が動いたかを示す推計値」であり、利益ではない。 その仮定には多め多めと見積もる傾向が強い。それにはいくつも理由がある。 (1)イベントで使われたお金は、イベントがなければ他で使われていたとは考えていない。 (2)自治体/主宰者の投入した、建設費や宣伝費などのお金を効果に含めていること。 (3)イベントの結果、交通渋滞や宿がとれないなどのマイナス影響を考慮しない。 このようにご都合主義だから、常にイベントの真のプラス効果より過大になる。 | |
| 注2 |
福島第一原発事故の被害額は、個別の賠償金として精神的損害に13,393億円、自主的避難等に4,729億円などが東京電力によって合意されており、事故処理費用全体では約23兆4000億円とされている。 但し、見積もりのたびに増加しており、最終的にいくらになるかは想像できない。 | |
| 注3 |
丸の内や大手町の良いビルのオフィスの家賃は、平米当たり9,000〜15,000円である。オフィス内の通路やパントリーなどを含むと一人当たり7〜13平米とされている。よって丸の内/大手町の一流のオフィスビルでは一人当たりの家賃は20万となる。 現役時代、私は自分一人当たり家賃が月23万と聞いて、相当の仕事をしないとならないと冷や汗をかいたのを覚えている。当時、私は市川市の65平米のマンションで家賃が16万だったから家族が暮らすマンションより、職場で自分一人分の家賃が高いのに驚いた。 同居していた息子は卒業後、宮城県名取市に就職した。月5万くらいのアパートを借りたいと不動産屋に言ったら、そんな高い物件はないと言われたそうだ。 息子は数年そこで働いたが、深夜が当たり前のブラック企業で体を壊し退職した。そこで働き続けていたら、東日本大震災で間違いなく死んでいた。 | |
| 注4 |
この当時は、省エネ法の届は事業所ごとだから、全社で集計も届も法的には不要である。 もちろん会社として省エネ法の届をしたかのフォローは必要だ。 フォローと集計を環境管理課がして、その報告を生産技術本部にするという意味 | |
| 注5 |
『連合赤軍「あさま山荘」事件』佐々淳行、文藝春秋、1996、 | |
| 注6 |
「ISO 19011:2018(JIS Q 19011:2019)マネジメントシステム監査 解説と活用方法」、日本規格協会編、日本規格協会、2019 | |
| 注7 |
2025年10月18日時点の数 電子政府にアクセスして法令検索で法律のすべてのラジオボタンにチェックをつけ、それ以外のチェックをすべてはずして検索ボタンを押すと、その時点の法律の数が出る。 中には「改正法」もかなりの数ある。 注:改正法とは法律を改正するための法律 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |
