��1�F���̕���̓t�B�N�V�����ł��B�o�ꂷ��l����c�͎̂��݂�����̂ƈ�؊W����܂���B
�A��ISO�K�i�̉��߂ƈ��p������@�ߖ��Ƃ��̓��e�͂��ׂĎ����ł��B
��2�F�^�C���X���b�vISO�Ƃ�
��3�F���̂��b�͉��N�ɂ��n�邽�߂ɁA������ɂ������ƔN�\�����܂����B
��119�b���瑱��
���삪�A���X�̐R�����@�ɂ��Ă̗����ɕ���A䩑R�Ƃ��Ă���ƁA�g�䕔����50���60�ɋ߂��j����l��A��ē����Ă����B
![]() �u�����A�u�`���A���܂�A���܂�A
�u�����A�u�`���A���܂�A���܂�A
�����@�č��̈ʒu�Â��ɂ��Ċč������Ƙb�������A�č������Վ��̊����@�č������{����A����Ɋ������Q������Ƃ����`�ɂȂ����B�����A�č��̍u�K�����Ă���Ƙb������A���Ќ��w�������Ƃ̂��Ƃ��B�v
�����ƁA������̕��͊č����̖k�삳��ƍ�����B
���������A�č����͉�X�̎��͂ɕs���������Ă���̂��낤�B�����A�č����̕��X�����S�����Ă����B
���Ⴀ�A���ӂ���A��낵�����肢���܂��v
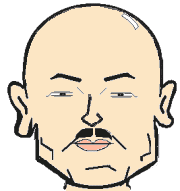 |
 |
| �k�� | ��� |
2025�N�� �m�[�x����҂�
�悤�ł����A�W����܂���B
�g�䕔���͂��������ƕ������o�čs�����B
�����Ċč����̓�l�́A�F�̌��̐Ȃɍ����Ă��܂����B�����Ƃӂ���Ƃ��o��������������Ȃǂ��C���Ă��āA��E��N�ɂȂ�č����ɗ���Ă����̂��낤�B
�č����͏o�����T���Ƃ���ƌ����Ă���B�o����̂Ȃ��̂����č����ɍݐЂ��A�֘A��Ђ�
��������\�肪���邩��A�C�����킸���܂ł̑��������悤�ƍ���͌��߂��B
![]() �u�č��́A�č�������Ă��邩�ۂ������邱�Ƃł��B�č�������Ă��邩�����₷��̂ł͂���܂���B���������Ⴂ���Ă͂����܂���v
�u�č��́A�č�������Ă��邩�ۂ������邱�Ƃł��B�č�������Ă��邩�����₷��̂ł͂���܂���B���������Ⴂ���Ă͂����܂���v
![]() �u���݂܂���w�č�������Ă��邩�����₷�邱�Ƃł͂Ȃ��x�Ƃ͂ǂ������Ӗ��ł����H�v
�u���݂܂���w�č�������Ă��邩�����₷�邱�Ƃł͂Ȃ��x�Ƃ͂ǂ������Ӗ��ł����H�v
![]() �u�č��Ƃ́A�č�������Ă���؋��������邱�Ƃł��B���₷��͎̂�i�̈�ł��v
�u�č��Ƃ́A�č�������Ă���؋��������邱�Ƃł��B���₷��͎̂�i�̈�ł��v
![]() �u����͕�����܂����A�w���₵�Ȃ��ŏ؋���������x���@�Ƃ͂ǂ��������̂ł����H�v
�u����͕�����܂����A�w���₵�Ȃ��ŏ؋���������x���@�Ƃ͂ǂ��������̂ł����H�v
![]() �u�ٔ��ł������ł����A�č��œK�����邢�͕s�K�����ؖ�����؋��������邪���`�ł��B���P�Ƃ��ĂƂ������č������؋����������Ȃ��Ƃ��A�č����͎���ł͂Ȃ��؋��̒����߂܂��B����Ȃ���Ύ��₵�܂����A�����œ�����،��͎O�P�ł��傤�v
�u�ٔ��ł������ł����A�č��œK�����邢�͕s�K�����ؖ�����؋��������邪���`�ł��B���P�Ƃ��ĂƂ������č������؋����������Ȃ��Ƃ��A�č����͎���ł͂Ȃ��؋��̒����߂܂��B����Ȃ���Ύ��₵�܂����A�����œ�����،��͎O�P�ł��傤�v
���F�u�؋��ٔ���`�v�Ƃ����悤�ɁA�u�؋��v�Ɉ�ԉ��l������B�u�،��v�͗��t�������Ȃ���ΗL���ł͂Ȃ��B���ɏ،������ŗL���Ȃ�u���͖��߂��v�ƌ����Ζ��߂ɂȂ�̂��Ƃ����b���B
�X�ɏ؋���������ߒ����d�v���B
�I�E�������̍�{�ٌ�m��ƎE�l�����ŁA�x�@�͊��Ɉ�̂߂��ꏊ��c�����Ă����炵�����A�e�^�҂����߂��ꏊ�܂ňē������ƕ��ꂽ�B���̏ꍇ�A�{���������炩�̕��@�ň�̂������̂ƁA�e�^�҂�����Ɉē������̂ł́A�e�^�҂��^�Ɛl�ł��邱�Ƃ̐M�������Ⴄ�B
�č��̏ꍇ���A���������؋��ƁA�č������������؋��ł͐M�������Ⴄ�BISO�R���ł́A�R�����鑤��������؋����������Ă���̂��ʗႾ�B
![]() �u�Ȃ�قǁA�����Ă݂�Γ�����O�̂��Ƃł��ȁv
�u�Ȃ�قǁA�����Ă݂�Γ�����O�̂��Ƃł��ȁv
![]() �u����Ɗ��č��Ɍ���܂��A�č��͎O����`(����E�����E����)�ɑ���܂�����A��Ɍ�������܂��B����Ƃ͐������ꂾ���ł͂���܂���B�o���̎����������ޑq�ɂ����ɂ��F����ł��B
�u����Ɗ��č��Ɍ���܂��A�č��͎O����`(����E�����E����)�ɑ���܂�����A��Ɍ�������܂��B����Ƃ͐������ꂾ���ł͂���܂���B�o���̎����������ޑq�ɂ����ɂ��F����ł��B
���ꏄ�̊ώ@�ŏ؋��������邱�Ƃ��ł���A���₷��܂ł�����܂���v
![]() �u�؋���������Ύ��₷��܂ł��Ȃ��Ƃ́A�ǂ��������Ƃł����H�v
�u�؋���������Ύ��₷��܂ł��Ȃ��Ƃ́A�ǂ��������Ƃł����H�v
![]() �u����Ōf������Ă����Ɨv�̏��ɏ������݂�����A�����Ǘ��ɖ�肪���邱�Ƃ�������܂��B�܂����[�ɖ��L���ӏ�������A���[���߂���܂ł��Ȃ��A���₷��܂ł��Ȃ��A�^�p�����[���ʂ�łȂ����Ƃ�������܂��B
�u����Ōf������Ă����Ɨv�̏��ɏ������݂�����A�����Ǘ��ɖ�肪���邱�Ƃ�������܂��B�܂����[�ɖ��L���ӏ�������A���[���߂���܂ł��Ȃ��A���₷��܂ł��Ȃ��A�^�p�����[���ʂ�łȂ����Ƃ�������܂��B
����̊ώ@�ŗv�������Ă��邩�E���Ȃ����̏؋���������A���߂Ď��₷��K�v�͂���܂���v
![]() �u��Ɨv�̏��ɏ������݂�����ƁA�Ȃ������Ǘ������Ȃ̂ł����H�v
�u��Ɨv�̏��ɏ������݂�����ƁA�Ȃ������Ǘ������Ȃ̂ł����H�v
![]() �u����!�A���X����͕����ւ̏������݂́AISO�K�i�̗v�������ɔ����Ă���Ǝv��Ȃ��̂��ȁH ������Ђ̕����Ǘ��K���ɂ������Ă��܂���v
�u����!�A���X����͕����ւ̏������݂́AISO�K�i�̗v�������ɔ����Ă���Ǝv��Ȃ��̂��ȁH ������Ђ̕����Ǘ��K���ɂ������Ă��܂���v
���X��ISO14001�Ζ�{�����o���āA�p���p���Ƃ߂���B
![]() �u����4.4.5�����Ǘ��̗v���ɁA�����Ƀ����������Ă͂����Ȃ��Ƃ͂���܂����v
�u����4.4.5�����Ǘ��̗v���ɁA�����Ƀ����������Ă͂����Ȃ��Ƃ͂���܂����v
![]() �u�I�C�I�C�A�N�͊č����������Ƃ��Ȃ��̂�������Ȃ����A����Ȃ��Ɠ�����O���낤�v
�u�I�C�I�C�A�N�͊č����������Ƃ��Ȃ��̂�������Ȃ����A����Ȃ��Ɠ�����O���낤�v
![]() �u�K�i�ɏ����ĂȂ��̂ł����瓖����O�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�u�K�i�ɏ����ĂȂ��̂ł����瓖����O�ł͂Ȃ��ł��傤�B
����Ɏ���ISO14001�̐R������ɓo�^���Ă��܂��B�����č������x�����Ă��܂��v
![]() �u�R�����o�^�����Ă��邩����A�n�n�n�v
�u�R�����o�^�����Ă��邩����A�n�n�n�v
���X�̓u�X�b�Ƃ����������B������ISO�R������͂��������i���Ǝv���Ă���̂��B
![]() �u�܂��܂��A�m����ISO�K�i�ɁA�����Ƀ�����������ȂƂ͏����Ă���܂���B
�u�܂��܂��A�m����ISO�K�i�ɁA�����Ƀ�����������ȂƂ͏����Ă���܂���B
�Ƃ����̂͋֎~��������̓I�ɏ������Ƃ���ƁA�����������Ă̓_���A�j��Ă�����_���A�Z���e�[�v�ŕ�C���Ă�����_���A�C���N���ސF���Ă�����_���A��������ɉ�����U���Ă�����_���A����Ă��Ă̓_���ƁA��������������܂���B
�������ʘ_�Ƃ����w�ǂ݂₷���x�Ə����Ă���킯�ł��v
![]() �u�����������Ă�������ꂽ���͕͂ς��܂���A�ǂ݂ɂ����͂Ȃ�܂���v
�u�����������Ă�������ꂽ���͕͂ς��܂���A�ǂ݂ɂ����͂Ȃ�܂���v
![]() �u���̖��ł����A���͂����w�ǂ݂₷���x�͌��ł��āA�p���legible�ł��B
�u���̖��ł����A���͂����w�ǂ݂₷���x�͌��ł��āA�p���legible�ł��B
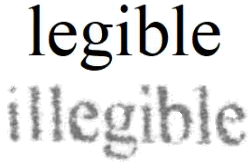 �����ƁAISO�K�i�͉p��ƃt�����X�ꂪ���ŁA����ȊO�̌���ɖꂽ���͎̂Q�l�ɂ����܂���B�^�`����ꍇ�͌����A�܂�p�ꖔ�̓t�����X���ISO�K�i�ɂ�邱�Ƃ͂������ł��ˁBJIS��ǂ�ł��āA���������Ǝv�����猴����ǂ݂Ȃ����B����A���߂���p����ǂނׂ��ł��B
�����ƁAISO�K�i�͉p��ƃt�����X�ꂪ���ŁA����ȊO�̌���ɖꂽ���͎̂Q�l�ɂ����܂���B�^�`����ꍇ�͌����A�܂�p�ꖔ�̓t�����X���ISO�K�i�ɂ�邱�Ƃ͂������ł��ˁBJIS��ǂ�ł��āA���������Ǝv�����猴����ǂ݂Ȃ����B����A���߂���p����ǂނׂ��ł��B
�b��߂��ƁA�p���legible�͓��{��́w�ǂ݂₷���x�ł͂Ȃ��w�N���x�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��B�ł�����K�i�v���͐������́A�������͂�����Ɠǂ߂邱�Ƃł��B
�����ɗ]�v�Ȃ��Ƃ���������A���ꂽ��A�j�����肵�Ă͋K�i�v�������܂���v
![]() �u�ւ��`�A�����ǂނ̂ł����H �ł����삳��́w�ǂ݂₷���x�͊ԈႢ�ƌ����܂������A����Ȃ當�͂�������ɂ����̂͋K�i�K���Ȃ̂ł����H�v
�u�ւ��`�A�����ǂނ̂ł����H �ł����삳��́w�ǂ݂₷���x�͊ԈႢ�ƌ����܂������A����Ȃ當�͂�������ɂ����̂͋K�i�K���Ȃ̂ł����H�v
![]() �u�܂����͊ԈႢ�Ƃ͌����Ă��܂����A���ł���ƌ������̂ł��B�������厖�ł��A���Ⴂ���Ȃ��悤�ɁB
�u�܂����͊ԈႢ�Ƃ͌����Ă��܂����A���ł���ƌ������̂ł��B�������厖�ł��A���Ⴂ���Ȃ��悤�ɁB
�ł͉�Ђ̕��͂��w�ǂ݂₷���Ȃ��x�̂͂ǂ����ƂȂ�܂��ˁB
�܂����͂��ǂ݂₷���E�ǂ݂ɂ����Ƃ͂��Ȃ��ϓI�Ȃ��̂ł͂���܂��B�ł�����P�������̔���́A���̉�Ђ̍l������ƂȂ�ł��傤�B
�Ⴆ�A��肭�ǂ��Ƃ���d�ے�ȂǁA�ǂ݊ԈႦ�̋��ꂪ���邩�ǂ����́A��Ђ����߂邱�Ƃł��B
����Ƒ��ɕ����ƌ����܂����A��Г��Œʗp�������Ƃ������������Ă��A�����ɏ����Ă����爫�����Ƃ͂Ȃ��A�����ǂ݂ɂ����Ƃ����̂͌���������ɂ����܂���v
���F����30�N���O�̂��Ƃ����AISO9001�R�����t�����̂��ƁA
�R�������\�h���u�����Ă��Ȃ�����s�K�����Ƃ����B���낢��b���ƁA����I�ɐ��������𑪒肵�ăt�B�[�h�o�b�N��������ȂǁA���낢��\�h���u�����Ă��邪�A������Г��ŗ\�h���u�ƌĂ�ł��Ȃ�����_�����Ƃ����B
����Ȃ��Ƃ������Ȃ�A������ISO9001�F1987�ł́u4.14�̐������u�v�̒��ŗ\�h���u��v�����Ă���̂�����A�����悤�Ȃ��̂��Ɣ��_�������A����ɂ���Ȃ������B
| 😠 |
���ǁA�s�K���ɂȂ������A�o�J�o�J�����̂ʼn������Ȃ������B����A�ʂ̐R�������������A���̐������u�m�F�͑f�ʂ肵���B
���̌�AISO9001�����x�����肪����A2015�N�łł�ISO�K�i�̗p��Ƃ������̍\��������������̂ł͂Ȃ��ƁA�`���̏����ɒ����������悤�ɂȂ����B
������O�ƌ����Γ�����O���B����A�킴�킴�����܂ł̂��Ƃł��Ȃ��낤�B
![]() �u��d�ے肪�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���shall�͂Ȃ��ł���v
�u��d�ے肪�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���shall�͂Ȃ��ł���v
![]() �u�m���ɂ�����K�i�ł͋�̓I�ɏ����Ă��܂���B�������̓I�ɏ�����������������܂���ˁB
�u�m���ɂ�����K�i�ł͋�̓I�ɏ����Ă��܂���B�������̓I�ɏ�����������������܂���ˁB
�w�ǂ݂₷���x�̂���i���̑O�A���i����
�������w����������I�Ƀ��r���[����A�K�v�ɉ����ĉ�������A������̐ӔC�҂ɂ���đÓ��������F����邱�Ɓx�Ƃ���܂��B
�ł����獲�X���S�z�������Ƃ́A�������菑����Ă��܂��B
�������N�Ă�����A�������背�r���[(�ƍ�)����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�`�F�b�N���ׂ����Ƃɂ́A������Ă���Ɩ��菇�����������A�W���镶���Ɩ�����d�Ȃ肠�邢�͌��Ԃ��Ȃ����A�l���E�����A�̔ԁA�뎚�E�E���E
�K�i�͂��������d�g�݂����Ə����Ă��܂��B
���X����͉�Ђ̋K����v�̏��Ȃǂ����S�����܂������A���͓��ȏ�A�܂�����قǏ����܂����B
�����������Ă��邩�ǂ����A�č��Ŋm�F���Ȃ���Ȃ�܂���v
![]() �u����N�̐����́A�܂��ɋK�i�̓ǂݕ��̋��ȏ��̂悤���ˁB���ۂ̊č��̂Ƃ��A������݂�q���������B
�u����N�̐����́A�܂��ɋK�i�̓ǂݕ��̋��ȏ��̂悤���ˁB���ۂ̊č��̂Ƃ��A������݂�q���������B
�����Ƃ���������Ƃ́A�T�o�̓ǂ݂������낤�v
![]() �u�܂��A�K���E�菇���E�v�̏��͓�A�O�������̂͊ԈႢ����܂���B
�u�܂��A�K���E�菇���E�v�̏��͓�A�O�������̂͊ԈႢ����܂���B
����Ɋč��ł����玸�]�͂����܂����v
�k��͊���Ђ��点���B
 |
||
|
![]() �uISO�K�i�̗v���������ׂĂɂ��āA�����ǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H�v
�uISO�K�i�̗v���������ׂĂɂ��āA�����ǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H�v
![]() �u��{�I�ɖ@����K���͕������߂ł��B�������߂͏����ꂽ�ʂ�̂��Ƃɉ߂��Ȃ��Ǝv����������܂���B�������������߂�������A��̓I�Ȃ��̂������Ă���ł��傤�B
�u��{�I�ɖ@����K���͕������߂ł��B�������߂͏����ꂽ�ʂ�̂��Ƃɉ߂��Ȃ��Ǝv����������܂���B�������������߂�������A��̓I�Ȃ��̂������Ă���ł��傤�B
���ꂩ���قǍ��X����́A�K�i�̕��̖͂������^�╶�ɂ��Ď��₷��ƌ����܂������A����͎���ł͎g���܂���B
����ȑO�ɁA�킴�킴���₷��܂ł��Ȃ��Ǝv���܂��v
![]() �u�ǂ����Ď��₷��܂ł��Ȃ��̂ł����H�v
�u�ǂ����Ď��₷��܂ł��Ȃ��̂ł����H�v
![]() �u�w�}�l�W�����g�V�X�e���̊j�ɂȂ�v�f�x�Ƃ́A�Ƃ���Ȃ�������4�̗͂v�������̊e���Ԃł��B�}�l�W�����g�V�X�e���̊j�ɂȂ�v�f�ɂ��Ă̗v���́A���ꂼ��̍��ڂ̒���shall�ŋL�q����Ă��܂��B
�u�w�}�l�W�����g�V�X�e���̊j�ɂȂ�v�f�x�Ƃ́A�Ƃ���Ȃ�������4�̗͂v�������̊e���Ԃł��B�}�l�W�����g�V�X�e���̊j�ɂȂ�v�f�ɂ��Ă̗v���́A���ꂼ��̍��ڂ̒���shall�ŋL�q����Ă��܂��B
�ł����炱���Łw�}�l�W�����g�V�X�e���̊j�ƂȂ�v�f����т����̑��ݍ�p���L�q���Ă��܂����H�x�ƕ�����Ă��A�����悤���Ȃ��B
�K�i�𗝉����Ă���l�Ȃ�A�e���Ԃŕ����悢�̂Ɏv���܂��ˁB�����Ă��̃��x���̎��������č�����[��������ɂ́A�ǂ����ׂ��������ł��傤�B
��قǁA���X����́A�w���₵�Ă����X�|���X�������āA���҂�������Ȃ��x�ƌ������B�B���͌Ђ̎��������Ή����҂ł��Ȃ��͓̂��R�ł��B
�č��̎���͑��肪�����ł���悤�ɁA���₷���悤�ɁA����͏��������ċ�̓I�Ƃ�����
�č��ŗǂ������炦�Ȃ��̂͊č����̋Z�ʂ̖��ŁA�č����̐ӔC�ł��v
���X�͖ʔ����Ȃ�������Ă��邪�A���͕����B
![]() �u���`�A�b�������Ȃ�܂����B���̘b�ɂ��O���Ă����ł��傤�B���������������A�܂��x�e����Ȃ���B
�u���`�A�b�������Ȃ�܂����B���̘b�ɂ��O���Ă����ł��傤�B���������������A�܂��x�e����Ȃ���B
����ł��̂ւ�ŗ��K�������܂��傤�B
�č����̕����Q�����Ă��������B
�p�����͈�@���������Ƃ���A�����@�č��ł͓O��I�Ƀ`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�܂���B���ł��_�ƃ}�j�t�F�X�g�̕s�����傫�Ȋ������߂Ă��܂��B
����͌`����
�ł�����A�@�Œ�߂�ʂ�ɂ��Ă��邩���m�F����͔̂��ɏd�v�ł��B
�Ƃ������ƂŁA���K��������Ă��܂����B�p�������_���������Ƃ��Ȃ��Ă����v�ł��B����̖��Ǝv���čl���Ă���đ��v�ł��B����̖��ƌ����Ă������̏������ł͂���܂���B�_���w�̖��ł��B
�F����ЂƂ�ЂƂ�ɗ��K���ꎮ�����n�����܂��B���n�����鎎�����́A���̍�����w�p���������ϑ��_�x�ŏ����Ɖ^���̓������܂��B
����ƑP�������f���邽�߂̎Q�l�����Ƃ��āA���Œ��́w�����̎����
�����͂��ꂩ�珅�@�č�����Ƃ��̎Q�l���ƂȂ�܂��B�č��ɂ͕K�����Q���Ă��������B�܂��A10����č�������Γ��ɓ����Ă��܂��܂��B
���ꂼ����e�͖��N�X�V����܂�����A�N�Ɉ�x�A�e�����l�b�g����v�����g���āA�ŐV�̂��̂����悤�ɂ��Ă��������B
�݂Ȃ����낵���ł����A�ł̓X�^�[�g���Ă��������B
�����ƁA�債�Ď��Ԃ͂�����܂���B20������Ώ\���ł��傤�v
�V�l3���A�R���A�č����̂ӂ��肪�A�������ɂƂ�ꂽ������Ă��邪�A����͋C�ɂ����������o��B
![]() �u�ǂ�A�����̃q�[���[�̎��͂��݂Ă�邩�v
�u�ǂ�A�����̃q�[���[�̎��͂��݂Ă�邩�v
���������Ȃ���k��́A�ׂ̍���������n�߂��̂�`������B
![]() �u���`�A�k�삳��A���邢�ł���B�����ōl���܂��傤��A�����ť���v
�u���`�A�k�삳��A���邢�ł���B�����ōl���܂��傤��A�����ť���v
�E
�E
�E
�E
10�������Ȃ��ō���́A�z�b�g�R�[�q�[�̓��������R�b�v��6�l���A�g���C�ɍڂ��Ė߂��Ă����B���ꂼ��̘e�ɃR�[�q�[�J�b�v��u���Ă����B
 |
 |
 |
 |
|
 |
|||
![]() �u���삳��A�ԈႢ�͂�������܂����H�v
�u���삳��A�ԈႢ�͂�������܂����H�v
![]() �u����͓����ł��B���Ȃ�̐�����Ɛ\���グ�Ă����܂��B
�u����͓����ł��B���Ȃ�̐�����Ɛ\���グ�Ă����܂��B
���z�肵���Q�l�����ƌ���ׂ�A���ׂČ�������͂��ł��B
�č����̕��́A���z���炢�Q�l����������܂ł��Ȃ��ł��傤���ǁv
![]() �u�����Ƃ��A���V�͈����ŁA����3���������v
�u�����Ƃ��A���V�͈����ŁA����3���������v
![]() �u����������3�ł����B����Ȃ�S�̂ł�10��20�͂���܂��ˁB���������͂܂�4���������Ă��܂���v
�u����������3�ł����B����Ȃ�S�̂ł�10��20�͂���܂��ˁB���������͂܂�4���������Ă��܂���v
![]() �u�R�{�N�͔p�����S������Ȃ����A��X�̃G�[�X�����v
�u�R�{�N�͔p�����S������Ȃ����A��X�̃G�[�X�����v
![]() �u�G�[�X���ł��ꂽ��s�b�`���[��ゾ�A�A�n�n�v
�u�G�[�X���ł��ꂽ��s�b�`���[��ゾ�A�A�n�n�v
�a�C���������ƌ������A���ӂ����Ƃ������A�y���C�ȕ��͋C��20�����߂����B
�E
�E
�E
�E
| �p���������@�͉��x����������Ă���B�����ŕ����1999�N���_�̋K���Ή��ɏ����Ă��Ӗ����Ȃ��̂ŁA�@�K���ɂ��Ă�2025�N���݂̂��̂Ƃ��Ă��܂��B |
![]() �u����ł͈�l����A�ԈႢ���w�E���Ă��������B�ŏ��̐l�������������Ă��܂��ƁA���̐l���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�����A��l����ł���B
�u����ł͈�l����A�ԈႢ���w�E���Ă��������B�ŏ��̐l�������������Ă��܂��ƁA���̐l���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�����A��l����ł���B
�ł͂����瑤���炢���Ă݂܂��傤�B��J����ǂ����v
![]() �u�����̌_�́w�ŏI�����Ɋւ�����x���Ɂw�_�ɋL�ڂ̒ʂ�x�Ƃ���܂����A�{�����ɁA����ɓ����镶�͂�����܂���B�Ƃ������Ƃ�NG�Ǝv���܂��v
�u�����̌_�́w�ŏI�����Ɋւ�����x���Ɂw�_�ɋL�ڂ̒ʂ�x�Ƃ���܂����A�{�����ɁA����ɓ����镶�͂�����܂���B�Ƃ������Ƃ�NG�Ǝv���܂��v
![]() �u�p�����̐��Ƃ͎R�{����̂��ӌ����f���܂��傤�v
�u�p�����̐��Ƃ͎R�{����̂��ӌ����f���܂��傤�v
![]() �u�ŏI�����Ƃ́A�����A�C�m�����A�Đ��݂̂��ł��B�C�m�����͓��ʂȏꍇ����������܂���
�u�ŏI�����Ƃ́A�����A�C�m�����A�Đ��݂̂��ł��B�C�m�����͓��ʂȏꍇ����������܂���
�����������Ă���܂���@�K���̗v�������Ă��܂���v
![]() �u�܂�s�K���Ƃ������Ƃł��ˁB����Ō��\�ł��B
�u�܂�s�K���Ƃ������Ƃł��ˁB����Ō��\�ł��B
���͎R�{����ł��v
![]() �u���Љ�͂ɂ��Ă̋L�ڂ�����܂���B�@���ł͂���܂��A�����̂̏��ɂȂ��Ă��܂��v
�u���Љ�͂ɂ��Ă̋L�ڂ�����܂���B�@���ł͂���܂��A�����̂̏��ɂȂ��Ă��܂��v
![]() �u�͂�OK�ł��B���͍��X����ǂ����v
�u�͂�OK�ł��B���͍��X����ǂ����v
![]() �u������O�ɁA���̌��ɂ��Ď���ł��B���Љ�]�X�͔z��ꂽ�����ɂ���܂���B���͐���̔��f���ł��܂���ł����v
�u������O�ɁA���̌��ɂ��Ď���ł��B���Љ�]�X�͔z��ꂽ�����ɂ���܂���B���͐���̔��f���ł��܂���ł����v
![]() �u��Ƃ�c�͔̂��Љ�I���͂Ǝ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA�x�@������o�Ă��܂��B����͔p���������ϑ������łȂ��A��Ƃ͂����Ȃ鐻�i�ł��T�[�r�X�ł��A�\�͒c�W�҂Ǝ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�u��Ƃ�c�͔̂��Љ�I���͂Ǝ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA�x�@������o�Ă��܂��B����͔p���������ϑ������łȂ��A��Ƃ͂����Ȃ鐻�i�ł��T�[�r�X�ł��A�\�͒c�W�҂Ǝ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
 �c�Ƃ�w������Ȃ�A�@�����Ȃǂ̂Ƃ�������܂��B�����łȂ�����ł����m�͂���Ă���͂��ł������
�c�Ƃ�w������Ȃ�A�@�����Ȃǂ̂Ƃ�������܂��B�����łȂ�����ł����m�͂���Ă���͂��ł������
�ł������X�͐��i�̔����ɂ͋q���\�͒c�W�҂łȂ����Ƃ��m�F���Ȃ���Ȃ�܂���B�p�����Ɍ��炸�A�@���͂����Ȃ��Ă��܂��B
�������ł���A�Ԃ�����Ȃ�
�w��\�͒c�ɊW���Ă���l�́A���R�A�p���������Ƃ̋������炦�܂���B��X���猩��A����Ė\�͒c�W�҂̊�ƂƎ�����Ȃ��悤��������m�F���Ȃ���Ȃ�܂���v
���F�x�@���̎哱�ɂ��A�e�s���{�����u�\�͒c�r�����v�𐧒肵���B���̂��b�����12�N�ゾ���A�`���ɏq�ׂ��悤�ɖ@�K����2025�N���_�Ƃ��Ă���B
![]() �u�ǂ����ꎄ�͒m��܂���ł����v
�u�ǂ����ꎄ�͒m��܂���ł����v
![]() �u�������w�@�̕s�m�͂�����������x�Ƃ���
�u�������w�@�̕s�m�͂�����������x�Ƃ���
���{�ł͊���Ō������ꂽ�@���́A�����͒m���Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�w�����͒m��Ȃ������x�ƌ����Ă��ʗp���Ȃ��̂ł��B
������{�͖@���̐������͊W����l�ɒm�炵�߂�悤�A�\���w�͂����Ă��܂��B�@�̑����͊�ƂɊW���܂�����A�ƊE�c�́A���H��c���Ȃǂ�ʂ��Ď��m��}���Ă��܂��B����@�̉����́A�Ƌ����������̍ۂɎ��m���Ă���̂͂������ł���ˁB
���X����͂��ꂩ�炢�낢��Ȏd���ɏA���ł��傤�B�d���ɂ���Ă��낢��Ȗ@���Ɋւ��܂��B���̂Ƃ��m��Ȃ������͒ʗp���܂���B
���̒��͂����Ȃ��Ă���Ɨ������Ă��������v
���X�͔[���ł��Ȃ��悤�Ȋ�����Ă������A���������Ȃ��Ǝv�����悤�Řb��i�߂��B
![]() �u�_���z�`�L�X�~�߂ł����A���{���Ȃ��ƃ_�����Ǝv���܂��v
�u�_���z�`�L�X�~�߂ł����A���{���Ȃ��ƃ_�����Ǝv���܂��v
![]() �u�č����̖k�삳��A�������ł����H�v
�u�č����̖k�삳��A�������ł����H�v
![]()
|
|
�����ւ��h�~�̐S�z���낤���A����͑S�y�[�W��
�T���v���͍���N��������̂��낤���ǁA�����Ȃ��ȁB
�Ƃ������A����͖�肠��܂���B���ۂ̊č��ł�OK�ɂ��Ă��������v
![]() �u���X����A��낵���ł����H
�u���X����A��낵���ł����H
����ł͊č��̃v���k�삳��A���C�Â��̖����ǂ����v
 |
|
| �����1�����ł��ǂ��B �_��ґo���������Ă��ǂ��B |
![]() �u�����������ĂȂ��ȁv
�u�����������ĂȂ��ȁv
���F�u�����������v�Ƃ́A�����ɉ���Ȃ�T�C���Ȃ肵�Ďg���Ȃ����邱�ƁB
�Ȃ��A�n���R�������̂�Y�ꂽ��A���������n���R���������ĂȂ����̂��͂����čēx�g���̂͒E�łɂȂ�˃z���g����
![]() �u���i�ł��B
�u���i�ł��B
�Ƃ���ŁA���ɏ��Ȃ��Ƃǂ��Ȃ�܂����H �܂��ǂ�������ǂ��ł��傤�H�v
![]() �u�E�łɂȂ�Ǝv���B
�u�E�łɂȂ�Ǝv���B
���u�́A�ォ��ł�����������悢�̂��ȁH�v
![]() �u�ォ�����������Ă��������Ǝv���܂���v
�u�ォ�����������Ă��������Ǝv���܂���v
![]() �u�������̂��������ʂ�ł��B�Ŗ@��8����2���̈ᔽ�͔���30���ł��B�Ƃ͂����A���ƂŎ������C���t���ĉ������ɂ͖��Ȃ��Ǝv���܂��B
�u�������̂��������ʂ�ł��B�Ŗ@��8����2���̈ᔽ�͔���30���ł��B�Ƃ͂����A���ƂŎ������C���t���ĉ������ɂ͖��Ȃ��Ǝv���܂��B
����Y��͍߂ɂȂ邱�Ƃ����͊o���Ă����Ă��������v
![]() �u�������������A���������d�������˂��`�v
�u�������������A���������d�������˂��`�v
![]() �u�ł́A���͍������ł��v
�u�ł́A���͍������ł��v
![]() �u�����������_�Ă��邪�A�n���R���E��łȂ��l�̔F�v
�u�����������_�Ă��邪�A�n���R���E��łȂ��l�̔F�v
���F�ЊO���M�Ƃ��_�������ł��ǂ��ƌ����ڏ����ꂽ��E�̐l�ɂ́A�E��(��E��)�Ƃ������̂��ݗ^����Ă���B���ʊO���ɉ�Ж��A���̒��ɖ�E��������Ă��āA�����͂Ȃ��B�_�E�s���͂ȂǂɎg���B
�Г��̏��ނ̌��قɂ͓��t��(�����{��E�{���t)�������B����͎ЊO�ɏo�����̂ɂ͎g���Ȃ��B
| ���t�� | ��E�� | �F�� | ||
|  |
��
�� |
||
| �Г��̌��قȂǂɗp����B �ЊO�ɂ͎g���Ȃ��B | �ЊO�ɏo�������Ɏg���B ���̊G��`���̂�10�������������̂�B | �l�I�ȗp�r�A������A�Г��̐\�����A�n�����Ȃǂɗp����B |
���F�F��Ǝ���E��s��̈Ⴂ�͎����̂��s�ɓo�^���Ă��邩�ۂ��̈Ⴂ�ł���B�O�����ł����h�ȃn���R�ł�����ɂ��Ȃ邵�F��ɂ��Ȃ�B
�����������Ă���ƈ�ӓo�^����s��ɂ��g���Ȃ��B���̘͂g�������Ă���ƁA�o�^�ł��Ȃ����Ƃ�����B
![]() �u����͂ǂ������߂ɂȂ�܂����H�v
�u����͂ǂ������߂ɂȂ�܂����H�v
![]() �u�߂ɂ͂Ȃ�Ȃ����A��肪�N����Ή�Ђ̖��łȂ��A�n���R���������l�̐ӔC�ɂȂ��Ă��܂��B�x�������x�ꂽ�琻�������l���������ƂɂȂ邩������Ȃ��v
�u�߂ɂ͂Ȃ�Ȃ����A��肪�N����Ή�Ђ̖��łȂ��A�n���R���������l�̐ӔC�ɂȂ��Ă��܂��B�x�������x�ꂽ�琻�������l���������ƂɂȂ邩������Ȃ��v
![]() �u���������ʂ�ł��B����͖@�I�Ȗ��ł͂Ȃ��A��Ђ̉^�p�̖��ł��B�Ђ���Ƃ��ĐE�����̂��Ă��Ȃ������Ƃ���ƁA���̐l�͎ЊO�_��̌����������Ă��Ȃ������̂�������܂���B
������ɂ���A��ЋK���ᔽ��NG�ł��v
�u���������ʂ�ł��B����͖@�I�Ȗ��ł͂Ȃ��A��Ђ̉^�p�̖��ł��B�Ђ���Ƃ��ĐE�����̂��Ă��Ȃ������Ƃ���ƁA���̐l�͎ЊO�_��̌����������Ă��Ȃ������̂�������܂���B
������ɂ���A��ЋK���ᔽ��NG�ł��v
![]() �u�Ȃ�قnj������Ȃ��E��������Ă��Ȃ�����A�����̃n���R�ő�p�����\��������B
�u�Ȃ�قnj������Ȃ��E��������Ă��Ȃ�����A�����̃n���R�ő�p�����\��������B
�Ƃ͂����A���삳�r�{�����������b�Ȃ̂�����A�^���ɍl���邱�Ƃ��Ȃ����A�A�n�n�n�v
![]() �u����N�͂Ȃ�ł��m���Ă���悤���ˁv
�u����N�͂Ȃ�ł��m���Ă���悤���ˁv
![]() �u�����������̂ł����璲�ׂ܂���B������Ȃ����̂́A�����s�A�Ŗ����A�@�����A���ޕ��Ȃǂɖ₢���킹�܂��v
�u�����������̂ł����璲�ׂ܂���B������Ȃ����̂́A�����s�A�Ŗ����A�@�����A���ޕ��Ȃǂɖ₢���킹�܂��v
![]() �u�k�삳��A���삳��̓v���ł���B�ォ��ڐ��͎���ł���v
�u�k�삳��A���삳��̓v���ł���B�ォ��ڐ��͎���ł���v
![]() �u�����A�C��t�����v
�u�����A�C��t�����v
![]() �u����ł͍ŏ��̎R�{����ɖ߂�A�ڂ��n�߂܂��傤�v
�u����ł͍ŏ��̎R�{����ɖ߂�A�ڂ��n�߂܂��傤�v
�E
�E
�E
�E
�O�����炢����ƁA���������������Ȃ��Ƃ����l����l��l�Ƒ����A���肪�����Ȃ�B
![]() �u���X����A�ǂ����v
�u���X����A�ǂ����v
![]() �u���W�^���Ə����̌_����z�������ł����A�����̊z�ʂ��Ⴂ�܂��v
�u���W�^���Ə����̌_����z�������ł����A�����̊z�ʂ��Ⴂ�܂��v
![]() �u�p�����S���̎R�{����A�������ł����H�v
�u�p�����S���̎R�{����A�������ł����H�v
![]() �u���W�^���̌_�͕ʕ\����1����4�̕����ŁA�p���������͐����ɂȂ̂�2�������ł�����Ŋz���Ⴄ�̂ł��B
�u���W�^���̌_�͕ʕ\����1����4�̕����ŁA�p���������͐����ɂȂ̂�2�������ł�����Ŋz���Ⴄ�̂ł��B
���m�ɂ͊o���Ă��܂��A�_����z��500���ȉ��ł��ƁA�����̌_�̈ł͉^���̌_��3�����炢�ł��B
500���ȏ�ɂȂ�ƁA�A���Ɛ����̍��͏������Ȃ�܂��B�����Ƃ���Ђ̔p�����_���500���ȏ�Ȃ�Ă܂�����܂���v
![]() �u���̒ʂ�ł��v
�u���̒ʂ�ł��v
![]() �u�����A������w�@�̕s�m�͂�����������x�Ȃ�ł����H�v
�u�����A������w�@�̕s�m�͂�����������x�Ȃ�ł����H�v
![]() �u���X����A�p�����S���̎R�{������w���m�Ɋo���Ă��Ȃ��x�ƌ����Ă��܂��B�����܂Ŋo����Ƃ͌����܂���B
�u���X����A�p�����S���̎R�{������w���m�Ɋo���Ă��Ȃ��x�ƌ����Ă��܂��B�����܂Ŋo����Ƃ͌����܂���B
�����������Ƃ����낤���ƁA���O�ɂ��n�������w�ł̎�����x��35�y�[�W�ɕ\������܂��B
���ꂩ��̔т̎�ł�����A�S���o���邱�Ƃ͂���܂��A�̂��Ƃ́w�ł̎�����x���Q�Ƃ��邱�Ƃ����͊o���Ă����Ȃ����v
�E
�E
�E
�E
![]() �u���C�Â����̂ł����A�����̌_�̕ʕ\1�ɁA��ނ̔p�����������Ă���܂����A�w�p�_�x�̗\�萔�ʂ����L���ł��B����Ō_����z�����܂�Ȃ��̂ŁA�̋��z���킩��܂���v
�u���C�Â����̂ł����A�����̌_�̕ʕ\1�ɁA��ނ̔p�����������Ă���܂����A�w�p�_�x�̗\�萔�ʂ����L���ł��B����Ō_����z�����܂�Ȃ��̂ŁA�̋��z���킩��܂���v
| �p�����̎�� �i�p�����f�[�^�V�[�g�ԍ��j |
�_��P��(�~) | �\�萔�� (���E�T�E���E�N) |
���̎{�� | �Z�Z�Z | ||
| �������@ | �����\�͖��� �����e�� |
�Z�Z�Z | ||||
| �p�v�� �iobaq001�j |
10,000�~ �^(�s�El�Em3�E��) |
(�s�El�Em3�E��) |
�j�� | 30t�^�� | �Z�Z�Z | �Z�Z�Z |
| �������� �iobaq012�j |
1500�~ �^(�s�El�Em3�E��) |
10t (�s�El�Em3�E��) |
�j��/Td> | 120t | �Z�Z�Z | �Z�Z�Z |
| �K���X���� �iobaq024�j |
2,000�~ �^(�s�El�Em3�E��) |
50 (�s�El�Em3�E��) |
�j�� | 30t | �Z�Z�Z | �Z�Z�Z |
�i�@�@�@�@�j |
�^(�s�El�Em3�E��) |
(�s�El�Em3�E��) |
||||
���F��\�̉��F�������ɗ\�萔�ʂ̋L�ڂ��Ȃ��B
![]() �u�ł͌_����z�������ĂȂ��Ă����܂邼�B
�u�ł͌_����z�������ĂȂ��Ă����܂邼�B
����͐���������2�������ŁA�_����z���L�ڂ̏ꍇ��200�~�ƂȂ��Ă���B�w�ł̎�����x�������܂��B
����N�A����ŗǂ����낤�v
![]() �u�c�O�Ȃ���A�Ŗ@��͗ǂ��̂ł����A�p���������@�ł͕ʂ̖�肪����܂��B
�u�c�O�Ȃ���A�Ŗ@��͗ǂ��̂ł����A�p���������@�ł͕ʂ̖�肪����܂��B
�p���������@�̎{�s�K���ɁA�_�ɋL�ڂ��ׂ����������߂Ă���܂���
![]() �u�Ȃ�قǁA�����������܂肪����̂��B���ɂȂ����v
�u�Ȃ�قǁA�����������܂肪����̂��B���ɂȂ����v
![]() �u���͈ȑO����s�v�c�Ɏv���Ă����̂ł����A�_����z���_�ɏ����Ȃ���200�~�ōςނȂ�A�ʂ��P�����L�����Ă����Ȃ���A�ł��ߖ�ł��܂��ˁB
�u���͈ȑO����s�v�c�Ɏv���Ă����̂ł����A�_����z���_�ɏ����Ȃ���200�~�ōςނȂ�A�ʂ��P�����L�����Ă����Ȃ���A�ł��ߖ�ł��܂��ˁB
�������p���������̌_�ł͖@�ᔽ�ł����A�ʏ�̎���̌_�̋��z�𖢋L�ڂɂ���200�~�̈�\��ǂ��Ȃ�܂����H�v
![]() �u�k�삳��A��������Ɖ������ɂȂ�̂ł��傤���H �E�łł����H
�u�k�삳��A��������Ɖ������ɂȂ�̂ł��傤���H �E�łł����H
�ł̎����������ƁA���i���ӏ����͂���܂���ˁv
�F���k��̊�����߂�B
![]() �u���`��A�ǂ��Ȃ�̂��ȁH
�u���`��A�ǂ��Ȃ�̂��ȁH
����グ���B����搶�Ȃ炲�������ȁH�v
![]() �u�����^��Ɏv���܂����B����Ŗ₢���킹�܂����B
�u�����^��Ɏv���܂����B����Ŗ₢���킹�܂����B
���{�̐Ŗ����͂���قNJÂ��Ȃ��A�_�ɋL�ڂ��Ȃ��Ă����Ϗ���x�����т�����A������_����z�Ƃ݂Ȃ��ĉېł��邻���ł��B
�����Ȃ�Ɛ�قǂƓ������ߑӋ���˂Ȃ�܂���B
�������A���̏ꍇ�͋��z����܂�Ȃ��ꍇ��200�~�ƒm���Ă��āA�Ӑ}�I�ɋ��z�������Ȃ������Ǝv���܂��B�������z������~�Ȃ�A����Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ł��傤�B
�ł����\�����̎���Ȃ�A�����Ƃ݂Ȃ���āA�ƍ߂Ƃ��ċN�i����邩������܂���v
![]() �u�Ȃ�قǁA�o���ɕ����Ă݂悤�v
�u�Ȃ�قǁA�o���ɕ����Ă݂悤�v
���F�Ŗ�����������O�Ɉ��z�s���ɋC�Â����Ƃ��́A���₩�ɕs�����̈Ł{�ߑӐł��x�����悤�ɂ���B�ߑӐł͕K�v�Ȉł�2�{�ł���B���ꂪ�D�����̑Ή��Ƃ����B���̏ꍇ�́A�ߑӐł����z�����炵���B
�\�ɏo�ĂȂ��Ȃ�A�s���z��lj����������Ŏ������͂Ȃ����낤�Ǝv���͈̂��Ȃ̂��H
�Ŗ������Ō��������ꍇ�A���ƂȂ������̂����łȂ��A���̌_�̓_���Ƃ��̓_�����ʂ̕��w�������B��肪����Γ��l�ɑΏ����K�v�ƂȂ�B
200�~�̈�\��Ƃ��B���ȂLj����Ȃ��̂́A�Y�������ɂȂ邻�����B
2000�N�㏉�߂ǂ����̑��ЂŁA�����̌_�Ɉz�s�������o���ĕ��ꂽ�B������������̉�Ђ��A�_�̑��_���������B���͎����K���œ_�������҂ł���(��)�B
![]() �@�{���̍�����
�@�{���̍�����
����Ƃ��b�̂Ȃ�����������菑�����Ƃ���ƁA�~�܂�܂���A�I���܂���B
�Ƃ������ƂŁA�����ň�U���Ď���ɑ����`
�Ƃ���ő�120�b�������Ă���ƁA������13,000���ɂȂ����̂ŁA��120�b�Ƒ�121�b�̓�ɕ����܂����B
�������Ƃ��A�O�������̑�120�b��7,000���ł����B
���̌�A���������������Ă��邤���ɁA�Ȃ����A�܂�10,000�����܂����B
���̕��ł͌㔼��121�b�͍X��2�����ɂ��Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ����ƥ�����
�ǂ�ł������X�A�����l�ł��B
��Ђœǂ�ł��āA��������܂��ʂ悤��
| �����O�̘b | ���̘b���� | �ڎ� |
| ��1 |
�`���ƂƂ͎����I�Ȕ�Q��댯�������炷���̂ł͂Ȃ��A�s�ׂ��ւ���`���I�Ȉᔽ�ɂ��ƍ߂ł���B �Ƌ��s�g�сA�e��s���͏o�R��Ȃǂ�����B �����|���m�͏������Ă��邾���ł͔ƍ߂ɂȂ炸�A�`���Ƃł͂Ȃ������ł��B�����|���m�����߂ƂȂ�v���́A�u�����|���m�ł���Ƃ̔F���v�Ɓu�̈ӂɏ������Ă���Ƃ̔F���v�����āu���Ȃ̐��I�D��S�����ړI�v�̎O�_���K�v�ŁA�p�\�R���ɉ摜�⓮�悪�����Ă��������Ȃ�߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��ƁB ���Ȃ݂ɐ��l�|���m�͏������邱�Ƃ͍߂łȂ��A���Еz(�s���葽���̐l�ɓn�����ƁA�L���E�������Ɋ܂�)���邱�Ƃ��߂ɂȂ�܂��B �Ȃ��L���Ƃ͗L�������łȂ������ȊO�̑㏞���܂ނ����ł��B | |
| ��2 |
�E���Œ��u�ł̎�����v | |
| ��3 |
�E�����s�����u�_�ɓY�t���ׂ����ʁv | |
| ��4 |
���E�I�ɉ������D�̊C�m������1990�N�㔼�܂ōL���s���Ă���A1996�N�́u�����h�����i�C�m�����h�~���j�v�����Ō����֎~�ɂȂ�2007�N�Ɋ��S�֎~�ƂȂ����B ����ɂ��C�m�ւ̉h�{���̕�[�����������킯�����A���l���̌����͂Ȃ��ƌ����Ă���B�܂������p�Ȃǂł͗n���_�f���������ċ���ނ̑����̕�����B �����{��k�Ђ̂��ꂫ�ނɂ��ẮA���ʂɊC�m�����������ꂽ�B | |
| ��5 |
���̃��[�������S�ɓK�p�����A�\�͒c�W�҂͎Ԃ����ĂȂ��͂������A�F�����Ԃɏ���Ă��܂��B�ŋ߂̓x���c�͌����āA�A���t�@�[�h��N�T�X�����������ł��B �ǂ����Ă���̂��Ƃ����ƁA���l���`�̎Ԃɏ���Ă���(���`��)�A�K�������܂���Ȃ����ÎԎs���l�Ԃ̔����A���l�̎Ԃ����(�����^�J�[�͖���)�A�Ȃǂ������ł��B �Z�ނƂ���������ł��B | |
| ��6 |
�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���{�s�K��(��8����4��2) |
����800�̖ڎ��ɖ߂�
�^�C���X���b�vISO�̖ڎ��ɖ߂�
     |
