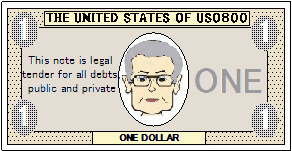注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
第120話から続く
佐川の講義が終わり、北川と坂口は監査部に戻ってきた。二人は自席に戻らず、給茶機で紙コップにコーヒーを注いで打ち合わせ場に座る。
本日の反省会、いや先ほどまでの講習の棚卸だろうか。
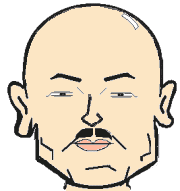 北川 |
|
|
 坂口 |
![]() 「午後
「午後
![]() 「私は吉井部長との話に最初から出ていませんので、まだ目的を聞いていないのです。
「私は吉井部長との話に最初から出ていませんので、まだ目的を聞いていないのです。
どんなお話だったのですか?」
![]() 「坂口君は未来プロジェクトって知っているか?」
「坂口君は未来プロジェクトって知っているか?」
![]() 「未来プロジェクト?・・・・・・そう言えば、名前を聞いたことがあります。イントラの社内電話帳に載っていましたね。何をしているかは存じません」
「未来プロジェクト?・・・・・・そう言えば、名前を聞いたことがあります。イントラの社内電話帳に載っていましたね。何をしているかは存じません」
![]() 「未来プロジェクトは経営企画室の下部組織、正しくはプロジェクトだからタスクを果たせば解散なのだが、もう既に2年以上も活動している。
「未来プロジェクトは経営企画室の下部組織、正しくはプロジェクトだからタスクを果たせば解散なのだが、もう既に2年以上も活動している。
業務内容が内容だから課とか部にすると差しさわりがあるのだろう。
ところで何をしているかと言えば、当社は未来を予知する方法を開発したそうだ」
![]() 「未来を予測!、まさかエライサンが占いにでもはまったのですか?」
「未来を予測!、まさかエライサンが占いにでもはまったのですか?」
![]() 「私もそう思ったよ。だが現実に未来プロジェクトは、毎年極めて大きな成果を出している。証拠も見せられた。
「私もそう思ったよ。だが現実に未来プロジェクトは、毎年極めて大きな成果を出している。証拠も見せられた。
もう2年前かな、営業秘密を漏洩したと懲戒処分になった奴がいたのを覚えているか? そいつはその未来の情報を週刊誌に売ったそうだ。
未来予測をしている会社の記事が週刊誌に載ったのを、あれがそうだ。
覚えていないか。それじゃ、今年の2月、テレビ朝日のニュースステーション![]() が、所沢はごみ焼却炉から発生するダイオキシンで汚染されていると報道したのを知っているかい?
が、所沢はごみ焼却炉から発生するダイオキシンで汚染されていると報道したのを知っているかい?
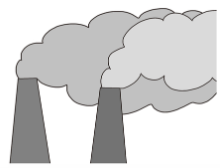
![]() 「知らないわけありませんよ。あれ以来、日本中が大騒ぎですからね。
「知らないわけありませんよ。あれ以来、日本中が大騒ぎですからね。
私の住んでいる市単独でごみ焼却炉を更新するのは経済的に無理で、近隣のいくつかの市と共同して新しい設備を入れると言っています。大金がかかるそうです」
![]() 「1996年に・・・ニュースステーションが報道する3年前だ・・・それを予知したことが、未来プロジェクトを作るきっかけとなったそうだ。
「1996年に・・・ニュースステーションが報道する3年前だ・・・それを予知したことが、未来プロジェクトを作るきっかけとなったそうだ。
それを契機に当社は、工場や関連会社、支社、健保会館などにある焼却炉すべてを、去年までに全廃した」
![]() 「ほう、それはまたどうしてですか?」
「ほう、それはまたどうしてですか?」
![]() 「簡単さ、ダイオキシンは猛毒だと判明したため、君が言ったように、今後は高性能な焼却炉以外、運用できなくなる。更に今までの焼却炉を撤去し無害化するのに一基1億以上かかるそうだ。
「簡単さ、ダイオキシンは猛毒だと判明したため、君が言ったように、今後は高性能な焼却炉以外、運用できなくなる。更に今までの焼却炉を撤去し無害化するのに一基1億以上かかるそうだ。
全社の焼却炉は数十基、グループ全体なら百基はあるだろう。
だがニュースステーションで報道する前、問題が公になる前に処分してしまえば、その1割のお金で処理できた。もちろん100基も一度にはできない。だから3年かけて処分したわけだ。
それによる費用削減効果は50億とか60億とか聞いた」
![]() 「それって法違反スレスレではないのですか?」
「それって法違反スレスレではないのですか?」
![]() 「いや、法規制はまだないのだ
「いや、法規制はまだないのだ
それにM電器は2月に問題になってすぐに、使用している社内の焼却炉を全部廃棄すると公表した。もちろん今まで通りダイオキシン除去処理せずに廃棄した。
世間は、即座に焼却を止めた判断を評価した。そのときは誰も焼却炉がダイオキシンに汚染されていることに気づかなかったようだ。現時点まだ焼却炉の廃棄方法は規制されていないのだよ」
![]() 「多くの会社はどう対応しているのですか?」
「多くの会社はどう対応しているのですか?」
![]() 「多くは、現有の焼却炉をダイオキシンが発生しないよう、改造とか運転条件を検討しているところだ。
「多くは、現有の焼却炉をダイオキシンが発生しないよう、改造とか運転条件を検討しているところだ。
半年もすると、そんなことではダイオキシン発生を止めることはできないと分かることになる」
![]() 「なるほど、それじゃM電器のように『止めます』と宣言したほうが、潔い良いと世間から見られますか。
「なるほど、それじゃM電器のように『止めます』と宣言したほうが、潔い良いと世間から見られますか。
おっと、そしたらニュースステーションが報道する前に、全廃した当社グループはどういう評価なのでしょう?」
![]() 「当社が既に廃棄したことは公表していない。知られても、他人様にはまぐれ当たりと思われるだけじゃないか。
「当社が既に廃棄したことは公表していない。知られても、他人様にはまぐれ当たりと思われるだけじゃないか。
それに目立たたないのも良い。悪目立ちは憎まれる。
ダイオキシンだけでなく、1997年のアジア通貨危機もあった」
| |||||
| |||||
![]() 「アジア通貨危機で何かしたのですか?」
「アジア通貨危機で何かしたのですか?」
![]() 「聞いた話だが、アジア通貨危機発生の1年以上前に知っていたそうだ。それで投資計画、生産計画に反映して損害を最小にした。
「聞いた話だが、アジア通貨危機発生の1年以上前に知っていたそうだ。それで投資計画、生産計画に反映して損害を最小にした。
また取引先の倒産なども知っていたから、取引の決定とか契約条件などに反映して損失の最小化・利益の最大化を図ったそうだ。
知らぬままでアジア通貨危機に直面したのに比べて数百億の差が出たとか」
![]() 「数百億ですか・・・・・・そりゃすごい」
「数百億ですか・・・・・・そりゃすごい」
![]() 「そして今、未来プロジェクトを信用したウチの経営陣が懸念しているのは、これからの企業不祥事の多発だ」
「そして今、未来プロジェクトを信用したウチの経営陣が懸念しているのは、これからの企業不祥事の多発だ」
![]() 「企業不祥事と言っても、思い当たりがありません。どんなことがありました?」
「企業不祥事と言っても、思い当たりがありません。どんなことがありました?」
![]() 「いや、まだ問題になっていない。これから発覚するんだ。
「いや、まだ問題になっていない。これから発覚するんだ。
未来プロジェクトの報告書では、2000年代初めに企業不祥事が多発するという。
問題がある車をリコールしなかった、製紙会社とか家電メーカーは材料表示を偽る、原発では異常の記録を改ざん、公害防止では測定データの改ざん、大企業による不法投棄などが発覚するという
これも所沢のダイオキシンのように連日報道され大騒ぎになる。ダイオキシンと違い、こちらは明確に騙されたということもあるし、命の危険や安全に関わることが多いからだ」
![]() 「それはまた・・・・・・当社はどうなのですか?」
「それはまた・・・・・・当社はどうなのですか?」
![]() 「実は当社で不祥事が発覚するのか・しないのか、そこは曖昧で良く分からないそうだ。
「実は当社で不祥事が発覚するのか・しないのか、そこは曖昧で良く分からないそうだ。
ワシの想像だが、我々の行動で変わるものは、予測できないのではないのかな? 我々が何もしなければ問題になり、これからしっかり点検して是正すれば問題にならないのかと・・・
そんなわけで経営企画室から、環境部には環境不祥事がないかどうか、今年中に調査して綺麗にしておけと指示が出たわけだ。
しかし会社規則から、環境部が社内の監査をすることはできない。ISOの内部監査などは会社の公式な内部監査じゃないからね。顧客との契約による内部監査と同じ扱いだ」
![]() 「そこらへんからは、私も呼ばれて話を聞いていました。
「そこらへんからは、私も呼ばれて話を聞いていました。
取締役会に報告する監査は、会社規則で監査部がすることになっていますからね。ISO認証対応の内部監査は、監査部にこない。
言い換えると、取締役会に報告されない内部監査は、会社の規則で定める内部監査ではない」
注:会社の内部監査というのはいろいろある。
法で決まっているものは会社法第362条第4項で「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」とあり、会社法施行規則で委員会設置会社・監査役設置会社・監査役設置会社以外の株式会社に分けて記述がある。
二者間の品質保証要求やISO認証のための内部監査は法的な根拠はなく、商取引上の契約による内部点検に過ぎない。
![]() 「最初、吉井部長の話では、監査部が未来プロジェクトからの報告に基づき、臨時の環境監査をすることにして、それを環境部に丸ごと委託するような形でどうかと言ってきたらしい」
「最初、吉井部長の話では、監査部が未来プロジェクトからの報告に基づき、臨時の環境監査をすることにして、それを環境部に丸ごと委託するような形でどうかと言ってきたらしい」
![]() 「筋から言えば、未来プロジェクト、いやその上の職制である経営企画室から、監査部に環境監査をせよと言った方が正しい形でしょう」
「筋から言えば、未来プロジェクト、いやその上の職制である経営企画室から、監査部に環境監査をせよと言った方が正しい形でしょう」
![]() 「そこが問題なのだが、経営企画室長の中山取締役が、監査部は環境監査をする実力がない・・・・・・いや弱いと考えて、環境部に話を持って行った経緯があるのだ」
「そこが問題なのだが、経営企画室長の中山取締役が、監査部は環境監査をする実力がない・・・・・・いや弱いと考えて、環境部に話を持って行った経緯があるのだ」
![]() 「まあ〜、それは事実かもしれませんね。
「まあ〜、それは事実かもしれませんね。
現実に知的財産、情報セキュリティ、輸出管理などの業務監査は、社内の専門家に委託していますからね」
![]() 「監査部が行う業務監査の中の環境監査は環境部ではなく、工場の環境部門を担当している部長級に委託している・・・・・・でも環境管理に詳しい部長なんていないよ。
「監査部が行う業務監査の中の環境監査は環境部ではなく、工場の環境部門を担当している部長級に委託している・・・・・・でも環境管理に詳しい部長なんていないよ。
そもそも環境部門は日陰の仕事、『高卒で現場上がりの課長
5年前環境部ができたとき『業務監査の環境のパートを環境部に委託する』と書き換えていたら良かったのだが。監査部はこのとおり部長も部員も出入りが激しくて、長期的な視点がないからね」
![]() 「ということで、今日は環境監査を環境部に委託するにあたり、環境部の監査の様子を探りに行ったということですか?」
「ということで、今日は環境監査を環境部に委託するにあたり、環境部の監査の様子を探りに行ったということですか?」
![]() 「そういうことだ。坂口君は吉井部長に引っ張られて鳩豆だったろう」
「そういうことだ。坂口君は吉井部長に引っ張られて鳩豆だったろう」
![]() 「最初はそうでしたが、話を聞き、手を動かすと勉強になりました。
「最初はそうでしたが、話を聞き、手を動かすと勉強になりました。
あの契約書のチェックもためになりましたし」
![]() 「見たところ講師をしていた佐川は監査についても、環境法についてもしっかりしていると思った。だが佐々木という若造は使い物にならんな。環境部の応援のときは、参加を断ろう。
「見たところ講師をしていた佐川は監査についても、環境法についてもしっかりしていると思った。だが佐々木という若造は使い物にならんな。環境部の応援のときは、参加を断ろう。
明日もやるらしいが、坂口君は明日以降も聞きに行ってくれないか?
廃棄物だけでなく、環境監査の要点を把握しておくことは我々にも必要だ」
![]() 「えっと、北川さんの話を聞いて、ちょっと気になるのですが、企業不祥事には環境だけでなく、リコール隠しとか賞味期限改ざん、材料偽装などもおっしゃいましたね。
「えっと、北川さんの話を聞いて、ちょっと気になるのですが、企業不祥事には環境だけでなく、リコール隠しとか賞味期限改ざん、材料偽装などもおっしゃいましたね。
当社も環境だけでなく品質関係や営業なども、いや全部門の監査が必要ではないですか?」
![]() 「言われるとその通りだ。
「言われるとその通りだ。
ちょっと待てよ」
北川はポケットから構内用PHS電話と取り出す。
![]() 「あっ、吉井部長、監査部の北川です。今日は講習に参加させていただきありがとうございます。勉強になりました。
「あっ、吉井部長、監査部の北川です。今日は講習に参加させていただきありがとうございます。勉強になりました。

明日以降もウチの坂口が参加させてもらいます。
ところで別件ですが、環境については吉井部長からお話がありまして、監査部が実施しお宅に協力を求めることになりましたね。
しかし監査部で話し合ったとき聞いたのは、環境以外にも企業不祥事が問題になるということでしたね。よく考えてみれば、環境以外の部門についても臨時の業務監査をせんといかんですよね?」
![]() 「私はそうするものと考えておりました。
「私はそうするものと考えておりました。
先月の取締役会で、経営企画室から未来プロジェクトの次年度のイベント報告があり、その中に不祥事多発がありました。そして社長から事前の点検と是正処置を指示されています。
事業本部や本社部門には、未来プロジェクトの報告書が回っています。今頃はすべての部門で、不祥事の類型を想定して内部で点検をしていると思います。
そもそも不祥事対策は監査ではありません。
第一義にはそれぞれの部門が、違法や手抜きがないかを確認するのが基本です。それをどのように進めるか、計画を立てて実行し、フォローするのは、それぞれの部門の責任でしょう。
監査部としては、各部門が点検と不具合の是正が完了したかの確認として、半年後に業務監査をする思っていました。
私としては、その前に監査部が臨時監査をした方が良いと思い、お節介ながら環境についてはお手伝いしようと、本日、お話を持って行ったつもりです。
北川は吉井部長の言葉を聞いて、愕然とした。吉井部長の話は、理にかないまた現実的でもある。でもなぜか一枚上手に感じて、いや優等生のような弁に少し反感を持った。
それなら、なぜもっと早く声をかけてくれなかったのか・・・
もっともそれを監査部長は知っていたはずだ。なぜそれを部内に周知し、監査部の対応を考えさせなかったのか。監査部次席の北川でさえ未来プロジェクトの報告を知らなかったのだ。
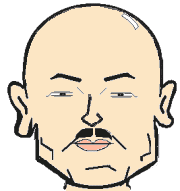 | |||
| なんということだ ! これは監査部の怠慢だ |
|||
十分情報はあるのに、それを無視し対策せずに問題を起こすなど許しがたい。ましてやここは監査部だ。
監査部の使命は悪者を見つけることじゃない、会社を健全で信頼される組織として存続・発展させることじゃないか。
万が一、いやこのままでは間違いなく問題が起きる。問題が起きたとき、監査部は使命を果たすため最大の努力をしたと申立てできるのか。
北川は脇の下に冷や汗が流れるのを感じた。
いや、まだ時間はある・・・そう思い直した。。
![]() 「いや、おっしゃる通りです。しかし私は今日、吉井部長から言われるまで未来プロジェクトの報告というものを知りませんでした。ということは監査部長が後生大事にしまっているのか、それとも何もしないで良いと判断したのか・・・
「いや、おっしゃる通りです。しかし私は今日、吉井部長から言われるまで未来プロジェクトの報告というものを知りませんでした。ということは監査部長が後生大事にしまっているのか、それとも何もしないで良いと判断したのか・・・
もちろん、吉井部長以外の事業本部や本社部門は何をしているのか、これはどこかがフォローすべきでしょうけど・・・・」
*
*
*
翌日である。
坂口は昨日に続いて午後から廃棄物の監査の講習を行った。
受講者は新人3人と山口、そして監査部の坂口である。
今回はマニフェスト票とはなにか、法規制、使い方、ルート、書き方、チェックなどを行った。
これも一通りすると、もう半日が過ぎている。
注:マニフェスト票が特管産廃だけでなく産廃全体に義務化されたのは1998年で、このお話のときは完全適用されていた。
また電子マニフェスト票が使われるようになったのは1998年からですが、1998年に使われたのは全体の1%もなかった。
廃棄物と言っても、廃棄物の管理、リサイクル、削減など、法に関わることはたくさんある。公害防止、化学物質管理などもするとあと半月はかかりそうだ。
それに大事なことには監査の方法論もある。力を入れないと佐々木のような鬼っ子を産み出す。7月には監査開始になることだし・・・・・・佐川は気をもむ。
・
・
・
・
佐川がホワイトボードを消したり、椅子を元に戻したりしようとすると、山本と大谷が「課長、私たちがします」と仕事を代わった。
それで佐川が帰ろうとすると、坂口が後ろの方の席に座って佐川を呼ぶ。
何事かと佐川が傍に行って座る。
![]() 「いやあ、佐川さんの話を聞く前は、ISOの内部監査のような形式だけで意味のない監査かと思ったが、お話を聞いていると実戦的で徹底的な内容で感心しました。
「いやあ、佐川さんの話を聞く前は、ISOの内部監査のような形式だけで意味のない監査かと思ったが、お話を聞いていると実戦的で徹底的な内容で感心しました。
佐川さんは監査のしかたをどこかで習ったのですか?」
![]() 「誰にも習ったことはありません。もう6年前になりますか、ISO9001が始まったとき、工場で私が認証の担当になりました
「誰にも習ったことはありません。もう6年前になりますか、ISO9001が始まったとき、工場で私が認証の担当になりました
ともかく規格を入手してから、何度も読んで考えました。たくさんある規格要求はいったい何を求めているのか、その規格要求を満たすにはどうするのか、適合を立証するには、どうすればよいのかと、
昨日、若手の佐々木さんが、監査とは規格の文言の文末を疑問文にすれば良いと言いました。坂口さんがここに来る前だったかもしれません。
それは1993年当時、内部監査どころかISO審査でも行われた方法です。
でもちょっと考えればおかしいというか、まったく使えない方法です。
まずISO規格はたくさんの要求事項がありますが、それを従業員に知らしめろという要求はありません。
そもそも、ISO認証はビジネス上必要だから認証するとしても、なんで審査員のために余計なことを勉強しなければならないのか、それを疑問に思わなければ企業人ではありません」
![]() 「従業員に規格を理解させる要求はないのですか?」
「従業員に規格を理解させる要求はないのですか?」
佐々木の声を聴いて、佐川と坂口が驚いて声の方を向いた。なんと隣の机で四名がノートを開いてメモまでして聞いている。
まあ一人を相手に話すのも5人を相手に話すのも同じだし、お互いに時間があるなら問題ないだろう。
![]() 「今の時代、お客様は神様と敬うだけでなく、もっと実質的な顧客満足を満たすことが重要になっている。それは監査も同じです。
「今の時代、お客様は神様と敬うだけでなく、もっと実質的な顧客満足を満たすことが重要になっている。それは監査も同じです。
まず監査のお客様は誰なのかとなると、形上は監査を依頼した経営者でしょう。しかしお客様といってもそれを考える主体の立場によって異なります。
 よく言われるのはディズニーランドのお客様は誰なのかという話があります。
よく言われるのはディズニーランドのお客様は誰なのかという話があります。
ジジ・ババの金で、赤ん坊を連れてディズニーランドにいくジジ・ババと赤ちゃんを連れた若夫婦がいたとして、そのうちの誰が顧客かというものです。
ジジ・ババは金を出す人、サービスを受ける赤ん坊が顧客というのが正解かもしれませんが、実際は赤ちゃんはミッキーも白雪姫も分からない。いつも子供の世話で大変な若夫婦が安息をえる顧客にも思えるし、赤ちゃんを愛でるジジ・ババが顧客とも思えます。
ISO規格では顧客とは『最終段階の消費者、使用者、得意先、受益者、すなわち第二者
でも最終顧客だけが顧客ではないですね。問屋の顧客は最終顧客でなく買いに来る小売店でしょう。最終顧客でないからと、対応が悪くて良いはずがありません。
監査で誰が顧客かはともかく、質問しても回答が得られなければ監査をすることはできません。であれば監査を受ける人が監査員は分かってもらえる言葉を分かるように話さないといけません。
それは顧客満足ではなく、監査員満足かもしれません。いずれにしても監査をスムーズにする方法ではあります。
ただ監査が行われる理由は、仕事を頼むためとか、何か問題を起きてその原因を調べるため、そして今後も取引できるかの調査です。ですから監査を受ける側が拒否するようなことはあまりありません。まあ、拒否されたら監査員としては手がありませんから監査を終了して良いと思います。
現在計画している環境遵法監査は中止するわけにはいきません。もし回答を拒むなら、強権発動しても、真面目に監査を受けるよう指示してもらいます。
現実にはそのような理由で、回答が得られないということはまずありません。
最大の原因はコミュニケーションがとれないことです。もっと具体的に言えば、言葉が通じないことです。
監査員の言葉が理解されないなら、理解してもらえるよう手を打たねばなりません。
現在はありませんが、ISO9001の初版が作られたときには、『品質システムの監査の指針 ISO10011』というのがありました。その中に監査の準備という項番があり、そこで利用できるようにするものの中に『監査で使用する言語』が挙げられています。
理解してほしいのは、監査で使用する言語が利用できるようにするのは、監査側の責任です。もちろん準備するのは被監査側かもしれない。
監査で使う言語は何かを調べて、それが使えるようにするのは監査側だということです」
![]() 「おっしゃる意味が分かりません」
「おっしゃる意味が分かりません」
![]() 「例えばこの工場にイギリス人が監査に来るとしましょう。その場合、審査に来る人がこちらに連絡を取り、監査は何語で行うのか、日本語なら監査員は話せないから通訳を用意してくれと要求する責任は監査側にあるということです。
「例えばこの工場にイギリス人が監査に来るとしましょう。その場合、審査に来る人がこちらに連絡を取り、監査は何語で行うのか、日本語なら監査員は話せないから通訳を用意してくれと要求する責任は監査側にあるということです。
監査を受ける側がウチは日本語しか使えませんからどうしますかと、問い合わせる義務はないということです
もちろん通訳の費用は監査を受ける側の負担ですね。移動する電車の切符を手配するのは監査側ですが、その費用を払うのは監査を受ける側というのと同じです
![]() 「よく分かりました」
「よく分かりました」
![]() 「ここで考えてほしいのですが、日本人が監査に来るとき、監査前に何語で監査しますかと事前確認をするでしょうか?」
「ここで考えてほしいのですが、日本人が監査に来るとき、監査前に何語で監査しますかと事前確認をするでしょうか?」
![]() 「日本でそんな状況が起こりますか? 関西弁の人が東北に行っても、監査はできるでしょう」
「日本でそんな状況が起こりますか? 関西弁の人が東北に行っても、監査はできるでしょう」
注:私個人の経験では、東北生まれ東北弁の私が、北海道、関西、九州、沖縄まで行ったが言葉で困ることはなかった。もちろん私はISO用語など使うわけはない。
![]() 「話が通じないことはあります。
「話が通じないことはあります。
例えば『当社ではISO用語は通用しないので、監査にあたってはISO用語を使わないようにするか、通訳を用意してください』と要求することはおかしくないでしょう」
![]() 「ISOの審査をするのに、ISO用語を使わないでできますか?」
「ISOの審査をするのに、ISO用語を使わないでできますか?」
![]() 「私に言わせるとISO用語を使わずに審査できなくちゃ、一人前の審査員/監査員じゃないと思う」
「私に言わせるとISO用語を使わずに審査できなくちゃ、一人前の審査員/監査員じゃないと思う」
![]() 「そんなこと不可能だと思います」
「そんなこと不可能だと思います」
![]() 「定義されているものは、定義に置き換えればよいですかね?」
「定義されているものは、定義に置き換えればよいですかね?」
![]() 「そう簡単でもないですよ。
「そう簡単でもないですよ。
定義そのものを読んでも分からないものはたくさんあります。
環境の定義は『大気、水質、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの(ISO14001:1996 定義3.2)』です。
それを聞いて、『環境には人間関係は含むのか?』と聞かれたら、答えられますか?
大谷さん、質問です。『環境』の定義は、人間関係を含むのでしょうか?」
![]() 「日本語の文章を読むと人間関係も含むようですが、どうなんでしょう?」
「日本語の文章を読むと人間関係も含むようですが、どうなんでしょう?」
![]() 「私が質問したのですから、質問で返されても困ります。
「私が質問したのですから、質問で返されても困ります。
人はhumansの訳です。humansは複数の人ではなく、『ヒト』という生物種を意味します。
workplace environmentと言った場合、職場環境と訳されます。働く人々に直接影響を与えるもの意味で、物理的なものとして騒音・振動・気温・照明などがあり、非物理的なものには企業文化、人間関係、ポリシーなどがある。
着目するのは、従業員の幸福・健康、生産性、そして組織運営です。
environmental problemと言った場合、地球環境問題と訳される。これは人間の活動や自然現象によって引き起こされる、気候や生態系の広範囲ときには地球規模の変化や異常をいう。着目するのは、地球とその生態系の健全さにある。
(global) environmental issuesという表現もある。どちらも意味は同じかな。
定義と語義を考えあわせると、ISO14001の環境は人間関係は含まないと言えます」
![]() 「『環境』に人間関係を含むかどうか考えるのに、そんなにいろいろ調べないといけないのですか?」
「『環境』に人間関係を含むかどうか考えるのに、そんなにいろいろ調べないといけないのですか?」
![]() 「審査員の中には『環境には人間関係も含む』という方もいます。するとセクハラ・パワハラもISO14001に含めなくちゃならないでしょう。そういう拡大解釈を、断れるようにしておかないとね。
「審査員の中には『環境には人間関係も含む』という方もいます。するとセクハラ・パワハラもISO14001に含めなくちゃならないでしょう。そういう拡大解釈を、断れるようにしておかないとね。
大谷さんが、著しい環境側面に上司の言葉使いまで含めろと言われたら断れないといけないよ。
規格で使われている定義されていない言葉は、普通の辞書に載っている意味で使われていることになっています。もちろん原文がですよ。
JIS規格を読んで意味が分からないとき、JIS訳の言葉を広辞苑で調べても意味はありません。英語原文の単語を英英辞典で調べないと意味が分かりません。よろしいですか?」
![]() 「英語で理解するものと納得するしかないのですか?」
「英語で理解するものと納得するしかないのですか?」

![]() 「そういう約束の上に成り立っていますから仕方ないです」
「そういう約束の上に成り立っていますから仕方ないです」
![]() 「分かりました」
「分かりました」
![]() 「佐川さん、興味深い話ですが、そういうことは監査に必要なことですか?」
「佐川さん、興味深い話ですが、そういうことは監査に必要なことですか?」
![]() 「必要だと思います。基本というよりレディネスというべきでしょうか?
「必要だと思います。基本というよりレディネスというべきでしょうか?
ISO規格は英語で読むとか文字解釈することを、習慣にしなければなりません」
・
・
・
・
![]() 「往々にして書いてないことを書いてあるように思いこむことがあります。
「往々にして書いてないことを書いてあるように思いこむことがあります。
『環境方針を全従業員に周知する仕組みを作れ』とありますね。
佐々木さんはどういう状況にすることだと思いますか?」
![]() 「『環境方針を全従業員に周知しろ』という文言はありません。『環境方針は、文書化され、実行され、維持され、かつ全従業員に周知される』です。昨日、佐川さんから言い回しが大事と注意されました(第120話)」
「『環境方針を全従業員に周知しろ』という文言はありません。『環境方針は、文書化され、実行され、維持され、かつ全従業員に周知される』です。昨日、佐川さんから言い回しが大事と注意されました(第120話)」
![]() 「佐々木さんは記憶力が良いですね。
「佐々木さんは記憶力が良いですね。
英文の主語は『Top management shall define〜』ですから、受け身の文ではありません。能動態です。ただ要件が多々あるのでいくつものフレーズを並べています。並べられた主語がないフレーズの訳が『(環境方針は)文書化され(中略)周知される』とあるだけで、経営者への命令は仕組みを作れです。『される』の主語はドキュメントですからね。まあどうでも良いです(ヤレヤレ)。
佐々木さんへ質問です。文書化され、実行され、維持され、周知されるとはどういうことですか?
いや、一人では大変だな。佐々木さんは『文書化する』を説明してください」
![]() 「そのままです。紙に書いて決裁を受けて正式な文書、つまり強制力があり皆が従う文書にすることです」
「そのままです。紙に書いて決裁を受けて正式な文書、つまり強制力があり皆が従う文書にすることです」
![]() 「結構です。
「結構です。
では山本さん、『実行する』とは何でしょうか?」
![]() 「昨日、佐川さんが英英辞典を引けとおっしゃたので、学生時代使った英英辞典を持ってきました。
「昨日、佐川さんが英英辞典を引けとおっしゃたので、学生時代使った英英辞典を持ってきました。
実行するだから英単語はexecuteと思ったらimplementedなんですね。
Implementedとは目標に向けて計画を立て予定表などに展開することで、executeはひたすら実行するということのようですね」
![]() 「良いことに気づきました。JIS訳の実行は、日本語の実行と違うのです。
「良いことに気づきました。JIS訳の実行は、日本語の実行と違うのです。
implementとは展開とも訳しますね。軍事では作戦命令を受けて、部隊の配置を決め、輸送し、作戦できるようにすること、まさに広げること、展開ですね。
 山口さん、維持するとは何ですか?」
山口さん、維持するとは何ですか?」
![]() 「一定の状況を保つことだと思います」
「一定の状況を保つことだと思います」
![]() 「大谷さん、周知とは何ですか」
「大谷さん、周知とは何ですか」
![]() 「英英辞典には『to express your thoughts and feelings clearly, so that other people understand them』とありました。『あなたの考えや思いを他の人々に伝え理解させること』とでも訳しましょうか」
「英英辞典には『to express your thoughts and feelings clearly, so that other people understand them』とありました。『あなたの考えや思いを他の人々に伝え理解させること』とでも訳しましょうか」
![]() 「すばらしい。『周知する』とは話して聞かせるだけじゃないのです。納得させ動かすことです。しかし言葉を覚えろというニュアンスはありません。
「すばらしい。『周知する』とは話して聞かせるだけじゃないのです。納得させ動かすことです。しかし言葉を覚えろというニュアンスはありません。
社長方針に『品質を上げよう』とあり、従業員が一生懸命不良対策をしていれば十二分の周知されていることになります。その従業員が社長方針を覚えていなくてもOKです」
![]() 「それっておかしいでしょう。たまたま偶然かもしれないでしょう」
「それっておかしいでしょう。たまたま偶然かもしれないでしょう」
![]() 「人が心の中で何を考えているかなど他人には分かりません。行動で表されたことがすべてです。
「人が心の中で何を考えているかなど他人には分かりません。行動で表されたことがすべてです。
マタイによる福音書 21章28-32節にある『二人の息子のたとえ』そのものです。
さて、日本語訳では『文書化され、実行され、維持され、周知される』となっていますが、実行と周知は逆じゃないかとか、方針を維持するとはわけ分からないと思います。
これを理解して質問してきた審査員に会ったことがありません。
文書化はまだ良いですが、多くの審査員は実行とか周知するの意味を理解してませんね。
佐々木さん、今4人が説明した意味で『方針を実行する』とはどういうことでしょうか?」
![]() 「山本君は、『目標に向けて計画を立て予定表などに展開する』と説明しました。まず方針の目標って何ですかね?
「山本君は、『目標に向けて計画を立て予定表などに展開する』と説明しました。まず方針の目標って何ですかね?
でもISO規格でそんな要求はなかったなあ〜」
![]() 「それは環境マネジメントプログラムを作れということではないのですか?」
「それは環境マネジメントプログラムを作れということではないのですか?」
![]() 「環境マネジメントプログラムを作るのは、環境目的・目標を実現するためです。環境方針の目標ではありません」
「環境マネジメントプログラムを作るのは、環境目的・目標を実現するためです。環境方針の目標ではありません」
![]() 「ISO規格に目的・目標は環境方針と整合させなければならないってあるじゃない」
「ISO規格に目的・目標は環境方針と整合させなければならないってあるじゃない」
![]() 「目的・目標は環境側面から選ぶものです」
「目的・目標は環境側面から選ぶものです」
![]() 「佐々木君は文字を読んでも、意味を読んでいないようだよ」
「佐々木君は文字を読んでも、意味を読んでいないようだよ」
![]() 「まあまあ、もう時間だからこの辺で終わりにしましょう。
「まあまあ、もう時間だからこの辺で終わりにしましょう。
山本さんが言ったように英英辞典を手元に置いて読むと良いですね。日本語の訳は、難しい言葉ばかり使って、こなれていないのですよ。
易しい大和言葉に訳してくれたら良かったのですが、ともかく英英辞典を引いて漢語を使わない文章に訳してみましょう。きっとためになります」
*
*
*
坂口が監査部に戻ると、北川が手招きする。
坂口が北川の席に行こうとすると手のひらで坂口を止め、打ち合わせ場に引っ張っていく。
途中、給茶機でコーヒーを注ぐ。
これでコーヒーは今日何杯目だろうか。まだ5杯なら大丈夫だろう。
![]() 「何か進展がありましたか?」
「何か進展がありましたか?」
![]() 「あったとも、ワシが未来プロジェクトの佐山リーダーに会いに行ったら、奴は異動というか出向になったそうだ。
「あったとも、ワシが未来プロジェクトの佐山リーダーに会いに行ったら、奴は異動というか出向になったそうだ。
ということで後任の伊達と話してきた。奴が言うには未来プロジェクトは、調査、対策立案、提言だけで、提言を採用するか否か、そして実行を指示するのは取締役会だという。

そして2000年代初頭の不祥事報道対策については、各取締役がそれぞれ自分の担当部署に一斉点検を指示することを申し合わせているという。
監査部所管の取締役は、財務部と経理部も担当している。それで顔見知りの財務部の野村課長と大木経理課長に聞いてみたよ」
![]() 「で、どうでした?」
「で、どうでした?」
![]() 「いずれの部も先月指示があり、現在はしっかり点検中だってさ」
「いずれの部も先月指示があり、現在はしっかり点検中だってさ」
![]() 「では監査部長が忘れていたということですか?」
「では監査部長が忘れていたということですか?」
![]() 「だけど昨日、吉井部長が来たときの打ち合わせに監査部長もいたわけで、そうとも思えない。
「だけど昨日、吉井部長が来たときの打ち合わせに監査部長もいたわけで、そうとも思えない。
監査部は不祥事となるような仕事をしていないと考えているのだろうか?」
![]() 「そういう可能性もありますね。でも環境部は工場の監査をしようと考え、それは監査部も巻き込まないと不味いとこちらに話を持ってきた。
「そういう可能性もありますね。でも環境部は工場の監査をしようと考え、それは監査部も巻き込まないと不味いとこちらに話を持ってきた。
それと比較すると、ウチの部長は危機感がないというか真剣さがないようですね」
![]() 「面倒くさいと思ったのかもしれんな。
「面倒くさいと思ったのかもしれんな。
ちょっと部長に話してみるわ」
北川はヨイショと立ち上がり、部長室に入っていく。
監査部に異動してまだ半年も経っていない坂口は、気安く部長室に入っていく北川を度胸があると感心した。
![]() 本日の思い出
本日の思い出
1999〜2003年頃に業種・会社を問わず、多種多様な不祥事が多発した。原因としては社会構造の転換期にあったという説がある。
- バブル崩壊後、企業経営が厳しくなり、コスト削減・納期優先・数字重視が厳しく問われ、現場の安全・品質・倫理が後回しになった。
- 終身雇用の崩壊から愛社心が薄れ、不平不満から内部告発が増加した。
- コンプライアンスが厳しく言われる時代になり、反社会勢力との付き合い、会社の金を個人的に使う経営者が許されなくなった。
- 不祥事は世間に受け視聴率を取れるようになった。
私は正直言って、不祥事が増えたのか、実際は増えておらず、今までしていたことが表に出たのかは分からない。
「人間だもの間違いはある」と相田みつをのようなことは言わない。
悪いことは悪い、ダメなものはダメだ。
だが、そういう問題を起こした会社は、ほとんどがISO認証停止とかになった。
賞味期限を改ざんして品質保証ができてないから認証取り消しだというなら、品質保証の意味とかISOのルールは置いといても、なるほどという気はする。
だけど品質のISO9001だけでなくISO14001認証も認証停止とか取消となると、もうなんでもありの弱い者いじめ、認証機関は独裁者じゃないかと思うのである。
私は認証機関の仁義なき、そしてルールもない、感情任せに見える認証停止や取り消しを許さない。
ISO認証がそんなものなら、審査などせず審査登録料金を払った会社には審査登録証(認証証)をジャンジャン発行し、不祥事がでたら即座に取り消しをしたら手間もかからずお金になって良いではないか。
認証とはそういうものではないだろう。
ISO17021には
| |
ましてISO認証はプライズではないし、ISO9001は製品やサービスの品質保証であり、社内の業務の品位を保証するものではない。
ならばセクハラがあろうと、談合があろうと、贈賄事件があろうと、ISO認証とは無縁ではないか。
かって審査員がお土産をねだり、宴席を要求し、企業の内部資料の提供を必須とした時代があった。そういう脛の傷は忘れたのか?
認証は感情と勢いで決まるのか?
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
参考資料「ニュースステーション問題」 | |
| 注2 |
ダイオキシン特措法(ダイオキシン類対策特別措置法)が成立したのは、1999年2月にテレビ朝日のニュースステーションが報道してから、大騒ぎになり7月に成立した。その間たったの5カ月、何かの出来事から作られた法律としてはものすごい短期間だ。 法制定までの最短記録かと思ったら、出来事があってからもっと早く成立した法律もある。 短期間で作られた法律には ・復興庁設置法 20日後 東日本大震災発生後 ・新型インフルエンザ特措法改正 38日後 新型コロナで死者発生(20/5/9)して ・阪神淡路大震災復興特別措置法 40日後 地震発生後 ・国民生活安定緊急措置法 77日後 起点が不明 ・ダイオキシン特措法 5か月後 ニュースステーション放送後 ・国旗国歌法 6か月 国旗国歌問題で校長が自殺後 短期間で制定改正されたものは、特別措置法、緊急措置法がほとんど。これらは特殊な状況対応とか緊急に制定が必要なもの、そして時限立法(廃止されずに残っているものあり)ですから、何事かあって短期間に制定された法律であることは納得です。 国旗国歌法も緊急ではあったでしょうけど、普通の法律としては最短記録と思います。 | |
| 注3 |
あの数年間の不祥事の騒ぎは今も忘れない。そういうことに関わる仕事をしていたせいだろう。 思いつくままに挙げると、M自動車のリコール隠し、Y乳業の食中毒・賞味期限改ざん、食中毒発生を隠した、T電力の原発トラブル記録の改ざん・隠ぺい事件、リサイクルを宣伝していた家電品のプラスチックがバージンだった、製紙会社で再生紙使用を謳っていたものがバージンパルプだったなどなど、 環境に限っても大手化学工業・鉄鋼会社・製紙会社が、ばい煙の測定値書き換え、基準を超える工場排水放出、有名企業が不法投棄していたなど多様だった。 笑ってしまうのはISO14001活動で、紙節約のために裏紙を使ったら情報漏洩したというのもあった。 | |
| 注4 |
ISO規格の顧客の定義は何度も変わった。 ・ISO9004:1987定義3.4によると 「最終段階の消費者、使用者、得意先、受益者、すなわち第二者」であった。 ・この物語の1999年では ISO8402:1994定義1.9 「供給者が提供する製品の受け取り手」 ここで製品の定義は「活動又はプロセスの結果」で「製品にはサービス、ハードウェア、プロセス製品、ソフトウェア、又はこれらの組み合わせがある」とされている。 ・ISO9000:2005定義3.3.5 「製品を受け取る組織または人」 ・ISO9000:2015定義3.2.4 「個人若しくは組織向け又は個人若しくは組織から要求される製品・サービスを受け取る又はその可能性のある個人又は組織」 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |