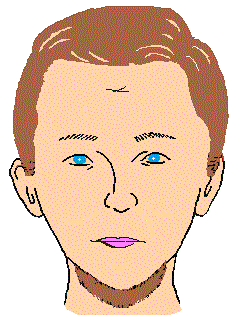注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
業界の環境ISO研究会が始まった。だがメンバーは、それがどんなものかを把握していない。まあ佐川のように、未来から戻ってきたわけではないから当たり前なのだ。
 |
|
| どうしたものか? |
何を知らないかと言えば、環境ISO規格で求めているのは何か? 審査がどういうものか想像もつかない状況だ。そういうことは規格案を読んでも分からない。
ISO9001でも、実際に審査を受けてみて、細かいことに拘るのかとか、実行とは徹底することだとか理解したはずだ。
佐川は、まずそれについての情報を提供しなければ、何もできないと考えた。
上長である吉井部長に相談すると、佐川が面識ある認証機関のゼネラルマネージャーのデイブに、講演を頼んだらどうかと言われた。
佐川がデイブに、規格解説の講師を頼めるかとメールを送ったら、翌日に返事が来た。
|
佐川さんはお元気ですか? お問い合わせのメール、ありがとう 私は日本語を話すことも書くこともできるけど、日本的な文章は書けません。見よう見まねで日本的メールを書いてみます。 日本では冒頭に、時候の挨拶とか近況報告をするのですね。 大地震で私の住む芦屋市でも多くの人が亡くなりました。市内の建物も半分は壊れたと思います。恐ろしいことです
しかしたくさんの家やお店が壊れて、また道路も直っていないので、暮らしは普通まで戻っていません。 地震後、まず私は社員の状況確認をしました。社員は幸い皆無事でした。しかしご家族、ご親族には何人もの死傷者が出ています。 事務所に借りていたビルは倒れはしませんでしたが、火事になってすべて燃えてしまいました。 そうそう、横浜事務所から聞きましたが、御社の三重工場の審査登録証はイギリス本社が発行してくれたそうですね 神戸でも地震被害のひどい地域は限定されていて、あまり被害のなかったところを借りて仮事務所を置いて仕事を始めています。 事務所を大阪に移すとか横浜に集約する案もありましたが、復興を信じてここで営業を再開しました。 さて、お問い合わせの件ですが、 日本では審査員がコンサルした会社を審査していますが、イギリスでは審査員がコンサルした会社を審査するのは堅く禁じられています 日本のルールがどうかはともかく、私の信条として審査する会社およびその従業員へのコンサルはできません。 但し規格解説だけならコンサルにならないので、講習しても問題ありません。規格要求を実現する方法を教えると、コンサルになります。 その意味で、あなたの業界団体が作った認証機関に依頼するなら、当社がコンサルするのは問題ない。もっとも前に言ったように、日本では認証機関のコンサルを規制していないようだから、審査する認証機関がコンサルもしてくれるかもしれない。私はそれをあるべき行為でないと思う。 FDIS(最終案)は来年5月に出るそうです まだ1年も先です。皆さんが検討するには、その正式な和訳が出てからで間に合うと思います。 FDISから正式に発行するまで半年はかかります。ですから私は今から急いで規格の勉強をすることはないと思います。規格が正式に発行されたら、すぐに審査を受けるとしても、半年も準備すれば十分でしょう。 さて、佐川さんの希望する講習が、DISの解説であるなら実行は可能です。 ただDISの解説ですとただ話すだけになりますから、既に審査を行っているBS7750も踏まえた話をしたほうが良いでしょう。そうなると最低8時間は必要です。 講師料ですが、通常同等の講習会を行えば、場所代込みで20人として一人3万は頂きます。場所の提供を頂いても賃料は2・3万ですから大して変わりません。 しかし何度も言いますが、今から焦ることはありません。来年の初夏にFDISの和訳が出てからの方がよろしいでしょう。 お問い合わせに以上の通り回答します。ご検討ください。 |
佐川はデイブからのメールを見て、ギョッとした。想定をはるかに超える価格だ。それと彼は急ぐことはないと力説している。確かにFDISが来年の5月なら1年先だ。さて、どうしたものか?
とりあえずできることとして、立ち上がってファイル棚から認証機関や審査員研修機関からの講習会の案内を眺める。昨今はISO9001の研修会とか、内部監査員講習とかの宣伝が数多く来る。捨てないで取っておいたのが役立つ。眺めると
| ・半日コース | 11,000〜20,000 | ||
| ・1日コース | 26,000〜32,000 | ||
| ・2日コース | 55,000〜62,000 | ||
個人的でなく、認証機関が受注したと考えればおかしくはない。
それに佐川がイメージしたのは、規格の説明と質疑応答なのだが。しっかりした講演をするとそれくらいにつくのかどうか?
デイブはテキストを配って行うとか、アクティブなロールプレイとかを考えたのかもしれない。BS7750の対訳本を配るとすると本代も高い
自分で考えても分からなければ、アドバイスしてくれる人に相談するのが吉。
佐川は首を伸ばして部長席を見る。吉井部長は在籍している。あの様子なら忙しくはないようだ。いつも部長が暇なときは佐川が呼ばれて話し相手をしているのだから、たまにはこちらから声をかけても良いだろう。
佐川は立ち上がって部長席に行く。
![]() 「なんだ、何か用か?」
「なんだ、何か用か?」
![]() 「先日お話したイギリス人に講演を頼む件ですが、とんでもない値段が提示されまして。メールはこれです」
「先日お話したイギリス人に講演を頼む件ですが、とんでもない値段が提示されまして。メールはこれです」
吉井部長はメールのプリントアウトを受け取って、見ながら言う。
![]() 「値引き交渉か? 俺は苦手だな」
「値引き交渉か? 俺は苦手だな」
![]() 「そうではなくて、私はメールで規格解説を頼んだのですが、向うは解説つまりlectureではなく、研修trainingと受け取ったのかなと思いまして。
「そうではなくて、私はメールで規格解説を頼んだのですが、向うは解説つまりlectureではなく、研修trainingと受け取ったのかなと思いまして。
メールは日本語で……彼は日本語が流暢ですから……『半日ほど規格解説を頼めないか』と書いたのですが、ニュアンス的にどう受け取ったのか?」
![]() 「先方の提示した金額は……受講者を20名として、ひとり3万か。
「先方の提示した金額は……受講者を20名として、ひとり3万か。
日本でISO関係の研修会の相場はどんなものかな?」
![]() 「半日で1万から2万、1日で3万前後、2日で5〜6万というところです」
「半日で1万から2万、1日で3万前後、2日で5〜6万というところです」
![]() 「相場としてはおかしくないか。拠点が東京になければ場所代もかかると。
「相場としてはおかしくないか。拠点が東京になければ場所代もかかると。
規格解説を半日と言っても、準備というか事前勉強もあるし資料作りもある。審査料金が一日15万くらいというから数日かけるならおかしくないか」
![]() 「でも審査料金は、個人の手間賃だけでなく、会社のオーバーヘッドが載ってますよ」
「でも審査料金は、個人の手間賃だけでなく、会社のオーバーヘッドが載ってますよ」
![]() 「だが、このメールでは講演を、個人でなく会社で受けるように書いてある。なら同じことだ。ゼネラルマネージャーが内職はできないのだろう」
「だが、このメールでは講演を、個人でなく会社で受けるように書いてある。なら同じことだ。ゼネラルマネージャーが内職はできないのだろう」
![]() 「確かに。ということは、元々の講演料見積もりが甘かったということですか?」
「確かに。ということは、元々の講演料見積もりが甘かったということですか?」
![]() 「言い方変えればちゃんと金を払って、しっかりした講演を頼むのもありかな。
「言い方変えればちゃんと金を払って、しっかりした講演を頼むのもありかな。
工場や関連会社にも参加料を取って参加を募ると
しかしだ、その前に、このメールではFIDSが出るのは今から1年後だから焦るなと書いてある。なら今から騒ぐこともなさそうだ」

![]() 「部長、うーん、いろいろ考えることがあるのですが」
「部長、うーん、いろいろ考えることがあるのですが」
![]() 「なんだ?」
「なんだ?」
![]() 「未来の知識を紐解けば、そのB○○社の規格解釈はまっとうです。もしそこに当社の環境ISOの審査を依頼するなら、わざわざ講習を受けることがありません」
「未来の知識を紐解けば、そのB○○社の規格解釈はまっとうです。もしそこに当社の環境ISOの審査を依頼するなら、わざわざ講習を受けることがありません」
![]() 「講習を受けるのは当社のためだけでなく、仲間を増やすためじゃなかったのか。この前は味方が多いほうが良いと言ってたじゃないか?」
「講習を受けるのは当社のためだけでなく、仲間を増やすためじゃなかったのか。この前は味方が多いほうが良いと言ってたじゃないか?」
![]() 「当社が業界の認証機関に頼むなら、見解でもめるでしょうから味方が多いほうが良いです。しかし当社がB○○社に頼むなら産業環境認証機関とは無縁です。それなら、そこがどんな審査をしようが、当社に関係ありません。
「当社が業界の認証機関に頼むなら、見解でもめるでしょうから味方が多いほうが良いです。しかし当社がB○○社に頼むなら産業環境認証機関とは無縁です。それなら、そこがどんな審査をしようが、当社に関係ありません。
他の会社が苦労するでしょうけど、それは我々に関係ないです」
![]() 「なるほど、だが、当社がB○○社に頼むと決まったわけではない。それに関連会社は親会社であるウチの意向に拘わらず、取引先との関係とかで業界の認証機関に流れる可能性は大きい。
「なるほど、だが、当社がB○○社に頼むと決まったわけではない。それに関連会社は親会社であるウチの意向に拘わらず、取引先との関係とかで業界の認証機関に流れる可能性は大きい。
そのときトラブルが起きれば、お前のところにヘルプがくるぞ」
![]() 「分かりました。いずれにしてもまっとうな規格解釈を、広めておかねばならないということですね」
「分かりました。いずれにしてもまっとうな規格解釈を、広めておかねばならないということですね」
![]() 「そういうことだ。
「そういうことだ。
一度、イギリスでBS7750を審査していた人の話を、聞いたほうが良いのではないか。ちょっと値段が値段だが。話の持って行き方をもう少し考えてみてくれ。
ただ今日・明日に、対応しなければならないこともない」
![]() 「承知しました」
「承知しました」
佐川は考える。ISO14001のFDISが出るのを待つか、DISを眺める価値があるか、それとは別にBS7750の審査経験者の話を聞くことが役に立つのか?
そんなことを考えこんでいて、ふと、デイブと話すことが第一だと気づいた。
現在の状況、これから起こるであろう問題の数々、企業にとって従業員にとって、認証機関にも悪くない妥協点があるのか聞いてみたいと思う。
・
・
・
佐川はデイブにメールを打つ。講習会は当分お預けとして、自分たちの検討会の進め方についてちょっと話をしたい。福島工場の審査の後でも良いし、ひと月に数回は東京に来るだろう。貴方の都合の良いときにお会いして1〜2時間話ができないかと、
今回は彼も出張だったのか、二日後にメールが来た。
デイブは、東京近辺の審査に6月末に数日滞在する。某日午後半日空くから、その時打ち合わせようという返事が来た。
佐川はではそのとき弊社を訪ねてきてほしい。夜は一席設けるから付き合って欲しいと返事を出した。
もちろん、BCCを吉井部長と山口に送る。
6月になっても、業界団体の会合は予定通り、2週間に一辺集まって話し合いをしているが、情報がDISとISO14001の基になったと言われるBS7750しかなく、規格解釈や運用についての疑問は積み重なる一方で、検討するにも新しい情報はなく足踏み状態は変わらない。
デイブとの打ち合わせの10日ほど前、佐川は吉井部長と山口を集めて話し合いをする。
![]() 「先日、皆さんにメールを送っておりましたが、来週の水曜日の午後2時に、B○○社のゼネラルマネージャーのハワード氏が当社に見えます。
「先日、皆さんにメールを送っておりましたが、来週の水曜日の午後2時に、B○○社のゼネラルマネージャーのハワード氏が当社に見えます。
場所はロビー階の小会議室を取っております。
午後一杯、私どもの現状の説明、それからISO14001審査が始まってから想定されるトラブル、規格解釈とかどこまですれば規格を満たすのかといったことですね、そういうことについてお聞きしたいと思います」
![]() 「彼はBS7750の審査はしても、ISO14001はこれからだから、そういうことを聞いても応えられるのか?」
「彼はBS7750の審査はしても、ISO14001はこれからだから、そういうことを聞いても応えられるのか?」
![]() 「確かにBS7750とDISは大きく異なりますね。特に環境側面(environmental aspect)という概念がありません」
「確かにBS7750とDISは大きく異なりますね。特に環境側面(environmental aspect)という概念がありません」
![]() 「まあ確かに……イギリス人としてDISを読んで、どういうものを想定されるかということならお聞きできるかと思いますが」
「まあ確かに……イギリス人としてDISを読んで、どういうものを想定されるかということならお聞きできるかと思いますが」
![]() 「あまり曖昧な質問では、相手も困るだろうし生産性も悪い。
「あまり曖昧な質問では、相手も困るだろうし生産性も悪い。
ふたつに限定しろ。
ひとつはBS7750について疑問点をまとめて教えてもらう。
BS7750での審査の問題などを聞く

|
もうひとつは、DISの中でBS7750と異なること、環境側面とか計画、管理、訓練などについて彼がどう考えているか、
そこに限定して聞くだけでも情報は得られるだろうし、彼もそれ以上の情報はないのではないかな?」
注:environmental aspect(ISO14001では「環境側面」訳された)という熟語は、BS7750では4.4.3で1回のみ使われており、対訳本では「環境面」と訳されている。
なお、BS7750では「environmental aspect」は定義されていない。
これからBS7750では「environmental aspect」は特段意味のある熟語ではなかったと思われる。
![]() 「分かりました。研究会のメンバーにも声をかけて質問をまとめておきます。
「分かりました。研究会のメンバーにも声をかけて質問をまとめておきます。
ええと、5時で終えて、それから……彼は東京泊とのことですので、軽く健保会館で飲もうかと思っているのですが」
![]() 「イギリス人というけど、そのへんの感覚は日本人と同じか?」
「イギリス人というけど、そのへんの感覚は日本人と同じか?」
![]() 「日本に住んでもう3年ですし、その前にもたびたび日本に仕事(審査)で来ていると聞いています」
「日本に住んでもう3年ですし、その前にもたびたび日本に仕事(審査)で来ていると聞いています」
![]() 「じゃあ、夜の部は俺も参加する。金は会議費で間に合わせろよ。
「じゃあ、夜の部は俺も参加する。金は会議費で間に合わせろよ。
昼の部は佐川と山口だけか?」
![]() 「その予定ですが、研究会で話して参加したいという人が出れば、少人数なら良いかと思います」
「その予定ですが、研究会で話して参加したいという人が出れば、少人数なら良いかと思います」
6月下旬、業界団体の定例の環境ISO研究会である。
![]() 「このところ新しい情報がなく、足踏み状態が続いています。皆さんの方から何か新しい情報がありますか?」
「このところ新しい情報がなく、足踏み状態が続いています。皆さんの方から何か新しい情報がありますか?」
![]() 「では私から、弊社でも伝手を頼ってBS7750のことについて調べておりました。
「では私から、弊社でも伝手を頼ってBS7750のことについて調べておりました。
その結果、今月末に認証機関B○○社に弊社に来てもらい、BS7750の状況をお聞きすることになりました。その際、DISについてもお聞きしたいと思います」
![]() 「佐川さんとしてはどんな質問を考えているのでしょうか?」
「佐川さんとしてはどんな質問を考えているのでしょうか?」
![]() 「実は私は知らなかったのですが、審査員は自分が審査する企業にコンサルをしてはいけないというルールがあるそうです。それで先方から規格の解説はできるが、どのようにすれば規格を満たすかはコンサルになるので語ることはできないとのことです。
「実は私は知らなかったのですが、審査員は自分が審査する企業にコンサルをしてはいけないというルールがあるそうです。それで先方から規格の解説はできるが、どのようにすれば規格を満たすかはコンサルになるので語ることはできないとのことです。
弊社ではまだ依頼する認証機関は決まっていませんが、すべてを産業環境認証機関に依頼することもないと思いますので、対応する手順は教えてもらえないとのことです。
ただ規格の解説だけでなく、こちらから事例をあげての合否判定をお聞きするのは良いらしいです」
![]() 「産業環境認証機関なんて審査する審査員が、事前に来て状況を見てくれるよ、もちろん1日10数万取るけどね」
「産業環境認証機関なんて審査する審査員が、事前に来て状況を見てくれるよ、もちろん1日10数万取るけどね」
注:当時は認証機関が審査契約するときに、予備審査をしませんかと声をかけてきた。予備審査とは、事前に模試をおこなうようなもので、点検するだけでなくこうしたら良いとかアドバイス(コンサル)をするものだった。
不適合が出ると、予備審査をしなかったからだと責められた(笑)
それって、マッチポンプとは違うのか?
![]() 「外国では審査をする予定の審査員が、事前に見てやることは完全にNGらしいね。日本は甘いからOKのようだ」
「外国では審査をする予定の審査員が、事前に見てやることは完全にNGらしいね。日本は甘いからOKのようだ」
![]() 「佐川さんが発言したのは、ここで我々の疑問をまとめれば、その場で質問してくれるということだね?」
「佐川さんが発言したのは、ここで我々の疑問をまとめれば、その場で質問してくれるということだね?」
![]() 「そのつもりです」
「そのつもりです」
![]() 「それじゃ皆聞きたいこと、確認してもらいたいこと、どんどん挙げて佐川さんに頼もうぜ」
「それじゃ皆聞きたいこと、確認してもらいたいこと、どんどん挙げて佐川さんに頼もうぜ」
・
・
・
30分くらい多数の提案があり、それをまとめた。
メンバーは今日来た甲斐があったという顔をしている。
![]() 「佐川さん、話し合いというかその席に参加しても良いかな?」
「佐川さん、話し合いというかその席に参加しても良いかな?」
![]() 「そのつもりでおりました。
「そのつもりでおりました。
この全員となると対応もできませんから、この中で2・3名に限定して出席を募ろうと思っていました」
![]() 「それならぜひとお願いしたいですね」
「それならぜひとお願いしたいですね」
![]()
 |  |
業界団体としては業界各社が出資して作った産業環境認証機関を使って欲しいという考えです。他の認証機関を使うなとは言いませんが、それ以外の認証機関に講習会とかを依頼するのは芳しくないのですよ」
![]() 「おっしゃることは良く分かっております。ただ業界が認証機関を立ち上げる前にISO9001を認証している工場も多く、そういったところはすぐに鞍替えすることも不適切です。特に原発に関する工場を審査できるのは日系の認証機関にありませんし
「おっしゃることは良く分かっております。ただ業界が認証機関を立ち上げる前にISO9001を認証している工場も多く、そういったところはすぐに鞍替えすることも不適切です。特に原発に関する工場を審査できるのは日系の認証機関にありませんし
また弊社では競争原理もありますから、ひとつの認証機関に集約する予定はありません」
![]() 「まあそうですねえ〜」
「まあそうですねえ〜」
![]() 「ここだけの話ですが〜、出向者とトレードで依頼するってフェアじゃないわね」
「ここだけの話ですが〜、出向者とトレードで依頼するってフェアじゃないわね」
![]() 「オイオイ、お嬢さん、それは言わない約束だぞ」
「オイオイ、お嬢さん、それは言わない約束だぞ」
吉本は苦虫をかみ潰したような顔をしている。
彼女は認証機関と何かつながりがあるのか、それとも業界系の認証機関を利用しないことが問題なのか?
![]() 本日の疑問
本日の疑問
ISO9001でもISO14001でも、認証が始まった頃は、審査の前に予備審査とか事前審査とかいって、審査員が会社に来ていろいろとアドバイスをしてくれた。
あれはISO17021に決めてある、要求事項が明確に規定され文書化されていることを確認しなければ審査してはならない
Guide62にもそんな事前審査は決まっていなかったと思う(皮肉だ)。)
1993年頃は、こちらは何も知らず指導してくれてありがとうと思っていた。
それを頼まずに本チャンの審査で問題があると「だからお金を出して予備審査を受ければ良かったのに」と審査員から笑われた。あれは正しいことだったのか?
コンサルした人が審査するというのは、その後もなくならなかった。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
・芦屋市 阪神淡路大震災の記録 | |
| 注2 |
日本で「審査員は自分がコンサルをした会社を審査してはいけない」という通知が出たのは20世紀末だったと思う。 Guide66が発行されたのは1999年7月で、そこでは明確にコンサルした企業を審査してはダメと会ったと記憶している。 残念ながらGuide66の1999年版はネットで見つからなかった。2006年版は下記にあるが、その中で審査員がコンサルした組織の審査禁止と認証機関についてもいろいろ規制がある。 ・IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 66 | |
| 注3 |
FDISが公開されたのは1996年の4月か5月だったと思う。忘れた。 | |
| 注4 |
BS7750の対訳本が1994年に出ている。 「環境管理・監査システム」日本規格協会編、発行 日本規格協会、1993、 100ページそこそこだが価格は8,000円した。 1987年版のISO9001の対訳本も13,000円もした。日本規格協会の本は、今も昔もとんでもなく高い。困ったもんだ。 だが、ISO9001:2015は5,500円、ISO14001:2015は4,100円、ページ数から考えるとべらぼう高いけど、過去に比べれば安くなったものだ。 | |
| 注5 |
認証機関は審査する企業の業種の認定を受けていなければならない。(農業・林業・漁業・食料品・木材など) 日本でISO審査が始まった当初は、LRQAと他1社しか核燃料の分類で認定を受けていなかった。 | |
| 注6 |
Guide66の時代からISO17021になっても、申請のレビューの項目で「要求事項が明確に規定され文書化されている」ことを確認しないと審査に進んではならないと記されている。 |
外資社員様からお便りを頂きました(25.02.17)
おばQさま >「だからお金を出して予備審査を受ければ良かったのに」と審査員から笑われた ピンポイントの反応で済みません。 あの時代って、こういうのが多かったですね。 ISOではありませんが、東京都の先端技術の補助金申請。 先端技術で内容には自信があったので、自分で資料をまとめて申請したが落とされました。 その時に「こんなに大変なことしないでも行政書士に頼めばよかったのに」 そういえば、申請書を請求した時点で、付き合いのない行政書士事務所から、いくつかメールや郵便が来ていました。 他の会社の人に聞くと、みんな東京都の元職員なんですって。 あの頃って、こういう退職後 サポートシステムが出来ていたんですね。 補助金も、内容よりも、期待しているステークホルダーが絡んでいるかが大事だったんだろうなぁ あの頃 私も若かったw |
外資社員様、毎度、お便り、ありがとうございます。 行政書士というのはれきとした国家資格でありますが、国家資格とは公務員が必要なものであるわけです。 それで国家試験を受けなくても公務員は合格するようになっている……あっ、内緒です 司法書士は裁判所とか検察の事務官を10年していると大臣の認定でなれます。 環境計量士というとけっこう難しい試験ですが、自治体の環境部門で働いていると講習を受けると合格します。 計量士というのはお店の秤とか物差しを検査して丸い市町村の名前を書いたラベルを貼るお仕事ですが、これも行政で秤の校正をしていると合格です。 税理士は税務署勤務、行政書士は市役所で(以下略) もう40年も前ですが、小学校同級だった人から声をかけられました。偶然、同じ県営住宅に住んでいたのです。小学4年までしか一緒のクラスでなかったのに20年も経ってよく私が分かったものと驚きました。 ⇒20年後 ともかく彼は県の環境課で働いているということと、環境計量士だと聞いて驚きました。 私が必死に勉強して〇回目のチャレンジで合格したのに…… 後で調べたら……ということで、ああ、そうかとため息をつきました。 まあ税理士とかに比べたら、お金になるかという意味では環境計量士なんてたいしたものではありません。 私が子供の頃、市役所を定年退職した人が「行政書士」の看板をあげていました。道路沿いでなく普通の民家で宣伝もしなかったようで、商売になるのかどうか近所の人が心配していました。 もう何十年か前にお亡くなりになりましたが、どうだったのでしょう。 そんなこと考えると資格商売は資格を取るよりも、その後の繁盛次第と思います。いやそう思わないと(以下略) |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |