注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1995年、梅雨が明け夏になった。
佐川と山口は、業界主催の環境ISO研究会に参加しているだけではない。
 環境部ができたことから生産技術部は、公害防止とか廃棄物については環境部に移管する考えである。とはいえ人は出したくないから、異動する予定の佐川と山口に現在担当している人から知識やノウハウを聞いて仕事を持って行けという。ということで二人は勉強集というか、工場や関連会社の対応はもう移管されているのだ。
環境部ができたことから生産技術部は、公害防止とか廃棄物については環境部に移管する考えである。とはいえ人は出したくないから、異動する予定の佐川と山口に現在担当している人から知識やノウハウを聞いて仕事を持って行けという。ということで二人は勉強集というか、工場や関連会社の対応はもう移管されているのだ。
その他に、ISO9001認証は形としては手離れしているが、ISOコンサルをしている関連会社の柳田企画の佐々木、片岡からたびたび問い合わせや相談がある。それも電話とかメールだけでは用が済まず、2週間に一度くらい会って打ち合わせをしているのが実態だ。
今日も午後一杯打ち合わせである。
時間通り佐々木と片岡がやって来た。
![]() 「お二人がコンサルを始めて4か月くらいになりますか。もうコンサルをしていて、分からないことなどないでしょう」
「お二人がコンサルを始めて4か月くらいになりますか。もうコンサルをしていて、分からないことなどないでしょう」
![]() 「そうつれないことを言わないでよ。まだひよっこだよ」
「そうつれないことを言わないでよ。まだひよっこだよ」
![]() 「客先はすべてがユニークですから、常に初めての経験になり、新しい問題、疑問が絶えることはありません」
「客先はすべてがユニークですから、常に初めての経験になり、新しい問題、疑問が絶えることはありません」
![]() 「大先輩たちにそう言われると、裏があるのではと心配です」
「大先輩たちにそう言われると、裏があるのではと心配です」
![]() 「まあ、外交辞令はともかく、いろいろと悩みがあるので相談に乗ってほしい。
「まあ、外交辞令はともかく、いろいろと悩みがあるので相談に乗ってほしい。
まずはつまらないと言っちゃつまらないことだが、ISO認証の効果を問われて困っている。どう説明したらよいものか?」
 |  | |||||
| 山口 |  |  | 片岡 |
![]() 「それはつまらないことではありません。ISO認証の本質ですね。
「それはつまらないことではありません。ISO認証の本質ですね。
会社が良くなるとか儲かるとか語る人も多いですが、それは間違いです。
ISO9001認証の効果というか意味は、その工場なり会社が規格を満たす品質保証の仕組みを持っていることを確認したことです」
![]() 「品質保証の仕組みがあることを確認したと言われても、それが価値あるものとも思えないが……」
「品質保証の仕組みがあることを確認したと言われても、それが価値あるものとも思えないが……」
![]() 「片岡さんは BtoC のビジネスでしたね。それなら品質保証と無縁だったかもしれませんね。
「片岡さんは BtoC のビジネスでしたね。それなら品質保証と無縁だったかもしれませんね。
とはいえアメリカの工場にいたとおっしゃいましたから、ULのことはご存じでしょう?
![]() 「ULは国内の工場にいたときにも受審していたな。私は特段、関りはなかったが」
「ULは国内の工場にいたときにも受審していたな。私は特段、関りはなかったが」
![]() 「UL審査は何のためにするのでしょう?」
「UL審査は何のためにするのでしょう?」
![]()
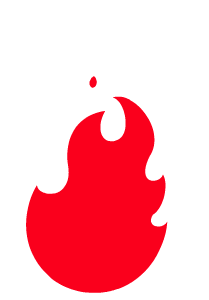 | |
 |
だからunder writers laboratoryって言うと聞いた。
その後、対象製品が広まっていったそうだ。
その結果、今はULの認定を受けないと実質的に販売できない
注:「under write(underwriter)」とは何かの下や末尾に書き込む意味であるが、そこから契約書や証書にサインすることになり、保険を引き受ける人(保険会社)の意味になった。
ULつまり「underwriters laboratory」とは保険引受人(保険会社)が、作ったから保険会社の検査機関という意味。
![]() 「片岡さんは物知りだねえ〜。私もULの検査など毎年受けていたけど、そういう経緯があったとは知らなかった」
「片岡さんは物知りだねえ〜。私もULの検査など毎年受けていたけど、そういう経緯があったとは知らなかった」
![]() 「ULは出来上がったものを検査するだけでなく、製造する工場の検査とか使われている部品がULに適合しているかを確認します。品質を確認するにはそういう仕組みが必要だということです」
「ULは出来上がったものを検査するだけでなく、製造する工場の検査とか使われている部品がULに適合しているかを確認します。品質を確認するにはそういう仕組みが必要だということです」
![]() 「そういえば日本でも電気製品は電取法の規制を受けるね。製品の検査だけでなく工場も検査される
「そういえば日本でも電気製品は電取法の規制を受けるね。製品の検査だけでなく工場も検査される
![]() 「品物が複雑になり、見ただけでは良否が分からなくなり、更には検査をしても良否が分からなくなってきた。そうなると買い手は、使われている部品の良否や製造過程を検査しなければ安心できなくなった。
「品物が複雑になり、見ただけでは良否が分からなくなり、更には検査をしても良否が分からなくなってきた。そうなると買い手は、使われている部品の良否や製造過程を検査しなければ安心できなくなった。
それで最初は軍用品、だんだんと航空とか鉄道そしてインフラ関係など信頼性が要求されるもの、主に BtoB において品質保証という発想が広まった。
BtoC の場合は、買い手の力が弱く情報がないために、品質保証の考えが広まらなかった。
ULは最終消費者でなく保険会社が始めましたからね」
![]() 「スマン、品質保証とISOはどう結びつくのか?」
「スマン、品質保証とISOはどう結びつくのか?」
![]() 「『ご冗談でしょうファインマンさん』は本のタイトル、ご冗談でしょう片岡さん、品質保証はISO9001のタイトルですよ」
「『ご冗談でしょうファインマンさん』は本のタイトル、ご冗談でしょう片岡さん、品質保証はISO9001のタイトルですよ」
![]() 「えっ、えっ」
「えっ、えっ」
![]() 「片岡さん、ISO9001のタイトルは『品質システム-設計・開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル』ですよ。設計なんちゃらとあるのは、ISO9002とかISO9003もあるから区別するためで、ISO9001のタイトルは『品質保証の規格』なのです」
「片岡さん、ISO9001のタイトルは『品質システム-設計・開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル』ですよ。設計なんちゃらとあるのは、ISO9002とかISO9003もあるから区別するためで、ISO9001のタイトルは『品質保証の規格』なのです」
![]() 「あっ、そうだったのか」
「あっ、そうだったのか」
![]() 「話を続けると、売り手の品質保証を確認するために、買い手は売り手の工場に行って、部品や製造工程を点検することになった。
「話を続けると、売り手の品質保証を確認するために、買い手は売り手の工場に行って、部品や製造工程を点検することになった。
めんどうですよね。その費用も売値にオンしなければならない。
売り手も、買い手が複数なら度々品質監査に来れて仕事にならないし、買い手によって要求することが違うから困ってしまった。ある客は測定器の校正を半年毎にしろと言い、別の客はインターバルは1年毎で良いから精度を要求するとか大変です。
そんなことで品質保証の要求を統一しようという発想が現れた。初めは国ごとにそういう動きがあり、最終的にはISO(国際標準化機構)が規格を作ったという流れです。
その先はもう見えてますでしょう。買い手から依頼を受けて検査をする代行業者が登場し、彼らは顧客の代わりに品質監査をすることから『顧客の代理人』を自称した。
更には買い手でなく売り手が検査を依頼して品質保証のISO規格を満たしている証明を出してもらうことになった。そうすれば売り手は品質保証の証明をもって、買い手に売り込みに行ける。
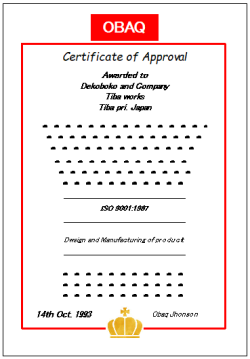
更に進んで、顧客が品質保証を要求していない……BtoC がこれに当たる……製造者のところに行って審査して証書を出す商売を始めた。つまり、今がそうです」
![]() 「あ〜、そういうことか。
「あ〜、そういうことか。
待ってくれよ、そうするとISO認証の価値というのは?」
![]() 「ISOの品質保証規格を満たしているという証明ということ」
「ISOの品質保証規格を満たしているという証明ということ」
![]() 「だが、それって、客から品質保証が要求されていれば意味があるけど、要求されていないなら意味がない。
「だが、それって、客から品質保証が要求されていれば意味があるけど、要求されていないなら意味がない。
要求されていないのに、認証するのはお金と労力の無駄だ」
![]() 「おっしゃる通り。自動車は BtoC がメインです。だからメーカーは納入先に品質保証を要求するけど、自社が認証しても意味がない。まあイメージアップにはなるでしょうけど」
「おっしゃる通り。自動車は BtoC がメインです。だからメーカーは納入先に品質保証を要求するけど、自社が認証しても意味がない。まあイメージアップにはなるでしょうけど」
片岡はしばし無言の後に口を開いた。
![]() 「つまりISO認証とは、取引で品質保証を要求された売り手がすることか?」
「つまりISO認証とは、取引で品質保証を要求された売り手がすることか?」
![]() 「買い手が認証を受けても意味がありません」
「買い手が認証を受けても意味がありません」
![]() 「売り手であっても、客から要求されていなければ無用であると……」
「売り手であっても、客から要求されていなければ無用であると……」
![]() 「そこで問題があります。
「そこで問題があります。
日本で客から品質保証を要求されている企業が、いかほどあるかということです。
それが日本のISO9001認証件数の限界です」
![]() 「私どもと佐川さんが最初に会ったとき、そんな話がありましたね
「私どもと佐川さんが最初に会ったとき、そんな話がありましたね
![]() 「そうでした。あのときは、そこまで突っ込んだ話ではありませんでしたが。
「そうでした。あのときは、そこまで突っ込んだ話ではありませんでしたが。
ともかく1995年の今の認証件数は1,300件くらいですかね
![]() 「となると、私の質問の回答は……」
「となると、私の質問の回答は……」
![]() 「ISO認証の効果を問われたとおっしゃいましたね。
「ISO認証の効果を問われたとおっしゃいましたね。
コンサルの依頼を受けたいなら、会社を良くすると言っても良いのかもしれません」
![]() 「佐川さんらしくないですね。いつも本音、正直が売りの佐川さんではないですか」
「佐川さんらしくないですね。いつも本音、正直が売りの佐川さんではないですか」
![]() 「会社が良くなるとは、会社の仕組みを見直して、仕事がミスなく円滑に動くようになると言えば良いのです」
「会社が良くなるとは、会社の仕組みを見直して、仕事がミスなく円滑に動くようになると言えば良いのです」
![]() 「認証の効果が、かかる費用より大きいか否かですね」
「認証の効果が、かかる費用より大きいか否かですね」
![]() 「そうです。例えば顧客が1社しかないなら、わざわざ認証をする意味もなさそうです。顧客の品質管理の出張を作ってやるのも意味があるかもしれません」
「そうです。例えば顧客が1社しかないなら、わざわざ認証をする意味もなさそうです。顧客の品質管理の出張を作ってやるのも意味があるかもしれません」
注:品質管理の仕事をしていると、出張があると嬉しいものだ。北海道とか九州などになると、めったに行けないところだから、出張でお土産を買ってくるのが楽しみであった。
![]() 「それに必要がなくて認証した企業は、ゆくゆくは認証を返上、止めてしまうでしょう。そうなるのはやむを得ないとしても、売り込んだ人が恨まれないためには、なにか良かったと思われる成果を出すべきでしょうね。そうでなけらば認証にかかったお金は無駄だったという意識しか残りません。
「それに必要がなくて認証した企業は、ゆくゆくは認証を返上、止めてしまうでしょう。そうなるのはやむを得ないとしても、売り込んだ人が恨まれないためには、なにか良かったと思われる成果を出すべきでしょうね。そうでなけらば認証にかかったお金は無駄だったという意識しか残りません。
でもそれなら、同じコンサルの仕事をするなら、ISO認証より、会社の仕組みの見直しとかプロセスの改善の依頼を受けたほうがやりがいがありますね。依頼する方も何十万も毎年払って免状一枚より、遥かに実質のある改善が期待できますよ」
![]() 「結局、ISO認証の効果は費用分はないということかね?」
「結局、ISO認証の効果は費用分はないということかね?」
![]() 「だって本来なら客から品質保証を要求された会社がすることですよ。
「だって本来なら客から品質保証を要求された会社がすることですよ。
それを必要ない会社がやろうとすることが、目的と手段と見合っていませんよ。
山口さんはどうお考えですか?」
![]() 「えっ、私ですか!」
「えっ、私ですか!」
![]() 「次回、皆さんがいらっしゃるまでに、山口さんが考えておきますからご安心ください」
「次回、皆さんがいらっしゃるまでに、山口さんが考えておきますからご安心ください」
柳田企画の二人が帰った後、佐川と山口が会議室に残り雑談をする。
![]() 「ISO9001とは売り手と買い手の関係であることは明確です。
「ISO9001とは売り手と買い手の関係であることは明確です。
ではISO14001は何のために認証するのでしょう? まさに顧客から要求されていないのにする、ISO9001認証と同じとしか思えません」
![]() 「まず商取引でISO認証を要求するのは独禁法違反だそうだ。未来の記憶ではあと10年もすると公正取引委員会から正式に通知が出される。
「まず商取引でISO認証を要求するのは独禁法違反だそうだ。未来の記憶ではあと10年もすると公正取引委員会から正式に通知が出される。
但し、ISO認証していると優遇措置を取るのは合法らしい。要するに取引の必要条件にしてはまずいようだ。
ISO9001は製造業以外あまり関心を呼んでいないが、ISO14001は政府機関、自治体、学校、商業、サービス業などの認証が多くなり、意識高いことの証明みたいになる」
![]() 「そうなるとISO14001認証は必需品ということですか?」
「そうなるとISO14001認証は必需品ということですか?」
![]() 「いっときはそのような状況になる。しかしすぐに流行は過ぎ去る。
「いっときはそのような状況になる。しかしすぐに流行は過ぎ去る。
ところでISO9001の意図は何だっけ?」
![]() 「顧客満足です」
「顧客満足です」
![]() 「良くできました。ではISO14001の意図は?」
「良くできました。ではISO14001の意図は?」
![]() 「遵法と汚染の予防でしたっけ?」
「遵法と汚染の予防でしたっけ?」
![]() 「その通り。ということはISO14001認証企業の環境法違反率と環境事故発生率が、未認証企業より優れていなければ、認証の価値がないとみなされると思わないか?」
「その通り。ということはISO14001認証企業の環境法違反率と環境事故発生率が、未認証企業より優れていなければ、認証の価値がないとみなされると思わないか?」
![]() 「当然そうなりますね。
「当然そうなりますね。
しかし、待ってください。先ほどの話でISO9001の認証は『品質保証規格を満たしているという証明』でしたよね。
その伝で行けばISO14001認証は『環境マネジメントシステム規格を満たしているという証明』です。
環境マネジメントシステム規格を満たしていれば、違反も事故も起きないのですか?」
![]() 「ISOを認証すれば規格の意図が実現できるという、理屈もなければ保証もありませんね。
「ISOを認証すれば規格の意図が実現できるという、理屈もなければ保証もありませんね。
今までだってISO9001認証企業が、品質問題を起こしたりして報道されています。
いや、遡ればISO9001登場以前に、二者間で品質保証協定を結んでいても不良はなくなりませんでしたよ」
![]() 「そう言われるとその通りですが……
「そう言われるとその通りですが……
規格要求は環境方針を作れとか、文書の管理をしっかりしろとか、改善計画を進めろしかありません。それと遵法と汚染の予防がイコールなのでしょうか?」
![]() 「明らかにイコールではないね。ただ仕組みを作る意味はありますね。いや、仕組を作る意味しかないというべきか。
「明らかにイコールではないね。ただ仕組みを作る意味はありますね。いや、仕組を作る意味しかないというべきか。
長い目で見れば規格を満たしているほうが、満たさないよりは良いかなとは思います。

ただDISの序文にあったはずですが、規格を満たしてもパフォーマンスが異なる場合もある、いやパフォーマンスが異なっていても規格を満たすこともあるかな(注4)、どっちだか忘れたが、ISO14001を満たしたすべての組織が、素晴らしい成果、具体的には遵法と汚染の予防を達するわけではないと、規格の序文で言い訳している」
![]() 「序文で言い訳ですか。予め逃げを打っているだけじゃないですか」
「序文で言い訳ですか。予め逃げを打っているだけじゃないですか」
![]() 「現実はそうだろう。完全な仕組みなんてない。有資格者、熟練者でも確率的にミスは起きるだろうし、整備された機械だって偶発的な故障はするだろう。
「現実はそうだろう。完全な仕組みなんてない。有資格者、熟練者でも確率的にミスは起きるだろうし、整備された機械だって偶発的な故障はするだろう。
結果として、違反も事故もゼロは維持できそうない。
しかし社会が求めるのは、事故を起こさない仕組みではなく、事故を起こさないことだ
![]() 「佐川さんは、ISO14001の行く末を知っているのでしょう?
「佐川さんは、ISO14001の行く末を知っているのでしょう?
それはどうなったのですか?」
![]() 「認証件数が増えれば事故も起こす認証企業も増えるし、違反する認証企業も増える。当たり前だ。
「認証件数が増えれば事故も起こす認証企業も増えるし、違反する認証企業も増える。当たり前だ。
そのとき認証機関や認定機関が、認証は仕組みの保証であってパフォーマンスじゃないと言えば良かったのだが、彼らは認証企業がウソをついたと責任転嫁した」
![]() 「それは詭弁でも……ないか、単なる言い訳ですね。
「それは詭弁でも……ないか、単なる言い訳ですね。
それは通用したというか、信用されたわけですか?」
![]() 「企業は違反とか違法とか起きたことは事実であり、負い目がある。だから反論はしなかった。
「企業は違反とか違法とか起きたことは事実であり、負い目がある。だから反論はしなかった。
そして認証停止とか認証取り消しとかを受け入れたわけだ」
![]() 「民事で争った企業はなかったのですか?」
「民事で争った企業はなかったのですか?」
![]() 「今から10年以上
「今から10年以上
まあ、1兆円企業の商社と10億円企業の認証機関の争いだ。良い弁護士も揃えるだろうし、商社の言い分はもっともだし、まともに裁判やったら認証機関の負けだと思うよ。
結末は分からない、闇の中で手打ちしたようだ。
認証機関は正義とか、世の悪を討つという思い上がりというか勘違いしているのではないか。法律も知らんでよくやるよ。
私としては、認証停止された多くの企業は、裁判に訴えるべきだと思う。高い金をとって認証して、企業が違反や事故を起こしたとき、認証停止とか認証取り消しするとは、信義則に反する(注5)。
ISO審査は無事故・無違反を保証するものではないと、説明すれば良かったのさ。実際に審査登録証にそう書いてあった。認証とはそういうものだ」
![]() 「ええと、でもUL認定を受けた製品でも火災は起きます。でも認定を受けていれば火災保険が支払われる。
「ええと、でもUL認定を受けた製品でも火災は起きます。でも認定を受けていれば火災保険が支払われる。
ではISO14001の認証を受けた企業でも、違反も起きるし事故も起きるのは確率問題だ……それは分かります。
しかしそれならISO認証しても、メリットは何でしょう? なにもなさそうです」
![]() 「そう思えるね。ISO認証の費用を払うなら、そのお金を結果が出ることに使うという選択もありそうだ。
「そう思えるね。ISO認証の費用を払うなら、そのお金を結果が出ることに使うという選択もありそうだ。
あるいはISO14001適合の仕組みを作っても、認証費用が無駄だから認証しないというのが正しいのかもしれない。
だが、そもそもISO9001と認証制度は無関係だ。今、制定を急いでいるISO14001だって
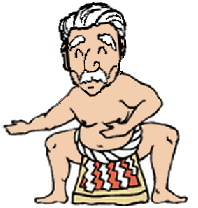 第三者認証とは無縁と言っても良い。言い方悪いけど、人の
第三者認証とは無縁と言っても良い。言い方悪いけど、人の
企業はISO9001の良いところを真似して会社の仕組みを見直しても良いし、ISO14001の良いとこどりをしても何も悪いことはない。
ISO認証しないとならないということはないのよ」
![]() 「認証しないと箔が付かないのですね」
「認証しないと箔が付かないのですね」
![]() 「箔をつけるというのは、それを素晴らしいとみなす人がいるからだろう。ある意味というか、全ての意味でというべきか、第三者認証は裸の王様なのだ。
「箔をつけるというのは、それを素晴らしいとみなす人がいるからだろう。ある意味というか、全ての意味でというべきか、第三者認証は裸の王様なのだ。
自分がバカに思われたくないから見えない服を素晴らしいという。意味のない認証をすごいという。全く同じだ」
![]() 「それをいっちゃお終いです」
「それをいっちゃお終いです」
![]() 「実を言って、それは2010年頃のISO担当者に共通な、疑問というか、主張というか怒りというか、そんなことだったな」
「実を言って、それは2010年頃のISO担当者に共通な、疑問というか、主張というか怒りというか、そんなことだったな」
![]() 「そういうことが解決できなかった。そしてISO認証は下火になっていったということですね」
「そういうことが解決できなかった。そしてISO認証は下火になっていったということですね」
![]() 「下火というか、必要でない企業は認証を止めてしまったと私は考えている。
「下火というか、必要でない企業は認証を止めてしまったと私は考えている。
だいぶ前に言ったと思うけど、ISO認証を始めたとき、おかしな解釈とか要求事項の拡大解釈をしないで、まともな解釈をして、事故や違反が起きたときに、しっかりと認証の意味を説明すれば、ひたすら認証件数減少の道を歩むのではなく、最低でも現状維持ができたのではないかと思う。
認証機関が、自分は悪くないと言い訳しているうちに、認証ビジネスが信頼を失って、市場が崩壊してしまった……いやこれからそうなるだろう。そうでなく、認証制度の意味をしっかりと説明して、その価値を理解してもらうべきだったのだ」
![]() 「まずは規格の理解がしっかりしてなくちゃ、審査の信頼を得ることができませんね。
「まずは規格の理解がしっかりしてなくちゃ、審査の信頼を得ることができませんね。
そのために認証機関に規格の正しい理解をさせようと、佐川さんは考えているわけですね」
![]() 「そうだったけど、もう過去形かな。今はISO認証をまともにすることもなく、消滅したほうが良いと思う気持ちが強くなってきたよ」
「そうだったけど、もう過去形かな。今はISO認証をまともにすることもなく、消滅したほうが良いと思う気持ちが強くなってきたよ」
もう完全な夏だ。梅雨の前には昼休みに桜田門あたりまで歩いていたが、もう暑くて外を歩く気がしない。
朝、佐川と山口は、吉井部長から午後一から先週の週報の説明を求められた。
時間になり、小会議室で佐川から説明する。
![]() 「研究会もほぼ筋道がついて、今はISOのDISの正しい解釈を進めているところです」
「研究会もほぼ筋道がついて、今はISOのDISの正しい解釈を進めているところです」
![]() 「正しい解釈というと、正しくない解釈もあるのか?」
「正しい解釈というと、正しくない解釈もあるのか?」
![]() 「一応、仮訳はあります。ただ我々が読んでも翻訳がおかしいところがあり、正しくはどうなのかメンバーで協議しています。
「一応、仮訳はあります。ただ我々が読んでも翻訳がおかしいところがあり、正しくはどうなのかメンバーで協議しています。
英語原文は1,600語ほどしかありません。ただ関係代名詞や関係副詞でつながった長い文章で、そうですね1文の単語が30から50くらいあって、長く複雑です。
4行も議論するとその日は終わりです」
![]() 「それにしても三月もかけたら終わるじゃないか」
「それにしても三月もかけたら終わるじゃないか」
![]() 「おっしゃる通りです。実際にはメンバー同士で分担して訳していますから、集まったときは解釈の確認とかですね。
「おっしゃる通りです。実際にはメンバー同士で分担して訳していますから、集まったときは解釈の確認とかですね。
ただ皆が満足できる見解には、なかなか至りません」
![]() 「わけわからないのに時間をかけてもしょうがない。ウチにだって技術管理には規格翻訳のベテランがいるだろう。そういう人に頼むとか考えてみたまえ」
「わけわからないのに時間をかけてもしょうがない。ウチにだって技術管理には規格翻訳のベテランがいるだろう。そういう人に頼むとか考えてみたまえ」
・
・
・
![]() 「大体状況は分かった。
「大体状況は分かった。
それでこれからの計画は?」
![]() 「とりあえずFDISがでる1996年5月までに、DISの完全訳とそれの解釈集とどのようなアプローチをとるべきかをまとめておく予定です。
「とりあえずFDISがでる1996年5月までに、DISの完全訳とそれの解釈集とどのようなアプローチをとるべきかをまとめておく予定です。
FDISが出たら早急にその反映をして世に広めようかと思います」
![]() 「ほう、それはまたどうして?」
「ほう、それはまたどうして?」
![]() 「FDISが出た時点で、すぐに認証機関は具体的な対応を取れないでしょう。先手を打って完全版と称して国内に示せば、それが規格解釈のデファクトスタンダードになると考えます。
「FDISが出た時点で、すぐに認証機関は具体的な対応を取れないでしょう。先手を打って完全版と称して国内に示せば、それが規格解釈のデファクトスタンダードになると考えます。
私としてはまっとうな理解が広まればよいので、金も名も求めません」
![]() 「どうかなあ〜、お前は怪しげな解釈が出る前に、主流派になろうと考えているが、認証機関もプライドがあるから、それを尊重するかな?」
「どうかなあ〜、お前は怪しげな解釈が出る前に、主流派になろうと考えているが、認証機関もプライドがあるから、それを尊重するかな?」
![]() 「失礼ながら部長はアイデアをお持ちですか?」
「失礼ながら部長はアイデアをお持ちですか?」
![]() 「DISの完全訳を作りFDISが出たらその対応をするのは良いと思うが、世に広めるに方法はイマイチだ。
「DISの完全訳を作りFDISが出たらその対応をするのは良いと思うが、世に広めるに方法はイマイチだ。
必要なのは権威だ、箔付けが必要だ。例えばハワード氏を引き込んだらどうか。餅は餅屋、英語の理解はイギリス人だろう。彼がこの文章はこういう意味だと言えば、日本人がそうではないとは言いにくいだろう。
彼だって規格解説本とか出す気はあるだろう。うまくコラボする方法はないか?
あるいは複数の認証機関とタッグを組んでいくとか、それもハワードさんに相談してみろ」
![]() 「業界の研究会が外資系認証機関と、タイアップするのは抵抗されますね。
「業界の研究会が外資系認証機関と、タイアップするのは抵抗されますね。
実を言いまして、研究会が始まった頃、ハワードさんの講演を聞いたらどうかと部長がおっしゃいました。
それでそういう提案をしたところ、研究会のメンバーは好意的に受け止められましたが、研究会の幹事をしている業界の職員から参加を控えろという話があり、当社の山口さんと二人だけでお話をしました」
![]() 「しょうがねえなあ〜、これが日本スタイルか。まともなことをしているならともかく、世間知らずでおかしな解釈しているくせにジコチューなんだから。
「しょうがねえなあ〜、これが日本スタイルか。まともなことをしているならともかく、世間知らずでおかしな解釈しているくせにジコチューなんだから。
佐川が主導しても研究会の成果であれば、自分勝手に使うことはままならぬだろうから、そこのところをどうするか……
いいアイデアがないなら、とりあえずは完全訳を進めろ。
もちろんその作業では、佐川が経験したおかしな解釈を否定することを入れ込めよ。闇落ちしないよう山口が研究会を誘導しろ
ともかく何かいい方法を考えるんだ。
佐川の未来の記憶を研究会のメンバーにばらしてもダメかな?
研究会がISO14001の規格解釈と認証手順をまとめたら、産業環境認証機関に乗り込むというのもありかな?」
![]() 本日の考察
本日の考察
正直言って、スコアリング法でないと不適合、環境目的は3年以上でないと不適合、環境側面を有益と有害に分けないと不適合、環境目的と環境目標の計画は別にしないと不適合(その他多数)と語る、アホな審査員、認証機関を説得する方法は思いつきません。
そりゃ、まっとうな認証機関を選べばよいですが、それは言わない約束(注6)でしょう。
日本のISO認証をダメにしたのは業界系認証機関ではないかという気がします。
悪貨は良貨を駆逐するは真実だった。正義を実現するのはただ自由競争あるのみ。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
UL | |
| 注2 |
電取法(電気用品取締法)は1999年に電安法(電気用品安全法)に代わった。 変更点は多々あるが、製品に対する責任を国からメーカーに移したことが大きい。 | |
| 注3 |
ISO9001の認証件数は、1995年6月末1,232件、9月末で1,377件であった。 前途洋々の時代であった。 | |
| 注4 |
ISO14001:1996 序文 『同様な活動を実施してはいるが異なる環境パフォーマンスを示す場合であっても、共にその要求事項を満たすことがあり得る』 | |
| 注5 |
民法第1条第2項 | |
| 注6 |
ザピーナッツとクレージーキャッツのシャボン玉ホリディーの中で「お父っつあん、お粥ができたわよ」から「それは言わない約束でしょう」と続くコントがありました。そのときのBGMは「アメリアの遺言」という曲だそうです。 1960年代の話です。 |
外資社員様からお便りを頂きました(25.02.27)
おばQさま >規格解釈のデファクトスタンダード せっかく正しい解釈と翻訳が出来ても、それが主流にならなければ自己中解釈が罷り通る。 となると、経産省管轄のJEITA(2000年にEIAJとJEIDAが合併)でしょうかね。 ISO専門委員会を作って出版物が出来れば、それがデファクトに出来ると思います。 もし佐川氏の会社が幹事会社ならば、社長は理事、正しい日本語訳の発行は大きな社会貢献ですから、上を動かす事も可能かも。 でも、頭が痛いのはISO14000 JIS規格とEIAは経産省扱いですが、環境となると2001年発足の「環境省」となる可能性大。 そうなる前に、さっさとISO規格シリーズとして翻訳を発行していまうか、それとも環境省と認証機関が組んで、巻き返しを図ってくる可能性も大きそう。 いづれにせよ、省庁縦割り、縄張り争いは激烈だから、いくら良いものでも政治的駆け引きは絡みそうです。 |
外資社員様 毎度お便りありがとうございます。 JEITAと聞いて、一瞬JATAかと思ってしまいました。JATAは審査員研修機関連絡協議会の略で、日本の審査員研修機関の業界団体です。とはいえ20年前はザクザク会員企業(研修機関)がありましたが、昨今は審査員希望者減少で研修機関も10社となってしまいました。 話は更にそれますが、私のズーズー弁でJEITAと言うと、よく同僚から「自衛隊がどうした」とからかわれました。 ええと、若干説明しますと、私の場合はその前に問題がありました。上長が審査員が間違ったことを言っても、更に上長がそれを知っていても「気持ちよく帰ってもらおう」なんて寝ぼけたことを言って、不適合を受け入れてしまうことでした。 何か役職に就くと鷹揚な対応がらしく見えるのか、自分の裁量でできることはどんどん妥協してしまう人が多くて困りました。 上長が了解してしまえば私が認証機関に異議申し立てできません。 実を言って関連会社の方が、銭に細かいですから(それがまっとうです)、不適合を出されたときは私を呼んで、認証機関に講義に行くから同行してと言われたことは何度もあります。筋の通らないこと、規格解釈が誤っていることなら堂々と抗議すべきです。 とはいえ認証機関&審査員が「分かりました、不適合を削除します」なんて言ったことは一度もないです。言を左右して、せいぜいが「次回の審査では不適合のフォローをしないから、よろしいですね」なんて対応でした。私はよろしくなかったですが、関連会社の人は書類を書き換えなくてもOKしてました。そんなものですかね? 小説では今回はまっとうな上長にしたつもりです。 私たちはビジネスで契約で仕事しているわけですから、認証機関が業界設立で10%株主だと言っても甘やかすことなく、契約違反で訴えるくらいの行動をとってほしいものです。 全然話が変わりますが、行政が音頭を取ったらデファクトスタンダードではなくデジュリスタンダードになりませんか? |
外資社員様からお便りを頂きました(24.02.28)
おばQさま コメントへのお返事 >何か役職に就くと鷹揚な対応がらしく見えるのか、自分の裁量でできることはどんどん妥協してしまう人が多くて困りました。 私の昔の会社にもいましたね、何だったんでしょう。 あの無責任さ。 もっと不思議なのは、それが管理職のマイナス評価にならない。 いつもの例で恐縮ですが、帝国陸海軍も同じで、兵や下級将校には捕虜になるなと強要するのに、参謀長福留繁海軍中将は捕虜になっても、海軍省は問題を見ないフリして何と栄転。 偉い人になると、オカシナ事をしても罰せられないのは、悪しき伝統だったのか? もしかして、日本の凋落につながった生産の海外移転も、そんな鷹揚さで始まったのかもしれません。 |
外資社員様 ご意見、ありがとうございます 日本あるあるですか(涙 質問です。 そういう人の下にいた場合、どう対応すればよいのでしょうか? 1案 部長のおっしゃる通りです、ワッショイ そういう人が出世しましたね。 2案 面従腹背で流す⇒組織が腐るでしょうね。 3案 正論を吐いて嫌われる⇒これ私です。 今、自分は後悔してませんし、出世すれば良かったとも思いません。 自分の主張が通らなくても、自分に嘘をつかないで良かった……のでしょうか? |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |