注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
認証機関のゼネラルマネージャーであるハワードさんと会った翌日である。
朝一番に山口が佐川のところに来て話をしたいという。佐川は例の件かと察して、
![]() 「昨日、ハワードさんと話していたとき、佐川さんは未来から戻ってきたと言いましたね。あれって、どういうことですか?」
「昨日、ハワードさんと話していたとき、佐川さんは未来から戻ってきたと言いましたね。あれって、どういうことですか?」
![]() 「秘密ではないけど、あまり広めないでくれよ。妄想癖とかボケとか言われると嫌だから」
「秘密ではないけど、あまり広めないでくれよ。妄想癖とかボケとか言われると嫌だから」
![]() 「具体的には、タイムマシンとか、魔法とか?」
「具体的には、タイムマシンとか、魔法とか?」
![]() 「そういうことでなく、2020年頃まで生きていた記憶があるのです。ずっと前からでなく、一昨年の11月に突然その記憶が浮き上がってきた感じ」
「そういうことでなく、2020年頃まで生きていた記憶があるのです。ずっと前からでなく、一昨年の11月に突然その記憶が浮き上がってきた感じ」
![]() 「ラノベのようですね」
「ラノベのようですね」
注:「ラノベ」とはライトノベルの略で、深刻でない若い人向けの軽い読み物。
![]() 「だから言っただろう、君のように若い人からは、妄想じゃなくて、ラノベの読み過ぎと言われそうだ」
「だから言っただろう、君のように若い人からは、妄想じゃなくて、ラノベの読み過ぎと言われそうだ」
![]() 「だとすると、ISO9001認証は当然として、これからのISO14001の審査とかも覚えているのですか?」
「だとすると、ISO9001認証は当然として、これからのISO14001の審査とかも覚えているのですか?」
![]() 「山口さんが20年前に、どんな本を読んだとかどこで遊んだかなんて、細かく覚えていないでしょう。
「山口さんが20年前に、どんな本を読んだとかどこで遊んだかなんて、細かく覚えていないでしょう。
私も時間を戻ってもう一度生きることができると知っていたら、覚えようとしたと思いますが、どんどん忘れましたね。人間はメモリー容量が一定なのか、新しいことを覚えると、古いのを忘れてしまうようです。
もちろん大きな出来事は覚えています。この前の阪神淡路大震災とかオウム真理教事件とかね。
それから審査員が灰皿を投げたことも覚えていました。尾関副工場長からいじめられるのは、未来の記憶を思い出す前からでしたけどね」
![]() 「ぜひお聞きしたいのは、私はこれからどうなりますか?」
「ぜひお聞きしたいのは、私はこれからどうなりますか?」
![]() 「記憶を思い出してから2年半経ちましたが、既に私の二回目の人生は前回とはかなり変わっています。そして山口さんの現時点は、私の一度目の人生でみたあなたの人生とは既に大きく違います。
「記憶を思い出してから2年半経ちましたが、既に私の二回目の人生は前回とはかなり変わっています。そして山口さんの現時点は、私の一度目の人生でみたあなたの人生とは既に大きく違います。
だからあなたの未来も前回と違うはずです。あなたがどうなるかは分からない」

![]() 「佐川さんが未来の記憶を持ってからの行動は、過去と変わりましたか?」
「佐川さんが未来の記憶を持ってからの行動は、過去と変わりましたか?」
![]() 「そりゃもちろんですよ。悪くなると知っていて、前回と同じ決断や行動をするわけないじゃないですか。
「そりゃもちろんですよ。悪くなると知っていて、前回と同じ決断や行動をするわけないじゃないですか。
自分にとっても周りにとっても、少しでも良い選択をしようと行動しますよ」
![]() 「その結果、状況は良い方に変わったのでしょうか?」
「その結果、状況は良い方に変わったのでしょうか?」
![]() 「変わったね」
「変わったね」
![]() 「意思で人生は変えられるのですか?」
「意思で人生は変えられるのですか?」
![]() 「もちろんです。そうでなければ運命論が絶対ということになる。
「もちろんです。そうでなければ運命論が絶対ということになる。
二度目の人生というかここ2年間の出来事は、1回目とだいぶ変わった。それは私の意志ばかりでなく、周りの環境が変わったこともあり、他人の意志というか決定が前回と変わったこともある」
![]() 「私の個人的関心は、私のこれからの20年がどうなるか知りたいです」
「私の個人的関心は、私のこれからの20年がどうなるか知りたいです」
![]() 「先ほど言ったように、お役に立てそうありません。それは前回と大きく変わることもあるけど、前回はあなたと付き合いがなくなってしまったからです」
「先ほど言ったように、お役に立てそうありません。それは前回と大きく変わることもあるけど、前回はあなたと付き合いがなくなってしまったからです」
![]() 「佐川さんがこの会社を退職したと言いましたが、それでですか?」
「佐川さんがこの会社を退職したと言いましたが、それでですか?」
![]() 「そうです。福島工場がISO9001を認証しようとしていたとき、當山さんがトラブルを起こして会社を辞めたでしょう
「そうです。福島工場がISO9001を認証しようとしていたとき、當山さんがトラブルを起こして会社を辞めたでしょう
![]() 「ありましたね、あれから2年半になりますか」
「ありましたね、あれから2年半になりますか」
![]() 「前回のとき、その件は大きな問題にならず、當山さんは懲戒処分を受けなかった。もちろんそういったことに、私は関わっていない。
「前回のとき、その件は大きな問題にならず、當山さんは懲戒処分を受けなかった。もちろんそういったことに、私は関わっていない。
彼は退職はしなかったが、ISO9001の認証指導には能力不足とみられて、担当を外され関連会社に出向になった。
山口さんはひとり生産技術部に残って、工場の認証指導に頑張った。苦労しただろうけど最初の数工場が認証してからは、上司や工場から信頼を得た。その後、ISO14001の認証の指導もしていた。
他方、私は本社に来ることもなく、福島工場でISO9001の認証をしてからISO14001認証もした。しかし尾関副工場長との関係がドンドン悪くなり辞めてしまった。
そのときまで時々山口さんと会うことはあったが、退職してからは縁が切れた」
![]() 「ハワードさんに灰皿事件
「ハワードさんに灰皿事件
![]() 「そうとも言える。あの事件に私は無関係なのだが、尾関副工場長は私の責任だと内外に公言していてね、多くの人、特に偉い人はそれを信じた。昇進どころか査定も最低で針の筵の日々だったよ。
「そうとも言える。あの事件に私は無関係なのだが、尾関副工場長は私の責任だと内外に公言していてね、多くの人、特に偉い人はそれを信じた。昇進どころか査定も最低で針の筵の日々だったよ。
1996年だったと思う……来年だな、彼は副が取れて工場長になった。それからますます私への当たりが厳しくなってね、1997年にISO14001認証してすぐに辞めた」
![]() 「佐川さんは、それからどうしたのです?」
「佐川さんは、それからどうしたのです?」
![]() 「高卒だし役に立つような資格もなくて参ったよ。それでもISO9001やISO14001の認証経験があることから、都内の中堅企業に採用してもらった、まさに芸は身を助けるだ。
「高卒だし役に立つような資格もなくて参ったよ。それでもISO9001やISO14001の認証経験があることから、都内の中堅企業に採用してもらった、まさに芸は身を助けるだ。
もちろんISO認証なんて一過性の仕事だから、その後は環境管理の仕事をして定年まで十数年勤めることができた」

![]() 「バタフライ効果
「バタフライ効果
![]() 「それって元々は気象予測のとき、一つの変数がほんの少し違うと、結果に大きな変化が出たことが始まりらしい。
「それって元々は気象予測のとき、一つの変数がほんの少し違うと、結果に大きな変化が出たことが始まりらしい。
意思と向上心を持つ人間の世の中は、単なる物理の法則とは異なる別の理屈で動いているんじゃないかな。私は個人も社会もランダムなブラウン運動ではなく、良い方に動かそうという力が働いているように思う」
![]() 「それじゃ、灰皿事件の影響はどうでしたか?」
「それじゃ、灰皿事件の影響はどうでしたか?」
![]()
 |
前回は怪我した女性の容貌へのダメージは大きく、皆が心配した。幸い以前から付き合っていた人と結婚して幸せだったよ。
しかし今回は怪我がない分、一層幸せになれたと思う。
私は彼女の代わりに代わりに、ひと月痛い思いをした。しかしその一方、尾関副工場長は、事件の責任が私にあると嘘がつけなくなった。総合すればプラスかな。
いや、灰皿事件で彼の悪事がばれるきっかけになったからラッキーだったね。
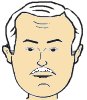 事件を起こした審査員は、前回同様、執行猶予は付いたけど有罪になった。しかし前回は被害者の女性に後遺症の残ったため、その慰謝料のために自宅を売ったと聞いた。
事件を起こした審査員は、前回同様、執行猶予は付いたけど有罪になった。しかし前回は被害者の女性に後遺症の残ったため、その慰謝料のために自宅を売ったと聞いた。
今回は刑事罰も賠償金も軽くてハッピーだったんじゃないかな。
尾関副工場長は、この事件をきっかけに本社人事の調査でいろいろ悪事がばれて懲戒解雇と有罪になった。
 でも、それ以降の悪事を阻止してもらったのだから、メタ的には彼も良かったのではないですか。
でも、それ以降の悪事を阻止してもらったのだから、メタ的には彼も良かったのではないですか。
そう考えると、灰皿事件に関わったすべての人が、良い方に変わったと思う。
![]() 「未来を知っているなら、何か金儲けになることをご存じありませんか?」
「未来を知っているなら、何か金儲けになることをご存じありませんか?」
![]() 「アハハハ、吉井部長からも聞かれたよ」
「アハハハ、吉井部長からも聞かれたよ」
![]() 「部長も佐川さんが未来から戻ってきたことをご存じなのですか?」
「部長も佐川さんが未来から戻ってきたことをご存じなのですか?」
![]() 「これから起きるISO認証の問題を説明したときに、その話はした。そうでないとISO認証の問題がオカルトになってしまうから」
「これから起きるISO認証の問題を説明したときに、その話はした。そうでないとISO認証の問題がオカルトになってしまうから」
![]() 「佐川さんの話を聞いてもオカルトでしょうけど」
「佐川さんの話を聞いてもオカルトでしょうけど」
注:オカルト(occult)とは、「魔法のような」とか、「神秘的な」という意味
![]() 「金儲けか……まあ、当分の間、株価は変わらない。外国為替相場は、今1ドル96円位だが3年後は130円になる。
「金儲けか……まあ、当分の間、株価は変わらない。外国為替相場は、今1ドル96円位だが3年後は130円になる。
しかし元手がないとね。30万のために100万を3年塩漬けではね。使う当てのない金が3千万もあれば濡れ手に900万か、何をするにも元手がいる」
注:バブル崩壊後、銀行の預金の金利は下がる一方だったが、それでもこのお話の1995年頃はまだ今までよりはましだった。長らくゼロ金利が続いたが、2024年、2025年と預貯金の金利がわずかに上がったのがうれしい。
ゼロ金利といっても全くゼロではなく0.001%前後であった
我が家ではメインバンク(笑)の三菱UFJの普通預金に、400万くらい入れておく。それ以外は定期だ。その口座に年金が入り、生活費が出る。総合して毎年数十万減になる。余り少なくなると引き落としできなくから、数年に一度、満期になった定期を解約して補充する。
| 年/月 | 2022/08 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | 2025/02 |
| 利息(円) | 12 | 12 | 14 | 17 | 273 | 1376 |
 |  | |
 |
定期にしても利息は普通預金より25%しか多くない。

![]() 「競馬はどうですか、重賞レースの菊花賞とかダービーとか」
「競馬はどうですか、重賞レースの菊花賞とかダービーとか」
![]() 「残念ながら、私は競馬には興味がなくてね」
「残念ながら、私は競馬には興味がなくてね」
![]() 「それはホントに残念です」
「それはホントに残念です」
7月の第1回環境ISO研究会である。
今日は環境ISOに関して情報収集した2名の報告である。
まずはN社の金子さんからの報告だ。
![]() 「弊社はイギリス工場があります。従業員約600人で、事業はすべて向こうの人が動かしており、日本人は営業担当が数人駐在しているだけです。
「弊社はイギリス工場があります。従業員約600人で、事業はすべて向こうの人が動かしており、日本人は営業担当が数人駐在しているだけです。
BS7750を認証していますので、そこに認証のアプローチ方法を問い合わせました。
すべて現地の人が行っていますので、英文メールで問い合わせたので、向うもこちらも話が通じているのかどうか心配なところも多々あります。
その辺は割り引いてください。皆さんからの質問で回答できないことがあれば、問い合わせたいと思います。
まずどういうアプローチとか各項番に対する取組手法などを聞いたのですが、当初はそういう発想が分からないという回答が来ました。
分からないとはどういうことかと聞きますと、文章に書いてある通りだというのです。
例えば該当する環境法を調べるにはどうしたのかと聞きますと、向うから言われたのはよく読め、書いてある通りにしたとのことでした。
BS7750の『4.4.3法律上、規制上、及びその他の方針上の要求事項の登録』の和訳は
『組織は、その活動、製品及びサービスの環境面に適用される法律上、規制上及びその他の方針上の要求事項及びコードで機構が予約しているものすべてを記録するための手続を確立し、保持しなければならない(注2)』
英語原文は下記
The organization shall establish and maintain procedure record and legislative, regulatory and other policy requirements and codes (to which the organization subscribes) applicable to the environmental aspects of its activities, products and services.
まずこれは和訳がこなれていないと思います。『organization』の訳が『組織』とか『機構』の揺らぎもあります。その他『Code』が『コード』では意味が分かりません。『Code』は『規則』とか『規範』あるいは『原則』でしょう。
『subscribe』が『予約』もおかしく、『賛同する』とか『合意する』ではないかと思います。
まあ、それはそれとして、文章の意味は『環境面に適用される法律、規制その他の方針で定めたものや組織が同意した規範を記録する』でしょう。
先ほど言いましたが、彼らはそれをどうしたかというと、書いてある通りにしたというのです。つまり以前から該当すると認識して対応していたことの一覧を書いて、今後変更があればメンテするというのです。
というわけで法規制を調べるという発想がありません
![]() 「調べる必要がないってこと?」
「調べる必要がないってこと?」
![]() 「そうなのです。
「そうなのです。
原文は『record』ですから、『記録する』とか『登録する』でしょうか。間違っても調査ではありませんね」
注:recordという語は、ラテン語の「覚える」「記憶するために繰り返す(暗唱)」という意味から「証拠として書き留める」という意味になったそうだ(出典)。
調査するというニュアンスはない。
![]()
![]() 「つまり調べて記録するのではなく、単に記録するだけと理解して良いのかな?」
「つまり調べて記録するのではなく、単に記録するだけと理解して良いのかな?」
![]() 「そうです。というのは会社が昨日・今日できたわけではない。過去から法を守っていれば新たに調べることはなく、今まで対応していた法律などを一覧できるようにまとめることで用は済むと言います。確かにそう言われるとそうですよね」
「そうです。というのは会社が昨日・今日できたわけではない。過去から法を守っていれば新たに調べることはなく、今まで対応していた法律などを一覧できるようにまとめることで用は済むと言います。確かにそう言われるとそうですよね」
![]() 「最初に調べるときはどうするのだろう?」
「最初に調べるときはどうするのだろう?」
![]() 「日本の場合なら、新設備を導入するときに、メーカーから届け出とか有資格者が必要とか説明した資料が提供される。
「日本の場合なら、新設備を導入するときに、メーカーから届け出とか有資格者が必要とか説明した資料が提供される。
メーカーや代理店はお客にそういうサービスはするのが当たり前の認識だ。売った後でお客さんが問題を起こせば、次の商売に差し支えるからね。
もちろんローカルなことはメーカーも目が届かない。自治体の条例については県の環境課や市の環境課に相談に行く。危険物なら消防署だね。だいたいはそれで間に合う。
行政の言う通りしていれば、後で問題になっても、そう悪くはならないよ」
![]() 「イギリスでは弁護士に頼むと、そういう調査をしてくれるそうです」
「イギリスでは弁護士に頼むと、そういう調査をしてくれるそうです」
![]() 「それは日本でも同じだよ。でもそこまでしなくても市役所と県庁で大丈夫だよ」
「それは日本でも同じだよ。でもそこまでしなくても市役所と県庁で大丈夫だよ」
![]() 「当社の関連会社は、当社に問い合わせてくることが多いですね。小さな会社は行政に行くのも敷居が高いと感じるものですよ」
「当社の関連会社は、当社に問い合わせてくることが多いですね。小さな会社は行政に行くのも敷居が高いと感じるものですよ」
![]() 「あるあるですね。税理士の先生などが、そういうことを勉強して、いろいろ指導してくれるところもありますね。
「あるあるですね。税理士の先生などが、そういうことを勉強して、いろいろ指導してくれるところもありますね。
指導料を取ると弁護士法か何かに引っかかると聞きます。無償で教えて、本来の税理士の仕事に結びつけるのでしょう」
![]() 「『同意した規範』とは何ですかな?」
「『同意した規範』とは何ですかな?」
![]() 「省エネ法の場合、使用エネルギーが大きな事業所には省エネ義務があります。それだけでなく多くの業界は、それを越える省エネの業界目標を立てるのが普通です。ああいったものでしょうか」
「省エネ法の場合、使用エネルギーが大きな事業所には省エネ義務があります。それだけでなく多くの業界は、それを越える省エネの業界目標を立てるのが普通です。ああいったものでしょうか」
![]() 「なるほど、それなら義務じゃないから、取り入れるかどうかは自分が決められるね」
「なるほど、それなら義務じゃないから、取り入れるかどうかは自分が決められるね」
![]() 「話を戻しますが、法規制を調べるというよりも、まとめるという発想は素直に理解できますね。それに元々のBS規格の文言を見ればそうとしか読めない。
「話を戻しますが、法規制を調べるというよりも、まとめるという発想は素直に理解できますね。それに元々のBS規格の文言を見ればそうとしか読めない。
というと環境法を調べる方法を考えることは不要だね」
![]() 「水を差すようですが、今までの話はBS規格の場合です。
「水を差すようですが、今までの話はBS規格の場合です。
ISO規格のDISでは『identify』でした。意味は『識別する』『見分ける』『選別する』『明らかにする』とかですか、私の英語力ではニュアンスは分かりませんが、単に今までのものをまとめるだけでは済まないように思います」
![]() 「佐川さんのおっしゃる通りです。イギリス工場の担当もBSからISOになるときには、なにかしら調査などが追加になるだろうと言っていました。
「佐川さんのおっしゃる通りです。イギリス工場の担当もBSからISOになるときには、なにかしら調査などが追加になるだろうと言っていました。
ただBS7750の認証を受けた人たちの反応は、規格を読んで悩むようなことはないということです」
![]() 「それはあれでしょう、法律で言う文字解釈ですよ」
「それはあれでしょう、法律で言う文字解釈ですよ」
![]() 「イギリスでは皆大人で、文章の意図を組んで対応しているということかな」
「イギリスでは皆大人で、文章の意図を組んで対応しているということかな」
![]() 「じゃあ、日本ではうまくいかないね。日本人は細かいことに囚われて、目的を見失ってしまうよ、アハハハ」
「じゃあ、日本ではうまくいかないね。日本人は細かいことに囚われて、目的を見失ってしまうよ、アハハハ」
![]() 「確かに細かい検討した証拠がないと、しっかりやっていないとみなされるかもしれませんね」
「確かに細かい検討した証拠がないと、しっかりやっていないとみなされるかもしれませんね」
・
・
・
![]() 「『4.4.2の環境影響の評価及び登録』ですが、ここはISOのDISでは全く違います。BS規格では工場からでる環境影響を把握して、それを登録し管理する手順を作ることが要求されています。
「『4.4.2の環境影響の評価及び登録』ですが、ここはISOのDISでは全く違います。BS規格では工場からでる環境影響を把握して、それを登録し管理する手順を作ることが要求されています。
これについてもイギリス工場の考えは『既にしていること』だという認識です
騒音が出る機械を導入するときには、メーカーから防音、遮音などの方法を聞いて法規制以下にするようにしている。導入時に環境影響を想定し規制以下にする手順はあるということでした。
一方、ISO規格はBS規格と大きく違って、環境影響を調べるのは一緒だけど、管理する対象は環境影響を出す『環境側面』とある」
![]() 「ISO規格の意図は『遵法と汚染の予防』と言われるから、公害を出さないことが要求されるのだろう」
「ISO規格の意図は『遵法と汚染の予防』と言われるから、公害を出さないことが要求されるのだろう」
![]() 「基は同じ『environmental aspect』を、BS規格では『環境面』をDISでは『環境側面』と訳していますね」
「基は同じ『environmental aspect』を、BS規格では『環境面』をDISでは『環境側面』と訳していますね」
![]() 「熟語は同じ『environmental aspect』だけど、BS規格とDISでは異なる概念のように思えますね」
「熟語は同じ『environmental aspect』だけど、BS規格とDISでは異なる概念のように思えますね」
![]() 「済みません、おっしゃる意味が分かりません」
「済みません、おっしゃる意味が分かりません」
![]() 「BS規格では『environmental aspect』の定義がありません。そして使われているのはたった一度、『4.4.3法律上、規制上及びその他の方針上の要求事項の登録』で『製品及びサービスの環境面に適用される』と使われているだけです。
「BS規格では『environmental aspect』の定義がありません。そして使われているのはたった一度、『4.4.3法律上、規制上及びその他の方針上の要求事項の登録』で『製品及びサービスの環境面に適用される』と使われているだけです。
この文章からは、『環境面』とはDISの定義とは違い、単に製品やサービスの環境面というだけのように思います。
そして何よりも『環境面』を重要なものとしていません」
![]() 「突き詰めるとDISと同じじゃないですかね」
「突き詰めるとDISと同じじゃないですかね」
![]() 「そうかな〜、BS規格では環境影響を管理せよと語っていて、環境面を管理せよとは言っていないね」
「そうかな〜、BS規格では環境影響を管理せよと語っていて、環境面を管理せよとは言っていないね」
![]() 「重要なことですが、そもそも環境影響の管理はできないと思います。騒音や汚水を管理するというのは非常時だけです。
「重要なことですが、そもそも環境影響の管理はできないと思います。騒音や汚水を管理するというのは非常時だけです。
通常は騒音を出す機械とか排水処理設備を管理するのではないですかね」
![]() 「なるほど、ということはISO規格の方が進化しているということかな。いや現実を書いているということか?」
「なるほど、ということはISO規格の方が進化しているということかな。いや現実を書いているということか?」
![]() 「私の話が中途半端になりましたが、向うの工場ではここについては、今後大きな見直しをしなければならないかと言っていました。
「私の話が中途半端になりましたが、向うの工場ではここについては、今後大きな見直しをしなければならないかと言っていました。
とはいえ、環境影響ではなく環境側面のリストの作成とか、環境影響を防止することでなく環境側面を管理するような書き方の変化なのか、あるいはもっと違ったことなのかは分からないとのことです。
そういうことになると、BS規格で認証経験があると言っても、このあたりはそのままスライドとはいきませんね」
![]() 「皆さん一旦休憩しましょう」
「皆さん一旦休憩しましょう」
金子氏の報告が終わった後、20分ほど山口がハワード氏と話をした件を報告する。
規格の意図は英語話者には素直に理解できても、そうでない人、特に翻訳を見て考えては正しい規格解釈はできないだろうこと。
ISO14001はISO9001よりも漠然としているから、意図を理解して読む必要があること。あまり規格から外れたり拡大解釈をしたりしてはいけない、書いてないことまで行間を読まないこと。
但し、日系の認証機関ではISO9001の審査でそうだったように、ISO14001でも拡大解釈するかもしれないと言っていた。
法規制の調査や環境側面の決定などは、規格をしっかり読んで進めないとならないこと。評価や決定方法にはしっかり理屈を考えること。
そのようなことを言われた。
宣伝ではないが、B○○社は吉宗機械がISO認証を依頼している認証機関4社の中でも規格の理解はまっとうだと考えていること。
規格解釈で疑問があれば認証機関に問い合わせることが良いが、規格を理解していない審査員もいるから注意がいる。
そんなことを説明した
・
・
・
山口の説明が終わると、だくさん質問された。
![]() 「和訳を読んでも分からないとあったが、どういうところか?」
「和訳を読んでも分からないとあったが、どういうところか?」
![]() 「例えば目的や目標の違いは我々にとって馴染みがありません。ISO関係者の話を漏れ聞くと、目的は長期で目標は短期というが、そうなのでしょうか?」
「例えば目的や目標の違いは我々にとって馴染みがありません。ISO関係者の話を漏れ聞くと、目的は長期で目標は短期というが、そうなのでしょうか?」
![]() 「原文の単語を英英辞典で引くとか、インターネットでどんなふうに使われているかを見て考えたほうが良い。
「原文の単語を英英辞典で引くとか、インターネットでどんなふうに使われているかを見て考えたほうが良い。
『目的(objective)』とは到達点だろう。『目標(target)』は、途中の目標だね」
![]() 「小林さんのおっしゃる通りです。ですが実際の審査では、目的は何年以上だ目標は年度だとか言い出す審査員は必ず出ます」
「小林さんのおっしゃる通りです。ですが実際の審査では、目的は何年以上だ目標は年度だとか言い出す審査員は必ず出ます」
![]() 「そういう可能性はあるだろうね」
「そういう可能性はあるだろうね」
![]() 「教育訓練という項番がありますが『training』を教育訓練と訳しているところと、『education and training』を教育訓練と訳しているところがある。和訳だけでは騙されてしまう」
「教育訓練という項番がありますが『training』を教育訓練と訳しているところと、『education and training』を教育訓練と訳しているところがある。和訳だけでは騙されてしまう」
個人的意見であるが、JIS訳は全体的に
徹底的に逐語訳にすべきだろうし、意訳するなら和文を信頼できるレベルにしなければならない。
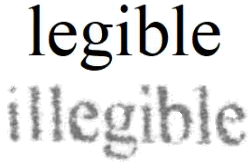
度々書いているが「legible」を「読みやすく」は誤解されやすい、というかひんぱんに誤解されている。「文字は明瞭であること」と誤解されないように訳すべきだ。
審査で「分かりにくい文章だからlegibleでありません」と不適合を出されたこと数えきれず。
本当に分かりにくいなら、文書のレビューを問題にしろ!
質問は尽きることはなかった。それは皆が真剣だということと、分からないことばかりということだ。
会社に戻ってから佐川と山口が話す。
![]() 「佐川さんが経験したおかしな規格解釈を、まとめてもらえますか?
「佐川さんが経験したおかしな規格解釈を、まとめてもらえますか?
その検討をして対策案を立てて置きましょう」
![]() 「それもなあ〜」
「それもなあ〜」
![]() 「佐川さんが乗り気でないのは何でしょう?」
「佐川さんが乗り気でないのは何でしょう?」
![]() 「つまらないことを考えても無駄かなって。
「つまらないことを考えても無駄かなって。
とはいえ、つまらないことを考える認証機関は絶えないだろうね。来週にでも思い出してまとめておきましょう。
未来の知識を持っていれば、何でもできるように思うかもしれないけど、現実はそう簡単ではないね。悪い方に進むと知っていて自分に変える力がなければ、先が見えているからこそ無力感、虚無感に囚われる」
![]() 「どうして実行できないのですか?」
「どうして実行できないのですか?」
![]() 「状況として個人的なことと、企業なり社会に及ぼすことは種類が違うけれど、結局は同じだな。
「状況として個人的なことと、企業なり社会に及ぼすことは種類が違うけれど、結局は同じだな。
まず実行する力が必要だ。吉井部長は説明して納得してもらえれば、正しい決定をしてもらえるが、尾関副工場長は審査員の間違えを私が説明しても、それを無視して審査員の言いなりになっていた。ああいう対応では審査員を付けあがらせてしまうし、当社の損失になるだけだ。
大きなことでは、政治的とか経済的な問題を解決する案があっても、我々には何もできないよ。
それからお金がないと何もできない。これは簡単明瞭だ。あなたがお金儲けをしたいなら元手がないと。競馬だって万馬券を1000円買っても10万円にしかならない
大金が欲しければ大金がないとどうしようもない。
それと未来の情報が役立つときに存在しなければならない。ナンバーズの当選番号を知っていても、買えるとき買えるところにいなければならない」
![]() 「でも佐川さんが田舎の工場の担当者であった前回と、本社にいて名刺だけでも課長が付いている今では、できることは大違いですよ。
「でも佐川さんが田舎の工場の担当者であった前回と、本社にいて名刺だけでも課長が付いている今では、できることは大違いですよ。
例えば、佐川さんから聞いて、私はドル高を期待して2万ドル買いましたよ」
![]() 「へえ!両替の限度はなかった?」
「へえ!両替の限度はなかった?」
![]() 「トラベラーズチェックです」
「トラベラーズチェックです」
![]() 「そうか、トラベラーズチェックもあったか。ただ持っていても利子がつかないな」
「そうか、トラベラーズチェックもあったか。ただ持っていても利子がつかないな」
注:トラベラーズチェックは2014年に発行が終了したそうだ。安全かもしれないけど使うのはめんどくさかった。クレジットカード万歳。
![]() 本日の心情
本日の心情
少し前に「未来は変えられるか」というタイトルで書きました。その後、いろいろ考えました。自分が過去に戻って仕事を過去にした以上にできるのか、良い成果を上げられるかとなると、なかなか難しいと思います。
 |
 |
しかし「為せば成る」は論理学では偽ですが、「やらねば出来ぬ」は真です。
ハードルが高くてもチャレンジしなければならない。学び続けなければならないと、佐川さんに再認識してもらったということです。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
バタフライ効果とは小さな出来事が将来大きな変化につながることを意味する言葉。 時と場合によって言い回しにバリエーションが多く、「ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こす」とか、有名なのは「北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起きる」略して「北京のチョウ」と言われる。 | |
| 注2 |
出典 「環境管理・監査システム」日本規格協会編、日本規格協会発行、1994 | |
| 注3 |
馬券(勝馬投票券)の配当は100円当たりで示す。万馬券とは勝馬投票券100円につき配当が1万円になること。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |