注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
佐川は山口に、過去に規格解釈で認証機関ともめたのに、どんなことがあったのかまとめて欲しいと言われた(第59話)。
記憶を手繰り、審査員の判定に疑義があり認証機関と交渉した、いろいろを思い出す。
その原因の中でトップだと思うのは、読解力不足だと思う。文章を虚心坦懐に読まず、拡大解釈、取違い、勘違い、思い込み、そういうことが多い。彼らは一旦発言すると訂正はまずしない。名誉がかかっているのだろう。
文章の理解で一致せず妥協もならず、不適合とされたことは多々ある。
難しいことではなく、日本語の文章が読めない超初歩的なことだ。
いろいろなことが思い浮かび、多種多様であったように思えたが、起きた問題を整理すると、種類はそう多くなく、グルーピングすると10種類はない。
もちろんその解釈が審査員個人に起因するものもあるだろうし、認証機関の統一見解なるもので強制されているものもあるだろう。認証機関の統一見解がおかしければ、その原因は認証機関で規格解釈についてリーダーシップをとる人間のせいだろう。
またJIS和訳が英語原文の意味を、正しく伝えているのかという疑問もある。
真っ先に頭に浮かんだのは、文章を正しく読んでいないのではないかという思いだ。
例えば規格にある文言が、方針やマニュアルにないことを問題にされたことだ。
 たびたび例に挙げるが、環境方針に規格の文言が入っていないことを不適合にされた。不適合1件ではなく、不適合4件である。
たびたび例に挙げるが、環境方針に規格の文言が入っていないことを不適合にされた。不適合1件ではなく、不適合4件である。
具体的には環境方針の項番の規格にある「継続的改善」、「順守する約束」、「枠組み」、「周知」という語句が環境方針の中に入っていないという理由だった。
笑ってしまうといいたが、その時は頭に血が上った。審査員を怒鳴らなかった私を褒めてほしい
規格要求は「継続的改善をすると書け」ではない。「(方針が)継続的改善の約束をすること」である。それを満たすには方針に「継続的改善をすることを約束します」と書くことではなかろう。そもそも継続的改善とはパフォーマンスを改善することではなく、パフォーマンスを向上するために繰り返し行われる活動である。
いかなる活動をするのかは企業によって異なる。「継続的改善をします」と書いても意味がないと思う。
それに方針の語句が問題だったとして、方針というひとつの項番にある全く同じ状態のものを別々にカウントして、不適合を4件出すものだろうか? それだけを見ても審査員の力量がないとしか言えない。
不適合とはなんだろうか?
規格要求や組織が決めたことに適合しないことだ。そのとき不適合とするのはルールや基準に反している個々の事物なのか、ルールや基準に反している状況なのか?
逸脱した事物を不適合にするなら、不具合の事物を4個見つけたら4件の不適合だろう。そうでなく逸脱した状況を不適合にするなら、4件の証拠で1件の不適合を立証するだろう。
不適合とするには単に異常な事物でなく、受けた側が是正しやすい形で問題を整理して提示すべきだ。
ビギナーの審査員なら「○○工場の温度記録が漏れていた」、「○○事務所の温度記録が漏れていた」と、それぞれを別個の不適合とするかもしれない。
だが考えてみると記載漏れが複数カ所で発生しているなら、個々の状況でなくその問題は何かを考えるだろう。そして不適合の指摘も考える。そもそもルールはどうなのか、それは教育がされてないのか、認識が徹底していないのか、過去の記録を見て過去からか/あるときからか・ランダムか/規則性があるのか、そういう情報収集によって不適合のカテゴリーが変わるだろうし、そもそも認証機関が売りにしている審査の成果/効果は大きく変わる。
普通に考えて環境方針に規格の語句がないことは不適合ではない(注1)。
しかし仮に規格の語句が環境方針にないことが不適合だとして、不適合は4件ではなく、「方針の要求事項を満たしていない」という不適合にして、その証拠として4件を記載するのがまっとうだ。
本来ならそういう基本的なことは審査員研修で習うはずだ。だが環境方針で4件の不適合を出した審査員は、審査員研修の講師をしていた。この審査員を雇っていた研修機関&認証機関は大丈夫か?
あの審査員は1997年から引退するまで10年以上、ISO規格と異なる脳内の基準で審査員を教え自らも審査をしていたのだ、恐ろしいことだ
なおここでは問題にならなかったが、方針(1996年版)の e)とf)については、元々方針に記載する要求ではない
e)は「文書化され従業員に周知すること」
f)は「一般の人が入手できること」
ではマニュアルはどうだろうか?
ISO規格の「4.4.1体制及び責任」で「役割、責任及び権限を定め、文書化し、かつ伝達する」とある。
| 🦜 |
人によっては、マニュアル審査で組織(審査を受ける機関)の規格適合性が判断できないとだめだから、マニュアルには規格要求の語句を全部包含しなければならないと語るかもしれない。
残念ながら、それは大きな勘違いである。
理由は簡単だ。1996年版から2015年版に至るまで、環境マニュアル作成の要求はない。じゃあ、なぜマニュアルを作っているのかとなると、認証機関が環境マニュアル(別名のところもあるが)作成を要求していたからだ。
これは過去形ではない。2025年の現在でも多くの認証機関は環境マニュアル(イクイバレント)を要求している。していないところもある。
私がなぜ知っているか?
認証機関のウェブサイトに、認証を受ける際の提出資料が提示されているよ。
そして認証機関の環境マニュアルへの要求内容は、大体次のようなことだ。
| 組織の範囲(地理的、組織的、業務的)を明記すること、規格要求と関連手順書とのつながりが分かるように記述したもの。 次のものを記載もしくは添付すること。 環境方針 著しい環境側面の一覧表 関係する法規制一覧表 |
|
多くの人は審査員のために、要求以上のサービスを尽くしてるのだ。
ISO規格にないことを認証機関が要求することは、二者間の契約とみなせるからおかしくない。
だがそれは契約書に書かれたことのみが有効であり、契約書に書いてないことを要求することは契約違反である。契約違反というのは、審査契約の中でISO14001:2015で審査しますと書いてあるのだから、規格要求と法規制と組織のルール以外を根拠に不適合は出せないということだ
新たな疑問が出てきた。
「経営に寄与する審査」とか「改善につながる審査」とは何だろうか?
私は未だかって、「当認証機関はISOMS規格で審査と共に改善提案をします」と書いてある審査契約書を見たことがない。
もっともそんなことを書いたら、即座に認定停止を食らうだろう
上記したことを理解できないかもしれない。
契約書に書かれた「規格要求と関連手順書とのつながりが分かるように記述したもの」を満たすマニュアルを、企業はどういうふうに書けばよいのか?
例を挙げよう。
環境方針についてISO14001:1996では4.1で
「最高経営者は、組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならない」とある。
環境マニュアルは「規格要求と関連手順書とのつながりが分かるように記述する」のであるから、「環境方針の制定、周知、広報については『環境方針規定○○』で定める」で必要十分であると考える。
それでは素っ気ないというなら「環境方針は工場長が定める。その策定、周知、広報については『環境方針規定○○』で定める」くらいだろうか。
なにも「工場長は、当認証組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にする。その手順の詳細は『環境方針規定○○』で定める」と名詞だけ入れ替えて規格の文章を丸々載せることはない。普通はそれだけでなく、やっている仕事の手順の概要を記述している。
方針だけなら文字数はたいしてないが、規格全項目を書くと大変だ。マニュアルが50ページとか60ページになる。
要求されていないことをすることはない。
もしその認証機関が、規格の文章をそのまま載せないと審査員が審査のとき規格を参照するのが手間だというなら、レベルの低い認証機関を使うのを止めるのが吉である。
ご存じと思うが、マニュアルの送付不要という認証機関もある。ついでに言えば、私が現役のときマニュアルなどなくても、二者監査をしていた。
審査員にはマニュアルが何者か理解していない人もいる。
つまらない実例を挙げる。
2010年代の審査でのこと、既に認証して10年経過して、何度も審査を受けていて、マニュアルも規定も書いてあることに不備はないはずだった。
だが審査員の目は鋭く(皮肉だ、目にウロコがついていたのかもしれない)問題を見つけた。
マニュアルの冒頭を読んで問題を二つ挙げた。
ひとつ、「マニュアルは環境に関する最高位の文書である」と記述していないのが問題と言う。
私は「弊社では環境マニュアルは環境管理の最上位の文書でないのはもちろん、強制力のある文書ではありません」と説明した。するとレベルアップしてお怒りモードとなり、そんな文書では意味がないと言う。
環境マニュアルは社内で強制力のある文書でなければならないらしい。
前述したように、そもそも環境マニュアルは、ISO規格で要求されている文書ではない。認証機関が、審査員の効率的運用(楽するため)にマニュアル(要するに解説書だ)を作ってほしいという要求を受けて、面倒くさいと思いつつ企業側が作成しているものに過ぎない。
それを「社内で強制力のあるものでなければいけない」とは、盗人猛々しい。
そんな勘違いに対応できませんよ。じっくりと説明しました。だけどその審査員は理解できないのですよ。
要するに実際に文書作成とか文書管理をしたことがない人は、文書体系なるものを、体で理解していないのです。
文書とはすべて最上位の文書を基に制定されます。当然、上位の文書で「これを別途定める」とあるわけで、それを受けて下位文書は「○○に基づきこの文書を定める」と親子関係が明確です。
法律を読むと分かりますが、細かいことは「政令で定める」、「環境省令で定める」、「条例で定める」と振っているのを見たことがあるでしょう。そうなると私たちは下位文書を探して詳細を調べるわけです。
下位文書(施行令など)では、それを受けて、「法第〇条第〇項の政令で定める○○は次のとおりとする」とつながるわけです。
施行令のとき「法第〇条第〇項の政令で定める」と書くだけで「○○法」とは書きません。なぜなら「○○法」と「○○法施行令」は親一人子一人ですから、わざわざ「○○法第〇条第〇項」と書かなくてもどの法律か考えることはありません。
法律を基にした条例の場合、トップに「地方自治法第○○条〇項の規定に基づき」とかになります。
そうでなければ「○○市○○条例に基づき」となります。
この文書の親子関係を示すファミリーツリーの流れに沿っていない法律とか規定は、あってはならないことです。
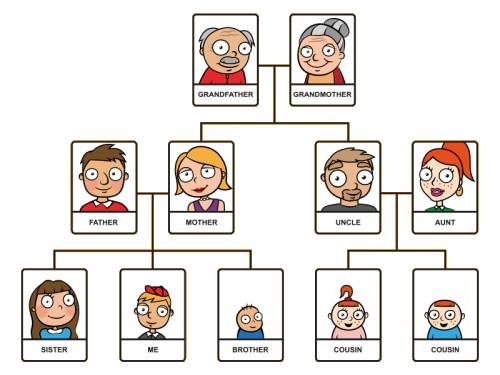 但し法律でも条令でもトップレベルの基本法などは親がありません。強いて言えば上位文書は憲法でしょうか?
但し法律でも条令でもトップレベルの基本法などは親がありません。強いて言えば上位文書は憲法でしょうか?
ファミリーツリーとは系図のこと。祖先から子孫へのつながりを書いたもの。
我が家は爺さんの代までしか分からないから、系図を書くまでもない。
注:ここで文書とは報告書とか記録ではなく、「決裁を受けて発行され、発行管理され、バージョン管理される、強制力のある文書」のことで、法律とか会社の規定などのことです。
記録や報告書の他、文書と内容が同一であっても参考用など発行管理されないものは文書でありません。
さて、そう言った基礎知識を再確認して、環境マニュアルは最上位の文書なのでしょうか? 環境マニュアルの記述を受けて、制定された文書は存在していますか?
会社の最上位の文書とは定款ですかね? まあ定款は別扱いとして、およそ、まっとうな会社なら、しっかりした文書体系を定めているはずです。
なぜ、そう言えるか?
好き嫌いではなく、必然的にそうなってしまうのです。
私は現場上がりの人間です。新しい機械が導入されると、それを預けられて使うわけです。メーカーから取説はもらいますよ。でも取説では仕事はできません。保守点検のパートは現場の人には無用ですし、段取りのノウハウなどは取説に書いてありません。

となると機械を使っている私が、日常作業に使う作業要領書とか操作マニュアルと呼ばれるものを書くわけです。それは文書なのでしょうか?
もちろん会社の正式な文書です。最初に使った人が試行錯誤で編み出した使い方を、永続的な共有財産とするためには、会社の文書体系の中に織り込まなければなりません。そうしないと、父なし子になってしまいます。
もっと簡単なことを例にとりましょう。「ここに物を置いてはいけない」と決めたとしましょう。
朝礼で皆に伝えてもその場限り、管理者なり現場の人が代わったら、すぐにルールは忘れられます。
たとえ壁に貼り紙あるいは看板をつけておいても、それはいかなる効果を持つでしょうか?
|
この場所に物を 置くこと禁止 |
看板は誰が書いたのか? 既にいない管理者のハンコなら無効です。なぜなら命令した人は責任を負わねばなりません。今ここの管理者でなく、責任を取れない人の指示に従ってはいけません。従わなくても良いのではなく、従ってはいけないのです。就業規則違反になりますよ。
じゃあ、どうしたら良いのか?
いかなる決まりでも恒久的に残すなら、工場のルールとか課のルールにしなければならない。工場全体に関わるなら工場のルール、課内なら課のルールです。課のルールなら、他の課の人が従う義務がありません。
つまりルールに定めてある通りに書式通りに書いて、採番して、決裁を受けて、バージョンを付けて、コピー配布する。今どきならイントラネットにアップする方法もあります。
そんな大げさなとか面倒くさいとか言ってはいけない。それがマネジメントシステムというものです。
対して見学者に、工場の機械を説明する資料を書いて配付したとしましょう。それが正確で細かいノウハウが書いてあろうと、それをバージョン管理しますか? それを使って仕事をしますか? 内容を変更したら過去に配布した人に差し替えを求めますか?
何年か前に工場見学に来た人に、そんなことできますか?
認証機関に提出する環境マニュアルは、文書なのでしょうか?
なもの、管理なんてしませんよ。
もしマニュアルを文書として管理するとするなら、マニュアルで引用している数多くの規定が改定されるたびに、それを環境マニュアルに反映して改定し、認証機関に差し替えと旧版の回収を求めるのですか?
認証機関はそんなことに対応しません。
私の体験ですが、1993年頃ISO9001の認証を受けたとき、イギリスの認証機関に提出した品質マニュアルを管理文書としていました。
というのは当時のイギリスの認証機関から送られてきた資料に、マニュアルを改定したときは認証機関に最新版を送ることと書いてあったのです。
引用している文書の改定があり、マニュアルの記載と引用文書の番号とタイトルが変わりました。それでイギリスに「御社に提出したマニュアルに改定が発生し、差し替えたいのだがどうしたら良いか?」と問い合わせしました。
私にとっては、そんな英文レターを書くのも大仕事でした。当時は翻訳ソフトなんてなかったしね、
返事が来ました。「気にするな、次回の審査のとき事前に配布してくれたらよろしい」
その後すぐにそのルールはなくしたと連絡を受けました。正直言って認証機関も、受領したマニュアルの管理などできなかったのでしょう。
その後、日本の認証機関からISO14001の認証を受けたときも同様なことが発生し、問い合わせました。そこもまた改定の送付は不要と回答がありました。
前述した事件の審査員はその認証機関ですが、マニュアルを文書管理しなければいけないとおっしゃったのでありますが……周知徹底とは困難なことである証左でありましょうか?
あっ、認証機関が周知徹底できないということですヨ
マニュアルの話に戻ります。
申し上げたようにマニュアルは社内の最上位の文書でもなく、認証機関でも最適版を維持していないものであることがお分かりになったでしょう。
審査員はそういうことを理解していないのでしょうか?
理解していないようです。
その審査員は逆に質問してきました。
「マニュアルに工場長のサインがある。それは文書であるから決裁した証ではないのか?」
冗談言わないでよ。会社から社外に提出する資料なら、担当者である私が提出したのではなく、会社が責任をもって提出したと保証する裏書でしょう。
見積書だって、注文書だって、皆、責任者の押印があるじゃないですか。
見積書も注文書も文書じゃないよね?
更に言われたのは、環境マニュアルを従業員に読ませないといけない、だから環境マニュアルのトップに「これは当社の環境マネジメントシステムに関する教育資料である」と記載せよと言うのです。
もうね、呆れて物も言えません。
だって認証機関が要求したことは、環境マニュアルは、ISO規格要求と会社の規定のつながりを示すものですよ。当然、会社の規定は別にあるわけです。
まして審査契約に「マニュアルを従業員に読ませること」などと書いてありません。
従業員は、幹部も含めて、会社の規定を理解して、それに基づいて仕事をしてくれればよいので、余計なマニュアルなど知る必要はありません。ISO規格と会社の規定の関連を知るのは、お金をもらって審査する審査員だけで良いのです。
そして私の本音を言えば、マニュアルがなくても審査できなくちゃ一人前の審査員じゃありませんよ、
コンサルとか企業経営者の中にもおかしな人がいる。マニュアルに仕事の手順すべてを書き込んでしまえば、会社の規定は要らないという。
どうしてそういう発想が起きるのか理解できない。
元々、品質保証では顧客から顧客対応の要求があり、それに対して当社はお客様の要求はこのように満たしていますと説明するために、要求事項に該当する会社の規定を要約して顧客に渡すものがマニュアルである。
なぜ会社の規定をそのまま出さないかというと、コンフィデンシャルだからだ。そしてまた顧客要求以外のたくさんの情報が網羅されている。例えば、お金のこと、ノウハウ、ノウホワイが盛りだくさんだ。
ISO14001審査も同様で、審査員に必要以上の情報を与えることは企業の損失である。
マニュアル書いてないこと、例えばお金の処理、不良が出ればその品物は手直しするにも廃棄するにも材料は余分に必要になるだろうし捨てるのも発生する、修理する手間も発生する、その処理をどうするのか、そういうことはマニュアルに書いてない。マニュアルでは仕事にならないのだ。そしてそういう情報を社外流出させたくない。
また、実際問題として企業の手順は過去から存在しており、それを捨て去ってISO規格に合わせて新しく作り直す意味はない。
それに、いつなんどきISO規格など消滅するかもしれないのだ。
まっ、ISO認証制度が消えるというのは乱暴かもしれない。だが顧客によって異なる要求事項があり、御社には品質マニュアルか環境マニュアルが複数あるとする。当然その中は異なるわけだ。
さあ! お宅ではどちらのマニュアルを社内の仕事で使うのだろう?
そんなことはあり得ないなんて言ってはいけない。
品質保証をしている人なら、よくあることだ。
佐川はいろいろなことを思い返すと、研究会のメンバーにそういった審査での問題を伝えることができるか、伝わるかが非常に疑問になってくる。
これから起きる問題と理解するには、佐川と同じ体験をしなければならない気がする。
佐川は山口と話をする。
![]() 「山口さんは私とだいぶ話をしたから、これから始まるISO審査の状況を理解してくれるだろう。
「山口さんは私とだいぶ話をしたから、これから始まるISO審査の状況を理解してくれるだろう。
だけど、研究会のメンバーに認識させて、それを予防あるいは対応することを考えさせることはできそうにない」
![]() 「私だって佐川さんのおっしゃることを、理屈では分かっても信じられませんね。
「私だって佐川さんのおっしゃることを、理屈では分かっても信じられませんね。
いやしくも審査員になる人は、理を重んじる心の広い人だと思います」
![]() 「そうか……私も山口さんが思うことを否定できないけど……ということは実際に審査が始まり、企業側が負担を負い効果のないISO認証を是とするしかないということか」
「そうか……私も山口さんが思うことを否定できないけど……ということは実際に審査が始まり、企業側が負担を負い効果のないISO認証を是とするしかないということか」
![]() 「佐川さんも前世の経験から疑心暗鬼になっているのではないですか。案外、今世の審査員はまともかもしれませんよ。
「佐川さんも前世の経験から疑心暗鬼になっているのではないですか。案外、今世の審査員はまともかもしれませんよ。
できることなら認証機関との話し合いとかできませんか。
そして向こうがまっとうな考えであればそれでよし、佐川さんの前世と同じであれば、理論武装して戦うという流れでどうでしょう?
研究会のメンバーも、向うの話次第では問題に気づくでしょうし、問題なければ更に良し」
![]() 「なるほど、それはアイデアですね。
「なるほど、それはアイデアですね。
認証機関との話し合いを持つには、どうしたら良いだろう?」
![]() 「幹事の吉本さんに段取りをしてもらいましょう。
「幹事の吉本さんに段取りをしてもらいましょう。
彼女は何も仕事しないで、私たちを彼女の考えている方向に誘導しようとしているだけですもん」
![]() 本日の疑念
本日の疑念
私がISO規格を愛している反面、認証制度に強い不信感を持っていることが理解できないかもしれない。
まあ、世に愛憎半ばすることは、良くあることです(笑)。
誰もが自分の仕事をしっかりやろうと思うはずです。でもさまざまな外乱や変化する状況によって、やる気をなくすのも世の常。
品質保証に携わっていて、ISO9001が登場して品質保証の標準化が成ると思い素晴らしいと思いました。数年経たずしてがっかりしました。実際の運用つまり審査は二者間監査と違い真剣みのない形式だったからです。
ISO14001になると、もうカオスです。審査員によって考えることが違い、審査基準が違います。これ言葉の遊びでなく本当のことです。
以前問題を提示しましたが、認証機関によって、適合・不適合が反対というのも珍しくなかったのです
ましてや有益な環境側面となると腹を抱えて笑うしかありません。おっと、その場にいたときは、笑うどころか怒り心頭でした。
暴れん坊将軍ではありませんが叩き切ってやると叫びたい。
レベルの低い審査で、一番迷惑を受けたのは私を含めた企業の担当者でしょう。
挙句の果ては、ISO認証の信頼性が落ちたのは企業がウソをついたからだと。良くもぬけぬけとそんな法螺を騙ったものだ。
私はそれを追求し断罪したい。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
・ISO14001:2015 A.2参照 | |
| 注2 |
方針を従業員に周知することや外部の人にも提示すると方針に書くことは、方針の役目ではない。 ISO規格では「方針について次の事項を確実にしなければならないとあるから、確実にする(define)とは文書化であることは自明だろう。 方針を策定しどのように運用するかを定めた文書の中に「方針を作ること、周知すること、外部に提供すること」は、方針の文中でなく、その方針の管理を決めた規定で定めることになる。 ・ISO14001:1996 4.1 ・ISO14001:2004 4.2 ・ISO14001:2015 5.2 | |
| 注3 |
契約は必ずしも書面を必要とせずに成立するが、証拠となる契約書がないと裁判で争うことができない。 | |
| 注4 |
ISO17021-1:2015 5.2.5参照 | |
| 注5 |
「認証機関勝手格付け」 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |