注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1995年の東京の夏は暑かったが、9月中旬になると、最高気温は30℃どころか25℃前後で推移している。
![]() ちなみに1995年9月には30℃以上が6日しかない。2024年には19日であった。年々暑くなっているのは間違いない……と続くと思うだろうが、現実はそう単純ではない。
ちなみに1995年9月には30℃以上が6日しかない。2024年には19日であった。年々暑くなっているのは間違いない……と続くと思うだろうが、現実はそう単純ではない。
気象というものは日々で異なり暑い寒いは連続的なものではなく、ランダムというか変動が大きい。
それに東京の気温測定位置は2014年に移動した。それで東京の気温と言っても、2013年までと2014年以降では連続性がなく比較できない。
1995年9月の気温と測定点が移動前最終年の2013年の最高気温を比較すると、1995年が20.1℃、2013年が21℃であった。じゃあ、1℃近く温暖化しているねとなりそうだが、2012年の最高気温は20.0℃、2011年は20.3℃であった
1995年とほとんど変わっていない。
こうなると気候変動なるものは、体感とか単年度あるいは短期間の気温を比較しても意味がないと分かる。長期の気候変動を調べている学者が語ることを、信用するしかないのが現実だ。
とりあえずとしては、我々は自分の感じとか記憶で、暑くなったとか寒くなっていると語るのを控えるべきだろう。
注:私は何でも興味を持つと、本当なのか事実なのかを調べる。よほどのもの……犯罪に関わることなど……以外はネットに情報が載っている。
 官公庁が行っている各種統計は精粗はあってもネットにある。人口、経済や国力に関するものは総務省統計局のウェブサイトに公開されている。
官公庁が行っている各種統計は精粗はあってもネットにある。人口、経済や国力に関するものは総務省統計局のウェブサイトに公開されている。
だから、レタスの値が上がったとテレビが言えばすぐに調べる。犯罪が増えたと言えばすぐに調べる。ゴホン!といえば龍角散、暑いと言えば気象庁だ。
はっきり言って、テレビ報道の半分はデマゴーグである。
環境ISO研究会は設立から5カ月目に入った。メンバーは皆、真面目に集まり、DISの読み合わせと要求事項の検討を行ってきた。環境ISO認証を必達せよ・他社に負けるなという圧力は、どの会社でも強かった。
DISの要求事項の4章は、英語原文は1,600単語、和訳でも4,322字、文章の数を数えれば62文しかない
おっと、言いたいことは、ISO14001規格はボリュームが小さいのである。その読解をしようと毎回、時間をかけ数個の文章しか検討できなくても、4か月も議論すればおしまいだ。
これ以上、真理を究めようとしても、このメンバーでは堂々巡りだ。
次なるは、権威者にその解釈で良いのかどうか確認して、要求事項を満たす方法を考える段階に進むことになる。
さて、どうしたものか?
![]() 「これ以上、我々だけで議論しても意味がありませんね。今まで議論した結果が正しいのか、議論しても分からなかいことは専門家に聞くしかないと思う。
「これ以上、我々だけで議論しても意味がありませんね。今まで議論した結果が正しいのか、議論しても分からなかいことは専門家に聞くしかないと思う。
皆さんはどうお考えでしょうか?」
![]() 「同意で〜す。別の業界でも検討会とか研究会をしていると思うので、お互いに共同して考えるというのも、ありかなと思います。
「同意で〜す。別の業界でも検討会とか研究会をしていると思うので、お互いに共同して考えるというのも、ありかなと思います。
幹事の吉本さんから、他業界に声をかけてもらえませんか?」
![]() 「この業界に加盟されている会社さんは、業界設立である産業環境認証機関に審査を依頼することになるでしょう。ですから、他業種の声を聴いてもあまり参考にならないと思います。審査するところの見解を聞くのが一番かと思います」
「この業界に加盟されている会社さんは、業界設立である産業環境認証機関に審査を依頼することになるでしょう。ですから、他業種の声を聴いてもあまり参考にならないと思います。審査するところの見解を聞くのが一番かと思います」
![]() 「ちょっと吉本さん、業界傘下の企業といえど、そこに頼まなければならないこともありませんよ」
「ちょっと吉本さん、業界傘下の企業といえど、そこに頼まなければならないこともありませんよ」
![]() 「そういう発言は困りますよ。業界団体としてではありませんが、業界各社の出資で作った認証機関ですから、基本はそこに依頼するでしょ」
「そういう発言は困りますよ。業界団体としてではありませんが、業界各社の出資で作った認証機関ですから、基本はそこに依頼するでしょ」
![]() 「吉本さんの立場では、そうかもしれません。しかしこういうところで、はっきり言っては困りますよ。
「吉本さんの立場では、そうかもしれません。しかしこういうところで、はっきり言っては困りますよ。
というのは当社の事業は多岐にわたっており、別の業界団体にも加盟していまして、そちらで設立した認証機関にも出資をしています。当然、出向者も両方に出しますし、認証も両方に頼まざるを得ない。この顔ぶれを見ますと、そういう会社は、私のところばかりでなさそうです」
![]() 「そこは、まあ、そこらへんはよろしくお願いします。
「そこは、まあ、そこらへんはよろしくお願いします。
とりあえずこの業界団体のISO研究会ですから、業界設立の認証機関の見解を聞くということで進めたいです」
![]() 「細かいことは、いいじゃないか。吉本さんが話を付けてくれますか?」
「細かいことは、いいじゃないか。吉本さんが話を付けてくれますか?」
![]() 「それができれば大変ありがたいです。ただこれから審査対応の方法とか具体的な良否の判断を確認したいわけで、一般論とか当たり障りのないことでは意味がないです。
「それができれば大変ありがたいです。ただこれから審査対応の方法とか具体的な良否の判断を確認したいわけで、一般論とか当たり障りのないことでは意味がないです。
認証機関としての見解をお聞きしたい。ぜひ責任ある方のご出席をお願いしたいですね」
![]() 「もちろんです。もう皆さんだけでは進展がないなら、なるべく早く開催できるようにお話してみましょう。交渉次第ですが、すぐには無理かもしれません。
「もちろんです。もう皆さんだけでは進展がないなら、なるべく早く開催できるようにお話してみましょう。交渉次第ですが、すぐには無理かもしれません。
規格解釈となりますと、審査員ではなく認証機関の技術部長の出席をお願いしたいですね」
技術部長といっても、認証機関に設計開発部門があるわけではない。認証機関の技術部とは規格解釈とか規格改定対応を考える部門である。
認証機関にはその他に、営業部長、審査員を束ねる審査部長、事務部門の業務部長がいるのは一般的だった。
2010年頃から、認定審査対応の責任者を置くようになったはず。
佐川と山口は顔を見合わせた。認証機関と話す場は、二人が希望していたことであるが、意外にも簡単に実現しそうだ。
それからはどんな質問をするべきかという議論に移る。
吉本 |  須藤 須藤 | |||
| 金子 |  佐川 佐川 |
|||
| 田中 |  山口 山口 |
|||
| 高橋 |  鈴木 鈴木 |
|||
| 小林 | ||||
![]() 「あまり時間がとれないだろうから、こちらから質問することを、まとめておいたほうが良いんじゃないかな」
「あまり時間がとれないだろうから、こちらから質問することを、まとめておいたほうが良いんじゃないかな」
![]() 「皆さん会社を代表してここに参加されているわけで、会社によって状況も違います。
「皆さん会社を代表してここに参加されているわけで、会社によって状況も違います。
ですから全体をまとめることは必要ないでしょう。それぞれが聞きたいことをまとめてきて、質問するのがよろしいかと」
![]() 「そうですね。切り口がそれぞれ違うと思います。私は公害関係についての審査を知りたいね」
「そうですね。切り口がそれぞれ違うと思います。私は公害関係についての審査を知りたいね」
![]() 「公害関係とかってISO規格と関係ありますか?」
「公害関係とかってISO規格と関係ありますか?」
![]() 「審査で公害関係を細かく調べるなら、それなりの現場の人に対応してもらわなければならない。どういう審査をするのか知っておかないとね。現場の作業者までとなると、審査を受けるのが大変だな」
「審査で公害関係を細かく調べるなら、それなりの現場の人に対応してもらわなければならない。どういう審査をするのか知っておかないとね。現場の作業者までとなると、審査を受けるのが大変だな」
![]() 「それは私も気にしていた。廃棄物なんて細かく審査するなら、構内で仕事している外注業者にも出てもらう必要があるかもしれない」
「それは私も気にしていた。廃棄物なんて細かく審査するなら、構内で仕事している外注業者にも出てもらう必要があるかもしれない」
注:私は既にISO9001は数件認証していたが、ISO14001審査が始まるときは、分からないことが多々あった。というのはISO9001は品質だけしかない。
しかし環境は法規制も関り、省エネとか排水処理など技術的なことも関わる。実際の審査では専門家がそういうことについて技術的なこと、法規制などを根掘り葉掘り監査するものと思っていた。その詳しさとか現場でどのように審査するのか、全く想像つかなかった。
実際に始まってみれば、専門家でない人が書類を眺めるだけだった。
BOD測定になぜ5日もかかるんだ! もっと早くしろなんて語る人が、専門家であるはずがない。
![]() 「まあ、その辺も聞けばよろしいでしょう。やはり皆さんが聞きたいことを聞く、それでよろしいでしょう。
「まあ、その辺も聞けばよろしいでしょう。やはり皆さんが聞きたいことを聞く、それでよろしいでしょう。
どうですか金子さん」
![]() 「ええと、吉本さん、質問が細かいことまで至るなら、相当時間がかかると思います。先方に時間を取ってもらえるものでしょうか?」
「ええと、吉本さん、質問が細かいことまで至るなら、相当時間がかかると思います。先方に時間を取ってもらえるものでしょうか?」
![]() 「私たちはお金を払う客です。客が聞きたいなら、売り手はお客様に対応するのが普通でしょ。まして工場を10カ所認証してもらうとすると、取引額が何千万のお客様ですよ」
「私たちはお金を払う客です。客が聞きたいなら、売り手はお客様に対応するのが普通でしょ。まして工場を10カ所認証してもらうとすると、取引額が何千万のお客様ですよ」
![]() 「私もそう思います。正直言って複数の認証機関の話を聞いて、良いと思えるところに依頼したいですね」
「私もそう思います。正直言って複数の認証機関の話を聞いて、良いと思えるところに依頼したいですね」
![]() 「鈴木さん、同感です。ところでお願いですが、もし産業環境との話し合いで疑義があれば、同じことをお宅が出資している別の認証機関に質問してもらえますか?」
「鈴木さん、同感です。ところでお願いですが、もし産業環境との話し合いで疑義があれば、同じことをお宅が出資している別の認証機関に質問してもらえますか?」
![]() 「おお、もちろんです。私もそう考えていました」
「おお、もちろんです。私もそう考えていました」
![]() 「へえ〜、認証機関によって規格解釈が違うこともあるのですか?」
「へえ〜、認証機関によって規格解釈が違うこともあるのですか?」
![]() 「大ありですよ。特に日系の認証機関はバラツキがありますね。英国の認証機関はバラツキがないようです」
「大ありですよ。特に日系の認証機関はバラツキがありますね。英国の認証機関はバラツキがないようです」
![]() 「ウチの工場がISO9001の審査で審査員からおかしいこと言われて、他の工場を認証している外資系認証機関に、その真偽をお聞きしたことがありました(第40話)。認証機関によって規格の解釈はだいぶ違いますね。
「ウチの工場がISO9001の審査で審査員からおかしいこと言われて、他の工場を認証している外資系認証機関に、その真偽をお聞きしたことがありました(第40話)。認証機関によって規格の解釈はだいぶ違いますね。
あっ、正確に言えば間違えている認証機関もあるということです」
![]() 「私の会社がISO9001の審査を受けたときは、
「私の会社がISO9001の審査を受けたときは、
 まだ産業環境認証機関ができる前で、日系大手のJ○○でした。
まだ産業環境認証機関ができる前で、日系大手のJ○○でした。
そこから来た審査員は『品質方針を知っているか?』とガードマンにも聞いたし、構内で植栽の維持をしていた植木屋にも聞いていましたね」
後で思ったのだが、審査員はガードマンや植木屋を、業者でなく会社の従業員と思ったのかもしれない。それならおかしいということもない。
審査員が元働いていた会社では社員がしていたならば、そう思うことは責められない。
![]() 「ガードマンに質問したとは聞いたけど、植木屋は初耳ですね」
「ガードマンに質問したとは聞いたけど、植木屋は初耳ですね」
![]() 「なんでも教育訓練の項番で『組織のすべての階層によって理解される
「なんでも教育訓練の項番で『組織のすべての階層によって理解される
![]() 「それって拡大解釈じゃないですか」
「それって拡大解釈じゃないですか」
![]() 「誰が聞いてもおかしいですよ。常識で考えてほしい」
「誰が聞いてもおかしいですよ。常識で考えてほしい」
![]() 「審査員相手に常識を説いてもダメですよ。規格でどうかという論法でないと」
「審査員相手に常識を説いてもダメですよ。規格でどうかという論法でないと」
![]() 「そうなのでしょうけど……なかなかできなくて……ここに来るときはいつも、同僚たちから環境ISOでは小難しいことをなくせと言われてまして……肩の荷が重いですよ」
「そうなのでしょうけど……なかなかできなくて……ここに来るときはいつも、同僚たちから環境ISOでは小難しいことをなくせと言われてまして……肩の荷が重いですよ」
![]() 「私の経験は要求が品質に関係するかどうかです。是正処置は根本原因を突き止めろというのは理解します。でも『手直しと修理
「私の経験は要求が品質に関係するかどうかです。是正処置は根本原因を突き止めろというのは理解します。でも『手直しと修理
![]() 「『修理』も『手直し』も英語を訳しただけでしょう。訳された日本語は仮の姿と思えば、どうでも良いように思いますね」
「『修理』も『手直し』も英語を訳しただけでしょう。訳された日本語は仮の姿と思えば、どうでも良いように思いますね」
当時、私が勤めていた工場では、ISOの定義と「手直し」と「修理」の意味が逆だった。社内用語と割り切ればおかしくないと思うが、それを「ダメだ、ISO規格に合わせろ」と言われると変えるしかない。
そのときは、英国系の認証機関から日系の認証機関に切り替えていた。英国の認証機関だったら、問題にしなかったと思う。
![]() 「社内ではそういう言葉を使わないと言ったらどうですか?」
「社内ではそういう言葉を使わないと言ったらどうですか?」
![]() 「それが通じれば良いのですが、審査員には通じませんでした」
「それが通じれば良いのですが、審査員には通じませんでした」
![]() 「そうですか、そういうことありますよね」
「そうですか、そういうことありますよね」
いろいろとメンバーから経験談や悩み事の発言があった。
とりあえずは吉本に交渉を頼み、各メンバーは認証機関への質問を考えてくることが宿題になった。
会社に戻ると、佐川と山口は早速話を始めた。
![]() 「なんか調子よく佐川さんの願望が叶いましたね」
「なんか調子よく佐川さんの願望が叶いましたね」
![]() 「まだ先方の回答待ちだから分からないよ。でもどうなるにしろ質問集を考えておきましょう」
「まだ先方の回答待ちだから分からないよ。でもどうなるにしろ質問集を考えておきましょう」
![]() 「佐川さんは既に問題点というか、認証機関との確認事項を決めていると思います。どんなものがありますか?」
「佐川さんは既に問題点というか、認証機関との確認事項を決めていると思います。どんなものがありますか?」
![]() 「一番は認証機関が、統一見解というものを決めているかどうかだな」
「一番は認証機関が、統一見解というものを決めているかどうかだな」
注:統一見解とは言葉から考えると、認証機関が定めた見解と思える。実際にそれが存在するのかとなると分からない。
アイソス誌が各認証機関に「御社では統一見解を決めていますか?」とアンケートしたことがある。回答はすべて「ない」であった。
私の経験した審査では、複数の認証機関の多くの審査員が「ウチの統一見解では」と語っていたのが事実である。
統一見解を決めるのは勝手だが、それがISO14001の要求事項を超えるなら、事前に公表が必要だ。
そして統一見解を策定するのは認証機関の勝手、それが気に入らなければ認証機関を替えるのは企業の勝手である。
![]()
 「統一見解? なんですか、それ?」
「統一見解? なんですか、それ?」
![]() 「ISO認証の審査のルールは、ISO9001やISO14001では決めていない。ISO9001などは企業がするべきことで、認証機関がするべきことは書いてない。
「ISO認証の審査のルールは、ISO9001やISO14001では決めていない。ISO9001などは企業がするべきことで、認証機関がするべきことは書いてない。
認証機関がするべきことは、ISO14010
それらの規格で認証機関がするべきことを決めている。その中で認証機関が独自に審査基準を追加することは許されている
![]() 「佐川さんの懸念は、認証機関がヤミテンで独自ルールを決めていないかですね?」
「佐川さんの懸念は、認証機関がヤミテンで独自ルールを決めていないかですね?」
![]() 「そうです。彼らはguide 66
「そうです。彼らはguide 66
![]() 「どういうことでしょうか?」
「どういうことでしょうか?」
![]() 「私の経験だが、不適合を出されて我々が規格にないというと、審査員は認証機関の統一見解で決めていると言う。要するに認証機関内で判断基準を決めておいて、審査員はそれに従って判断しているという。
「私の経験だが、不適合を出されて我々が規格にないというと、審査員は認証機関の統一見解で決めていると言う。要するに認証機関内で判断基準を決めておいて、審査員はそれに従って判断しているという。
だけど公表していないから企業側はなぜNGなのか分からない。それってアンフェアだよね。いやルール違反だ
![]() 「具体的には、どんなことを決めていたのですか?」
「具体的には、どんなことを決めていたのですか?」
![]() 「いろいろあったね、『環境目的』という言葉を知っているね?」
「いろいろあったね、『環境目的』という言葉を知っているね?」
![]() 「もちろんです、『計画』の項番でしたね」
「もちろんです、『計画』の項番でしたね」
![]() 「その環境目的は計画時点から完了予定まで、3年以上でないと不適合だという」
「その環境目的は計画時点から完了予定まで、3年以上でないと不適合だという」
![]() 「はっ、意味が分かりませんが?」
「はっ、意味が分かりませんが?」
![]() 「そのままだよ、目的を達成する計画は、3年以上でなければならないのだ」
「そのままだよ、目的を達成する計画は、3年以上でなければならないのだ」
| 目的 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 判 定 |
| 目的A | 活動開始 |
達成期限
|
不適合 | ||
| 目的B | 活動開始 |
達成期限 |
適 合 | ||
注:実際には活動における、様々なプロセスやイベントを盛り込まないとプログラムとは言えない。必要要件はISO14001:1996の4.3.4/ISO14001:2015なら6.2.1参照のこと
![]() 「上図のような環境マネジメントプログラムがあったとして、活動Aは開始から完了まで2年間しかないから不適合とされて、活動Bは3年間なので適合とされたのだ。
「上図のような環境マネジメントプログラムがあったとして、活動Aは開始から完了まで2年間しかないから不適合とされて、活動Bは3年間なので適合とされたのだ。
もちろんISO審査で3年未満の活動をしてはいけないとは言わない。活動期間が3年以上ないと、環境目的とみなさないのだ。
だからISO規格に合格するには、3年以上のスパンがある目的が、いくつかなければならない」
注:当時は考えもしなかったが、民事訴訟を起こしたらどうだったのだろう?
審査契約書では審査基準は「ISO14001の規格と組織自らが決めたルール」である。
ISO規格には目的が3年以上とはないし、他の認証機関では問題ないことである。ならば契約違反は間違いない。
認証機関と企業のやりとりではごまかせるかもしれないが、一旦訴訟となれば「環境目的が3年に足らないから不適合」と書かれた所見報告書を証拠として出したらどうだろう。
今まで誰も思いつかなかったはずはない。どこか提訴した会社はないのか?
![]() 「訳が分かりません。例えば省エネなら活動が終わることなく、永遠に続くでしょう。でも法律対応の施策は、法律が施行されるまでに達成しなければなりませんよね。
「訳が分かりません。例えば省エネなら活動が終わることなく、永遠に続くでしょう。でも法律対応の施策は、法律が施行されるまでに達成しなければなりませんよね。
オゾン層保護のフロン代替えを決めたオゾン層保護法
しかしその統一見解では、規制達成を3年ですから……1991年以降に設定しないと不適合になるのですか?」
![]() 「おかしいと思うのが当たり前だ。でも統一見解でダメと言われたら、こちらが折れるか認証機関を替えるしかない。」
「おかしいと思うのが当たり前だ。でも統一見解でダメと言われたら、こちらが折れるか認証機関を替えるしかない。」
![]() 「3年以内の活動計画は、環境マネジメントプログラムと認められないのですか?」
「3年以内の活動計画は、環境マネジメントプログラムと認められないのですか?」
![]() 「そうだ、活動期間が3年間未満は環境目的とみなさないのだから、3年以上のものを作るしかない。
「そうだ、活動期間が3年間未満は環境目的とみなさないのだから、3年以上のものを作るしかない。
そしてだ、更に大きな問題がある。最初は3年計画であっても、翌年は完了予定まで2年になってしまう。とはいえ完了予定を1年伸ばせば、未達が問題になる。だから翌年は新しい3年以上のものを見繕わなければならない。
バカバカしいと思わないか?」
注:環境目的はいくつ必要かというのも、認証機関によって様々だった。ある認証機関は最低3個といい、別の認証機関は最低5個とか言っていた。
これも統一見解で決めていたのだろうか?
そういうことは審査を依頼する前の打ち合わせ時にはっきりと説明すべきだ。認証機関のレベルが低いと分かれば依頼なんてしませんよ。
ANAB(アメリカの認定機関)は、目的は最低1個ないと不適合と言っていた。これは規格要求そのままだ。
工場なら省エネ、廃棄物削減、法改正対応の活動、新設備導入とかあるから3つでも5つでもあるだろうが、販売会社などでは、該当するものがなく四苦八苦する。そこで紙ごみ電気の出番だ(笑)。
![]() 「えっ、そうなんですか!どうしてそういう発想をしたのでしょう。
「えっ、そうなんですか!どうしてそういう発想をしたのでしょう。
目的の原語はobjectiveですよね、objectiveに時間的な意味はないですね」
![]() 「規格原文でも日本語訳でも、計画のスパンには言及していない。しかし産業環境認証の審査員は皆同じことを言うのだから、統一見解で決めているに違いない。
「規格原文でも日本語訳でも、計画のスパンには言及していない。しかし産業環境認証の審査員は皆同じことを言うのだから、統一見解で決めているに違いない。
認証機関との話し合いで統一見解を公表すること、公表しないなら認証機関が追加する要求事項はないとみなすことを要求したいな。って、要求するようなことじゃなくて当たり前なんだが」
![]() 「おっしゃることが分かりました。
「おっしゃることが分かりました。
でも統一見解が公表したとして、それが妥当でないとしても、認証機関を替えることは難しいでしょう。業界設立ですから」
![]() 「いや、こちらは客だ。もしISO規格以外の要求が理不尽なら認証機関を替えるということは可能だ。困難であることは分かるけど、可能性がないわけではない。
「いや、こちらは客だ。もしISO規格以外の要求が理不尽なら認証機関を替えるということは可能だ。困難であることは分かるけど、可能性がないわけではない。
それにウチはISO14001の要求事項以外のオプションを付けないよう注文することは可能だろう、認定機関が文句を言ったら、そのときはそのときだ」
![]() 「佐川さんの経験では、問題になることはたくさんあったのですか?」
「佐川さんの経験では、問題になることはたくさんあったのですか?」
![]() 「たくさんといっても20も30もパターンがあったとは思わない。10種類くらいはあったかね。
「たくさんといっても20も30もパターンがあったとは思わない。10種類くらいはあったかね。
ともかくISO14001が下らないと思うほど、やる気を失わせるほどには問題があったね」
![]() 「教えてください。どんなものがあったのか?」
「教えてください。どんなものがあったのか?」
 |
佐川はA4の1枚に箇条書きしたものを、山口に渡した。
![]() 「山口さんから頼まれていたから、思い出したものを簡単にまとめておいた」
「山口さんから頼まれていたから、思い出したものを簡単にまとめておいた」
![]() 「著しい環境側面の決定方法は、スコアリング法に限る……これは?」
「著しい環境側面の決定方法は、スコアリング法に限る……これは?」
![]() 「アハハハ、それを語ると恨みつらみが多くなりそうで、一日かかるよ」
「アハハハ、それを語ると恨みつらみが多くなりそうで、一日かかるよ」
![]() 「マニュアルには規格の文言をすべて盛り込むこと。
「マニュアルには規格の文言をすべて盛り込むこと。
うーん、これは審査員に分かりやすく楽ができるようにですかね。
あっ、そう言えば、マニュアルを作れというのも規格要求にプラスしているわけですね?」
![]() 「それは審査契約書に書いてある。だから公明正大でルール違反ではない
「それは審査契約書に書いてある。だから公明正大でルール違反ではない
だけど世の中にはマニュアルなどいらないという認証機関もある。技量があれば余分なものを要求しないということだろうね。
はっきり言って、顧客企業にマニュアル作成という余分な仕事をさせるわけだ。
マニュアルを作るくらいいいじゃないかという発想はダメだ。会社ではすべてお金に換算して考えないとね。
審査費用は審査単価と審査工数をかけたものになる。
審査単価、つまり審査員一人一日の費用だ。それと審査工数、審査に何日かけるは業務の内容と組織の人数によって決まる。審査単価は10万から15万だろう
審査工数はJABの文書に日数の表がある。組織の事業内容と対象人員、場所がひとつか複数かなどで決まる。
審査単価が高い認証機関だと思っても、マニュアルが要らないというなら、そうだね審査料金が50万くらい高くても良いのかもしれない」
![]() 「50万ですって? マニュアルを作るのにそんなに費用が掛かりますか?」
「50万ですって? マニュアルを作るのにそんなに費用が掛かりますか?」
![]() 「だって山口さんがマニュアルを書くとなると、各部門と打ち合わせたりと調整したり、そしてワープロするなど2週間はかかるだろう」
「だって山口さんがマニュアルを書くとなると、各部門と打ち合わせたりと調整したり、そしてワープロするなど2週間はかかるだろう」
![]() 「2週間でできるかどうかはともかく、それで50万もかかりますか?
「2週間でできるかどうかはともかく、それで50万もかかりますか?
2週間で50万なら、私の月給は100万になりますよ。そんなにもらっていませんよ」

![]() 「人件費は主費だけでなく副費
「人件費は主費だけでなく副費
我々は自分の総人件費の4倍や5倍稼がなければならないよ。だいたい1時間あたり1万5千円は成果を出さなくてはならない。
一日8時間、山口さんだけでなく、相手する人の時間を山口さんの半分としてその1.5倍、2週間で10日、それに1万5千円をかけると180万になる。
マニュアル作成するだけで工場の審査費用の半分かかっていることになる。
実を言って、認証にかかる総費用の内、認証機関に払うのは1割もないんじゃないかな。内部の費用が9割だろう。社外流出ではないとはいえ大金だ。
二回目の審査から半分に減るとしても、そのときは審査費用も減るか」
注:2回目以降の維持審査の工数は初回審査の3分の1と言われる。審査員の旅費は固定費だからまあ半減として、対応する部門も時間も少ないから、内部費用も減る。
![]() 「なるほど、目に見える費用だけではないのですね。審査単価が高くてもマニュアルをいらないという認証機関の方が安いかもしれないとは考えもしませんでした」
「なるほど、目に見える費用だけではないのですね。審査単価が高くてもマニュアルをいらないという認証機関の方が安いかもしれないとは考えもしませんでした」
注:そればかりでなく審査員の説得、解釈のもめごとなどを考慮すると、レベルの低い認証機関は使いたくない。だけどそうはいかないのよ。
![]() 「細々したことはともかく、私の希望をまとめると、規格は英語原文を読むこと、文字解釈に徹すること、統一見解があるなら公開すること、そんなとこかな」
「細々したことはともかく、私の希望をまとめると、規格は英語原文を読むこと、文字解釈に徹すること、統一見解があるなら公開すること、そんなとこかな」
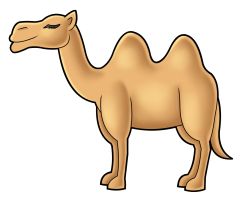
![]() 「お話から推察するとその三つを実現するのは、ラクダが針の穴を通るようなものですね」
「お話から推察するとその三つを実現するのは、ラクダが針の穴を通るようなものですね」
![]() 「なことはない。だって認証機関は認定審査に合格してるんだよ」
「なことはない。だって認証機関は認定審査に合格してるんだよ」
![]() 「それはジョークですか」
「それはジョークですか」
注:あるとき某認証機関の社長と話す機会があった。
話の流れでISO17021のことになった。
社長曰く
「ISO17021を満たす審査員なんていたら神様だ」
神様はともかく、ISO17021を自家薬籠中のものとしている審査員は何割いるのか。
![]() 本日の怨念
本日の怨念
このお話を読んで、被害妄想と思われる方もいらっしゃるでしょうけど、固有名詞は書けませんがすべて事実に相違ありません。
私と相まみえた審査員たちは今頃は優雅な老後を過ごし、10年前、15年前の己の
しかし加害者は忘れても、被害者は忘れません。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
気象庁 過去のデータ検索 | ||
| 注2 |
数えたのかって?
もちろんです。とはいえ私はクリックしただけで、wordが数えてくれましたけどね。 | ||
| 注3 |
ISO9001:1987「4.1.1 方針が組織のすべての階層で理解され、実施され、維持されること」 組織(認証範囲)外の人も構内で働くことは大いにある。組織外の人に規格要求は適用されない。品質に影響するなら「4.6.2下請負契約者の評価」を適用すべきだろう。 | ||
| 注4 |
ISO9001の1996年版では「修理(repair)」と「手直し(rework)」の区別があり、2008年版では「再格付け(regrade)」なるものも現れた。 手直しとは仕様通りの状態にすることで、修理とは完璧に仕様通りでなくても使用できる状態にすること、再格付けとは当初の用途には使えないが他の用途に使える場合に等級を変更すること。 欧州では不良がたくさんできて、どうにか使えるようしている状況なのだろうか? | ||
| 注5 |
ISO14001:1996が発行されたとき、同時に審査の決め事もISO規格として制定されている。 ・JIS14010:1996(JISQ14010)環境監査の指針−一般原則 ・JIS14011:1996(JISQ14011)同上−監査手順−環境マネジメントシステムの監査 ・JIS14012:1996(JISQ14012)同上−環境監査員のための資格基準 その後、認証規格の増加などがあり、審査のルールはどんどん変化している。 ISO9001の審査にはguide62、ISO14001はguide66が具体的に決めていた。 | ||
| 注6 |
guide66(JISQ0066:1999)のG.4.1.4に「JISQ14001以外の規格又は基準文書を使って審査登録するときは、その他の規格又は基準文書は一般に入手できるものでなければならない」という記述があった。ISO17021を見たが見当たらない。 | ||
| 注7 |
・マネジメントシステム認証機関に対する認定システム guide66とは、ISO14001審査の手順やルールを定めたもの。現在はISO17021にとって代わられた。 ・GUIDE 66:1999 | ||
| 注8 |
裁判には罪刑法定主義という原則がある。犯罪となるのはどんなことかを予め法律で定め、それを公表していなければならないという考えである。また法制定前に遡って裁く遡及法は禁止されている(韓国を除く)。 ISO審査においても、ISO17021では、認証機関独自の要求事項を定めることは認めているが、それは事前に公開しておかなければならない。 | ||
| 注9 |
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)は1988年制定で早いものは1996年全廃を定めていた。 | ||
| 注10 |
Guide66では認証機関が審査前に受査企業から入手すべき資料として次を挙げている。なお助動詞は、shouldであり、shallではない。また、これは認証機関へのガイドであって、受査企業が対応する義務はない。 なお、下記の通り「情報」とあって、マニュアルのようにまとまったものを想定していない。
| ||
| 注11 |
審査単価(審査員一人一日の審査料金)は、1995年頃10〜15万だった。21世紀に入り新規参入による競争激化があり、2010年頃はその7割ほどに下がった。それ以降、大きな変化はないようだ。 審査工数はJABの文書類に載っていたが、2025/3/7時点見つけることができなかった。ただJABの文書にある日数と、実際に認証機関が出してくる日数はだいぶ違う。そして認証機関によって数割違うことも多々ある。これまたISO認証の七不思議である。 ISO七不思議とは一体いくつあるのだろう? | ||
| 注12 |
人件主費とは賃金、賞与、退職金積み立てなどで、副費とは社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険I、福利厚生費(寮や社宅の補助、社内イベント、作業服、通勤手当、講習や資格試験の補助など 一般に主費8割・副費2割と言われる。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |