注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1995年10月、今日は定例の業界の環境ISO研究会がある。今回は業界系の認証機関である産業環境認証機関から人が来て説明会をする予定だ。
研究会の幹事、吉本が、先方に話をすると即座に了解の返事が来たそうだ。業界系の認証機関だから業界加盟企業の多くは依頼してくるとは言え、研究会に主要10社参加していて、そのメンバーがISO14001認証の中心となる人たちと聞けば、濡れ手に粟、いや何羽もの鴨が葱を背負って鍋持参でやって来たとウェルカムだろう。
 |  |  |  |
 |
| 「鴨が 来るという、相手の行動が自分の思惑通り都合の良いことの決まり文句 |
||||
説明してその気にさせれば、間違いなく審査依頼が来るだろう。規格制定まで1年もあるのに、ウハウハが止まらない。
佐川も山口も期待と興奮を抑えきれない。思っていることは認証機関とは違うが。
予定通り午後一から研究会が始まり、吉本が来訪者を紹介する。
やってきたのは産業環境認証機関の
 |  |
|
| 時田技術部長 | 小杉主任審査員 |
![]()
まずは時田部長のお話である。挨拶かと思ったら講演のようで延々と終わらない。
皆がISO規格の解釈と期待していたが、時田部長の話は、ISOMS規格が作られた経緯とか認証制度の一般論、それも上っ面を語るばかりである。
時計はもう10分も進んでいる。
田中が手を挙げた。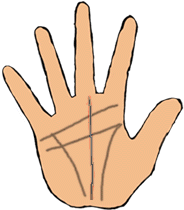
時田部長が話を止めて、田中にどうぞという。
![]() 「お話をさえぎって大変恐縮でありますが、弊方の要望が御社に伝わっていなかったようです。
「お話をさえぎって大変恐縮でありますが、弊方の要望が御社に伝わっていなかったようです。
ここにいる者は既にそれぞれの勤務先でISO9001の認証をした者や、これから認証する環境ISOの担当をしている者たちです。いずれもISOMS規格とか第三者認証制度については十分に承知しております。
この度、御社にお願いしたのは、規格要求……まだDIS段階でありますが、その個々の要求事項について御社としてはどのような解釈をしているか、この研究会やメンバーの勤務先で検討している方法でOKと判断されるのかといったことについて、具体的なお話を伺いたいのです。
時間も押しておりますから、各項番について私どもの考えで問題ないか問題か、御社のお考えというか解釈をお聞かせ願いたいと思っております」
時田部長は、鳩が豆鉄砲を食らったような顔をして、小杉審査員と顔を見合わせた。
吉本が焦った顔をして発言する。
![]() 「田中さん、お話し中の時田部長さんを遮るなんて失礼ですよ。そういう話はこれからしましょう」
「田中さん、お話し中の時田部長さんを遮るなんて失礼ですよ。そういう話はこれからしましょう」
![]() 「はて、吉本さんからお聞きした内容はそうではありませんでしたね。ISO認証を検討しているので、認証制度や認証の効用についてのお話をしてほしいと伺いました」
「はて、吉本さんからお聞きした内容はそうではありませんでしたね。ISO認証を検討しているので、認証制度や認証の効用についてのお話をしてほしいと伺いました」
![]() 「話が伝わる過程で変わってしまい、私どもの意向が伝わらなかったようです。
「話が伝わる過程で変わってしまい、私どもの意向が伝わらなかったようです。
とはいえ、時田部長さんも小杉さんもISO認証の専門家ですから、そういう趣旨とご理解いただければ、私どもの疑問にご教示いただけますよね?」
![]() 「もちろんです」
「もちろんです」
![]() 「ありがとうございます。それじゃ時間ももったいないですから、少し休憩を取ったのち、私どもの方から質問させていただきますのでよろしくお願いします」
「ありがとうございます。それじゃ時間ももったいないですから、少し休憩を取ったのち、私どもの方から質問させていただきますのでよろしくお願いします」
![]() 「ああ、そうしましょう」
「ああ、そうしましょう」
時田部長 | ||||
吉本 |  佐川 佐川 |
|||
| 田中 |  山口 山口 |
|||
| 金子 |  須藤 須藤 |
|||
| 高橋 |  鈴木 鈴木 |
|||
| 小林 | ||||
メンバー側は立ち上がって部屋から出るものもあり、背伸びする者あり、雑談するものもあり……
![]()
吉本が田中のところに歩み寄る。
![]() 「田中さん、私が段取りしたことに横やりを入れないで欲しいです」
「田中さん、私が段取りしたことに横やりを入れないで欲しいです」
![]() 「吉本さん、困りますよ。前々回、認証機関と話し合いを設定してほしいとお願いしたときと、全然違うじゃないですか。
「吉本さん、困りますよ。前々回、認証機関と話し合いを設定してほしいとお願いしたときと、全然違うじゃないですか。
原因は吉本さんです。時田さんに謝罪するのは吉本さんでしょう」
![]() 「まあまあ、多少すれ違いがあったのでしょう。私どもでもDISは十分に読んでおり各要求事項について吟味を重ねております。
「まあまあ、多少すれ違いがあったのでしょう。私どもでもDISは十分に読んでおり各要求事項について吟味を重ねております。
特に小杉さんは詳しいですよ。ご安心ください」
![]() 「それはありがたいです。ではあと5分もしたら初めてよろしいでしょうか?」
「それはありがたいです。ではあと5分もしたら初めてよろしいでしょうか?」
・
・
・
![]() 「僭越ですが私が司会をさせていただきます。
「僭越ですが私が司会をさせていただきます。
私どもでいろいろ議論してきまして分からないことがありますので、個々に質問させていただきます。
では吉宗機械さんから始めますか」
![]() 「吉宗の山口と申します。よろしくお願いいたします。
「吉宗の山口と申します。よろしくお願いいたします。
環境側面を決定するとありますが、具体的な方法としてどのようなことを考えていますか?」
![]() 「方法を示すことはコンサルティングとみなされます。皆さんが考えたものを説明いただければ、それに善し悪しをコメントするならよろしいかと思います」
「方法を示すことはコンサルティングとみなされます。皆さんが考えたものを説明いただければ、それに善し悪しをコメントするならよろしいかと思います」
![]() 「了解しました。
「了解しました。
私どもが考えたのはインプット、アウトプットなど、考えられるものを徹底的にリストアップすることを考えております」
![]() 「徹底的と言っても、漏れが起きることも考えられますね」
「徹底的と言っても、漏れが起きることも考えられますね」
![]() 「法律関係や費用関係から、現実に購入している物品や、行っている作業など、思いつけるものを書き出してもダメですか?」
「法律関係や費用関係から、現実に購入している物品や、行っている作業など、思いつけるものを書き出してもダメですか?」
![]() 「例えば通勤などもあると思います」
「例えば通勤などもあると思います」
![]() 「通勤も考えています。もっともドラフトにある『組織が管理できる』には当たらないと思います」
「通勤も考えています。もっともドラフトにある『組織が管理できる』には当たらないと思います」
![]() 「『影響を与える』ことはできますよね」
「『影響を与える』ことはできますよね」
![]() 「影響を与えると言っても、車通勤を止めて公共交通機関で来いとは言えません。強制は論外で、呼びかけはできても要請することは法的にできません
「影響を与えると言っても、車通勤を止めて公共交通機関で来いとは言えません。強制は論外で、呼びかけはできても要請することは法的にできません
![]() 「環境保護という観点からお願いはできるでしょう」
「環境保護という観点からお願いはできるでしょう」
![]() 「聞くところによると、H製作所、M重工などでは通勤者用の専用駅があると聞きます。そういう場合は影響を与えることができると思います。
「聞くところによると、H製作所、M重工などでは通勤者用の専用駅があると聞きます。そういう場合は影響を与えることができると思います。
しかし田舎では公共交通機関はなく、車通勤が不可欠です。環境保護のために車通勤を止めろとは言えません」
![]() 「相乗りで出勤するとか考えられるのではないですか?」
「相乗りで出勤するとか考えられるのではないですか?」
![]() 「田舎に行くと分かりますが、通勤の際、学校に行く子供を乗せていくとか、住まいの近くには商店がなく、会社帰りに買い物するとか、勤務者の住まいが大きく離れていて相乗りには余計に走行するなど、車の位置づけが都会と大きく違います」
「田舎に行くと分かりますが、通勤の際、学校に行く子供を乗せていくとか、住まいの近くには商店がなく、会社帰りに買い物するとか、勤務者の住まいが大きく離れていて相乗りには余計に走行するなど、車の位置づけが都会と大きく違います」
注:家内の姪の場合、高校に通う息子は朝は義弟(息子から見て祖父)が通勤の車に乗せて20キロ離れた学校に行き、
 夜は部活で遅くなるので姪が学校まで迎えに行く。
夜は部活で遅くなるので姪が学校まで迎えに行く。
娘は朝は路線バスで5キロ離れた中学に通い、帰りはやはり姪が車で迎えに行く。路線バスは日に数往復しかないから。
田舎では小中学校の統廃合が進み、今では子どもが歩いて通うことのできるところには中学校がない。小学生はまだ徒歩範囲にあるが、一学年数名で複式学級だ。
姪はパート仕事をしているし買い物もあるので、姪の軽自動車は月に2,000キロは走る。
![]() 「小杉さん、細かく入り込むと時間もあれだ……そういうことに留意してもらえば良いということでどうですか」
「小杉さん、細かく入り込むと時間もあれだ……そういうことに留意してもらえば良いということでどうですか」
![]() 「分かりました。そういうことを考慮されていればよろしいと思います。審査の際にそういう質疑があると思います」
「分かりました。そういうことを考慮されていればよろしいと思います。審査の際にそういう質疑があると思います」
![]() 「私の質問への回答としては、申し上げたように調べれば不適合にならないという理解でよろしいですね」
「私の質問への回答としては、申し上げたように調べれば不適合にならないという理解でよろしいですね」
![]() 「まあ、そうですね」
「まあ、そうですね」
![]() 「山口さん、私の方で記録して、終了時に時田部長さんのサインをもらいます。山口さんがメモすることはありません」
「山口さん、私の方で記録して、終了時に時田部長さんのサインをもらいます。山口さんがメモすることはありません」
・
・
・
![]() 「環境目的を設定するとき、目的が策定時から何年以降、つまり計画の長さが何年以上とか要求はありますか?」
「環境目的を設定するとき、目的が策定時から何年以降、つまり計画の長さが何年以上とか要求はありますか?」
![]() 「目的の期間ですね、我々も検討しまして、一応、マネジメントプログラムの期間として3年は必要かと思います」
「目的の期間ですね、我々も検討しまして、一応、マネジメントプログラムの期間として3年は必要かと思います」
![]() 「省エネですと省エネ法の定めもあり、計画は毎年ローリング
「省エネですと省エネ法の定めもあり、計画は毎年ローリング
しかし法改正対応とかになりますと、制定から施行まで3年ありません。1年どころかより短期のこともあります。3年と言いますと、そういう活動は環境目的にできないのでしょうか? 3年以上となると、現実の会社の動きにそぐわないですね」
![]() 「環境目的に期間の要求があるとは初耳ですが、根拠は何でしょうか?」
「環境目的に期間の要求があるとは初耳ですが、根拠は何でしょうか?」
![]() 「根拠といいますか、企業は長期的視点で計画を立てる必要があるということですね」
「根拠といいますか、企業は長期的視点で計画を立てる必要があるということですね」
![]() 「長期的視点と言っても、1年後に達成しなければならないものは1年で仕上げないとなりませんよ。
「長期的視点と言っても、1年後に達成しなければならないものは1年で仕上げないとなりませんよ。
ところで規格要求ではどのshallに該当しますか?」
![]() 「それは当社で有識者が集まって検討した結果です。環境活動が3年以内では規格の意図にあいません」
「それは当社で有識者が集まって検討した結果です。環境活動が3年以内では規格の意図にあいません」
![]() 「規格の意図に合わないって言われてもなあ〜」
「規格の意図に合わないって言われてもなあ〜」
![]() 「目的達成の計画に期間の要求があると聞いて驚きました。
「目的達成の計画に期間の要求があると聞いて驚きました。
私は電取法とかULとか担当しております。そういった法規制とか規格で期間を示すときは、はっきりと文章で記述しています。明文化された根拠がなければ、3年以上でなければダメとは言えないでしょう」
![]() 「いや、これは大事なことです」
「いや、これは大事なことです」
![]() 「大事なことだからこそ明文化が必要です。
「大事なことだからこそ明文化が必要です。
ISO9001では判定が規格と違う場合、異議申し立てとかできるはずですね?」
![]() 「そのようですね」
「そのようですね」
![]() 「するとこれは異議申し立てできるのですね? もちろん実際の審査のとき、3年未満を不適合にされたときですが」
「するとこれは異議申し立てできるのですね? もちろん実際の審査のとき、3年未満を不適合にされたときですが」
![]() 「ちょっと、大げさですよ。それくらい認証機関の指導と思っていただきたい」
「ちょっと、大げさですよ。それくらい認証機関の指導と思っていただきたい」
![]() 「おっしゃることは無理筋
「おっしゃることは無理筋
日本の行政なら、法律、施行令、省令で間に合わないときは、行政が方法とか基準を定めて正式に通知しますし、公式に説明会もします。
ISO審査で、根拠なく独断で規格にない要求をすれば訴訟でしょう」
![]() 「裁判沙汰なんて、大げさなことをおっしゃる。
「裁判沙汰なんて、大げさなことをおっしゃる。
我々が検討した結果ですから、それに対応してもらわないと困ります」
![]() 「ISO審査とはISO規格を審査基準にして、それに適合しているかいないかを判定することですよ。
「ISO審査とはISO規格を審査基準にして、それに適合しているかいないかを判定することですよ。
規格以上の基準を勝手に決めて、それを広報もせずに、それを基準に審査するとは、明確な不法行為
注:私は30年も前からこれを当たり前だと考えていた。
だが、世の審査員も認証機関も当たり前とは考えていないようだ。法治国家に住んでいないのか? あるいは自分は神とか全権者と思っているのか?
![]() 「まあまあ、そんな大げさにせずにご了解願いたいですよ」
「まあまあ、そんな大げさにせずにご了解願いたいですよ」
![]() 「了解できません。電取法やULでは、そういういい加減な運用はありません。時田部長さんはそういう常識をご存じないのですか」
「了解できません。電取法やULでは、そういういい加減な運用はありません。時田部長さんはそういう常識をご存じないのですか」
![]() 「折り合いがつかない場合は、認証機関を替えるしかないですね」
「折り合いがつかない場合は、認証機関を替えるしかないですね」
![]() 「そう角を立てずに、この業界団体に加盟されているのですから、弊社に審査依頼していただきたい」
「そう角を立てずに、この業界団体に加盟されているのですから、弊社に審査依頼していただきたい」
![]() 「業界傘下の企業だから御社に依頼せよというなら、規格に付加する要求事項を止めるように要求したい。出資しているとか出向者を出しているとか関係ありません。正しいか間違いかをはっきりさせましょう。
「業界傘下の企業だから御社に依頼せよというなら、規格に付加する要求事項を止めるように要求したい。出資しているとか出向者を出しているとか関係ありません。正しいか間違いかをはっきりさせましょう。
我々は業務として認証をしなければならず、それはISO規格適合を達することと理解しています。余計なことは無用です」
・
・
・
時田部長と小杉審査員が小声での話が長引くので、田中が声を上げた。
![]() 「まだ二問目ですが、お聞きすると認証機関の見解は、我々が考えたものと相当違うことに驚きました。やはり御社の規格解釈を説明してもらわないと、我々は手も足も出ないですね」
「まだ二問目ですが、お聞きすると認証機関の見解は、我々が考えたものと相当違うことに驚きました。やはり御社の規格解釈を説明してもらわないと、我々は手も足も出ないですね」
![]() 「そうでしょう、そうでしょう。規格の理解は難しいのです」
「そうでしょう、そうでしょう。規格の理解は難しいのです」
![]() 「いえ、規格の理解が難しいのではありません。お宅の理解が我々と大きく違うのが問題です。まず規格要求にない要求があるのに驚きです。
「いえ、規格の理解が難しいのではありません。お宅の理解が我々と大きく違うのが問題です。まず規格要求にない要求があるのに驚きです。
たった二問でそうとうな見解の相違のあることが分かりました。他の項番も徹底的に議論して納得できないと、御社に審査を依頼はできないですね」
![]() 「産業環境認証さんの話を伺っただけではお宅の規格解釈に正しいのか確信が持てません。他の認証機関の解釈も調査しないとなりませんね」
「産業環境認証さんの話を伺っただけではお宅の規格解釈に正しいのか確信が持てません。他の認証機関の解釈も調査しないとなりませんね」
![]() 「ちょっと何を考えているの、吉宗機械さんでしたか、御社からは三田取締役が来られていますね。三田さんから御社のトップに話をしてもらわないとまずいな」
「ちょっと何を考えているの、吉宗機械さんでしたか、御社からは三田取締役が来られていますね。三田さんから御社のトップに話をしてもらわないとまずいな」
![]() 「常識で考えてほしいのですが、法律の解釈で一企業の取締役の意見が通用するなんてありえません。御社の見解が他の認証機関と異なる場合は、ISOTC委員などISO関係者の見解を聞く必要があります。
「常識で考えてほしいのですが、法律の解釈で一企業の取締役の意見が通用するなんてありえません。御社の見解が他の認証機関と異なる場合は、ISOTC委員などISO関係者の見解を聞く必要があります。
私どもの工場では、ISO9001は複数の認証機関から認証を受けていますので、審査の判断が納得できないときは他の認証機関、特にイギリス系のところに相談に行っております」
![]() 「なるほど、それは良い考えだ。ウチでもISO9001の審査で納得できないこともあるが、方法がないから向こうの意見を飲んでいる。今後はとりあえず同意せずに他の認証機関に相談するということにしよう」
「なるほど、それは良い考えだ。ウチでもISO9001の審査で納得できないこともあるが、方法がないから向こうの意見を飲んでいる。今後はとりあえず同意せずに他の認証機関に相談するということにしよう」
注:これも実行している人は少ないようだ。私は審査でおかしいと思えば、審査の場から抜け出して面識のない認証機関に電話して相談した。連絡先はJABのウェブサイトに載っている。
ほとんどが鞍替えしてくれることを期待して真面目に対応してくれた。どこも最後は「ウチに鞍替えしてください」と言われた。
もちろん法律関係は行政機関に電話した。「消防署より消防法に詳しい」と語った審査員もいたけどね。
・
・
・
![]() 「すみません、別の質問です。
「すみません、別の質問です。
著しい環境側面の決定ですが、こういった場合、決まりきったいくつかのテクニックがありますね。
私のところではロジックゲート法と呼んでいるのですが、いくつかの条件に合ったとき、それを著しい環境側面にしようと考えています。
そういう方法でよろしいですか?」
![]() 「ロジックゲート法ですか? フィルタリング法と同じですね。
「ロジックゲート法ですか? フィルタリング法と同じですね。
フィルターを適切に設定すれば悪いとは言えませんね。ただ私どもではそれよりもバラツキのない誰がしても同じ結果になる方法を推奨しています」
![]() 「私どもが考えた方法では不適合ですか?」
「私どもが考えた方法では不適合ですか?」
![]() 「不適合とは言いませんが、実際にやってみて人が変わると違う結果になるとか、理屈が通っていないといけませんね。
「不適合とは言いませんが、実際にやってみて人が変わると違う結果になるとか、理屈が通っていないといけませんね。
そのあたりは今後、ISO認証のための講習会をいろいろ考えていますから、それに参加していただき勉強してもらいたいと考えています」
![]() 「認証機関は方法を教えることはできないと言いましたが、講習会はよろしいのですか?」
「認証機関は方法を教えることはできないと言いましたが、講習会はよろしいのですか?」
![]() 「特定の問題でなく、一般的な規格の解釈とか方法を教えることは問題ではありません」
「特定の問題でなく、一般的な規格の解釈とか方法を教えることは問題ではありません」
![]() 「じゃあ、私が最初に質問したものも一般論ですよね。どうして教えられないと言ったのですか?」
「じゃあ、私が最初に質問したものも一般論ですよね。どうして教えられないと言ったのですか?」
![]() 「……」
「……」
![]() 「小杉審査員のおっしゃるのはスコアリング法ですか?」
「小杉審査員のおっしゃるのはスコアリング法ですか?」
![]() 「おっ、ご存じでしたか。そうです、私どもではそれが一番客観性があり、評価者によるバラツキが少ないと考えています」
「おっ、ご存じでしたか。そうです、私どもではそれが一番客観性があり、評価者によるバラツキが少ないと考えています」
![]() 「それ以外では不適合となるのでしょうか?」
「それ以外では不適合となるのでしょうか?」
![]() 「先ほど言いましたが、スコアリング法でなければ不適合とは申しません。
「先ほど言いましたが、スコアリング法でなければ不適合とは申しません。
ただ客観性があり、信頼できる方法となると、他にありますかね」
![]() 「スコアリング法以外でも不適合にしないということでよろしいですか?」
「スコアリング法以外でも不適合にしないということでよろしいですか?」
![]() 「審査では客観性とか、評価者が変わっても結果が変わらないかを確認します」
「審査では客観性とか、評価者が変わっても結果が変わらないかを確認します」
![]() 「どうもスコアリング法以外ならスコアリング法に誘導すると聞こえますね」
「どうもスコアリング法以外ならスコアリング法に誘導すると聞こえますね」
![]() 「弊社は複数の業界団体に加盟しています。それらでも認証機関を作っていますから、著しい環境側面の決定方法についての意見を聞いて、我々が考えた方法を適正と考える認証機関を選ぶことになるでしょうね」
「弊社は複数の業界団体に加盟しています。それらでも認証機関を作っていますから、著しい環境側面の決定方法についての意見を聞いて、我々が考えた方法を適正と考える認証機関を選ぶことになるでしょうね」
![]() 「ちょっと待ってください。弊社は規格解釈では卓越していると思いますよ」
「ちょっと待ってください。弊社は規格解釈では卓越していると思いますよ」
![]() 「この業界団体の検討会で、他の認証機関が良いなんて言わないでください」
「この業界団体の検討会で、他の認証機関が良いなんて言わないでください」
![]() 「先ほどからの話を聞くと、産業環境認証さんは規格を理解しているとは思えませんね。私は海外規格の翻訳と、その社内展開などをしています。英文の規格解釈なら自信があります。
「先ほどからの話を聞くと、産業環境認証さんは規格を理解しているとは思えませんね。私は海外規格の翻訳と、その社内展開などをしています。英文の規格解釈なら自信があります。
御社で規格を扱っていた人はいないのですか?」
![]() 「何をおっしゃいます。私どもは業界各社から、皆さんのところですよ、優秀な方に来ていただいて検討をしております」
「何をおっしゃいます。私どもは業界各社から、皆さんのところですよ、優秀な方に来ていただいて検討をしております」
![]() 「それにしちゃ規格の読み方が杜撰だ」
「それにしちゃ規格の読み方が杜撰だ」
![]() 「ロジックゲート法がまずいと言うなら、考えないとならないなぁ〜」
「ロジックゲート法がまずいと言うなら、考えないとならないなぁ〜」
![]() 「この分では他の項番でも、大きな問題がありそうですね」
「この分では他の項番でも、大きな問題がありそうですね」
![]() 「時田部長さん、御社の規格解釈を尊重するとしても、御社が考える規格の解釈をあらかじめ文書で頂きたいですね。そうしないと我々はどのように判断するか分からず、途方に暮れてしまいます。
「時田部長さん、御社の規格解釈を尊重するとしても、御社が考える規格の解釈をあらかじめ文書で頂きたいですね。そうしないと我々はどのように判断するか分からず、途方に暮れてしまいます。
事前に御社の統一見解と言いましょうか、そういうものを頂いていれば右往左往せずに進めると思います」
![]() 「それはアイデアですね。部長そういう方法を取りましょう」
「それはアイデアですね。部長そういう方法を取りましょう」
![]() 「難しいと思うが検討しよう」
「難しいと思うが検討しよう」
![]() 「マネジメントレビューも年に何回とか決めていますか?」
「マネジメントレビューも年に何回とか決めていますか?」
![]() 「最低年一回は、会議形式で行うよう求めます」
「最低年一回は、会議形式で行うよう求めます」
![]() 「大手のJ○○もそう要求していますね。
「大手のJ○○もそう要求していますね。
それも規格にありませんから、その御社の審査基準というものに盛り込んでくださいね。
あのうですね、私たちも会社でいろいろ言われているわけですよ。会議とか作成する文書を最小限にしたいのは当然です。
規格にshallで書かれているものは必須と理解しますが、追加とか、より厳しい要求があれば、理由をお聞きして納得できなければ受け入れられません。
まずは審査前に御社から文書で頂けなければ話になりません」
![]() 「難しいですが、考えましょう」
「難しいですが、考えましょう」
・
・
・
![]() 「環境目的というのは何件必要なのでしょうか?」
「環境目的というのは何件必要なのでしょうか?」
![]() 「規格では決めてありませんが、どの会社でも現実には5件から10件は活動していると思います。省エネ、廃棄物削減、省エネ製品開発、輸送の省エネ、オフィスの環境活動とか」
「規格では決めてありませんが、どの会社でも現実には5件から10件は活動していると思います。省エネ、廃棄物削減、省エネ製品開発、輸送の省エネ、オフィスの環境活動とか」
![]() 「でも3年以上のものだけが目的なんでしょう?」
「でも3年以上のものだけが目的なんでしょう?」
![]() 「そうです。3年以上に限っても5件や6件はあるでしょう」
「そうです。3年以上に限っても5件や6件はあるでしょう」
![]() 「3年というのは計画策定時と思います。当然、1年経過したら残りは2年になりますが、それはよろしいのですね」
「3年というのは計画策定時と思います。当然、1年経過したら残りは2年になりますが、それはよろしいのですね」
![]() 「いやぁ〜、そこはですね……計画が進んで、目的まで3年を切ると目的の要件を満たさないのですよ」
「いやぁ〜、そこはですね……計画が進んで、目的まで3年を切ると目的の要件を満たさないのですよ」
![]() 「なんと、3年の目的を作っても、策定時はOKでも1年経つと不適合ですか。そりゃないよ」
「なんと、3年の目的を作っても、策定時はOKでも1年経つと不適合ですか。そりゃないよ」
![]() 「えっ、それってどうなのよ、オカシイジャン」
「えっ、それってどうなのよ、オカシイジャン」
![]() 「企業は長期的視点で活動を進めているはずですから、そういうことはないでしょう」
「企業は長期的視点で活動を進めているはずですから、そういうことはないでしょう」
![]() 「でもおかしいなあ〜、一つの目的達成の環境マネジメントプログラムを作って審査のときフォローするわけでしょう。最初3年ありました。翌年はもう目的の要件を満たさないからISO審査で審査対象の目的じゃないです。すると全ての目的は達成2年前から審査を受けないことになる。
「でもおかしいなあ〜、一つの目的達成の環境マネジメントプログラムを作って審査のときフォローするわけでしょう。最初3年ありました。翌年はもう目的の要件を満たさないからISO審査で審査対象の目的じゃないです。すると全ての目的は達成2年前から審査を受けないことになる。
達成を確認しない審査なんて適合なんですか?」
皆が時田部長と小杉審査員を見つめる。
二人は顔を見合わせて無言だ。
・
・
・
![]() 「外部コミュニケーションとは、どういうものをイメージしているのですか?」
「外部コミュニケーションとは、どういうものをイメージしているのですか?」
小杉氏は脇から新しい質問をされて、これ幸いとそちらに顔を向ける。
![]() 「第一には環境報告書ですね。あとは近隣への広報とかアンケートなどによって意見を吸い上げるとか」
「第一には環境報告書ですね。あとは近隣への広報とかアンケートなどによって意見を吸い上げるとか」
![]() 「本社では環境報告書を作っていますけど、工場では作っていません。ISO認証は工場単位を予定していますが、そのときはどうするのでしょうか?」
「本社では環境報告書を作っていますけど、工場では作っていません。ISO認証は工場単位を予定していますが、そのときはどうするのでしょうか?」
![]() 「私は公害防止担当です。外部コミュニケーションと聞いて私が一番先に思いつくのは行政との交渉ですが、そういうものも該当するのでしょう?」
「私は公害防止担当です。外部コミュニケーションと聞いて私が一番先に思いつくのは行政との交渉ですが、そういうものも該当するのでしょう?」
![]() 「行政への届出、報告などは『法的及びその他の要求事項』に当たります。外部コミュニケーションではありません」
「行政への届出、報告などは『法的及びその他の要求事項』に当たります。外部コミュニケーションではありません」
注:ISO14001:1996では『4.3.2法的及びその他の要求事項』は『4.3計画』の項番にあり、そこでの要求は法的要求事項をしっかり把握せよであり、そこからのアクションは記述していない。行政届け出などは『4.4の実施及び運用』で定めているが、そこで該当するのは『4.4.3コミュニケーション』しかない。
時田部長が規格を理解していないことがバレバレだ。
![]() 「法に基づく届け出とか事故報告がコミュニケーションの一番目に来ると思うがね。事故が起きたときのことをコミュニケーションに入れずに、環境報告書でもないと思うが……」
「法に基づく届け出とか事故報告がコミュニケーションの一番目に来ると思うがね。事故が起きたときのことをコミュニケーションに入れずに、環境報告書でもないと思うが……」
![]() 「コミュニケーションとは日本では一般的に、気持ちや考えを話し合うことですが、本来はもっと広い意味で、行政との交渉とか外部との法的なやりとりは完璧に該当しますよ。会社での命令、報告もコミュニケーションですし」
「コミュニケーションとは日本では一般的に、気持ちや考えを話し合うことですが、本来はもっと広い意味で、行政との交渉とか外部との法的なやりとりは完璧に該当しますよ。会社での命令、報告もコミュニケーションですし」
注:当時、いや今でもか、認証機関に限らず多くの人の認識はそんなものだった。「行政との関りが外部コミュニケーションで一番大事です」なんて言っていた認証機関はなかったし、ネットで外部コミュニケーションとは環境に関わる届け出や近隣との対応だと語った人を私は知らない。
ネットに「口語訳ISO14001」なんて銘打って独自訳をアップしていた人がいた。その中で「外部コミュニケーションとは環境報告書を出すこと」と書いていた。
私はそれに納得いかず、ISOTC委員に問い合わせた。するとメールが返ってきた。文面は「そんな解釈は間違っている。規格に書いてある通り、外部とのコミュニケーションをしっかりやれということだ」とお怒りだった。
お節介な私は、ウェブの主宰者にそのことをメールした。すると、その方も強い調子で返事を寄こした。
「それはISOTC委員が間違っている。私はISOTC委員より詳しい人に聞いた」とあった。各国代表と議論して規格を作っているISOTC委員より詳しい人とは誰なのか?
皆がワイワイやりあっているのを、吉本は面白くない顔で見ていた。
![]() 本日のお話は夢です
本日のお話は夢です
認証機関を選ぶときに、このような規格解釈のすり合わせが、できたら良かったのにと思って書きました。
対等な立場で自由に認証機関と話し合い出来たらよかったですね。
そんな夢のようなこと、私はしたことありません。
ISO14001が登場したときもISO9001と同じく、売り手市場、認証機関が強かった。
例えば審査員は大層エライようで、「先生」と呼ばれないと返事をしないという都市伝説を、聞くのでなくリアルで見る幸運に恵まれました。歩き方も違うのです。工場巡回でもサッサと歩かず、膝が悪いのかと思わせるほどゆっくりと歩きました。威厳付けだったのでしょうね。
営業も上から目線でした。認証機関に審査の詳細の問い合わせメールを送ってもまず返事が来ません。督促の電話をすると「あ〜、そんなことあったな」なんて軽く言われました。
某認証機関のこと、審査に必要と言われた資料一式を、余裕をとってメール添付で送信していたのに、実施日寸前にまだ送らないのかと苦情を言ってきた。このように資料が行方不明になることがたびたび発生したので、我々はバミューダトライアングルならぬバミューダ認証機関と呼んでいた。
あれは都合が悪いものは見ないことにしたのか、それとも単に管理が悪かったのか、分かりません。
今回は
じゃあ、次回は悲劇で行こうか?
現在はハッピーエンドでない物語を悲劇というが、元々は死で終わるドラマのこと。
![]() 本日のご招待
本日のご招待
上に書いたもろもろに、ご意見をどうぞ。
実際にあったことばかりですから、どなたかは時田部長や小杉審査員の言葉を語っていたはずです。
- 環境側面をリストアップしただけじゃダメだ、
- 環境目的は3年以上は当たり前だろう
- 認証機関が要求事項を追加してもいいじゃないか
- 著しい環境側面の決定はスコアリング法しかない
- マネジメントレビューとして年1回は会議しろ
- 外部コミュニケーションとは環境報告書だ
- 行政報告は外部コミュニケーションではない
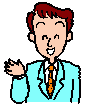
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
会社指定の通勤方法を取らせることはかなり難しい。強制でなく納得させなければ不法労働行為になりそうだ。 納得させるには、 ・通勤手段の変更が合理的であること ・通勤手段の変更が従業員にとって不利益にならないこと ・通勤手段の変更が従業員の安全に影響を与えないこと 等の条件をクリアしなければならない。 | |
| 注2 |
ローリングとは、計画を定期的に見直して常に一定期間の計画を持つ手法。 | |
| 注3 |
無理筋とは囲碁用語で、理屈に合わない強引な戦い方をいう。相手が正しく受ければ必ず負ける。 | |
| 注4 |
不法行為とは民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」に反する行為を言う。 相手に知らせずルールを作り、それに反しているからと不適合にするのはズバリこれに該当する。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |