注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
業界団体から産業環境認証機関に、ISO認証の解説をしてほしいと依頼がきた。時田部長と小杉審査員の二人で、審査依頼に繋がるだろうと気軽に出かけた。
![]()
 |  |
|
| 時田技術部長 | 小杉主任審査員 |
「ISO認証とは」と説明を始めると、聴講者から予定していた内容と違うと物言いが付き、初歩的な説明でなく、認証機関がどのように規格解釈をしているか説明してほしいという。
間に入った業界団体の人が、いい加減なことを伝えてきたようだ。
それを了承したら、規格要求をどのように考えているのかと、具体的で細かく厳しい質問が絶え間なく飛んできた。
不思議なことに認証機関の内部で検討していることを知っているかのような質問が飛んできて、回答するとそれに対して更なる質問がくる。
それは考えがおかしい、根拠は何か、規格にないことを要求するのは間違いだと、被告人にするような質疑が続いた。
嫌気がさしたが、今までのような認証機関が尊敬された殿様商売が続くわけがない、いずれは審査が議論の場になるだろうと、覚悟を決めた。

その場で説明できないことも多く、いや正直言えば質問のほとんどが回答に困ることだった。一段落ついたとき、長居は御免とサッとお暇して帰ってきた。
山手線で数分、新橋駅から歩いて数分の産業環境認証機関に戻ったのは、まだ4時を少し過ぎたときだった。午後からだから、質疑応答は2時間半くらいしかしていないが、ぐったり疲れた。
認証機関に着くと自席に戻らず、認証機関にあるあるの、4人も入れば満員の小部屋に入ってホッと一息つく。この小部屋は顧客との相談用で、どこの認証機関にも何室もあるのだ。もっとも小さな認証機関では、個室でなく部屋の一角をパーテーションで仕切っただけのところも多い。
二人は座るとホッとした。暑い中、新橋駅から歩いてきて冷房の効いた部屋に入りアイスコーヒーを飲んだこともあるが、一番は答えられそうのない質問の連射から解放されたことだ。
![]() 「いやはや、かなり厳しい質問の連発だったね」
「いやはや、かなり厳しい質問の連発だったね」
![]() 「そうですね、しかし審査ではこれを軽く切り返えせることが必要だと実感しました。これからは企業側も勉強していますから、以前のような楽な審査はできなくなります」
「そうですね、しかし審査ではこれを軽く切り返えせることが必要だと実感しました。これからは企業側も勉強していますから、以前のような楽な審査はできなくなります」
![]() 「アハハハ、立派な心構えだ。
「アハハハ、立派な心構えだ。
さて、我々もいろいろ考えてきたつもりだが、相手を説得する理論武装はまだまだと思い知らされたよ。
『4.3.1環境側面を特定する手順を確立し』とあるが、その方法をどのように決めるのか、具体的な方法を教えることはないが、こちらは幾通りか準備しておかなくてはならないな」
小杉は、研究会のリーダー的存在だった田中が、作成した質疑応答にサインしてコピーをもらってきた。
それを取り出して、時田に向けて二人の中央に置いた。
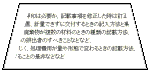
![]() 「真っ先に聞かれたのがそれでしたね。翻訳は『特定する』ですが原語は『identify』ですから、正しくは『識別する』とすべきでしょう」
「真っ先に聞かれたのがそれでしたね。翻訳は『特定する』ですが原語は『identify』ですから、正しくは『識別する』とすべきでしょう」
![]() 「ええと、『特定する』というと『原因を特定する』なんて言うね。いろいろ要因を調べてみて、どれが原因か絞っていくイメージか。
「ええと、『特定する』というと『原因を特定する』なんて言うね。いろいろ要因を調べてみて、どれが原因か絞っていくイメージか。
『識別する』とは、ISO9001で部品を識別しろとあったな(ISO9001:1994 4.8)。この意味は異なるものは区別しろということだった。
あれ、ISO規格を翻訳するとき、特定の言葉は常に同じ日本語に訳するという決まりがあったはずだ。となるとこのDISの訳はルール違反になる」
注:海外規格をJIS規格に翻訳する場合、同じ原語は必ず同じ日本語に訳すとは定めていない。「同じ概念には一貫した訳語を使うことが推奨」とある。
ところでISO14001ではidentifyとspecificを「特定」と訳している。原文の同じ単語は同じ訳語を当てるべしとあるが、ふたつの単語をひとつの日本語に当てるのはどうなのだろう? なかなか難しいですね(笑)
![]() 「それは母集団から1個ずつ抜き取って該非を判断する段階だ。その前段階、母集団というか対象範囲をどうとらえるのだろう?
「それは母集団から1個ずつ抜き取って該非を判断する段階だ。その前段階、母集団というか対象範囲をどうとらえるのだろう?
たくさんリストアップすれば良いとも思えない。最初に対象となる母集団をどう定義するのか、調査範囲が適正か、調査範囲に漏れがないと立証するのはどうするのだろう?」
![]() 「そう言われるとそうですね。私たちは著しい環境側面を決定することは考えましたが、環境側面をどう把握するか、漏れがないのかを考えていなかったようです。
「そう言われるとそうですね。私たちは著しい環境側面を決定することは考えましたが、環境側面をどう把握するか、漏れがないのかを考えていなかったようです。
![]()
あのとき私は通勤を考えたかと問いましたが、通勤は氷山の一角です。社内外のイベント、CM、カタログ、冠大会、会社や組合主催のボランティアなどは業務外・敷地外ですが、通勤以上に影響力は持ちますね」
![]() 「君の言う通りだ。考えれば考えるほど広がっていく。どこまでか、そもそも限界があるのかどうか……」
「君の言う通りだ。考えれば考えるほど広がっていく。どこまでか、そもそも限界があるのかどうか……」
![]() 「部長がお書きになられた『環境側面の理解』という書籍の草稿がありましたね。ここは、どう書いてありましたっけ?」
「部長がお書きになられた『環境側面の理解』という書籍の草稿がありましたね。ここは、どう書いてありましたっけ?」
![]() 「ああ、あれか、覚えている、『各部門は自部門の諸活動(定常時、非定常時、緊急時を含む)における環境側面のうち、自部門が管理できる及び影響力を及ぼせる範囲で環境側面をリストアップする』とした。環境側面の探す範囲は書いていない。強いて言えば諸活動かな?
「ああ、あれか、覚えている、『各部門は自部門の諸活動(定常時、非定常時、緊急時を含む)における環境側面のうち、自部門が管理できる及び影響力を及ぼせる範囲で環境側面をリストアップする』とした。環境側面の探す範囲は書いていない。強いて言えば諸活動かな?
 |  |
リストアップする前に対象範囲をどう決めるか、抜けが出ないと言えるか……ここをどう考えるか?
質問者は既にトライしてみた上での質問だろう。
規格制定と同時に出版しようと考えていたけど、まだまだ生煮えどころか検討不十分だ」
![]() 「ところで通勤は管理もできず影響も与えられないと言いましたが、それも本当にそうなのかはっきりしませんね。もう一押しすべきかと思います」
「ところで通勤は管理もできず影響も与えられないと言いましたが、それも本当にそうなのかはっきりしませんね。もう一押しすべきかと思います」
![]() 「あの……名前を聞かなかったが、あの若者は田舎の例を挙げたが、状況を知らないと何とも言えないな。
「あの……名前を聞かなかったが、あの若者は田舎の例を挙げたが、状況を知らないと何とも言えないな。
実際の審査では、あの程度の説明があれば諾とするしかないだろう」
![]() 「話は変わりますが、著しい環境側面の決定方法では、彼らはスコアリング法を十分知り尽くしているようで、その採用は問題が多いと言われましたね」
「話は変わりますが、著しい環境側面の決定方法では、彼らはスコアリング法を十分知り尽くしているようで、その採用は問題が多いと言われましたね」
![]() 「我々はイギリスで調査したとき、これが決定版だと思った。視点が違うと評価も変わるのだろうか?」
「我々はイギリスで調査したとき、これが決定版だと思った。視点が違うと評価も変わるのだろうか?」
![]() 「私もスコアリング法には反論はないと思っていたので意外でした。
「私もスコアリング法には反論はないと思っていたので意外でした。
実際にやってみれば簡単で議論の余地がないように思いますが」
![]() 「スコアリング法なら客観的だから、不具合を突っ込まれることはないと考えていたのだが」
「スコアリング法なら客観的だから、不具合を突っ込まれることはないと考えていたのだが」
![]() 「あのメガネをかけたおとなしそうな男、何と言いましたっけ?
「あのメガネをかけたおとなしそうな男、何と言いましたっけ?
彼が大分スコアリング法に拘って質問していましたね」
![]() 「吉宗機械の人だったな。スコアリング法を否定はしなかったが、スコアリング法以外を不適合にするのかと何度も質問していたな」
「吉宗機械の人だったな。スコアリング法を否定はしなかったが、スコアリング法以外を不適合にするのかと何度も質問していたな」
![]() 「彼は統一見解なるものも気にしていましたね。統一見解とは何ですか?」
「彼は統一見解なるものも気にしていましたね。統一見解とは何ですか?」
![]() 「ISO9001の審査の場で、審査員と会社側の規格解釈が相違することもある。そんなとき口のうまい審査員が、これは自分個人の考えでなく、認証機関の決めた解釈だから妥協できないという意味で使ったらしい。
「ISO9001の審査の場で、審査員と会社側の規格解釈が相違することもある。そんなとき口のうまい審査員が、これは自分個人の考えでなく、認証機関の決めた解釈だから妥協できないという意味で使ったらしい。
それ以降、認証機関を問わず広まって、認証機関の定めた見解という意味で統一見解と言われている」
![]() 「私は聞いたことなかったです。ウチでは統一見解を決めているのですか?」
「私は聞いたことなかったです。ウチでは統一見解を決めているのですか?」
![]() 「審査でももめたとき、関係部長とか古参審査員が話し合いして判断基準を決めている。明文化はしてないけど、そういうものの積み重ねはある。
「審査でももめたとき、関係部長とか古参審査員が話し合いして判断基準を決めている。明文化はしてないけど、そういうものの積み重ねはある。
あの男が、ISO規格にない要求を付け加えることはできるが、そのときはそれを対外的に公表しなければならないと言い出してから、あそこのメンバーが活気付いて困った
![]() 「考えればそれは当たり前に思えます」
「考えればそれは当たり前に思えます」
![]() 「そうかもしれないが、現状では明文化されたルールはない。もちろん対外的に公表などしていない。
「そうかもしれないが、現状では明文化されたルールはない。もちろん対外的に公表などしていない。
規格解釈で統一見解を持ち出して、相手から正当性を問われると説明できないね。
例えば環境目的は3年以上と考えているのは、小杉さんも知っているだろう。規格にはそういうことは書いてない。そう決めたのは、あまり短期の目的では会社の活動には不適当と思ったのだが」
![]() 「法改正の場合、長短ありますが3年はないですね。たいていは施行まで半年とか1年でしょう。
「法改正の場合、長短ありますが3年はないですね。たいていは施行まで半年とか1年でしょう。
環境法の中で大物と言えば廃棄物処理法ですが、ほぼ2年に一度は改正があります。公布から施行日まで短いものは10カ月、長くても1年半ですね
そうそう、これから始まる欧州の鉛はんだ禁止なんて、半田メーカーからフロー・リフローメーカー、そして電子機器製造業を巻き込んだ一大プロジェクトになりますよね。それが期間が短いから、環境目的にならないなんてありえません。
目的の条件を3年以上としたら、現実問題としておかしくないですか?」
![]() 「あの場でそう言われて、悩んでしまったよ。どうしたものかな?」
「あの場でそう言われて、悩んでしまったよ。どうしたものかな?」
![]() 「今思いついたのですが、環境目的は個々の課題でなく、カテゴリーとする考えもありますね。環境目的の定義は『環境方針から生じる全般的な環境の到達点で、組織が自ら達成するように設定し、可能な場合は定量化されるもの』です。
「今思いついたのですが、環境目的は個々の課題でなく、カテゴリーとする考えもありますね。環境目的の定義は『環境方針から生じる全般的な環境の到達点で、組織が自ら達成するように設定し、可能な場合は定量化されるもの』です。
廃棄物処理法を例にとると、個々の改正対応を目的にするのではなく、法規制を遵守することを目的として、それらいくつもある対策を目標1件とするという表現もありますね」
注:この考えは日本語の「目標」ならおかしくないが、原語は「target」だから意味が通じないように思う。
語義辞典でないが、objectiveとtargetの解説で次のような文章を見つけた。
![]()
Objectives are broad, overall aims or goals, while targets are specific, measurable milestones or benchmarks set to track progress towards those objectives.
objectiveは広範で全体的な目標であり、targetはobjectiveの進捗状況を追跡するために設定された具体的で測定可能な日程管理または成果の評価である。
このように上位・下位の階層というより、targetは進捗を管理するものと思える。
![]() 「それもありえるが、それで良いのかな?
「それもありえるが、それで良いのかな?
『objective(s)』は日本語の『目的』とはイコールではない。
Objectiveは戦争目的、戦争目的というと物騒だけど、大体こういう用語は軍事から来ているからね。
上位は戦略目的(Strategic Objectives)次が戦術目的(Tactical Objectives)そして運用目的(Operational Objectives)となる。
戦争用語はビジネスでも使われる。ビジネスで戦略目標とは、組織の全体的な方向性とビジョンを定義する高レベルの長期目標で通常 3 〜 5 年以上とされる。
戦術目的とは戦略目的をブレークダウンしたもので半年とか1年、運用目的となれば毎日の達成目標とか週や月の目標となる。
- Strategic Objectives = "Where do we want to be in the future?"
我々はどこに行くのか? - Tactical Objectives = "How do we get there?"
どうやって到達するのか? - Operational Objectives = "What do we need"
今何をすべきか?
言いたいことは、規格のobjectiveをそのいずれのobjectiveに当てても間違いではないということだ。
ゼロエミッションなら戦略目的以上かもしれず、今年廃棄物〇トン削減は戦術目的としても間違いではない。
そういう見方をすると、我々が3年以上としたのは、環境目的を戦略目的と理解したことになる。
よく部長は戦略、課長は戦術なんて言い方もある。まあ、そんな感じかな」
![]() 「そういう見方をすると、あの研究会の企業は戦略を持っていないということですか?」
「そういう見方をすると、あの研究会の企業は戦略を持っていないということですか?」
![]() 「そういう会社もあるかもしれないが、環境ISOを担当者レベルに任せると戦略に思い至らないことかもしれない。だがそうであっても、彼らが運用目的と理解しても間違いではない。
「そういう会社もあるかもしれないが、環境ISOを担当者レベルに任せると戦略に思い至らないことかもしれない。だがそうであっても、彼らが運用目的と理解しても間違いではない。
それに法改正の対応が1年以内と数年かかるものに、本質的な違いはない。
ただ、環境マネジメントプログラムという項があるね。そこでは『4.3.4その目的及び目標を達成するためのプログラムを策定』せよとある。ということは環境目的はプログラム、その精粗は分からないがWBSに展開できる程度には具体化されたものではないのだろうか。
同じ意味で、戦術目的であってもプログラムではない」
![]() 「なるほど、すると3年とかでなく長期的視点を持てと言うべきでしょう」
「なるほど、すると3年とかでなく長期的視点を持てと言うべきでしょう」
![]() 「長期的視点を持てというのも余計なお世話かもしれない。というのは、あの議論を聞いていて、私は環境目的なんて、そもそもないのかもしれないと思った」
「長期的視点を持てというのも余計なお世話かもしれない。というのは、あの議論を聞いていて、私は環境目的なんて、そもそもないのかもしれないと思った」
![]() 「環境目的がないとは?」
「環境目的がないとは?」
![]() 「私の若いころは皆ドラッカーを読んだものだ。そんな中に『企業の目的は存続すること』という言葉があった。
「私の若いころは皆ドラッカーを読んだものだ。そんな中に『企業の目的は存続すること』という言葉があった。
企業が存続するためには、さまざまな規制を守り、市場競争に勝ち、利益を出さなければならない。まあ、当たり前だ。
このとき環境というものは、たくさんある要求事項というか制約条件の一つに過ぎない。環境以外の財務、技術、CSR(企業の社会的責任)など、すべての要求事項を完璧に満たすことはできないだろうから、折り合いをつけて会社の目標を決めて進むことになる。そのとき目指すものは環境目的と呼ぶものではなく、すべてを考慮した総合的な目的だ。
思い出したのだが、数年前(1992)バランストスコアカードという考え方が発表された。経営を4つの視点(財務・顧客・業務プロセス・学習と成長)に分けて、それぞれをどのように向上させていくかを考えるものだった。
そこにISO9001も入っているのだが主要アイテムどころか刺身のつまだ。経営レベルから見れば顧客満足は重要でもISO9001などその手法の一つに過ぎないのだろう。当然環境ISOが登場しても、会社の柱ではなく、柱を強化維持するひとつの手法に過ぎないのだろう」
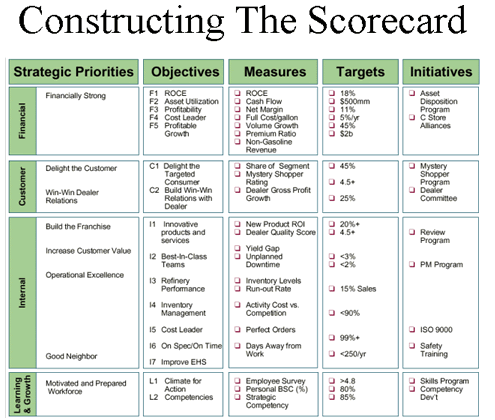
● ISO9000は、上表の3行目、右端のマスの下から2番目
![]() 「となると環境目的とは、企業の戦略目的Strategic Objectivesではなく、それを支えるTactical Objectivesレベルなのかもしれない。
「となると環境目的とは、企業の戦略目的Strategic Objectivesではなく、それを支えるTactical Objectivesレベルなのかもしれない。
ならばまず企業の長期計画を見せてもらい、それに環境対応が織り込まれているかを見るべきだ。そこに環境が考慮されていれば、その実現のための計画があるかを見ることになる。
名称などどうでも良いが、企業活動に関わる環境規制や社会の状況に合わせた環境対策が盛り込まれ、展開されているなら規格適合だろうな」
![]() 「ISO規格を作る人たちは、objectiveをそう考えているのでしょうか?」
「ISO規格を作る人たちは、objectiveをそう考えているのでしょうか?」
![]() 「それは分かりません。ただ以前から考えていることですが、現在たくさんのISOMS規格が検討されていて、これから制定されていくでしょう。
「それは分かりません。ただ以前から考えていることですが、現在たくさんのISOMS規格が検討されていて、これから制定されていくでしょう。
でもそんなにたくさんのISOMS規格が乱立して、品質方針、環境方針、情報セキュリティ方針、労働安全衛生方針を作るのか、そして方針だけでなく、それぞれの側面を把握して対応する手順を作る、監査をする、マネジメントレビューをする、そういうことになりますよね。
でも現実的に、そんなことが実行可能とも役に立つとも思えない。
すぐにそれらを統合することになるでしょう。あるいは実務と矛盾のないように、企業の負荷を少なくするように考えざるを得ない。
いずれにせよ戦略目的レベルで、環境の目的、安全の目的……なんてあるはずがない。あるのはすべてが統合された目的であるはず」
![]() 「なるほど、しかし審査の場でそこまで考えていたら仕事になりませんね」
「なるほど、しかし審査の場でそこまで考えていたら仕事になりませんね」
![]() 「審査とは一目でOK/NGが分かるものじゃないよ。いろいろな切り口で情報を集め、それをを分析して規格要求を満たすかどうかを考えることだ」
「審査とは一目でOK/NGが分かるものじゃないよ。いろいろな切り口で情報を集め、それをを分析して規格要求を満たすかどうかを考えることだ」
・
・
・
![]() 「今回多数の質問をいただき、……期限は約束しませんでしたけど、回答はしなければなりません」
「今回多数の質問をいただき、……期限は約束しませんでしたけど、回答はしなければなりません」
![]() 「そうだ。今回連中が提起した問題はたくさんあったな。いくつありましたか?」
「そうだ。今回連中が提起した問題はたくさんあったな。いくつありましたか?」
![]() 「これを見ていただければわかりますが、問題はたくさんあります。
「これを見ていただければわかりますが、問題はたくさんあります。
ただ彼らの主張は共通していますね。それは『根拠を示せ』です。不適合にするにはISO規格あるいは会社の規則に反していないとならないです」
![]() 「審査員研修で習う基本だな。とはいえ今回論点となったすべての根拠を明らかにしろと言われると……」
「審査員研修で習う基本だな。とはいえ今回論点となったすべての根拠を明らかにしろと言われると……」
![]() 「審査を受ける側としては、それは当然です。裁判なら罪刑法定主義、スポーツならルールブックが絶対です」
「審査を受ける側としては、それは当然です。裁判なら罪刑法定主義、スポーツならルールブックが絶対です」
 |
審査基準があいまいで、審査ができるのか? |  |
![]() 「分かった、分かった、すまんが向こうからもらった記録と、小杉さんが書いたメモをワープロ起こししてくれませんか。
「分かった、分かった、すまんが向こうからもらった記録と、小杉さんが書いたメモをワープロ起こししてくれませんか。
なるべく早く、幹部を集めて対策を検討したい。回答は会社として決めないとまずいから。そのときは小杉さんも出てください。
話し合った結果が統一見解になるのかな……」
数日後、産業環境認証機関の会議室である。
社長以下、総務部長、営業部長、技術部長、審査部長そして小杉審査員がいる。部長はすべて取締役である。
この他にも非常勤の取締役が数人いる。社員100名の会社で、取締役が10人もいるのは、どう考えても多過ぎだ。
 山形社長 | 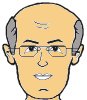 本間審査部長 | ||
 時田技術部長 時田技術部長 |
|||
三田総務部長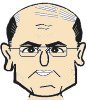 |  小杉主任審査員 小杉主任審査員 |
||
会議のテーマは、この認証機関を設立した業界団体から、規格説明の要請を受けて出向いたことの報告である。
そして多数の質問を受けて、それに対するこちらの回答がお眼鏡にかなわず苦情を出され、正式な回答として、明文化した統一見解を出す必要があることを説明した。
![]() 「何をおっしゃるかと思えば、そんなことですか。
「何をおっしゃるかと思えば、そんなことですか。
環境目的は3年以上、スコアリング法以外はダメと言い切ったら良いのです」
![]() 「いやいや、そんな強引な対応では、真面目に相手しない当社に依頼がこない恐れがあります」
「いやいや、そんな強引な対応では、真面目に相手しない当社に依頼がこない恐れがあります」
![]() 「業界傘下の企業、ましてウチの株主企業がそんなことをしようとするなら、向うのトップに申し入れしましょうや。そんな我儘されては困る。
「業界傘下の企業、ましてウチの株主企業がそんなことをしようとするなら、向うのトップに申し入れしましょうや。そんな我儘されては困る。
問題のあるのは、どの会社ですか?」
![]() 「研究会のリーダーは田中と言ってH社でしたね。その他に一家言ありそうなのが、佐川という吉宗機械でした」
「研究会のリーダーは田中と言ってH社でしたね。その他に一家言ありそうなのが、佐川という吉宗機械でした」
「H社には常勤取締役はいないな。吉宗機械は三田取締役ですね」
![]() 「一般論ですが株主企業だからと言って、ここに依頼しなければならないという縛りはありません。事業によってウチが審査できない認定範囲
「一般論ですが株主企業だからと言って、ここに依頼しなければならないという縛りはありません。事業によってウチが審査できない認定範囲
![]() 「そういうのは順次、ウチに移管してほしいのだがね」
「そういうのは順次、ウチに移管してほしいのだがね」
![]() 「方向は理解しますが、簡単ではありません。私の元勤務先は取締役を出しているのはここだけです。しかしここの株主会社にも、他の認証機関に取締役を出しているところもあるのです。
「方向は理解しますが、簡単ではありません。私の元勤務先は取締役を出しているのはここだけです。しかしここの株主会社にも、他の認証機関に取締役を出しているところもあるのです。
本間さんのところもそうでしたね」
![]() 「うーん、まあ〜、簡単ではないな」
「うーん、まあ〜、簡単ではないな」
![]() 「ところで弊社のメンバーが他の認証機関を使うと語ったのでしょうか?」
「ところで弊社のメンバーが他の認証機関を使うと語ったのでしょうか?」
![]() 「いや、彼が発言したわけではありません。そこに10人ほどいましたが、審査基準が明確でないなら、他の認証機関にも当たらなければという発言があったということです」
「いや、彼が発言したわけではありません。そこに10人ほどいましたが、審査基準が明確でないなら、他の認証機関にも当たらなければという発言があったということです」
![]() 「じゃ、しっかりした判断基準を明文化して周知すれば問題解決じゃないですか」
「じゃ、しっかりした判断基準を明文化して周知すれば問題解決じゃないですか」
![]() 「本間部長はS社出身でしたね。S社の研究会メンバーはかなり強硬でしたよ」
「本間部長はS社出身でしたね。S社の研究会メンバーはかなり強硬でしたよ」
![]() 「強硬とは?」
「強硬とは?」
![]() 「ウチの規格の読み方が甘いと言われました。法律とかULでは、文字解釈というのですか、書かれた文言をしっかり読み取り、それに則った判断をしていること。ISO審査においても、書いてないことで不適合を出してはイカン、拡大解釈をするなと厳しい発言しています」
「ウチの規格の読み方が甘いと言われました。法律とかULでは、文字解釈というのですか、書かれた文言をしっかり読み取り、それに則った判断をしていること。ISO審査においても、書いてないことで不適合を出してはイカン、拡大解釈をするなと厳しい発言しています」
![]() 「まあ、それは正論だろうな。とはいえ、時田さんが、ウチは文字解釈ではないと言ったわけではないのでしょう?」
「まあ、それは正論だろうな。とはいえ、時田さんが、ウチは文字解釈ではないと言ったわけではないのでしょう?」
![]() 「文字解釈と言ってもDISの翻訳を読んでもダメで、英語の原文をしっかり読めと言われました。
「文字解釈と言ってもDISの翻訳を読んでもダメで、英語の原文をしっかり読めと言われました。
それに翻訳だって環境目的が3年と書いてありません。そのような要求には納得しないと、大多数から反論を受けました」
![]() 「3年以上でないとダメと言い切れば良いじゃないか」
「3年以上でないとダメと言い切れば良いじゃないか」

![]() 「そんな乱暴な、それにそれじゃ文字解釈じゃありません。
「そんな乱暴な、それにそれじゃ文字解釈じゃありません。
知的財産を担当している彼らにとって、裁判など日常茶飯事ですよ。もし判定で不適合を出して、躊躇なく裁判所に提訴されたらどうします?」
![]() 「それこそ、その会社から来ている方の仕事でしょう」
「それこそ、その会社から来ている方の仕事でしょう」
![]() 「そう発言したのは本間さんの出身会社ですよ」
「そう発言したのは本間さんの出身会社ですよ」
![]() 「えっ……」
「えっ……」
![]() 「ちょっと、待ってください。
「ちょっと、待ってください。
今、我々はISO14001の規格解釈について検討しているわけですが、規格要求を超えるような判断をするつもりですか?」
![]() 「今話題にした環境目的が3年以上というのは、規格にありません。計画が3年より短いからと不適合するのは根拠がありません」
「今話題にした環境目的が3年以上というのは、規格にありません。計画が3年より短いからと不適合するのは根拠がありません」
![]() 「なぜ規格にないことを要求するのですか? その発想がおかしいでしょう」
「なぜ規格にないことを要求するのですか? その発想がおかしいでしょう」
![]() 「ISO9001の認証が
「ISO9001の認証が
環境ISOではそういうことのないように、認証したら良くなった、儲かったと実感するようなものにしたい」
![]() 「ISO認証の意味ってそういう実利を保証しているのですか。仮にそうだとして、そのような効果をISO認証が出せるものですか?
「ISO認証の意味ってそういう実利を保証しているのですか。仮にそうだとして、そのような効果をISO認証が出せるものですか?
効果を出すと言って、逆にその成果が出ないと、認証機関が提訴されたらどうしますか?」
![]() 「裁判所が受理するかどうかですが……」
「裁判所が受理するかどうかですが……」
![]() 「今までISO審査で裁判になったのはあるの?」
「今までISO審査で裁判になったのはあるの?」
「私が聞いたことがあるのは、ISO9001の審査で工場巡回中に、作業を見ていた審査員が品質改善のアドバイスをして、その結果、逆に品質問題が起きたことで民事訴訟になったというものです
![]() 「ないわけではないのか。
「ないわけではないのか。
仮に提訴されたら勝つか負けるか?」
![]() 「審査契約書では『ISO規格と会社の定めたルール』を審査基準とすると記載してありますから、ウチが審査基準を追加したなら契約不履行で負けるでしょうね」
「審査契約書では『ISO規格と会社の定めたルール』を審査基準とすると記載してありますから、ウチが審査基準を追加したなら契約不履行で負けるでしょうね」
![]() 「いや、規格から類推されることなら負けませんよ」
「いや、規格から類推されることなら負けませんよ」
![]() 「ぜひ本間さんに頑張ってもらいたいですね」
「ぜひ本間さんに頑張ってもらいたいですね」
![]() 「あとで顧問弁護士に相談しよう。ウチが追加しようとしている要求事項は、たくさんあるのか?」
「あとで顧問弁護士に相談しよう。ウチが追加しようとしている要求事項は、たくさんあるのか?」
![]() 「著しい環境側面の決定方法としてスコアリング法を推奨する予定です。推奨はともかく、その方法でないことを理由に不適合にした場合は問題になりますね」
「著しい環境側面の決定方法としてスコアリング法を推奨する予定です。推奨はともかく、その方法でないことを理由に不適合にした場合は問題になりますね」
![]() 「あれは我々が編み出した方法で、ここにいる皆さんの賛同を得ていると思います」
「あれは我々が編み出した方法で、ここにいる皆さんの賛同を得ていると思います」
![]() 「そうなのだが、他の認証機関の見解が耳に入って来ると、あれは絶対的なものではないと気が付いた」
「そうなのだが、他の認証機関の見解が耳に入って来ると、あれは絶対的なものではないと気が付いた」
![]() 「ある程度広まれば、
「ある程度広まれば、
著しい環境側面を決定する方法は、当社の講習を受けなければならないという評判が確立すれば、問題になりません」
![]() 「いや、その研究会での意見は、他の認証機関に相談するとかISOTC委員に問い合わせるとか意見が出ていました」
「いや、その研究会での意見は、他の認証機関に相談するとかISOTC委員に問い合わせるとか意見が出ていました」
![]() 「おい、小杉君、黙ってないで発言しろよ」
「おい、小杉君、黙ってないで発言しろよ」
![]() 「ハイ、その研究会のメンバーの多くは既にISO9001の認証をしており、審査経験も豊富でした。
「ハイ、その研究会のメンバーの多くは既にISO9001の認証をしており、審査経験も豊富でした。
審査で審査員と見解が異なった場合、審査中にJABのウェブサイトを見て他の認証機関に相談していると発言がありました。またISOTC委員に問い合わせたという人もいました」
![]() 「そりゃ真面目に取り組まないとまずいな。
「そりゃ真面目に取り組まないとまずいな。
全く無縁の認証機関に問い合わせたとき、相談に乗ってくれるものかい?」
![]() 「そんなのハッタリですよ。実際にはそんなことしてませんて」
「そんなのハッタリですよ。実際にはそんなことしてませんて」
「実を言ってウチにも、まったく縁のない会社から、規格解釈の相談が何度か来ています。
当社以外の認証機関の審査中だが、審査員の規格解釈がおかしいが、当社の解釈はどうなのかという問い合わせでした」
![]() 「どう対応したの?」
「どう対応したの?」
「電話を取ったのが私ではなかったのです。電話を取った者は、状況の詳細が分からないからコメントできないと断ったと報告がありました」
注:物語なので、ここでは断ったことにしたが、私の経験では断られたことはない。問い合わせに嘘は言わないだろうけど、教えたことが正しいとは限らない。
もっとも私も1社だけということはなく、3社くらいに電話すれば大体のことは分かった。
![]() 「時田部長、そういう場合、技術部に回せば回答してくれるか?」
「時田部長、そういう場合、技術部に回せば回答してくれるか?」
![]() 「そういう方針なら対応します」
「そういう方針なら対応します」
「無縁の人からの相談でも、受けたほうが評判は良くなるでしょうね。鞍替えしてくれれば御の字です」
![]() 「もちろん回答が正しければそうでしょうけど、誤った回答であれば評価は悪くなるな」
「もちろん回答が正しければそうでしょうけど、誤った回答であれば評価は悪くなるな」
![]() 「当社では誤った回答などしないよ」
「当社では誤った回答などしないよ」
![]() 「仮に著しい環境側面の決定方法をロジックゲート法でしていた会社が、審査でスコアリング法でないと難色を示されたと問い合わせあったとき、本間部長はどう答えるのですか?」
「仮に著しい環境側面の決定方法をロジックゲート法でしていた会社が、審査でスコアリング法でないと難色を示されたと問い合わせあったとき、本間部長はどう答えるのですか?」
![]() 「以前の話し合いではスコアリング法以外なら、徹底的にあら捜しをしてそれを問題にして、スコアリング法を推奨するということだったはず。
「以前の話し合いではスコアリング法以外なら、徹底的にあら捜しをしてそれを問題にして、スコアリング法を推奨するということだったはず。
スコアリング法にすべきと回答します」
![]() 「規格でスコアリング法以外はダメとなっていない以上、それは危険ですね。あとで各認証機関の考えの一覧表など作られてネットに揚げられるかもしれない。これからはインターネットの時代ですから」
「規格でスコアリング法以外はダメとなっていない以上、それは危険ですね。あとで各認証機関の考えの一覧表など作られてネットに揚げられるかもしれない。これからはインターネットの時代ですから」
注:Windows95の発売は1995年11月23日。この物語はまさに10月末である。
古くからISO認証に関わっていた人なら、某企業のウェブサイトでISO認証機関も審査員名も実名で、審査でこのように判断された、それ間違いだと大書していたのをご存じだろう。
今もあるのかと探したらありました。(2025.03.14確認済)
孔子の「過ちて改めざる、これを過ちという」ごとく、その認証機関もすぐさま訂正し、是正処置を取れば良かったのにと思う。
「三田部長は、スコアリング法はダメということですか?」
![]() 「私は転籍してきたところなので、その著しい環境側面の決定方法を議論したとき参画していない。これから勉強します。
「私は転籍してきたところなので、その著しい環境側面の決定方法を議論したとき参画していない。これから勉強します。
しかしお聞きしたところ、問題はスコアリング法の善し悪しではなく、それ以外を否定して良いのかどうかでしょう。これも勉強させてください」
![]() 「まだ先は長い。いろいろ議論してより良い形を見出そう」
「まだ先は長い。いろいろ議論してより良い形を見出そう」
![]() 「業界の研究会には再来週くらいには回答せねばなりません。回答を約束したわけではありませんが、回答しないとか回答が遅くなると、心証を悪くして、他の認証機関に依頼されるかもしれません」
「業界の研究会には再来週くらいには回答せねばなりません。回答を約束したわけではありませんが、回答しないとか回答が遅くなると、心証を悪くして、他の認証機関に依頼されるかもしれません」
![]() 「よし、時田さんが配布したこの質問に対する見解を考えてくれ。明後日の定時後に打ち合わせを持とう。小杉さんも参加してくれよ」
「よし、時田さんが配布したこの質問に対する見解を考えてくれ。明後日の定時後に打ち合わせを持とう。小杉さんも参加してくれよ」
|
|
|
 |
|
| 小杉審査員 |
私、小杉はここで一番若い、といっても52歳になる。
幹部連中の話を聞いていると、考えているのだろうがまっとうとは思えない。それに問題の先送りばかりしてそうだ。これじゃ会社の将来が危ぶまれる。
転職しようかという考えが頭をよぎる。
![]() 本日の謎
本日の謎
認証機関が訳の分からないことを言いだしたのは、どうしてなのでしょうか?
そして一旦言い出したら、決して変えないのも理解できません。
プログラムは目的用と目標用のふたつ必要と語った、某認証機関の取締役はボケていたのでしょうか?
スコアリング法以外はダメと言い続けた人は、○○の一つ覚えだったのでしょうか?
引退するまで有益な環境側面を唱え続けた某認証機関の社長は、ヒトでなくオウムだったのでしょうか?
20世紀の末に参入したいくつものノンジャブ認証機関は、規格通りの審査をした。規格以上のことをしなかった。企業担当者の多くは大いにそれを評価し歓迎した。
エスタブリッシュメントの認証機関は、そういう審査をバカにして、安かろう悪かろうと陰口した。
実際は、ノンジャブは安かろう良かろう、エスタブリッシュメントは高かろう悪かろうだったのでしょうか?
某と言いながら御芳名はしっかりと覚えております。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
この時点では当然Guide66(1999)も制定されていない。だから認証機関が定めた場合公開すれば良いということもなかったかもしれない。 | |
| 注2 |
心配になって過去10年間の公布日と施行日を確認した。間違いなかった(笑) | |
| 注3 |
認定範囲とは、認証機関が審査できる業種である。農業、林業、漁業、鉱業、採石業、食料品、飲料、タバコなどなどの区分がある。 原子力発電といっても原子炉だけでなく、そこで使われる監視カメラなどもISO9001認証を得るには原子力発電の認定を受けた認証機関でないとできなかった。認証が始まったときは原子力発電の審査できる認証機関はふたつしかなく、そこは繁盛したらしい。 | |
| 注4 |
ISO14001が制定されてからは、『ISO9001を認証しても良くなったのは文書管理だけ、ISO14001を認証して良くなったのはゴミの分別だけ』と言われた。 | |
| 注5 |
私は1996年頃にG審査員研修機関の研修でその話を聞いた。詳細は不明だ。
裁判例検索をしたが見つからなかった。(2025.03.14) 想像だが和解したのだろうと思う。和解は非公開が原則だ。 |
外資社員様からお便りを頂きました(25.03.17)
おばQさま いつも内容の濃い、経験に基づいたお話を有難うございます。 ISO14000については、直接関係しなかったので素人のたわごとです。 「ある程度広まれば、デファクトスタンダード」:これは市場次第なのでしょうね。 受験希望者が多く、認証会社が少なければ認証側の無理が通ってしまいます。 規格が普及すれば需給関係も変わり、お客の声も気にする必要あり。 力関係で変わるのは、本当はISO9001のCSを考えたら、オカシイのですけれどね。 それに日本でデファクトでも、海外で違ったら、最後は外資系にお客が流れるだけ。 「スコアリング法の問題」 以前 おばQさまも触れていましたが、ソフトウエア会社と製造会社では環境への影響も違う。 そもそも物を作っていない会社が受ける必要があるのか、でも電力は使うかもしれない。 省エネは業種に変わらず等しく環境に関係、同じ電力でもクリーンエネルギーならばスコアは変わるのか? カーボンオフセットで数値化が出来るというのも一つの考えです。 ならば、それをISOの基準に盛り込むべきだけれど、法規要求は無く、EUですらやっていない。 それで企業の価値が上がるのかといえば、高いエネルギー代を払えるというアピールでしかなかった気がします。 一時流行った再生紙アピールも消えたし、土に返るお皿も東オリが終わったら消えました。 優等生のGoogle,Amazonは、データセンターの電力に原子力を使う事を表明。 原子力エネルギーがクリーンで再生可能なのかは企業の立場で表明したとも言えます。 ならば、それに対して、認証会社が違うと言えるかは、「デファクトだぁ」何て浅い問題じゃない。 結論を言えば、「スコアリング法」の問題は、判定基準が明確でない点に尽きる気がします。 当時なら無邪気に原子力エネルギーはクリーンで持続可能と言えたかもしれませんが、それでも反対勢力はおりました。 当時の政治がらみの問題まで、スコアリング法は解決できるほど普遍的な価値基準をもっていないですよね。 素人考えなので、間違いはご指導ください。 |
外資社員様、毎度厳しいご指摘、ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 言い訳させてもらうと、そのあたりは次回、次々回で話を進める(というか解説を)予定です。 現実を振り返ると、ISO14001認証が始まった数年間、トップシエアを占めた某認証機関はスコアリング法を広めてデファクトスタンダードの地位を占めたのは事実です。欧州から見たら笑われるというのは事実でしょう。私が1998年頃タイで14001の指導をしたとき、現地の審査員と話したことがありますが、スコアリング法を笑われました。まあ私が推薦していたのではないので気は悪くはしませんでしたが、日本の恥と思いました。 なぜおかしな方法がデファクトスタンダードの地位を得たのかとなると、多くの認証機関は独自の方法を提案しなかったからだと思います。実名を挙げますがBV社は、解説本でフィルタリング法を示しています。そういう方法が広まれば、スコアリング法はおかしいぞと、裸の王様を嗤うようになったと思いますが、そうはならなかったのです。 それはおかしいと思います。どうしてなのでしょうか? スコアリング法を広めた認証機関の話を聞いた某ISOTC委員は「環境側面を決めるとはこうするのか」と感動したと言ったそうです。ISO規格を作る人が頭の中で考えただけで、自分なら要求を満たすにはどうするかを考えなかったのが問題かもしれません。 とはいえ欧州でもアメリカでも、スコアリング法を推薦するウェブサイトも論文も見当たらないですから、ISOTC委員みんながみんなおかしいわけではなさそうです。 単純に物価を下げろとか、国家の借金がとか、訳も分からず騒いでいる程度だから騙されてしまうということですかね? 認証機関の幹部にスコアリング法以外でも良いと確認を取っていても、来る審査員がスコアリング法以外では難癖をつけたという経験から、認証機関単位で信じているのでもなさそうで、そうなると審査員全体のレベルの問題なのか、まったく見当が付きません。 今現在、ネットに上がっている環境側面の決定方法の9割はスコアリング法を説明しているのは間違いない事実です。本屋に並んでいる本でも9割はスコアリング法です。そうでない本は詳しく書かないで逃げています。もっとも環境側面を解説した本はここ数年は発行されていません。 最後に歌を一曲 時が過ぎ、風あざみ、 環境側面も彷徨えば ISOは夢花火、私の心は夏模様 井上陽水の少年時代で歌ってください。 支離滅裂と言わないでください。元々の歌詞も意味不明ですから。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |