注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
承前、産業環境認証機関で会議があった翌日である。
山形社長は佐川に来てもらい話を聞けと指示した。とはいえ部下とか取引先ではない、
 | ||
そもそも取引があるわけではない。単に電話一本で来てくれでは失礼だろうし、話し合いにどういう立場で来てもらうのか。
総務部長か技術部長名で、新しい認証規格について懇談したいというのがいいのか、そもそも顧客でもない企業の人を呼びつけるなんてありえないし、理由づけがない……
真面目に考えると、立場とか会合の位置づけとか悩むのである。
考えあぐねた結果なのだろう、その日の夕方に時田技術部長の名で佐川にメールが来た。もちろん佐川は、そんな議論があったとは知る由もない。
メールの要旨は
|
先日、業界団体でお会いしたこと、三田総務部長が訪問して話を伺って聞いたことにいたく関心を持った。故に一度、認証機関に来てお考えを聞かせてほしいこと、 業界団体で佐川氏と若い人が一緒だったので、ぜひその方にも同行願いたい。 日時については貴方にて都合の良い日時をいくつか指定してほしい。時間は3時間程度を考えていること。 終了後に一席設けたいとある。 |
そんなことであった。
佐川は椅子に寄りかかってしばし考える。一体全体どういう風の吹き回しだろう。
 三田さんはここでの話をどのように伝えたのだろう。ここで佐川の話を聞いたときは納得されたようだったが、本意はそうではなかったのか。
三田さんはここでの話をどのように伝えたのだろう。ここで佐川の話を聞いたときは納得されたようだったが、本意はそうではなかったのか。
あるいは三田さんの話を聞いて他の人たちが佐川に反論したいのか?
あり得ないとは思うが、佐川の論に興味を持って聞きたいというのか?
佐川の後ろを吉井部長が通りかかり、声をかけた。
![]() 「佐川君、どうかしたか? 気が抜けたようだぞ」
「佐川君、どうかしたか? 気が抜けたようだぞ」
![]() 「あっ、部長、ぜひ相談に乗ってください」
「あっ、部長、ぜひ相談に乗ってください」
・
・
・
会議室を使うほどの話でもないだろうと、パントリーのそばの椅子とテーブルのところに座る。
![]() 「というわけです。行くべきか行かざるべきか?」
「というわけです。行くべきか行かざるべきか?」
![]() 「別に命を取られるわけでもあるまいし、行かないという選択肢はないな。
「別に命を取られるわけでもあるまいし、行かないという選択肢はないな。
むしろ相手の考えを聴取して、どう対応するか考えることに意味がある」
![]() 「おっしゃる通りですね。何かあっても、私が気を悪くするだけのこと」
「おっしゃる通りですね。何かあっても、私が気を悪くするだけのこと」
![]() 「三田さんからお前の話を聞いて、向うは必死に規格の解釈を考えているだろう。彼らの考えと異なる佐川君の考えを聞きたいのが、正直なところだろう。君を論破するために呼ぶわけではあるまい」
「三田さんからお前の話を聞いて、向うは必死に規格の解釈を考えているだろう。彼らの考えと異なる佐川君の考えを聞きたいのが、正直なところだろう。君を論破するために呼ぶわけではあるまい」
![]() 「やり取りとしては私がボールを投げたのですから、投げ返される質問を受ければ良いのですね」
「やり取りとしては私がボールを投げたのですから、投げ返される質問を受ければ良いのですね」
![]() 「そういうスタンスで良いだろう。
「そういうスタンスで良いだろう。
それと主役は君だけではない。メールにあったように、山口も連れていって議論に参加させろよ。それが教育だ」
![]() 「承知しました」
「承知しました」
こちらはその頃の産業環境認証機関である。時田技術部長と本間審査部長が話をしている。
![]() 「本間さん、イギリスで著しい環境側面を決める方法を習ったときのことを思い出すと、スコアリング法がメインではなかったですよね」
「本間さん、イギリスで著しい環境側面を決める方法を習ったときのことを思い出すと、スコアリング法がメインではなかったですよね」
![]() 「そうだっけか? もう1年近くなる。忘れちゃったなあ〜」
「そうだっけか? もう1年近くなる。忘れちゃったなあ〜」
![]() 「初めに教えられたのは文章だけの、あまり論理的にまとまっていないものでした。
「初めに教えられたのは文章だけの、あまり論理的にまとまっていないものでした。
考えられるいろいろな環境側面を調べ上げて、エクセルの表にまとめ、それぞれをいろいろな観点から吟味するとあったと記憶しています」
![]()
 「だんだんと思い出した。評価する人の考え次第で、どうとでもなるようなものだったな」
「だんだんと思い出した。評価する人の考え次第で、どうとでもなるようなものだったな」
![]() 「本間さん、今になって気付いたのですが、あれを曖昧だと受け取ったのが間違いだったかもしれません」
「本間さん、今になって気付いたのですが、あれを曖昧だと受け取ったのが間違いだったかもしれません」
![]() 「おいおい、今になって何か気づいたのかよ」
「おいおい、今になって何か気づいたのかよ」
![]() 「まあまあ、あれはスクリーニング法だったのではないでしょうか?
「まあまあ、あれはスクリーニング法だったのではないでしょうか?
資料がここにありませんので記憶ですが……
ええと著しい環境側面を決定する手順としてまず一番目は、その環境側面に関連する法規制があるかどうか調べる、ないときは次に進む、
その環境側面は環境に悪影響があるかでしたね」
![]() 「今もその資料を持っているかい?
「今もその資料を持っているかい?
私は忘れてしまったようだ。あれば、それを見せてくれ」
時田は自分の席に行きロッカーを漁り、A4紙ファイルを数冊持って来る。
![]() 「ありました、これでしたね。
「ありました、これでしたね。
これ
法規制に該当しないときは次の設問に進み、その側面が、環境への悪影響がある、影響するおそれがある、ない、に分けて2点・1点・0点と点数を付けます。次に発生可能性がアリに1点・ナシに0点を付ける。
次にその環境側面に罰金があるかないかを調べて、アリ1点・ナシ0点を付ける」
![]() 「法規制への該非と罰金の有無って、ダブっていないのか?
「法規制への該非と罰金の有無って、ダブっていないのか?
法規制がなくて罰金があるなんてありえないだろう」
![]() 「翻訳したとき、上手く日本語に当てはまる語がなかったのか、普通の辞書と異なる意味なのか?
「翻訳したとき、上手く日本語に当てはまる語がなかったのか、普通の辞書と異なる意味なのか?
とりあえずそれは置いといて、進みましょう。
ええと、その続きですが、そこからが、なぜか複雑な方法で評点を付けますね。説明を受けたときは納得したのですが、今はその理由を思い出せません」
![]() 「つまりこの方法は、フィルタリング法とスコアリング法のハイブリッドなのか?」
「つまりこの方法は、フィルタリング法とスコアリング法のハイブリッドなのか?」
![]() 「法規制、罰金、事故発生についてはイチゼロ判定で著しい環境側面にして、そうでないものは量的と発生可能性に評点を付けて計算し、著しいものの該非を決める仕組みですね。
「法規制、罰金、事故発生についてはイチゼロ判定で著しい環境側面にして、そうでないものは量的と発生可能性に評点を付けて計算し、著しいものの該非を決める仕組みですね。
我々は最初にこれが複雑だとして、もっと簡単で誰でも判定できるものを考えたのですね。
それでフィルタリングの段階を省いて、スコアリング法のみにした……私はそう覚えています」
![]() 「そうだったかもしれん。最初に教えられた方法は、それなりに理屈付けがしてあったのかな。
「そうだったかもしれん。最初に教えられた方法は、それなりに理屈付けがしてあったのかな。
演習問題がなかったから、文章を読んで手順が複雑と思ったのだろう。当時、自分の考えたがどうだったのか思い出せない」
![]() 「そしてこのときのスコアリング法ですが、環境側面に点数を付けて著しいかどうかを判断していますが、環境側面同士での点数の比較をしていませんね」
「そしてこのときのスコアリング法ですが、環境側面に点数を付けて著しいかどうかを判断していますが、環境側面同士での点数の比較をしていませんね」
![]() 「ええと、それはどういう意味?」
「ええと、それはどういう意味?」
![]() 「ひとつの環境側面において絶対基準で該非を判断するので、他の環境側面との相対評価じゃないということです」
「ひとつの環境側面において絶対基準で該非を判断するので、他の環境側面との相対評価じゃないということです」
![]() 「うーん、すると各環境側面の点数を計算して順位付けするという発想は、どこから来たのだろう?」
「うーん、すると各環境側面の点数を計算して順位付けするという発想は、どこから来たのだろう?」
![]() 「出張者の中で、著しい環境側面が多いとか少ないときどうするか、という議論があったじゃないですか。そのとき誰だっけかな、著しい環境側面の数が一定範囲になるように、工夫をしようと言い出したのです。
「出張者の中で、著しい環境側面が多いとか少ないときどうするか、という議論があったじゃないですか。そのとき誰だっけかな、著しい環境側面の数が一定範囲になるように、工夫をしようと言い出したのです。
誰だか思い出せませんが、労働安全衛生でのことを持ち出して、それを取り入れた記憶があります。労働安全衛生のリスク評価では発生頻度と危害の程度のマトリックスで評価するらしいです」
![]() 「そうだったのか。その理屈は正しいのか、間違いなのか?」
「そうだったのか。その理屈は正しいのか、間違いなのか?」
![]() 「労働安全衛生の手法が、環境影響評価に使えるのかどうか、ちと分かりません」
「労働安全衛生の手法が、環境影響評価に使えるのかどうか、ちと分かりません」
![]() 「著しい環境側面の数を、ある程度にするという考えはどういう理由だっけ?」
「著しい環境側面の数を、ある程度にするという考えはどういう理由だっけ?」
![]() 「私も覚えていません。今まで環境目的は著しい環境側面から選ぶと考えていました。その理屈では著しい環境側面は最低でも5つ6つは必要となりますが、他方、手順を作ったり教育訓練をするには、多すぎると困るということはありました。
「私も覚えていません。今まで環境目的は著しい環境側面から選ぶと考えていました。その理屈では著しい環境側面は最低でも5つ6つは必要となりますが、他方、手順を作ったり教育訓練をするには、多すぎると困るということはありました。
でも三田部長が聞きましたが、環境目的は方針と整合させるのであって、著しい環境側面から選ぶのではないのでした。それに著しい環境側面が多くても、『管理しなければならないものは管理しなければならない』というのは真理ですね。
多い少ないというのは、どうでも良いことのように思えます」
![]() 「いずれにしてもイギリスで習った方法を、我々はだいぶ変えてしまったわけだ。
「いずれにしてもイギリスで習った方法を、我々はだいぶ変えてしまったわけだ。
イギリスに行ったメンバーを集めて再度、検討会をしようか?」
![]() 「もう1年近く前ですから、もう皆さん忘れているでしょう。私も経緯や議論がどうだったか忘れてしまいました。ですから集まって議論しても意味がないと思います。
「もう1年近く前ですから、もう皆さん忘れているでしょう。私も経緯や議論がどうだったか忘れてしまいました。ですから集まって議論しても意味がないと思います。
あの頃は予定より遅れていて、気をもんでいましたからね」
![]() 「確かにあの時は、とにかくなにか手っ取り早く成果を出そうとしたのだな。
「確かにあの時は、とにかくなにか手っ取り早く成果を出そうとしたのだな。
視野狭窄になっていたのかもしれん」
吉宗機械である。佐川と山口が話している。
![]() 「私は基本的に、文字解釈からはずれたらおかしいと思います。それと今まで佐川さんから聞いた、認証機関や審査員のユニークな要求事項は根拠があいまいですよね。それは絶対に納得いきません。
「私は基本的に、文字解釈からはずれたらおかしいと思います。それと今まで佐川さんから聞いた、認証機関や審査員のユニークな要求事項は根拠があいまいですよね。それは絶対に納得いきません。
佐川さんは不適合を出されたとき、どうして拒否しなかったのですか?」
佐川は山口からそう言われ、苦笑いする。
![]() 「山口さん、それは上長が審査員の判断を受け入れてしまったからです。環境マネジメントプログラムが目的用、目標用が必要だと寝ぼけたことを語る審査員は多かった。いや、これから大発生するはずだ。
「山口さん、それは上長が審査員の判断を受け入れてしまったからです。環境マネジメントプログラムが目的用、目標用が必要だと寝ぼけたことを語る審査員は多かった。いや、これから大発生するはずだ。
私は断固拒否しようとしたのだが、部長が審査員は我々のためを思って言ってくれたから受け入れることにすると、バカなこと言うんだよね。もう手がなかった」
![]() 「吉井部長ならそこは大丈夫でしょう」
「吉井部長ならそこは大丈夫でしょう」
![]() 「そう期待したい。でも我々レベルでは、審査員がバカなことを言わないように、釘を刺しておかねばならない。当社だけでなく関連会社もあるし、世のため人のためでもある。
「そう期待したい。でも我々レベルでは、審査員がバカなことを言わないように、釘を刺しておかねばならない。当社だけでなく関連会社もあるし、世のため人のためでもある。
社内的にもすることはある。そういう状況になれば、相手の判断が間違いであることの証明と、受け入れることによる費用増加を、はっきりと説明しなければならない」
![]() 「大丈夫ですよ、そこんところは」
「大丈夫ですよ、そこんところは」
約束の日、10分前に認証機関に着いた。1990年代の認証機関の窓口は、しまっているドアの外から、インターフォンで呼びかけるなんて不人情な仕組みではなかった。
 美人かどうかはともかく、若い女性が座っていて客が来ると愛想笑いをしてくれた。
美人かどうかはともかく、若い女性が座っていて客が来ると愛想笑いをしてくれた。
もちろん、生きている受付がいればサービスが良いとは限らない。
アポイントがあるのを知っていて、受付は二人をすぐに……例の小部屋ではなく……更に奥の10人ほど入れる会議室に案内した。
待つほどもなく出席者が入室する。
三田部長には会社で会ったし、時田技術部長は先日、業界会館で名刺交換した。初対面の方は、薄営業部長と本間審査部長だった。
三田総務部長が司会をするらしい。まずはメンバーの紹介があった。
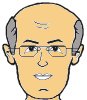 本間審査部長 本間審査部長 |
||
佐川 |  時田技術部長 時田技術部長 |
|
山口 | ||
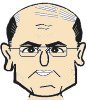 三田総務部長 三田総務部長 |
![]() 「ええと今回のテーマですが、先日の業界団体での話し合いで、業界の環境ISO研究会メンバーから頂いたご質問に対する返答をするにも、弊方は未だ回答を検討中です。もちろん、皆さんは研究会の代表でもありません。
「ええと今回のテーマですが、先日の業界団体での話し合いで、業界の環境ISO研究会メンバーから頂いたご質問に対する返答をするにも、弊方は未だ回答を検討中です。もちろん、皆さんは研究会の代表でもありません。
それで皆さんのお考えを聞いて、回答の参考にさせていただきたいと考えております。
まあ、そこまでいかずとも主たるご質問について意見交換できればと考えております」
![]() 「それは大変ありがたいことです。ただ三田部長さんもおっしゃったように、私たちは研究会の代表ではありません。ですから、もし私どもの発言が参考になったとしても、業界の研究会への回答は御社で検討した結果であることを明確にしてください。
「それは大変ありがたいことです。ただ三田部長さんもおっしゃったように、私たちは研究会の代表ではありません。ですから、もし私どもの発言が参考になったとしても、業界の研究会への回答は御社で検討した結果であることを明確にしてください。
なお、本日、山口と私の発言は、吉宗機械の見解ではなく環境担当としての見解、意見であると受け取ってください。ただ工場などを意見を集めておりますから、当社の担当者の総意であることを申し添えておきます」
![]() 「了解しました。
「了解しました。
そいじゃ時田さん、本間さんからランダムでよろしいですから発言してください。
時間は限られていますから、絶対に議論したいというものを優先してください」
![]() 「まず3年目標だが、一般的にobjectiveの翻訳には、企業の長期計画が当てられていると思う。企業の長期計画となると最低3年、通常は5年だ。そういう意味で3年としていた。
「まず3年目標だが、一般的にobjectiveの翻訳には、企業の長期計画が当てられていると思う。企業の長期計画となると最低3年、通常は5年だ。そういう意味で3年としていた。
故に目的が3年必要と解したのだが、いかがだろうか?」
![]() 「笑わないで欲しいのですが、私は予言者と自認しています。3年、5年でなく、20年ほど先まで見えます。
「笑わないで欲しいのですが、私は予言者と自認しています。3年、5年でなく、20年ほど先まで見えます。
目的が3年以上とした場合、問題になります。多くの認証機関は業界のリーダーたる御社の見解を尊重して、目的3年というのを要求事項としています。その結果、環境目的が3年に満たないものを不適合とする判定の多発です。
しかしISOMS規格もISO認証もグローバルなものです。日本国内でも外資系は、今後もかなりのシエアを占め続けます。
そのとき3年未満を不適合とする認証機関と、適合とする認証機関が併存するわけで、企業担当者にとって大きな不満となります。当然3年という要求に反旗が翻ります」
![]() 「予言者ですか、いろいろこれからのことをお聞きしたいですね。
「予言者ですか、いろいろこれからのことをお聞きしたいですね。
それはともかく、おっしゃる意味は分かりました。内部で検討いたします」
![]() 「常識ですが審査や監査において、不適合を立証するには、不適合になる根拠、不適合の証拠が絶対に必要です。いずれかを示せなければ不適合ではありません。
「常識ですが審査や監査において、不適合を立証するには、不適合になる根拠、不適合の証拠が絶対に必要です。いずれかを示せなければ不適合ではありません。
今後、特に21世紀になりますと、異議申し立ては重大な決心がいるものではなく、気軽に認証機関に異議申し立てするようになります。それを覚えておいてください」
![]() 「根拠のない不適合は拒否されるということかな」
「根拠のない不適合は拒否されるということかな」
![]() 「そうです」
「そうです」
![]() 「研究会の席で、環境目的の環境マネジメントプログラムと環境目標の環境マネジメントプログラムが必要ということを申しましたが、これについては環境目的と環境目標を満たすなら環境マネジメントプログラムがひとつで良いと解釈します」
「研究会の席で、環境目的の環境マネジメントプログラムと環境目標の環境マネジメントプログラムが必要ということを申しましたが、これについては環境目的と環境目標を満たすなら環境マネジメントプログラムがひとつで良いと解釈します」
![]() 「了解しました」
「了解しました」
![]() 「著しい環境側面を決定する手法を、いろいろ議論しておるんだがね。
「著しい環境側面を決定する手法を、いろいろ議論しておるんだがね。
佐川さんは、どういう方法が好ましいと考えているのか、お聞きしたい」
![]() 「私が考えるまでもなく、規格要求を満たすものなら、どんなものでも適合となります。それが理屈です」
「私が考えるまでもなく、規格要求を満たすものなら、どんなものでも適合となります。それが理屈です」
![]() 「規格要求とは?」
「規格要求とは?」
![]() 「ドラフトの4.3.1に書いてある通りです。
「ドラフトの4.3.1に書いてある通りです。
お断りしておきますが、私はスコアリング法が悪いとは申しておりません。ただその配点表を作るのは、とても困難だろうと思います。はっきり言えば完成しないでしょう」
![]() 「佐川さんはスコアリング法を批判されていたと思いますが?」
「佐川さんはスコアリング法を批判されていたと思いますが?」
![]() 「そうではありません。私はスコアリング法以外を不適合とすることは間違いであると言いました。
「そうではありません。私はスコアリング法以外を不適合とすることは間違いであると言いました。
スコアリング法を間違いと言ったのではありません」
![]() 「ああ、了解しました」
「ああ、了解しました」
![]() 「スコアリング法以外となると、具体的にどんなものになるのかね?」
「スコアリング法以外となると、具体的にどんなものになるのかね?」
![]() 「著しい環境側面を決定する方法は、定義を読んでも、環境側面の4.3.1項を読んでも分からないのですよ。それは本文の中で著しい環境側面について書かれているところを熟読するしかない。
「著しい環境側面を決定する方法は、定義を読んでも、環境側面の4.3.1項を読んでも分からないのですよ。それは本文の中で著しい環境側面について書かれているところを熟読するしかない。
おっと、釈迦に説法ですね、
著しい環境側面について書かれているのは多くありません。法規制に関わる、手順を決めないと問題が起きる、教育訓練をしないと問題が起きる、外部コミュニケーションが必要、目的策定の際考慮する、経営層に報告が必要、の6点です。
逆説的になりますが、それが著しい環境側面であるということです。
ですからそれを選び出す方法ならすべて適合だと思います」
![]() 「その表現ならフィルタリング法一択になってしまうね?」
「その表現ならフィルタリング法一択になってしまうね?」
![]() 「そうは限りません」
「そうは限りません」
![]() 「他に良い案があれば教えてほしいですね」
「他に良い案があれば教えてほしいですね」
![]() 「今現在、ISO14001を認証している企業はありません。まだ制定されていませんからね。しかし企業はISOMS規格登場の、はるか前から存在しています。
「今現在、ISO14001を認証している企業はありません。まだ制定されていませんからね。しかし企業はISOMS規格登場の、はるか前から存在しています。
世の中のたくさんある企業の中には、法違反や事故を起こして、ときたま新聞記事にはなりますが、違反や事故を起こす企業の割合は微々たるものです。
じゃあ、なぜ違反しない、事故を起こさない企業が多いのかとなれば、そういう仕組みを備えているからです」
![]() 「えっ、すみません、理解できないが」
「えっ、すみません、理解できないが」
![]() 「新しい化学物質、大げさなことではなく新規のプラスチックや塗料を採用するとき、労働安全衛生法ではMSDSなどを入手して、安全や衛生に対応すること、資格者が必要なら用意することを決めています。危険物については、消防法もありますね。
「新しい化学物質、大げさなことではなく新規のプラスチックや塗料を採用するとき、労働安全衛生法ではMSDSなどを入手して、安全や衛生に対応すること、資格者が必要なら用意することを決めています。危険物については、消防法もありますね。
おっと、プラスチックといっても、遮断型最終処分場でないと不味いという物質もあります。
機械についても安全衛生の規制もあり、公害防止の観点からも導入前に、企業は事前審査をして対応するはずです。
何を言いたいかと言えば、そういうフィルターをかけて採用しているわけで、その結果、著しい環境側面という言葉を使ってはいないけれども、現実には先ほど言いました6項目の対応をしているということです。
逆説的に言えば、今わざわざ著しい環境側面を探し回るのではなく、過去より法対応のルールを作る、教育する、有資格者を育成する、外部コミュニケーション……つまり行政報告、申請、町内会と協定を結ぶ、経営層に報告するといったことをしており、すなわちそれば著しい環境側面なわけです。
簡単でしょう」
![]() 「えっ!」
「えっ!」
![]() 「というと何もしないで良いということになりますか?」
「というと何もしないで良いということになりますか?」
![]() 「そうはなりません。企業のすることは変わらないとしても、ISO審査のために著しい環境側面のリストとかは作らないとならない」
「そうはなりません。企業のすることは変わらないとしても、ISO審査のために著しい環境側面のリストとかは作らないとならない」
![]() 「ISO14001はマニュアルを要求しないと聞きました。
「ISO14001はマニュアルを要求しないと聞きました。
それに、ドラフトにリストを作れとありましたか?」
![]() 「ドラフトにはなかった。しかし認証機関はマニュアルがなしでは審査できないから、マニュアルを作り提出することを審査契約書に盛り込むだろう。
「ドラフトにはなかった。しかし認証機関はマニュアルがなしでは審査できないから、マニュアルを作り提出することを審査契約書に盛り込むだろう。
更に環境マニュアルには、法規制一覧表、著しい環境側面一覧表、目的目標の一覧、そして環境マネジメントプログラムを盛り込むこと、又は添付するように書き込むはずだ。
いや、私の予言ですよ。産業環境認証機関さんではマニュアルなど要求しないかもしれない。実際にイギリス系の認証機関は要求していなかったはずだ」
![]() 「審査契約書などまだ作っておりません。しかし弊社では環境マニュアルに要点を網羅していただいた方が、効率的な審査が行えると考えております。
「審査契約書などまだ作っておりません。しかし弊社では環境マニュアルに要点を網羅していただいた方が、効率的な審査が行えると考えております。
おっしゃるように審査契約書に提出文書として盛り込む予定です」

![]() 「アハハハ、参ったな。佐川さんは予言者に間違いないようだ」
「アハハハ、参ったな。佐川さんは予言者に間違いないようだ」
![]() 「フィルタリング法とかロジックゲートでさえない、というのを聞いて驚きました。
「フィルタリング法とかロジックゲートでさえない、というのを聞いて驚きました。
いや、全く異なったアプローチですな」
![]() 「佐川さんのお話を聞いていると、過去よりある仕組みを最大限に活用すると聞こえました。それはそれで意味のあることだと思いますが、ISO規格を基に会社の改革、改善を図るという意図もあると思います。それはどう考えますか?」
「佐川さんのお話を聞いていると、過去よりある仕組みを最大限に活用すると聞こえました。それはそれで意味のあることだと思いますが、ISO規格を基に会社の改革、改善を図るという意図もあると思います。それはどう考えますか?」
![]() 「ISO認証を使って革新を図るのですか? それは可能でしょうか?
「ISO認証を使って革新を図るのですか? それは可能でしょうか?
ISO14001のタイトルは『環境マネジメントシステムの仕様及び利用の手引き』です。設計書ではなく仕様書です。規格はすべて『組織は、何々すべし』と要求するだけです。
何を言いたいかと言えば、ISO14001……ISO9001も同じですが、それを基に会社の仕組みを作ることはできません」
![]() 「ISO規格を基に会社の仕組みを作れない……どうして?」
「ISO規格を基に会社の仕組みを作れない……どうして?」
![]() 「ISO規格は達成することを要求しますが、どのように(How)するかは書いてない。
「ISO規格は達成することを要求しますが、どのように(How)するかは書いてない。
そしてマネジメントシステム、つまり会社の仕組みは業種や社風や従業員によって異なるものになります」
![]() 「9001は品質保証の規格とあるし14001は環境マネジメントシステムの規格とあるが、本当はいずれもマネジメントシステムの標準化ではないのか?」
「9001は品質保証の規格とあるし14001は環境マネジメントシステムの規格とあるが、本当はいずれもマネジメントシステムの標準化ではないのか?」
![]() 「ISO9000という規格があります。ISO9000シリーズには3種類
「ISO9000という規格があります。ISO9000シリーズには3種類
あっ、今は1994年版ですね。そちらでは序文でなく、本文にしっかり書いてあります
![]() 「ISO14001になくちゃ意味がないだろう」
「ISO14001になくちゃ意味がないだろう」
![]() 「ISO9001のことを話したのは、ISO9001も会社の仕組みであるマネジメントシステムの標準化を目指してはいないということを言いたかったのです。
「ISO9001のことを話したのは、ISO9001も会社の仕組みであるマネジメントシステムの標準化を目指してはいないということを言いたかったのです。
ISO14001はまだ制定されていませんが、ドラフトにはちゃんとあります。
ええと序文の一番後ろだったと思いますが、『この規格に規定する環境マネジメントシステムの要求事項は、既存のマネジメントシステム要素と独立に設定される必要はない。場合によっては、既存のマネジメントシステム要素を当てはめることによって、要求事項を満たすことも可能である
要するに規格制定者は、マネジメントシステム……環境マネジメントシステムではありませんよ、会社の包括的なマネジメントシステムです、その中にISOMS規格要求事項が盛り込んであれば良いと言っているのです」
![]() 「なるほど、ISO規格とはそう読むのですか」
「なるほど、ISO規格とはそう読むのですか」
![]() 「ISO規格の専門家が、そんなことをおっしゃってはいけません。
「ISO規格の専門家が、そんなことをおっしゃってはいけません。
私はISO規格が好きだとか、読むのが仕事だというわけではありません」
![]() 「佐川さんは環境担当をされていたと聞きましたが」
「佐川さんは環境担当をされていたと聞きましたが」
![]() 「単に品質保証に流れ着き、ISO9001を担当し、その流れでISO14001が登場したら担当したというだけですよ」
「単に品質保証に流れ着き、ISO9001を担当し、その流れでISO14001が登場したら担当したというだけですよ」
![]() 「それでは次の論点に移りましょう……」
「それでは次の論点に移りましょう……」
・
・
・
1時間半ほど過ぎて、一旦休憩しようとなった。
休憩と言ってもお互い顔を見れば疑問を問い、意見が異なれば議論になり、何も変わらない。
![]() 「私も技術部長なんて拝命してますが、佐川さんの知識には舌を巻きました。いろいろなISO規格を読んで暗記しているのですね」
「私も技術部長なんて拝命してますが、佐川さんの知識には舌を巻きました。いろいろなISO規格を読んで暗記しているのですね」
![]() 「ISO規格を読むのにも、いろいろな読み方があります。
「ISO規格を読むのにも、いろいろな読み方があります。
法律を読むには成文法主義というのがあります。これは書き表された法律を尊重する考え方です。
よく法の趣旨はそうじゃないなんて語る人がいます。法律を作った議員でさえ言いますね。『そういう意図で作った法律じゃない』なんて……
それは大きな間違い勘違いでしょう。書かれた文言が唯一の根拠です。
もしISOTC委員が『規格の意図はそうじゃない』と言ったら、まともに規格も作れないのかと思われるだけです。もちろん法の趣旨は違うという議員も同様です。
成文法主義から演繹されるのは、文字解釈(文理解釈)しかありません」
![]() 「すまん、文字解釈とはなんだね?」
「すまん、文字解釈とはなんだね?」
![]() 「法令や規格に書かれた字面通り、何も加えず何も省かずに、忠実に解釈することです。これは野球のルールブックでもゲームのルールでも皆同じです。
「法令や規格に書かれた字面通り、何も加えず何も省かずに、忠実に解釈することです。これは野球のルールブックでもゲームのルールでも皆同じです。
文字解釈の対義語は論理解釈で、条文の趣旨や目的、関連する法律との整合性を考慮して解釈することです。ISO規格ではこれをしちゃいけません。
環境目的は何年と書いてないのですから、『何年ですか?』という質問には決めてないという回答しかありません。同様に著しい環境側面の決定方法を、規格は決めてないのだから、規格要求を満たす限り、どんなものでもOKです
おっと、文字解釈が通用するには、英語原文を読む前提です。和訳を文字解釈しても意味がありません」
![]() 「環境マネジメントプログラムが二つとは書いてないから一つで良いと」
「環境マネジメントプログラムが二つとは書いてないから一つで良いと」
![]() 「それはちょっと違います。規格では『目的及び目標を達成するためのプログラムを作れ(4.3.4)』とあります。ですから、それを満たすならひとつでもふたつでも、多数でも良いのです。
「それはちょっと違います。規格では『目的及び目標を達成するためのプログラムを作れ(4.3.4)』とあります。ですから、それを満たすならひとつでもふたつでも、多数でも良いのです。
英語原文は『programme(s)』と、単数でも複数でもOKと書いてあるでしょう」
注:環境マネジメントプログラムは目的用と目標用が必要だとCEAR誌に書き、批判されると切れたT審査員は、この(s)の意味を理解できなかったのだろうか?
![]() 「あっ、なるほど……」
「あっ、なるほど……」
![]() 「佐川さんは予言者と言ったね、これからのISO認証はどうなるのだ?」
「佐川さんは予言者と言ったね、これからのISO認証はどうなるのだ?」
![]() 「それは予言者でなくても、誰にだって分かるはずです。まして営業部長さんなら、見えなくちゃいけません」
「それは予言者でなくても、誰にだって分かるはずです。まして営業部長さんなら、見えなくちゃいけません」
「えっ、営業部長なら先が読めなくちゃいけないの?」
![]() 「今、ISO9001の認証件数は急上昇しています。それをみて喜んでいると思います。ですが、認証している企業は認証が必要なわけではありません」
「今、ISO9001の認証件数は急上昇しています。それをみて喜んでいると思います。ですが、認証している企業は認証が必要なわけではありません」
| 期 | ||
| 1994-Q3 | 755 | |
| 1994-Q4 | 928 | |
| 1995-Q1 | 1,078 | |
| 1995-Q2 | 1,232 | |
| 1995-Q3 | 1,377 | |
| 1995-Q4 | 1,619 | |
| 1996-Q1 | ?,??? | |
| 注: | この物語は今、1995年11月頃である。 日本適合性認定協会の設立は1993年11月で、統計は1994年から |
![]() 「本当にISO9001認証が必要だったのは欧州統合のとき、輸出していた企業だけです。
「本当にISO9001認証が必要だったのは欧州統合のとき、輸出していた企業だけです。
今は、ISO認証すると品質が良くなるとか、良い品質と思われるという、実体のないブームで認証しているだけです」
「では、ブームは去るのかい?」
![]() 「廃れない流行はありません。何年続くか、10年は続かないでしょう。
「廃れない流行はありません。何年続くか、10年は続かないでしょう。
昔、数学で微分とか差分を習いましたね。四半期ごとの差を取れば今後の増加傾向が分かります。その差分を取れば加速度、つまり増加分の増加傾向が分かります。
今は増加傾向にありますが、増加の増加分は減少傾向、つまり先は増分が減っていくから、ゆくゆくは減少になることが見えるでしょう」
![]() 「高校・大学と微分積分を習ったが、そういう実戦的な使い方は思いもしなかったな。まだデータが4回分しかないけど20回、5年もデータが蓄積されれば傾向ははっきりしますね」
「高校・大学と微分積分を習ったが、そういう実戦的な使い方は思いもしなかったな。まだデータが4回分しかないけど20回、5年もデータが蓄積されれば傾向ははっきりしますね」
![]() 「もちろん、それだけじゃありません。外乱と言ってはおかしいか、これから認証を取り巻く環境にいろいろ変化が起きます。
「もちろん、それだけじゃありません。外乱と言ってはおかしいか、これから認証を取り巻く環境にいろいろ変化が起きます。
東京都が公共入札の際に、ISO認証企業は色を付けると、言ったのかな?」
「そういう動きがあると聞いている」
![]() 「都の入札にISO認証が条件とか、認証していると優遇するとなれば認証の追い風になります。
「都の入札にISO認証が条件とか、認証していると優遇するとなれば認証の追い風になります。
2000年頃には、建設省
「ほう! 佐川さんの予言ですか?
それはISO9001ですか、環境ISOですか?」
![]() 「両方です。両方認証していると加点される点数は倍のはず。2001年からでしょう。
「両方です。両方認証していると加点される点数は倍のはず。2001年からでしょう。
対象は建設業ですが、商社も建設業の許可を取っているところがほとんどですから、すごい数になりますね」
「ならば認証件数はどんどんと伸びますね、ありがたいことです」
![]() 「でも自分だけが認証していればすごいアドバンテージですが、みんなが認証したら差別化になりません。結局、認証はお金の無駄です」
「でも自分だけが認証していればすごいアドバンテージですが、みんなが認証したら差別化になりません。結局、認証はお金の無駄です」
「するとどんどん認証を止めていくわけですか?」
![]() 「そうなります。製造業のISO9001認証が止まったのを建設業界が補完しますが、それは数年間のことです。
「そうなります。製造業のISO9001認証が止まったのを建設業界が補完しますが、それは数年間のことです。
建設業界だって皆が認証すれば終わりどころではなく、最終的には認証件数は減少に移ります。
そんなこともあって、ISO9001の認証件数の総数は2006年、ISO14001は2009年がピークで、あとは減る一方です」
![]() 「佐川さんの予言は当たるかい?」
「佐川さんの予言は当たるかい?」
![]() 「当たらなくちゃ予言者じゃありません。私は真の予言者ですから100%的中します」
「当たらなくちゃ予言者じゃありません。私は真の予言者ですから100%的中します」
![]() 「しかし減るに至った理由は、そればかりでなくいろいろあるのでしょう」
「しかし減るに至った理由は、そればかりでなくいろいろあるのでしょう」
![]() 「そうです。エクセレント企業、まあ大手優良企業がISO認証しているだけなら、違反や事故発生は少ないでしょう。
「そうです。エクセレント企業、まあ大手優良企業がISO認証しているだけなら、違反や事故発生は少ないでしょう。
でも非上場とか中小企業まで認証が広まれば、違反や事故発生は全企業の平均に近づきます。当たり前ですね。
日本でペーパーカンパニーや冬眠会社を除いて、活動している企業は300万社
ISO9001の認証件数がピークのとき、45,000件くらいになります。意外に少ないと思うかもしれませんが、一人親方とか冬眠会社を除いた1.5%が認証していると思えば、とんでもない割合だと言えるでしょう。
ともあれ、認証件数が増えれば事故も増える。その結果、ISO認証は役に立たないと言われるようになります」
![]() 「ISO認証はプライズなのか、ツールなのかという問題になるな」
「ISO認証はプライズなのか、ツールなのかという問題になるな」
![]() 「おっしゃる通り。それは認証ビジネスを始めるときに、しっかり考えておくべきでした
「おっしゃる通り。それは認証ビジネスを始めるときに、しっかり考えておくべきでした
どんなビジネスでも母数が大きくなければ規模が大きくなりようがありません。
薄部長さんはどうか知りませんが、ISO認証を広めよう、客を取ろうと仲人口を語る認証機関が増えていきます。
ISO認証すると、品質が良くなる、儲かる、省エネが進む、会社を良くする、まあそんなことです」
「確かにそういうことを言わないと、客は付かないな」
![]() 「ならば、語ったことが成就しなかったときのことも考えておくべきです。
「ならば、語ったことが成就しなかったときのことも考えておくべきです。
ISO9001は品質保証だ、だから談合があっても認証機関は無関係だ、ISO14001は環境管理だ、だから品質問題が起きても無関係だ、そう言い切るべきです」
「佐川さんの見える未来は、そうではなかったのですな?」
![]() 「本来なら品質保証の規格に、談合しないこととかセクハラ防止を期待しません。ですが品質が良くなる、遵法が良くなる、儲かると言いたい放題だったのです。認証機関ばかりでなく、コンサルや大学教授まで」
「本来なら品質保証の規格に、談合しないこととかセクハラ防止を期待しません。ですが品質が良くなる、遵法が良くなる、儲かると言いたい放題だったのです。認証機関ばかりでなく、コンサルや大学教授まで」
「私はそこまでは言ってはいませんが、営業の第一線となれば言いたくなるでしょうな。まあ、仲人口というか、リップサービスですよ」
![]() 「消費者団体もいい加減ですからね。
「消費者団体もいい加減ですからね。
今、ISO認証企業の製品を買おうとする人がいると思いますか?」
「ウチの家内なんてISOなんて知らないよ」
![]() 「そうでしょうね。ISO9001は元々 BtoB の規格でしたし、ISO14001なら一般消費者に宣伝する意味がありません。自らを高める効果はあっても営業効果はないでしょうね。
「そうでしょうね。ISO9001は元々 BtoB の規格でしたし、ISO14001なら一般消費者に宣伝する意味がありません。自らを高める効果はあっても営業効果はないでしょうね。
でもISO14001認証しました、環境にやさしい企業ですと宣伝しますよ。数年後には。
環境にやさしい企業と言いながら公害を出せば、何も言わないで公害を出すより悪く見られますよね。人間とはそんなものです。
ISO9001認証企業から買いましょうなんて、消費者団体は言いません。でも一旦、企業不祥事が起きると、ISO認証の信頼を裏切られたと放言するのが消費者団体です。購買のときの参考情報に使ってもいなかったのに、裏切られたとはまた悪どい言いざまですよ、アハハ
自分を神だと勘違いしているんじゃないですか。
しかしそんな消費者団体とかマスコミの扇動で、認証機関も経産省……おっと通産省は2001年に経産省と名前が変わります……ともかく認証機関も通産省も、そんな雑音に対してISO認証制度を説明すれば良かったのですよ。
まだISO14001の認証書を作っていないでしょうけど、そこに必ず書くと思いますよ」
「何を書くのでしょう?」
![]() 「たぶん『この審査登録証は組織の遵法を確認したことを意味しない』あるいは『遵法を保証するものではない』そんな文句になるでしょう」
「たぶん『この審査登録証は組織の遵法を確認したことを意味しない』あるいは『遵法を保証するものではない』そんな文句になるでしょう」
「そう書いてあるなら、それを説明すれば済むのではないですか?」
![]() 「私もそう思います。しかし世の認証制度側は……認証機関とか認定機関ではなく、全体がですよ……『我々は審査のとき企業に嘘をつかれた』と説明したのです」
「私もそう思います。しかし世の認証制度側は……認証機関とか認定機関ではなく、全体がですよ……『我々は審査のとき企業に嘘をつかれた』と説明したのです」
「それは一認証機関ではどうにもならないのではないかな、たぶん通産省とかの圧力だろう」
![]() 「私もそう思います。しかしISO認証企業の多くがウソをついているというニュアンスの言い訳をしては、自分の商売のタネを殺してしまうだけです。
「私もそう思います。しかしISO認証企業の多くがウソをついているというニュアンスの言い訳をしては、自分の商売のタネを殺してしまうだけです。
せめて我々は抜取で審査をしている。見逃しというより確率的なものだ……というくらいは説明してほしいですね。
嘘をつかれたと言えば、社会は嘘を検出できない程度の審査なら無意味だと解するでしょう。
あのね、裁判で偽証罪というのは証人にだけです。被告人が嘘をつこうが罪になりません。というのは犯行した人は嘘をつくのが前提なの。検察官とか裁判官が嘘をつかれたと言ったら、無能だということです。
ISO審査では嘘をつくのが前提ですよ。商取引じゃないから商法の信義則は対象外です。審査員はしっかりと証拠を見て判断するのです。
もちろん審査を受ける人すべてが嘘をつくわけはない。だけど審査員は証拠だけを根拠に判断する覚悟が要りますよ
![]() 「仮定の話ではないなら、行く末は見えてしまうね。
「仮定の話ではないなら、行く末は見えてしまうね。
真面目に審査するだけではどうしようもないようだ」
![]() 「仮定の話ではなく、予言です。そうなることを保証しますよ。
「仮定の話ではなく、予言です。そうなることを保証しますよ。
端的に言って認証機関、いや認証制度のスタンスが、しっかりしていなかったというべきですね。
聞くところによると外資系認証機関は、そういう対応に反対したそうです」
![]() 「佐川さんの話ぶりは予言者というのではなく、未来を見てきたように思える」
「佐川さんの話ぶりは予言者というのではなく、未来を見てきたように思える」
![]() 「私自身、予知なのか未来の記憶があるのか、良く分かりません。
「私自身、予知なのか未来の記憶があるのか、良く分かりません。
ともかくISO認証企業の増加による不祥事の多発……その言い方は語弊がありますね、認証している企業としてない企業の差がないということです。ISO認証すると不祥事が多発するわけじゃないです。ISO認証は不祥事防止に効果がないと言われたわけです。
その結果、ISO認証の信頼性、ここでいう信頼性とは信頼性工学などの定義ではなく、人がISO認証は信頼できる/できないと考える割合でしかありません。
信頼性工学なら、システムや機器が機能する割合だから測定もできます。でもあの人は信頼できると言っても、借金を返した割合とかでなく言葉使いとか態度での感じでしかありません。つまり信頼性を上げるには、認証制度の仕組みとか審査員の訓練とかでなく、ISO認証は信頼できるというイメージの宣伝ですよ」
![]() 「どうでも良いような資格とか検定をでっちあげ、それを付与するビジネスを、資格商法とかサムライ商法と呼ぶね。あれと同じく、ISO認証ビジネスもサムライ商法のひとつにすぎないってことか」
「どうでも良いような資格とか検定をでっちあげ、それを付与するビジネスを、資格商法とかサムライ商法と呼ぶね。あれと同じく、ISO認証ビジネスもサムライ商法のひとつにすぎないってことか」
注:国家資格には「○○士」とつくものが多い。誤解されやすいような民間資格(実際は登録商標)として「○○士」というのを作って資格取得で利益を上げるのが「
![]() 「まあ、そう卑下することはありません。しかし己のビジネスの性質をしっかり認識して、そのメリットとできることできないことを説明できるようにしておくべきですね」
「まあ、そう卑下することはありません。しかし己のビジネスの性質をしっかり認識して、そのメリットとできることできないことを説明できるようにしておくべきですね」
![]() 「ISO認証とは何だろうな?」
「ISO認証とは何だろうな?」
「ISO9001は、元々は品質保証要求事項の統一標準化だった」
![]() 「おっしゃる通り。ならばメリットは、顧客対応の品質保証協定をしないで済むとなるはずです。それはほぼ達せられたでしょう。
「おっしゃる通り。ならばメリットは、顧客対応の品質保証協定をしないで済むとなるはずです。それはほぼ達せられたでしょう。
自動車とか航空などは、ISO9001では不足だとしてISO9001に要求を追加した規格になりましたが、まあ、本質的な問題ではない。
![]()
ではISO14001認証の効用は何でしょうか?」
![]() 「ドンドン厳しくなる環境規制や社会的要求に対応できる」
「ドンドン厳しくなる環境規制や社会的要求に対応できる」
![]() 「別に認証しなくても法は守らなくちゃなりません。ましてISO14001認証して事故が起きれば、認証していないより責められるなら、ありがたみがありません。
「別に認証しなくても法は守らなくちゃなりません。ましてISO14001認証して事故が起きれば、認証していないより責められるなら、ありがたみがありません。
認証のためにお金を払うだけ損じゃないですか?」
![]() 「ブランドイメージが上がる」
「ブランドイメージが上がる」
![]() 「確かに認証が始まったとき認証すればそうでしょうけど、皆が認証すれば意味がなくなります」
「確かに認証が始まったとき認証すればそうでしょうけど、皆が認証すれば意味がなくなります」
![]() 「その回答は何だ?」
「その回答は何だ?」
![]() 「またの機会にしましょう。
「またの機会にしましょう。
では本日は、これまででよろしいでしょうか?」
![]() 「定時まであと40分ほどで、その後、宴席を用意しております」
「定時まであと40分ほどで、その後、宴席を用意しております」
![]() 「三田部長さん、メールでお断りしますと書いていたはずです。
「三田部長さん、メールでお断りしますと書いていたはずです。
私はこれから会社に戻って、一仕事しなくちゃなりません」
![]() 「佐川さん、私が代理でご意見を賜りましょう」
「佐川さん、私が代理でご意見を賜りましょう」
![]() 「おお、じゃあ頼みます。
「おお、じゃあ頼みます。
三田部長さん、そういうことでよろしくお願いします」
![]() 本日の願望
本日の願望
現実はこんな風に説明して、認証機関が納得するはずがない。
私は口を酸っぱくして所見報告には証拠・根拠を書けと言ったが、それさえしっかり書かない審査員は多かった。
それでも21世紀にはだいぶ良くなった。私が説教したことではなく、ISO17021がしっかり適用されるようになったからだと思う。
まあ、真面目になるのが遅すぎた感はある。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
Google UKで検索して見つけた、ISOコンサルらしきウェブサイトにあった、ISO14001が始まった頃の著しい環境側面の決定方法である。 21世紀に書かれた著しい環境側面の決定方法は結構見つかるが、20世紀のものは希少である。 | |
| 注2 |
ISO9000シリーズは1987年制定時にはISO9001/ISO9002/ISO9003の3種類があった。2000年改定でISO9002/ISO9003はISO9001に統合されて廃止された。 | |
| 注3 |
ISO9001:1987『序文』 | |
| 注4 |
ISO9001:1994 4.2.2最終段落 「品質システムの構成部分となる手順の範囲及び詳しさは、業務の複雑さ、適用される方法、業務の遂行に関係する人々に必要とされる技能及び訓練によって異なる」 | |
| 注5 |
ISO14001:1996 『序文』最終段落 | |
| 注6 |
建設省が国交省になったのは2001年1月6日。 | |
| 注7 |
2022年度の法人税申告件数は、約306万8,591社であった。 | |
| 注8 |
ISO9001認証が始まったとき、認証機関は雨後の筍のように設立された。確かに認証機関は製造業のように大資本は必要としないが、これほど認証機関ができて大丈夫かと心配したのは本当だ。 認証機関の設立者、経営者はどう考えていたのだろうか? 設立して数年稼げればヨシと考えていたのかどうか。 第三者認証の事業についての検討は、2003年の日本工業標準調査会適合性評価部会「管理システム規格適合性評価専門委員会報告書」しかないようだ。2003年のものだが、その中で競争が激しくなること、利幅が小さくなることを心配していた。 | |
| 注9 |
「証言を信ぜず証拠だけを根拠に判断する」のは審査の基本だ。2001年に企業の口頭説明だけを根拠に適合判定をして、認定停止をくらった認証機関がありましたね。 |
外資社員様からお便りを頂きました(25.03.27)
おばQさま いつも有難うございます。 いつものピンポイント感想で恐縮です >現実はこんな風に説明して、認証機関が納得するはずがない。 仰る通りで、タイムスリップしようが認証機関の考えは絶対に変わらないと思います。 でも、現実が十分理不尽ですから、お話の中くらい良い結末の方が読んでいて楽しいですね。 >その後宴席が 試験機関の独立性から考えると、大丈夫なんでしょうかねw 利益を受けるのでなく、提供するから良いのか? いつもながら断っている佐川は立派です。 |
外資社員様、毎度お便りありがとうございます。 私も認証機関に文句を言うばかりではありません。知り合いが○○認証機関の人と話をしてみたいなんて言ってくることもありました。直接、認証機関に審査を依頼したいから見積もりがどうのとかの話をする前に、そこの幹部と話をしてみたいということでした。 あいよ!ってなもんで、私が面識のある取締役に電話して取り持ったことも何度かあります。向こうとしては客の紹介ですからありがたいと、その後飲ませてもらいました……といっても自分の金で飲んだ方が酒は旨いですけど。 あれも考える何か支障があったのかもしれません。 21世紀になると一生添い遂げるなんて価値観もなく、4年審査をしてもらったから替えてみるかなんて、軽くチェンジする会社も増えました。 今は軽く認証返上しようとかになっているのですか? |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |