注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1995年12月 今日は業界の環境ISO研究会である。
なぜか今回は参加者が少ない。業界団体職員の幹事を含めてメンバーは13人だ。全員集まることはめったにないが、普通は欠席が多くても3人くらいなのに、今回は6人も欠席して7人しかいない。
理由は単純明快だ、人数が多いと発言者の識別が面倒だから。
吉本 吉本 吉本 | ||||
| 田中 |  佐川 佐川 |
|||
| 高橋 |  山口 山口 |
|||
| 小林 |  須藤 須藤 | |||
![]() 「今日は出席者が少ないですね。とは言いまして、環境部では毎年数件は研究会とか法規制の検討会などを設置して活動していますが、多くは半分集まれば良い方です。代理者も多いですしね。
「今日は出席者が少ないですね。とは言いまして、環境部では毎年数件は研究会とか法規制の検討会などを設置して活動していますが、多くは半分集まれば良い方です。代理者も多いですしね。
これは事実、私はたびたび上司の代理で、高い仕出し弁当を食っていた。
今回のISO研究会ほど出席率の良い、熱心なプロジェクトはありませんでしたね。それだけISO14001認証が重要だからでしょう。
ところで本日は良いお知らせがあります。先だって産業環境認証機関の方を招いて講演をしてもらいましたが、そのときこちらがした質問への回答書が送られてきました。
皆さんにお配りしますね。欠席に方には、こちらからメールで送っておきます。
今日はその内容確認と、これからの活動を話し合いたいと思います。
と言いますのは、この回答でほとんどの悩みとか不明点が解消されれば、この研究会の目的の大半は片付いたのかなと思えるからです」
![]() 「まずは中身を拝見したいですね」
「まずは中身を拝見したいですね」
吉本は出席者にA4を数枚綴じたものを配る。
皆、配られるとすぐに中身を読み始める。
![]()
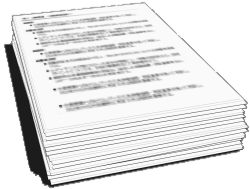
![]() 「まず目的3年以上が必要とか、環境マネジメントプログラムふたつ必要は、こちらの意見通り撤回ね」
「まず目的3年以上が必要とか、環境マネジメントプログラムふたつ必要は、こちらの意見通り撤回ね」
![]() 「著しい環境側面の決定方法はいかなる方法でも良い。もちろん規格要求を満たすものであることか……
「著しい環境側面の決定方法はいかなる方法でも良い。もちろん規格要求を満たすものであることか……
先日、時田部長が話したことと全然違うね」
![]() 「会社に帰って内部で相当検討したのでしょう」
「会社に帰って内部で相当検討したのでしょう」
![]() 「だろうね、我々の方が認証機関より深く考えていたということかな、アハハハ」
「だろうね、我々の方が認証機関より深く考えていたということかな、アハハハ」
![]() 「とはいえ、質問に答えていないことがいくつかあるね。質問そのものが記載されていない」
「とはいえ、質問に答えていないことがいくつかあるね。質問そのものが記載されていない」
![]() 「どんなことですか?」
「どんなことですか?」
![]() 「環境側面の対象範囲は書いてあるけど、そこからどのように選び出すというか、環境側面を見つけ出す方法は書いてない」
「環境側面の対象範囲は書いてあるけど、そこからどのように選び出すというか、環境側面を見つけ出す方法は書いてない」
![]() 「あっ、そうですね。載っていませんね。彼らもアイデアがないのでしょう」
「あっ、そうですね。載っていませんね。彼らもアイデアがないのでしょう」
![]() 「まあ、そうだろうな。要するにどうでも良いということか」
「まあ、そうだろうな。要するにどうでも良いということか」
![]() 「とはいえ、回答には特段新しい見解とか情報が含まれているわけではないね。よく読めば、書いてあることはすべてISO規格、おっとまだドラフトだが……それを基に私たちの質問に答えたとしか思えない」
「とはいえ、回答には特段新しい見解とか情報が含まれているわけではないね。よく読めば、書いてあることはすべてISO規格、おっとまだドラフトだが……それを基に私たちの質問に答えたとしか思えない」
![]() 「私もそう思いました。3年目標は規格にないから要求しない、著しい環境側面の決定方法も規格に書いてないから自由ですよ、その代わり規格要求を満たしなさいと、規格通りですね」
「私もそう思いました。3年目標は規格にないから要求しない、著しい環境側面の決定方法も規格に書いてないから自由ですよ、その代わり規格要求を満たしなさいと、規格通りですね」
![]() 「まあ、認証機関独自の要求を加味しないと言葉質がとれたのだから、良かったではないですか」
「まあ、認証機関独自の要求を加味しないと言葉質がとれたのだから、良かったではないですか」
![]() 「なるほどそういう見方なら、質問に対して当たり前の回答を引き出したことは大成功だ、満額回答だね」
「なるほどそういう見方なら、質問に対して当たり前の回答を引き出したことは大成功だ、満額回答だね」
![]() 「すると、もうこの研究会は目的を果たしたことになりますか?」
「すると、もうこの研究会は目的を果たしたことになりますか?」
 |
![]() 「そうではないでしょう。この研究会は業界団体として設置したわけで、それなりの時間と金をかけているわけです。その成果物を形にして、業界傘下の企業に知らしめなければなりません。その役目がありますよ」
「そうではないでしょう。この研究会は業界団体として設置したわけで、それなりの時間と金をかけているわけです。その成果物を形にして、業界傘下の企業に知らしめなければなりません。その役目がありますよ」
![]() 「おお、もちろんそうでした。それはどうしましょう?」
「おお、もちろんそうでした。それはどうしましょう?」
![]() 「となると全体をまとめて、形態は冊子、場合によってはpdfでも良いでしょうけど、そういったまとまった形にしなければならないね」
「となると全体をまとめて、形態は冊子、場合によってはpdfでも良いでしょうけど、そういったまとまった形にしなければならないね」
![]() 「ここに来ている人たちを送り出した会社は、既に認証の意味とか価値を理解しているはずだ。だけどそうでない会社、特に中小はISOそれおいしいのという状況だろう。
「ここに来ている人たちを送り出した会社は、既に認証の意味とか価値を理解しているはずだ。だけどそうでない会社、特に中小はISOそれおいしいのという状況だろう。
そういうところの人たちでも1冊読めば、初歩から認証までの手順と、具体的な規格対応の方法が分かるものにしたいね」
![]() 「そうなると私たちが規格解釈で迷ったことの回答はここにありますが、質問するまでもなかったことも含めたものにしなければなりませんね」
「そうなると私たちが規格解釈で迷ったことの回答はここにありますが、質問するまでもなかったことも含めたものにしなければなりませんね」
![]() 「小林さんのお考えは分かります。ただそうなると書籍一冊で完結するかどうか分かりませんね」
「小林さんのお考えは分かります。ただそうなると書籍一冊で完結するかどうか分かりませんね」
![]() 「まあ、最初に大枠を作って体系的に作っていくのもあり、一部を作っているうちに周囲に広がっていって大きなものになるかもしれません。
「まあ、最初に大枠を作って体系的に作っていくのもあり、一部を作っているうちに周囲に広がっていって大きなものになるかもしれません。
まずはこのQ&Aだけでなく、すべての要求事項がどんな意味を持っているのか、何をしなければならないのか、Q&Aの形でなく解説する形で完成させましょう。
思ったのですが、規格の一行一行の解説を書いていけば、気づかなかった問題や疑問が新たに見つかるはずです。ただ文章を読むより文章を書く方がしっかり考えますからね。そうでなくちゃ文章が書けないわけで……
そんなことでいかがでしょう」
![]() 「具体的な作業になると、そういうことでしょうね。」
「具体的な作業になると、そういうことでしょうね。」
![]() 「完成した暁にはそれを一般書として市販できたら良いと思います。我々の成果物として残ります」
「完成した暁にはそれを一般書として市販できたら良いと思います。我々の成果物として残ります」
![]() 「それならせっかくだから、認証機関に監修してもらいましょうか」
「それならせっかくだから、認証機関に監修してもらいましょうか」
![]() 「名ばかりでも監修を頼めば、印税の何パーセントか払わないとならないよ。
「名ばかりでも監修を頼めば、印税の何パーセントか払わないとならないよ。
いや待てよ、そうか、認証機関の口止め料か、それに認証機関にとっても名前が売れる。ウィンウィンだな。
山口さん、お主やるな、フフフ」
 |  |
![]() 「なるほど、夢は大きくと、
「なるほど、夢は大きくと、
次なる仕事は各項番の解説だね」
![]() 「各項番解説でなく各文解説ですよ」
「各項番解説でなく各文解説ですよ」
![]() 「各文解説となるとどれくらい時間がかかりますか?」
「各文解説となるとどれくらい時間がかかりますか?」
![]() 「今11月です。FDISが来年5月の見込みですから、それまでにDISで草案を完成させておいて、それが出たら一部修正を施して監修を頼む。夏には出版したいですね
「今11月です。FDISが来年5月の見込みですから、それまでにDISで草案を完成させておいて、それが出たら一部修正を施して監修を頼む。夏には出版したいですね
注:DISはISO規格の草案、FDISは最終案
![]() 「そうなりますね。規格には62の文章がありますので、これをメンバーに割り振って、解釈というかその文章の意味を解説してもらうことにしましょう」
「そうなりますね。規格には62の文章がありますので、これをメンバーに割り振って、解釈というかその文章の意味を解説してもらうことにしましょう」
![]() 「いつも来ているメンバーは9名、今日は6名か……、とりあえず次回までに今回の出席者が2文ずつサンプルを書いて来ることにしませんか。
「いつも来ているメンバーは9名、今日は6名か……、とりあえず次回までに今回の出席者が2文ずつサンプルを書いて来ることにしませんか。
それをここで皆が議論してまとめていくことどうだろう?」
![]() 「そういう方法でよろしいと思います。1文と言っても、原文が関係副詞などでつながっていて、和訳では100文字以上ですから、2行から3行になります。簡単ではありません。
「そういう方法でよろしいと思います。1文と言っても、原文が関係副詞などでつながっていて、和訳では100文字以上ですから、2行から3行になります。簡単ではありません。
とはいえ62文でしたっけ? この6名だけとしても週にひとつ仕上げれば、3カ月、来年の2月には完了です」
![]() 「書き方ですが、まず英語原文、JIS訳……これはとりあえずドラフトの和訳をそのまま写す、それからその文章が意味していることを正しく意訳する。これは原文の長さを気にせず、文章が長くても、複数の文章になっても良いと思います。
「書き方ですが、まず英語原文、JIS訳……これはとりあえずドラフトの和訳をそのまま写す、それからその文章が意味していることを正しく意訳する。これは原文の長さを気にせず、文章が長くても、複数の文章になっても良いと思います。
その他あれば注意事項などでしょうか」
それから数日後、山口が佐川に声をかける。
![]() 「佐川さん、研究会の宿題を書いてます?」
「佐川さん、研究会の宿題を書いてます?」
![]() 「ああ、この前割り当てられたふたつは書いたよ」
「ああ、この前割り当てられたふたつは書いたよ」
![]() 「サンプルを見せていただけませんか。どういった形にすれば良いのか……」
「サンプルを見せていただけませんか。どういった形にすれば良いのか……」
![]() 「いいよ、打ち合わせ場に行こうか。コピーして持って行くよ」
「いいよ、打ち合わせ場に行こうか。コピーして持って行くよ」
|
![]() 「ああ、こんな風に書けばよいのですか?」
「ああ、こんな風に書けばよいのですか?」
![]() 「あまり手本にならないよ。手抜きだよ、手抜き。
「あまり手本にならないよ。手抜きだよ、手抜き。
とりあえず宿題分はしておこうと思ってね、様式や形態は、他の人のものも出てくるわけで、皆が議論して良さげなものを選んだら、それに合わせるつもり。みんなも最初は様子見だろう。
JIS訳が間違いないと思えば、わざわざ書き加えることもないでしょう。主語が正しいか、動詞の意味が伝わっているか、形容詞の程度があっているか、チェックするのはそんなとこですか」
![]() 「佐川さん、ふと思ったのですが……先日の研究会では書籍にまとめて発行するという話でしたね。今までの流れを作ったのは佐川さんじゃないですか。それに内容的にも佐川さんのアイデアとか情報が占める割合は大きいです。
「佐川さん、ふと思ったのですが……先日の研究会では書籍にまとめて発行するという話でしたね。今までの流れを作ったのは佐川さんじゃないですか。それに内容的にも佐川さんのアイデアとか情報が占める割合は大きいです。
だったら佐川さん個人の著作物として出版すべきでしょう。研究会に成果を取られたら損じゃないですか」
![]() 「まず従業員が会社の業務として書いた本の著作権は、会社に帰属する
「まず従業員が会社の業務として書いた本の著作権は、会社に帰属する
それに研究会がなかったら、そもそもそういう流れにならなかっただろうし、私一人が作成したら自費出版でもなくちゃ、出版できるはずがない。まして無名だから売れないよ」
![]() 「そんなものですか?」
「そんなものですか?」

![]() 「私の名前なら、300部売れるかどうかだ。編集が研究会のメンバーなら、メンバーの会社や関連会社がそれぞれ数十部は買うだろうし、業界傘下の会社も買う。それでも1万部いくかいかないかだ。この類の本は、そんなに売れるものではない。
「私の名前なら、300部売れるかどうかだ。編集が研究会のメンバーなら、メンバーの会社や関連会社がそれぞれ数十部は買うだろうし、業界傘下の会社も買う。それでも1万部いくかいかないかだ。この類の本は、そんなに売れるものではない。
仮に1万部で売値が1,800円とする。印税が8%として140万、監修者に1割、残りを12人で割ってひとり10万、もっとも業務上だから会社の規則で丸まる自分に入るわけではない。まあやったことが形として残れば悪くない
私の願いは、まっとうな審査が行われることで十分だ。前世のような無茶苦茶、出鱈目の審査はなくなれば満願成就だ。まっとうな審査が行われ、皆が幸せに暮らしましたというエンディングになれば最高だね」
![]() 「佐川さんは仏様のようですね」
「佐川さんは仏様のようですね」
![]() 「また前世と同じく審査でもめると思うと嫌です。そうならないようにと願っているだけです」
「また前世と同じく審査でもめると思うと嫌です。そうならないようにと願っているだけです」
1996年3月
規格解説本の内容が決まった後、業界団体の環境部長名で、産業環境認証機関に書籍の監修を依頼した。認証機関は業界団体が設立したわけではないが、まあ深い関係にあるわけで、依頼を拒否するいわれはない。
・
・
・
産業環境認証機関の小部屋である。
取締役兼部長4名が座っている。
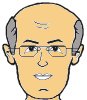 本間審査部長 本間審査部長 |
||
三田総務部長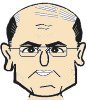 |  時田技術部長 時田技術部長 |
![]() 「いやはや、業界団体の環境ISO研究会から、認証のテキストの監修依頼が来たとは、驚いたね」
「いやはや、業界団体の環境ISO研究会から、認証のテキストの監修依頼が来たとは、驚いたね」
「これは監修をしたからには、そのテキスト通りなら審査でケチをつけるなよという意味でしょうね」
![]() 「そうだろうな。
「そうだろうな。
一通り読んだけど、ウチでまとめた環境側面解説本の草案より、出来が良いんじゃないか?」
![]() 「当社はISO14001認証のために規格解説、法規制、環境側面、文書化の方法、内部監査といくつも著作を出す予定でしたが、このテキストは全部まとめて書いてありますね。
「当社はISO14001認証のために規格解説、法規制、環境側面、文書化の方法、内部監査といくつも著作を出す予定でしたが、このテキストは全部まとめて書いてありますね。
ウチの予定していたものは、これ一冊で間に合いそうです」
![]() 「そもそもそんなにたくさんの本を書くことはなかったのか?
「そもそもそんなにたくさんの本を書くことはなかったのか?
こいつは仮製本だけど、A5判で220ページ、よくできている。売値2,200円というところか」
![]() 「当社の場合、出版も認証機関の事業の一つと位置付けていましたから、それなりに品ぞろえを予定していました」
「当社の場合、出版も認証機関の事業の一つと位置付けていましたから、それなりに品ぞろえを予定していました」
「元々ウチで本を出版しても、市販はせいぜいが2,000部でしょう。メインは講習会のテキストに配布する予定です
![]() 「出版を認証機関の事業にしようとしたのは無理だったのかな」
「出版を認証機関の事業にしようとしたのは無理だったのかな」
![]() 「会社設立時に営業部長は、認証機関の事業は、3本柱だと言ってたじゃないですか。認証、講習会、そして出版ですよ」
「会社設立時に営業部長は、認証機関の事業は、3本柱だと言ってたじゃないですか。認証、講習会、そして出版ですよ」
| 講 習 会 | 認 証 事 業 | 出 版 事 業 | ||||
「確かにそう言ったが……考えてみれば認証以外は、長期的に続けられる事業じゃなかったようだ。
講習会はISO14001規格が登場したときは受講者はいるだろうが、その次に現れる規格になれば、規格の中身は異なっても、認証のアプローチ方法も知れ渡っているから、受講者はがた減りだろう」
![]() 「ISO審査員研修は、新しい規格が出るたびに相当数が受講するでしょう。審査員が必要ですから」
「ISO審査員研修は、新しい規格が出るたびに相当数が受講するでしょう。審査員が必要ですから」
![]() 「認証件数は増えても、無限に増えるわけではない。認証が必要な企業を一巡すればお終いです。後は維持だけ。となると審査員数はそんなに多くない数で間に合う。
「認証件数は増えても、無限に増えるわけではない。認証が必要な企業を一巡すればお終いです。後は維持だけ。となると審査員数はそんなに多くない数で間に合う。
ISO9001では認証1件あたりの審査工数は書面審査を含めて4人工くらいです。
今ISO9001は伸びているけど、上限は5万でしょうね。そうすると審査工数は20万人工です。審査員の稼働日数を200日として、20万割る200で1,000人です。稼働を250日まで上げれば800人で済む。日本全体でですよ。
そしてISO14001の認証件数も5万件として、同じく800人です。
今は急激に伸びてますが、落ち着けば審査員は引退する人の補充分しか需要がありません。審査員を10年務めるとして、年に200人じゃビジネスになりませんよ。
注:実際はISO9001のピークは43,500件、ISO14001のピークは20,800件だった。
![]()
吉澤正先生が亡くなる少し前だから2012年、ISO14001の認証件数を4万めざそうなんて、なにかの会議で叫んだ。ありえないよ。当時認証件数は既に減少に入っていた。
あの先生、良い人だったけど先を見る目はなかったようだ。それとも分かっていても「進め1億、火の玉だ」の世代だったのか?
「だが今いろいろ新しい規格が検討されているでしょう」
![]() 「ISO9001は成功しました、そしてISO14001も成功すれば、これからドンドン新規のISO認証規格が登場するでしょう。でもあまり多すぎると企業が疲れてしまいます。せいぜい伸びるのは4種類くらい、あるいは新しい規格が登場すれば、古いISO9001から認証を止めていくと思います。
「ISO9001は成功しました、そしてISO14001も成功すれば、これからドンドン新規のISO認証規格が登場するでしょう。でもあまり多すぎると企業が疲れてしまいます。せいぜい伸びるのは4種類くらい、あるいは新しい規格が登場すれば、古いISO9001から認証を止めていくと思います。
4つのMS規格それぞれ認証が5万件なんて想像できませんね。新しい規格が登場しても合計で10万件じゃないかな。すると審査員工数は40万人工となる。MS規格全部合わせて審査員は1,600人で間に合う計算です。
仮にウチがISO認証のマーケットシエアを1割確保したとして、審査員160人となる。
それに現時点、認証組織の規模は多くが200名以上ですが、これから認証する規模はだんだん小さくなりますから、一拠点2人工とかになれば必要な審査員数は半分になってしまう」
「私より三田さんが営業部長をした方が良さそうだ」
![]() 「審査員必要数が増えなければ、審査員研修機関も先がないか」
「審査員必要数が増えなければ、審査員研修機関も先がないか」
![]() 「そうなりますね」
「そうなりますね」
![]() 「ということは、3本柱どころではない。認証機関は認証事業1本で、生きて行かねばならないことになる。
「ということは、3本柱どころではない。認証機関は認証事業1本で、生きて行かねばならないことになる。
それで負荷とか損益とかどうなるだろう?」
「認証機関はまだ良いよ。講習会を止めても何とかなる。だけど審査員研修機関は今いくつあったっけ?」
![]() 「20いくつかあったはずだ」
「20いくつかあったはずだ」
「それがすべて生き残るはずはないな。まあ、残るのは1社ってことはないだろうけど、2社か3社だろう。ウチの場合は、審査員研修事業から撤退か。
数年先は、毎週、審査員研修が20名フル受講なんてありえず、最低限の人数さえ確保できなくなるかもしれない
![]() 「先行きはそんなに悪いのですか?」
「先行きはそんなに悪いのですか?」
![]() 「今から気にすることはないでしょう。佐川さんの予言では、ISO9001の認証件数は2006年頃までは伸びるそうですから、減少するのは10年先ですよ」
「今から気にすることはないでしょう。佐川さんの予言では、ISO9001の認証件数は2006年頃までは伸びるそうですから、減少するのは10年先ですよ」
![]() 「彼は2006年まで伸びるとは言わなかったぞ。ピークが2006年と言ったのだ。ということはその数年前から増加は微々たることになる」
「彼は2006年まで伸びるとは言わなかったぞ。ピークが2006年と言ったのだ。ということはその数年前から増加は微々たることになる」
注:2010年前から身売り、撤退をする審査員研修機関や認証機関が散見された。
偶然だが同時期に、携帯電話から撤退する電器メーカーも多かった
いずれも先見の明があったのだ。携帯電話は薄利多売で数が出ないとダメ。ISO審査は数の減少が始まっていた。ぬるま湯でズルズル行くのが最悪だ。
「とはいえ、企業は先を読まなくちゃならないから、それ以前に対応措置を取るだろう。撤退するとか身売りとか」
![]() 「ウチはどうなりますか?」
「ウチはどうなりますか?」
![]() 「時田君、我々は経営者だぞ。どうなりますかなんて言って欲しくない。どうするかを言って欲しい。
「時田君、我々は経営者だぞ。どうなりますかなんて言って欲しくない。どうするかを言って欲しい。
わしはその前に、まずはオーバーヘッドを軽くすることだと思う。事務は派遣に切り替える。審査員もかなりの割合を契約審査員にして、とにかく固定費を減らす。
また審査員のゾーンデフェンス体制を構築し、旅費や宿泊費を減らし、夜間や土日の審査もできる体制だな。その結果、審査費用を下げて客を取りたい」
「認定費用の低減もあるでしょうね。必要もないのに外国の認定を受けないとか、認定そのものを受けないノンジャブとか。オフィスも所在地やビルに拘らず、安いところにしないとね」
![]() 「認証ビジネスを考えると、審査を受ける企業が、規格解釈をしっかりしろなんて注文は、当然というか、かわいいものだったのですね」
「認証ビジネスを考えると、審査を受ける企業が、規格解釈をしっかりしろなんて注文は、当然というか、かわいいものだったのですね」
![]() 「正しい規格解釈は当たり前だが、それだけでなく、審査のルール、礼儀作法、そういうことをしっかりしないと客が逃げていくよ」
「正しい規格解釈は当たり前だが、それだけでなく、審査のルール、礼儀作法、そういうことをしっかりしないと客が逃げていくよ」
「表沙汰にはなっていませんが、大手の○○協会では、審査員の態度が大きいと苦情が絶えないそうですね」
![]() 「そういえば何年か前、審査員による灰皿事件という噂話がありましたね。都市伝説ですかね?」
「そういえば何年か前、審査員による灰皿事件という噂話がありましたね。都市伝説ですかね?」
 | 💥 | |
![]() 「それ都市伝説じゃなくて実話です。そして被害者は、あの佐川氏だぞ」
「それ都市伝説じゃなくて実話です。そして被害者は、あの佐川氏だぞ」
![]() 「なんと!、奴は口だけじゃなくて、歴戦か」
「なんと!、奴は口だけじゃなくて、歴戦か」
・
・
・
![]() 「そいじゃ、時田さん、技術部で検討してもらい半月くらいでまとまるかな?
「そいじゃ、時田さん、技術部で検討してもらい半月くらいでまとまるかな?
FDISが6月に出るというから、連中はDISからの変更を反映して8月発売を目指すそうだ。間に合うね?」
![]() 「そのように進めます。監修ですと印税の1割ですか、売値の1%弱でしょう」
「そのように進めます。監修ですと印税の1割ですか、売値の1%弱でしょう」
「そこは顧問弁護士の先生と相談します」
![]() 「ところで、可能ならこの本の版権
「ところで、可能ならこの本の版権
「お金が欲しければ乗ってくるかもしれませんが、業界団体が制作したわけでないでしょうから、無理じゃないですか
![]() 「聞くだけ聞いてみろ。
「聞くだけ聞いてみろ。
よそさんが書いた本をウチの講習では使えないぞ。
外聞も悪いし、ウチに実入りがない」
・
・
・
薄営業部長が業界団体の吉本に版権を売らないかと問い合わせたら、業界団体として参加メンバーにそのようなことを強制できないと吉本が断った。
![]() 本日の予言
本日の予言
半年をたった一話で終わらすとは、もう物語はお終いかですって?
なことありませんよ。
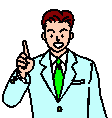
今まで、ISO認証に伴う問題はたくさんありました。問題は、規格解釈だけではありません。
ハテ、どんな問題が? とボケないでください。
たった15年前のことを忘れてはいけません。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
コンサルが書くISO認証の参考書は規格発行や改定後の1年頃に出版される。しかし規格協会のISOMS規格の対訳本は、ISO規格が制定されるとき同時に発行されている。当然JIS化される前だ。あらかじめ用意しているとしか思えない。もっとも対訳本の和文とJISの文章が異なることもある。 | |
| 注2 |
会社の業務として作成され、法人名で発行、契約や就業規則に特別な定めがない場合は、著作権は会社に帰属する。 | |
| 注3 |
私の経験だが、個人で仕事の成果を本に書いて出版した人はいないが、ある製品開発に関わった人たちが、その物語を本にして出したことがあった。やはり本に自分の名前が残るのはうれしいものだろう。 私の知り合いで引退してから、ISO認証について本を書いた人は数人いる。多くは自費出版のようで売れたなら良いが、売れ残ると大変だろうな。私はおばQ名でアイソス誌に何度か載せてもらったから、それで十分だ。 | |
| 注4 |
ISOに限らず、いろいろな講習会に行くと、講師の書いた本(ISBNコードがしっかり付いている)を配付されることが多い。確かに簡易製本とかA4紙ファイルに綴じた資料よりありがたみがある。 一説によると廃刊になったグローバルテクノ社の「アイソムズ誌」は、そんな用途だったらしい。 | |
| 注5 |
ISO審査員研修は、ルールで受講者が5人以上20人以下でなければならなかったと記憶している。2010年を過ぎると受講者が集まらなくて、年度首の開催予定が中止になるところが多かった。 年度首に審査員研修機関のウェブサイトに開催計画がアップされ、時が進むと開催中止の注記が付くから分かる。 審査員研修機関を持つ認証機関で働いている審査員が資格更新時に他の研修機関で受講していたからどうしたのと聞くと、受講者がいないから開催できないと聞いた。 そういえば某審査員研修機関では受講者が揃わず、既に資格を持っている人を参加させて最少人数を確保したとか……これって良いのかな? | |
| 注6 |
 携帯電話(ガラケー)最盛期には、日本に携帯電話メーカーは12社あった。
携帯電話(ガラケー)最盛期には、日本に携帯電話メーカーは12社あった。NTTドコモ、NEC、パナソニック、富士通、シャープ、三菱電機、東芝、ソニーエリクソン、カシオ、日立、京セラ、三洋電機である。 2025年現在、日本のスマホメーカーは、はシャープ(AQUOS)、京セラ(DIGNO)、ソニー(Xperia)、FCNT(中国に身売り)の4社である。 | |
| 注7 |
著作権は昔、版権と言った。 著作権には著作者人格権の「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」がある。「氏名表示権」とは著作物に氏名を表示する権利で、法律上譲渡できない。つまり作者を変えることはできない。 
「海月のななり」のように、他人の著作物を我が物にするのはダメ。 ゴーストライターは氏名表示権の放棄でなく、氏名表示権を行使しないことと作者であると公表しない守秘義務契約をするそうだ。 もし本を編集したISO研究会のメンバーが、氏名表示権を行使しない契約に同意すれば、認証機関の著作物として売り出せることになる。 | |
| 注8 |
参加メンバーが社命で参加している以上、著作権は派遣元の会社に帰属(職務著作)するらしい。だが業界団体が参加企業との間に著作権の契約をしているかどうかもあるが、会社によって就業規則によって著作権の定めが違い、調整するのが面倒事であることが見える。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |