注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1996年8月末である。
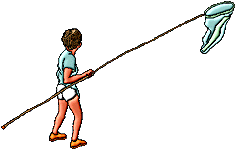 小中高の学校に通っている子供たちは「もう夏休みも終わりか、いやだなあ」と思っているだろう(自分の体験です)。
小中高の学校に通っている子供たちは「もう夏休みも終わりか、いやだなあ」と思っているだろう(自分の体験です)。
大学によっては夏休みが始まったばかりで、これからひと月以上夏休みかもしれない。
会社はお盆休みがあるだけだ。もっとも最近の会社ではお盆休みのないところもある。
昔は盆と正月は地獄のふたも開くと言われた。本当は「盆には地獄のふたも開く」と言い、お盆には地獄で罪人を煮る釜の蓋を開けて罪人も休めるという宗教的な意味だったらしい。だが私が子供の頃は、商店も工場も日曜休みしかなく、お正月とお盆は年に二度ある希少な連休だったので、「盆と正月は地獄のふたも開く」と言ったと母から聞いた。
佐川がというか未来プロジェクトのメンバーが、第1回目の報告を出してホッと一息していると、山口がやって来た。
未来プロジェクト室では情報漏洩以降、入口部分に外来者との打ち合わせ場を作って、今は中まで入れないようにしている。
佐川はそこにホットコーヒーを2個持っていって、山口の話を聞く。
 |  |
||
![]() 「多くの認証機関が、9月から仮審査を始めるようです。
「多くの認証機関が、9月から仮審査を始めるようです。
それでウチの工場も関連会社も認証に向けて鋭意努力中なのですが、規格解釈についてまだネゴが取れてないのです」
![]() 「産業環境認証機関は問題ないのでしょう?」
「産業環境認証機関は問題ないのでしょう?」
![]() 「あそこは今までやり取りしましたから問題はありません。
「あそこは今までやり取りしましたから問題はありません。
またイギリス系は問題ありません。ディブ(第40話)には私たちの作った本を贈呈して了解をもらっています」
![]() 「ハワードさんは何も言わなかったの?」
「ハワードさんは何も言わなかったの?」
![]() 「ええ、贈った本を読んでくれて、立派なものだと言ってくれました。
「ええ、贈った本を読んでくれて、立派なものだと言ってくれました。
彼らもISO14001のテキストを編集しているようです。完成したら送ってくれると言っていました」
![]() 「それは楽しみだ」
「それは楽しみだ」
![]() 「でも認証機関によっては独自の規格解釈をしていて、私たちが考えた理解と相容れないところもあるのです」
「でも認証機関によっては独自の規格解釈をしていて、私たちが考えた理解と相容れないところもあるのです」
![]() 「私の
「私の
![]() 「それでですね、ウチばかりでなく、例の研究会のメンバー企業も共同で、話を付けようということになりまして」
「それでですね、ウチばかりでなく、例の研究会のメンバー企業も共同で、話を付けようということになりまして」
![]() 「それは面白そうだ、期待しているよ」
「それは面白そうだ、期待しているよ」
![]() 「いえ、研究会の総意で交渉担当として佐川さんにご出馬を願いたいと……」
「いえ、研究会の総意で交渉担当として佐川さんにご出馬を願いたいと……」
![]() 「ギョ!、そりゃ、また、どうしてよ?」
「ギョ!、そりゃ、また、どうしてよ?」
![]() 「そりゃ規格を一番理解しているのは、佐川さんと目されているわけで」
「そりゃ規格を一番理解しているのは、佐川さんと目されているわけで」
![]() 「確かに今は、未来プロジェクトも第1回報告書を出したところで、ここ半月くらいはどうとでもなるのはなるけど」
「確かに今は、未来プロジェクトも第1回報告書を出したところで、ここ半月くらいはどうとでもなるのはなるけど」
![]() 「ここはみんなを助けると思って、片肌脱いでくださいよ」
「ここはみんなを助けると思って、片肌脱いでくださいよ」
![]() 「どんなところで見解の相違があるのですか?」
「どんなところで見解の相違があるのですか?」
![]() 「ISO9001とはかなり様相が違いますね。一番はやはり規格の記述が曖昧模糊ですから、認証機関によって解釈の幅が広いです」
「ISO9001とはかなり様相が違いますね。一番はやはり規格の記述が曖昧模糊ですから、認証機関によって解釈の幅が広いです」
|
ここで描くストーリーはフィクションであるが、登場する規格解釈、いや規格誤解釈は実際に何度も体験したものであり、私が創作したものではない。 残念ながら私の想像力はあまり豊かではなく、経験しないものは語れない。 |
山口は、A4で数枚の資料を佐川に渡す。
![]() 「マニュアルに規格の用語が全て入っていないとダメ……アハハハ、前世ではよく言われたな」
「マニュアルに規格の用語が全て入っていないとダメ……アハハハ、前世ではよく言われたな」
![]() 「どういう論理で説得したら良いものですか?」
「どういう論理で説得したら良いものですか?」
![]() 「オイオイ、山口さんとあろうものが何をおっしゃる。基本に戻れば一発アウトでしょう、もちろん認証機関側が」
「オイオイ、山口さんとあろうものが何をおっしゃる。基本に戻れば一発アウトでしょう、もちろん認証機関側が」
![]() 「基本に戻ると言いますと?」
「基本に戻ると言いますと?」
![]() 「魔法の呪文は『マハリーク マハーリタ』、ISOの呪文は『規格のどこにありますか』に決まっているよ」
「魔法の呪文は『マハリーク マハーリタ』、ISOの呪文は『規格のどこにありますか』に決まっているよ」
魔法の呪文は 規格のどこにありますか〜
| |||
 | |||
![]() 「そう言えばマニュアルを作れという要求は、規格にありませんね。
「そう言えばマニュアルを作れという要求は、規格にありませんね。
規格にないマニュアルを、認証機関に作れと言われて作っているのだから、マニュアルが規格不適合になるはずがない。
認証機関との契約でマニュアルに書けとされていることは書いているから、契約違反でもない。いや不適合にされたら契約不履行で、契約解除と賠償を要求しないとなりませんね」
![]() 「ならばそう言えば良い。
「ならばそう言えば良い。
ついでになぜ規格にも契約にもないことを要求するのか、問い詰めてほしいね」
![]() 「他社ですが、認証の相談に行ったときマニュアルを見て環境側面を特定する手順がないと言われました。著しい環境側面を決める手順は考え付くのですが、環境側面を決める手順は思いつかなかったです。
「他社ですが、認証の相談に行ったときマニュアルを見て環境側面を特定する手順がないと言われました。著しい環境側面を決める手順は考え付くのですが、環境側面を決める手順は思いつかなかったです。
佐川さんも、環境側面を把握する手順を書いていなかったようですが」
![]() 「環境側面を特定する手順がない……これって規格要求にあったかな?
「環境側面を特定する手順がない……これって規格要求にあったかな?
そもそも著しい環境側面を決定する手順が、必要なのか私は疑問なのよ。だって現実を考えると、新設備、新物質、新工程を導入する際に、安全衛生、消防法、非常時の対応などを検討し、その対応をしなければならないのが日本の法律だ。
新しいものが加わる都度、それを調査し対応するのだから、それが環境側面を特定し著しい環境側面があれば対応するというのが現実のフローだ。だから著しい環境側面に当たらないかを調べた結果、著しい環境側面とそれ以外ということになるのではないですかね?
規格でも著しい環境側面でないと判断されたものを、(著しくない)環境側面として登録しておけという文言はないよね」
1996年版では環境側面を決定して、その中から著しい環境側面を決定するとは記述していない。2004年版では、その流れが二段階に明文化された(4.3.1a)。
だが規格にどう書いてあろうと、組織の環境側面にどんなものがあるか調べましょう、そしたら環境側面にしたものから著しい環境側面に当たるのはどれかを調べましょうなんてオママゴトに付き合えない私である。要するに規格が間違っているのだ。
仮に二段階に作業することを正としても、環境側面のリストが必要かは大いに疑問だ。一旦著しい環境側面か否か決めた後に、著しいものになったり、著しいものでなくなることがあるのかと考えると、あり得ないように思う。
おっと、PCB機器の一部をJESCOに依頼したのを見て、「保管しているPCB機器が減ったのだから、PCBを著しい環境側面から落とせ」なんて言った審査員は論外だよ。
注: 「人外」には「じんがい」と「にんがい」の二通りの読みがあり、意味が違う。「じんがい」は尋常な世界でない異世界であり、「にんがい」は「人でなし」のことだ。
PCBを著しい環境側面から落とせと語った審査員は「にんがい」なのか「じんがい」なのか、私も分からん(笑)
![]() 「 『著しい』の付かない環境側面が出てくるのは、4.3.1で『活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し、維持』とあるのと、4.3.2で『環境側面に適用可能な、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定』そして4.4.3で『環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立し、維持しなければならない』だけだ。
「 『著しい』の付かない環境側面が出てくるのは、4.3.1で『活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し、維持』とあるのと、4.3.2で『環境側面に適用可能な、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定』そして4.4.3で『環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立し、維持しなければならない』だけだ。
(すべてこの時点の最適版であるFIDSを基にしている)
いずれも著しい環境側面を決定するための前段階についての要求であって、活動、製品又はサービスの環境側面を決定しろとは理解できないな。著しい環境側面を決定するための流れを述べているだけと思う。違うと言われると途中のリストを作るしかないね」
注: 「違う」と言えるのが「誰か」となるが、ISOTC委員にしても「その解釈は違う」とは理屈上言えない。
法律の解釈は制定した国会議員ではなく、第一段階は行政官であり最終判断は裁判官である。もし彼らの解釈が制定した国会議員の意図と異なれば、それは法律の文章が稚拙だということでしかない。
翻ってISO規格の解釈は誰かとなれば、商取引のトラブルであれば裁判官になるだろうが、根拠は翻訳されたJIS規格でなく英文のISO規格になるだろう。
そこにISOTC委員の入る余地はないと考えられる。ISOとしての公式見解が出るとは思えない。それはISO規格の文章が未熟であることになってしまう。
![]() 「規格の各項番の冒頭は一般論ですからね。具体的要求はその後に続いていて、そこでは皆『著しい環境側面』になっている……」
「規格の各項番の冒頭は一般論ですからね。具体的要求はその後に続いていて、そこでは皆『著しい環境側面』になっている……」
・
・
・
![]() 「おお、『著しい環境側面はスコアリング法が望ましい』というのがある。我々にとっては望ましくない認証機関だね、アハハハ」
「おお、『著しい環境側面はスコアリング法が望ましい』というのがある。我々にとっては望ましくない認証機関だね、アハハハ」
![]() 「だから冗談でなく、困っているわけですよ〜」
「だから冗談でなく、困っているわけですよ〜」
![]() 「環境マネジメントプログラムは目的用と目標用が必要と、疲れるねえ〜
「環境マネジメントプログラムは目的用と目標用が必要と、疲れるねえ〜
『マニュアル制定時に内容を審議した記録がありますか?』
マニュアルって制定するものなのか? 制定って『掟や規則として決めること』だよね。マニュアルが強制力のある規則と理解しているんだ、この認証機関は……
『環境方針が組織の活動製品及びサービスの、性質、規模及び環境影響に対して適切かを検証しているか?』
検証するほどのものかな? 経営者が自分の会社の規模や業種を理解していないで経営できないと思うけど。
『継続的改善の絵がマニュアルに載っていない』ときた、笑うしかないねえ〜」
|
右の絵が環境マニュアルに書いてないから不適合と言った審査員がいた。 果たしていかなる要求事項に不適合なのか? 教えてもらおうじゃないか! | 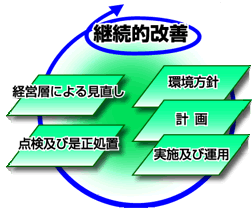 |
![]() 「おお、『著しい環境側面から環境目的を選ぶと書いてない』とあるぞ、
「おお、『著しい環境側面から環境目的を選ぶと書いてない』とあるぞ、
これは山口さんの説得力に期待しよう」
![]() 「ええ〜」
「ええ〜」
![]() 「魔法の呪文を唱えるだけの、簡単なお仕事じゃないか」
「魔法の呪文を唱えるだけの、簡単なお仕事じゃないか」
人事の吉田は未来プロジェクト兼務になったが、なぜかフルタイムで未来プロジェクト室にいる。実は、組織図上、専任者はプロジェクトマネジャーの佐山だけだ。
ということで佐川は佐山に、本務である環境部の仕事でISO14001認証が始まるので、未来プロジェクトに支障のない範囲で認証の指導をしたいと話した。
 |
|
| 吉田 |
吉田はその分自分が頑張るから大丈夫という。それを聞いて佐山は佐川がISO14001に関わるのを了解し、そちらの仕事もしっかりやってくれと激励した。
吉田は佐川は情報のソースでしかないとみなしており、未来予測の活用である対策や活用方法には佐川は無力だと見ている。実を言って下山次長と話して、いずれ情報を抜き取ったら佐川の兼務解任を予定している。
 |
|
| 佐山マネジャー |
佐山はプロジェクトが佐川の情報に頼っているのはしかたないが、佐川がリーダーシップをとるのは困ると考えている。
当然、リーダーシップをとるのは佐山でなければならない。組織論としてそれは当たり前のことだ。
佐川は早いところ未来プロジェクトと縁を切り、ISO認証も素早く終えて、根本的には当社グループの遵法と汚染の予防ができる体制の実現をしなければと考えている。
佐川の前世の経験から、ISO14001はその目的には無力なのだ。
 | |
おっとISO的には環境担当者の一層のレベルアップではなく、そういう体制と活動を会社の仕組みに盛り込んでいくことだ。
目指すところは三者三様であるが、当面の目標はなぜか一致している。まさに呉越同舟である。
今日、佐川は久しぶりに業界団体に来ている。認証機関と規格解釈の協議をする事前勉強なのだ。
出席者はH社の田中、N社の金子、F社の中村、それに業界団体の吉本、吉宗機械の佐川と山口である。
F社 中村 |  業界団体 吉本 業界団体 吉本 |
|||
H社 田中 |  吉宗機械 佐川 吉宗機械 佐川 |
|||
N社 金子 |  吉宗機械 山口 吉宗機械 山口 |
![]() 「やあ、佐川さん久しぶり。仕事替わったんだって?
「やあ、佐川さん久しぶり。仕事替わったんだって?
仕事が変わったと聞いて、またISOに参加してもらうのは気が進まなかったのだけど、頼れる人がいなくてね」
![]() 「いや、変わったというか兼務が付いたというか。環境も担当してますよ」
「いや、変わったというか兼務が付いたというか。環境も担当してますよ」
![]() 「そうなの、それならよろしくお願い」
「そうなの、それならよろしくお願い」
![]() 「我々が1年かけて自信をもってまとめたはずなんだけど、認証機関によってはけんもほろろというか、当社はそうは考えていませんなんて言うんだぜ」
「我々が1年かけて自信をもってまとめたはずなんだけど、認証機関によってはけんもほろろというか、当社はそうは考えていませんなんて言うんだぜ」
![]() 「業界系の産業環境認証機関に頼めばよいのに」
「業界系の産業環境認証機関に頼めばよいのに」
![]() 「吉本さん、それは何度も言っているでしょう。
「吉本さん、それは何度も言っているでしょう。
認定を受けていない業種は審査できませんし、取引上の
![]() 「話は聞いたのですが、具体的にはどうするのでしょう。面倒だから審査を予定している認証機関を一堂に集めて一挙に決めたらどうですかね?」
「話は聞いたのですが、具体的にはどうするのでしょう。面倒だから審査を予定している認証機関を一堂に集めて一挙に決めたらどうですかね?」
![]() 「おいおい、そんな乱暴な!」
「おいおい、そんな乱暴な!」
![]() 「ウチの場合、産業環境認証機関以外7社の審査機関に依頼する予定なんだ」
「ウチの場合、産業環境認証機関以外7社の審査機関に依頼する予定なんだ」
![]() 「それを皆、産業環境認証機関にはできないの?」
「それを皆、産業環境認証機関にはできないの?」
![]() 「先ほど金子さんが言ったように、産業環境認証機関が審査できない業種があったり、取引している顧客からぜひ使って欲しいと認証機関を指定されていることもあるのですよ」
「先ほど金子さんが言ったように、産業環境認証機関が審査できない業種があったり、取引している顧客からぜひ使って欲しいと認証機関を指定されていることもあるのですよ」
![]() 「そこをなんとか」
「そこをなんとか」
![]() 「吉本さん、それはこちらの言い分ですよ。ビジネスとして考えてください」
「吉本さん、それはこちらの言い分ですよ。ビジネスとして考えてください」
吉本氏は業界団体にいるから、傘下企業を目下に見ているのではないかという気がする。
こういう人はいずれ淘汰されるだろうと、皆、内心思う。
実を言いましてね、私が現役時代、某工業会にそんな女性がいました。事あるたびに私に突っかかってきました。困りますよねえ〜
![]() 「複数の認証機関に出さざるを得ないのは、どこも同じでしょう。それで、面倒事は一挙に片付けたいから、この業界の全企業は無理だけど、研究会の企業が依頼を予定している認証機関を、全部集めたらどうでしょうかね?」
「複数の認証機関に出さざるを得ないのは、どこも同じでしょう。それで、面倒事は一挙に片付けたいから、この業界の全企業は無理だけど、研究会の企業が依頼を予定している認証機関を、全部集めたらどうでしょうかね?」
![]() 「さすが佐川さん、おっしゃることがドラスティックだ」
「さすが佐川さん、おっしゃることがドラスティックだ」
![]() 「実際には大きなところ5社とか6社とか集めれば間に合うのかな」
「実際には大きなところ5社とか6社とか集めれば間に合うのかな」
![]() 「もちろん産業環境認証機関とイギリス系のまっとうなところを入れないとまずいね」
「もちろん産業環境認証機関とイギリス系のまっとうなところを入れないとまずいね」
![]() 「それは既に話がついているから、わざわざ呼ばなくても良いと思います」
「それは既に話がついているから、わざわざ呼ばなくても良いと思います」
![]() 「そうだけど、規格解釈がああだこうだ議論になってしまうと、研究会の見解が正しいと言ってくれるところがいないとまずいでしょ。
「そうだけど、規格解釈がああだこうだ議論になってしまうと、研究会の見解が正しいと言ってくれるところがいないとまずいでしょ。
既にイギリスでBS7750で審査している認証機関が、問題ないと言ったら反論できるわけないよ」
![]() 「さすが佐川さんですな」
「さすが佐川さんですな」
![]() 「実は研究会のメンバー企業が依頼を予定している認証機関のリストは作ってあるんだ。そうすると14社くらいかな。多くても16社くらいだろう」
「実は研究会のメンバー企業が依頼を予定している認証機関のリストは作ってあるんだ。そうすると14社くらいかな。多くても16社くらいだろう」
![]() 「それは研究会のメンバー企業が既に依頼を予定しているわけで、規格解釈を打ち合わせたいと招集すれば喜んでくるでしょうね」
「それは研究会のメンバー企業が既に依頼を予定しているわけで、規格解釈を打ち合わせたいと招集すれば喜んでくるでしょうね」
![]() 「そこんとこはどうだろうねえ〜、喜んでくるかどうかは定かではないんだ」
「そこんとこはどうだろうねえ〜、喜んでくるかどうかは定かではないんだ」
![]() 「へえ、どうして?」
「へえ、どうして?」
![]() 「いくつも認証機関が集まって規格解釈を討議するとなると、自分のところの解釈が間違っているとなると名誉問題だからね、討議することは必要ないとか、個々に打ち合わせすべきと言い出すかもしれない」
「いくつも認証機関が集まって規格解釈を討議するとなると、自分のところの解釈が間違っているとなると名誉問題だからね、討議することは必要ないとか、個々に打ち合わせすべきと言い出すかもしれない」
![]() 「まあ、出てこないならそれまでってことで」
「まあ、出てこないならそれまでってことで」
![]() 「出てこないなら審査依頼しないと言ったら」
「出てこないなら審査依頼しないと言ったら」
![]() 「各社によってそのへんは色合いが違うからね」
「各社によってそのへんは色合いが違うからね」
![]() 「出席しなければ受注するのに不利なのは理解するでしょう」
「出席しなければ受注するのに不利なのは理解するでしょう」
![]() 「皆がそう割り切っているならいいけど、取引上とか付き合い上、審査依頼をせざるを得ないこともあるだろうね」
「皆がそう割り切っているならいいけど、取引上とか付き合い上、審査依頼をせざるを得ないこともあるだろうね」
![]() 「皆と堂々と議論はできなくても、見解は他社に合わせるんじゃないか。
「皆と堂々と議論はできなくても、見解は他社に合わせるんじゃないか。
出席しなくても規格解釈は出席した他社に合わせないとダメなことは理解すると思うけど」
![]() 「個々に打ち合わせなくても、合同の説明会でこうなりましたと言えば、大勢に従うんじゃないかな。
「個々に打ち合わせなくても、合同の説明会でこうなりましたと言えば、大勢に従うんじゃないかな。
仕事が取れなくちゃ困るわけだし、よほど信念があるなら我々も変えろと要求することもない。仕事を出さないだけだ」
![]() 「我々がそこまで気を使うことはないか」
「我々がそこまで気を使うことはないか」
・
・
・
最終的に業界団体の環境ISO研究会のメンバー企業がISO14001審査依頼を予定している14社に招集をかけることになった。ディブのB○○社も入っているから彼でなくても誰かが参加するのは間違いない。
|
認証機関各位
ISO14001のFDISが発行されました。既にFDISによる仮審査・仮認証を始めるとしている認証機関も散見されます。 この規格はISO9001に比べて要求の記述が具体的でなく、読む人により規格の解釈に幅があると思われます。 弊工業会では昨年からDISを基に規格の解釈を進めてまいりました。 ついては弊工業会傘下の企業が審査を依頼する予定の皆様に、審査の前に、お互いの見解を明確にしておきたいと考えまして、弊工業会の見解を申し上げ、そのご理解を頂きたいと考えます。 下記により説明・検討会を持ちたいと思いますので、ご参集願います。 以上
|
|||||||||||
研究会のメンバーはレター文言を見て武者震いをした。
1年間、認証機関よりは真剣に考えてきたつもりだ。
招待状をもらった認証機関の人もいろいろであった。
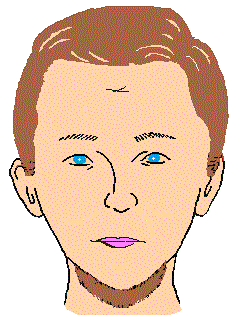 ディブ・ハワードはニヤリとした。招集された審査員の中で、自分は一番経験がありまっとうだとディブは考えている。
ディブ・ハワードはニヤリとした。招集された審査員の中で、自分は一番経験がありまっとうだとディブは考えている。
ISO9001やISO14001は、BS5750とBS7750をベースにしている。いずれも審査経験は豊富だ。
産業環境認証機関の取締役の4名は、招待状を見て自分たちは問題ないだろうと自認した。1年間、佐川を初めとするISO研究会にだいぶもまれたが、それは非常にありがたかったのだと今は認識している(cf.第64話)。
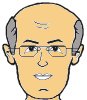 |
 | 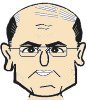 | |
怒りで手が震えた認証機関もあっただろう。
「ふざけるな!何も知らんくせに」と招待状を床に叩きつけたところもあるかもしれない。
あるべき姿かどうかはともかく、普通なら認証機関が認証を受ける企業に指導するところだ。それを認証を受ける企業が上から目線である。産業環境認証機関のようにISO研究会と関係を持たなかった認証機関は、血が上ったに違いない。
20世紀はそういう認証機関と審査員が普通だった。彼らは企業の担当者をISOを理解できない愚者だと信じていたから。
![]() 本日のお知らせ(その1)
本日のお知らせ(その1)
本日の小文に異議、苦情のある方は是非とも苦情窓口へ投稿願います。
お待ちしております。
 |
||
| 苦情窓口 |
![]() 本日のお知らせ(その2)
本日のお知らせ(その2)
次回更新は5月8日(木)の予定です。
5月5日(月)は更新ありません。
特段理由はないのですが、世間並みに連休というのをとってみようかと……
誰だ! 「毎日休みだろう」って言ったのは、
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |