注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
まず私の所信表明をしておく。
私はISO14001の著しい環境側面の決定方法として、スコアリング法を使うのは間違いだと考えている。
スコアリング法は物事を評価や比較する方法で、方法に問題があるわけではない。しかし使える場は限定される。いや使える場が限定されるのはいかなる方法も同じだ。
予防接種による病気の予防効果とその予防接種による副反応の比較を、感染者数、死者数、副反応の症状や発生数などを、実際の数字によって計算し評価するのは誠に正しい使い方だ。
元々、労働安全衛生でリスク評価に使われていたらしい。
だが労働安全衛生の使い方をみると、その数字の根拠を知らない私は信頼性を疑う
2010年頃、ISO14001審査に、企業で安全衛生を担当していたという人が審査員で来た。当時、私は先人が構築したスコアリング法による著しい環境側面決定手法を、新規導入時に法規制で評価することを著しい環境側面決定とすることに切り替えていた。
それを見た審査員が、その方法を批判したが、その変更は認証機関の幹部に話を付けていたから、審査員が不適合とすることはできなかった。
その代わりその審査員は、労働安全のリスク評価にスコアリング法を使うすばらしさを、熱く語っていた。
まあ、惚れ込むのは勝手だが、それを他人に押し付けるのは止めてほしい。
労働安全衛生でリスク評価にスコアリング法を使った経緯は知らない。その理論についての論文があるのかと、調べたが見つからなかった。少なくてもCINIIにはない。案外、理論的な根拠はないのかもしれない。
まあ、関係者が素晴らしい方法だと喜んでいるのに、疑問を呈することはない。
最近は発生確率を実情調査結果に、損失も実際の喪失日数など基にする方法の採用も多くなっている。
また重大であればそれだけで高リスクと判断することが多くなっている。東日本大震災以降は、原発の安全対策には発生確率を盛り込まず、発生が予測されるなら対策する考えも唱えられている。
スコアリング法を著しい環境側面決定の手段として使うなら、発生、重大性について客観的な数字を使ったものでなければ私は不適切だと断じる。
そしてそれは不可能に違いない
ISO14001の認証が始まったときも、私は当時の勤め先でISO14001認証担当だった。知り合いの伝手で、認証活動を進めていた某社に教えを請うた。
対応してくれた方が
「著しい環境側面の決定方法の見当がつかないので、近隣工場と集まって検討している。法規制に関わること、公害問題になる恐れのあるものなどを抽出すれば良いのかと考えている」
と話してくれた。
それから半年ほど経って、その工場が認証したと聞いてまた出かけた。
以前の方とお会いして話を聞くと
「著しい環境側面の決定を検討していたことはすべて否定されてしまった。認証するにはスコアリング法しかない。その方法でやらないと審査する以前に門前払いを食らう。お宅は何も考えずに、その方法を取りなさい」
と疲れたきった顔で言われた。
なお、スコアリング法を学ぶには、その認証機関の講習を受けるしかないそうだ。そしてその講習会は大盛況で部屋の外まで椅子を並べるほどだという。受講の予約が取れないと困っている人が多いそうだ。
なんかマッチポンプの臭いがする。
その認証機関の講習を同僚と二人で受けた。1997年の夏であった。
噂たがわず、教室備えつけの椅子では足りず、その後ろにパイプ椅子を並べてあった。流石に廊下までというのは大げさだったようだ。
前の方はテーブルがあるが、後ろの方は資料をひざの上においてメモをした。
しかし内容はひどいものだった。スコアリング法とはデタラメを意味するのかと思った。
講師が言うには、発生頻度、悪影響、影響の続く期間、そんなことを3つか4つ取り上げて、それぞれに階級を付け配点する。それらを影響を表す算式を考えるのだそうだ。加減乗除なんでもござれだという。
要素も自由、算式も自由、配点も自由、皆が著しい環境側面と考えたものの点数が、大きくなるようにしろと言う。
発想がデタラメというか自由奔放だが、更に面白いというか興味を持ったことは、配った資料には、そういうことは一切書いてない。資料にはそういう要素を全体的に考慮して著しい環境側面を決定するのだと書いてあるだけだ。
要素も自由、算式も自由、配点も自由、皆が著しい環境側面と考えたものの点数が、大きくなるようにしろとは、一切書いてないのである。
これって面白くないですか?
証拠隠滅でしょうか?
そのときは著しい環境側面の決定方法にスコアリング法を使うこと一択で仕方なく従った。ただ私は納得できずその作業をしたくなかった。それで同僚にお願いした。
彼はエクセルの表を作り、著しい環境側面にすべきと皆が考えたものが上位20位になるように、かなり複雑な関数を仕込んだ。とはいえ一日もかけずに作り上げた。
お疲れ様と労わったが、本人も含めてバカバカしいと思ったものである。
ともかくISO14001の著しい環境側面の決定には、スコアリング法しか認めないのが、当時のデファクトスタンダードだった。
審査が始まる前の1996年頃には、著しい環境側面の決定方法が、品質管理関係とか業界の雑誌に多様な方法が提案されていた。私もそういうのを読んでいた。
だが前述したように、1997年審査が始まると、「スコアリング法にあらずばISOにあらず
もちろん少数の認証機関では、いかなる方法でも真っ当ならOKしたのだが、日本は業界系認証機関という悪弊があるから、良い審査をする認証機関を選ぶことは、事実上、不可能なのだ。
中小企業ならそんな
外資系認証機関では、スコアリング法以外の著しい環境側面の決定方法の講習会を開いていた。ただ外資系の講習会は審査を依頼した企業に対して、無料で情報提供するものであり、誰もが参加できるものではなかった。受講しても使えない手法なら習う意味がないしね。
私は伝手を頼って2回そういうものに参加したことがある。講師はスコアリング法を、けちょんけちょんに貶していた。それも含めて大変勉強になった。
なお誤解をされないように、付け加えておく。講習内容は一般的な手法であり、コンサルに抵触するものでないのはもちろんである。
もっとも、それを言ったら当時ISO14001認証件数がトップだった某認証機関が、著しい環境側面の決定方法の講習をできるわけがない。
スコアリング法以外の手法を書いた書籍は、私は度々取り上げているBVQI社の1点だけであった
それは過去の話ではない。あれから30年経った今でも、入手できるISO14001本でスコアリング法以外の存在を記しているのは少数だ。更にスコアリング法以外の手順詳細を述べた書籍はBVQIのもの以外見たことがない。
ネットでも、著しい環境側面の決定方法とググれば、99%がスコアリング法だ。このウェブサイト以外で、著しい環境側面の決定方法を多々取り上げて解説しているのはないはずだ。 私がウソをつくかもしれないから、一日くらい潰してネットで調べてもらいたい。 まさに悪貨は良貨を駆逐する、そのものだ。
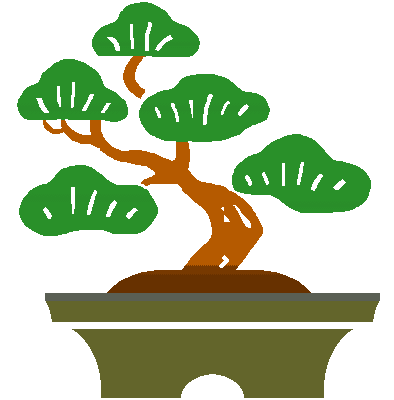 |
|
| 盆栽なら捻じくれたのが 良いかもしれないが・・・ |
ISO14001は盆栽のように、人為的に捻じ曲げられてしまったのだ。
盆栽なら、ねじくれて素直でないのが良いかもしれないが、ISOMS規格も人間も、まっすぐで素直でなければならない。
昼休み休憩が終わり、審査の午後の部が始まる。
午前中の予定では、環境側面、法及びその他の要求事項、目的目標、環境マネジメントプログラムまで審査する予定だったが、現実には環境側面さえ完了どころかまともに審査をしていない。
どこまで審査したことにして、午後はどこから始めるのか、辻井課長も内山も予想もできないが、審査員のやりたいようにやってもらおうと考えている。
関係者が午前と同じ部屋で待っていると、審査員2名が入って来る。
![]() 「午後は法的及びその他の要求事項から始めたいと思います。
「午後は法的及びその他の要求事項から始めたいと思います。
対応される方はどなたですか?」
![]() 「私です」
「私です」
 |
||
 |
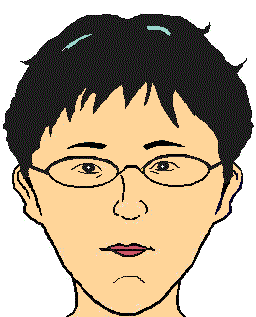 内山担当 内山担当 |
法規制と考えている範囲、調べる方法、該否の決定などについて、まあ審査としては妥当な質疑応答が続く。
辻井課長は脇で見ていて、審査員たちは反省というか、ウチの姿勢を見て余計なことを言わないよう舵を切ったようだと考える。
内山も審査対応を無難にこなしている。これで問題なく進むなら良いなと思うのだった。
審査は順調に進んでいく。そして目的目標となる。
ISO14001の審査が始まったとき、一番論争となり不適合が多かったのは「環境側面」であった。
だが「環境側面」の不適合は、半年ほどで急速に終息して……認証機関がスコアリング法を強制したからともいえる……次に不適合のトップの座を奪ったのは「目的、目標及び実施計画」だった
なぜ「目的、目標及び実施計画」なのかと考えると、審査が非常に簡単だからだと思う。例えば「内部監査」とか「遵守評価」などになれば、内容をよく見て規格要求に照らして不適合を出すのは簡単ではない・・・まあ人によるけど
「目的、目標及び実施計画」なら、「計画より遅れているね」、「何パーセント遅れたら是正を開始するのか」、「計画より進んでいても是正処置をしなければならないだろう」、「目標の中に、絶対値のものと、昨年との相対値のものがあるが統一すべきだ」てなことを語り、不適合を出せば良いのだ。専門知識不要で1日習えばできる。
すべて私の実体験である。
非常に楽で簡単だ。1時間2万円も取るお仕事ではない。弁護士だって5千円だぞ。
ちなみにISO9001のときの不適合の多い項番は、文書管理と教育訓練だった。これも審査は簡単だよね。
「○○課に配布されていた工場の規定集の文書番号○○のバージョンは正しくEなのにDがファイルされていた」とか「○○課の教育計画で受講していない人が〇名いたが、その対策が取られていない」なんて書けばOKなんだもん。
「資格不要、経験不問、誰にでもできます」
20世紀は「ISO9001を認証して良くなったのは文書管理だけ」と言われた。本当を言えば、文書管理も良くなってなく、見せかけただけではないのか?
なにごとも「上に政策あれば下に対策あり」、人間は相手の裏をつくのは上手いのだ。
おっと、審査は進んでいるようです。
![]() 「省エネで人感センサーを付けたとありますが、本日、巡回したとき、倉庫に入る前に照明がついていましたね」
「省エネで人感センサーを付けたとありますが、本日、巡回したとき、倉庫に入る前に照明がついていましたね」
![]() 「職場の照度基準はJISや安衛法の規則で決まっています
「職場の照度基準はJISや安衛法の規則で決まっています
今どき100Lx(ルックス)では危険です。同じく事務所で300Lxじゃ仕事になりません。
そして通常は人感センサーを付けるとなると、照明のON/OFFを人感センサーでしているのが多いです。
当社では労働組合との協議や、今まで各現場から出ていた要望や提案などから、安衛法の基準は常時維持して、人が入った場合に当社が決めた基準まで明るさをアップするという基準にしています」
注:私が子どもの頃、家庭の照明なんてひどいものだった。白熱電球であるのはもちろんだが、家庭では40Wとかが普通で、100Wなど見たことがなかった。トイレに至っては10Wとか15Wだった。真っ暗闇でなければ良かったとしか思えない。
 だからトイレのお化けの話ができたのだ。明るくてはお化けは出ない。
だからトイレのお化けの話ができたのだ。明るくてはお化けは出ない。
![]()
そして二部屋あれば、部屋を仕切る欄間に電球を一個付け、両方の部屋を照らすとか、お風呂と洗面所の間の壁に30センチ四方の穴をあけ、そこに電球を付けるというのも一般的だった。
そんなわけで1戸建ての家に電球が6個くらいしかなかったのだ。当然一般家庭の契約は10Aで、使用電力量も月50kWh位しかなかった。
![]()
学校の教室には部屋の真ん中に100Wくらいの電球を付けていただけ。日中でも雨が降ったりすると、暗くて黒板に書かれたものなど見えないのが当たり前だった。
そういう時代だから、会社でも官庁でも、暗いのは当たり前だったのだろう。
![]() 「どれくらい違うのですか?」
「どれくらい違うのですか?」
![]() 「ロッカールームや倉庫や通路は無人のときで100Lxを維持して、人がいる場合500Lxにしています」
「ロッカールームや倉庫や通路は無人のときで100Lxを維持して、人がいる場合500Lxにしています」
![]() 「それじゃ省エネ、いや環境保護に逆行じゃないか」
「それじゃ省エネ、いや環境保護に逆行じゃないか」
![]() 「今この部屋の明るさはいかほどと思いますか?」
「今この部屋の明るさはいかほどと思いますか?」
![]() 「事務所は法で300Lxだったね、それと同じくらいかな」
「事務所は法で300Lxだったね、それと同じくらいかな」
![]() 「いえ、700Lxあります。事務所と言っても、手書きの大きめの文字の時代とパソコンモニターを見る時代では環境条件が変わります。
「いえ、700Lxあります。事務所と言っても、手書きの大きめの文字の時代とパソコンモニターを見る時代では環境条件が変わります。
倉庫の仕事で電卓は必需品です。当初は今より照度を下げていたのですが、今の電卓はほとんどソーラー電卓で、
 省エネにするため反射型液晶なので暗いと見えないのです
省エネにするため反射型液晶なので暗いと見えないのです
そもそもソーラー電卓は、暗いと動作しません。カタログでは120Lx以上あれば動作するとありますが、常に太陽光パネルが光源を向いているわけでないので、それ以上に明るさが必要です。
それに今は監視カメラなどで監視していることもあり、常に最低限の照度は必要です。そんなことで倉庫も明るさの基準をあげています」
![]() 「それは無駄なエネルギーですね」
「それは無駄なエネルギーですね」
![]() 「そうとも言えますが、保安と安全と目の健康には恩恵ですね。でも省エネに努めて目が悪くなり健康寿命が短くなっても理想ではないでしょう。
「そうとも言えますが、保安と安全と目の健康には恩恵ですね。でも省エネに努めて目が悪くなり健康寿命が短くなっても理想ではないでしょう。
それに皆さん気づいてないでしょうけど、どの会社でもオフィスは事務所規則の照度(300Lx)じゃありませんよ。それ以上に明るくしないと快適に仕事ができません。
あなたも今私に言われて気が付いたくらいでしょう。
もちろん省エネもしています。以前は天井が高いところは水銀灯でしたが、照明の位置の見直しなどで消費電力を減らす工夫をしています。
数年前から電球型蛍光灯も広まってきました。LED照明が現れれば大きく省エネになります
「なによりも安全第一です。法を守って暗いところで怪我してもしょうがない、アハハハ」
後ろに座っている面々も一緒になって笑う。
辻井課長は笑い声から、開始時より大分人が増えたように感じて振り向く。
お、組合委員長もいる。ISO審査と聞いて視察に来たか、ご苦労なことだ。
二人の審査員は面白くない顔をする。
![]() 「計画は順調ですが、毎月をみると進捗に凸凹もありますね。
「計画は順調ですが、毎月をみると進捗に凸凹もありますね。
未達と判断するのはどういう基準ですか?」
![]() 「未達と言ってもいろいろあると思います。機械の設置工事が遅れるのも未達、工事完了しても、予定通りのパフォーマンスが出ないのも未達です。
「未達と言ってもいろいろあると思います。機械の設置工事が遅れるのも未達、工事完了しても、予定通りのパフォーマンスが出ないのも未達です。
ただ内容に差があります。
まず原因不明で工事が遅れるということはありません。工事が遅れるには理由があります。言い方を変えると事情があるから工事を遅らせたといいますか。
もちろん小まめに計画を見直せばよいでしょうけど、短期間の変更をわざわざ計画表に反映するのも手間暇、つまりお金がかかります。
当日朝、業者が作業員が具合が悪くて休みが出たと連絡があれば、それじゃ明日以降人数かけて挽回してよというのを、計画変更することもないでしょう。
そういうことを考えて指示するのは、担当者の裁量範囲です。
工事完了して期待通りにならないものは、もちろん原因調査をします。ただ予期せぬこと、例えば建物の柱とか基礎が図面通りでなかったとかありますと、現状追認ということもありますね」
![]() 「そういういい加減な仕事をしているの?」
「そういういい加減な仕事をしているの?」
「この工場は建ててから50年経過しています。当時の図面などありませんよ。
現場は生きていますから、常にそのとき、そのとき、最善を選択していると考えてください」
![]() 「目標の中に、絶対値のものと、昨年との相対値のものがあります。
「目標の中に、絶対値のものと、昨年との相対値のものがあります。
エネルギー原単位は前年度比1.9%減で、上水使用は3,500トン目標、廃棄物排出量が198トン以下と、見ごとにバラバラですね。
これは統一すべきです」
「測定の対象物の性格によるでしょうね。エネルギーは省エネ法とかグループ全体の目標の展開上、削減割合で示しています。そうでないとどこかで換算する工程が入りまして面倒です。
そればかりでなく用途次第というところがあります。工場排水の測定値であっても、排水処理装置の運転状況把握なら相対値でしょうし、排水の測定なら絶対値だと思います」
![]() 「そういうことであっても相対/絶対は合わせるべきでしょう」
「そういうことであっても相対/絶対は合わせるべきでしょう」
![]() 「NCプログラムなんて、絶対値指定と相対値指定が、混在してもおかしくもないですね。必要に応じて使い分けます
「NCプログラムなんて、絶対値指定と相対値指定が、混在してもおかしくもないですね。必要に応じて使い分けます
注:NCプログラムは環境管理とは関係ない、単なる例だ。
辻井課長は、また始まったかとニヤニヤする。
丁度、休憩のチャイムが鳴る。
「おーい、休憩時間だ。一旦休憩しよう」
審査の休憩を断りなしに言われて、小畑と須田は面白くない顔をしていたが、辻井課長に苦情は言わなかった。
休憩になったのを見計らって、辻井課長のところに女性事務員が佐川を連れてくる。
二人は名刺交換する。
「お呼びだてしてすみません。当初は環境側面の決定方法で議論となって、にっちもさっちも行かなくなりました」
![]() 「現状は特段、トラブルはありませんか?」
「現状は特段、トラブルはありませんか?」
「昼休み前に少し脅しをかけました。そのせいか脱線はなくなりました。
とはいえ、先ほども重箱の隅をつつくような感じでした」
![]() 「いやいや、あの程度なら、審査では普通と思わなくちゃいけません。
「いやいや、あの程度なら、審査では普通と思わなくちゃいけません。
ちょっと、審査員に挨拶してきますね」
佐川は所在なげに座っている審査員のところに行く。
接客用の笑顔を顔に貼り付けて審査員二人と名刺交換する。
 |  |
小畑は佐川の名刺を眺めて、困った風に言う。
![]() 「ISO審査に外部の方が陪席されるのは、お断りしているのです」
「ISO審査に外部の方が陪席されるのは、お断りしているのです」
![]() 「お宅の会社の了解は得ております。ええと三崎部長さんとおっしゃいましたが、親会社が立ち会って状況を確認するのは良いことだと誉められました。
「お宅の会社の了解は得ております。ええと三崎部長さんとおっしゃいましたが、親会社が立ち会って状況を確認するのは良いことだと誉められました。
ここは吉宗グループではISO14001認証のトップを切っていますので、これから始まるグループ企業の審査を受ける参考にしたいと考えております」
![]() 「上が了解しているなら仕方がないですね。発言、撮影、録音などはご遠慮ください」
「上が了解しているなら仕方がないですね。発言、撮影、録音などはご遠慮ください」
![]() 「分かりました」
「分かりました」
 |
 |
佐川は部屋の一番後ろに下がってパイプ椅子に座る。
えー、今回も審査が終わりません。
![]()
次回に続く
![]() 本日の謎
本日の謎
審査員の資格には、主任審査員と
複数人で審査をするとき、リーダーは主任審査員でなければならない。一人で審査するには主任審査員の資格が必要だ。要するに主任審査員になって一人前ということだ。
だが主任審査員になるには、審査員になって、何回、何日以上の審査実績などの要件を満たさないとなれない。
ISO14001審査が始まったとき、最初の主任審査員はどう見繕ったのか、私は分からない。
ISO9001のときは、最初はイギリス人が来たし、その助手として日本人のアプレンティスが付いてきたこともある。だから順々に育成されていったのだろう。
おっと、それはイギリスだって同じだろうというと、その通りだ。イギリスの最初の主任審査員は誰だったのだろうか?
謎である(笑)
![]()
いや、冗談ではなく、審査員の教育・育成の制度的欠陥が、まともな審査が行われなかった原因かもしれない。
なお、2006年にISO17021が制定され、審査員の力量は審査員登録機関が保証するのではなく、認証機関が保証しなければならないことになった。
ということで審査員、主任審査員は認証機関が認めれば良くなった。
![]()
となると審査員登録機関の役割というか存在意義はなんだろうとなるが、それは言わない約束らしい。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
・厚生労働省 危険性又は有害性等の調査等に関する指針 ・厚生労働省 リスクアセスメント評価基準(例) 数字は(例)であるのだろう。この例の数字をそのまま使って良いのか分からないが、ともかくその数字をみると私はおかしいと思う。 表で重篤度は「致命傷」が「軽傷」の3.3倍の点数だが、とても妥当とは思えない。「軽傷」とは通常全治1カ月以内をいう。  仮に「致命傷」による労働できる期間の喪失を20年とすれば、「軽症」の240倍の損失となる。「致命傷」は「軽傷」の無限倍とは言わないが、絶対に3.3倍ではない。
仮に「致命傷」による労働できる期間の喪失を20年とすれば、「軽症」の240倍の損失となる。「致命傷」は「軽傷」の無限倍とは言わないが、絶対に3.3倍ではない。表で発生の可能性は、「確実に起きる」が6点、「ほとんどない」が1点とは感覚とマッチしない。「確実」なら99%、「ほとんどない」は1%だろう。ついでに言えば「稀にしか起きない」は0.1%、「非常にまれ」は0.01%というところではないか? ひょっとして配点表の数字は、等差数列でなく対数かもしれない。だが対数とすると、「確実」が6なら「ほとんどないは」2桁違うから4のはずで、どうも違う。それに「致命傷」では軽傷と7違うから、対数なら10の7乗となり83万年となり、これもおかしい。 とすると常用対数でなく自然対数とか底を2くらいにするのだろうか、と思ってやってみたがすべてを同じ底にするのは無理のようだ。となると底が違う対数の足し算などできるわけがない。いったいどういうことだ! 労働安全のリスク評価はどうでも良いが、環境影響の評価に持ち込むのは無理筋である。 | |||||||||||||||||
| 注2 |
よく「平家にあらずんば人にあらず」と言われるが、平家物語の原文は「この一門(平家)にあらざむ人は、みな人非人なるべし」であり、更に語ったのは平清盛でなく、平 なお それでこの文は「平家一門でないと宮中では出世できない」という現実を言っただけという説もある。 | |||||||||||||||||
| 注3 |
正確には1996年対応と2004年対応の2点がある。 「環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き」原田 伸夫, 土屋 通世、システム規格社、2000 「ISO14001:2004対応 環境マネジメントシステムの構築と認証の手引き」土屋通世、システム規格社、2004 いずれも当時でも入手困難な稀本であった。私が指導していた会社で欲しいと言われて差し上げたが、今思うと返してもらえば良かった。 | |||||||||||||||||
| 注4 |
このウェブサイトの「ISO14001審査不適合の分布」参照 | |||||||||||||||||
| 注5 |
明るさを定めている法令 ・労働安全衛生規則 第604条 ・事務所衛生基準規則 第10条 倉庫が75Lx、通路が100Lxなんて、とてもじゃないけど歩くのが戸惑われる。製図室が750Lxだが、これでも暗いと思う。 要するに法令で定めるものは最低基準で、それ以上でないと仕事にならない。 蛇足だが、法令とは、法律・施行令・省規則を合せて言う。 | |||||||||||||||||
| 注6 |
反射型液晶とは外部からの光を反射して表示するために、暗いと画面が見えない。 対して透過型液晶はバックライトを用いて表示する。暗くても良く見えるが電源が必要。 | |||||||||||||||||
| 注7 |
電球型蛍光灯の登場は1980年であるが、一般に使われたのは21世紀になってからだ。2008年の洞爺湖サミットで電球型蛍光灯がもてはやされた。 LED電球は2006年登場したが、普及したのは2010年以降である。 白熱電球・蛍光灯との比較とメリット・デメリットをご紹介します より引用
同じ明るさでの電気代の比較
現実には、価格、寿命の違い、器具との互換性などいろいろ考慮しなければならない。 | |||||||||||||||||
| 注8 |
NCフライスでは、絶対値指定か相対値指定かは個人の好みというより、プログラム作成上 必然的に決まる。個々の加工をサブルーチンにするなら、サブプログラムは相対値指定で書き、メインプログラムはそれぞれの加工起点を絶対値指定するのが普通だと思う。 そういうことをしていると、様々な管理指標に絶対値/相対値が混在しても変だとは思わない。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |