注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
88話の続きです。
アジア通貨危機始まりの翌日である。
佐川がメールチェックしていて、山口から転送されたメールを見つけ、佐川はいろいろ考える。
まず、広報部に電話が来て、広報部がこちらの電話番号だけを教えたというのが腑に落ちない。広報部が返事をする前に、佐川の意向を聞くのではないか? 最低でも事後に経過を伝えて対応を依頼するメールくらい寄こすだろう。
それは礼儀というものではなく仕事の基本だ。
それと、個人名を指定するなら、未来プロジェクトが本務の佐川より、環境部にISO担当の山口がいるのだから、彼を指名するのが筋だろう。
そうそう山口が知らないのだから、山口が噛んでいるわけがない。
要するに経緯が見えないが、いずれにしても筋が通らない。
佐川は仕掛かりを残さない人間だ。即断即決のみならず、即行動だ。
山口からの転送メールにコメントを付けて、広報部の課長宛と環境部の藤田課長に写を転送する。
TO:広報部 広瀬課長殿 CC:環境部 藤田課長殿 環境部 山口殿 未来プロジェクト 佐川です。 本メールが私宛に転送されましたが、事前に何も相談もありません。先方の聞きたいことなど一切なく、日時なども私が設定するのでしょうか? 脈絡なく困惑しています。 認証計画などでしたら、広報部が情報を持っているでしょうし、認証制度などについては企業の者が説明するまでもなく、認証制度がウェブサイトなどに説明をあげています。 認証指導のノウハウとか規格解釈となりますと、社外秘的なことですし、世のコンサルはそれでお金を儲けているわけで、簡単に話すべきことではありません。 会社の考えとして、何をどこまで情報公開しても良いとかなどの条件を聞かないと私は対応できません。 以上のことから、このメールについて私は対応できません。再度、広報部、環境部で決めていただきたく 広報部、環境部で対応できない場合、私が対応することに異存はありません。 ご検討ください。 ---------------- TO:未来プロジェクト 佐川様 佐川様 環境の山口です。 環境部からのメールアドレスに佐川様宛のメールが入っていました。 私は心当たりありませんので、佐川さん個人宛と思い転送いたします。 ---------------- TO:吉宗機械株式会社 本社 環境部 佐川課長様 CC:吉宗機械株式会社 本社 広報部 ご担当者様 ISO14001の件、インタビューのお願い
初めてメールを差し上げます。 *********************************************** *********************** ******************** |
1時間もしないうちに、広報部所属で未来プロジェクト兼務の![]() 石川から電話が来た。いつも明るい女性だ。広報部とは彼女のようなタイプが合うのだろうか?
石川から電話が来た。いつも明るい女性だ。広報部とは彼女のようなタイプが合うのだろうか?
![]() 「佐川さんからウチの課長と環境部の藤田課長に、雑誌社の取材要請のメールに問い合わせしたでしょう。今、広報部でいったい誰が何をしたかって、大騒ぎで調査中よ、なにしろ職制無視の行動ですもんね。
「佐川さんからウチの課長と環境部の藤田課長に、雑誌社の取材要請のメールに問い合わせしたでしょう。今、広報部でいったい誰が何をしたかって、大騒ぎで調査中よ、なにしろ職制無視の行動ですもんね。
佐川さん、まさに爆弾投下ね、アハハハ」
![]() 「オイオイ、爆弾を落としたのは私じゃないよ。誰なのかを調べてよ。
「オイオイ、爆弾を落としたのは私じゃないよ。誰なのかを調べてよ。
私は押田氏と面識はない。そもそも広報部からメールアドレスを聞いたと書いてあるのだから、お宅の誰かがあのメールアドレスを教えたわけだ。外部用のメアドだとしても私宛にメールが来ること自体おかしい。それに取材をOKしたのは誰なのよ?」
![]() 「山口さんからの転送だから、山口さんが教えたかもしれないわ」
「山口さんからの転送だから、山口さんが教えたかもしれないわ」
![]() 「それはないな、彼が私にメールを転送してくれたのだから」
「それはないな、彼が私にメールを転送してくれたのだから」
![]() 「そうねえ、どういうことなのかな? とにかく状況報告よ。じゃ、一旦切るわ」
「そうねえ、どういうことなのかな? とにかく状況報告よ。じゃ、一旦切るわ」
その日の夜、7時過ぎ、山口から電話が来た。
![]() 「まだ、いらっしゃいましたか。相変わらずですね」
「まだ、いらっしゃいましたか。相変わらずですね」
![]() 「まだ宵の口ですよ。どうしました?」
「まだ宵の口ですよ。どうしました?」
![]() 「私が転送して佐川さんが広報とウチの課長に問い合わせたメールがありましたね。大騒ぎになりました。
「私が転送して佐川さんが広報とウチの課長に問い合わせたメールがありましたね。大騒ぎになりました。
犯人は環境部の![]() 坂内さんでした。広報から
坂内さんでした。広報から![]() 藤田課長宛てに、押田さんのメールが転送されてきて、藤田課長が坂内さんに押田さんに内容などを確認してほしいと指示したそうです。
藤田課長宛てに、押田さんのメールが転送されてきて、藤田課長が坂内さんに押田さんに内容などを確認してほしいと指示したそうです。
坂内さんは面倒なこと大嫌いな人で、なにもせずに佐川さんの外部用メアドを押田さんに送って詳細は直接話し合ってくださいとやったそうです」
![]() 「なるほど、坂内さんらしいな。じゃあ、その後のことは広報と環境でやってくれるのね?」
「なるほど、坂内さんらしいな。じゃあ、その後のことは広報と環境でやってくれるのね?」
![]() 「そうでもないのです。犯人が見つかったのは夕方ですが、どうするかは決まっていません。押田さんに佐川さんの名前を教えたからには、私を代役に立てるのもはばかられて、明日双方の課長が集まって考えるそうです」
「そうでもないのです。犯人が見つかったのは夕方ですが、どうするかは決まっていません。押田さんに佐川さんの名前を教えたからには、私を代役に立てるのもはばかられて、明日双方の課長が集まって考えるそうです」
![]() 「私に塁が及ばないように頼むよ」
「私に塁が及ばないように頼むよ」
電話を切ると、佐川はもう押田氏の取材話とは縁が切れたと忘れた。
翌朝、10時頃、広報の広瀬課長が佐川を訪ねてきた。
未来プロジェクトの事務室には外部の人を入れないので、広瀬課長は表のドアと内側のドアの間にあるパントリーと机ひとつにパイプ椅子が数脚置いてある小部屋で話をする。
![]() 「ここはなんだか国家機密みたいだねえ〜」
「ここはなんだか国家機密みたいだねえ〜」
![]() 「国家はつきませんが機密に間違いないですよ。もう言って良いかな? 最近のヒットはアジア通貨危機を予言したことです」
「国家はつきませんが機密に間違いないですよ。もう言って良いかな? 最近のヒットはアジア通貨危機を予言したことです」
![]() 「アジア通貨危機、ああ一昨日の東南アジア諸国の為替レートの暴落ね。どうなるのかね? 日本にも累が及ぶのかな」
「アジア通貨危機、ああ一昨日の東南アジア諸国の為替レートの暴落ね。どうなるのかね? 日本にも累が及ぶのかな」
| ฿ | |
| バーツ燃ゆ |
![]() 「日本は直接的なダメージよりも、バブル崩壊からの回復にとどめを刺される感じでしょうね。ここ数年上向いてきましたが、だいぶ影響を受けるでしょう
「日本は直接的なダメージよりも、バブル崩壊からの回復にとどめを刺される感じでしょうね。ここ数年上向いてきましたが、だいぶ影響を受けるでしょう
幸い、財務部と経営企画室はこれを半年前から把握していて、タイに所在する工場の生産計画、出荷計画へ反映していましたし、投資計画なども見直ししています。
数十億の被害を減らし利益を増やしたと言えますよ」
![]() 「なるほど、頭に入れておくわ。
「なるほど、頭に入れておくわ。
数日したら当社も東南アジア諸国の為替が経営にどう影響するかという広報をすると思うの」
![]() 「広報というのは工場と違って、国際政治や経済に直結しているのですね。もっとも作文は経営企画室とか財務部が書くのでしょうけど。
「広報というのは工場と違って、国際政治や経済に直結しているのですね。もっとも作文は経営企画室とか財務部が書くのでしょうけど。
工場にいたときはバブル崩壊をテレビニュースで見ても会社がどうなるのか、どう対応するのかなんて考えたこともなかったですよ」
![]() 「それはさておき、『ISO認証』という雑誌のことはご存じですよね。その取材対応なんだけど……」
「それはさておき、『ISO認証』という雑誌のことはご存じですよね。その取材対応なんだけど……」
![]() 「もう片付いたんでしょう、私はノータッチですよ」
「もう片付いたんでしょう、私はノータッチですよ」
![]() 「話は最後まで聞きなさい。
「話は最後まで聞きなさい。
環境部と話し合ったのですが、結論として佐川さんに取材を受けてもらうことにしたの」
![]() 「私は未来プロジェクト所属ですよ」
「私は未来プロジェクト所属ですよ」
![]() 「でも環境部兼務ですから環境部長の命令には従います」
「でも環境部兼務ですから環境部長の命令には従います」
![]() 「部長まで引っ張り出したの?」
「部長まで引っ張り出したの?」
![]() 「あまり佐川さんに手間をかけないことにしました。既に環境部の坂内
「あまり佐川さんに手間をかけないことにしました。既に環境部の坂内
当日、先方から問われたことに佐川さんが思うことを語ってくれれば良し。
広報部が陪席するので、発言に支障があれば最後に削除してほしいことを先方に伝えることとします」
![]() 「支障があることって? セクハラとかですか?」
「支障があることって? セクハラとかですか?」
![]() 「佐川さんがそういう人とは思ってないわ。会社の数字とかそういうこと」
「佐川さんがそういう人とは思ってないわ。会社の数字とかそういうこと」
![]() 「分かりました。時と所は?」
「分かりました。時と所は?」
![]() 「今考えているのは、来週、火曜日、午後1時半から3時半までの予定で延長は可、決まり次第、私の方から押田氏に連絡する」
「今考えているのは、来週、火曜日、午後1時半から3時半までの予定で延長は可、決まり次第、私の方から押田氏に連絡する」
![]() 「私の予定はどうだったかな?」
「私の予定はどうだったかな?」

![]() 「サイボウズは確認済で、ダブルブッキングはないわ」
「サイボウズは確認済で、ダブルブッキングはないわ」
![]() 「ヘイヘイ、問題を起こした人はどうなるの?」
「ヘイヘイ、問題を起こした人はどうなるの?」
![]() 「坂内は広報から異動したのよね。当時厄介払いと喜んだけど、出戻ってしまったわ。
「坂内は広報から異動したのよね。当時厄介払いと喜んだけど、出戻ってしまったわ。
環境部でも持て余していたようね。
前科が大分溜まったから、次があったらもう終わりヨ」
![]() 「私も彼女には随分言いがかりをつけられましたね(第46話)」
「私も彼女には随分言いがかりをつけられましたね(第46話)」
翌週の火曜日午後、「ISO認証」の押田記者がやって来た。
広報はロビー脇の一番贅沢な小部屋を予約していた。
佐川は初めて知ったが、ロビーの小部屋には3ランクあって高い部屋は豪華だ。佐川は本社に来て4年になるが、一番安い部屋しか使ったことがない。
こちらは佐川と広報部の石川、環境部の山口が出た。
石川が出席者の紹介をしたあとで、山口は終了後、業界団体の件を話したいと言って了解をもらった。
 | 広報部 石川 | |||
| 押田記者 |  |  | 佐川 | |
 | 環境部 山口 |
![]() 「ISO9001認証が始まって5年ほど経ちますが、当時から御社の認証の考えが他社と異なっているように思っていました。そういうスタンスはISO14001になっても同じようです。
「ISO9001認証が始まって5年ほど経ちますが、当時から御社の認証の考えが他社と異なっているように思っていました。そういうスタンスはISO14001になっても同じようです。
そういうことが実際あるのか、お話しいただけますか」
![]() 「杓子定規の話でも面白くないでしょうから、
「杓子定規の話でも面白くないでしょうから、
私は元々工場の現場管理者でした。たまたまISO9001が登場する半年ほど前に、品質保証部門に異動しました。
それで品質保証業務の見習いを始めたわけですが、品質保証課には品質保証の専門家がいませんでした。
驚くことはありません。品質保証とはBtoBにおいて1970年頃から広まりましたが、BtoCにおいては一般化していませんでした。今でもBtoCの会社に真の品質保証業務があるかどうか疑問です」
![]() 「ISO認証が始まる前とは、良い時期に品質保証に異動しましたね」
「ISO認証が始まる前とは、良い時期に品質保証に異動しましたね」
![]() 「うーん、良かったのか悪かったのか?
「うーん、良かったのか悪かったのか?
それで私は品質保証とは何かを調べました。当時は、今もかもしれませんがQuality assurancesについて書かれた本は少ないですね
一番参考になったのは、防衛やNTTの品質保証をしていたの方の話を聞いたことですね。
押田さんのおっしゃるように、ISO9001が品質保証の標準化を目指した規格であるから、当然ISO9001の認証は顧客の品質保証要求に対応することと同じであると演繹されます」
![]() 「ISO9001は新しいものではないということですか?」
「ISO9001は新しいものではないということですか?」
![]() 「新しくないどころか、古いものだということです。標準化・規格化とは、ある程度、世に広まって、規格や考えがバラバラで困る段階になったとき、基準を決めて皆がそれに合わせることです。
「新しくないどころか、古いものだということです。標準化・規格化とは、ある程度、世に広まって、規格や考えがバラバラで困る段階になったとき、基準を決めて皆がそれに合わせることです。
当然、それは最大公約数を標準にすることが多く、最先端ではなく、皆がなじんでいるものになります。そもそも標準化されるのは枯れた技術とか考えしかできません。日々新しいものが現れる技術分野では標準化などできません」
![]() 「なるほど」
「なるほど」
![]() 「私は指導者も先輩もいないところで、半年、客先からの品質保証要求に対応してきました。半年は短いですが、そういうことをしていると、いろいろ考えるものです。
「私は指導者も先輩もいないところで、半年、客先からの品質保証要求に対応してきました。半年は短いですが、そういうことをしていると、いろいろ考えるものです。
ISO9001は欧州のEU統合対応でした。当然ながら今までの品質保証要求事項と同じと認識しました。そうでないと考える理由がありません。
さて勤め先の工場も認証を受けないと商売あがったりです。審査を依頼しようと認証機関を訪ねましたが、当時はどの認証機関も多忙で依頼を受けてくれません。それで弊社のイギリス支社に頼んで、イギリスの認証機関に審査を依頼しました。
日本にもその認証機関の営業拠点がありましたが、そこも満杯で身動き取れず、本部に頼んだわけです」
![]() 「イギリスからでは費用が大分掛かったのでしょうね?」
「イギリスからでは費用が大分掛かったのでしょうね?」
![]() 「そうでもありませんでした。当時は日本の顧客開拓で出精値引きだったのかもしれません。それに我々だけを審査に日本に飛んで来たわけでなく、数社審査する予定を組んでいたようです」
「そうでもありませんでした。当時は日本の顧客開拓で出精値引きだったのかもしれません。それに我々だけを審査に日本に飛んで来たわけでなく、数社審査する予定を組んでいたようです」
![]() 「なるほど」
「なるほど」
![]() 「私は自分の工場の認証を終えると、本社から他の工場の認証の支援を依頼され、ここにいる山口と二人で日本全国の工場を歩きました。
「私は自分の工場の認証を終えると、本社から他の工場の認証の支援を依頼され、ここにいる山口と二人で日本全国の工場を歩きました。
そこで感じたのですが、私が依頼した認証機関、名前を出してしまえばB○○社です。ゼネラルマネジャーのハワード氏をご存じでしょう。最初に審査を受けたとき、彼は審査員でした。
普通の会社でISO担当している方はなかなか気づかないかもしれませんが、私は幸か不幸か、ものすごい数の認証を手伝いましたし、それにこれまたかなりの数の認証機関の審査に立ち会いました」
![]() 「普通、審査には部外者の立ち合いを断ると思いますが」
「普通、審査には部外者の立ち合いを断ると思いますが」
![]() 「おっしゃる通りです。山口と私は、本社あるいは親会社の立場でしっかりと認証準備をしたのか審査の立ち合いに来たという理由で、審査前に立ち会いを通知しました。
「おっしゃる通りです。山口と私は、本社あるいは親会社の立場でしっかりと認証準備をしたのか審査の立ち合いに来たという理由で、審査前に立ち会いを通知しました。
難色を示したところはありましたが、我々が工場や関連会社の認証機関の選択に力を持っていると言えば、断るところはなかったですね。いや脅しでなく本当ですし」
![]() 「はあ〜、すごいですね」
「はあ〜、すごいですね」
![]() 「最初に審査を受けたB○○社の審査の方法とか規格解釈と、他の工場で審査に来た認証機関……ほとんど日系の審査は大きく異なっていました」
「最初に審査を受けたB○○社の審査の方法とか規格解釈と、他の工場で審査に来た認証機関……ほとんど日系の審査は大きく異なっていました」
![]() 「どんな違いでしょう」
「どんな違いでしょう」
![]() 「まずB○○社の場合、ISO規格を満たしているかを点検します。それ以上でもなくそえ以下でもない、それだけです。
「まずB○○社の場合、ISO規格を満たしているかを点検します。それ以上でもなくそえ以下でもない、それだけです。
他方、日系の認証機関は会社を良くしようという意思があるようです。現状で規格を満たしていても更に完璧を求めると感じました。
しかし顧客から品質保証を求められたと考えると、それを満たせば良いわけで、今より一層良くしようということはありません。
普通の二者監査はB○○社の審査方法と同じです。一部の二者監査の場合、親会社が子会社を監査するとか、顧客が現在の品質を挙げようとする場合は問題の原因究明から対策案の検討まで入り込むこともあります。
正確に言えば、これは監査ではなく指導です」
![]() 「なるほど」
「なるほど」
![]() 「発言してよろしいですか?」
「発言してよろしいですか?」
![]() 「どうぞ、どうぞ」
「どうぞ、どうぞ」
![]() 「当時、日本人の審査員は守衛所でガードマンに品質方針を聞いたり、お茶を出した事務員に品質方針を暗唱させたりしたものです。宴席の準備を確認したりもありましたね。
「当時、日本人の審査員は守衛所でガードマンに品質方針を聞いたり、お茶を出した事務員に品質方針を暗唱させたりしたものです。宴席の準備を確認したりもありましたね。
B○○社はさすがそういうことはしませんでしたね」
![]() 「審査の問題ですね。実を言いまして私はそういうレベルの苦情をお聞きしようという気持ちでしたが、佐川さんのお話ははるかに上位概念でしたね」
「審査の問題ですね。実を言いまして私はそういうレベルの苦情をお聞きしようという気持ちでしたが、佐川さんのお話ははるかに上位概念でしたね」
![]() 「今の話だけで当社のISO9001認証の考えが、他社と異なるということの答えかなと思います。
「今の話だけで当社のISO9001認証の考えが、他社と異なるということの答えかなと思います。
我々はガードマンに方針を聞くようなレベルにお金を払いたくないのです」
![]() 「お宅の場合、規格を満たせばよいということですか? いやしっかり規格適合を確認しろということですね」
「お宅の場合、規格を満たせばよいということですか? いやしっかり規格適合を確認しろということですね」
![]() 「そうです。そもそもISO9001は、会社を良くすることを求めているのか、会社を良くすることができるのか、そう考えるといずれも違います」
「そうです。そもそもISO9001は、会社を良くすることを求めているのか、会社を良くすることができるのか、そう考えるといずれも違います」
![]() 「会社を良くしなくても良いということですか?」
「会社を良くしなくても良いということですか?」
![]() 「まず会社を良くすることとは何でしょうか?
「まず会社を良くすることとは何でしょうか?
ISOコンサルには、いや認証機関にも、マスコミも、ISOTC委員にさえ、ISOMS規格は会社を良くすると語る人が多い。いったい彼らは会社を良くするとは、どんなことか考えているのですかね?
もちろん押田さんはご存じでしょう。だって、先月号の特集は『ISO認証で会社を良くする』でしたから」
![]() 「いやあ、参りました。会社を良くするとはどんなことでしょう?」
「いやあ、参りました。会社を良くするとはどんなことでしょう?」
![]() 「彼らが何を考えているのかは分かりません。ともかく会社を良くするというなら、まず『良い会社』を定義しなければなりません。
「彼らが何を考えているのかは分かりません。ともかく会社を良くするというなら、まず『良い会社』を定義しなければなりません。
一般市民が考えると、規模が大きい、利益が大きい、株価が高い、ブランドイメージが良い、ホワイト企業、企業犯罪がない、入社希望者が多い、そんなことですか?
従業員としては、賃金が高い、勤務時間が短い、福利厚生が良い、ホワイト企業である、
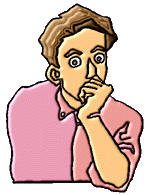 |
|||
株主から見れば、配当が良い、株価が上昇傾向である、株主特典が良い、不祥事がない、
近隣住民から見れば、雇用が拡大している、公害を出さない、自治体や町内会へのサービスがある、そういうことでしょう。
顧客から見れば、良い製品……良い製品と言っても様々ですね。仕様が良い、品質が良い、デザインが良い、頻繁なモデルチエンジをしない、供給が安心、値段が安い、
学生から見れば、採用している、雇用条件、賃金、福利厚生とか
ISO認証は会社を良くすると語る、ISOコンサル、認証機関、マスコミ、ISOTC委員は、何をもって会社を良くすると語っているのでしょう。ハッキリ言ってそういう人は何も考えていないと思います」
![]() 「佐川さんはISO認証をどう思っているのですか?」
「佐川さんはISO認証をどう思っているのですか?」
![]() 「そう話を転じる押田さんも強かですね。ここで、お宅の先月号の意味を、説明してもらおうと思っていました。
「そう話を転じる押田さんも強かですね。ここで、お宅の先月号の意味を、説明してもらおうと思っていました。
はぐらかすのが上手な人も、嫌いじゃありません。
まあ、ISO認証をどう思っているのか?という質問に答えましょう。
私は何度も言いました。ISO9001が登場したとき顧客からの品質保証がひとつ増えたと思っただけです。
つまり単純に品質保証です」
![]() 「それは誰に対してですか?」
「それは誰に対してですか?」
![]() 「それが微妙なんですよね。BtoBの顧客企業はISO9001を信じていません。そりゃISO9001に適合であることは信じるでしょうけど、それだけじゃ足りないのです。現実にISO9001を認証しても二者監査はなくなりません。
「それが微妙なんですよね。BtoBの顧客企業はISO9001を信じていません。そりゃISO9001に適合であることは信じるでしょうけど、それだけじゃ足りないのです。現実にISO9001を認証しても二者監査はなくなりません。
今も、顧客企業からは、ISO9001の一般論でなく、計測器の校正間隔や顧客指定の校正機関での校正などを要求されてます。そういうものはISO規格では規定していません。それはISO9001に追加すればいいというなら、初めからISOなんぞ利用せず、二者監査にした方が手っ取り早い。
それから変更管理などもありますね。大きなシステムとか設備ですと、常に改良とか個別対応の変更があります。ISO9001はそこまで進んでいません。
昨日今日でなく大昔から品質保証を求めていた防衛やNTTは、ISOなんて鼻にもひっかけてませんよ
他方、中小に発注しているレベルではISO9001いやISO9003でも複雑すぎますよ。
注:「鼻にもひっかけない」と書いて、似た表現を思い出した。そしてどれが強烈なのかと疑問に思った。
調べると
「眼中にない」>「歯牙にもかけない」>「鼻にもひっかけない」
の順序だそうだ。
ここは「ISO9001など眼中にない」と言ったほうが侮蔑のレベルは最強らしい。とはいえ今の人には、あまり使わない言い回しのほうが良いかなと・・・
![]() おっとISO9001は誰に対して品質保証をするのかという問いは、場合、場合によって変わるでしょうね。顧客がISO9001認証せよと……まてよ公正取引委員会の回答は21世紀か
おっとISO9001は誰に対して品質保証をするのかという問いは、場合、場合によって変わるでしょうね。顧客がISO9001認証せよと……まてよ公正取引委員会の回答は21世紀か
![]() 「21世紀がどうしたのです?」
「21世紀がどうしたのです?」
![]() 「買い手が売り手にISO認証を要求することは、売り手にとって負担が大きいことから、必要性を説明できなければISO認証を要求してはならないと、公正取引委員会が裁定するのです」
「買い手が売り手にISO認証を要求することは、売り手にとって負担が大きいことから、必要性を説明できなければISO認証を要求してはならないと、公正取引委員会が裁定するのです」
![]() 「なるほど、そう言われるとそういう方向にはありますね。
「なるほど、そう言われるとそういう方向にはありますね。
しかし商取引においてISO認証を要求することを禁止できるでしょうか?」
![]() 「できますよ。それこそが不当競争防止法の目的です。
「できますよ。それこそが不当競争防止法の目的です。
でも法で無制限に禁止はできません。買い手がISO認証の必要性を説明できれば、調達先にISO認証を要求しても良いのです。
あるいはISO認証を要求するのではなく、従来通りの二者間での品質保証を要求するならそれでよく、調達先に大金をかけさせて認証を要求することはないでしょう。
折衷的ですが、品質保証体制の整備は売り手の義務、認証費用は買い手の義務でも良いかもしれません。結果は二者間の品質保証協定と、ほとんど同じことですがね。
考えてみれば規格要求事項の4.1は不要、4.2は決まりきっているとか、客先指定なら不要、4.3は受注連動型調達なら不用、4.4はパス、4.5は厳しいことは言わないでしょう、4.6は指定されることが多いし、4.7は言わずもがな、4.8も4.9も指定されてますよ。わざわざISO9001認証を要求する意味はなさそうです。
どう考えてもISO認証など無用でしょう」
![]() 「いやあ……何と言いますか、佐川さんは枯れているというか、いやそうじゃない、すべてを見極めて開き直っているというか」
「いやあ……何と言いますか、佐川さんは枯れているというか、いやそうじゃない、すべてを見極めて開き直っているというか」
![]() 「どうとでもご自由に。
「どうとでもご自由に。
そういう発想をしていると、会社を良くするなんて笑いたくなります。
お断りしておきますが、私というか弊社が、受入検査でOKになれば良いとか、表面を繕えば良いと考えているわけではありません。
広義の品質管理の三本柱というのをご存じでしょうか?」
![]() 「広義の品質管理の三本柱ですか? TQCでしょうか?」
「広義の品質管理の三本柱ですか? TQCでしょうか?」
![]() ISO9001が登場して品質関係のJISも大幅に書き換えられてしまいました。
ISO9001が登場して品質関係のJISも大幅に書き換えられてしまいました。
1990年頃、広義の品質管理(Quality management)とは狭義の品質管理(Quality control)、品質保証(Quality assurances)、品質改善(Quality improvement)で構成されると言われました。これが品質管理の三本柱です。
私が言ったのではありません、JISに書いてあったのです。
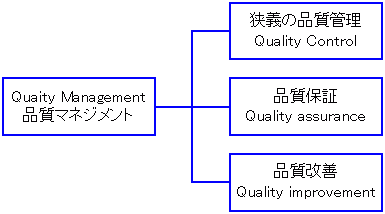
いつしかQuality managementの訳は『広義の品質管理』から『品質経営』になったようです。
話を戻しましょう。
先ほど押田さんは『会社を良くしなくても良いと考えているのか?』と聞いた。
弊社ではしっかりと品質改善をしていますよ。しかしそれは品質保証の範疇外で、品質改善というカテゴリーで行っています。そしてまた会社を良くするということでもなさそうです」
![]() 「品質改善とはどういうものですか?」
「品質改善とはどういうものですか?」
![]() 「それは一つの概念であり、手法は多々あり、会社によっていろいろ組み合わせて行います。
「それは一つの概念であり、手法は多々あり、会社によっていろいろ組み合わせて行います。
石川さん、私が余計なことを言った場合は止めてくださいね」
![]() 「押田さん、佐川さんは正直で物知りですから、機密に関することをいうかもしれません。そのときはストップをかけますし、最終時にここは削除してほしいとお願いしますのでよろしく」
「押田さん、佐川さんは正直で物知りですから、機密に関することをいうかもしれません。そのときはストップをかけますし、最終時にここは削除してほしいとお願いしますのでよろしく」
![]() 「承りました」
「承りました」
![]() 「そいじゃ言いたい放題で行きましょう」
「そいじゃ言いたい放題で行きましょう」
![]() 「今までは抑えていたのですか?」
「今までは抑えていたのですか?」
![]() 「行儀よく話しているつもりですよ。
「行儀よく話しているつもりですよ。
ええと弊社においても品質改善は多々行っています。
弊社には技師長とか技能長という職務というか称号みたいなものがあります。技術者を長らくやって来た方、現場作業で監督職を長くしていたとか卓越技能者とかがそれら任命されます。
そして複数人で工場や関連会社を巡回して、製造や開発のプロセスの指導とか、品質改善の指導を行っています。
テクノロジートランスファーというのもありますね。一工場の改善とか新工法を全社に広めるとか、転用の検討です。
小集団活動も品質改善の一手法ですし、改善提案もあります
ここで、品質改善には良くも悪くも主観が入るということです」
![]() 「主観が入るとは?」
「主観が入るとは?」
![]() 「指導者・参加者の価値観ですか、あるいは技術的に解明されていないこともあります」
「指導者・参加者の価値観ですか、あるいは技術的に解明されていないこともあります」
![]() 「ISOには確かに確立した製品を間違いなく作るという考えですね。そういう品質改善の要求を含めれば一層良い規格になるということでしょうか?」
「ISOには確かに確立した製品を間違いなく作るという考えですね。そういう品質改善の要求を含めれば一層良い規格になるということでしょうか?」
![]() 「それはムリでしょう。品質改善には主観が入ると言ったでしょう。それは失敗したら指導者が責任を負うという前提だから許されます。
「それはムリでしょう。品質改善には主観が入ると言ったでしょう。それは失敗したら指導者が責任を負うという前提だから許されます。
押田さんは耳が早いからご存じと思いますが、ISO審査で工場巡回中に審査員が不良対策のアドバイスをして、損害賠償の裁判になったのをご存じでしょう」
![]() 「いえ、初耳です」
「いえ、初耳です」
![]() 「ISO審査中にそんなことをするのは、審査員がルール違反なのはもちろんです。
「ISO審査中にそんなことをするのは、審査員がルール違反なのはもちろんです。
品質改善とはそういうリスクがある。品質改善の指導をするとはそのリスクを負うことです」
![]() 「なるほど、リスクを負えないなら指導できないということですか?」
「なるほど、リスクを負えないなら指導できないということですか?」
![]() 「指導できなくもないですよ。依頼先と、指導して問題が起きても責任を負わないと契約しておくことですね。コンサルはそうですよね」
「指導できなくもないですよ。依頼先と、指導して問題が起きても責任を負わないと契約しておくことですね。コンサルはそうですよね」
![]() 「佐川さんには圧倒されますね」
「佐川さんには圧倒されますね」
![]() 「アハハハ、次はどんなことをお聞きしたいですか?」
「アハハハ、次はどんなことをお聞きしたいですか?」
![]() 「ISO14001も同じアプローチですか?」
「ISO14001も同じアプローチですか?」
![]() 「もちろんです。ISO14001も基本は品質保証だと理解しています」
「もちろんです。ISO14001も基本は品質保証だと理解しています」
![]() 「佐川さん、質問です。ISO14001のどこが品質保証なのですか?」
「佐川さん、質問です。ISO14001のどこが品質保証なのですか?」
![]() 「品質保証とは製品の品質を保証するのではなく、製品が管理された状態で作られたことを保証するものです。
「品質保証とは製品の品質を保証するのではなく、製品が管理された状態で作られたことを保証するものです。
そして品質とは、製品品質だけではありません。サービスの品質保証もあり、そして顧客とは買い手のことではなく、後工程のことなのです。
そう考えるとISO14001は環境管理業務の品質保証だと理解できるでしょう」
![]() 「あっ、そうか!」
「あっ、そうか!」
![]() 「今、情報セキュリティとか言われていますが、それも品質保証なのですか?」
「今、情報セキュリティとか言われていますが、それも品質保証なのですか?」
![]() 「そうです。成すべきことを文書で規定し、実行したことを記録で証明することは、品質保証の基本です。
「そうです。成すべきことを文書で規定し、実行したことを記録で証明することは、品質保証の基本です。
言い換えると、管理技術で保証するとは、それ以上のことはできません。それを理解できない人間が多いのは、悲しいことです。
話を進めましょうか、ISO規格で不良を出さないことも公害を出さないことも、情報漏洩も防ぐことはできません。ISO認証ができるのはシステムが規格に適合していることの証明だけです。お忘れなく、ISO規格適合なら完璧な会社であることも立証されていません。
そしてまたISO規格はシステムの設計も作り方も示していません。ISO規格を満たす仕組みを作るのは、会社の自由であり責任なのです」
![]() 「ISOMS規格がシステムの設計ではないですって?」
「ISOMS規格がシステムの設計ではないですって?」
![]() 「そのとおり。ご存じのようにISOMS規格はシステムの規格ではありません」
「そのとおり。ご存じのようにISOMS規格はシステムの規格ではありません」
![]() 「お二人とも規格を読んでないのですか?
「お二人とも規格を読んでないのですか?
タイトルにはしっかりと『環境マネジメントシステム−仕様及び利用の手引き』と書いてあります。システムの設計ではなく仕様なのです。その仕様をどう実現するかは利用者が決めるのです。
営業は客先で客の望むものを把握してきます。それが顧客要求仕様です。
小さく軽く、消費電力はわずかで、できることはたくさんという曖昧模糊で不可能な要求仕様だって紙に書くことはできます。
ISOMS規格はまさにそれです」
![]() 「はあ〜」
「はあ〜」
![]() 「気を付けてほしいことがあります。
「気を付けてほしいことがあります。
ISO規格にはいろいろあります。紙のサイズからねじの寸法、そして品質保証や環境マネジメントシステムと……
ねじとマネジメントシステムの規格は何が違いますか?」
![]() 「対象が物と仕組みの違いです
「対象が物と仕組みの違いです
![]() 「それだけではありません。ねじの場合、それを見て作れば同じものができます。しかし品質保証とか環境マネジメントシステムでは、規格は仕様書ですから出来上がった物は作る人によって違うことになる」
「それだけではありません。ねじの場合、それを見て作れば同じものができます。しかし品質保証とか環境マネジメントシステムでは、規格は仕様書ですから出来上がった物は作る人によって違うことになる」
![]() 「ちょっと待ってください、違ったものが双方とも規格適合になりますか?」
「ちょっと待ってください、違ったものが双方とも規格適合になりますか?」
![]() 「ISO14001の序文にあるでしょう。このマネジメントシステムを満たしていても同じパフォーマンスを示すとはかぎらないって。
「ISO14001の序文にあるでしょう。このマネジメントシステムを満たしていても同じパフォーマンスを示すとはかぎらないって。
仕様書といっても仕組みの仕様書だから性能が同じことを保証しない。仕様書を満たすように作るのは組織の責任です」
![]() 「言われてみると……」
「言われてみると……」
![]() 「そうしますとISOMS規格の、ありがたみがありませんね」
「そうしますとISOMS規格の、ありがたみがありませんね」
![]() 「そもそもありがたみがあると思うのが、間違い。顧客から要求された品質保証協定をありがたがる人がいるか? ISO9001もそれと同じです。
「そもそもありがたみがあると思うのが、間違い。顧客から要求された品質保証協定をありがたがる人がいるか? ISO9001もそれと同じです。
環境で言えば、日本において省エネ法、公害防止組織法、消防法などで、公害防止から省エネまで完璧に網羅されている。さて、環境管理に何が不足しているだろう?
不足はないのではないかな?」
![]() 「じゃあISO規格の出番はないのか?」
「じゃあISO規格の出番はないのか?」
![]() 「正直言って低開発国で環境規制が整っていない国くらいじゃないですか?」
「正直言って低開発国で環境規制が整っていない国くらいじゃないですか?」
![]() 「でもISO14001は法以上の取り組みを求めていますよ」
「でもISO14001は法以上の取り組みを求めていますよ」
![]() 「希求するのは結構ですが、現実は求めているのでしょうか?」
「希求するのは結構ですが、現実は求めているのでしょうか?」
![]() 「発言します。ISO14001が対象とする環境側面は、法規制を受けるもの、大きな環境負荷のあるもの、組織が決めたものとなっています。
「発言します。ISO14001が対象とする環境側面は、法規制を受けるもの、大きな環境負荷のあるもの、組織が決めたものとなっています。
大きな環境負荷のあるものは99%法規制を受けますね。
となると文章でどう書いてあろうと、日本の場合、法規制をしっかり把握して管理すれば、ISO14001と同等であると言えるでしょう」
![]() 「そうなのですか? となるとISO14001認証の意味は何ですか?」
「そうなのですか? となるとISO14001認証の意味は何ですか?」
![]() 「今現在はISO14001認証がブランドとなり、認証の有無でコンペティターに対して優位となれる見込みがあるからでしょう」
「今現在はISO14001認証がブランドとなり、認証の有無でコンペティターに対して優位となれる見込みがあるからでしょう」
![]() 「ええー、それだけですか?」
「ええー、それだけですか?」
![]() 「押田さんが質問したことです。それは記者の務めとして聞いたのではなく、分からないから質問したのだと思いますね。違いますか?
「押田さんが質問したことです。それは記者の務めとして聞いたのではなく、分からないから質問したのだと思いますね。違いますか?
私は社内で予言者と呼ばれています。ISO14001認証はどんどんと増えていきますが、問題も多く出ています。
来年でしょうけど、ISO14001認証をした工場で、有機塩素系化合物による地下水汚染が見つかります。
さあ、その工場のISO認証はどうなりますか?」
![]() 「仮定の話ですよね。
「仮定の話ですよね。
ISO規格では法違反でも認証取り消しはありませんね。ISO規格に基づいて是正を進めるということになるのでしょうね」
![]() 「現時点、法違反があった、あるいは法違反を是正中であるなら、認証は受けられません」
「現時点、法違反があった、あるいは法違反を是正中であるなら、認証は受けられません」
![]() 「そうなんですか?」
「そうなんですか?」
![]() 「そうです。ISO14001はブランドなのです。認証の際、そういう
「そうです。ISO14001はブランドなのです。認証の際、そういう
篩をかけた上で認証した企業が、事故を起こしたとか、法違反が発覚すれば、認証のブランド価値が下がります。認証側として、そういうことを看過できません。
バッグでも魚でもタオルでも、ブランドを守るために、模造品の摘発に必死です。ISO認証企業から不祥事が起きては困るでしょう」
![]() 「ならば法違反が見つかれば認証取り消しですか?」
「ならば法違反が見つかれば認証取り消しですか?」
![]() 「そんなことしませんよ、認証辞退を求めるのです。陰湿ですね」
「そんなことしませんよ、認証辞退を求めるのです。陰湿ですね」
![]() 「架空の話ですよね?」
「架空の話ですよね?」
![]() 「ISO14001は実力の証明なのかなのか、名誉なのかというとどちらでしょう?
「ISO14001は実力の証明なのかなのか、名誉なのかというとどちらでしょう?
本来の意味から言えばISO14001は組織の環境管理の仕組みが、ISOの考える基準を満たしていることでしかありません。素晴らしくもなく名誉でもない。
しかしISO認証がプライズであるから、事故や違反を起こすと、認証取り消しか停止になるということです」
![]() 「規格適合していても、環境事故や違反が起きますか?」
「規格適合していても、環境事故や違反が起きますか?」
![]() 「起きますよ。当たり前でしょう。
「起きますよ。当たり前でしょう。
逆の質問を返すなら、完璧にISO規格適合なら事故も違反も起きないと思います?」
![]() 「どうなのでしょうか?」
「どうなのでしょうか?」
![]() 「事故というと極端ですが、定められた手順を守らない、計画を達成しないことが多々発生するから、是正処置の項番があり、事故が起きるから緊急時代の項番があるとは考えられませんか」
「事故というと極端ですが、定められた手順を守らない、計画を達成しないことが多々発生するから、是正処置の項番があり、事故が起きるから緊急時代の項番があるとは考えられませんか」
![]() 「そう言われるとそう思いますね」
「そう言われるとそう思いますね」
![]() 「IBM社の環境報告書をお読みになったことありますか?」
「IBM社の環境報告書をお読みになったことありますか?」
![]() 「すみません、読んだことありません」
「すみません、読んだことありません」
![]() 「1993年からだと思いますが、環境報告書の中に、社内犯罪、横領とかですねそういう詳細が書いてあります。その他、罰金をいくら払ったか、どんな事故が起きたかも書いてあります」
「1993年からだと思いますが、環境報告書の中に、社内犯罪、横領とかですねそういう詳細が書いてあります。その他、罰金をいくら払ったか、どんな事故が起きたかも書いてあります」
![]() 「それはどのように評価されているのでしょう?」
「それはどのように評価されているのでしょう?」
![]() 「アメリカでは清廉潔白だと高く評価されています。日本でもその情報公開を素晴らしいと語る人はいますが、自分の会社の実態を公表する度胸はないでしょう。
「アメリカでは清廉潔白だと高く評価されています。日本でもその情報公開を素晴らしいと語る人はいますが、自分の会社の実態を公表する度胸はないでしょう。
 ちょっと違いますが、アメリカの航空機事故で人為的なミスの場合、失敗の情報を集めて再発防止をします。
ちょっと違いますが、アメリカの航空機事故で人為的なミスの場合、失敗の情報を集めて再発防止をします。
それは当たり前ですが、ミスをした人を罰することをしません。そのほうが正確な情報収集ができ、再発防止に役立ち、総合的に社会に貢献すると考えているからです。
国の文化の違いもあるでしょうけど、隠さない、ごまかさないですね」
![]() 「土壌汚染も同じと?」
「土壌汚染も同じと?」
![]() 「そう思いますね。
「そう思いますね。
事故が起きたら、規格に基づいて是正処置、つまり再発を防げと言えば良いと思いませんか?」
![]() 「それが先ほどの問題につながるわけですね?」
「それが先ほどの問題につながるわけですね?」
![]() 「そうです。
「そうです。
今現在、有機塩素系の地下水汚染や金属などの土壌汚染を引き起こすと、即法違反になるわけではありません。もちろん地下水汚染などを引き起こして無罪放免はありませんが、明確に定めた法律があるわけではなく、水濁法とか廃棄物処理法などを持ち出して対応している状態です(注6)。
ましてや過去に地下水汚染や金属などの土壌汚染をしていたことが発覚しても犯罪ではありません。もちろん何もしなくて良いわけではありません。原因者が改善に努めれば良いだけの話です。
しかし先ほどの事例では、ISO認証した企業が、何十年か前に当時は法規制がなかった地下水汚染や土壌汚染をしていたことが発覚したら、即ISO14001認証を返上することを求められるというのはどうですかね?」
![]() 「というと先ほどの有機塩素系による汚染で認証を辞退することは、法以上の制裁ということですか?」
「というと先ほどの有機塩素系による汚染で認証を辞退することは、法以上の制裁ということですか?」
![]() 「制裁というよりも認証を与える側としては、認証のブランド価値を落としたくない思いしかないのでしょう。
「制裁というよりも認証を与える側としては、認証のブランド価値を落としたくない思いしかないのでしょう。
まあ、ISO認証に対する私の疑問の一つです」
![]() 「あのう、今時刻は3時40分です。一応場所は終業時まで確保しておりますが、まずは一旦休憩しませんか。
「あのう、今時刻は3時40分です。一応場所は終業時まで確保しておりますが、まずは一旦休憩しませんか。
私の感想を述べますと、押田さんが希望したISO認証についての弊社の考えやスタンスということからだいぶ離れているか、あるいはまだその前段なのか、本題に至っていないように思えます。
このような話し合いというか、主義信条の主張でよろしいのでしょうか?」
![]() 「確かに石川さんがおっしゃる通り、私の想定していた応答とは全く離れているように見えるかもしれません。
「確かに石川さんがおっしゃる通り、私の想定していた応答とは全く離れているように見えるかもしれません。
しかし私の最初の質問である『他社が認証を受けようとするスタンスと、吉宗グループが認証を受けるスタンスはなぜ違うのか?』ということへの回答そのものであります。
そして今まで多数の認証機関とか認証を受ける企業に取材しましたが、このような認証そのものの意義を語るお話を聞けたのは初めてです。私はその内容に圧倒されました。
とりあえず休憩して、今後のことをお話したいと願います。できれば月一で2・3時間お話を聞くということはできないでしょうか?」
![]() 「あのう……業界団体の押田さんの取材の件ですが・・・」
「あのう……業界団体の押田さんの取材の件ですが・・・」
その日は5時前にお開きとなった。これからのことは広報部で検討するという。早い話が佐川との対談が、当社にメリットがあるのかどうか判断するのだろう。
![]() 本日コンテンツの意味
本日コンテンツの意味
前段のおバカな話は、いったいなんだ? と思われた方も多いでしょう。まず、その弁明を・・・
会社の仕事をしているとトラブルというか様々な困難に出会います。その原因にはいろいろあります。
- ひとつは仕事が開発的であり未知なことが多い。
- ふたつはリソースが足りず実行困難である。
- みっつは個人によるサボタージュやミスによるもの。
現実には三つ目によるものが多い。その呪いから逃れられない情景を盛り込んだということです。
何故かと言えば、仕事がスイスイと進んだら現実の会社と乖離しちゃうじゃないですか。予定した品物が納入されない、電車が遅れる、頼りにしていた人が病欠、そういう日々が現実ですって、
じゃあ、後段のお話は何かとなるとですね……私はいろいろ言いたいわけですよ。
私の主張を佐川に託して語らせても面白くもなんともない。議論する相手が必要です。突っ込み厳しい人物が良いですね。そういう人間を持ってきて議論させたいということです。
勿論今回で終わりません。何度か語り合ってもらいます。
記者の名前がどこかで聞いた苗字に似ているかもしれません。気にしてはいけません、私の田舎では履いて捨てるほどいる苗字です。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
アジア通貨危機(のちにアジア金融危機と呼ばれた)は、以前から弱含みだったタイのバーツ暴落をきっかけに東南アジアの国々に広がった。 日本もそれなりに影響を受けたが、当時の日本経済はバブル崩壊後の真っ只中で、間接的なダメージが深刻だった。山一證券・北海道拓殖銀行など大手が1997年に倒産。信用収縮が起き、貸し渋りが深刻化。内需低迷と相まって物価は下落基調となる。 GDP実質成長率は1998年度マイナス1.9%となった。これはバブル崩壊からリーマンショックの間の唯一のマイナス成長である。ITバブルまで回復に3年を要した。 参考:「現代アジア経済論」遠藤 環他、有斐閣ブックス、2018 | |
| 注2 |
純粋にQuality assurancesについて書いた本は数えるほどもない。タイトルや副題に「品質保証」とあるものでも、多くは狭義の品質管理とか信頼性評価についてであり、あるいはISO9001についての本であることがほとんどだ。 特に1992年以前(ISO認証以前)に、品質保証を書いたものはまずない。 | |
| 注3 |
NTTはISO9001登場後もNQAS(NTT品質保証協定)を取り交わしていたが、後にISO9001に切り替えた。私は外部の人間だがNQASがISO9001に劣っていたわけではない。結局長いものに巻かれたのだろう。 | |
| 注4 |
公正取引委員会がISO認証について強制は違反だと言ったのは2003/10/24である。 製造業者が部品等の納入業者に対し,品質マネジメントシステム(ISO9001)構築の認証取得を要請すること等について | |
| 注5 |
小集団活動/サークル活動と提案制度は混同されているが、全くの別物である。 | |
| 注6 |
「土壌汚染対策法」は2002年に制定された。 それ以前でも、地下水や土壌の汚染が「合法だった」わけではないが、根拠として水質汚濁防止法や廃棄物処理法などで対応していた。 そういうものが発覚しても罪刑(犯罪とする根拠)としては不明確だったのである。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |