注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
89話から続く
押田・佐川対談?が終わってから、石川さんが17時から地下の居酒屋で一席設ける話をして押田氏の了解を取る。
石川は広報の広瀬課長と環境の藤田課長に声をかけたが、藤田課長は出られないとのことで、対談のメンバーと広瀬課長となった。
それから山口と押田の打ち合わせである。
山口は押田氏が希望した業界団体への取材について、内部で不一致があることを説明して、山口が考えた提案をした。
ひとつは業界団体への要請としては、内部でもめないものとして、研究会が著して既に出版された『ISO14001規格解説本』作成のいきさつをまとめて記事にすること。
研究会のメンバーとの本音の話し合いの場として、業界団体に対してでなく、個人あるいは同好のグループ(仮)に対して、審査の問題を聞く場を設けることである。
アイソス誌はときたま、「○○フォーラム」の集まりなどを記事にしているから、それと似たようなものでも良いし、居酒屋で酒飲んで語り合うだけでも良い。記事にしなくてもガス抜きになればと山口は思ったのである。
山口の提案に対して、押田はふたつともその場でOKした。
ひとつは、業界団体には前回の申し込みを変更して「ISO虎の巻作成の伝」というタイトルで10ページくらい書いてもらうことにするという。
それなら吉本さんも田中さんも納得するだろう。
ふたつめの研究会メンバーとの会合は、ぜひやろうという。業界団体名を出さないことはもちろんだが、各メンバーの位置づけと個人名を出して会社を匿名とするか、個人も匿名にするか、あるいは記事にせず単なる情報交換会にするのか、そのへんはメンバーと話し合って決めたいという。あるいはやってみてから考えても良いという。
そんなことを話しているとすぐに終業のチャイムが鳴り、地下の居酒屋に行く。
翌日、山口は吉本と研究会のメンバーにメールを打つ。
TO:環境ISO研究会 各位 吉本機械の山口です。 昨日、雑誌「ISO認証」の押田記者が弊社の佐川課長に取材に来ました。これは業界団体への取材とは全くの別件で、弊社が独特の認証指導をしていることを知って、弊社の指導方法の取材にきたものです。 押田記者と弊社の佐川課長とのやりとりでした。私も陪席しましたが発言はしませんでした。 対談の内容は、即物的な手法や対応を語るのではなく、認証に対する考え方、認証に求めるものなど包括的な見方考え方についての、ある意味禅問答のようなものでした。 対談記事は来月号に載るらしいです。 対談終了後、私が業界団体への取材について話したところ、押田氏から次の提案がありました。 業界団体への依頼を見直し、次の2件を提案する。
以上で進めれば、吉本さんも田中さん初めとするメンバーの意向も満たせたかなと思います。 |
その日のうちに、吉本さんを含めた全メンバーから回答が返ってきた。
吉本さんとして全く異議はない。工業会としては成果が雑誌の記事になることとは確保でき、メンバーの様々な意見はあずかり知らぬこととなった。
田中をはじめとするメンバーも不満はない。
もちろん『ISO14001規格解説本の物語』をうまく書かねばならないが、そこは田中さんに調整してほしいと丸投げだ。
押田記者との飲み会は、中村さんと高橋さんが幹事となり、押田さんとの調整を含めて進めることになった。
意外だったのは、吉本さんも参加するという。それにはメンバーから大反対の声が出たが、業界団体として行うわけではないから一個人として参加する分には良しとなった。要は吉本さんに仕切らせないということだ。
それからおよそ半月ばかり後の宵、企業でISO14001認証を
JR秋葉原駅から歩いて2分ほどにある、チェーン店でない居酒屋を貸し切りだ。皆の勤務地からのアクセスを考えると神田の方が良いのだが、神田は認証機関が多数あり、そこから離れたほうが良いという意見からだ。
考えてみればJR神田駅の一日の利用者数は8万数千人、東京メトロが5万数千人と、ものすごい人がいるわけで気にすることもなさそうだ。
 |
||
| 増子記者 | ||
押田記者は増子という若手を一人連れてきた。
都合、出席者は合わせて12名である。
まだスマホ登場の10年前である。カメラ付き携帯電話も登場していない
それで増子は一眼レフカメラとステレオのデジタルレコーダーを持ってきた。
主催者として田中、共催者として押田が挨拶し、乾杯して飲み始まるのだが、普通の飲み会と違うのは、宴席の一方に鴨居から白い布を垂らして、そこにプロジェクターでパソコン画面を写し、一人一人、言いたいことを語るという流れだ。
それぞれパワーポイントの力作持参だ。
もちろん当人の発言より茶々が多い。

モバイルのプロジェクターが登場したのは2000年代後半で、この時代はまだ天井に吊り下げるような大きなものしかない。それにこの時代はVGAからやっとSVGAに変わりつつあったときだ。
プロジェクターなど重いものを、一体だれが持ってきたのだろう?
・
・
・
・
佐川はヒラメンバーだから、目立たない中ほどに座っている。誰から演目が始まるのだろう。
と思っている間もなく、田中氏が差し棒を持って白い布の前に出る。

![]() 「今晩はISO雑誌の方に審査の愚痴を語る会と聞きましたので、審査の不満で腹が膨れている私がトップバッターを務めさせていただきます。
「今晩はISO雑誌の方に審査の愚痴を語る会と聞きましたので、審査の不満で腹が膨れている私がトップバッターを務めさせていただきます。
まず一般論ですが、規格要求にないことを要求する認証機関や審査員がいて困ります。
環境方針に規格のフレーズがないという不適合が多々あります。実は初めてそれを聞いたときは冗談かと思いました。冗談ではありませんでした。
『継続的改善及び汚染の予防の約束』という言葉が環境方針にない、『見直す枠組み』という言葉が方針にない、『全従業員に周知する』と書いてない。
これだけでげっそりしてしまいますが、似たようなものはたくさんあります」
注:これは実話である。そう語った審査員は複数いた。一部は御芳名も覚えている。
![]() 「質問です。規格要求はそういう文言を書き込むことではなく、そういう趣旨が盛り込まれていれば良いのではないですか?」
「質問です。規格要求はそういう文言を書き込むことではなく、そういう趣旨が盛り込まれていれば良いのではないですか?」
![]() 「私もそう考えます。しかし、そう考えない審査員が多数いるので困っています。
「私もそう考えます。しかし、そう考えない審査員が多数いるので困っています。
次は、環境目的の環境マネジメントプログラムと環境目標の環境マネジメントプログラムが必要で、両方を兼ねるものは不適合と言われました」
![]() 「そうなのよ、規格でプログラムの単語の末尾に(s)とあり、複数でも良し・単数でも良しとあるのが見えないのかしら。老眼の審査員は辞めてほしいわ」
「そうなのよ、規格でプログラムの単語の末尾に(s)とあり、複数でも良し・単数でも良しとあるのが見えないのかしら。老眼の審査員は辞めてほしいわ」
注:これは有名な話である。この不適合は審査開始直後から問題視されていたが、2005年頃、マネジメントプログラム2種必要論者であるJ△〇〇社のT氏が、CEAR誌に持論を書いて大騒ぎになり、各方面から批判された。
![]()
その後は規格要求を満たすならひとつでも良くなったのかと言えば、それ以降もマネジメントプログラムが2種ないと、審査でケチ(不適合)を付けられることは続いた。どうしてだろうね?
審査員の頭はROMと同じく、新しい情報を書き込むことはできないのか?
![]()
異議申し立てしたのかって?
私が付き合っていた会社ではなかったので、余計なことはしませんでした。自分が問題だと認識すれば立ち上がれば良し、気が付かない、あるいは諦めたならそれは自己責任。
![]() 「それと環境目的は3年後以上の長期であることという主張があります。
「それと環境目的は3年後以上の長期であることという主張があります。
省エネ計画はローリングしていきますから良いのですが、設備導入なんて、予算の関係で年度内に完了が必須です。となると省エネ機器の導入は環境目的にならない、これはもう笑うしかありません」
![]() 「法改正もそうなんだよ。法改正が1年後に施行というものは、施行までに対策を完了しなければならない。だけどそれは環境目的にならない。
「法改正もそうなんだよ。法改正が1年後に施行というものは、施行までに対策を完了しなければならない。だけどそれは環境目的にならない。
となると現実を離れて適当なものを環境目的にでっち上げてやり過ごすしかない。
これはISO規格を貶めるものだ」
 |
|
| 中村は暴れ馬だ! |
![]() 「ウチの会社でも同じことを言われたよ。
「ウチの会社でも同じことを言われたよ。
理屈も何もあったものじゃない。それに環境保護と全く関係ないじゃないか。まったく許しがたい。
そんな連中は審査員資格を取り上げろ!」
![]() 「ドウドウ、中村さん、落ち着いて、まだ酔うには早いですよ」
「ドウドウ、中村さん、落ち着いて、まだ酔うには早いですよ」
・
・
・
・
![]() 「高橋です。私も腹ふくるる思いです。審査員の規格の理解が大いに怪しいです。
「高橋です。私も腹ふくるる思いです。審査員の規格の理解が大いに怪しいです。
例えば『自覚』の意味が審査員によっていろいろです。
ある審査員は『自覚とは訓練が必要ない、覚えさえすれば良いこと』と言う。
ある審査員は『自覚とは仕事の意図を理解すること』と言う。
別の審査員は『自覚とはゴミの分別や照明の省エネなど、みんなが知るべきこと』と言う。
途方にくれますよ」
![]() 「高橋さんは分かっているんだろう? 途方に暮れることないじゃないか」
「高橋さんは分かっているんだろう? 途方に暮れることないじゃないか」
![]() 「あのね。知っているのは当たり前でしょう。だって規格に書いてあるもの。
「あのね。知っているのは当たり前でしょう。だって規格に書いてあるもの。
どう考えるべきか途方に暮れるのではなく、審査員の説得に途方に暮れるわけよ。
![]()
|
ISO14001:1996 4.4.2訓練、自覚及び能力 組織は、関連する各部門及び階層においてその従業員又は構成員に、次の事項を自覚させる手順を確立し、維持しなけれ ばならない。
|
規格にはっきりと書いてあるのに、なんで審査員様がそれを理解してないのかが分かりませ〜ん」
注:これも実話である。こんなことさえ理解していない審査員には、お金を払いたくない。
![]() 「そういうことが起きた場合、企業はどういう対処をするのでしょうか?」
「そういうことが起きた場合、企業はどういう対処をするのでしょうか?」
![]() 「まず規格を見せて説明します。ですが、9割の方は理解しません。
「まず規格を見せて説明します。ですが、9割の方は理解しません。
それにまつわって不適合を出されると、いくら説明しても審査員は理解しませんから手がありません。
どうせたいして大問題じゃないから、手順書の文章を少し直す程度で、是正処置したことにします」
![]() 「反論を聞きたくないから、分からない振りをしているとしか思えない」
「反論を聞きたくないから、分からない振りをしているとしか思えない」
![]() 「泣き寝入りせずに、認証機関に異議申し立てだよ」
「泣き寝入りせずに、認証機関に異議申し立てだよ」
![]() 「須藤さんのおっしゃる気持ちは分かりますが、面倒くさいですよ。
「須藤さんのおっしゃる気持ちは分かりますが、面倒くさいですよ。

 |
 |
||
でも不適合を出された、ご本人が出てこないんですよね。審査で不適合を出されて文句があるなら自分で苦情を言えばいいのに、他人に頼るとは、弱腰、逃げ腰、及び腰、へっぴり腰も良いところです。
一般の人は認証機関とか審査員を専門家、プロフェッショナル、もっと言えば偉い人と思っていて恐れ多いと考えているのでしょうね」
![]() 「おっしゃる通りよ、私も異議申し立て行くならお供するというと、いや、それじゃ良いですってなるのよ、フザケルナって!」
「おっしゃる通りよ、私も異議申し立て行くならお供するというと、いや、それじゃ良いですってなるのよ、フザケルナって!」
![]() 「やはり会社の人たちは、審査員を上に見ているのでしょうね」
「やはり会社の人たちは、審査員を上に見ているのでしょうね」
・
・
・
・
![]() 「外部コミュニケーションを理解していない審査員が多いですね。
「外部コミュニケーションを理解していない審査員が多いですね。
押田さん、外部コミュニケーションって何かご存じですか?」
![]() 「主に近隣住民とか行政とのやり取りでしょう」
「主に近隣住民とか行政とのやり取りでしょう」
![]() 「その通りです。でも審査員によっては、外部コミュニケーションとは、環境報告書を出すことと思い込んでいる人がいますね。
「その通りです。でも審査員によっては、外部コミュニケーションとは、環境報告書を出すことと思い込んでいる人がいますね。
確かに環境報告書も外部コミュニケーションでしょうけど、それは外部コミュニケーションのほんの一部であり、必須ではありません」
![]() 「環境報告書を出していないと不適合になりますか?」
「環境報告書を出していないと不適合になりますか?」
![]() 「不適合になったことは、まだありません。初回審査ですからね。ただ次回までに発行せよとは言われています。
「不適合になったことは、まだありません。初回審査ですからね。ただ次回までに発行せよとは言われています。
ご丁寧にカラーコピーでホチキス止めで良いから作って、近隣住民に配りなさいと語っていました。いくらかかるか想像できないようです。カラーコピーで500部もプリントしたら、数十万かかりますね。大金ですわ。
今年は初回審査ですが、来年は同じ人が審査に来るかどうか?」
注:1990年代半ばは、カラーコピー1枚が50円くらいした。A4サイズで30ページの環境報告書を作るとして、一部1,500円である。認証機関がお金でも出さないと作れません。
近隣住民に工場の環境方針や工場長の笑顔の写真付きの環境報告書を配って評判でも良くなるものでしょうか?
![]() 「人が変わっても認証機関のルールかもしれないよ」
「人が変わっても認証機関のルールかもしれないよ」
・
・
・
・
![]() 「誰も言わないですが、著しい環境側面の決定方法が重大問題ですね」
「誰も言わないですが、著しい環境側面の決定方法が重大問題ですね」
![]() 「やはりスコアリング法でなければという話になりますか?」
「やはりスコアリング法でなければという話になりますか?」
![]() 「昨年、我々は業界傘下の会社に、どの認証機関に依頼するかというアンケートを取りました。
「昨年、我々は業界傘下の会社に、どの認証機関に依頼するかというアンケートを取りました。
その結果、20社以上にバラツキました。
その上位16社の認証機関に、この業界団体の規格解釈を説明するから集まれと呼びかけました」
![]() 「オーオー、強気ですね」
「オーオー、強気ですね」
![]() 「増子さんでしたか? 勘違いしてほしくないのですが、我々はお金を払う客、認証機関は請負業者であること、それを忘れないでください。
「増子さんでしたか? 勘違いしてほしくないのですが、我々はお金を払う客、認証機関は請負業者であること、それを忘れないでください。
集めたのは去年の秋です。結局、来てくれたのは14社でした。こないところは、我々の仕事などいらないのでしょう。
そこでスコアリング法でなくても良いということを説明しました。そして我々の解釈を納得して審査してくれるかという問いに、すべてはYESとは回答しませんでしたね」
![]() 「お宅の解釈が正しいという証拠はありますか?」
「お宅の解釈が正しいという証拠はありますか?」
![]() 「我々はしっかり規格を読みました。ISO14001の基になったBS7750も読みました。ここにも英文規格を日常読んでいる方が二人います。読解力はお墨付きです。
「我々はしっかり規格を読みました。ISO14001の基になったBS7750も読みました。ここにも英文規格を日常読んでいる方が二人います。読解力はお墨付きです。
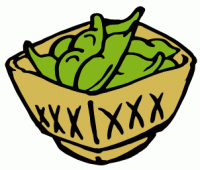 またイギリスでBS7750の審査していたイギリス人の審査員にも教えを乞いました。
またイギリスでBS7750の審査していたイギリス人の審査員にも教えを乞いました。
完成したテキストを業界設立の認証機関である産業環境認証機関に依頼して、監修してもらいました。
またB○○社にも内容の確認をお願いしています。
それくらいの裏付けがあれば正しいとご理解いただけますか?」
![]() 「はあ、そうですか」
「はあ、そうですか」
![]() 「増子君、ここにいる人たちは工場の環境管理ではなく、本社で工場や関連会社を指導して、行政とやりあい、近隣住民とのトラブル対策をしている者たちだ。
「増子君、ここにいる人たちは工場の環境管理ではなく、本社で工場や関連会社を指導して、行政とやりあい、近隣住民とのトラブル対策をしている者たちだ。
環境管理の仕事を引退した審査員とか、無関係の職種からISO審査員になるため勉強して公害防止管理者資格を取った審査員とは、真剣さもレベルも違うんだ。
失礼以前に、君はこの場にいる資格がないと思われるぞ。うかつなことは言うなよ」
・
・
・
・
![]() 「私は1970年からずっと環境管理、正確には公害防止を担当してきました。その仕事で何が一番重要かと言えば法規制と測定値です。
「私は1970年からずっと環境管理、正確には公害防止を担当してきました。その仕事で何が一番重要かと言えば法規制と測定値です。
法律、施行令、省規則、県条例、市条例、自分が関わるものは暗記します。というか覚えちゃいますね。
審査員を見ていて絶対問題だと思うのは法律を知らないことです」
![]() 「ISO審査は遵法点検と違うから、法律を知る必要はないのではないですか?」
「ISO審査は遵法点検と違うから、法律を知る必要はないのではないですか?」
![]() 「おっしゃる通り……と言いたいですが、法律の規制とか数字を知らなくても、法律の読み方は必要です。
「おっしゃる通り……と言いたいですが、法律の規制とか数字を知らなくても、法律の読み方は必要です。
例えば法律では同じことを繰り返して書かないのですよ。ですから『○○の定義は○○法による』という表現も多いし、一度『○○する』という記述があると、それ以降は『第〇条第〇項の規定を準用する』とします。どんどんと遡って読まないと法律が分からない。
そういうのを知らない審査員が法律を全文検索して、『法律に書いてない』とか言われても困ります」
![]() 「ウチに来た審査員は『私は消防法については消防署より詳しい』と言っていた。
「ウチに来た審査員は『私は消防法については消防署より詳しい』と言っていた。
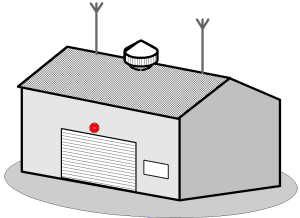 その審査員が『危険物貯蔵所が違法だ』と不適合を出したので、慌てて消防署に聞きに行ったら、法改正前の設備は旧来のままで良いという通知があると言われた。
その審査員が『危険物貯蔵所が違法だ』と不適合を出したので、慌てて消防署に聞きに行ったら、法改正前の設備は旧来のままで良いという通知があると言われた。
いい加減なことを言わないで欲しいよ。
せめて違法の恐れがあるから、消防署に確認すること程度に言って欲しい」
![]() 「審査員、あるあるだな。迷惑千万な話だ」
「審査員、あるあるだな。迷惑千万な話だ」
・
・
・
・
![]() 「私は技術管理、つまりJIS規格とか海外規格とか業界規格などを整備したり、読解をするのが仕事です。
「私は技術管理、つまりJIS規格とか海外規格とか業界規格などを整備したり、読解をするのが仕事です。
須藤さんが言われたように、審査員が規格を理解していないのはもうはっきりしていますね。それは規格の読み方を知らないからです」
![]() 「大分厳しいな」
「大分厳しいな」
![]() 「先ほど高橋さんが『自覚』の意味を理解していないと話していましたが、私はその根本原因は英語で読んでいないからだと思います。
「先ほど高橋さんが『自覚』の意味を理解していないと話していましたが、私はその根本原因は英語で読んでいないからだと思います。
『自覚』の原文は『aware』です。これをJISでは『自覚』と訳していますが
『aware』は自覚って言っちゃ自覚だけど、その意味は『存在を認識する』とか『気配を感じる』ことなんです。悪いことをしたと認識するとか反省することじゃあない。
一字一句、英英辞典を引いて、どんな意味かを確認する必要がある。
話はそれるけど、4.4.2のJIS訳は『組織は、関連する各部門及び階層においてその従業員又は構成員に、次の事項を自覚させる手順を確立し、維持しなければならない』です。
ですから審査員は会社に『自覚させる手順はあるか、しているか?』と聞くのは当然です。でも従業員に『自覚したか?』と聞く要求はありません」
![]() 「でも自覚させる仕組みがあっても、機能しているか・効果的かどうかは従業員に聞くしかないでしょう」
「でも自覚させる仕組みがあっても、機能しているか・効果的かどうかは従業員に聞くしかないでしょう」
![]() 「おっしゃる通り。しかし認識するとは心の内面です。例えば……あなたは彼を愛しているか?
「おっしゃる通り。しかし認識するとは心の内面です。例えば……あなたは彼を愛しているか?
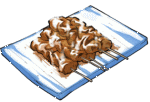 と聞いても意味がありません。どんな答えであっても、本音かウソか分かりませんからね。
と聞いても意味がありません。どんな答えであっても、本音かウソか分かりませんからね。
じゃあ、どうするか?
簡単です。その人の行動を見るのです。彼を愛しているか否かは判断が難しい。しかし仕事で自覚したかどうか確認するのは可能です。いやできなければ審査員の資質がないということでしょう」
![]() 「何を言っているのか分かりません」
「何を言っているのか分かりません」
![]() 「少なくとも、あなたに審査員の資質がないことは分かりました。
「少なくとも、あなたに審査員の資質がないことは分かりました。
『自覚』とは、もとい『aware』とは、その仕事の重要性を理解して、それに注意を払うことなんです。
仕事を観察して確かに重要なことに注意を払っているかを見る、そしてなぜそれをするのか聞く、そういうことが審査ですよ。
書類のハンコを見たり、チェックリストが埋まっているか確認したりするのは審査ではありません。
『著しい環境側面を決定する』とあると『判断すれば良い』と思うかもしれない。残念ながら原文は『determine』で『決める』というより『決まってしまう』という意味です」
![]() 「そうだったのか」
「そうだったのか」
![]() 「押田さんは上智だそうですね。英語が得意だと思います。
「押田さんは上智だそうですね。英語が得意だと思います。
原文がDetermineと知っていれば、著しい環境側面を計算で決めるなんて発想は起きません。なぜなら白黒つけるぞということでなく、調べれば自然と判明するわけです。まあ、アホには分かりませんよ。
文書管理では『legible』を『読みやすく』なんて訳している。それを読んで『手順書は読みやすいこと』と理解している審査員が多い。
意味が全然違います。『legible』とは『鮮明であること』です。
ウチに来た審査員が『この規定は文章が分かりにくいからlegibleでありません』なんて不適合を出しました。
帰れと言いたかったのですが、上役が静かにしろと
![]() 「静かにしろと
「静かにしろと
![]() 「まったく、口から先に生まれたような・・・
「まったく、口から先に生まれたような・・・
読みにくいのが良いとは言いません。不適合にしたけりゃ『legibleでない』じゃなく『レビューが不十分』として不適合にすべきです」
![]() 「『Policy』だって日本語の方針とは違いますよ」
「『Policy』だって日本語の方針とは違いますよ」
![]() 「おっしゃる通り。審査員には英語の試験が必要です。会話は不要でしょうけど、英文読解力は一定以上のレベルを要求すべきでしょうね」
「おっしゃる通り。審査員には英語の試験が必要です。会話は不要でしょうけど、英文読解力は一定以上のレベルを要求すべきでしょうね」
![]() 「日本語の試験も必要だよ。中学3年程度の国語の力は必要だ」
「日本語の試験も必要だよ。中学3年程度の国語の力は必要だ」
![]()
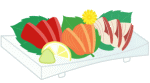 「そもそもJIS訳がまずいんだろうなあ〜」
「そもそもJIS訳がまずいんだろうなあ〜」
![]() 「いっそのこと、ISO原文を正とすれば良いのに。JISは参考の位置づけで」
「いっそのこと、ISO原文を正とすれば良いのに。JISは参考の位置づけで」
![]() 「いやあ、すごいですね。日常苦しんでいるのが良く分かります」
「いやあ、すごいですね。日常苦しんでいるのが良く分かります」
![]() 「ULやISO規格に限らず、私は日本の法律でもJIS規格でも、同じスタンスで読み、理解し社内に展開しているのですよ。私はこれで飯を食っていますからね。
「ULやISO規格に限らず、私は日本の法律でもJIS規格でも、同じスタンスで読み、理解し社内に展開しているのですよ。私はこれで飯を食っていますからね。
増子さん、仕事は真剣に取り組まないといかんよ」
![]() 「分かりました」
「分かりました」
言葉は素直そうだが、憎々しげな眼をしている。
もっとも研究会のメンバーは、全く気にもしない。いつも審査員や認証機関と丁丁発止でやっている。子猫みたいな増子を相手にする暇はない。
・
・
・
・
![]() 「押田さん、本日の話合いは参考になりましたか?」
「押田さん、本日の話合いは参考になりましたか?」
![]() 「非常に参考になりました。審査員が問題だという話はよく聞きますが、実際にどんな問題があるのか、その原因は何かとなると、闇の中、
「非常に参考になりました。審査員が問題だという話はよく聞きますが、実際にどんな問題があるのか、その原因は何かとなると、闇の中、
規格を英語で読まないで、先輩審査員の語ることを鵜呑みにしているかな?
法律は、読む力がないからでしょうね。
おっと、佐川さん、今日は一言も発言がありませんが?」
![]() 「いつも私ばかり話しているようなので、今日は飲む方に努めていました。
「いつも私ばかり話しているようなので、今日は飲む方に努めていました。
一言述べよとおっしゃるなら一言、
出される不適合は審査員のレベルに応じたものである、という佐川説をお話します。
 ISO14001審査が始まって以降、私は統計を取っていますが、多い不適合は、環境側面、文書管理と記録管理、環境マネジメントプログラムです。これは当社グループ30数回の審査結果をまとめたものです。
ISO14001審査が始まって以降、私は統計を取っていますが、多い不適合は、環境側面、文書管理と記録管理、環境マネジメントプログラムです。これは当社グループ30数回の審査結果をまとめたものです。
全部が不適合になったわけでなく、審査中に指摘されて修正してOKされたものも含めています。
環境側面はスコアリング法でないものは、ほどんどダメとされています。そんなこと誰にでもできますね。
文書管理は決裁印、発行日の整合性確認、バージョンが合っているか、書き込みがないか、子供でもできます。
記録の管理は、ハンコの有無と日付、感熱紙はないか、すぐに出てくるか、もう赤ん坊にもできます。
環境マネジメントプログラム、これは規格で決めている要素に抜けがないか、日付、数字、進捗状況、要するに誰でもできます。
是正処置とか遵守評価なんてなると、一面からだけでなく多面的に見て、整合しているか、おかしなところがないか、漏れがないかと見なければならず、教科書を読んだだけでは分からない。
現場を歩いて表示が薄れている、閉めるべきドアが開いている、そんなことを指摘するのは誰でもできる。
表示が薄れている、ドアの開閉が守られていない、そういう状況を見て総合的に考え、問題を指摘できないと審査員ではないですね」
![]() 「佐川さんでしたっけ、あなたはできるのですか?」
「佐川さんでしたっけ、あなたはできるのですか?」
![]() 「私はISO9001を含めて、もう300回くらい審査に立ち会いました。冗談抜きに、私より上手と思った審査員は片手いないですね。
「私はISO9001を含めて、もう300回くらい審査に立ち会いました。冗談抜きに、私より上手と思った審査員は片手いないですね。
ISO審査員というものは、日本では誕生してまだ5年くらいでしょうけど、業務監査というものは何十年という歴史があります。おっと、審査と監査を日本語では区別しているけど、英語では同じauditです。
ISO審査を特別だと思うのは間違いですよ。どの会社にも監査部があるでしょう。そんな人に極意を学ぶべきですね。
増子さんは今日この場で聞いたことを、くだらないと思っているようですね。まあ、どう思ってもご自由ですが、お金を取って仕事するなら相手が感心するような成果を出さないと、ビジネスが長続きしません。
1997年現在、審査料金は審査員1人1日14万も取るのですよ。弁護士を頼んだことがあるかもしれませんが、せいぜい1日10万でしょう。

おっと、手取りは違うとか、
本日の発表者は皆、ISO審査員が提供するサービスと受け取る対価が見合っていないと考えている、ということを理解しないといけませんね。
そしてそれは思い込みとか偏見ではないのです。
日々の仕事で話が通じない、文章を理解しない人たちと闘っている人が、肌で感じていることなのです。
蛇足ですが、ISO認証機関は、日本標準産業分類における業種区分は「7299 他に分類されない専門サービス業」という範疇になります。
7299にどんなものがあるかというと、広告代理業、広告制作業、イベント企画・運営、その他専門サービスといって、鑑定業、司会業、コピーライター、投資顧問など、専門的な知識や技術を活かしたサービスを提供する事業ですね。
これらの仕事で、お客様に丁寧語を使わない仕事ってありますか?
そこらへんから考えないといけませんね、アハハハ」
田中はじめ多くの研究会のメンバーは、なぜ増子が審査員批判を憎々しげに聞いているのか不思議に思うのであった。
![]() 本日の主張
本日の主張
私は審査員すべてが力量不足とは思っていない。しかしどうしようもないレベルの審査員がいるのは間違いない。
そもそも、審査員研修機関の「ISOxxxx審査員研修コース」5日間程度では有効でないのです。
まずMS規格の理解がしっかりしていることを確認すべきだ。スコアリング法以外はダメとか、有益な環境側面とか言い出すようでは、MS規格を読んでないと言われてもしかたないだろう
1996年版、2004年版、2015年版、どれを読んでもそんなことは読み取れない。
ISO規格は英文を読んで理解していることが最低限でしょうね。しっかりISOMS規格の理解を試験すべきだ。
専門知識の保有を確認しているかも怪しい。
資格を持っているからとは言えない。
私自身も力量は不十分と思う。公害防止管理者はすべて持っているけど、届出したのは1種類1度限り。ハッキリ言って名前だけです。
危険物取扱者は保安監督者として届け出していたし、実際に10年以上、仕事をしていた。作業環境測定士は数年しか実務をしなかった。環境計量士は試験だけ。
審査員になるとき、資格がないからと技術士(環境)を取ったという方を知っているが、そういうレベルではダメだと思う。
「なぜBOD測定に五日もかかるのか?」という審査員には来てほしくない。
注:審査で測定会社からの報告が10日後だったので「BOD測定に5日もかかるのはおかしい」と言われたのは事実です。
専門分野の認定だって大甘だ。審査に何回参加すれば良いなんてことはないだろう。
条件をもっと厳しくすべきだと思う。国際ルールかもしれないが運用でできるだろう。
法律もしっかり読むには、最低でも行政書士くらいの力量が必要だろう
それから現場も設備も知らないとダメです。
ISO審査は遵法点検じゃない、安全パトロールでない、というご意見もあります。否定はしませんが、じゃあ、どういう資質、力量があれば審査員が務まるとお思いでしょうか?
まさか審査員研修コース修了ならOKとは言わんでしょう。
審査というサービスで対価をもらうというビジネスをするならば、それなりのレベルでないとお足はもらえない。審査会場で笑われないようにしてほしい。
個人的には、審査員は審査を受ける人の3倍の経験と知識が必要だと思います
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
スマホ登場はIBMやブラックベリーがあったが、2007年のAppleのiPhoneが事実上のスマホの開祖だろう。カメラ付携帯電話は2000年1月Jフォン(ソフトバンクモバイルの前身)が発売したのが最初。 | |
| 注2 |
「aware」を英英辞典で引くと
| |
| 注3 |
トンデモ本を例に挙げる。 「マネジメントシステム進化論」という本がある。著者には認証機関社長、審査員研修機関講師など、そうそうたる方々の名が並ぶ。 その本の中では「有益な環境側面」があり、「legibleは読みやすいこと」としっかり書かれている。著者の方々はISO14001を読んだことがあるのだろうか? | |
| 注4 |
行政書士の資格を取らないにしても、最低でも基礎法学を学んでおく必要がある。 | |
| 注5 |
うそ800「つまらない話」 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |