注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
本日はサイドストーリーです。読まなくても全然関係ありません。もっともこのお話そのものも読まなくても、あなたの人生には全然関係ありませんね。
嗚呼、私はなんと無価値なことをしているのでしょう😅
ここは社長室、佐川との話を終えたのち、応接テーブルに社長と下山次長と中山室長が残って話を続けている。
| 中山経営企画室長 |  |
机だよ |
||
| 奥田社長 |  | 下山人事部次長 | ||
![]() 「佐川の話を聞いたが、正直言って未来から戻ったとは信じられないな」
「佐川の話を聞いたが、正直言って未来から戻ったとは信じられないな」
![]() 「私も信じられません。とはいえ彼の予言は100%当たっています」
「私も信じられません。とはいえ彼の予言は100%当たっています」
![]() 「私は彼とは長い付き合いです。先ほど話に出た、灰皿事件から関わりがあります」
「私は彼とは長い付き合いです。先ほど話に出た、灰皿事件から関わりがあります」
![]() 「灰皿事件か、名前を聞けば笑ってしまうが、現実は大変だったのだろう?」
「灰皿事件か、名前を聞けば笑ってしまうが、現実は大変だったのだろう?」
![]() 「ISO9001の審査で、審査員が書類を出すのが遅いと怒って、重いガラスの灰皿を、書類を持ってきた女性に投げつけたとんでもない事件でした
「ISO9001の審査で、審査員が書類を出すのが遅いと怒って、重いガラスの灰皿を、書類を持ってきた女性に投げつけたとんでもない事件でした

1990年代は誰でもタバコをスパスパ吸っていた。
お客様が来ると上等な重い灰皿を出すのがお約束
ドラマでは敵を灰皿で殴り殺すとこまでがお約束
![]() 「なんでもISO審査では書類は、何分以内に出さないとならないとかいうルールがあったんじゃないか
「なんでもISO審査では書類は、何分以内に出さないとならないとかいうルールがあったんじゃないか
![]() 「それは存じません。何年も前の帳票は事務所に置かず倉庫に置いています。それを持って来る往復20分くらいは問題ないでしょう。
「それは存じません。何年も前の帳票は事務所に置かず倉庫に置いています。それを持って来る往復20分くらいは問題ないでしょう。
それに客先で怒り狂い物を投げつけるとか、話になりません。
佐川の話では、彼の最初の人生では灰皿は女性に当たり、顔がひどい状態になったそうです。
結婚を控えていて、周りの人も会社も真っ青になりました。加害者からの賠償以外に、会社からもお見舞いとしてかなりの金額を出したそうです。
私は彼の前世を経験していませんというか、経験していても彼の行為で上書きされてしまったのかもしれません。ともかくその事実を知りません」
![]() 「とんでもないことだな。ISO審査というのは、そういうものがつきものなのか?」
「とんでもないことだな。ISO審査というのは、そういうものがつきものなのか?」
![]() 「直接的な暴力は聞いたことがありませんが、机を叩く、椅子を蹴る、怒鳴るなど
「直接的な暴力は聞いたことがありませんが、机を叩く、椅子を蹴る、怒鳴るなど
また宴席、会社の製品、サンプルなどの提供を求められることも多いです。
まあ、お金をもらう請負業者の態度ではありませんね」
注:下山が現在形で話しているのは、この時点でそのようなことは公然と行われているからだ。
ISO審査における宴席や土産の強請りの批判は、2003.08.01読売新聞の報道が嚆矢である。認証機関が是正するのはその後のことだ。
![]()
当時、読売新聞をとっていたので、その記事をリアルタイムで読んだ。大きさは横幅4〜5センチ、高さ2段だったと記憶している。大きな記事ではなかった。威力は大きかったけど。
興味あれば「ヨミダス」で「ISO+饗応」で見つかると思う。
![]() 「ISO審査は請負ではないのだろう。法による許認可なら準公務員みたいなものだろう」
「ISO審査は請負ではないのだろう。法による許認可なら準公務員みたいなものだろう」
![]() 「いえ、法に基づくものではありません。民間であってもUL認定は保険などとの関係がありますが、ISO認証はそれとも違い何事かの権益があるわけでもありません。単にISO規格を満たしているか見てもらうだけです。公的なメリットはなく、単なるプライズでしょうか?」
「いえ、法に基づくものではありません。民間であってもUL認定は保険などとの関係がありますが、ISO認証はそれとも違い何事かの権益があるわけでもありません。単にISO規格を満たしているか見てもらうだけです。公的なメリットはなく、単なるプライズでしょうか?」
注:ULとはUnderwriters Laboratoriesの略で、元々はUnderwriters(保険会社)の団体が作った、保険を払うべきものを決める機関だった。UL合格した品物が原因での火災なら保険金を払う、そうでなければ払わないなど。
![]() 「それではなぜ認証を受けるの?」
「それではなぜ認証を受けるの?」
![]() 「ISO9001は、欧州統合により輸出の際に必須ということで、認証することになりました。まあ認証する理由としては十分でした。しかしその後、弊社の取引先で、認証していない会社も輸出しています。どういうからくりか逃げ道があるのか分かりません。
「ISO9001は、欧州統合により輸出の際に必須ということで、認証することになりました。まあ認証する理由としては十分でした。しかしその後、弊社の取引先で、認証していない会社も輸出しています。どういうからくりか逃げ道があるのか分かりません。
ISO14001は必要に迫られたというよりも、ISO9001で煮え湯を飲まされたということから世界に先んじて認証がブームになりました。
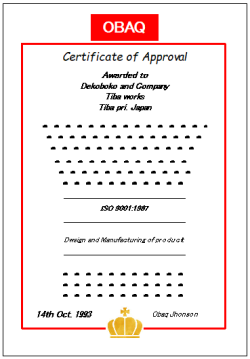 必要性は・・・なさそうですね」
必要性は・・・なさそうですね」
![]() 「私もそれが不思議です。
「私もそれが不思議です。
何のご利益もないものに大金を払って免状を頂く、私には理解できません。
しかも免状は頂くのではなく借りているだけです」
![]() 「認証している会社より劣っていると、思われたくないだけでしょう。
「認証している会社より劣っていると、思われたくないだけでしょう。
認証そのものより、それに付帯していろいろ問題が起きています。饗応、お土産の要求、審査の横暴などです。
なににせよ
![]() 「佐川の話では、昼飯、宴席など求める行為は、21世紀に入ってすぐにマスコミに叩かれて、襟を正すそうです。
「佐川の話では、昼飯、宴席など求める行為は、21世紀に入ってすぐにマスコミに叩かれて、襟を正すそうです。
企業が苦情を言ってもダメ、マスコミが数センチ角の記事を書くとすぐに改めるって、どうなんですか」
![]() 「奴はそういう予言もしているのか……
「奴はそういう予言もしているのか……
ええと、奴が未来から戻ったかの真偽はおいといて、彼の予言は信用できるのか?」
![]() 「先ほども話に出ましたが、ドル円のレートは間違いありません」
「先ほども話に出ましたが、ドル円のレートは間違いありません」
![]() 「彼の予言は正しいとしても、欠陥があります」
「彼の予言は正しいとしても、欠陥があります」
![]() 「欠陥?」
「欠陥?」
![]() 「彼は為替のトレーダーでもなく証券会社勤務でもなく、経営者でもありません。どこにでもいる工場の現場管理者でした。ですから彼の関心は、その立場に限定されます。
「彼は為替のトレーダーでもなく証券会社勤務でもなく、経営者でもありません。どこにでもいる工場の現場管理者でした。ですから彼の関心は、その立場に限定されます。
円ドルのレートには関心があるかもしれません。しかし東証株価などになると、好況や不況の記憶はあっても、その日時とか
![]() 「なるほど、それはそうだ。そんなことを言ったら、私だってスポーツとか芸能のニュースに興味がないよ」
「なるほど、それはそうだ。そんなことを言ったら、私だってスポーツとか芸能のニュースに興味がないよ」
![]() 「ともかく天変地異については発生日時や被害状況に間違いないでしょうけど、政治や経済あるいは国際的なできごとについては、当てになりません」
「ともかく天変地異については発生日時や被害状況に間違いないでしょうけど、政治や経済あるいは国際的なできごとについては、当てになりません」
![]() 「それでも奴の話で、IT革命、リーマンショック、民主党政権での外交、社会、経済の混乱、自民党復権での株価急上昇などは十分信用できるし、価値ある情報だよ」
「それでも奴の話で、IT革命、リーマンショック、民主党政権での外交、社会、経済の混乱、自民党復権での株価急上昇などは十分信用できるし、価値ある情報だよ」
![]() 「確かにそうではありますが、それに目を奪われると、彼が忘れてしまった出来事に、足をすくわれる恐れが大です。
「確かにそうではありますが、それに目を奪われると、彼が忘れてしまった出来事に、足をすくわれる恐れが大です。
言いたいことは、リーマンショックは企業にとって重大な情報ですが、他社の新製品も大事ですし、独禁法違反で捜査が入ったという情報も重要です」
![]() 「まっ、確かに」
「まっ、確かに」
![]() 「それは分かった。ノストラダムスより具体的で当たるなら悪いことはない。
「それは分かった。ノストラダムスより具体的で当たるなら悪いことはない。
奴はISO認証にはだいぶ自信があるようだが、その辺の力量はどうなんだ。講釈通りか?」
![]() 「彼は高卒で現場に入り、すぐに頭角を現してリーダー、職長となり、稀有なことですが30代後半で課長になっています。全社でも年に一人もいないでしょう。
「彼は高卒で現場に入り、すぐに頭角を現してリーダー、職長となり、稀有なことですが30代後半で課長になっています。全社でも年に一人もいないでしょう。
天才ではないにしろ、行動する秀才であることは間違いありません。
課長解任したのは、覚えてらっしゃるかもしれませんが尾関という副工場長で・・・」
![]() 「ああ、当時は私は平執行役だったが話を聞いて覚えている。もう4年も前になるか」
「ああ、当時は私は平執行役だったが話を聞いて覚えている。もう4年も前になるか」
![]() 「彼は課長を首になって品質保証に異動します。そこで前任者が四苦八苦で仕事が滞っていたのを、彼はひと月で片付けました。その後、ISO9001登場に際しても、ものすごい力を発揮し社内で有名になりました。
「彼は課長を首になって品質保証に異動します。そこで前任者が四苦八苦で仕事が滞っていたのを、彼はひと月で片付けました。その後、ISO9001登場に際しても、ものすごい力を発揮し社内で有名になりました。
一回経験していたと言えばそれまでですが、ISOが登場したとき未来から戻っていますから、それ以前の仕事は本来の能力です。それを見れば只者ではありませんね」
![]() 「奴は今40代半ば、これからどう扱うつもりだ?」
「奴は今40代半ば、これからどう扱うつもりだ?」
![]() 「職制上、彼は私の部下になりますので、毎年自己申告で面談しています。
「職制上、彼は私の部下になりますので、毎年自己申告で面談しています。
本人はもう本社では自分のすることはないと言います。そして本音かどうか、関連会社でも良いから製造現場の仕事に就きたいと言っています」
![]() 「2023年までというとあと26年、今40代半ばでも定年を優に超える。情報源として定年まで本社のどこかに置いておいた方が良いな。ISOとか未来プロジェクトが終わっても役に立つだろう」
「2023年までというとあと26年、今40代半ばでも定年を優に超える。情報源として定年まで本社のどこかに置いておいた方が良いな。ISOとか未来プロジェクトが終わっても役に立つだろう」
![]() 「社長、それで計画などに、彼の予言を活用することについてはいかがですか?」
「社長、それで計画などに、彼の予言を活用することについてはいかがですか?」
![]() 「中山さんも人が悪い。3年も前から財務部が投資計画に彼の話を参考にしていたというなら、今更だよね」
「中山さんも人が悪い。3年も前から財務部が投資計画に彼の話を参考にしていたというなら、今更だよね」
![]() 「それでは『未来情報の取扱内規』とでもいうもののドラフトを作りましょう」
「それでは『未来情報の取扱内規』とでもいうもののドラフトを作りましょう」
![]() 「彼の予言を採用する前に、客観的な検証工程を入れることは漏らさないでください」
「彼の予言を採用する前に、客観的な検証工程を入れることは漏らさないでください」
増子家の夕餉である。
今週、増子(父)は審査員の仕事がないようで、終日家におり、夕飯も毎日作っている。
増子(子)が帰宅すると親子は缶ビールで乾杯し、今日一日のことを話し合う。意外とコミュニケーションは密なのだ。
| |||||||
 | ★ |  |
|||||
![]() 「ISO認証というものは理屈に合わないというか、通常の商取引と違うのが不思議だ」
「ISO認証というものは理屈に合わないというか、通常の商取引と違うのが不思議だ」
![]() 「どういうこと?」
「どういうこと?」
![]() 「取引には買い手と売り手がいる。物の売買だけでなく、弁護士はサービスを提供し、依頼者はそれを金で買う。建設などでは、売り手が複数絡むこともあるが、売り手と買い手という関係は変わらない。
「取引には買い手と売り手がいる。物の売買だけでなく、弁護士はサービスを提供し、依頼者はそれを金で買う。建設などでは、売り手が複数絡むこともあるが、売り手と買い手という関係は変わらない。
さて、通常は買い手を顧客という。ISO8402:1994
![]() 「顧客が買い手ではないとはどういうこと?
「顧客が買い手ではないとはどういうこと?
![]() 「ジジババの金で、赤ん坊を連れてディズニーランドにいく、
「ジジババの金で、赤ん坊を連れてディズニーランドにいく、
 若夫婦がいたとして、誰が顧客だ?
若夫婦がいたとして、誰が顧客だ?
![]() 「金を出す人が顧客でないなら、サービスを受ける赤ん坊が顧客かな?」
「金を出す人が顧客でないなら、サービスを受ける赤ん坊が顧客かな?」
![]() 「赤ちゃんにミッキーも白雪姫も関係ないだろう。若夫婦かご新造さんが顧客だろう」
「赤ちゃんにミッキーも白雪姫も関係ないだろう。若夫婦かご新造さんが顧客だろう」
![]() 「だれが顧客でも、どうでもいいじゃない?」
「だれが顧客でも、どうでもいいじゃない?」
![]() 「お前は法律とかISO規格などと無縁だなあ〜
「お前は法律とかISO規格などと無縁だなあ〜
法律や規格に関わると、定義とか言葉の使い方が、ものすごく気にするようになる。『及び』と『並びに』が違うと気になるとか。
ISO審査契約は、審査というサービスとその対価としてお金を払うという契約だ。実際に契約書にそう書いてある。
ここで顧客は誰だ?」
![]() 「金を払う方でしょう。あっ、定義によると『サービスの受け取り手』ですから審査を受ける企業ですね」
「金を払う方でしょう。あっ、定義によると『サービスの受け取り手』ですから審査を受ける企業ですね」
![]() 「認証機関はそうは考えていない。今はどうか知らんが、1993年頃は『顧客の代理人』と自称していた」
「認証機関はそうは考えていない。今はどうか知らんが、1993年頃は『顧客の代理人』と自称していた」
![]() 「『顧客の代理人』ということは、認証を受ける供給者
「『顧客の代理人』ということは、認証を受ける供給者
![]() 「そうとしか思えないな」
「そうとしか思えないな」
![]() 「しかし
「しかし
となると『顧客の代理人』ってことはないですよね。お金をもらうけど頭を下げたくないってことかな?
『顧客の代理人』と自称するとは自己中心で傲慢不遜、今風に言えば痛い人
![]() 「更に正確に言えば『顧客の代理人』は認証機関であり、審査員はその手足、調査する人ということだ」
「更に正確に言えば『顧客の代理人』は認証機関であり、審査員はその手足、調査する人ということだ」
![]() 「調査員とは?」
「調査員とは?」
![]()
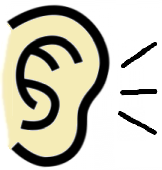 「監査員の原語は英語のauditorで、それは『聞く人』の意味だから、審査員は調査する人だ。
「監査員の原語は英語のauditorで、それは『聞く人』の意味だから、審査員は調査する人だ。
監査の歴史は3,000年くらいあり、発祥した頃は王様の目とか王様の耳と言われたそうだ。
当時、監査員とスパイそして影(VIPの護衛兼暗殺者)は、同じものだったのだろうなあ〜、要するに御庭番だったのだろう。
言いたいのは審査員が善し悪しを決定するのではない。それをするのは法人である認証機関、具体的には認証機関の経営者だ。
審査員はその手足となって審査し報告するだけだ」
注:「audition(オーディション)」も 「audit(監査・審査)」も、ラテン語の audire(聞く)を語源としている。
本来の意味は「聴く」だけでなく「聴いて評価する」という意味であったそうだ。
演技や演奏を聞いて審査する「オーディション」も、業務を観察したり帳票をめくって審査する「監査」も同じですね。
![]() 「なるほど、そういう制度なのですね」
「なるほど、そういう制度なのですね」
![]() 「まあ、そういう仕組みを知っている審査員はどれほどいるか……、多くは生殺与奪の力を持っていると勘違いしているんじゃないか。
「まあ、そういう仕組みを知っている審査員はどれほどいるか……、多くは生殺与奪の力を持っていると勘違いしているんじゃないか。
おっと、ISO審査における顧客とは何かというのは摩訶不思議なことよ
増子(子)は父親が問題だと言っていることは半分も分からない。だけどこういったことを「ISO認証」誌に書いてくれれば、企業の人の知識になり、歓迎されるのではないかと思う。
風呂から上がった増子(子)は、パソコンを立ち上げ、先ほど父親から聞いた話を思い出しながら物語になるように作文する。
ひとつは「顧客の代理人」というタイトルで、もうひとつは「定義が大事」という文である。それぞれ2,700字前後にまとめる。A4見開きで2ページというと、この程度の文字量だろう。
「ISO認証」誌の出版社である。押田編集長と増子(子)が話している。
![]() 「まず先日、押田さんから話がありました、オヤジのエッセイのドラフトです。2件作りました。実を言ってオヤジが語るのを私がメモして、文章を整えたものです。オヤジには内容を確認してもらっています。
「まず先日、押田さんから話がありました、オヤジのエッセイのドラフトです。2件作りました。実を言ってオヤジが語るのを私がメモして、文章を整えたものです。オヤジには内容を確認してもらっています。
文字数は見開きということでしたので、2,800字前後と推定しました。それより少なめにしています。
ちょっとしたアイデアですが、ひとつは通常のエッセイで、もうひとつはオヤジと私の対話にしてみました。そのほうが何も知らない一般人に受けるかと思いました。
一応お読みいただけますか。まずは内容と形式そして方向を考えてください。文体とか取り上げる事例などはご注文に合わせます。
オヤジは認証機関と守秘契約をしてるそうですが、一般的な規格解釈とかトラブル対応の見解は問題ないだろうと思います。正式に決まれば、認証機関に確認を取るとのことです」
![]() 「さすが仕事が早い。期待して読ませてもらう。君が文章を書くなら毎月1件は軽いね?」
「さすが仕事が早い。期待して読ませてもらう。君が文章を書くなら毎月1件は軽いね?」
![]() 「学生時代は論文以外に、数ページのレポートたくさん書いてましたから、このくらいの分量なら1時間で仕上げますよ。
「学生時代は論文以外に、数ページのレポートたくさん書いてましたから、このくらいの分量なら1時間で仕上げますよ。
それとオヤジも他の認証機関の実態を知らないだろうと思いましたので、例の研究会著作の本をオヤジに渡しました。審査の行き帰りの電車や飛行機の中で読んでくれるでしょう」
![]() 「そういえば、研究会対審査員という特集もありそうだな。
「そういえば、研究会対審査員という特集もありそうだな。
以前、吉宗機械の佐川という人から『ISOで会社を良くするとは何か』という話を聞かされたことがある(第89話)。
君のオヤジさんに『ISOで会社を良くするとは何か』に聞いてみてほしい。それができたら1回目に載せようか」
数日後、押田が中岡社長と話している。
![]() 「増子の書いたコラムはなかなか良かったな。それと、以前お前から借りたボイスレコーダー、聞いて面白い。落語のようだ。
「増子の書いたコラムはなかなか良かったな。それと、以前お前から借りたボイスレコーダー、聞いて面白い。落語のようだ。
畏まった文章も良いが、おやっさんの語り口そのままというのも面白そうだ」
![]() 「そう言ってくださるとうれしいです。
「そう言ってくださるとうれしいです。
増子は対談形式とエッセイ形式と、どちらが良いか知りたいと言っていました」
![]() 「対談形式も面白いが、問題は字数が多くなることだな。普段はエッセイで、何かのとき対談形式というのはどうだ。
「対談形式も面白いが、問題は字数が多くなることだな。普段はエッセイで、何かのとき対談形式というのはどうだ。
それより大事なことだが、読者層をしっかりフォーカスしようというのはどうなった?」
![]() 「他のISO雑誌と違う、企業担当者の視点に舵を切りたいですね。なによりも需要があります。
「他のISO雑誌と違う、企業担当者の視点に舵を切りたいですね。なによりも需要があります。
 独りよがりの訳の分からないISO談義でなく、今困っている人が欲しがっている情報提供です。これぞジャーナリズムでしょう」
独りよがりの訳の分からないISO談義でなく、今困っている人が欲しがっている情報提供です。これぞジャーナリズムでしょう」
![]() 「ジャーナリズムの本質…権力を監視し、公共の利益のために真実を伝えるか…」
「ジャーナリズムの本質…権力を監視し、公共の利益のために真実を伝えるか…」
![]() 「ISO認証機関や審査員の独善的な言いたい放題では、企業担当者はしらけるだけです。
「ISO認証機関や審査員の独善的な言いたい放題では、企業担当者はしらけるだけです。
そんなんじゃなくて、知りたいことを教える、トラブル解決に手を差し伸べる、それですよ、それ」
![]() 「審査員がちょっと有名になると、いいたい放題、講釈を語り、それがデファクトスタンダードになってしまうご時世だからな。
「審査員がちょっと有名になると、いいたい放題、講釈を語り、それがデファクトスタンダードになってしまうご時世だからな。
自分が権威、権力にならないよう気を付けろよ」
![]() 「いやいや、まずは権威になりたいものです。
「いやいや、まずは権威になりたいものです。
読者の特定の一貫として、とりあえず来月号から審査員のコラムを作ります。筆者は増子父は決まりですが、一人で行くか複数に頼むかは考え中です。
増子の話では、おやっさんと酒飲んでの対話をメモっていて、それを息子が文章にまとめているそうです」
![]() 「機会あったら顔を出してもらえ。連載の初めには顔写真くらい入れたほうが、架空の人物じゃないと理解されるだろう」
「機会あったら顔を出してもらえ。連載の初めには顔写真くらい入れたほうが、架空の人物じゃないと理解されるだろう」
![]() 本日の苦情
本日の苦情
ISO規格解釈で
- 某氏は「手順とは手段と順序だ」と語った。
手順は日本語の手順じゃない、procedureの訳でっせ、オジサン。手段と順序じゃ落語にもならない。 - 某氏は「legibleは読みやすいだ。読みやすい文章を書こう」と言った。
そうなのか? - 某認証機関は「経営に寄与する審査をする」と広告した。
ISO/IAFの共同コミュニケを読んだことがないのか? - 「有益な環境側面」を語った某認証機関社長の頭の中は、産業廃棄物が詰まっているのか?
ISOにまつわるおかしな主張を取り上げたら、きりも限りもない。
問題は、それを是正する動きがなかったことだ。
「legibleの意味は違うよ」と教える審査員はいなかったのか?
認証機関の社長はドクターが多い(これは事実)。英語くらい読めるだろうに、
「有益な環境側面って、ISO規格の定義と矛盾するのではないか」と注意する認証機関の社長はいなかったのか?
「そんなアホを語っていると、ISO認証制度は先細りだ!」と叱る認定機関はなかったのか?
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
審査が行われる前に「30分以内に出さないとならない」という噂が広まった。 だが私が最初に会ったイギリス人審査員は、そんなことないと言った。以降、私はそれを信じて生きてきた。 | |
| 注2 |
「そのようなことはなかった」とは言わせませんよ。私は歴史の証人です。 | |
| 注3 |
暴行とは直接被害者を殴る蹴るだけでなく、凶器を振り回す、服や体や髪の毛を引っ張る、(相手に接触しなくても)物を投げる、物を叩く、唾を吐きかけるなどが該当する。 相手に怪我をさせると傷害罪となり、こうなるとほぼ逮捕される。 | |
| 注4 |
ISO9001:1987が制定されたとき、ISO9000シリーズで使う言葉はISO8402:1986で定義されていたが、「customer(顧客)」は定義されていない。というか、ISO9001では「customer(顧客)」が使われていない。使われていたのは「purchaser(購入者)」であった。 ISO8402:1994改定で「customer(顧客)」の定義が追加された。 | |
| 注5 |
ISO9000シリーズは、元々、品質保証の規格だったから、その当事者は「供給者」と「購入者」と記されていた。 いつの間にか変質して、今では使い物にならない規格になった。 | |
| 注6 |
BtoBという表現はインターネットを通じたeコマースの発展に伴って誕生した言葉である。アメリカでは1990年代初め「B-to-B」という表記がされたが、すぐに「B2B」と書かれるようになった。 日本ではインターネットの利用が遅れ2000年代初めから使われるようになり「BtoB」という表記が定着した。 | |
| 注7 |
「痛い人」とは現代では、物理的、精神的に痛みのある人でなく、「傍から見て恥ずかしい」という、感覚的や社会常識がずれている人を意味する。 | |
| 注8 |
ISO17021:2006が発行された。その中では定義3.1で「被認証組織(certified client)」と呼ばれたが、その後の改定で「依頼者(client)」と修正された。 審査を依頼しても顧客ではないようだ。 怪しげな審査の結果を受け取る顧客がいないのかもしれない。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |